
マイページに作品情報をお届け!
あなたの液クロ正常ですか?
アナタノエキクロセイジョウデスカ
- 著: 松下 至
クロマトを日常使う人の最大の悩み、正常に作動しているか、点検はどうするか、異常を認めたときの対処法は、などに経験豊富な著者が答える実用的ガイドブック。
液体クロマトグラフィーが誕生してから 1 世紀が経ち、当初、M.S. ツウェットが行った実験技法は科学者達たちにより幾年にもわたり改良改善され、今日の自然科学研究にはなくてはならない測定装置になった。今後も環境研究分野や医療分野への活用が期待されている。また近年はクロマトグラフィーの有効活用として、成分の生理活性度や分子構造解析のために分取用の液体クロマト装置も脚光をあびてきている。液体クロマトグラフ(装置)は現在,世界中の研究機関に所狭しと導入され,研究にはなくてはならない装置になり、日々稼動している。その装置の性能は導入当初と変化はないのか、劣化度合はどうなのか、実験者にとっては心配な所である。
現実的には新規導入当時に比べて年々多少とも性能(測定感度と分離性)は下がってくる。その性能の度合いを実験者が把握できれば、安心して液体クロマトグラフを利用して正確なデーターを得る事ができる。
筆者はクロマト装置を何台か壊し、そしてメーカーの技術者と協力して治し、また改良もしてきた。その度にクロマトグラフィクパラメーター(流速,感度,理論段数等)で検定してきた。現在では小型のクロマト装置は自作するようになった。この際も上述の検定法が必要であった。このような経験を基に,本書はその判定技法をメインとして第 2 章に記したけれども、液体クロマトグラフィーを現在使用している実験者、今後活用しようとされている方々にも理解しやすいように、第 1 章で液体クロマトグラフィーの序章を記し導入部とした。第 3 章はクロマトグラファーのノウハウで、日々の実験ですぐに利用できそうなクロマト技法のコツを記した。
第 4 章では自らの HPLC をグレードアップしたい際の具体的な技法の説明を記した。
クロマトグラフィーの理解力を上げたり、知識を広めたりするためにクロマト解説、クロマト Box も挿入した。(本書序文より)
- 前巻
- 次巻
目次
第1章 液体クロマトグラフィーの序章
第2章 HPLCは正常か
第3章 クロマトグラフィーのノウハウ
第4章 HPLCをグレードアップしよう
書誌情報
紙版
発売日
2010年12月17日
ISBN
9784061543317
判型
A5
価格
定価:3,080円(本体2,800円)
ページ数
144ページ
著者紹介
関連シリーズ
-

PythonとChatGPTを活用する スペクトル解析実践ガイド
-

タンデム質量分析法 MS/MSの原理と実際
-

紫外可視・蛍光分光法
-

材料研究のための分光法
-

物質・材料研究のための 透過電子顕微鏡
-

リファレンスフリー蛍光X線分析入門
-

X線分光法
-

赤外分光法
-

X線光電子分光法
-

X線・光・中性子散乱の原理と応用
-

XAFSの基礎と応用
-

熱分析
-

近赤外分光法
-

NMR分光法
-

有機化学のための 高分解能NMRテクニック
-

分析化学
-

分光測定の基礎
-

分光測定のためのレーザー入門
-

分光装置Q&A
-

特論 NMR立体化学
-

電波を用いる分光―地球(惑星)大気,宇宙を探る―
-

絶対わかる分析化学
-

赤外・ラマン分光法
-

生命科学者のための電子スピン共鳴入門
-

若手研究者のための機器分析ラボガイド
-

光散乱法の基礎と応用
-

光学実験の基礎と改良のヒント
-
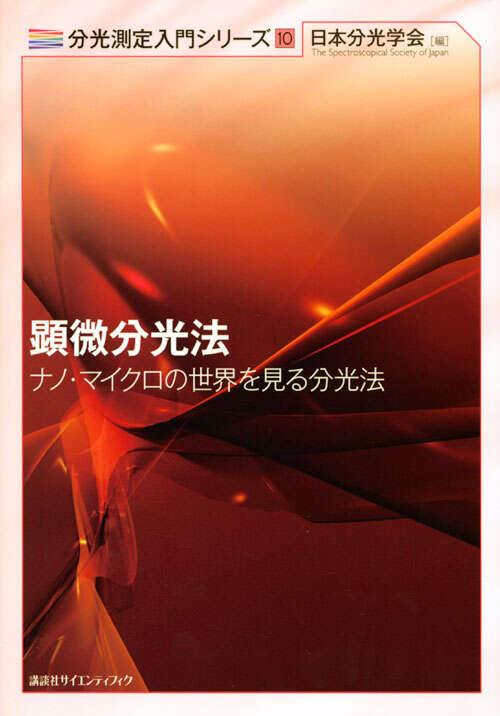
顕微分光法-ナノ・マイクロの世界を見る分光法-
-

機器分析
-

核磁気共鳴分光法
-

可視・紫外分光法
-

ラマン分光法
-

よくある質問 NMRの基本
-

よくある質問 NMRスペクトルの読み方
-

やさしい分析化学
-

バイオセンシングのための水晶発振子マイクロバランス法
-

なっとくする分析化学
-

なっとくする機器分析
-

スペクトル定量分析
-

X線反射率法入門
-

X線・放射光の分光
-

NMR入門プログラム学習