星海社新書作品一覧

大谷マーケティング 大谷翔平はなぜ世界的現象になったのか?
星海社新書
野球界と広告界、2つの世界を制覇した大谷翔平の秘密に迫る
大谷翔平のメジャーリーグでの活躍は毎日のようにニュースになり、多くの史上初記録を生み出しています。しかし、大谷の本当のすごさは野球界のみならず、広告界も制覇したことにあります。大谷は年俸を超える年間100億円もの広告を獲得し、今や日本では彼の広告を見ない日はなくなりました。そしてアメリカでも大谷翔平は社会現象となりつつあります。一体なぜ大谷は前代未聞の世界的熱狂を巻き起こしたのか、その背景にはいかなるマーケティング戦略があったのか――アメリカでマーケティングに携わる著者が、実体験を交えながら考察します。
*以下、本書目次より抜粋
まえがき ロサンゼルス在住マーケターから見た大谷翔平
第1章 誰が大谷翔平に熱狂しているのか
第2章 大谷はエンゼルスに何をもたらしたのか
第3章 エンゼル・スタジアムを彩った広告たち
第4章 ドジャース移籍で大谷のバリューはどれだけ上がった?
第5章 大谷翔平広告の批判
第6章 大谷翔平から見るアメリカ経済
第7章 大谷翔平をマーケティングで活かす方法
あとがき

音響監督の仕事
星海社新書
レジェンドが語る「音響監督」の黎明期から現代まで!
『鉄腕アトム』でアニメーションの世界に入り、1967年に『リボンの騎士』で音響監督デビュー。「音響監督」という言葉がなかった時代からアニメとともに歩み、音づくりの現場に立ち続ける著者が、いま音響監督の仕事を語る。本書を織りなす三つの〈音物語〉では「オーディション」や「アフレコ」、「声の芝居」といった役者たちが集う現場での考え方や、著者が関わった数々の名作の舞台裏、そして『鉄腕アトム』の頃の虫プロにまで遡る歴史が語られている。本書は、アニメを創り上げる数多くの人のつながりを記録する貴重なオーラルヒストリーであると同時に、アニメの音響の素晴らしさを次代に伝える一冊である。
*以下、本書目次より抜粋
まえがき アニメハック編集部
音物語1 音響監督が考えていること
音物語2 音響監督クロニクル
音物語3 音響監督はどう生まれたか
あとがき 明田川進
明田川進フィルモグラフィー 原口正宏(リスト制作委員会)

『ちはやふる』と学ぶ かるた名人の集中力
星海社新書
かるた名人に学ぶ、勉強にも仕事にも使える集中力の極意
「かるたは集中力を身につける上で最高の教材である」
競技かるたで名人戦3連覇を果たし、かるたで養った集中力を駆使して京都大学首席合格を果たした粂原圭太郎名人はこう語ります。一枚の札への短期的な集中、試合前に札の配置を暗記する中期的な集中、一日がかりの試合で最後まで本気を出す長期的な集中――この3つの集中力があれば、勉強や運動などあらゆることに本気で向き合い、結果を出すことが可能です。本書では、かるた選手のみならず誰でも応用できる集中力のエッセンスを、かるた漫画の金字塔『ちはやふる』の名シーンを実際に見ながらわかりやすく深く解説します。
*本書目次
はじめに かるたと集中力の深い関係
勉強にも応用できる集中の力
集中力に人生を救われた経験
なぜ集中力を鍛えるのにかるたが最高なのか
集中力とは何か──学術的視点からの定義
集中力は誰でも鍛えられる
かるた名人たちの「異次元の集中力」
本書の構成について
第1章 集中力を高めるために大事なこと
集中力を高めるのに最も大事なのは「気持ち」である
気持ちは技術でコントロールできる
自分なりの理想像を作る
瞑想をする
常に成長を意識する ──「成長マインドセット」で集中力を高める──
逆境こそ楽しむ
「才能なんてない」と言う
第2章 集中力を最大限に活かす方法
姿勢を保つ
結果を集める
自分を追い込む
負けを原動力にする
どんな時でも本気を出す
数値目標を設定する
第3章 集中力を支える生活習慣のつくりかた
集中力は「その日、その瞬間」の積み重ね
集中力を持続させるには体力が大事
集中するための運動のコツ
集中するための食事のコツ
集中するための睡眠のコツ
ストレスと向き合うコツ
第4章 かるた名人&クイーンと語り合う「競技かるた最高峰の集中力」
川瀬将義・第68~70期名人に聞く集中力の極意
自見壮二朗・現名人、第71期名人に聞く集中力の極意
矢島聖蘭・現クイーン、第69期クイーンに聞く集中力の極意
おわりに

現代ホラー小説を知るための100冊
星海社新書
日本の現代ホラー小説の歴史を100の名作で辿る!
貞子を生み出しホラー界に激震を走らせた鈴木光司『リング』が刊行、日本ホラー小説大賞が創設、角川ホラー文庫が創刊――日本のホラー小説史上の重大事件が続々と発生した1990年代。出版界を覆ったこのホラー小説の高波は、令和のいま巻き起こるホラーブームまで繋がっています。その潮流を辿るため、本書では『リング』が刊行された1991年から2024年までに刊行された日本のホラー小説より、100冊を厳選しご案内。ホラー小説の世界へ深く誘う〈併読のススメ〉も加え、総計200作品以上のホラー小説をご紹介します。怪異と恐怖の文学――ホラー小説の世界に、この本とともに呑み込まれましょう!
*以下、本書目次より抜粋
はじめに
第1章 現代ホラー勃興
第2章 ベストセラーホラーの時代
第3章 世紀末ホラー黄金時代
第4章 多様化の時代
第5章 怪談文芸ムーブメント
第6章 混沌の一〇年代前半
第7章 現代ホラーの新しい波
第8章 令和のホラーブーム
評論 現代ホラーの新しい波
おわりに
現代ホラー年表

アフリカの歴史と今がわかる本
星海社新書
国連加盟国の4分の1以上が並びたつ大陸、約15億人という膨大な人口、ジャズやラップなど多彩な世界的カルチャーの「ルーツ」とされる地ーーアフリカの重要度は現在、かつてないほど高まっています。しかし地理的・文化的にアフリカから遠い日本では、残念ながらアフリカの重要性が、さらには最新の動向があまり知られていません。そこで東京大学大学院でアフリカを研究する著者が、アフリカの政治・経済・文化の現在と、その背景にあるアフリカの歴史、さらにアフリカ大陸に位置する全54カ国(国連加盟国)の紹介を通してアフリカを立体的に解説します。本書がみなさんにとってアフリカを知る第一歩となれば幸いです。
*本書目次
はじめに 人類史上1位、2位の大富豪はともにアフリカ出身!?
第1章 日本人が知らないアフリカのアツさ 文化・国際政治・経済
第1節 奴隷貿易によるディアスポラ(離散)と汎アフリカ主義
第2節 アフリカと文化
第3節 アフリカと国際政治
第4節 アフリカと経済
第2章 アフリカの歴史
第1節 前近代のアフリカ 地中海世界やインド洋世界との深い関わり
第2節 近世のアフリカ ヨーロッパ人との接触とヨーロッパ人による「点の支配」
第3節 近代のアフリカ ヨーロッパによるアフリカ「分割」
第4節 二つの世界大戦を経て独立に向かうアフリカ
第5節 戦後のアフリカ
第3章 アフリカ各国の略史と現状
第1節 北アフリカ イスラーム化とヨーロッパによる支配を経て
第2節 西アフリカ 金の交易で文明が栄えた内陸部
第3節 東アフリカ 海上交易で育まれたスワヒリ文化
第4節 中部アフリカ 独立後は多くの国で苦悩が続く
第5節 南部アフリカ 南アフリカ共和国の存在感が大きい地域
おわりに
アフリカをさらに知るためのブックリスト

21世紀のクラシック新名盤 革新者たちの絶対必聴アルバム
星海社新書
クラシックの未来を拓く名盤21+19枚
現代のクラシック音楽は、デジタル音楽配信の登場でリスナーの二極化といった大きなうねりの中にある。そんな時代にクラシック音楽の名盤はどこへ向かうのか? アルゲリッチやクレーメルの円熟した表現力から、アーノンクールやロトら古楽派の革新的なアプローチ、マケラやユジャ・ワンの清新でダイナミックな演奏、ショパン・コンクールで輝いた角野隼斗や藤田真央、グリモーの深い詩情が響くブラームスまで。新時代の感性でクラシックを再定義する天才や革新者たちが生み出した新時代の名盤を厳選。カルチャー論を交えながら名盤の魅力を余すところなく解説する。クラシックの未来を体感できる一冊がここにある。
*以下、本書目次より抜粋
まえがき
episode 1 ヴィルトゥオーゾの饗宴 アルゲリッチ、クレーメル、マイスキー、バシュメット
episode 2 古楽器のフロンティア 最後の貴族アーノンクール
episode 3 ヴルトゥオーゾを葬り去る ロトの革命、シュタイアーの技巧
episode 4 21世紀の使徒降臨 マケラ&ヤンセン
episode 5 新世紀のじゃじゃ馬ならし ドゥダメルとユジャ・ワン
episode 6 トリガーとしてのショパン・コンクール 世界がかてぃんを見つけた日
episode 7 ルカ受難曲は名曲なのか 現代音楽というラビリンス
episode 8 21世紀のディーヴァは誰だ ネトレプコ? ゲオルギュー?
episode 9 狼と暮らす女 グリモーのブラームス
配信で聴く名盤・新名盤ガイド21+19
名盤・新名盤ガイドの使い方
あとがき
参考文献

室町史の新論点 混沌の時代を読みとく研究最前線
星海社新書
室町時代の混沌を最新研究で解き明かす!
三代将軍足利義満の栄華から応仁の乱を経て戦国時代へと突入する約100年間は、政治・社会の矛盾が顕著に現れた激動の時代だった。南北朝時代初期の足利一門の軍事制度、幕府の家格、守護の権力拡大が複雑に絡み合い、戦国時代への道を開く。天皇継承を巡る「正統」の争いは幕府の介入によってさらに複雑化し、後土御門天皇の葬儀が遅れる悲劇も生じた。一方、荘園の衰退で地方へ下向した公家は和歌や古典をその他に伝えた。また、コシャマインの戦いは蝦夷地を決定的に変容させた。本書は、気鋭の中世史研究者たちが最新の研究と史料をもとに、室町時代の混沌を鮮やかに解き明かした論稿集である。
*本書目次
はじめに
論点1 南北朝動乱初期に軍事制度はなかったのか? 漆原徹
論点2 室町幕府の家格とはどのようなものだったのか 小久保嘉紀
論点3 室町殿はなぜ明から日本国王に冊封されたのか 秦野裕介
論点4 室町殿御分国と東国との「国堺」はどのような役割を果たしたのか 花岡康隆
論点5 “京都の警備担当”室町幕府侍所とはどのような存在だったのか 松井直人
論点6 室町幕府と鎌倉府はどのような関係にあったのか 亀ヶ谷憲史
論点7 政治都市鎌倉は鎌倉幕府の滅亡とともに衰退したのか? 駒見敬祐
論点8 「守護」とは何か 今岡典和
論点9 隣国守護の役割と活動 川岡勉
論点10 安芸・若狭武田氏は甲斐武田氏に比べマイナーか 笹木康平
論点11 コシャマインの戦いと武田信広 新藤透
論点12 室町期の荘園制はどのようなものであったのか 廣田浩治
論点13 室町時代の天皇はどのように継承されたのか 秦野裕介
論点14 後土御門のたび重なる苦悩となかなか挙行されなかった葬儀 渡邊大門
論点15 室町期の公家が地方に下向した実像を探る 渡邊大門
おわりに

統計で問い直すはずれ値だらけの日本人
星海社新書
この統計データを見なければ「日本人」は語れない!
日本人は世界でも変わっている、とはよく言われる。しかしデータを丹念に調べたとき、どのような意味で「はずれ値」なのか。膨大な統計データを収集・分析し、社会経済動向を追い続ける伝説の統計サイト『社会実情データ図録』の管理人である著者が、「日本人」を真正面から分析したのが本書である。経済成長と寿命が軌を一にするはずの近代の法則からもはずれ、大食・肥満に不思議なほど縁遠く、無宗教なはずなのに霊的感度は高く、夫婦関係は良好なはずが夫婦間の誠実さは重視せず、社会保障を政府に期待しない。そして世界で唯一「思いやり」を異様に重視する日本人とはいったい何者なのか。縦横無尽に統計を読み解く唯一無二の日本人論である。
*以下、本書目次より抜粋
まえがき
第1章 日本人の実力はいかほど
第2章 しみこんだ日本人の省エネ体質
第3章 日本人のパッシブ志向を示すいくつものデータ
第4章 信じるのはちがう! 信じないのもちがう!
第5章 風変わりな男と女の国
第6章 政治や国家、敬してこれを遠ざく
第7章 世界とのズレが大きい「日本人の常識」:じつは未知の可能性
おわりに

東大の良問10に学ぶ日本史の思考法
星海社新書
「日本史の思考法」が学べる東大入試問題を堪能する
東大日本史は「日本史の思考法」を学ぶのに最適な題材です。東大はこれまでの入試問題を通じて、枝葉末節の暗記にとらわれない歴史の大きな流れを理解する重要性を世に問うてきました。本書では、そんな東大日本史を徹底的に研究した東大生が選りすぐった10問で、古代から現代までの日本史を見ていきます。各章前半の導入編では、予備知識のない方でも東大の議論がわかるように前提となる日本史知識をまとめました。そして各章後半の問題編では、東大日本史名物「史料読解」を実際に解いて、東大が問いかける問題意識や日本史の重要ポイントを詳細に解説しました。この1冊で東大レベルの日本史の考え方をマスターしましょう!
*本書目次
はじめに 日本史を学ぶとは
第1問 古代 外交における本音と建前 2003年第1問
第2問 古代 肩書きだけの上司による地方支配 2016年第1問
第3問 古代 予備校の模範解答を批判せよ 1983年第1問
第4問 中世 諸刃の剣としての武士 1987年第2問
第5問 中世 巧みすぎる室町幕府の財政 2018年第2問
第6問 近世 江戸時代に天皇家が存続した理由 1994年第3問
第7問 近世 生類憐みの令を評価せよ 2022年第3問
第8問 近世 琉球王国の生き残り戦略 2006年第3問
第9問 近代 伊藤博文の側近として憲法を作り上げよ 1989年第4問
第10問 近代 日本国憲法の弱点を検討せよ 2005年第4問
おわりに

棚橋弘至、社長になる プレジデントエースが描く新日本プロレスの未来
星海社新書
棚橋弘至が語る社長就任劇と新日の経営戦略、プロレスの未来
新日本プロレス「100年に一人の逸材」棚橋弘至、新日本プロレス社長に│2023年末の衝撃的な社長就任から1年余りを経た現在、社長・棚橋弘至はどのような日々を送り、経営者としていかなるビジョンを抱いているのか? 社長就任の知られざる舞台裏から選手兼社長としての日常、プロレスW字回復への逆転戦略、世界展開への意気込み、選手引退後のキャリア構想、そして尊敬する木谷高明オーナーとの経営問答まで、社長・棚橋弘至の頭の中が1冊で丸ごとわかる、全プロレスファン必読の仕事論にしてプロレス論!
新日本プロレスオーナー・木谷高明との特別対談収録!
*以下、本書目次より抜粋
はじめに 年に一人の逸材、19年ぶりの選手兼社長になる
第1章 社長就任まで
第2章 社長・棚橋弘至から見える新日本プロレスの現在地
第3章 現役レスラー社長の日常
第4章 これからの新日本プロレスが目指すもの
第5章 新日本プロレスの社長とオーナーが考えるプロレスの未来 木谷高明×棚橋弘至

世界観を創る クリエイターのための設定・考証入門
星海社新書
アニメーションの最前線を支える頭脳は「世界観」をこう考える!
アニメや漫画、小説や映画といった創作に必要不可欠な「世界観」の設定・考証ーー本書は、アニメーションの現場を支える第一人者による画期的な「世界観」入門である。「大きな噓を一つだけ/始めに地図ありき/リアルと心のリアル」といった数々の鉄則にもとづき、作品世界を整合的に創りあげる「思考の流れ」を詳述。キャラクターや物語・ジャンルの魅力を引き出し、監督や脚本家のクリエイティビティを加速させ、納期や予算といった条件さえも味方につけるプロフェッショナルの流儀を語り尽くした本書は、次代のクリエイター必読の書であると同時に、「架空世界」という真髄を味わい直すための一冊である。
*本書目次
序・はじめに
第1章 世界観と世界観考証
1・1 哲学における「世界観」と創作作品における「世界観」の違い
第2章 制作スタッフに与える指針
2・1 アニメスタッフの仕事の役割
2・2 オリジナル作品の企画開発
2・3 オリジナル作品のためのヒントを用意する
2・4 世界の作り方
第3章 神は細部に宿る
3・1 キャラクターの感情線と世界設定のリアリティライン
3・2 本物と心のリアリティ
3・3 現実の物語を扱う時
3・4 ネタ元を知る
3・5 原作のコマとコマの間を埋める
第4章 アニメ業界の分業
4・1 脚本作成のアイデア出し
4・2 資料を探す
4・3 外付け頭脳としての鉄則
4・4 オーダーと納期と予算
第5章 考証の歴史と考証家のなり方
5・1 設定考証の役割と誕生
5・2 どうやってなるか
付録 世界設定を愛する人のための書籍リスト
参考文献

スマホはどこへ向かうのか? 41の視点で読み解くスマホの現在と未来
星海社新書
スマホの過去、現在、そして未来を繫ぐ41の視点
スマートフォンの登場は人類史上前例のない新たなライフスタイルへの革新をもたらし、社会そのものを根底から変えてしまった。この巨大産業の軌跡を丹念に追い続けてきた気鋭のITジャーナリストが、2007年のiPhone登場から2025年までの18年間を独自の視点で考察し、巨大であるがゆえに摑みきれない「スマホという産業」と「スマホが世界にもたらしたもの」、そして「スマホの次に来るものは何か」について、41のテーマから分析する。AIを初めとする劇的な技術革新が進むなか、果たして「ポスト・スマホ」は存在するのか。本書を以て断言するーースマホの未来から、人類の未来がわかる。
*以下、本書目次より抜粋
はじめに
1 スマホの「基本」を理解する 歴史と仕組みの成り立ち
2 スマホの「多面性」とは 技術革新とライフスタイルの融合
3 スマホ時代の「光と影」 駆逐と共存、そして未来
おわりに

出口治明の 歴史と文化がよくわかる旅の楽しみ方
星海社新書
世界80ヶ国以上を旅した教養人が語る旅の楽しみ
教養を作るのは人・本・旅であるーー常々こう語る著者・出口治明がいかに旅を楽しみ、学んでいるのかを、記憶に残った旅の数々を通して語ったのが本書です。世界80ヶ国以上の旅を楽しんできた出口さんの経験をもとに、「旅に荷物はいらない」「目的は一つで十分」といった旅の心得から観光名所の知られざる歴史、日本では知名度が低いけれども魅力的な穴場、世界と日本の観光業の違いまで、旅から得られた発見をこの一冊に詰め込みました。みなさん一人一人が旅を楽しみ、旅からの学びを得るヒントになれば幸いです。
*本書目次
はじめに
1 僕の旅の仕方
2 フランス
3 イタリア
4 ポルトガル
5 チェコ
6 オーストリア
7 ポーランド
8 スペイン
9 ペルー
10 連合王国(英国)
11 ドイツ
12 ギリシャ
13 トルコ
14 中国(承徳)
終 章 日本の観光業の未来のために
おわりに

中東紛争 イスラム過激派の系譜からガザ危機・シリア革命の深層まで
星海社新書
混迷の中東情勢を読み解くポイントを総説する
中東はこの1世紀、抗争に次ぐ抗争によって混迷の中にある。そんな中東紛争の深層を、国際情勢を裏で動かす諜報機関と過激派組織から分析するのが本書である。モスレム同胞団を起源とするイスラム・テロ・ネットワークがアルカイダやイスラム国の誕生につながり、イスラエルのパレスチナ弾圧に抵抗するためファタハやハマスなどの武装組織が結成され、イラン革命政権は「革命の輸出」を掲げて中東全域のイスラム過激派を支援した。そして、これらの出来事は相互に絡み合い、複雑に影響し合っている。表面的なニュースや国際政治の建前だけでは分からない中東情勢を理解するための、インテリジェンス分析による中東論。
*以下、本書目次より抜粋
はじめに
序 章 トランプ大統領が搔きまわす中東
第1期トランプ政権の中東政策 親イスラエルと反イスラム、陰謀論のエコーチェンバー
第1部 激動の中東 2024~2025
第1章 シリア独裁を倒した元ジハード戦士・シャーム解放機構の奇跡
第2章 レバノン・ポケベル爆弾の衝撃とイスラエル情報機関・モサドの暗躍
第3章 イラン破壊工作機関・コッズ部隊&ヒズボラVSイスラエルの攻防
第2部 現代につながる20世紀中東戦国史
第4章 イスラム・テロ・ネットワークの現代史
第5章 イスラエル建国と中東紛争の本丸・パレスチナ問題
第6章 パレスチナ・ゲリラたちの戦い
第7章 イラン革命とホメイニの暗殺部隊
第3部 蠢く地下テロ水脈
第8章 アルカイダとつながる反米イスラム人脈
第9章 ハマス軍事部門の真相
第10章 イスラム国成立とスンニ派過激主義の盛衰
終 章 ガザ戦争 ハマス、イラン、イスラエルの“死闘”の深層
コッズ部隊司令官・ソレイマニの暗躍
コッズ部隊の工作は「革命の輸出」のため
2023年ハマス奇襲の衝撃
なぜ奇襲が成功したのか
イスラエルとイランの対立は続く

逆転合格東大生の受験お悩み相談
星海社新書
現役受験生から寄せられる勉強の悩みを東大生作家が解決!
「勉強中にスマホばかり見てしまう」「テスト当日に緊張して実力が出せない」「浪人するか第二志望で妥協するか」……全国の学校や予備校で勉強法を教える著者のもとには、学生さんや親御さん、浪人生の方からさまざまな受験相談が寄せられます。その中から特に多くの方が悩んでいること、毎年相談されることを精選し、偏差値35から逆転合格した経験をもとに40以上の受験相談に答えました。勉強の意義から勉強習慣の作り方、保護者の受験への関わり方まで、時に優しく時に厳しく受験の真髄を語った本書が、みなさんの受験の指針となることを願っています。
*以下、本書目次より抜粋
はじめに
第1章 受験や人生が不安なあなたに
第2章 受験に向けた勉強習慣の作り方
第3章 受験勉強の意味と勉強のコツ
第4章 後悔しない進路の決め方
第5章 もし受験に失敗してしまったら
第6章 受験生の保護者が悩んでいること
おわりに

オンライン教育で日本はどう変わるのか?
星海社新書
新時代の進路選択「オンライン教育」の全貌!
コロナ禍を機に広まった「オンライン教育」は現在、中高・予備校・大学での学びを革新しつつあります。既に全国290万人の高校生のうち30万人が通信制高校に通ってオンライン主体の学習を行っており、近い将来には3人に1人がオンライン通学する社会が訪れると予想されています。しかし、そんなオンライン教育革命の実態は関係者以外にあまり知られていません。そこで、多数の学校に携わる教育ベンチャーを経営する著者が、通信制高校の仕組みから動画授業やオンラインコーチングのメリットとデメリット、オンライン教育時代の社会変化まで包括的に論じた、オンライン教育のすすめが本書です。
*以下、本書目次より抜粋
はじめに オンライン化が教育を、社会を変える
第1章 オンライン教育との出会い
第2章 「通信制高校」で飛躍的に広がるオンライン教育
第3章 オンラインの学びのメリットとデメリット
第4章 オンライン教育ではどんな大人に育つのか
おわりに オンライン教育の課題

刑事コロンボ研究 上
星海社新書
稀代の異能批評家・菊地成孔による21世紀の「刑事コロンボ」研究。その決定版。
「刑事コロンボ(Columbo)」は1968年から2003年までの35年間、全69エピソードからなる、20世紀のTVドラマ史上、屈指の傑作として、世界中で熱中され、研究され、再放映され続けている名番組である。本書は21世紀の批評話法によるこの番組の研究成果であり、新鮮にして最大級の賛辞と愛を送る方法を模索する実験は、転倒と迂回を芳醇に含む、つまりは倒叙形式の書である。そして厳密には「続・倒叙形式の書」がより正しいことは言うまでもない。
*本書目次
頭語に代えて
前書き1 「〈倒叙〉とは何だったのか?」
前書き2 「続・〈倒叙〉とは何だったのか?」
前書き3 「弱度の推奨」
第1章 各 論
第1節「パス概念」
第2節「原題/邦題/ナ題」
第3節「リサ概念」
第4節「アイス概念」
中書き
~あなたが熱狂的に求めるかも知れない、
或いは〈手に取ると激しく後悔するのではないか〉という
奇妙な予感に囚われているかも知れない、
或いは全く欲望を持てないかも知れない「下巻」に向けて~

現代日本の医療問題
星海社新書
日本医療の諸問題を一冊で総覧する
日本の医療は世界的に高く評価されている一方、近年ではさまざまな問題を抱えていることも事実です。医師不足、医薬品不足、マイナ保険証、医療費増大、美容医療、終末期医療、医学部受験の過熱……こうした医療の諸問題について専門的な言説は数あれど、今後必要とされる医療制度改革に向けて、国民一人一人が日本の医療を考え、議論するための一助として、包括的な見取り図をいま改めて社会に発信する必要があります。そのために、現役医師にして医療研究者である著者が豊富なエビデンスをもとに日本医療の現在地を分析し、将来への提言とともにまとめたのが本書です。
*本書目次より抜粋
はじめに
第1章 日本医療の現在地
第2章 現代医療のトレンドと社会
第3章 医療DXの課題と展望
第4章 高齢化社会とこれからの医療
第5章 未来に向けて必要な改革
おわりに

東大1年生が学んでいること
星海社新書
東京大学式「教養」を20以上の講義で徹底解説!
教養の本質は「知識を結びつけること」であるーー東大総長(当時)がこう語るように、東大では入試でも授業でも、知識の多さではなく知識の活かし方を重視しています。そんな東大式教養の真髄が平易にまとめられた1年生向けの授業や演習のエッセンスを現役東大生が解説し、みなさんに東大講義を追体験いただけるのがこの本です。古代ギリシャ語を学ぶことで英語やフランス語をより深く理解する、高校世界史を批判的に検討しつつ国際関係史の最新学説を学ぶ、体力測定の統計を分析した上で運動をする……等々、学問の活かし方がよくわかる東大の授業をご堪能ください。
*本書目次
はじめに 東大が考える「教養」とは何か
第1章 語学
英語ライティング 1年生から英語で論文執筆
英語スピーキング 論理的思考力を英語で鍛える
フランス語 語学知識にとどまらず、第二外国語で世界の広さを体感する
トライリンガル・プログラム(TLP) 1年で実用レベルの外国語を習得
古典ギリシャ語 古代の哲学・思想を原語で味わう
ヘブライ語 まったく知らない別言語を学んで分かったこと
第2章 文系
国際関係史 高校世界史と大学の歴史学の違いとは?
社会学 東大式「社会学」とは何か
言語学 身近な言葉を学問でより深く広く調べ尽くす
心理学 東大生と研究者の裏の読み合い
初年次ゼミナール文科 1年生で学ぶ論文の書き方
第3章 理 系
力学 4ヶ月で高校・大学レベルの物理学を一気に学ぶ
数理科学基礎・微分積分学・線型代数学 大学数学は高校と何が違うか?
現代工学基礎 東大流イノベーションの作法
社会システム工学基礎 首都を支えるインフラの裏側
総合工学基礎 錚々たる第一人者たちに学ぶ航空宇宙学
認知科学 あこがれの研究者に学ぶ脳のメカニズム
第4章 学際分野
コンサルティング アクセンチュア×東大で学ぶコンサル実践
体育 東大生はスポーツから何を学ぶか?
ゲームデザイン論 ゲーム研究を踏まえて東大ならではのゲームを作る
森林環境資源学 さまざまな学問で森林を多面的に知る
サウンドデザイン入門 第一線のクリエイターから教わって実際に音を作る
おわりに
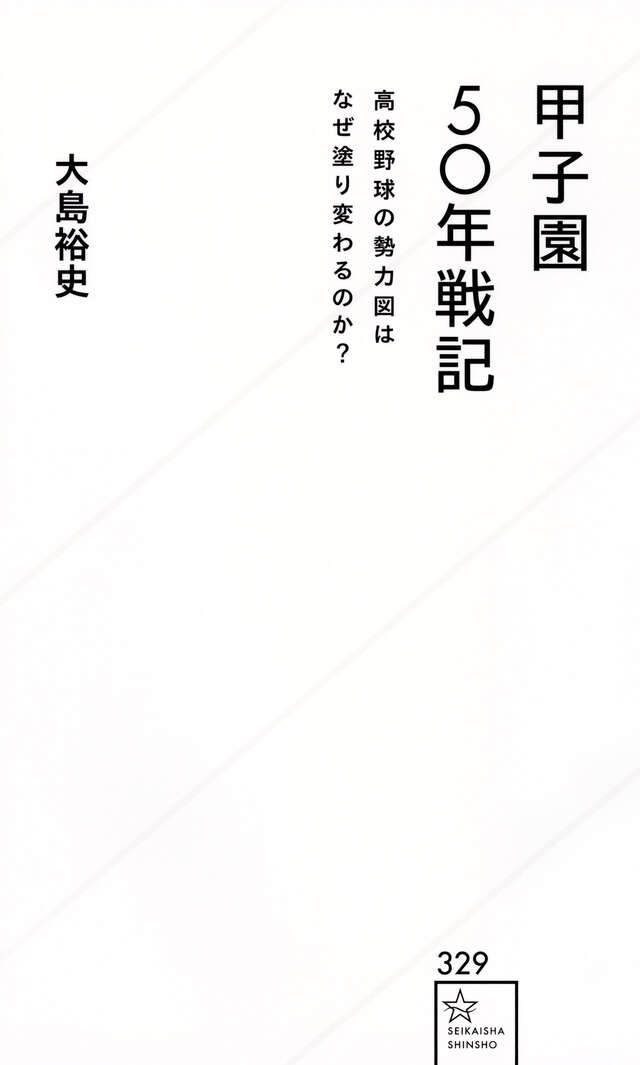
甲子園50年戦記 高校野球の勢力図はなぜ塗り変わるのか?
星海社新書
金属バットの導入で何が起きたか?
1970年代までの甲子園は、公立校が私立校に対して互角以上の成績を収めた時代だった。しかし、2000年以降、夏の甲子園大会で、公立校で優勝したのはわずか1校にとどまり、準優勝も1校のみで公立校はなかなか勝てなくなった。このような智弁和歌山、大阪桐蔭、常総学院、明徳義塾などの強豪校が台頭する私立優勢の時代は、どのようにして始まったのか。1974年に金属バットが導入されたことが、高校野球の競技環境にどのような影響を与え、私立優勢の時代をもたらしたのか。球史に名を刻む名勝負を通じて、半世紀にわたる甲子園の勢力図の変遷を探る。
*本書目次より抜粋
はじめに ~第106回の夏
第1章 金属バット時代の始まり ~申し子・原辰徳の登場
第2章 49代表時代の幕開け ~箕島、池田の全盛期
第3章 PL学園黄金時代 ~ライバルとなった公立校
第4章 団塊ジュニアの時代 ~古豪復活の一方で新勢力も続々登場
第5章 新世紀を前に ~強豪私立の時代へ
第6章 21世紀の甲子園 ~大阪桐蔭時代の一方で
第7章 高校野球100年 ~歴史の扉が開いた
終 章 高校野球のこれからを考える
日本野球の草の根を支える高校野球
変わりゆく高校野球と変えてはいけない価値観
巻末データ 全国高校野球 歴代優勝校 1974ー2024