創文社オンデマンド叢書作品一覧

ルネサンスの世界
創文社オンデマンド叢書
「ペトラルカと云えば人は直ちにヒューマニストでありルネサンス人であるとする。しかし、ブルクハルト以後十九世紀後半より二十世紀三十年代前半までかけて展開されたルネサンス概念論争によってルネサンス概念は非常に深められた。したがってペトラルカ研究にもかかる論争の結果が影響をもたずにはおかなかった。何となればペトラルカに関する歴史的研究の中心問題は彼に於いて如何にルネサンスの本質が現れているかという点にあるとすれば、かかる概念論争の問題は又ペトラルカ研究の問題でもあるわけである。しかるに一九三〇年代まで諸雑誌を賑わしていた概念論争もその後つまり新たな展開を示していないのでわれわれは一応この論争の結果を整理して今後のルネサンス研究への立場を定める時期に到達したのではないかという感を抱かせる。小論の目的はかかる論争の結果を考慮しつつペトラルカとルネサンスとの関係についての二三の問題について考究し、ペトラルカ研究への緒をあたえんとする点にある」(「序」より)
【目次】
論説
ペトラルカとルネサンスの問題
一 序
二 ペトラルカとルネサンス・ロマン主義
三 ルネサンスの概念 特にその二重性
四 ペトラルカに於ける再生(Rennovatio)の理念
中世イタリア・コムーネ研究の動向 オットカール及びプレスナーの所説について
一 序言
二 オットカールの所説
三 プレスナーの所説 Castello の性質
四 プレスナーの所説 十三世紀に於ける地方住民の都市移住の性質
五 結言
ブルクハルトの世界観
一 序言
二 浪漫的ドイツ的生
三 イタリアの発見 悲観主義の問題
四 倫理的生 理想と現実の分裂
五 異教的生 神の問題
六 ブルクハルト
ブルクハルトに於けるルネサンス概念
一 序
二 ブルクハルトに至るルネサンス概念 フランス的文化概念とドイツ的様式概念
三 ブルクハルトのルネサンス概念
一 その二重性
二 スタンダールとの関係
三 ミシュレとの関係
四 様式概念と文化概念の関係
四 結論
イタリア文化理解のために
人文主義
雑纂
シチリアについての感想
戦後のルネサンス研究 ファーガソンの著書を中心にして
あとがき 井上智勇
編輯後記 会田雄次 衣笠茂
塩見高年氏略歴・主要業績表

ヘブライズム法思想史の研究・序説(関西学院大学研究叢書)
創文社オンデマンド叢書
唯一なる神ヤハウェの民となる意味と精神、申命記の思想的枠組から発したヘブライズムの法思想を読み解くための基本図書。
モーセ的伝統から古代イスラエル社会における法と宗教の関係を読み解き、その後の展開を跡づける。
【目次】
〔正篇〕 序説
第一部 法源としての旧約聖書をめぐって
第一章 聖書理解の二面性
第一節 聖書の批判的理解
第二節 聖書の信仰的理解
第三節 二つの理解の相関性をめぐって
第二章 ユダヤ教の律法正典観
第一節 ユダヤ教の基本教理
第二節 ユダヤ教に於ける律法観
第三節 ユダヤ教に於ける「律法」の内容
第三章 モーセ五書の批判的理解
第一節 モーセ五書に対する批判研究史の概観
第二節 近東的世界観に基づくモーセ五書理解
第三節 モーセ五書を構成する主たる史料の概要
むすび
第二部 ヘブライ法に於ける法神授の思想をめぐって
序論
第一章 トーラーの語義をめぐって
第一節 旧約に於けるトーラーの意義
第二節 ユダヤ教に於けるトーラーの理解
第三節 類似術語をめぐって
第四節 トーラーの性格
むすび
第二章 立法者モーセと出エジプトとをめぐって
序説
第一節 出エジプトをめぐって
第二節 「出エジプト」に見るモーセ像
第三節 時間の観念をめぐって
第四節 補説 トーラーとホフマーとの関連をめぐって
むすび
第三章 契約の観念をめぐって
序説
第一節 用語をめぐって
第二節 対人間の契約をめぐって
第三節 神と人との間の契約
第四節 契約の本質をめぐって
おわりに
〔附篇〕 法思想史学とは何か 松尾助教授の見解に寄せて
著者略歴
著者主要論著
著者遺影(巻頭)
あとがき

ドイツ中世農業史
創文社オンデマンド叢書
ドイツの中世の農村は、どのように発展し、経済に、都市に、国家運営にどのように関わっていたのかを、中世経済・法制家が解き明かす。
一 基礎(太古代)
A 所有と保有の関係
B 農業の技術的側面
二 大莊園の完成(民族大移動よりカロリング朝の終末まで)
A 所有及び保有の関係
B 農業における技術的進歩
三 封建時代の農制(カロリング朝の終末より中世の末期まで)
A 所有と保有の関係
社会経済史家としてのゲオルク・フォン・ベロウ
訳者後記
再版校訂者あとがき

螢草
創文社オンデマンド叢書
「縁側近くの庭先で泰山木が咲いている。梅雨曇りの思い空を支えて、木蓮に似た盃状のこの大きな白い花は、軒先から程遠からぬところで豊かな幅の広い花びらをひらいているが、匂いは溢れて、部屋の真中にぽつねんと坐っている私の皮膚にまで深くしみてくる。
木斛や松などと一緒に、東向きの縁側に沿ってならんでいるのだが、ここで花を見るのは始めてである。家へ入るのに、隣の家の向う横についている細い貝殻道を通って迂廻して来なければならない。その隣の家の門あたりまでくると、花の匂いはもう私に呼びかけてきた。
・・・
戦争中でもこのように穏やかだったのだろうか、と思った。
この内海の、平凡な、単調な風景は、自分の家の池のように親しいのであったが、長い戦争の歳月は、苛立たしいほどの空白を私に押しつけてくる。それはあまりにかたくなで、眼前のこの内海に対する私の感覚が、屡々錯覚であるかのような戸惑った思いを抱かせる。私は、なにやら違った歳月の中を歩いてきた旅人のように、遠慮深い眼で、久しぶりの海の青さに見とれていた。」(「序の章」より)
【目次】
序の章
轉身
螢草
柿ノ木坂
落落の章
あとがき

鎮魂曲 短篇集
創文社オンデマンド叢書
「作家にはいつも人生の大きな問題で騒がしい言をたてる人があり、また好んで身辺さじに眼をとめて、さりげなくかたるタイプがある。そんないわば小さい作家の小さい作品にしばしば私たちが深く心を動かされるというのも、つまり私たちがパスカルのいう葦の葉で、ささやかな人生の悲喜にもうち砕かれたり、心おどらせたりする存在だからにちがいない。結城君はこのささやかなものを大切にし、その一本一本の糸をたどり織りあわせて、入念で美しい人生図を浮上させる名人だ。見かけはあくまで燻銀のように光を沈めて典雅ななかに、時の思いがけないパセテッィクな慟哭を迸らせるものがあるのは、氏が熱い浪漫家の夢を心の奥に秘めていて、いつもつねに死と隣り合いで住んでいるからであろう。一行一行を遺書のつもりで書くことはこの作家の戒律であるらしい。この寡作の良心の作家の久しぶりに世に問う作品集が少しでも多くの人の眼に触れることを願わずにいられない」(底本・オビより)
【目次】
「鎮魂曲」
「湖畔」
「夜の庭」
「インドネシアの空」
「木蓮」
あとがき
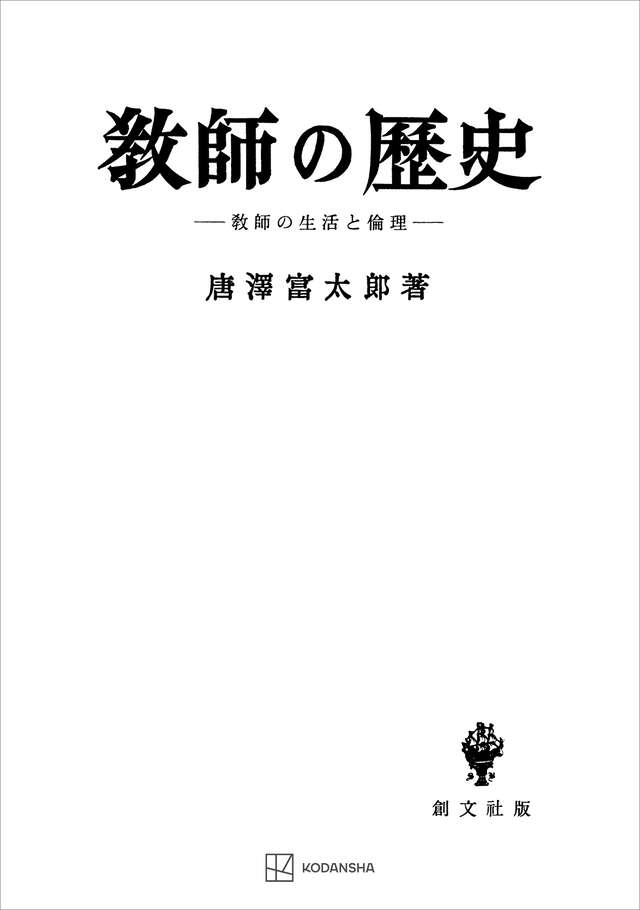
教師の歴史 教師と生活の倫理
創文社オンデマンド叢書
教師は「労働者」なのか、「天職」なのか。明治以降の教師の歴史を具体的にかつ俯瞰的に、また詳細に観察することで、教師のイメージと実際の変遷をあきらかにする力作。
「教師の問題が現代ほど活発に取り上げらた時代はかつてなかったし、また教師自身の団結が、現代ほど強くなされた時代もなかった。これらはいずれも時代的必然性のもとに起こってきた現象であるといわなければならない。このような時代に、教師は果たしていかなる教職者としての倫理を構成し、いかなる心構えをもって進んでいくべきであろうか。この問題を究明していく際に、一つの重要な手がかりを与えてくれるものは、何といってもその現代に至るまでの歴史であると考える。本書はこのような課題に答えて、教師の生きた生活変遷史を、しかもこれを回顧録や自叙伝、文学作品などおも能う限りほうふに取り入れて、その実態を把握したいと試みたものである」(「序」より)
【目次】
序
I 転換期の教師像 師匠より教員へ
II 士族的教師像 士魂と師魂
III 師範タイプの形成 森の師範学校令と教師像の確立
IV 士族階級より農民階層へ
V 女教員の登場 近代職業婦人としての女教員
VI 教員の職業人化
VII 経済と教員思想問題 抵抗の教員運動
VIII 政治的・軍事的権力下の教師
IX 戦後の教師
X 現代教職者の倫理と課題
XI 新しい日本の教師像
結語
附録I 経済界の変動と師範学校入学競争率ならびに教員過不足の変遷
II 師範生活の思い出
III 小学校教員に関する年表
參考文献
索引

学生の歴史 学生生活の社会史的考察
創文社オンデマンド叢書
「学生は時代を象徴する。
(略)
幕末より明治劈頭の近代日本形成期において、彼等は、正に崩壊に瀕した封建的権力の強圧と植民地化の野望を蔵した欧米諸国の重圧の中にあって、これにプロテストすべく闘ったのであり、その後の近代国家としての日本が、目ざましい発展を遂げつつあるときは、常にその発展の先駆けをなした。
この時代の学生は、いわば日本の資本主義の隆盛に赴く途上におけるチャンピオンであり、正に「よき時代」の「よき学生」であった。すなわち彼らは外国文化の担い手として、新しい国家の官僚として、インテリゲンチャとして、資本主義社会の指導者として生長し、特権階級として尊敬された。しかし大正期に入ると、日本の資本主義に行き詰まりを生じ、ここに社会が二つの階級に分裂し、この分裂とともに学生の悩みも深刻となった。更に昭和期に入るや、この資本主義の行き詰まりは、いよいよ軍国主義を喚起し、軍閥による強大な圧力の前に、遂に彼等のレジスタンスもむなしいものとなってきた。
思えば昭和二十年をどん底として、その前後数年間、学生は全く戦争の犠牲となって、灰色にぬりつぶされた青春を送った。そして終戦後においては、急激に過去数年間の真空圏内の生活から、自由の大地におし出され、却って自己を喪失したかの如く、的確な目標もつかみ得ないままに、或いは虚無的、享楽的となり、或いは哲学に人生のよりどころを見出そうとし、或いは社会科学研究にと、暗中に手探りしつつ、自己の主体性を得ようと歩んで来た。
(略)
学生生活の実態を明らかにしようと意図した本書においては、多くの回想録や自伝を取り入れて、当時を語らしめた。また、す半を挿入して、その情景を髣髴させようとした。その他聞き書きを入れてより具体化しようと試みた。」
【目次】
序
I 藩政末期の学生
II 明治前期の学生
III 明治中期の学生 近代学生の成立
IV 明治三十年代の学生
V 女子学生の登場
VI 日露戦争以後及び大正期の学生
VII 資本主義の発達と技術学生・実業学生
VIII 経済界の変動と入学競争率・就職率
IX 昭和初期における就職難と学生思想問題
X 戦時下の学生
XI 戦後の学生
XII 新しい学生像樹立のために
学生に関する年表
参考文献
索引

日本法制史概要
創文社オンデマンド叢書
「日本法制史学は、日本における法制の変遷発達を研究する学問である。それが歴史学であることは疑いないが、法制の歴史を対象とするものであるから、それはまた広義の法学の一部門をなすものとされている。・・・
古くなら時代頃には、全面的に中国大陸法系の影響を受けたが、その後次第に古代の固有法が復活発達して、独自の体系を樹立した。明治以後は、欧州系の法律、ことに、ローマ法体系の法制を継受したが、終戦後は、英米法系の影響を受けることが多い。・・・
法制を発展の過程において捉えると云うことは、法制が時代によって変遷していることを前提している。・・・
法制史はまとまった全体としての法が時代を逐って変遷していく過程を明らかにしようとするものであるが、両者を統一するものとしての、時代区分の重要性が指摘されなければならない。すなわち上に述べたように、法制史上、比較的変遷の緩い安定した時期があるが、このような性格を持つ時期の法、すなわちまとまった全体としての法を中心として、一つの時代を認むべきなのである。かくして、法制史上にいくつかの比較的安定した時期を認めて、これを一つの時代となし、これを前時代的発展における地位を表現するのにふさわしい名匠を付すべきである」(序説より)
【目次】
目次
序説
[第一部]
第一篇 上代
第一章 総説
第二章 法源
第三章 国家の成立及び発展
第四章 国家の組織
第五章 社会階級
第六章 財政制度 附、軍事制度
第七章 司度制度及び刑法
第八章 人法
第九章 財産法
第十章 身分法
第二篇 上世
第一章 総説
第二章 法源
第三章 天皇
第四章 統治組織
第五章 社会階級
第六章 財政制度
第七章 軍事、警察及び交通制度
第八章 司法制度
第九章 刑法
第十章 人法
第十一章 物権法
第十二章 債権法
第十三章 親族法
第十四章 相続法
第三篇 中世
第一章 総説
第二章 法源
第三章 天皇及び朝廷
第四章 庄園及び本所
第五章 武家の棟梁と封建制度
第六章 中央官制
第七章 地方制度
第八章 社会階級
第九章 財政制度
第十章 軍事、警察及び交通制度
第十一章 司法制度
第十二章 刑法
第十三章 人法
第十四章 物權法
第十五章 債權法
第十六章 親族法
第十七章 相続法
第四篇 近世
【ほか】

異なるレベルの選挙における投票行動の研究
創文社オンデマンド叢書
政治意識と投票行動をめぐる大量のデータを元に、衆院選、参院選、知事選、市長・市議選を心理学・社会学者が行動科学的に徹底分析した、選挙をめぐる実証的な貴重な緒である。
【目次】
緒言
第一章 研究の目的と方法
第二章 歴史的、社会的背景
第三章 政治意識の基本構造
第四章 投票行動を規定する態度要因とその構造
第五章 投票行動決定因分析
第六章 投票行動決定に関する若干の問題
第七章 政党支持態度、政策意見、投票意図の変動
第八章 政治的コミュニケーション行動とその影響
第九章 社会集団の投票行動に及ぼす影響
第十章 政治的認知の諸次元
第十一章 デモグラフィックな要因と政治的特性
補遺
引用文献
索引

哲学とは何か
創文社オンデマンド叢書
「本書は『哲学とは何か』という柔らかい書名になっているが、必ずしもやさしい入門の書というわけではない。本書は前篇と後篇の二部からできている。前篇の方は著者の考える哲学を概説したもので、入門書の意味をもつものであるが、後篇は専門学究の徒を念頭において書いたもので、西洋哲学史と仏教史の相当の知識を前提に執筆されている。・・・
著者は自分の哲学の概念を正統のものと確信しているのであるが、哲学を科学と同次元のものとする傾向の強い一部の考え方からは、直ちに理解されないだろう。プラトン哲学、カント哲学という風に、哲学に固有名詞が付せられるには必然的な意味があり、哲学の真理の複数多元性は哲学という学問に固有のものであると考える。この哲学的真理の多元性という事態を如何に処理すべきかは、著者が哲学に参入して以来の課題となり、この課題はいつも念頭より去ることがなかった。」(「序」より)
【目次】
前篇 哲学概説
第一章 哲学とは何か
第二章 哲学的精神
第三章 哲学の存在理由
第四章 世界観と哲学
第五章 実在と認識
第六章 科学と哲学 その一 自然科学の問題
第七章 科学と哲学 その二 社会科学の問題
第八章 技術哲学
第九章 文化哲学
第十章 社会哲学
第十一章 政治哲学
第十二章 歴史哲学
第十三章 哲学と道徳
第十四章 哲学と宗教
第十五章 論理学の課題 その一 科学的論理と形而上学的論理
第十六章 論理学の課題 その二 弁証法的論理と場所的論理
第十七章 理想主義の哲学
第十八章 汎神論の哲学
第十九章 実存主義の哲学
後篇 理性・精神・実存 理想主義・汎神論・実存主義の内面的聯関
第一章 理性・精神・実存の概念と問題の提示
第二章 ドイツ唯心論とその崩壊後に於ける問題の展開
第三章 問題の顕示 理性より精神へ、精神より実存へ
第四章 ギリシア哲学と、その没落期に於ける問題の展開
第五章 印度・中国・日本の仏教に於ける問題の展開
第六章 問題の第一次的整理
第七章 新しき問題の提出と展開
第八章 問題の究極的整理
第九章 哲学的論理の問題
人名索引
事項索引

キェルケゴオルからサルトルへ
創文社オンデマンド叢書

相続法講義 改訂版
創文社オンデマンド叢書
東北大学法学部での相続法の講義録。
相続法について体系的にまとめられた基本図書である。
「一、本書は、東邦大学法学部における相続法での講義(親族法とあわせて、通年4単位)をまとめたものである。小活字(8ポイント)の部分は時間の都合で省略する場合が多い。
二、抽象的な概念規定や用件・効果の羅列を極力避け、具体的な制度のあり方や機能をまず叙述し、定義などは学生にあとで構成させるように努力した。そのため、民法典や従来の許可書の叙述の順番は、かなりの程度これを変更せざるをえなかった。
三、相続税法の採用している考え方は、相続法自体の問題を批判的に検討するのに役立つので、所用の箇所に*印を附して、簡単に紹介しておいた。」(「初版まえがき」より)
「相続法講義を創文社から刊行して以来、一〇年近くが経過した。その間、この領域については、立法による変化はほとんどなく、凡例にも、世間的な目をひいたものは、非嫡出子相続分と相続させる旨の遺言とに関するものぐらいであったが、地味な問題について注目すべき判例は少なかった。そして、学説上は、田中恒朗教授や伊藤昌司教授等によって、多くの教示をあられた。それゆえ、久しぶりの相続法の勉強の意味もかねて、改訂版を出すことにした」(一九九六年の「改訂版について」より)
【目次】
まえがき
はじめに
第一章 相続の法定原則
第一節 相続人の種類・順位および法定相続分率
第二節 相続人の失格・放棄および単純承認
第三節 相続の対象
第四節 相続回復請求の期間制限
第五節 相続財産の清算
第六節 相続人の不存在
第七節 相続財産の管理
第二章 相続の法定原則の修正
第一節 序説
第二節 相続分指定
第三節 遺贈
第四節 遺言
第五節 遺留分の減殺
第三章 共同相続
第一節 共同相続財産
第二節 遺産分割
第三節 遺産分割分率
第四章 総括
第一節 相続と取引の安全
第二節 民法中での相続法の地位
第三節 相続の根拠
索引

日本経済論(現代経済学選書)
創文社オンデマンド叢書
「本書は、1970年代以降の日本経済の変動と政策形成を中心に扱った日本経済論である。従来、日本経済論は、書き手の関心のあるところに自由に焦点を合わせて、いわば「局所拡大的」に日本経済の一部を扱うものが普通であった。本書のねらいは、全体としてバランスのとれた日本経済論を書くことであり、多くの問題点を位置づける上で、部分に偏しないようにつとめたつもりである。
本書がマクロ経済分析の枠組みに依存していることはいうまでもないが、日本経済を論じる上で不可欠ともいえる自営業層の扱いに注意を払い、また政府・公共部門の立ち入った扱いをこころみて、入門的マクロ経済分析の非現実的な単純化におちいることをさけた。・・・
本書は、マクロ計量分析の限界を越えるところで、日本経済動の諸相を扱おうとしたものというべきであろう。企業間競争の在り方、民間と政府との関係、などの「産業組織論」的トピックは、今日の日本経済を論じる上で不可欠のものである。また労働市場の諸問題は、日本経済なかんずく企業経営の特徴をなし、多くの内外の研究者の関心を集めている、「終身」雇用制度と年功賃金制度、先進国の中でも突出した長時間労働、規模別および性別賃金格差、などの問題に触れない日本経済論の教科書はありえないのであり、本書ではこれにかなりの紙数を割いている」(「まえがき」より)
【目次】
目次
まえがき
第I部 高度成長の帰結と70年代における変貌
1 1970年の日本経済 高度成長の到達点ないし帰結
2 混乱期の日本経済:1971-75年
3 調整期の日本経済:1975-77年
4 均衡回復と新たな転換:1978-79年
第II部 家計と企業の経済行動 日本経済のマクロ分析
5 家計の行動 消費と貯蓄
6 家計の支出行動 住宅投資
7 マクロの企業行動(1) 生産と短期の雇用調整
8 マクロの企業行動(2) 設備投資
第III部 日本経済と公共部門
9 公共サービスの特徴
10 介入政策
11 マクロ経済政策
第IV部 日本経済の動態と構造調整
12 産業構造の変化とその動因
13 低成長経済への移行と景気変動
14 労働市場の動態
15 円高と日本経済
17 日本経済の転換能力
18 日本経済の不均衡と構造調整
参照文献
索引

型(叢書・身体の思想)
創文社オンデマンド叢書
「私の「型」と社会との関わりについての作業仮説(本書第一章参照)を実証する例がいままさしくここ〔猿之助の名優は「後世に残る作品をつくった人です」という発言〕にあるという実感を強くもったことをありありと思い出す。猿之助がもし自演を実現しようと思うならば、彼は世阿弥のようにみずから脚本を書き、みずから演出し、そしてみずから演技をしなければならないのではないかと思いながら、彼は自分の歴史的位置を、「型」を破る人でありつつ、同時に「型」を創造すべき人、として見据えている、立派なものだ、と思った。・・・後世に残る作品は今までの歌舞伎の型とはある程度異なるであろうが、歌舞伎である以上、それはやはり「型」の芸能であろう。だとすれば、その型はいったいどういう型なのだろうか、という疑問と好奇心が起こってきたことも事実である・・・
(玉三郎は)歌舞伎の国際的な存在意義について「気候風土、生活様式の違いからうまれた表現をまず珍しがり、面白がる。それは差の認識であり、その次に地球人としての共通の芸術的な精神をどう感じ取ってもらうのかが問題になる。そこを追究したい」と語っている。その独自性・固有性を明らかにすること、それをするとともに、その独自の形の中に潜んでいる普遍性、人類としての共通性を明らかにすること、それを玉三郎は違った仕方で表現しているのだ。彼は「伝統とその現代化」という問題に真正面からとりくんでいる芸術家であり、歌舞伎の俳優としてその伝統の具体的内容を「型」という点に求めているのだ。・・・
ところでここで私が二人の個性的な発言を引用したのは、人間にとって「型」という問題のもつ二重性を、二人の発言は期せずして示しているからだ。この二重性をどう考えるか、これは簡単に結論の出る問題ではないが、このことを念頭に置きながら、本書では「型」の問題を論じてゆきたいと思う」(「はじめに」より)
【目次】
まえがき
第一章 「型」とは何か
第二章 「型」の前史 古代・中世における「身」と「こころ」と「わざ」の思想
第三章 世阿弥の能楽理論における「型」の問題
(附論) 「序・破・急」の問題
第四章 剣法論に見られる「型」
第五章 「型」と稽古 「型」と日本人との交わりの「型」
結び 「型」における心
注
あとがき

落暉にむかいて
創文社オンデマンド叢書
哲学者・宗教学者による日常の何気ない出来事、作品論、交友関係などをめぐる随想集。滋味豊かな名文と対象への愛を感じさせる小品集
【目次】
落暉にむかいて
賀川豊彦氏のこと
日本人の女性への態度
内輪の友
友誼十五年
俳句会の思い出
日本人と政治への不信
内面性への逃避ということ
政治とのつきあい
野の鳥
国際日本研究所の創設
国際日本研究所に寄せる私の夢
正宗白鳥のキリスト教葬
死の効用
キリストとの出逢い
一つの坐像
プラグマティズムへの懐疑
武士道と現代
書の世界
叡山の行法
天下泰平の思想
全力的読書の一典型 田辺元博士のこと
田辺元先生の思い出
病床の人に
三つの姉妹団体
松山の旅
信州の旅
唐木順三氏の『無常』について
高見順氏の『死の淵より』について
トンキン湾事件に思う
漱石と二人の雲水
西田幾多郎と和辻哲郎
難死的人生の意味
椎名麟三氏の『信仰というもの』
或るキリスト者の生涯 森本慶三氏のこと
一つの邂逅 西田幾多郎と倉田百三
キリスト教と日本の伝統
晩夏
虫の秋
国民的感情について
河上丈太郎先生の逝去
あとがき

対話の倫理
創文社オンデマンド叢書
現代ほど対話が必要なときはない。しかし今日ほどこの言葉が弄ばれているときもない。真の対話への道をはっきりと示したのが本書である。ブーバーの死の直前に訳者と交わした世界平和についての書簡を含む。
「本書は、人間精神の歴史において、宗教と哲学とがどのような関係にあったかを調べ、あわせて近代哲学が神のような絶対者を非現実化してしまう上にどれほど大きな力となったかを、あきらかにしようとするものである」(「序説」より)
【目次】
序説 現代における対話の欠如について 神の蝕
第一章 対話の倫理 宗教と倫理の関係
第二章 思索と対話 宗教と哲学の関係
第三章 現代における神の沈黙 実存主義と深層心理学について サルトル、ハイデッガー、ユングを批判する
第四章 C・G・ユングとの対話
ブーバーの批判に答える ユング
ふたたびユングに与たう ブーバー
付録I キリスト教とユダヤ教の対話 マルティン・ブーバーについて パウル・ティリッヒ
II ユングの深層心理学における特殊用語解説
あとがき
索引

ドイツ法制史概説 改訂版
創文社オンデマンド叢書
「序論」より
「・法史学は法学の一分野であるとともに、同時に歴史学の一分野でもある。
・法史学はそれ自身にさまざまな分野【政治的、経済的、社会的基礎】を包含している。
・ドイツ法制史という場合、われわれはさしあたり、文化と言語とによって結合されたドイツ民族自身の法制史の意味に理解する。しかしながらこのようなドイツ民族は、カロリング朝時代の終わりになって、始めて国家の形をとった歴史的実在として現れてくるにすぎない。したがってドイツ法制史は、この二つの方向に拡張されることを必要とする【ゲルマン法制史として、ゲルマン民族の原初に遡り、古代文化とキリスト教の影響を考慮する】」
上記を前提に、ゲルマン、フランク、中世、近世、市民時代の法制を概説する。
【目次】
凡例
日本語新訳版への序文
第一一版への序文 第五版への序文 第四版への序文 第三版への序文 初版への序文
略記号
序論
第一章 ドイツ法制史の課題
第二章 ドイツ法制史の方法
第一部 ゲルマン時代
第三章 最古の法形成
第四章 ジッペと家
第五章 経済の法秩序
第六章 人民の身分
第七章 国制
第八章 王制・将軍制・従士制
第九章 違法行為の効果
第十章 訴訟
第二部 フランク時代
第十一章 ゲルマン人の建設した諸帝国
第十二章 中世初期の経済と社会
【略】
第十七章 イムニテート
第十八章 フランク時代の法源
第十九章 刑法と訴訟法
第二十章 カーロリンガ帝政
第三部 中世盛期
第二十一章 ヴォルムスの協約に至るまでの国制史
第二十二章 続き、シュタウフェン朝時代の終わりまで
第二十三章 王位の継承
【略】
第二十九章 経済
第三十章 身分
第三十一章 法源
第三十二章 国民国家の形成
第四部 中世後期
第三十三章 帝国の国制
第三十四章 裁判権
第三十五章 ランデスヘルシャフトとランデスホーハイト
第三十六章 都市制度
第三十七章 法源
第三十八章 刑法と訴訟法
第五部 近世初期
第三十九章 基礎
第四十章 ローマ法の継受と宗教改革
第四十一章 帝国の国制
第四十二章 ラント
第四十三章 民事訴訟と刑法
第六部 市民時代
第四十四章 帝国の終焉とドイツ同盟
第四十五章 主権的同盟諸国家
【略】
第四十九章 法思想と司法
第五十章 千年帝国
結語
旧訳への訳者あとがき
新訳への訳者あとがき
原語索引

ドイツ私法概説
創文社オンデマンド叢書
「初版への序」より
「ドイツ私法なる学問は、過去における自己の業績に正当な誇りを抱いているが、しかも外来法、とりわけローマ法に対して、それが外来法であるが故に敵愾心をいだくということは、今日すでに全く清算している。ローマ法は、今日なお、ヨーロッパ共同体の一要素をなしているからである。この学問は、専ら正義の実現のみを目指して仕事をしており、その故にこそ、外来の影響をも、それが正義の実現という目的に奉仕した度合いに応じて、評価するわけである。したがって、この学問は、法の比較にも導いてゆく。法の比較は本書全体を貫いており、外国の法形態が特質の理解を助けるような場合には、この比較が常に本文の中に織り込まれている」
「序論」より
「本書は、古代の終末以来の私法の歴史を包括するわけであるが、しかも同時に、ヨーロッパの法発展におけるゲルマン的基礎をも含めて考察する。叙述の前景におかれるのはドイツ法である。ドイツ民族は一つの自立的な・その民族的本質に即した私法を創造し、外来の諸影響はこのような〔民族的〕私法の中に融け込んでいったのであるということ、本書はこのことを明らかにしなければならない。……
われわれは法を文化現象として考察する。法はすべて文化と同様に歴史的に生成したものであり、その歴史から出発して始めて完全に理解されうるものとなる」
【目次】
目次
献辞
凡例
第三版への序
第一部 序論
第一章 課題
第一編 精神史的基礎
第二章 継受に至るまでのローマ法とドイツ法
第三章 外国法の継受
第四章 自然法の時代
【略】
第十三章 近代の法人
第十四章 人格権(概要)
第三編 家族法
第十五章 総説
第十六章 婚姻の締結
【略】
第二十三章 後見
第三部 財産法
第一編 物権法
A 基礎的諸概念
第二十四章 物権の本質および目的物
第二十五章 物権の種類
第二十六章 ゲヴェーレ
B 不動産法
その一 土地所有権の取得
第二十七章 原始取得
【略】
第三十五章 物上負担
第三十六章 土地担保権
C 動産法
第三十七章 動産に対する所有権の取得
第三十八章 非権利者からの取得
第三十九章 動産担保権
第二編 債務法
A 一般理論
第四十章 概説
【略】
第六十章 相続人の責任
第六十一章 意思執行者
訳者あとがき
原語索引
成句索引
条文索引

中世哲学研究3:在りて在る者
創文社オンデマンド叢書
「モーゼがシナイ山上において神にその名を問うたとき、神は、 「われは『在りて在る者』なり」と答えた。神がほかならぬ神自身によって「在る者」として啓示されたということは、聖書の伝統を受けつぐ中世の哲学者たちにとっては、決定的に重要な意味を有することであった。周知のように、ギリシア哲学はその発端から「存在」をめぐって動いてきた。しかしここにいわゆる存在をめぐる問題とは、決して一様のものではなかった。ひとびとはまず、もろもろの存在者がそこから生じてくるみなもとを探ねた。すなわち存在の根原を問うた。さらに、その根原からすべてのものがいかにして出てくるかを探ねた。根原と存在者との関係を問うた。ところで存在の根原こそは最も真実の意味で存在するものでなければならない。そこで或るひとは、もろもろの存在者のなかで最も真実の意味で存在するものは何かと問い、さらに或るひとは一歩を進めて、 ひとは、もろもろの存在者のなかで最も真実の意味で存在するものは何かと問い、またその真実の存在はいかにして認識されうるかと問うた。さらに或るひとは一歩を進めて、「そもそも存在とは何であるか」という最も根原的な問いを提起した。さらに或るひとは存在が多様な意味で語られ、したがって存在者の存在仕方は決して一様ではないことに注目し、意味の系譜を探ね、それらの意味を一貫する関連の理法(アナロギア)をみいだそうとした」
中世哲学は、「存在とは何か」という一つの究極的な問いを「神」の存在を軸に解明しようとした系譜をたどる論考である。
【目次】
まえがき
一 在りて在る者 序論
二 在りて在る者 トマスの解釈
三 在りて在る者 アウグスティヌスとの関係
四 在りて在る者 アウグスティヌスの解釈
五 無からの創造 その思想の形成
六 神と世界 創造における神の意志
七 非有のイデア 創造における自由の根拠
八 自然神学 その歴史と現代的意味
あとがき
人名索引
文献表

中世哲学研究2:トマス・アクィナスの〈エッセ〉研究
創文社オンデマンド叢書
「トマスの『スンマ(神学大全)』を読み進んでゆくうちに、私は、いわゆる「がある存在」といわれる「存在」(エクシステンチア)は、トマスが神の本質と同じであるという「存在」(エッセ)とは、別のものではないだろうかという疑問をいだくようになってきた。そのような疑問が心に浮かんだのは、『スンマ』の神の存在論証の箇所を読んだときである。そこでトマスは、神の存在、すなわち「神がある」ということは理性によって証明できるとはっきりいっている。他面トマスは、神において存在と本質は同一であるといっている。それゆえもしこの存在が、「神がある」と言われる場合の存在と同じものであるとしたならば、当然、存在と同意なる神の本質も理性によって認識される筈である。しかるにトマスは別の箇所においては、神の本質は絶対に認識できないといっているのである。これはあきらかな矛盾ではなかろうか。この矛盾を解決しようと思うのならば、神においてその本質と同一視される存在(エッセ)は、いわゆる「がある存在」としての存在(エクイスシテンチア)とは別のものであるとしなければならない。トマス自身、神の存在が理性によって証明されるか否かを論じた箇所において、神の存在(エッセ)が不可知であることを根拠として「神がある」ことを論証できないと主張する説を、一つの異論として提示している。それに対するトマスの解答をみると、たしかに「存在の現実態」としての神の存在は人間の理性認識を超越するが、「神がある」という命題が真であることは、結果の存在から原因の存在を推定するア・ポステオリな論証によって証明できるのであるという。・・・
しかしながら私はついに、この問題について単に「疑問をいだく」にとどまらず、断定を下さざるをえないところまで到達した。」
【目次】
まえがき
一 エッセの探究
二 存在とエッセ
三 神の存在とエッセ
四 神の内在と超越
五 存在と本質
あとがき
人名索引
文献表