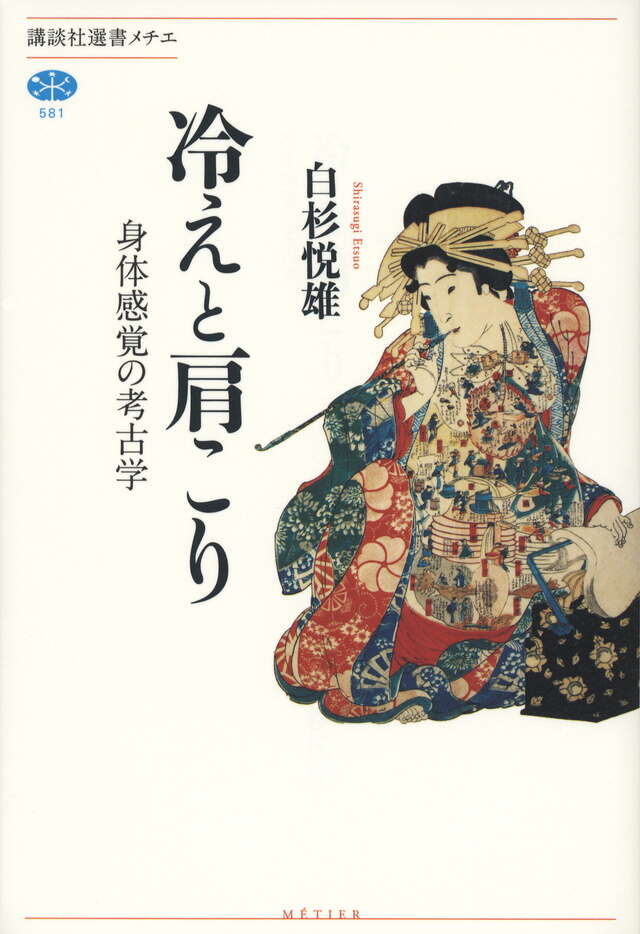
冷えと肩こり 身体感覚の考古学
ヒエトカタコリシンタイカンカクノコウコガク
- 著: 白杉 悦雄

「肩こり」を外国人に伝えようとしても、英語にも中国語にも訳語は見当たらない。日本人以外は肩がこらないから、とも言われる。冷え性に悩む女性は日本に数多くいるが、これも海外では治療の対象ではない。つまり、肩こりや冷えはわが国にしか存在しない病といえる。逆に、「うつ病」は西洋の病として捉えられてきた。中国や江戸の医学史研究をベースに、肩こり、冷え性、うつ、疝気などの「構造」をさぐる。
【目次】
第一章――――冷え性の発見(一九五六年/病気のなかの日陰者/冷え性の西洋医学的研究事始め/医学の新しい考えかた/木下杢太郎のエピソード/血の道/厥と痼冷/冷え性/冷え症/冷え/西洋医学の呪縛/漢方療法の再評価/冷え性の身体感覚)
第二章――――肩こりの謎(けんべき/痃癖/二つの謎/一気留滞説/江戸のバブル崩壊/腹診と背診/肩こりの身体感覚)
第三章――まなざしとことば(ことばの歴史/「うつ」をめぐるまなざしの変容/気の思想と鬱/六鬱説/七情の病/鬱の心理化/精神病としての鬱病/過労から過労死へ/古い物語の発見/神経衰弱とストレス/減少と滞り/脚から起こる病/脚気の病/風土病としての「脚弱」/地方性の否定/時代性の否定/厥は脚気なのか)
第四章――せんきの病(消えた病/滞りの病としての疝気/虫の病としての疝気/三虫/庚申信仰/疝鬼・せんきの虫・疝気)
第五章――庸医 江戸の民間医師(はじめに/『和漢三才図会』の良医と庸医/『養生訓』の良医と庸医/俗医/草医/浮世草子に描かれた藪医者/『人心覗機関』の藪医者/『世事見聞録』の藪医者)
第六章――江戸の体内想像図 『飲食養生鑑』と『房事養生鑑』(養生を教える一対の絵/体内を生活空間に見立てる絵/体内のからくりをのぞき見る絵/身体観の見立て絵/『養生鑑』が語るもう一つの身体観)
終 章(過去を体現する身体感/反復する歴史)
- 前巻
- 次巻
オンライン書店で購入する
目次
第一章――――冷え性の発見(一九五六年/病気のなかの日陰者/冷え性の西洋医学的研究事始め/医学の新しい考えかた/木下杢太郎のエピソード/血の道/厥と痼冷/冷え性/冷え症/冷え/西洋医学の呪縛/漢方療法の再評価/冷え性の身体感覚)
第二章――――肩こりの謎(けんべき/痃癖/二つの謎/一気留滞説/江戸のバブル崩壊/腹診と背診/肩こりの身体感覚)
第三章――まなざしとことば(ことばの歴史/「うつ」をめぐるまなざしの変容/気の思想と鬱/六鬱説/七情の病/鬱の心理化/精神病としての鬱病/過労から過労死へ/古い物語の発見/神経衰弱とストレス/減少と滞り/脚から起こる病/脚気の病/風土病としての「脚弱」/地方性の否定/時代性の否定/厥は脚気なのか)
第四章――せんきの病(消えた病/滞りの病としての疝気/虫の病としての疝気/三虫/庚申信仰/疝鬼・せんきの虫・疝気)
第五章――庸医 江戸の民間医師(はじめに/『和漢三才図会』の良医と庸医/『養生訓』の良医と庸医/俗医/草医/浮世草子に描かれた藪医者/『人心覗機関』の藪医者/『世事見聞録』の藪医者)
第六章――江戸の体内想像図 『飲食養生鑑』と『房事養生鑑』(養生を教える一対の絵/体内を生活空間に見立てる絵/体内のからくりをのぞき見る絵/身体観の見立て絵/『養生鑑』が語るもう一つの身体観)
終 章(過去を体現する身体感/反復する歴史)
書誌情報
紙版
発売日
2014年08月12日
ISBN
9784062585842
判型
四六
価格
定価:1,705円(本体1,550円)
通巻番号
581
ページ数
208ページ
シリーズ
講談社選書メチエ
電子版
発売日
2014年09月26日
JDCN
0625858400100011000I
著者紹介
1951年、北海道生まれ。1975年中央大学法学部卒業。1994年京都大学大学院文学研究博士課程修了。現在、東北芸術工科大学大学院長、教育センター長、デザイン工科学部教授。 専門は中国及び日本の医学思想史、中国科学史。日本中国学会賞(哲学・思想部門) 受賞。 共著に、 『近代日本の身体感覚』 (栗山茂久・北澤一利編、青弓社)、『東と西の医療文化』(吉田忠・深瀬泰旦編、思文閣出版)、『歴史の中の病と医学』 (山田慶兒・栗山茂久共著、思文閣出版)などがある。











