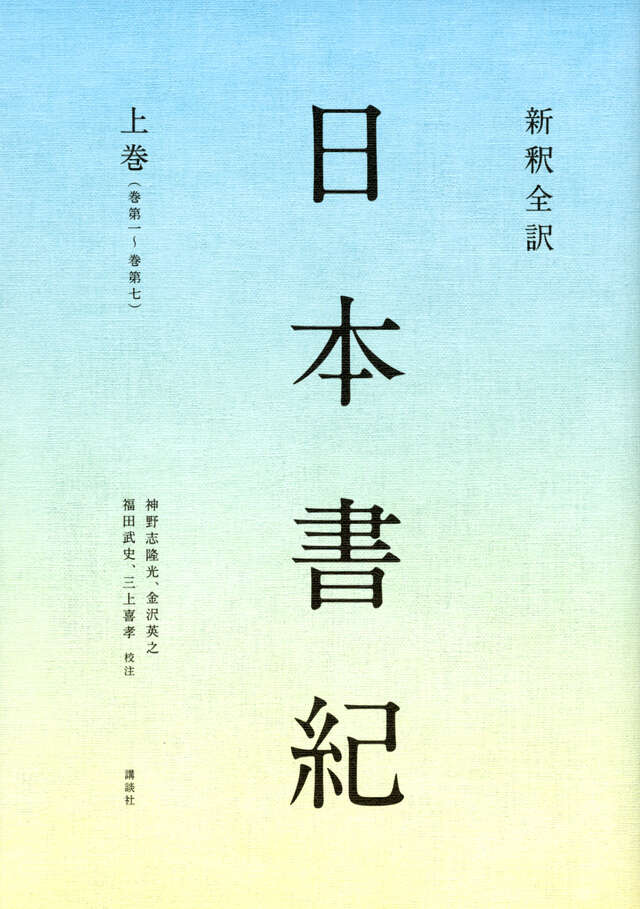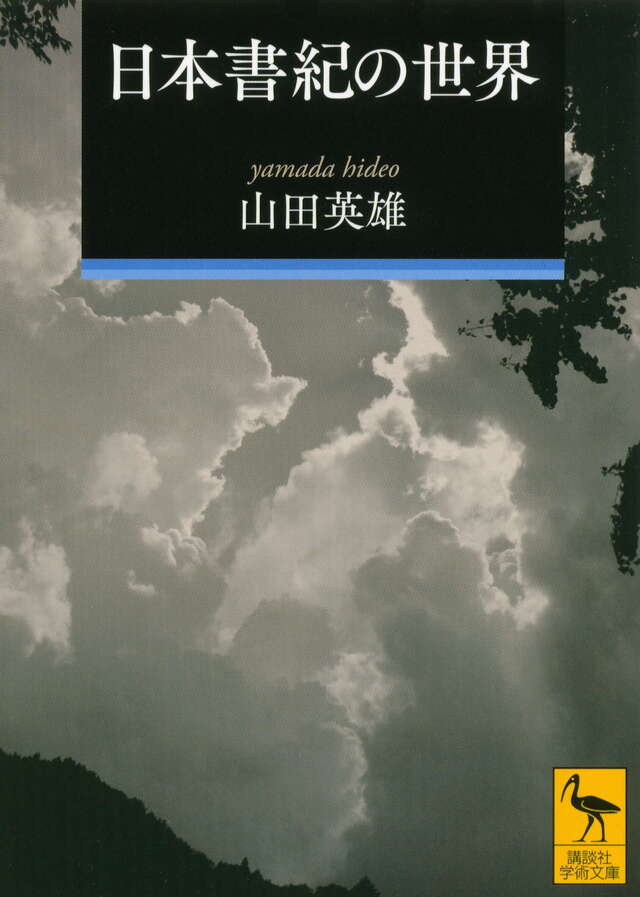マイページに作品情報をお届け!
「記紀」はいかにして成立したか 「天」の史書と「地」の史書
キキハイカニシテセイリツシタカ アメノシショトツチノシショ
- 著: 倉西 裕子

先行する史書は何か? 編纂思想の相違は何故か?
記と紀で天地生成記述になぜ相違があるのか。「帝記」「旧辞」を基に編纂され、ともに「日本式紀伝体」で記述されながら、意義と役割を異にする古事記と日本書紀。それぞれの背景にある天の思想と地の思想を解読する。
【目次】
プロローグ
序章 「歴史書」の歴史
1 歴史書の編纂記述様式 編年体と紀伝体
2 『日本書紀』と『古事記』の相関関係と成立過程をめぐる諸仮説
第一章 「日本式紀伝体」は存在したのか?
1 『帝紀』と『旧辞』
2 『日本書紀』と『古事記』以前の歴史書の実在 書紀区分論・暦法・紀年法をアプローチとして
3 「日本式紀伝体」は存在した 日本の史書を一対とする編纂記述様式
4 『日本書紀』における「天(あめ)」と「地(つち)」の思想 「日本式紀伝体」が考案された背景
5 「帝記」と「旧辞」の内容
第二章 似て非なる史書『日本書紀』と『古事記』
1 『日本書紀』と『古事記』の異同
2 『日本書紀』の「あまつひつぎしろしめす」と『古事記』の「治天下」
3 「あまつひつぎ」とは何か
4 「ひつぎ」と瓊瓊杵尊
5 原義が異なる「皇太子」と「ひつぎのみこ」
6 『古事記』の「天皇」
7 『古事記』の「天皇」と治天下の権
8 『日本書紀』の「治天下」
9 「あまつひつぎしろしめす」・「治天下」と「日本式紀伝体」
第三章 書名が語る『日本書紀』・『古事記』成立の経緯
1 草壁皇子の尊号の追贈問題
2 二つの持統天皇即位の年
3 持統朝における「皇太子」と「ひつぎのみこ」
4 太上天皇制における「天皇」と「太上天皇」
5 『古事記』の成立過程
6 『日本紀』の成立過程
7 『日本書紀』の成立過程
8 天武天皇は『書紀』・『記』の両書にかかわったのか?
エピローグ
注
索引
- 前巻
- 次巻
目次
プロローグ
序章 「歴史書」の歴史
1 歴史書の編纂記述様式 編年体と紀伝体
2 『日本書紀』と『古事記』の相関関係と成立過程をめぐる諸仮説
第一章 「日本式紀伝体」は存在したのか?
1 『帝紀』と『旧辞』
2 『日本書紀』と『古事記』以前の歴史書の実在 書紀区分論・暦法・紀年法をアプローチとして
3 「日本式紀伝体」は存在した 日本の史書を一対とする編纂記述様式
4 『日本書紀』における「天(あめ)」と「地(つち)」の思想 「日本式紀伝体」が考案された背景
5 「帝記」と「旧辞」の内容
第二章 似て非なる史書『日本書紀』と『古事記』
1 『日本書紀』と『古事記』の異同
2 『日本書紀』の「あまつひつぎしろしめす」と『古事記』の「治天下」
3 「あまつひつぎ」とは何か
4 「ひつぎ」と瓊瓊杵尊
5 原義が異なる「皇太子」と「ひつぎのみこ」
6 『古事記』の「天皇」
7 『古事記』の「天皇」と治天下の権
8 『日本書紀』の「治天下」
9 「あまつひつぎしろしめす」・「治天下」と「日本式紀伝体」
第三章 書名が語る『日本書紀』・『古事記』成立の経緯
1 草壁皇子の尊号の追贈問題
2 二つの持統天皇即位の年
3 持統朝における「皇太子」と「ひつぎのみこ」
4 太上天皇制における「天皇」と「太上天皇」
5 『古事記』の成立過程
6 『日本紀』の成立過程
7 『日本書紀』の成立過程
8 天武天皇は『書紀』・『記』の両書にかかわったのか?
エピローグ
注
索引
書誌情報
紙版
発売日
2004年06月12日
ISBN
9784062583015
判型
四六
価格
定価:1,650円(本体1,500円)
通巻番号
301
ページ数
234ページ
シリーズ
講談社選書メチエ
著者紹介
1963年、東京生まれ。日本女子大学文学部史学科卒業。日本赤十字社国際部を経て、日本史の研究に入る。主な著作に『日本書紀の真実 紀年論を解く』(講談社選書メチエ)など。