
マイページに作品情報をお届け!
ソーシャルブレインズ入門――<社会脳>って何だろう
ソーシャルブレインズニュウモンシャカイノウッテナンダロウ
- 著: 藤井 直敬

-内容紹介-
「ソーシャルブレインズ」は、「社会脳」と訳される、いまもっとも注目のキーワードです。
世の中には、人の数だけ脳があります。複数の脳がやりとりをすることで、人間関係や社会はなりたっています。見方を変えれば、脳は、そのような、他者との関係や社会の中で、初めてその機能を理解できるものです。
「ソーシャルブレインズ」とは、そんな「人間関係や社会に組み込まれた状態の脳の機能」のことです。「空気を読んだり、がまんしたり、人とつきあう」脳の機能です。
これは、専門家でなくても自然に理解できる考え方です。しかし、これまでの脳科学では、ソーシャルブレインズに着目した研究を行おうとしても、技術的な「研究の壁」に阻まれていました。
この壁を破りつつあるのが、著者の藤井直敬氏です。斬新な実験方法の開発を行うと同時に、「脳も社会も、ハブを持つネットワーク構造であり、共通したアプローチで理解できるもの」という考え方から、この新しい分野を切りひらきつつあります。
本書は、そんな著者の描いた「ソーシャルブレインズ研究の俯瞰図」であり「脳科学者が何を考えながら研究しているかを率直に綴ったノート」でもあります。やわらかな感性と冴えた知性、そして、毎日出版文化賞(前著『つながる脳』NTT出版)を受賞した魅力的な文章で語る、「新しい脳科学の時代」を告げる入門書です。
- 前巻
- 次巻
目次
<目次>
第1章 ソーシャルブレインズとは何なのか?
脳はどうやって機能を拡張してきたのか?/ひとりきりの脳はどこまで脳なのか?/お茶とケーキに手を出しますか?/社会的ゾンビ/「空気」とゾンビ/脳の自由度について考える/透明人間になったのび太/創造性との関係/ハブという考え方/脳と社会と階層性ネットワーク……
第2章 これまでのソーシャルブレインズ研究――顔、目、しぐさ
顔はなぜ特別なのか?/脳はどのように顔を認知するのか?/目の力/しぐさの力/ミラーニューロンの意義と問題/自他の境界/仮想空間の腹腕/コミュニケーションとタイミング/鏡の中の自分は誰?/脳の中のペプシマンと身体イメージ/他者認知のしくみを読み替える……
第3章 社会と脳の関わり――「認知コスト」という視点
ミステリで考えてみる/ミーティングで携帯を頻繁にチェックする部下/社会的駆け引き/頑固なサル/ルールと脳について考える/9・11のあとにアメリカで感じたこと/アイヒマンの発言「私は命令に従っただけだ」/ミルグラム実験/スタンフォード監獄実験/人は何でもやりかねない/脳と社会と倫理……
第4章 僕はどうやってソーシャルブレインズを研究しているか
第5章 ソーシャルブレインズはそもそもどこにあるのか?
キーワードは「関係性」/まず二頭のサルで考える/何でもかんでも記録する「多次元生体情報記録手法」/ECoG電極の試み/消えないコーヒーメーカー/脳内ネットワークの関係性をどう記述するか/「あの二人はつきあっているの?」/脳科学研究の革命
第6章 ソーシャルブレインズ研究は人を幸せにするか?――幸せとリスペクトの脳科学
脳科学が個人にできること/赤ちゃんとお母さんの関係/無条件で認めてくれる存在/リスペクトからはじまる/母子間コミュニケーションからソーシャルブレインズへ/ソーシャルブレインズ研究のこれから
書誌情報
紙版
発売日
2010年02月18日
ISBN
9784062880398
判型
新書
価格
定価:814円(本体740円)
通巻番号
2039
ページ数
240ページ
シリーズ
講談社現代新書
著者紹介
関連シリーズ
-

考える細胞ニューロン
-
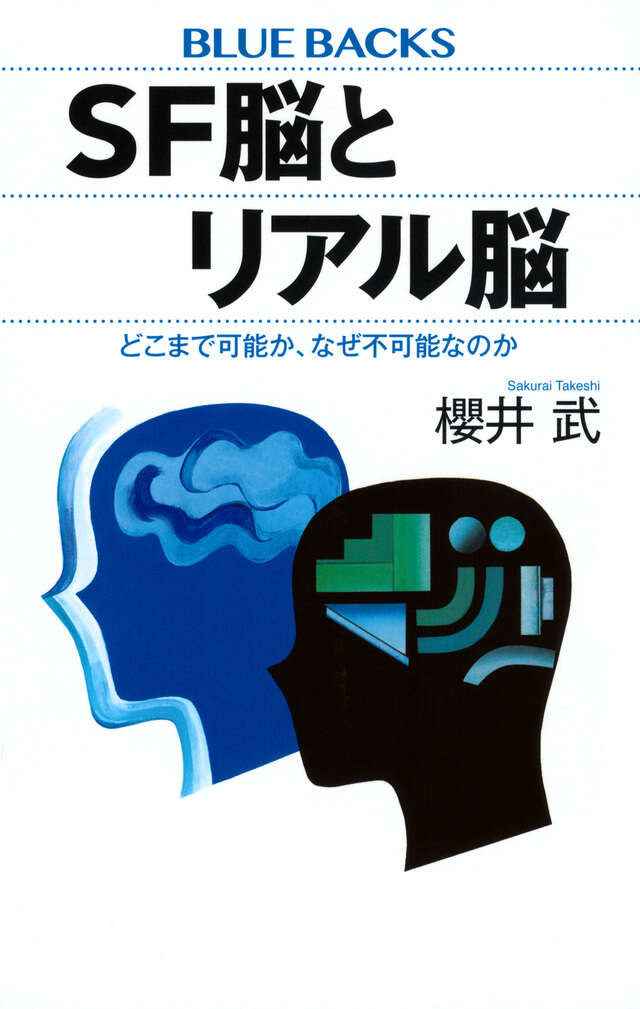
SF脳とリアル脳
-

意識の脳科学
-

顔に取り憑かれた脳
-

思い出せない脳
-

咒(まじない)の脳科学
-

脳の教科書
-

「心の病」の脳科学
-

生命知能と人工知能
-

脳を司る「脳」
-

脳から見るミュージアム アートは人を耕す
-

脳とクオリア なぜ脳に心が生まれるのか
-

感動のメカニズム 心を動かすWork&Lifeのつくり方
-

6つの脳波を自在に操るNFBメソッド たった1年で世界イチになるメンタル・トレーニング
-

50歳を超えても脳が若返る生き方
-

意識と自己
-

もうひとつの脳 ニューロンを支配する陰の主役「グリア細胞」
-

無意識の力を伸ばす8つの講義
-

痛覚のふしぎ
-

つながる脳科学
-

脳・心・人工知能 数理で脳を解き明かす
-

走り方で脳が変わる!
-

意識と無意識のあいだ
-

芸術脳の科学
-

神経とシナプスの科学
-

脳はなぜ都合よく記憶するのか
-

瞑想する脳科学
-

本がどんどん読める本 -記憶が脳に定着する速習法!
-

幸せのメカニズム 実践・幸福学入門
-

もの忘れの科学
-

マンガ脳科学入門
-

21世紀の脳科学
-

脳はいかにして言語を生みだすか
-

最新脳科学でわかった 五感の驚異
-

絵でわかる脳のはたらき
-

ほら、あの「アレ」は・・・なんだっけ? 私の記憶はどこ行った
-

ノーベル賞の生命科学入門 脳と神経のはたらき
-

なぜ年をとると時間の経つのが速くなるのか
-

<勝負脳>の鍛え方
-

「脳科学」の壁 脳機能イメージングで何が分かったのか
-

「運命の人」は脳内ホルモンで決まる!