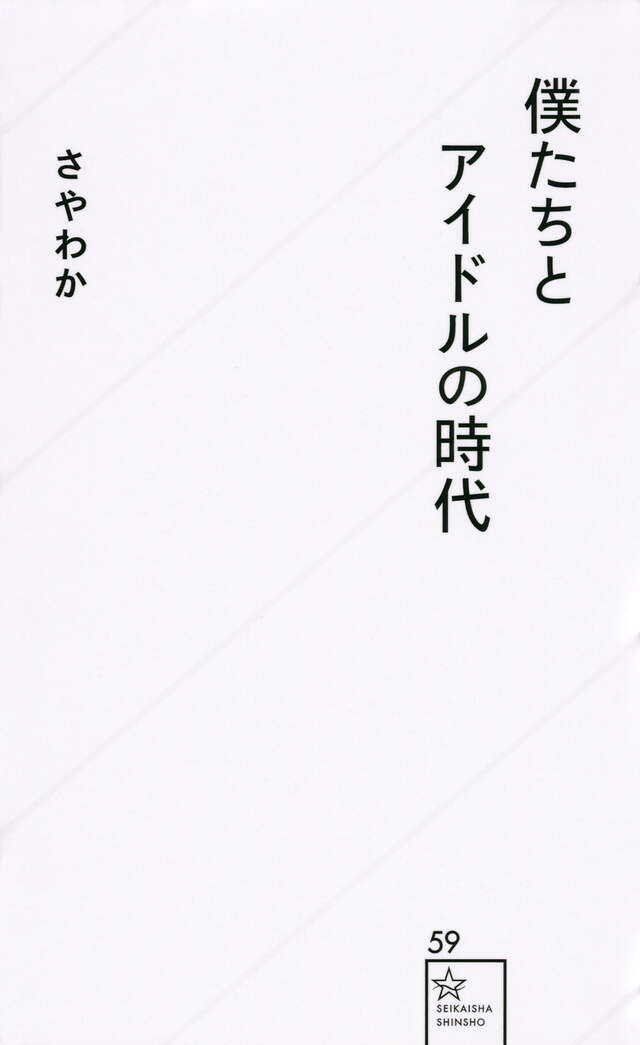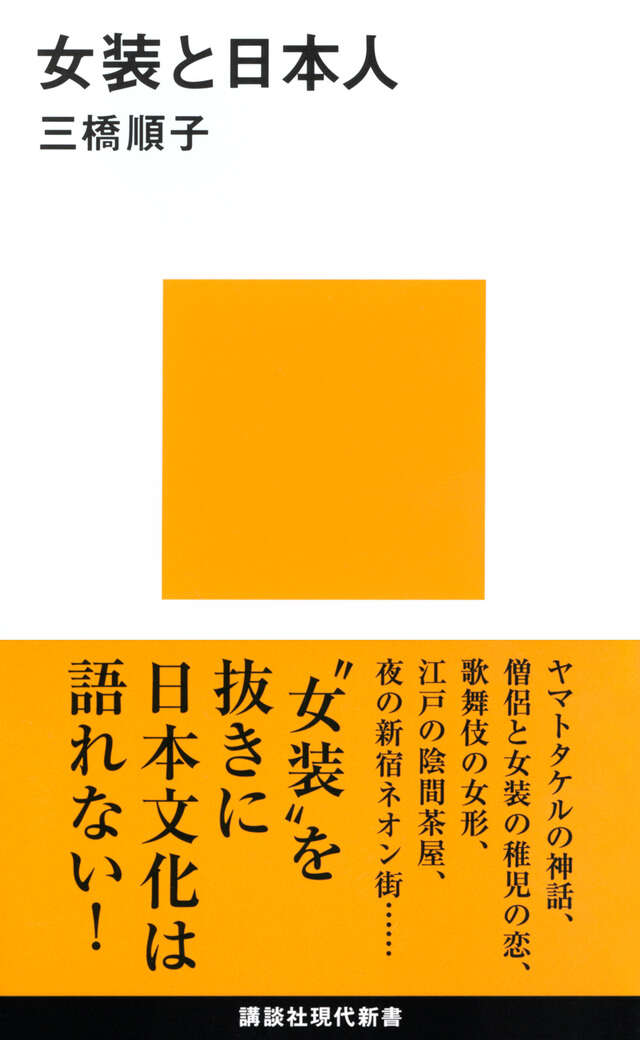マイページに作品情報をお届け!
日本人の数学 和算
ニホンジンノスウガクワサン
- 著: 下平 和夫

『塵劫記』の吉田光由、“算聖”関孝和、最上流の会田安明、そして東京数学会社へ
泰平の江戸に開花した日本数学の精華
『塵劫記』の吉田光由、高等数学を開拓した関孝和、和算が民衆に広がる契機を作った最上流の会田安明。そして明治維新、西洋文明が流入するなかで、日本中の数学者が一堂に会して発足したわが国最初の学会、東京数学会社――。幕藩体制下に独自の発展をとげ、世界に類を見ない大輪の花を開いた和算という文化とその歴史を描いた、格好の和算入門。
上代および中世の日本人の数的知識がどのようなものであったかを追求することは、日本人の一面を知る上に必要であるが、そのなかでも明治維新以前の日本人の一般的な数学知識を知ることは、和算から洋算への転機となるためのステップを知る上にきわめて貴重な手がかりを与えてくれるという意味で、ますます研究さるべき分野であろう。――<本書「はしがき」より>
※本書の原本は、1972年、河出書房新社より刊行されました。
- 前巻
- 次巻
目次
第一章 吉田光由
1 江戸時代の数学
2 『塵劫記』
3 『万葉集』と九九
4 まま子立て
5 『割算書』と『諸勘分物』
6 出題と解答のリレー
第二章 関孝和
1 関孝和の伝記
2 『荒木村英先生之茶談』
3 関孝和の師はだれか
4 関孝和の弟子たち
5 建部賢弘の『不休綴術』
6 関流と免許状
7 円理の発達
8 行列式の発見
第三章 会田安明
1 会田算左衛門の生い立ち
2 江戸での生活
3 会田安明と藤田貞資
4 浅草の算子塚
5 有馬頼徸(よりゆき)と藤田貞資
6 会田安明と算額
7 最上流の末裔たち
第四章 東京数学会社
1 わが国最初の学会と和算史
2 和田寧の円理
3 江戸時代の数学塾
4 長谷川数学道場
5 遊歴算家
6 洋算の摂取
7 菊池大麓と藤沢利喜太郎
8 日本人の数学
書誌情報
紙版
発売日
2011年08月12日
ISBN
9784062920667
判型
A6
価格
定価:1,012円(本体920円)
通巻番号
2066
ページ数
280ページ
シリーズ
講談社学術文庫
初出
原本は、1972年河出書房新社より刊行された。