
マイページに作品情報をお届け!
カフェと日本人
カフェトニホンジン
- 著: 高井 尚之

大正・昭和の「カフェー」とAKB48の類似点って? なぜ名古屋人は喫茶好き? 210年前にコーヒーを飲んだ「人気文化人」といえば? 100年以上営業している国内最古の喫茶店はどこ? 「音楽系喫茶」と「特殊喫茶」がたどった経緯とは? あなたにとって「カフェの存在」とは? 日本初の喫茶店から、欲望に応えてきた特殊喫茶、スタバ、いま話題の「サードウェーブ」までの変遷をたどった、日本のカフェ文化論。
大正・昭和の「カフェー」とAKB48の類似点って?
なぜ名古屋人は喫茶好き?
210年前にコーヒーを飲んだ「人気文化人」といえば?
100年以上続く国内最古の喫茶店はどこ?
「音楽系喫茶」と「特殊喫茶」がたどった経緯とは?
「カフェラテ」と「カフェオレ」の違いは?
あなたにとって「カフェの存在」とは?
--------------------------------------------------
日本初の喫茶店から、欲望に応えてきた特殊喫茶、スタバ、
いま話題の「サードウェーブ」までの変遷をたどった、日本のカフェ文化論。
--------------------------------------------------
【おもな内容】
第1章 カフェの誕生
「日本初」の喫茶店はビリヤードつき/100年以上続く現存最古の喫茶店/戦後に庶民化した「ハイカラな味」/「昭和の喫茶店」と「平成のカフェ」 ほか
第2章 日本独自の進化を遂げたカフェ・喫茶店
文壇バーならぬ文壇カフェ/「談話室滝沢」があった時代/菊池寛も愛用した文化人のサロン/名曲喫茶・シャンソン喫茶・ジャズ喫茶・歌声喫茶・ゴーゴー喫茶/美人喫茶からメイドカフェへ/西からやってきた「ノーパン喫茶」 ほか
第3章 なぜ名古屋人は喫茶好きなのか
始まりは尾張徳川藩の振興策/昭和30~40年代から続く人気店/「一宮モーニング」と「豊橋モーニング」 ほか
第4章 カフェ好きが集まる聖地
シングルオリジンの味わい深さを追求する「バルミュゼット」(仙台)/コロンビアに直営農園を持つ個人店「サザコーヒー」(ひたちなか)/川端康成や池波正太郎に愛された「アンジェラス」(浅草)/ジョン・レノンや柴田錬三郎も利用した「ミカドコーヒー」(軽井沢)/「ご近所のコーヒー店」から進化した「カフェタナカ」(名古屋)/日本有数の温泉地にある「ティールーム・二コル」と飲食専門誌『カフェ&レストラン』編集長が絶賛した「茶房 天井棧敷」(由布院)
第5章 「うちカフェ」という見えざる市場
定着した「コンビニコーヒー」は多様化へ/「無糖」や「健康」を打ち出す缶コーヒー/「サードウェーブは「昭和の喫茶店」そのものだ ほか
- 前巻
- 次巻
オンライン書店で購入する
目次
はじめに――スタバが開国した「女性向け」コーヒー
第1章 カフェの誕生
人類とコーヒーとの出合い/「日本初」の喫茶店はビリヤードつき/100年以上続く現存最古の喫茶店/一時代を築いた「大正ロマン」と「昭和レトロ」/戦後に庶民化した「ハイカラな味」/「昭和の喫茶店」と「平成のカフェ」 ほか
第2章 日本独自の進化を遂げたカフェ・喫茶店
文壇バーならぬ文壇カフェ/「談話室滝沢」があった時代/菊池寛も愛用した文化人のサロン/名曲喫茶・シャンソン喫茶・ジャズ喫茶・歌声喫茶・ゴーゴー喫茶/美人喫茶からメイドカフェへ/西からやってきた「ノーパン喫茶」 ほか
第3章 なぜ名古屋人は喫茶好きなのか
始まりは尾張徳川藩の振興策/「広ブラ」時代の名古屋のカフェー/昭和30~40年代から続く人気店/「一宮モーニング」と「豊橋モーニング」/若い女性に人気の「猿カフェ」 ほか
第4章 カフェ好きが集まる聖地
シングルオリジンの味わい深さを追求する「バルミュゼット」(仙台)/コロンビアに直営農園を持つ個人店「サザコーヒー」(ひたちなか)/川端康成や池波正太郎に愛された「アンジェラス」(浅草)/ジョン・レノンや柴田錬三郎も利用した「ミカドコーヒー」(軽井沢)/「ご近所のコーヒー店」から進化した「カフェタナカ」(名古屋)/日本有数の温泉地にある「ティールーム・二コル」と飲食専門誌『カフェ&レストラン』編集長が絶賛した「茶房 天井棧敷」(由布院)
第5章 「うちカフェ」という見えざる市場
コーヒーの6割以上を自宅で飲む/定着した「コンビニコーヒー」は多様化へ/「無糖」や「健康」を打ち出す缶コーヒー/「ミルク感」が人気のチルドカップコーヒー/「スティックコーヒー」市場も拡大/老舗も新興も手がける「通販のコーヒー」/サードウェーブは「昭和の喫茶店」そのものだ ほか
おわりに――それぞれの記憶に残る「カフェと人生」
書誌情報
紙版
発売日
2014年10月17日
ISBN
9784062882873
判型
新書
価格
定価:990円(本体900円)
通巻番号
2287
ページ数
224ページ
シリーズ
講談社現代新書
電子版
発売日
2014年11月28日
JDCN
0628828700100011000R
著者紹介
たかい・なおゆき 経済ジャーナリスト・経営コンサルタント。1962年名古屋市生まれ。日本実業出版社の編集者、花王情報作成部・企画ライターを経て2004年から現職。出版社とメーカーでの組織人経験を活かし、大企業・中小企業の経営者や幹部の取材をし続ける。「現象の裏にある本質を描く」をモットーに、「企業経営」「ビジネス現場とヒト」をテーマにした企画・執筆多数。2007年からカフェ取材も始め、専門誌の連載のほか、放送メディアでも解説を行う。『「解」は己の中にあり』 (講談社)、『なぜ「高くても売れる」のか』 (文藝春秋)、『日本カフェ興亡記』 (日本経済新聞出版社)など著書多数。
オンライン書店一覧
関連シリーズ
-

ハザマの思考 なぜ世界はニッポンのサブカルチャーに惹きつけられるのか
-

<個室>と<まなざし>
-

日本再発見
-

芸 秘伝伝授の世界
-

人類が永遠に続くのではないとしたら
-

難読珍読 苗字の地図帳
-

名師の訓え
-

出世と恋愛 近代文学で読む男と女
-

SNS天皇論
-

松と日本人
-

江戸の科学者
-

長崎丸山遊廓
-

外は、良寛。
-

日本人と神
-
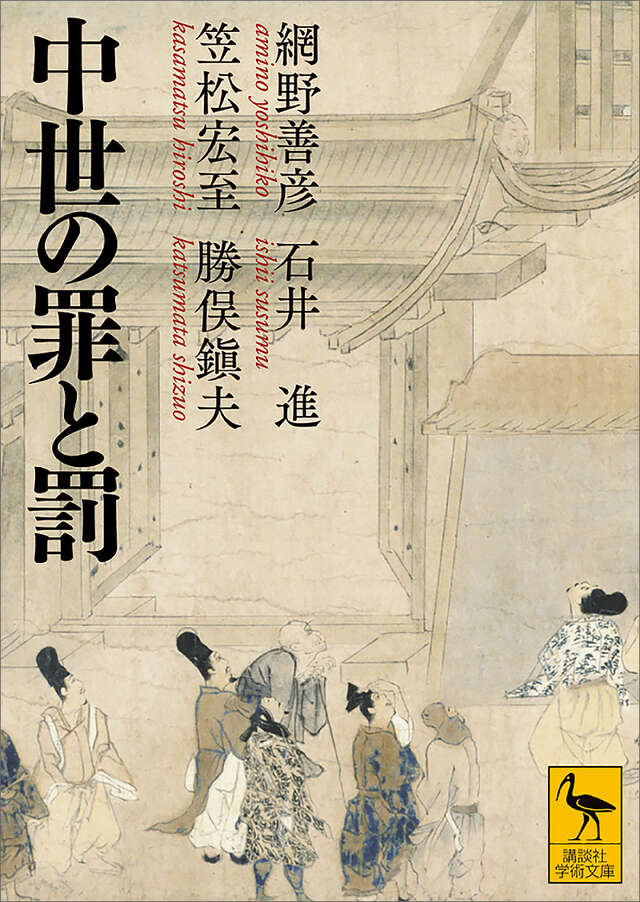
中世の罪と罰
-

「カッコいい」とは何か
-

昭和・平成精神史 「終わらない戦後」と「幸せな日本人」
-

いのちとかたち 天際の借景
-

アメリカと私
-

雑種文化
-

美と宗教の発見 <創造的日本文化論>
-

日本論 文字と言葉がつくった国
-

第二芸術
-

日本社会の構造に分け入る
-

しぐさの日本文化
-

「民都」大阪対「帝都」東京
-

日本文化論
-

日本は80年周期で破滅する
-

檀れいの今残しておきたい、日本の美しいものたち
-

正座と日本人

















