創文社オンデマンド叢書作品一覧

法制史論集8:近世民事訴訟法史
創文社オンデマンド叢書
前巻・取引法史と表裏の関係にある民事訴訟法史を幕府法について、とくに天保改革を境とするその変化に注目して研究したもの。
【目次より】
序
第一編 近世民事訴訟法の体系
第一章 公事人(訴訟当事者)
一 代人
二 介添人(差添人)
三 惣代
四 特別の身分
(1) 苗字帯刀御免
(2) 牧士、能役者および将棋所
五 訴訟人と相手方との関係
(1) 親族関係に基づくもの
(2) 主従関係に基づくもの
第二章 訴訟手続
一 訴状提出
(1) 添書(添使、添簡)
(2) 目安糺
二 本目安差糺出
三 訴状裏判
(1) 訴状裏判
(2) 差紙にて呼出
四 対決
(1) 対決手続
(2) 対決およびその実際
(3) 対決中の諸問題
五 内済
六 判決
七 身代限
八 分散
おわりに
第二編 評定所
はじめに
一 式日、立合および内寄合
(1) 式日、立合
(2) 式日立合に三奉行以外の役人出席
(3) 奉行宅にて吟味の事
(4) 内寄合
二 評定所留役
第三編 近世民事訴訟法の変遷
第一章 寛政相対済令と武家掛出入手続若干の史料
一 寛政相対済令について
二 天保改革以前の武家掛借金銀出入手続若干の史料
(1) 訴訟と公事
(2) 武家に対する判決と切金申渡
(3) 度懸公事
(4) 吟味下訴状と評定所差紙
第二章 享保改革以後天保改革までの民事訴訟法の変遷(切金制の剋服過程)
第三章 天保年間における借金銀取捌方改革
一 借金銀取捌方改革
二 金銀出入取捌改革の関連事項および史料
(1) 評定所公事取扱方申合書
(2) 貸金銀出入其外評定もの取調手続書
(3) 切金員数の改正
附録
第一 裁判の歴史
第二 明治初年の民事訴訟法
第三 大名の御代替朱印改について 棚倉藩の場合
第四 幕末の代官
第五 日本法制史雑観 波動的歴史観に立って
第六 高柳、牧両博士の教えに接して
第七 再び牧、高柳両博士の教えに接して
あとがき

法制史論集7:近世取引法史
創文社オンデマンド叢書
あらゆる意味で対照的な大坂と江戸の取引法を前期と後期に分けて考察した四論文を中心とする江戸時代の取引法史の研究。
【目次より】
序
第一 目安糺、相対済令および仲間事 近世債権法と民事訴訟法の接点
序
一 目安糺 二 無取上 三 相対済令 四 仲間事
第二 家質の研究
第三 江戸の町会所における家質金貸付
第四 江戸時代前期 大坂の取引法史
一 金銀出入 二 取上無き出入 三 一〇年越出入 四 売掛銀滞出入 五 年賦銀出入 六 請人証人出入
七 連判出入 八 利銀出入 九 座頭官 一〇 証文譲、借名前銀子出入 一一 家賃銀出入と借家明出入 一二 貸物出入など
第五 江戸時代後期 大坂の取引法史
一 金銀出入 二 売掛銀滞出入 三 受人、証人の加判差別と受人へ掛る出入 四 連判借出入 五 利銀出入
六 同家人、下人、親掛り之者并女房への金銀出入 七 親類縁者並主従金銀出入、合力出入 八 譲証文並仮名前証文出入
九 借屋明願、家賃銀出入 一〇 貸物および損料出入 一一 同職同商得意妨 一二 奉公人出入
一三 借地面取計 一四 地頭借出入など
第六 江戸時代前期 江戸の取引法史
一 借金銀と預金銀 二 仲ヶ間金 三 利息と高利 四 預ヶ金 五 先住借金 六 家質 七 店立と店賃地代
八 町屋敷の売買 九 普請請負金と大工作料 一〇 証人
第七 江戸時代後期 江戸の取引法史
第一章 大坂取引法と江戸取引法
第二章 江戸の取引法史
(1) 総説
一 相対済令 二 出訴最低額 三 高利
(2) 各説
一 借金銀 二 書入金 三 預金 四 証文譲(譲金) 五 年賦金 六 武士と金銀出入 附、堂上方家来と貸金 七 祠堂金(名目金)
八 官金 九 先納金 一〇 領主地頭借(郷印証文) 一一 地頭裏判借金 一二 売掛金 一三 家賃、地代金および店立地立
一四 損料借品の質入 一五 普請金など
第八 近世取引法史小考
一 「両替屋と餘商売人取引之事」 二 初期の相対済令 三 近世の請人と証人 四 起請文附の私法証文
附録
第一 江戸時代前期 庶民家族法雑考
一 婚姻 二 離別 三 養子縁組 四 後見 五 扶養義務 六 遺言 七 相続跡式
第二 書評 小早川欣吾著、日本担保法史序説
あとがき

法制史論集3:日本団体法史
創文社オンデマンド叢書
著者の史観にもとづく日本の団体法をめぐる通史。とくに江戸時代に関する、村、神社、寺院、猿飼などをめぐる法を紹介する。
【目次より】
序
第一 村の構成員と村中入会 江戸時代および明治初年における
第二 村明細帳
一 村明細帳、郷鑑(手鑑)と村鑑
二 村明細帳について
第三 江戸時代における神社および寺院の法人格
一 神社 (一)小社 (二)東照宮
二 寺院 一山体制
第四 猿飼、茶筅、夙および乞胸 江戸時代賤民の位置附に関する一つの試み
一 (はじめに)
二 猿飼
三 茶筅
四 夙
五 乞胸
六 (むすび)
第五 乞胸補考
第六 近世賤民に関する若干の考察 とくに穢多と非人との関係について
第七 明治四年のいわゆる賤民解放令について
附録
第一 中世人身法制雑考
第二 金沢文庫を探りて 人質文書および人売文書
第三 岡場所考
第四 遊女、飯盛等奉公請状
一 遊女奉公請状
二 飯盛奉公請状
三 飯焼(茶立)奉公人請状
四 洗濯下女奉公証文
五 三味線芸者奉公証文
六 芸者奉公請状
七 妾奉公人請状と役者弟子奉公人請状
第五 新吉原規定証文について
第六 一生不通養子
あとがき

法制史論集2:日本婚姻法史
創文社オンデマンド叢書
日本における婚姻をめぐる法・掟などを、中世から近世、そして明治時代の民法制定までを通して紹介・解説していく。法制史論集の1冊。
【目次より】
序
第一 中世婚姻法
第二 近世離婚法二題
一 離縁状の形式
二 子の帰属
第三 江戸時代の離縁状
一 江戸時代の離縁
二 三行り半の離縁状
三 離縁の理由
四 三行り半以外の離縁状
五 聟養子らへの離縁状
七 明治の離縁状
六 離縁後の手続き
第四 縁切寺 東慶寺の場合
第五 明治初年の婚姻法 とくに法律婚主義と妾について
一 明治初年の法制改革
二 婚姻法制上の改革
三 法律婚主義の成立
四 妾の地位
第六 明治初年の法律婚主義
第七 明治初年の内外人婚姻法
第八 婚姻法史雑考
一 上代婚姻法二題
二 不離縁の担保
三 離縁状の慣行
四 明治婚姻法雑話
五 縁切寺について
六 明治初年の婚姻法草案
七 日本婚姻法略史
第九 明治初年の離婚法 離婚原因の研究
一 裁判離婚
二 願出離婚
三 届出離婚
むすび
あとがき

法制史論集6:家と戸籍の歴史
創文社オンデマンド叢書
明治期の民法制定によって生まれた近代的な「家」の概念とその法規定とは? 江戸時代の「人別帳」は「戸籍」とどんな関係にあるのか。
【目次より】
序
第一 明治民法における「家」の制度生成
第二 戸主権の成立
第三 明治前期分家法
第四 明治民法施行前扶養法
一 序
二 扶養法
三 扶養に関する民法草案
第五 合力
第六 江戸の人別帳 人別高を含めて
第七 明治初年の戸籍法令、戸籍法令草案およびそれら関係資料
第一章 戸籍法令および関係資料
一 天皇直轄領の戸籍法令
二 版籍奉還時代の戸籍法令
三 明治四年の戸籍法とその施行状況
第二章 内務省の戸籍法要領および草案
第八 久雄考
附録 第一 江戸時代における女性(ことに妻)の地位小考
附録 第二 石井教授の『「いえ」と家父長制概念』を読んで
あとがき
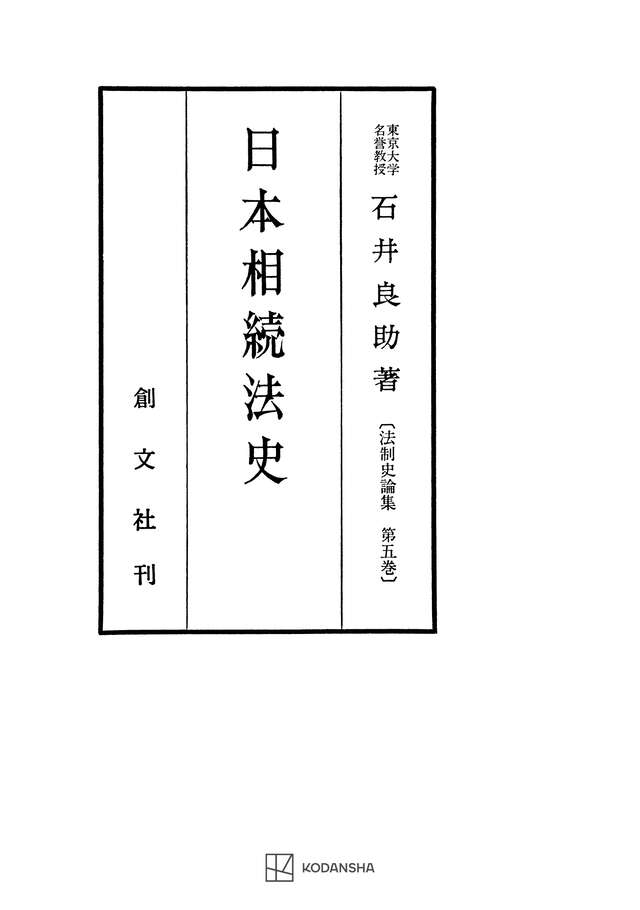
法制史論集5:日本相続法史
創文社オンデマンド叢書
身分・財産の両面にわたり重要な意味をもつ相続の本質は一貫して家業の相続であったと主張し、その各時代における様相を論じる。
【目次より】
序
第一 火継の行事 火切臼と火切杵
第二 長子相続制
第一章 上代(推古天皇―一年以前)
第二章 上世
一 家の相続
二 財産相続
第三章 中世
一 家督相続及び家相続
二 財産相続
第四章 近世
一 前期(戦国時代及び安土桃山時代)
二 中期及び後期(江戸時代)
第五章 近代
第三 我が古法における後見と中継相続 幼年保護を中心として
第四 我が古法における後見と中継相続続考 幼年保護を中心として
第五 明治初年の相続法
第一章 明治維新より明治六年太政官布告第二八号施行以前
一 明治維新より明治三年―二月新律網領施行の前まで
二 明治三年新律綱領(立嫡違法条)の施行より明治六年太政官布告第二八号制定まで
第二章 家督相続 明治六年~明治一四年
一 はじめに
二 死亡相続
三 生存相続
四 特殊相続
五 廃嫡
六 相続の効力
第三章 遺産相続
第四章 遺言
一 遺言
二 遺嘱贈遺
むすび
第六 相続法史料二種
一 法曹類林残缺
二 相続条例
附録 江戸幕府の武家婚姻法五題
一 縁組願とその認可
二 結納と縁夫、縁女
三 婚姻の制限
四 離縁届
五 離縁の場合の問題
あとがき
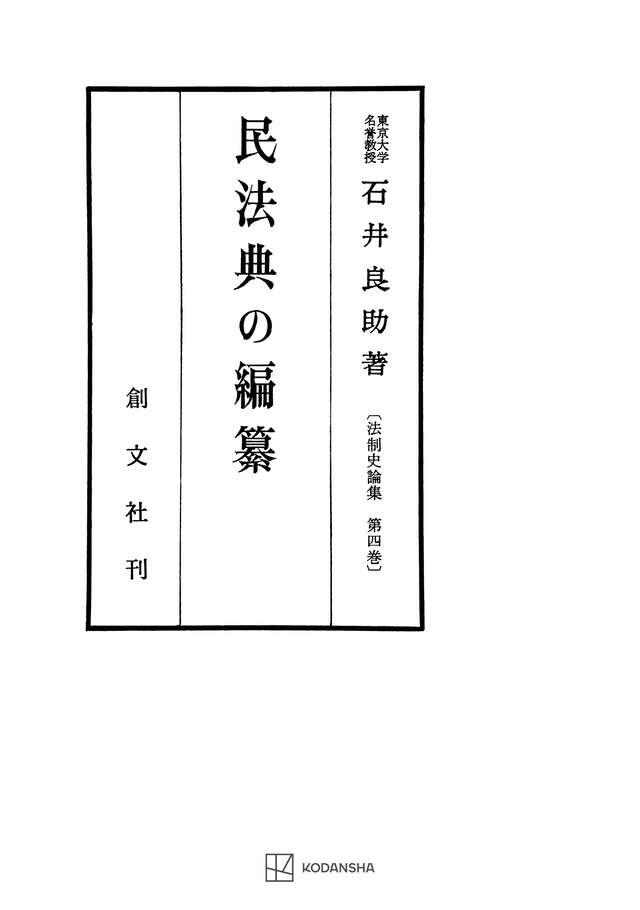
法制史論集4:民法典の編纂
創文社オンデマンド叢書
近代日本が整備した民法はどのような過程を経て成立したのか。明治期の編纂過程を追跡するとともに、江戸以前の法制も振り返る
【目次より】
序
目次
第一 民法典の編纂 民法決議より民法仮定則迄
第二 民法決議第三編至第五編
第三 左院の民法草案
第四 民旧法編纂関係史料若干
一 民効事時効規則と期満規則について
二 民法編明治一九年民纂局の法草案副進書およびボアソナードの上申書
三 民法草案解題
第五 明治初年民法典編纂略史
一 「民法決議」について
二 江藤司法卿時代の同省民法草案
三 明法寮法草案
四 左院の民法草案
五 明治一一年民法草案
六 民法編纂局の開設
七 ボアソナード氏起稿「日本民法草案財産篇」
第六 旧民法人事編元老院提出案、審査会案、議定案および内閣修正案
附録
第一 御成敗式目について
第二 近世法制史料集解説
一 総説
二 法令編
三 判例編
四 寺社奉行編
五 町奉行編
六 勘定奉行編
七 遠国奉行編
八 附札集等編
九 武家方編
第三 御触書集成編纂の沿革
第四 御触書集成について
第五 町式目
第六 いわゆる江戸町中定
第七 明治八年の一私擬憲法案
第八 ボアソナードによる性法の講義
第九 法の公示方法の沿革
第一〇 (書評)住田正一「廻船式目の研究」
あとがき

法制史論集1:大化改新と鎌倉幕府の成立(増補版)
創文社オンデマンド叢書
古代日本の二大画期・大化改新と鎌倉幕府の諸問題につき、法制史の立場よりする画期的な論文10編を収める。
【目次より】
増補版序
序
第一 大化改新の研究 大化改新より大寶律令の制定まで
第二 東國と西園 上代および上世における
第三 鎌倉幕府職制二題
一 征夷大将軍と源頼朝
二 文治守護職と總追捕使
第四 再び「征夷大将軍と源頼朝」について
第五 鎌倉幕府の成立時期
第六 鎌倉幕府の成立 文治の守護と地頭について
第七 大犯三箇條 鎌倉時代の守護の櫂限の研究
第八 東醐と西國 鎌倉時代における
第九 鎌倉幕府政所設置の年代
第一〇 鎌倉幕府成立期の二つの問題 文治地頭職と幕府裁判権
第一一 吾妻鏡文治三年九月十三日條所載のいわゆる北條時政奉書について 石井進氏の批判にこたえて
附録
第一 中世の訴訟法史料二種について
序言
一 沙汰未練書
二 庭訓往来
第二 日本法制史學八十八年 東京大學における
第三 中田博士の法制史の比較研究法について
あとがき

日本法制史概説
創文社オンデマンド叢書
日本法制史を学ぶ上で必要な事項をもれなくとりあげ、各時代におけるその発展と時代間の変遷を叙述した、望みうる最高の概説書。
【目次より】
緒論
本論
第一篇 上代
第一章 序説
第二章 国家組織
第三章 財政制 度附、軍事制度
第四章 司法制度
第五章 刑法
第六章 人法
第七章 財産法
第八章 身分法
第二篇 上世
第一章 序説
第二章 天皇
第三章 統治組織
第四章 財政制度
第五章 軍事、警察及び交通制度
第六章 司法制度
第七章 刑法
第八章 人法
第九章 物権法
第十章 債権法
第十一章 親族法
第十二章 相続法
第三篇 中世
第一章 序説
第二章 天皇及び朝廷
第三章 庄圏及び本所
第四章 武家の棟梁と封建制度
第五章 中央管制
第六章 地方制度
第七章 財政制度
第八章 軍事、警察及び交通制度
第九章 司法制度
第十章 刑法
第十一章 人法
第十二章 物権法
第十三章 債権法
第十四章 親族法
第十五章 相続法
第四篇 近世
第一章 序説
第二章 天皇及び朝廷
第三章 武家の棟梁と封建制度
第四章 中央管制
第五章 地方制度
第六章 財政制度
第七章 軍事、警察及び交通制度
第八章 司法制度
第九章 刑法
第十章 人法
第十一章 物権法
第十二章 債権法
第十三章 商法
第十四章 親族法
第十五章 相続法
索引

日本不動産占有論 中世における知行の研究
創文社オンデマンド叢書
中世から始まった領主が領地や財産を直接に支配することが知行である。ここからどのようにして本邦における不動産の占有が始まったのかを探る。
【目次より】
序
一 序説
二 知行制の成立
三 知行の構成要索
四 知行の本質及び法律上の意味
五 知行の効力
六 知行の保護
七 知行制の発展
八 GewereとPossessioと知行
九 結言

江戸時代土地法の生成と体系
創文社オンデマンド叢書
まず近世土地法の生成の歴史を叙述、ついで土地に関する法律用語の意義を明らかにし、合わせて難解な江戸時代土地法を解明。
【目次より】
序文
目次
第一 地租改正と土地所有権の近代化 第二七回東洋学者会議における報告
第二 江戸時代土地法の体系
第三 江戸時代土地法の生成
第四 統轄、領知、所持、進退および支配 江戸時代土地法の基礎構造
一 統轄(将軍による大名の統轄)
二 大名の領知
三 (庶民による)土地の所持
総説
A 田畑永代売の禁令
B 江戸時代における用水路の所有権
C 江戸の町屋敷
(i) 江戸の町屋敷
(ii) 江戸の町屋敷の売買
四 進退と入会権
A 江戸時代の入会権と地租改正
(i) 江戸時代の入会権
(ii) 地租改正
B 「江戸時代の入会権と地租改正」続考
C 安政五午年三月山田村秣場一件留 江戸時代入会権の性質をよく示す史料
D 山梨県山中部落の入会権 第一章 法制史的研究
五 江戸時代における土地の「支配」 物権の行使として
初出一覧

中国語学研究(東洋学叢書)
創文社オンデマンド叢書
音韻史研究を基礎に言語史の諸問題を、音韻史考説、語形と語義の変化、文字学と字書の研究、紹介と批評の四部に集大成。
【目次より】
目次
第一部 音韻史考説
一 詩経異文の音韻的特質
二 形聲字音の特質 カールグレン氏の学説を中心にして
三 反切の起原と四聲および五音
四 〓と爾および日母の成立
五 等韻図と韻海鏡源 唐代音韻史の一側面
六 「南朝四百八十寺」の読み方 音韻同化の一例
七 唐詩の押韻 韻書の拘束力
八 蘇東坡古詩用韻考
九 書史会要に見える「いろは」の漢字対音について
第二部 語形と語義の変化
十 代名詞〓們の沿革
十一 多少と早晩
十二 風流の語義の変化
第三部 文字学と字書の研究
十三 中国文字の構造法
十四 千字文について
十五 宋・遼・金時代の字書
十六 山梨稲川の説文学の著述 天理図書館所蔵の稿本について
第四部 紹介と批評
十七 李方桂氏「中国における諸民族の言語と方言」
十八 董同〓氏「中國における言語調査」
十九 趙蔭棠氏の『中原音韻研究』を読みて
二十 ポール・セリュイス氏「楊雄の『別国方言』にみえる漢代諸方言の研究」を評す
あとがき
掲載誌一覧

日本人と思想
創文社オンデマンド叢書
福澤諭吉、幸徳秋水、夏目漱石など近代日本の形成期の思想から、西田幾多郎、鈴木大拙、和辻哲郎などより深化した日本思想を問う。
【目次より】
文明と社会
一 福沢諭吉における「文明」の研究
二 幸徳秋水における「反逆」の研究
キリスト教と仏教および哲学
三 内村鑑三に現われた神と人に関する考察
四 東洋的空と無の関連における西田幾多郎の哲学と鈴木大拙の禅について
文学と教養
五 夏目漱石 世界における日本の天才と文学の問題
六 和辻哲郎 日本的エートスとパトスの探究者
民族の歴史と教育思想
七 津田左右吉の精神と内容
八 森信三の日本的正気の心実学と教育的実践
あとがき

神秘家と神秘思想
創文社オンデマンド叢書
西洋のゲーテの神秘思想から、中国の老子、インドの『ギーター』、仏陀の『スッタニパータ』を読み解き、古今東西の神秘思想を読解する。
【目次より】
献呈のことば
目次
第一章 ゲーテにおける神秘主義の近代的メタモルフォーゼ(変形)
序論
一 ゲーテ自身が語っている彼の神秘の体験について(『詩と真実』より)
二 ゲーテに現われた神秘主義の諸相
三 ゲーテによる神秘主義の近代化
四 成長する生命の樹 変身変化の術
五 ゲーテの芸術の秘密と言葉の不思議について
六 青春回帰と根源復帰の秘密について
七 女人神秘主義
八 神秘劇(ミステリウム)としての『ファウスト』
第二章 神秘主義者としての老子の新解釈
序論
一 老子が神秘家であることの証明
二 東洋的神秘主義における意識の下降性
三 神秘主義と政治
四 政治における道の効用と無の展開
五 老子の人物像
第三章 ヒマラヤの声 「バガヴァッド・ギーター」制作の秘密とその現代的意義
序論
一 アルジュナの存在状況と精神構造
二 声(幻聴)の問題
三 「ギーター」における神秘主義
四 「ギーター」に現われた神
五 「ギーター」において現代に生きるもの
第四章 仏陀の悟りと神秘主義 『スッタニパータ』を中心として
一 再び生れてこないために
二 仏教における純内面主義の神秘道
三 清浄行
四 慈悲行
五 不可知論的神秘主義(立場なき立場)
六 滅(時間停止)
七 仏教的聖の形成(歴史的仏陀の神秘的変容)
むすび
一 定義
二 形態学
三 近代神秘主義における冒険性と実験精神
四 カオスとポラリティの近代的性格
五 神秘主義におけるモダニズムの問題
六 現代における神秘主義の機能
未来へのプレリュード
後記

杜甫の研究
創文社オンデマンド叢書
杜甫の多彩な文学と人生を、文学的考察、作品研究、杜甫と仏教、杜詩の発見、日本における杜詩など広範な角度から考察した力作。
【目次より】
序
第一章 文学的考察
一 詩人としての自覚
(附録) 唐代における詩の伝播について
二 杜詩の象徴性とその哲学
三 杜甫における李白の意味
第二章 作品の研究
一 「崔氏東山草堂」詩の作時について
(附録) 芭蕉の「秋深き」の句と、杜甫の「崔氏東山草堂」の詩について
二 「秋興八首」序説
三 「又呈呉郎」の詩について 「即防遠客雖多事、便挿疏籬却甚真」考
四 「登岳陽楼」の詩について 「呉楚東南〓、乾坤日夜浮」考
五 「王洙、舟中伏枕書懐、三十六韻」の作時について
第三章 杜甫と仏教
一 杜甫の仏教的側面
二 杜詩における摩訶薩〓の投影
三 「秋日、〓府詠懐、一百韻」における「七祖禅」についての考察
第四章 杜詩の発見
一 中唐より北宋末に至る杜詩の発見について
二 「唐書」杜甫伝中の伝説について
三 王洙本「杜工部集」の流伝について
第五章 日本における杜詩
一 日本における杜詩享受の歴史
二 芭蕉文学における杜甫
三 島崎藤村における杜甫 「千曲川旅情の歌」を中心にして
第六章 雑考
一 杜詩「幽興」考 杜甫の自然観への手がかり
二 杜甫と薬草 「同谷七歌」黄精考
三 杜甫家族考
初出一覧

杜詩とともに
創文社オンデマンド叢書
杜詩の味わい、杜甫と日本文学、世界文学の中の中国文学、そして杜甫との触れ合いを求めた旅の数々を多彩に綴る珠玉のエセー。
【目次より】
はしがき
杜詩とともに
一 杜詩とともに 『杜甫の研究』に寄せて
二 杜甫の哲学
三 「春夜喜雨」詩小記
四 「遊何将軍山林、十首」覚え書
五 杜詩における景情一致について
六 杜甫における李白
七 「杜甫」「杜工部集」
八 杜甫と吉川先生とわたし
三笠の月 比較文学の試み(I)
一 三笠の月 阿倍仲麻呂の歌について
二 源氏物語と琵琶行 「桐壺」野分の段における月光描写をめぐって
三 杜甫と芭蕉 「行く春や」の句の出所について
四 富士川英郎『鴟〓庵閑話』
五 唐詩と三好達治
六 日本における中国文学(付華訳) 四川大学における講学
七 極東文学史の構想
悲哀と光明 比較文学の試み(II)
一 わが青春の読書
二 中国文学における悲哀の浄化について
三 文学としての『観無量寿経』
杜甫への旅
一 杜甫への旅
二 ヨーロッパ便り わが愛する小さなものたちに
三 ひとつの思い出 ミセス・オークスのこと
四 アグリゼントの春
五 薛濤の井戸 「音に見えしかそけき琴はかよひ来て」
六 杜甫紀行
あとがき

道徳とは何か 倫理学入門
創文社オンデマンド叢書
人格の平等、自由などの問題を身近な生活に即して考察し、倫理学の戸口にまで導いていく、ユニークな入門書。
【目次より】
まえがき
第一講 倫理の混乱と倫理思想の混乱
第二講 倫理は変化するか
第三講 横の倫理と縦の倫理
第四講 社会倫理と職業倫理
第五講 人格の平等と平等の倫理
第六講 人格の自由と自由の倫理
第七講 自由平等の矛盾と調節
第八講 保守と革新、伝統と創造
第九講 革命・暴カ・戦争
第十講 国家に於ける権力と倫理
第十一講 講国民道徳と愛国心
第十二講 文明の進歩と倫理
第十三講 倫理学の立場(一)自然主義
第十四講 倫理学の立湯(二)理想主義
第十五講 倫理学の立場(三)汎神論
第十六講 義務の葛藤と倫理の限界

政治家への書簡(続)
創文社オンデマンド叢書
混迷を深める世界情勢の中、正しい哲学をもつ政治のみが人類を救う。核、政治の問題に時に剣法の話も混じえ、明日への道を構想する。
【目次より】
前篇
一 日本人の平和主義の心理と論理
二 聖徳太子憲法の「和」の哲学
三 永久の友もなければ永久の敵もなし 歴史の教訓は世界史と共に変わる
四 ベトナムにおける米国挫折の教訓の数々
五 核兵器と称せられているものはどこまでが「兵器」か 核軍縮には兵器の定義を先行させよ 針谷夕雲の「相抜け」の剣法
六 政体の傑作と駄作
七 現代文明の知性と非叡知性
八 シビリアン・コントロール
後篇
九 国際政治の感覚を磨け
一〇 文明とは何か その進歩発展の様相について
一一 歴史意識育成の肝要性
一二 義務の闘争
一三 人間の自由と平等 その矛盾と調節
一四 人類の進歩と退歩
一五 進歩と進歩を越えたもの
一六 日本の建国神話
一七 共産革命は永久未完の革命か
一八 共産主義の多様性
一九 社会帝国主義とは何なのか
二〇 戦後日本の与党と野党
二一 政治責任皆無の野党天国
二二 ジリ貧・ドカ貧・さむらい精神
あとがき

政治家への書簡
創文社オンデマンド叢書
折にふれ問題となった事柄について、知友の政治家に送った書簡集、ひとり政治家のみならず国民大衆の教養識見に訴えんとする警世の書。
【目次より】
前篇
一 欠陥教育は半世紀後に民族の衰亡を
二 第二次世界大戦は何であったか その残した教訓
三 憲法を改正するには
四 アメリカ大統領制の平時と非常時
五 政党と派閥
六 「たてまえ」政治は政治というものか
七 科学的社会主義の自己矛盾
八 共産主義国の言動を理解するには
九 元首と象徴(天皇の御訪欧)
一〇 天皇の立憲的君主性(天皇の御訪米)
後篇
一一 権力の象徴と権威の象徴
一二 首相・総裁たるの資質
一三 選挙悪
一四 ”敵・味方“の政治
一五 国会の多数暴力と少数暴力
一六 軍人は軍国主義、文民は平和主義か
一七 奪うもならず捨つるもできぬ自衛権
一八 護憲論者は反革命の自由を擁護するか
一九 嘘は罪にならないのか
二〇 産業スパイと国家機密
二一 必要悪の善用
二二 秘密外交と民主主義
二三 十八歳選挙権への疑問
二四 「違憲」の乱用
二五 乱れる司法界の職域倫理
二六 冷戦とは何か、冷戦はもう終ったのか
二七 人民を人質にするストはストなのか
二八 自明なことが余りにも不明であり過ぎる
あとがき

ハイデッガーはニヒリストか(フォルミカ選書)
創文社オンデマンド叢書
20世紀最大の哲学者は、予言者なのか? 虚無主義者なのか? ハイデッガーの思想を俯瞰して、その思想の最奥部へと分け入る。
【目次より】
第一章 ハイデッガーはニヒリストか
一 存在の森
二 「形而上學とは何か」への回想
三 「存在と時間」から「時間と存在」へ
四 〈世界の夜〉と被投性
五 〈死への自由〉から〈開存〉の自由へ
六 〈存在の光〉と〈開け〉
七 避けらるべき三つの解釈
八 真理の本質は〈不・真理〉である
九 真理の本質は〈根源的な闘争〉である
十 〈存在〉と〈無〉
第二章 豫言者ハイデッガー
一 三つの問題
二 キェルケゴール的とニーチェ的
三 〈世界の夜の時代〉或ひは〈世界像の時代〉
四 〈存在の歴史〉の立場
五 〈存在の歴史〉は〈存在忘却〉と共に始まる
六 言葉は〈存在の家〉である
七 豫言者・詩人・人間
八 豫言者ハイデッガー
九 詩は歴史を支へる地盤である
第三章 ハイデッガーの〈祝福〉
一 〈人は存在の近きに住む〉
二 〈祝福の次元〉
三 〈存在の声〉と〈存在への畏敬〉
補遺第一 ハイデッガーの「帰向」と西田哲學
一 〈存在〉と絶対無
二 〈存在の思惟〉と思考法の転回
三 〈止まるもの〉と〈流れるもの〉
四 逆対応と〈逆投〉
補遺第二 ハイデッガー関係の二著作について
一 『実存と存在』について
二 『存在の問題』について
あと書