創文社オンデマンド叢書作品一覧

漱石の世界
創文社オンデマンド叢書
西田幾多郎とカール・バルトに学んだ神学者・哲学者の著者が、文豪夏目漱石の世界に迫る。西洋文明との出会いの中で、「則天去私」に至った明治の作家の心の内奥に迫る。
【目次より】
新版の序
序
第一章 倫敦の経験(「自己本意」の決意)
一 漱石の「自己」というもの
二 『私の個人主義』と謂わゆるエゴイズム
~
九 彼の不安は何故消えたか
十 彼が倫敦で「新しく掴んだ」「自己本位」の真義 それと「東洋趣味」及び「生涯の事業」との関係
十一 「自己本位」の信念は何故『文学論』の著述を断念した後にもその力を保ち得たか
十二 『私の個人主義』に於ける漱石の体験分析の曖昧とその原因
第二章『文学論』と神経衰弱
一 帰る日まで
二 帰ってから
三 『文学論』の骨組
~
七 日露戦争 友人と門下生 表現の意欲
八 漱石は何故彼の『文学論』を「学理的閑文字」と呼んだか 漱石の神経衰弱及び創作の意欲そのものと、それについての漱石自身乃至諸家の批評との間の隔たり
第三章 作品の発展 その一
第一節 『野分』まで
第二節 『虞美人草』
第三節 『坑夫』
第四章 作品の発展 その二
第一節 『三四郎』
第二節 『それから』
第三節 『門』
第五章 作品の発展 その三
第一節 『思ひ出す事など』 修善寺の大患とその意義について
第二節 『彼岸過迄』
第三節 『行人』
第四節 『こゝろ』
第六章 「則天去私」とその後の作品
第一節 『硝子戸の中』と「則天去私」
第二節 『道草』
第三節 『明暗』
結論
あとがき
新版の跋

実存倫理の歴史的境位 神人と人神
創文社オンデマンド叢書
京都学派の哲学者であった著者の本格的哲学論考。「近代の超克」を引き継ぐべき著者は、戦後早々に哲学的思索をやめてしまう。その思想の軌跡に迫るための必読書。
【目次より】
第一論文
一、本題名中の『歴史的境位』について
二、本題名中の『実存倫理』について
三、副題名『神人と人神』について
四、収録論文とその成立過程について
五、主体的現象学について
六、全文を反省して
第二論文
第一節 行為的人間
第二節 悲劇の誕生
第三節 悲劇の性格
第四節 悲劇的個体
第五節 悲劇的行為
第六節 ヒュブリスとネメシス
第七節 善悪と運命
第八節 和解とカタルシス
第九節 歴史の悲劇性
第三論文
第一節 黄金時代の想起
第二節 ユートピアの期待
第三節 ゼーノーンの反復
第四節 エピクテートスの克己の倫理
第五節 マールクス・アウレーリゥスの孤高の倫理
第六節 倫理と歴史的現実
第四論文
第一節 苦難の根本義
第二節 倫理と宗教の相剋
第三節 自主性のパラドックス
第四節 苦難の反復
第五節 苦難の超剋
第六節 神人と人神の相即の課題
第五論文
第一節 問題提起
第二節 カントの宗教論の主体的必然性
第三節 敬虔主義と啓蒙主義
第四節 理性的道徳宗教の第一歩
第五節 善悪の主体的相剋とその宿命
第六節 道徳的理念の宗教的理念への転化
第七節 心術の変革
第八節 自由の具現の現実的媒体
第九節 近代的理念の実存的限界
第六論文
第一節 ニヒリズムの到來
第二節 ニヒリズムの道徳的背景
第三節 クリスト教とニヒリズム
第四節 ヘレニズムとヘブライズムの抱合
第五節 近代科学とニヒリズム
第六節 道徳と宗教の亀裂
第七節 人神のニヒリズム
第八節 虚無への虚無
終論
第一節 イエスの弁証
第二節 自由の実存
第三節 愛の弁証法
第四節 受難と悔改の倫理
第五節 使徒対天才
第六節 イエスを師として

資本制経済の基礎理論(増訂版) 労働生産性・利潤率及び実質賃金率の相互関連
創文社オンデマンド叢書
資本主義経済とはどのような経済体制なのかを、労働生産性、利潤、実質賃金率を中心に探究する格好の入門書。
【目次より】
序章
第1章 価値
第1節 価値の決定
第2節 価値の理論的意義
第2章 利潤の存在条件
第1節 純生産可能条件
第2節 剰余条件
第3節 利潤の存在条件
第3章 平均利潤率
第1節 平均利潤率の存在条件
第2節 平均利潤率の決定要因
第3節 固定資本および生産方法の代替的変化
第4節 「利潤率傾向的低下法則」について
補論 疑問への回答
第4章 実質賃金率
第1節 階級対立と実質賃金率
第2節 実質賃金率の短期的決定
第3節 Wage-Price Spiral について
第4節 実質賃金率と資本蓄積

再生産の理論(現代経済学叢書)
創文社オンデマンド叢書
数理マルクス経済学の基本図書。資本家が投下した資本から生み出された剰余価値を自ら消費すれば、単純再生産となり、剰余価値の一部を新たに資本投下して、拡大再生産となる。社会的総資本は、生産のみならず流通にも投下され、それを考慮して資本総体の動きを数理的に捉えるための理論の入門書。
【目次より】
はしがき
序論
一 再生産の一般性と特殊性
二 再生産の二重性
第一篇 物質的財貨の再生産
第一章 労働生産性
第一節 労働生産性の概念
一 労働の限界生産力および貨幣費用による労働生産性の規定
二 投下労働量による労働生産性の規定
第二節 労働生産性を規定する諸要因
一 基本的要因=生産力
二 副次的要因
三 生産方法の選択
第三節 労働生産性と物質的財貨の再生産
一 生産財補填と労働生産性
二 労働力の再生産と労働生産性
三 社会発展と労働生産性
第二章 生産諸要素
第一節 労働力
一 総人口
二 総人口のうちで労働にたずさわる成員の比率
三 労働する成員のうちで物質的財貨の生産に従事する成員の比率
四 年間に物質的財貨の生産のために労働する日数
五 一日の労働時間および強度
第二節 生産財(労働生産物たる生産手段)
一 生産財の期首存在量
二 生産財の稼働度
第三節 自然的生産手段
第三章 生産編成
第一節 生産編成と物質的財貨の再生産
一 労働生産性と生産編成
二 生産要素の存在量と生産編成
三 総生産物・純生産物・剰余生産物
第二節 単純再生産の編成
一 剰余生産物なき場合
二 剰余生産物の存在する場合
第三節 拡大再生産の編成
一 労働生産性の不変な場合
二 労働生産性が変化する場合
第四章 生産物の再生産的充当
第一節 生産財補填、労働力再生産のための生産物充当
第二節 最大生産規模と現実生産規模
第二篇 生産関係の再生産
第一章 生産関係の基礎
第一節 生産関係の概念
第二節 生産関係の基礎
第二章 生産関係の基礎の再生産
第一節 生産関係再生産と上部構造
第二節 生産関係再生産と分配様式
第三節 生産関係再生産と物質的財貨の再生産
第三篇 生産様式の再生産
第一章 物質的財貨の再生産による生産関係の規定
第二章 特定の生産関係の下での物質的財貨の再生産
第一節 原始共同体での物質的財貨の再生産
第二節 奴隷制社会での物質的財貨の再生産
第三節 封建制社会での物質的財貨の再生産

作家の青春(フォルミカ選書)
創文社オンデマンド叢書
文芸批評家、劇作家、小説家で、文化功労者の著者は、私小説批判で知られている。明治期の二大文豪、漱石と荷風の若き日を論じた著作である。
【目次より】
永井荷風
I 荷風の青春
II アメリカを中心に
III フランスを中心に
IV 肉化と再生
夏目漱石
I 漱石の青春
II 文明批評
III 漱石の旅行記

尾崎喜八詩文集10:冬の雅歌
創文社オンデマンド叢書
詩人、随筆家、翻訳家、また、クラシック音楽への造詣も深い著者は、山や自然を描いた詩や散文の秀品を多く残した。
本書は、詩集・散文集である。
【目次より】
詩集『田舎のモーツァルト』(昭和四十一年)三八篇
冬の雅歌
不在
妻に
ハインリッヒ・シュッツ
秋
霧と風の高原で
岩を研ぐ
春の葡萄山
モーツァルトの午後
出合い
歳月
田舎のモーツァルト
ひとりの山
七月の地誌
回顧
車窓のフーガ
高処の春
あかがり
復活祭の高原
山中取材
野の仏
蝉
或る石に刻むとて
湖畔の朝
鴨
和田峠
馬籠峠
上越線にて
受胎告知
春興
桃咲く春
高地牧場
故園の歌
十年後
朝の門前で
草津白根
予感
飼育場風景
詩集『その空の下で』(昭和四十五年)から 一八篇
されど同じ安息日の夕暮れに
音楽会で
シューマンと草取り
一つのイメージ
ほほえましいたより
復活祭
晩年のベルリオーズ
森林限界
詩人と笛
夏行
鎌倉初秋
古い山の地図を前にして
続けかしの歌
二つの現実
エリュアール
その空の下で
黄道光
沈みゆく星に寄せて
散文 山は離れど
山は離れど
おおるり・こるり
小梨の花咲く上高地
秋の山にて
憧れのオーヴェルニュ
ヤドカリ
昔の仲間
夏の花
『緑の斜面』に寄せて
きれぎれの思い出
写真機と奥武蔵
三ツ葉ツツジ
自然・音楽・祈り
中世の秋とルネサンスの春
わが生の伴侶 歌
その時々のバッハ
バッハのオルガン音楽
バッハ音楽への感謝
私とベートーヴェン
クープランとラモー
私のベルリオーズ
カロッサ
ヘッセ
ジャム
思い出
私の語学独学自習
野のキリスト者
朝の山と夕べの渚
拾遺詩篇 一九篇
寒夜に思う
番所の原
山の湖
雉
秋
無名の冬
ひそかな春
大日小屋(金峰山)
行者小屋(八ガ岳)
七丈ノ小屋(東駒ガ岳)
将棋頭ノ小屋(木曽駒ガ岳)
今日
紐
演奏会から帰って
音楽に寄せて
詩を書く
オルガンのしらべ
浜辺
朝のコーヒーを前に
後記
著作年譜

尾崎喜八詩文集9:晩き木の実
創文社オンデマンド叢書
詩人、随筆家、翻訳家、また、クラシック音楽への造詣も深い著者は、山や自然を描いた詩や散文の秀品を多く残した。
本書は、散文集である。
【目次より】
一年の輝き(一九六二年)
1 芝生の中の宝石 2 イソギクの小曲 3 水辺の一場景 4 枯葉の歌 5 真冬のヒバリ 6 ふるさとの水の上に 7 波のように 8 皿の上の早春 9 受胎告知 10 町をゆく牧歌 11 ヴェロニカ・ペルシカ 12 まがきのほとり 13 王朝風な時間 14 別れの笛 15 山荘の森の灯 16 美の哀愁 17 世代の移り 18 初夏を彩る 19 初夏の歌 20 或るメーデー歌 21 警告 22 自然詩人の花 23 セレナード 24 高原の炎 25 庭の裁断師 26 水上の夏の歌 27 まろく、重たく 28 渓流の美魚 29 シャロンの野花 30 霧のコルリ 31 夏の焦燥 32 路傍のムクゲ 33 空の黒片 34 水を運ぶ母 35 晩夏の詩の花 36 初秋の輪唱 37 たそがれの夢の花 38 貝しらべ 39 誠実な訪問者 40 秋光燦々 41 寒気に追われて 42 充実と落下 43 合戦尾根にて 44 信濃路の秋 45 百合の木の歌 46 美しい吸血鬼 47 カラマツ荘厳 48 賢者の石 49 野性を恋う 50 微生物に思う 51 冬にも緑 52 年輪の含蓄
生活の中の音楽
バッハへの思い
ベートーヴェンと自然
冬の日記から
私と笛
ドビュッシーのバガテル
書窓雑録
カロッサへの感謝
詩と言葉
蔵書と読書
秋の日記から
野外手帖から
デュアメルのかたみ
デュアメル追悼
カロッサの教訓
若き日の友の姿
交友抄
自然と共に
1 五月の峠 2 富士見紀行 3 奥日光の一日 4 西伊豆の海と丘 5 武蔵野の早春賦 6 那須高原と久慈渓谷 7 春を待つ山
甲斐路の春
浅間山麓の一日
美ケ原の秋
武蔵野の鳥
知多半島の一角
高村光太郎
大いなる損失
あの手のイメージ
ふたたびの春
高村さんとの旅
初めて見たアトリエ
晩秋の午後の夢想
片思いの頃
智恵子さんの思い出(一) 智恵子さんの思い出(二)
鎌倉にて
その土地への愛の序曲
折り折りの記
初秋
友人
病院にて
心平さんの鎌倉来訪
海岸で
道
憩いの店
後記

尾崎喜八詩文集8:いたるところの歌
創文社オンデマンド叢書
詩人、随筆家、翻訳家、また、クラシック音楽への造詣も深い著者は、山や自然を描いた詩や散文の秀品を多く残した。
本書は、散文集である。
【目次より】
序詩
野外と屋内
家と環境
晩春の或る午後
孫
小さい旅
誌の鑑賞
夏から秋への一日
故園の歌
木曾の旅
旅の小鳥と庭のツグミ
冬晴れ
早春
日記から(一)
マドレーヌ・ロランのこと
私の愛鳥週間
日記から(二)
旅のたより
牧場の変奏曲
鳥居峠
梓山紀行
山口耀久
山の詩と山の詩人
山小屋への想い
詩と音楽
生きているレコード
エステルとアンリエット
ロマン・ロランと自然
秋を生きて
過ぎゆく時間の中で
旅で知る妻
小さい傑作への讃歌
友への手紙
砂丘にて
春浅き海と山
自然と共にある故に
『わが愛する山々』
『人類の星の時間』
タゴールについて求められて
処女詩集の思い出
或る小さい体験
結びの詩
後記

尾崎喜八詩文集7:夕映えに立ちて
創文社オンデマンド叢書
詩人、随筆家、翻訳家、また、クラシック音楽への造詣も深い著者は、山や自然を描いた詩や散文の秀品を多く残した。
本書は、散文集である。
【目次より】
詩人
雙眼鏡
クリスマスへの道
笛
或る回想
祖父の日
夏と冬の素描
胡桃の木の下で
焚火
氷の下の歌
復活祭
帰京
静かな時間の三部作
秋とルオー
夕日とデュパルク
オルゴールとジューヴ
季節の短章
八ガ岳を想う
初冬の心
鳥を見る二人の男
しぐれ
冬の庭
自然の中の春の歌
春の告知
五月のたより
晩夏
私の庭
末消ゆるこころの波
よみがえった句
霧ガ峯紀行
木曾の旅から
秋の日記
晩秋
高原の冬の思い出
折れた白樺
上高地紀行
同行三人
国立自然教育園
武蔵野晩秋
皇居に残る「江戸」
放送歳時記
郭公
焚火と霜
春の田園詩
リルケについて
訳詩の思い出
その詩の一面
ヘルマン・ヘッセと自然
後記

尾崎喜八詩文集6:美しき視野
創文社オンデマンド叢書
詩人、随筆家、翻訳家、また、クラシック音楽への造詣も深い著者は、山や自然を描いた詩や散文の秀品を多く残した。
本書は、散文集である。
【目次より】
高原暦日(一九四六年~一九四七年)
到着
恢復期
野薔薇
森のオルフォイス
真夏の散歩
晩夏
音楽会
野鳥と風景
冬空の下
美しき視野(一九四六年~一九四七年)
九月の断章
高原初秋
風の音
ホオジロの歌
菌類一種
エゾゼミ
ちいさい物
ウーロン茶
雲に寄せることづて
雲二題
或る夕べの雲
或る朝の雲
入笠山にて
採集行
別れの曲と到着の歌
湖畔の町の半日
ホトトギス
童話
秋の林にて
背負子
マーテルリンクの朝
春はふたたび
ベアルンの歌
背負子
山村俯瞰
友情
森の子供たち
碧い遠方(一九四七年~一九五〇年)
店頭の青げら
泉
初秋の数日
石の花びら
木苺の日
紫つめくさ
草に寝て
一日の終りに
乾草刈の頃
豆畠にて
落葉掻きの時
蹄鉄工
二月の春
春の雲
寂しさと桜草と
朴の杖
小さい旅人
盛夏白昼
冠着
初秋の湖
老の山歌
西穂高
入笠山
草山のはて
入笠小屋
或る遭遇
秋の隣人
初冬の客
柿
初心者
輝石
虹
秋の丘で
湖畔の星
黄びたきの災難
雛鳥記
黄昏の飛行家
ハドスン的な冬の一日
後記

尾崎喜八詩文集5:雲と草原
創文社オンデマンド叢書
詩人、随筆家、翻訳家、また、クラシック音楽への造詣も深い著者は、山や自然を描いた詩や散文の秀品を多く残した。
本書は、散文集である。
【目次より】
雲と草原
美ガ原
秋山川上流の冬の旅
戸隠と妙高
須走
灰のクリスマス
神流川紀行
一日
羽族の思い出
鴉とつばな
初心時代
蝶の標本とヘルマン・ヘッセ
雲を見る
初めに驚きありき
ノルウエイ・バンド
こころ
橡の実
信濃乙女
べにばないちご
遠い国での話
或る朝のおもい
雲の中で刈った草
春
少女の日
詩人の風土
泉
かんたん
信州峠
荒寥への思慕
早春の雨の夜
春の帰途
高原の朝
夏が又来た
単独登山
旅への祈り
大菩薩峠で
三城牧場
通過列車
小手指ガ原
麦刈の月
井荻日記
冬の途上
水車小屋へ
麦刈の月
二つの歌
秋の歌
冬の歌
蝶の渡海
一日の春
多摩河原
大平原
後記

尾崎喜八詩文集4:山の絵本
創文社オンデマンド叢書
詩人、随筆家、翻訳家、また、クラシック音楽への造詣も深い著者は、山や自然を描いた詩や散文の秀品を多く残した。
本書は、散文集である。
【目次より】
絵のように
たてしなの歌
念場ガ原・野辺山ノ原
花崗岩の国のイマージュ
神津牧場の組曲
御所平と信州峠
大蔵高丸・大谷ガ丸
蘆川の谷
新年の御岳・大岳
高原にて
一日秋川にてわが見たるもの
画因と素描
山への断片
木暮先生
子供と山と
「山日記」から
美しき五月の月に
山と音楽
高山植物雑感
追分の草
胴乱下げて
ハイキング私見
「山に憩う」友に
秩父の王子
松井幹雄君の思い出
秩父の牽く力
春の丘陵
一日の王
附録 山と芸術
山と芸術
或る単独登山者の告白
後記
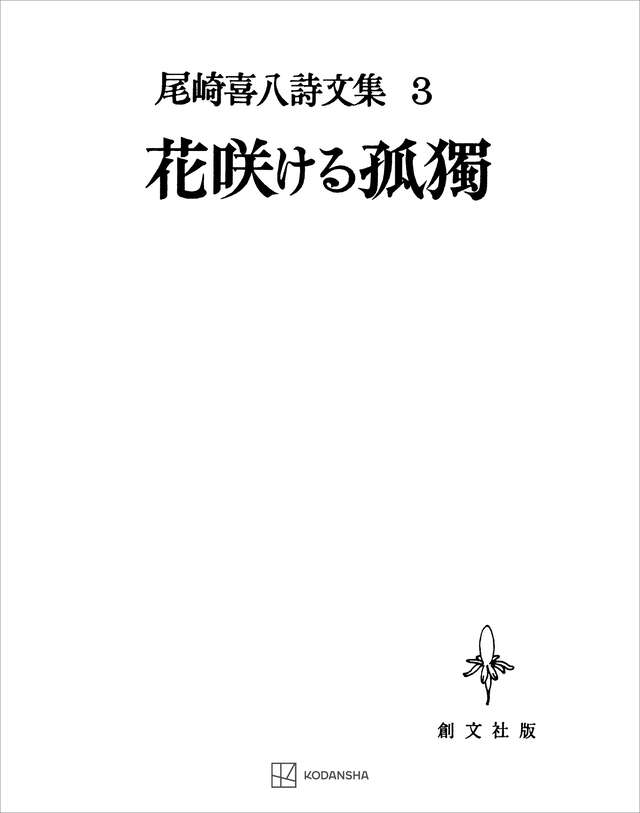
尾崎喜八詩文集3:花咲ける孤独
創文社オンデマンド叢書
詩人、随筆家、翻訳家、また、クラシック音楽への造詣も深い著者は、山や自然を描いた詩や散文の秀品を多く残した。
本書は、詩集である。
【目次より】
花咲ける孤独(昭和三十年) 七三篇
告白
冬野
詩心
本国
新らしい絃
存在
落葉
夕日の歌
土地
秋の日
首(造型篇の一)
トルソ(造型篇の二)
短日
朝のひかり
十一月
雨氷の朝
春の牧場
夏の小鳥が……
薄雪の後
旗
冬のはじめ
本村
夏野の花
或る晴れた秋の朝の歌
雪に立つ
足あと
雪の夕暮
春の彼岸
早春の道
復活祭
杖突峠
夏雲
山頂
秋の漁歌
農場の夫人
冬のこころ
地衣と星
雪山の朝
安曇野
葡萄園にて
八月の花畠
晩秋
炎天
盛夏の午後
路傍
幼女
老農
フモレスケ
或る訳業を終えて
展望
かけす
詩人と農夫
林間
初蝶
葡萄の国
単独行
木苺の原
日没時の蝶
音楽的な夜
黒つぐみ
郷愁
雪
人のいない牧歌
巻積雲
故地の花
言葉
林檎の里
夏の最後の薔薇
Pastoral scolastique
晩秋の庭で
反響
夕日の中の樹
詩術
『歳月の歌』(昭和三十三年)から 二四篇
蛇
遠い分身
雪の星月夜
山頂の心
岩雲雀
風景
台風季の或る日から
秋の林から
山荘の蝶
山荘をとざす
目木
女と葡萄園
峠
桃林にて(I)
桃林にて(II)
桃林にて(III)
渓谷(I)
渓谷(II)
渓谷(III)
木曾の歌(奈良井)
木曾の歌(鳥居峠)
木曾の歌(開田高原)
木曾の歌(寝覚)
我等の民話
その後の詩帖から 二一篇
久方の山
立春
眼前の蜜蜂に
花壇にて
二十五年
充実した秋
十一月
生けるがごとき君への歌
四月の詩
元旦の笛
春の前夜
眠られぬ夜に
春愁
受難の金曜日
関心
車窓
玉のような時間
転調
朝のひととき
雲の走る夜
夏への準備
後記
略年譜
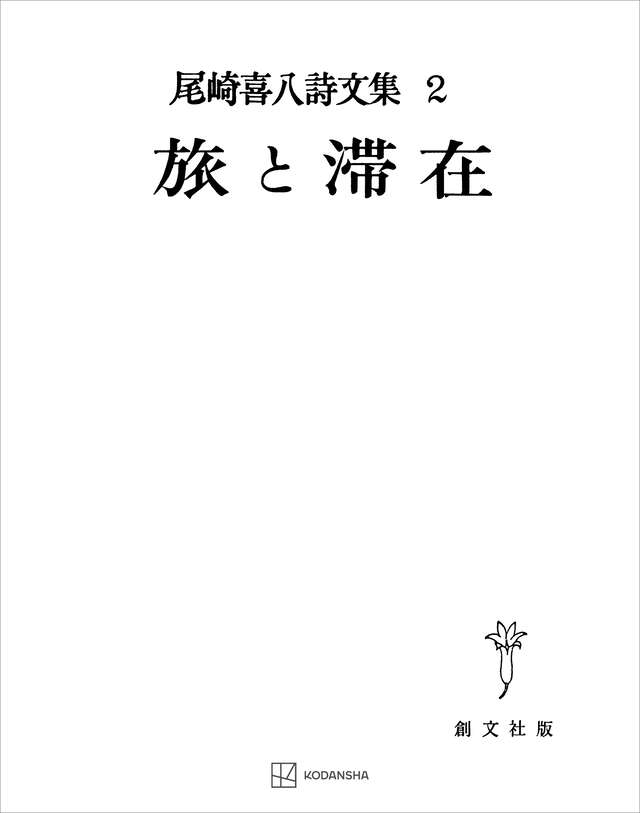
尾崎喜八詩文集2:旅と滞在
創文社オンデマンド叢書
詩人、随筆家、翻訳家、また、クラシック音楽への造詣も深い著者は、山や自然を描いた詩や散文の秀品を多く残した。
本書は、詩集である。
【目次より】
行人の歌(大正十四年 昭和十五年) 五九篇
曇り日の村 朝寒 夜をこめて 早春 バッハの夕空 十一月 希望 エネルギー 霊感挽歌 或る朝のおもい 慰め 熱狂 草に 夜の道 東京の秋 追憶 私の詩 夜 エレオノーレ 母性 日本の眼 暗い源泉から生れて 朝の書斎へ 私は愛する 今日という日は 今朝もまた 寄託 銃猟家に与う 中野秀人の首 霜どけ道 精神 この眼は何を 喪の春 夕陽哀歌 朽ちる我が家 郷愁 昔と今 旅のめざめ 道づれ 都会にて 秋 限界 思い出の歌 旅 シュナイダー シュプール 新年言志 早春の歌 樅の樹の歌 言葉 女の小夜楽 日の哀歌 野良の初冬 清福 訪問 五歳の言葉 カマラード 新戦場
旅と滞在(昭和八年 十三年) 三八篇
友 三国峠 一年後 神津牧場 前橋市遠望 猪茸 夕べの泉 若い白樺 アルペンフロラ 西北風 積雲の歌 夏野 秋 初冬に 覚めている貧 セガンティーニ 雲 下山 大いなる夏 八ガ岳横岳 輪鋒菊 星空の下を 朝の速記 山村にて 山麓の町 日川 甲斐の秋の夜 山中地溝帯で 金峯山の思い出 志賀高原 秩父の早春 飯綱高原 和田峠東餅屋風景 天上沢 信州追分 雪消の頃 高原の晩夏に寄せる歌
高原詩抄(昭和十七年) 二三篇
早春の山にて 春浅き かたくりの花 軍道 松本の春の朝 山小屋の朝 高原(その一 その二 その三 その四 その五) お花畠 槍沢の朝 帰来 牧場 野辺山ノ原 美ガ原熔岩台地 秋の流域 御所平 凍死 夏山思慕 山を描く木暮先生 噴水
此の糧(抄)(昭和十七年) 二〇篇
此の糧 若い下婢 連峯雲 大詔奉戴 少年航空兵 庭訓 峠路 登山服 特別攻撃隊 三粒の卵 窓前臨書 新緑の表参道 工場の娘等 父の名 若き応召使に つわものの母の夢の歌 つわものの父の歌 その手 歌わぬピッケル 少国民の秋
同胞と共にあり(抄)(昭和十八年) 二〇篇
同胞と共にあり 石見の国の日本の母 大阪 忙中閑 志を言う 隣組菜園 雪の峠路 アリューシャン 明星と花 軍艦那智 春の谷間 第二次特別攻撃隊 静かなる朝の歌 北門の春 勤労作業にて 消息 学徒出陣 工場の山男 弟橘媛 白鳥の陵にて
後記

尾崎喜八詩文集1:空と樹木
創文社オンデマンド叢書
詩人、随筆家、翻訳家、また、クラシック音楽への造詣も深い著者は、山や自然を描いた詩や散文の秀品を多く残した。
本書は、詩集である。
【目次より】
空と樹木(大正十一年) 四四篇
海へ
健康の朝
カルナヴァル・ロマン
カテージ・メイド
野薊の娘
スコットランドの娘
田舎娘
暁を呼ぶ声
テニスの試合
夜の樹々と星と私と
悦び
散歩
嵐の翌朝
冬空を讃う
雨後の住来
スイート・ピー
芝生
朝
ボン・ボック
田舎の夕暮
蝉
胸の松明
小景
窓から
雨
友だちが帰ったあと
雲と落日
四十雀
藪鶯
生活
新らしい季節
帰り道
冬の田舎
欅に寄す
或る宵
井戸端
雪
台所
東京へ
雪どけの日から
小さい墓地
収穫
幸いの日
雲雀
高層雲の下(大正十三年) 四二篇
新らしい風
高層雲の下
野の搾乳場
河口の船着
最後の雪に
野の小川
私の聖日曜日
音楽
夕ばえにむかって
明るい窓
ヴェルアーランを憶う
若い主婦
昆陽先生の墓にて
古いこしかた
草上の郵便
村の盂蘭盆
我が家の台所
裏道
日没の時
静かな夏
土用の入
水際
晩夏
秋風
女等
母
九月の樫
海
秋の朝
古典の空
樹木讃仰
朝狩にて
花崗岩
健康
もず
蹄鉄打ち
落葉
冬の木立
眠られぬ夜のために
日の暮
蛇窪に別れる
自我の讃美
曠野の火(昭和二年) 三六篇
小作人の墓銘
曳船の舵手
老教授
ひとり者の最後の春
靄
大根
冬の林
私の古い長靴
春を待つ間
久濶
天然の一日
麦
初夏の小屋
平戸島への消息
西瓜
老いたる樫
小鳥
積乱雲
秋の歌
朝の半時間
隼
かがやく稲田
夜あけの嵐
兜虫
甲州街道の牛
冬の蠅
朝の甲州街道
土と落葉と水溜り
冬
私のかわゆい白頭巾
夕暮の歌
菫
精神的寂静
クリスマス
青い鳥
故郷にて
後記

夕べの旋律
創文社オンデマンド叢書
詩人、随筆家、翻訳家、また、クラシック音楽への造詣も深い著者は、山や自然を描いた詩や散文の秀品を多く残した。
本書は、散文集である。
【目次より】
鎌倉住まい
春信
再生の歌
内と外(1)
内と外(2)
秋
早春
鎌倉随想
音楽
バッハへ傾く心
古い手箱と「別れの曲」
オーヴェルニュの歌
笛とレコード
モーツァルト
スカルラッティ
一枚のレコード
『ヨハネ受難曲』について
ブルーノ・ワルター
バイヤールの印象
「目ざめよと呼ばわる声す」
三詩人
『高村光太郎全詩稿』のために
「蝉を彫る」
星座早見
『道程』との出会い
「ぼろぼろな駝鳥」
千家元磨の人と作品
千家元磨の詩の解説
賢治を憶う
思い出の山
上高地行
山と音楽
思い出の山と人
夜明けの山の写真に添えて
ひとりの山
書評
串田孫一さんの『ゆめのえほん』
『東京回顧』
石川翠詩集
三人の永遠の音楽家
余録
ロマン・ロランの声
電話寸感
信州の酒に寄せて
自然の音
初めて『郷愁』を読んだころ
「井荻日記」について
私のヘルマン・ヘッセ(1)
私のヘルマン・ヘッセ(2)
白山小桜の歌
『ベートーヴェンの生涯』
「此の家の以前の子供」
デュアメルの訳書に添えて
一詩人のブールデル見学
後記

名もなき季節 富士見からの手紙
創文社オンデマンド叢書
詩人、随筆家、翻訳家、また、クラシック音楽への造詣も深い著者は、山や自然を描いた詩や散文の秀品を多く残した。
本書は、書簡集である。
書簡の宛先は、伊藤海彦、石黒栄子、串田孫一、石黒光三で、20の書簡を収録する。
【目次より】
伊藤海彦宛*昭23・9・28
伊藤海彦宛*昭23・10・21
伊藤海彦宛*昭24・1・26
伊藤海彦宛*昭24・1・31
伊藤海彦宛*昭24・3・30
伊藤海彦宛*昭24・4・8
石黒栄子宛*昭24・4・17
串田孫一宛*昭24・5・2
石黒光三・栄子宛*昭24・10・31
串田孫一宛*昭25・1・12
石黒光三・栄子宛*昭25・7・7
串田孫一宛*昭26・4・9
石黒栄子宛*昭26・5・1
串田孫一宛*昭26・5・17
串田孫一宛*昭26・6・21
串田孫一宛*昭26・6・30
石黒栄子宛*昭26・7・7
串田孫一宛*昭26・11・5
串田孫一宛*昭26・12・6
串田孫一宛*昭27・1・29
串田孫一宛*昭27・10・3
後書****伊藤海彦

田舎のモーツァルト 詩集
創文社オンデマンド叢書
詩人、随筆家、翻訳家、また、クラシック音楽への造詣も深い著者は、山や自然を描いた詩や散文の秀品を多く残した。
本書は、詩集である。
田舎のモーツァルト
中学の音楽室でピアノが鳴っている。
生徒たちは、男も女も
両手を膝に、目をすえて、
きらめくような、流れるような、
音の造形に聴き入っている
そとは秋晴れの安曇平、
青い常念と黄ばんだアカシア。
自然にも形成と傾聴のあるこの田舎で、
新任の若い女の先生が孜々として、
モーツァルトのみごとなロンドを弾いている。
【目次より】
冬の雅歌
不在
妻に
ハインリッヒ・シュッツ
秋
霧と風の高原で
岩を研ぐ
春の葡萄山
モーツァルトの午後
出合い
歳月
田舎のモーツァルト
ひとりの山
七月の地誌
回顧
車窓のフーガ
高処の春
あかがり
復活祭の高原
山中取材
野の仏
蝉
或る石に刻むとて
湖畔の朝
鴨
和田峠
馬籠峠
上越線にて
受胎告知
春興
桃咲く春
高地牧場
故園の歌
十年後
朝の門前で
草津白根
予感
飼育場風景
後記

私の衆讃歌
創文社オンデマンド叢書
詩人、随筆家、翻訳家、また、クラシック音楽への造詣も深い著者は、山や自然を描いた詩や散文の秀品を多く残した。
本書は、散文集である。
【目次より】
音楽
バッハをめぐって(一)
バッハをめぐって(二)
冬の或る日
『ベートーヴェンの生涯』
今と昔
ブクステフーデ
森の歌
合唱と私
自然
甲斐路の春
浅間山麓の一日
美ヶ原の秋
武蔵野の鳥
知多半島の一角
思い出の山の花たち
山にゆかりの先輩
道二題
図鑑について
先人と友人
デュアメルのかたみ
デュアメルの追悼
カロッサの教訓
若き日の友の姿
交友抄
わが師わが友
祝詞に代えて
清閑記
一詩人の告白
道にて
詩人の朝
近況
たしなみの美
わが愛誦の詩(一)
わが愛誦の詩(二)
ふるさとの一角
山小屋からの電話
その頃の孫
雑草
『思索する心』
新しい印章
たまたまの余暇
私の一冊の本
旅の宿
高村光太郎
大いなる損失
あの手のイメージ
ふたたびの春
高村さんとの旅
初めて見たアトリエ
晩秋の午後の夢想
片思いの頃
智恵子さんの思い出(一)
智恵子さんの思い出(二)
後記

その空の下で 尾崎喜八詩集
創文社オンデマンド叢書
詩人、随筆家、翻訳家、また、クラシック音楽への造詣も深い著者は、山や自然を描いた詩や散文の秀品を多く残した。
本書は、詩集である。
その空の下で (妻に代わりて)
安達太良山もここから先は足で登るか、
ガラガラ廻っている味気あじきないあのリフトで
吊り上げられて行くかするよりほかはない。
山麓をいろどる落葉松からまつの新緑、遠い郭公、
峰の高みに真白な残雪の帯、
そして頭の上は、見よ、この空だ。
おばさまが言ったという「智恵子のほんとの空」、
東京ならぬみちのくの空が、
「あどけない話」どころか真底女人の
思い入ったまじめさで、少し悲しく、
深く青々とひろがっている。
私はこの空を今は亡い人のその昔の郷愁と
同じ思いでしみじみと見上げる。
足もとには猩々袴か燕オモトか
つやつや光る強い緑の芽がぎっしり。
これもあのかたの故郷の山の草だと思えば、
踏むどころか、記念に一株掘るどころか、
気をつけて、丁寧に、
跨いで、 行く。
【目次より】
されど同じ安息日の夕暮れに
アイヒェンドルフ再読
よみがえる春の歌
音楽会で
シューマンと草取り
一つのイメージ
ほほえましいたより
復活祭
晩年のベルリオーズ
上高地にて
森林限界
詩人と笛 その一、その二
夏行
恢復期の朝
鎌倉初秋
明月谷
岩雲雀の歌
古い山の地図を前にして
雲表の十月
霧ガ峯の春
カエデの勉強
続けかしの歌
鈴
ヴィヴァルディ
『諸国の人々』
勉学篇
バッハの『復活祭オラトリオ』から
二つの現実
讃称
エリュアール
浄土平
その空の下で
春愁
命あって
黄道光
トンボの谷
詩「無常」の作者に
過去と現在
安らぎと広がりの中で
沈みゆく星に寄せて
後記