創文社オンデマンド叢書作品一覧
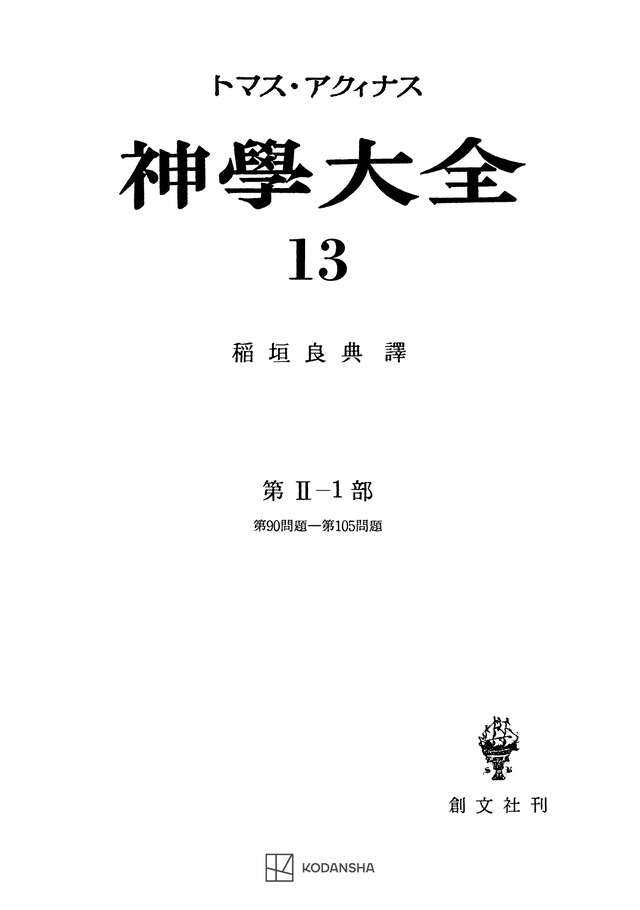
神学大全13 第II-1部 第90問題~第105問題
創文社オンデマンド叢書
13世紀、聖書解釈や神学者の注解を体系的に集大成した全45巻の中世キリスト教神学の金字塔。第II-1部第90問題~第105問題を収録。
主題は、法(旧法)。
【目次より】
凡例
第九十問題 法の本質について
第九十一問題 法の多様性について
第九十二問題 法の効果について
第九十三問題 永遠法について
第九十四問題 自然法について
第九十五問題 人定法それ自体について
第九十六問題 人定法の権能について
第九十七問題 法の改変について
第九十八問題 旧法について
第九十九問題 旧法の規定について
第百問題 旧法の倫理的規定について
第百一問題 祭儀的規定それ自身について
第百二問題 祭儀的規定の根拠について
第百三問題 祭儀的規定の存続について
第百四問題 司法的規定について
第百五問題 司法的規定の理由について
訳者注
あとがき

神学大全12 第II-1部 第71問題~第89問題
創文社オンデマンド叢書
13世紀、聖書解釈や神学者の注解を体系的に集大成した全45巻からなる中世キリスト教神学の金字塔。第II-I部第71問題~第89問題を収録。悪徳と罪が主題。
【目次より】
まえがき
第七十一問題 悪徳と罪について──それ自体において
第七十二問題 諸々の罪の区別について
第七十三問題 諸々の罪の相互比較について
第七十四問題 罪の基体について
第七十五問題 罪の原因について──一般的考察
第七十六問題 罪の原因について──特殊的考察
第七十七問題 感覚的欲求の側における罪の原因について
第七十八問題 罪の原因である悪意について
第七十九問題 罪の外的諸原因について──第一に神の側に関して
第八十問題 罪の原因について──悪魔の側に関して
第八十一問題 罪の原因についてー人間の側に関して
第八十二問題 原罪の本質について
第八十三問題 原罪の基体について
第八十四問題 ―つの罪が他の罪の原因である限りでの罪の原因について
第八十五問題 罪の結果について──第一に自然本性の善の損傷について
第八十六問題 罪の汚れについて
第一項 罪は霊魂のうちに何らかの汚れを生ぜしめるか
第二項 汚れは罪の行為の後も霊魂のうちに存続するか
第八十七問題 刑罰に値する罪責について
第八十八問題 小罪と大罪について
第八十九問題 小罪それ自体について
訳者注
解説 トマスの「罪」理解について
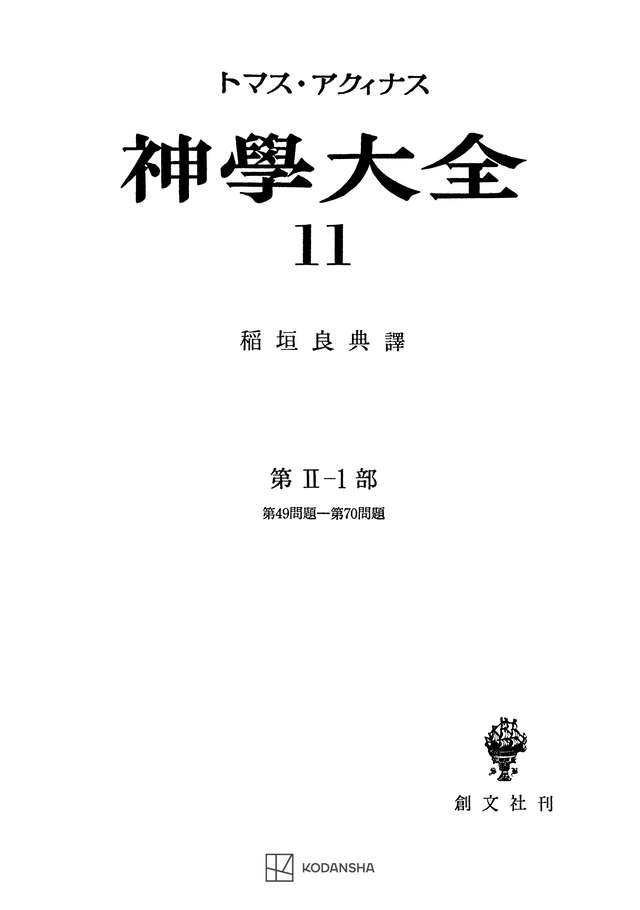
神学大全11 第II-1部 第49問題~第70問題
創文社オンデマンド叢書
13世紀になった、聖書解釈や神学者の注解を体系的に集大成した全45巻からなる中世キリスト教神学の金字塔。第II-1部 第49問題~第70問題を収録。
11 能力態 (第2-1部)49―70問
【目次より】
まえがき
第四十九問題 習慣一般について──その本質に関して
第五十問題 習慣の基体について
第五十一問題 習慣生成の原因について
第五十二問題 習慣の増強について
第五十三問題 習慣の消滅および弱減について
第五十四問題 習慣の区別について
第五十五問題 徳の本質について
第五十六問題 徳の基体について
第五十七問題 知的徳について
第五十八問題 倫理徳と知的徳との区別について
第五十九問題 倫理徳と情念との関係について
第六十問題 倫理徳相互の区別について
第六十一問題 枢要徳について
第六十二問題 対神徳について
第六十三問題 徳の原因について
第六十四問題 徳の中庸について
第六十五問題 諸々の徳の結合について
第六十六問題 諸々の徳の間の等しさについて
第六十七問題 現世の後における諸々の徳の存続について
第六十九問題 至福について
第七十問題 聖霊の結実について
訳者注

神学大全10 第II-1部 第22問題~第48問題
創文社オンデマンド叢書
聖書解釈や神学者の注解を体系的に集成した全45巻の中世キリスト教神学の金字塔。第IIー1部 第22問題~第48問題を収録。テーマは情念。
【目次より】
第二十二問題 情念の基体について
第二十三問題 情念相互の相違について
第二十四問題 題情念における善と悪について
第二十五問題 情念相互の序列について
第二十六問題 もろもろの情念について個別的に──そして、まずは愛について
第二十七問題 愛の因について
第二十八問題 愛の果について
第二十九問題 憎しみについて
第三十問題 欲情について
第三十一問題 快それ自体について
第三十二問題 快の因について
第三十三問題 快の果について
第三十四問題 快の善さと悪さについて
第三十五問題 痛苦、あるいは悲しみ、それ自身について
第三十六問題 悲しみ、または痛苦の因について
第三十七問題 痛苦または悲しみの果について
第三十八問題 悲しみ、または痛苦の治療手段について
第三十九問題 悲しみ、あるいは痛苦、の善さと悪さについて
第四十問題 怒情の諸情念について。そして、まずは希望と絶望について
第四十一問題 恐れについて──そのもの自体に即して
第四十二問題 恐れの対象について
第四十三問題 恐れの因について
第四十四問題 恐れの果について
第四十五問題 大胆について
第四十六問題 怒りについて──それ自体に即して
第四十七問題 怒りの作動的な因について、および、怒りの治療手段について
第四十八問題 怒りの果について
あとがき
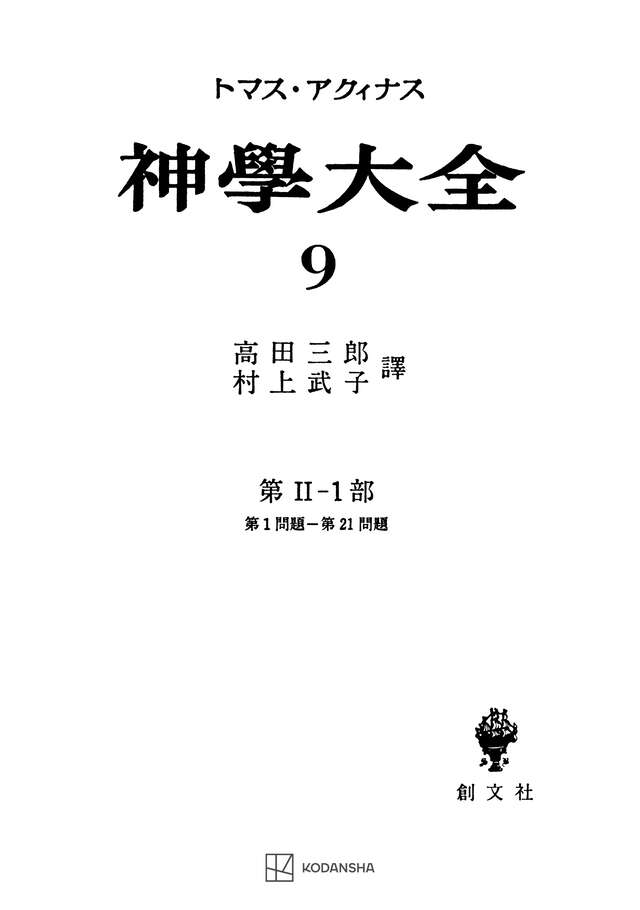
神学大全9 第II-1部 第1問題~第21問題
創文社オンデマンド叢書
13世紀、聖書解釈や神学者の注解を体系的に集成した45巻の中世キリスト教神学の金字塔。
人間の目的と行為 (第2-1部)1―21問
【目次より】
まえがき
序言
第一問題 人間の究極目的について
第二問題 人間の幸福の所在について
第三問題 幸福とは何なのであるか
第四問題 幸福のために要求されるものについて
第五問題 幸幅への到達について
第六問題 意志的ならびに非意志的について
第七問題 人間的行為の周辺について
第八問題 意志、その関わるところのものの何たるかについて
第九問題 意志を動かすものについて
第十問題 意志の動かされる仕方について
第十一問題 享受という意志の活動について
第十二問題 志向について
第十三問題 目的へのてだてについての選択という意志の働きについて
第十四問題 選択に先だつ思量について
第十五問題 同意という、目的へのてだてに関連しての意志の働きについて
第十六問題 用という、目的へのてだてに関連しての意志の働きについて
第十七問題 意志によって命ぜられるもろもろの働きについて
第十八問題 人間的行為の善性と悪性全般について
第十九問題 意志の内的行為における善性と悪性について
第二十問題 人間の外的行為の善性と悪性について
第二十一問題 人間行為に、それの善性または悪性のゆえをもって随いきたる各般のことがらについて
訳者注

神学大全8 第I部 第103問題~第119問題
創文社オンデマンド叢書
聖書解釈や神学者の注解を体系的に集大成した全45巻の中世キリスト教神学の金字塔。
神の世界統宰(第1部) 第103問題―第119問題。
【目次より】
凡例
第百三問題 諸事物の統宰全般について
第百四問題 神の統宰の果のそれぞれについて
第百五問題 神による被造物における変化について
第百六問題 如何なる仕方で―つの被造物が他の被造物を動かすか
第百七問題 天使における語るというはたらきについて
第百八問題 ヒエラルキアと階層とによる天使たちの序列について
第百九問題 悪しき天使たちの間における序列について
第百十問題 天使たちの物体的被造物に対する統轄について
第百十一問題 天使の人間に対する働きについて
第百十二問題 天使の派遣について
第百十三問題 善天使による守護について
第百十四問題 悪霊からの攻略について
第百十五問題 物体的被造物の働きについて
第百十六問題 宿命について
第百十七問題 人間の能動的な働きに属することがらについて
第百十八問題 魂に関するかぎりにおける、人間に基づく人間の産出について
第百十九問題 身体に関するかぎりにおける人間の増殖について
訳者注
あとがき

神学大全7 第I部 第90問題~第102問題
創文社オンデマンド叢書
7 人間の創造と最初の状態 (第1部)90―102問
【目次より】
第九十問題 魂に関するかぎりにおける、人間の最初の産出について
第九十一問題 最初の人間の身体の産出について
第九十二問題 女人の産出について
第九十三問題 人間の産出の目的乃至は終極について
第九十四問題 知性に関するかぎりにおける最初の人間の状態とか境位について
第九十五問題 最初の人間の意志の領域に属する諸般のことがら──即ちまず恩寵と義について
第九十六問題 無垢の状態における人間にふさわしい支配について
第九十七問題 個体の保存に関するかぎりにおける、最初の人間の状態に属することがらについて
第九十八問題 種の保存に関する諸般のことがらについて
第九十九問題 生まるべき子供の、身体に関するかぎりにおける境位について
第百問題 生まるべき子供の、義に関するかぎりにおける境位について
第百一問題 生まるべき子供の、知に関するかぎりにおける境位について
第百二問題 楽園という、かかる人間の場所について
訳者注
あとがき
索引
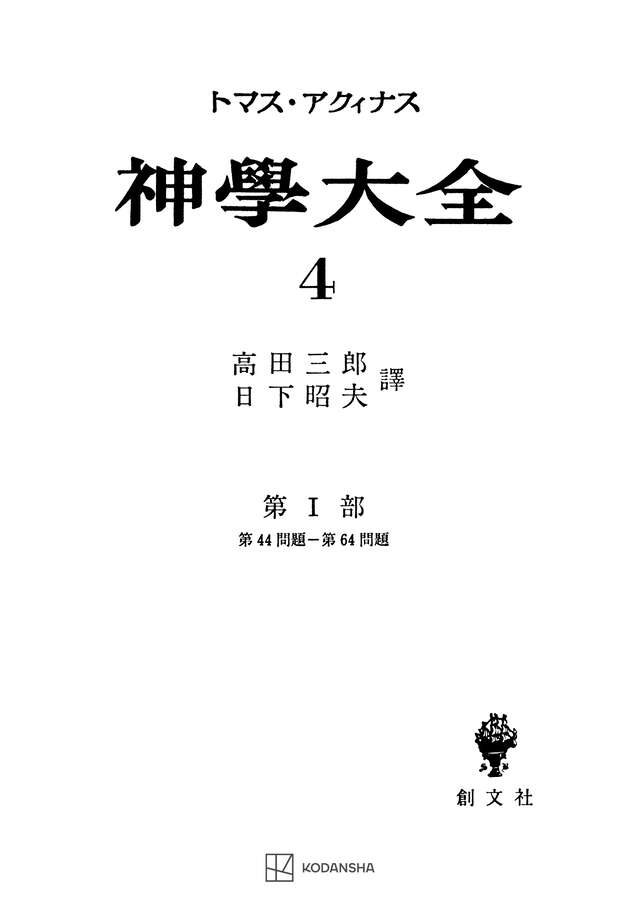
神学大全4 第I部 第44問題~第64問題
創文社オンデマンド叢書
4 創造、天使 (第1部)44―64問
【目次より】
凡例
第四十四問題 諸々の被造物の神からの発出について──万有の第一原因について
第四十五問題 諸事物の第一根源による流出の仕方について
第四十六問題 被造的諸事物の持続の始めについて
第四十七問題 諸々の事物の区別一般について
第四十八問題 諸々の事物の区別についての各論──悪について
第四十九問題 悪の因について
第五十問題 天使の実体そのものについて
第五十一問題 天使の物体に対する関係について
第五十二問題 天使の場所に対する関聯について
第五十三問題 天使の場所的運動について
第五十四問題 天使における認識について
第五十五問題 天使の認識の媒介について
第五十六問題 非質料的な諸事物に関しての天使の認識について
第五十七問題 質料的な事物についての天使の認識について
第五十八問題 天使の認識の様態について
第五十九問題 天使の意志について
第六十問題 天使における愛について
第六十一問題 天使の自然的存在への産出について
第六十二問題 天使たちの、恩寵的ならびに栄光的な存在においての完成について
第六十三問題 天使たちにおける罪科たるかぎりの悪というものについて
第六十四問題 悪霊たちの罰について
付録 第四十七問題 補遺
第三項 被造物にあっては、諸々の能動者のあいだに秩序が存在するか

神学大全3 第I部 第27問題~第43問題
創文社オンデマンド叢書
聖書解釈や神学者の注解を体系的に集大成した全45巻からなる中世キリスト教神学の金字塔。
3 三位一体 (第1部)27-43問
【目次より】
第二十七問題 神のベルソナの発出について
第二十八問題 神における諸々の関係について
第二十九問題 神のペルソナについて
第三十問題 神におけるペルソナの複数性について
第三十一問題 神における一または複数ということに関聯することがらについて
第三十二問題 神のペルソナの認識について
第三十三問題 御父のぺルソナについて
第三十四問題 御子のペルソナについて
第三十五問題 似像について
第三十六問題 聖霊のペルソナについて
第三十七問題 御愛という聖霊の名称について
第三十八問題 賜物という聖霊の名称について
第三十九問題 本質への比較におけるペルソナについて
第四十問題 関係乃至は固有性への比較において考察されたペルソナについて
第四十一問題 識標的はたらきへの比較において考察されたペルソナについて
第四十二問題 神のペルソナ相互の間における均等性と類似性とについて
第四十三問題 神のペルソナの派遣について
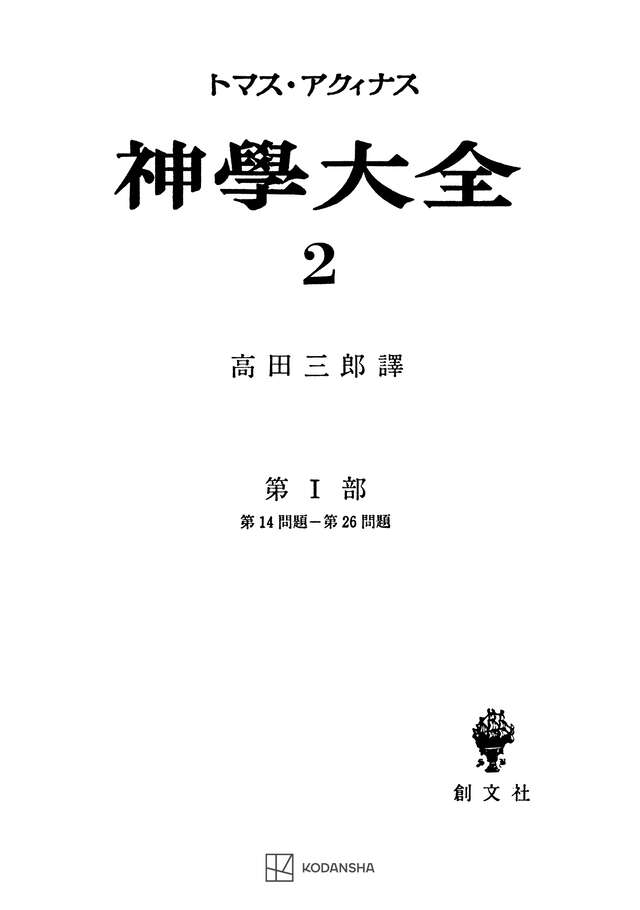
神学大全2 第I部 第14問題~第26問題
創文社オンデマンド叢書
聖書解釈や神学者の注解を体系的に集大成した全45巻からなる中世キリスト教神学の金字塔。
2 神の生、認識と意志 (第1部)14―26問
【目次より】
第十四問題 神の知について
第十五問題 イデアについて
第十六問題 真理について
第十七問題 虚偽について
第十八問題 神の生命について
第十九問題 神の意志について
第二十問題 神の愛について
第二十一問題 神の正義と憐憫について
第二十二問題 神の摂理について
第二十三問題 予定について
第二十四問題 「生命の書」について
第二十五問題 神の能力について
第二十六問題 神の至福について

神学大全1 第I部 第1問題~第13問題
創文社オンデマンド叢書
聖書解釈や神学者の注解を体系的に集大成した全45巻からなるキリスト教神学の金字塔
1 神の存在と本質 (第1部)1-13問
『神学大全』邦訳序文
凡例
目次
序言
第一問題 聖教について──それはどのような性質のものであるか、またその及ぶところ如何
第一項 哲学的諸学問のほかになお別個の教えの行われる必要があるか ~ 第十項 聖書は一つの字句のもとに幾つかの意味を含むものであるか
第二問題 神について──神は存在するか
第一項 神が存在するということは自明的なことがらであるか ~ 第三項 神は存在するか
第三問題 神の単純性について
第一項 神は物体であるか ~ 第八項 神は自己以外のものと複合を構成するか
第四問題 神の完全性について
第一項 神は完全なものであるか ~ 第三項 被造物は神に似たものであることができるか
第五問題 善一般について
第一項 善はことがらの上で有と異なるか ~ 第六項 善を分つのに、貴いもの・有用なもの・快適なものという区分を以てするのは適切であるか
第六問題 神の善たることについて
第一項 善であるということは神に適合するか ~ 第四項 ものが善であるのはすべて神の善たることによってであるか
第七問題 神の無限性について
第一項 神は無限であるか ~ 第四項 多ということにおいて無限なものが実際に存在しうるか
第八問題 事物における神の実在について
第一項 神は万物において存在しているか ~ 第四項 遍在ということは神に固有なことがらであるか
第九問題 神の不変性について
第一項 神はあらゆる意味において不変なものであるか 第二項 不変であるということは神に固有のことがらであるか
第十問題 神の永遠性について
第一項 永遠とは、『果しなき生命の、同時に全体的な、完全な所有』である、という定義は適切か ~ 第六項 単に一つの悠久があるのみであるか
第十一問題 神の一体性について
第一項 一は有の上に何ものかを附け加えるか ~ 第四項 神は最高度において一なるものであるか
第十二問題 神は我々によってどのような仕方で認識されるか
第一項 被造的な知性は神をその本質において見ることができるか ~ 第十三項 自然的本性的理性によって得られる以上の高次な神の認識が、恩寵によって得られうるか
第十三問題 神の名について
第一項 神に適合する何らかの名称があるか ~ 第十二項 肯定命題が神について形成されることができるか

宗教哲学の新しい可能性
創文社オンデマンド叢書
キリスト教と無の思想はどのような関係にあるのか。使徒パウロはどうして迫害をやめて回心したのか。内在的超越とはなにか?
【目次より】
序
宗教哲学の新しい可能性
キリスト教と無の思想
使徒パウロの回心とそれをめぐる諸問題
使徒パウロの思想と信仰
宗教における「内在的超越」ということについて
解釈学的原理としての「中」について 「非神話化」論と関連して

古ゲルマンの社会組織(歴史学叢書)
創文社オンデマンド叢書
古ゲルマンの社会組織や農地制度をめぐって、古くから激しい論争が繰り返されている。本書は1950年に発表され、19世紀末に台頭した領主制説を徹底的に批判し、修正された一般自由人学説が優勢となるきっかけをなした古典的な論文である。ウェーバー一流の鋭利な理論的分析は、今日なお高い価値をもつ。
【目次より】
凡例
目次
一 序論
領主制仮説/クナップ学派の仕事/農業史研究における欠陥/領主制仮説の古代・中世への拡大/マイツェンの見解/マイツェンヘの反論/ヒルデブラントの発展段階論/法制史の通説とヘックの見解/ヴィッティッヒによるヘック理論の利用/指導的ゲルマニストの見解/問題の所在と地域的限定/「文化段階」概念の理念型的性格
二 本論 ヴィッティッヒの二つの仮説
1 第一仮説の吟味
スエービー族とライン沿岸の諸部族/ゲルマン犁について/スエービー人の慢性的戦時状態/遊牧段階説について/ヴィッティッヒ批判(1)、遊牧生活説/ヴィッティッヒ批判(2)、家畜所有者としての magistratus ac principes の領主化/ガリアの状態とゲルマン人のそれとの比較/スエービー人における居住地の毎年の変更/グルントヘルシャフトの不存在/結論
2 第二仮説の吟味
プレーブスとその生活様式/男性の労働回避と婦人労働/男性労働の強化とその非戦士化/大量的奴隷化の現象はない/騎兵軍の問題/被解放自由人について/「ゲルマーニア」第二六章について/耕地の平等分配は自治的規制の産物である/平等思想は必ずしも厳格な「ゲヴァン分配」の形をとらない/「ゲヴァン原理」への移行/グルントヘルシャフト発展の担い手としての貴族/フランク部族における「人民貴族」の消滅/最古の階層分化は政治的事情に由来する/カーロリンガのノービレース/結論
訳註
訳者あとがき

経済と社会:都市の類型学
創文社オンデマンド叢書
第2部第9章8節。中世における都市の発展が近代資本主義発生の決定的因子である、とするウェーバー理論の基礎づけ。
【目次】
凡例
第九章 支配の社会学
第八節 非正当的支配(都市の類型学)
第一項 都市の概念と種類
一 都市の経済的本質、市場定住 二 「消費者都市」と「生産者都市」の類型 三 農業との関係 四 経済段階としての「都市経済」 五 政治的・行政的都市概念 六 要塞と衛戌地 七 要塞と市揚との統一体としての都市 八 西洋における都市「ゲマインデ」の団体的性格と「市民」の身分的資格、東洋におけるこの両概念の欠如
第二項 西洋の都市
一 土地法と人の法的地位 二 兄弟盟約によるポリスの形成 三 東洋においてはタブーや氏族制に伴うその他の呪術的制約によって阻止されたこと 四 兄弟盟約の前提としての・呪術的制約の破砕 五 古典古代および中世の諸都市に対するジッペの意義 六 西洋における誓約共同体的兄弟盟約、その法的・政治的結果 七 都市アイヌングの社会学的意味
第三項 中世および古典古代における門閥都市
一 門閥支配の本質 二 ヴェネツィアにおける-貴族の独占的・閉鎖的支配としての-門閥支配の形成 三 その他のイタリアのコムーネにおける・独占的結集を伴わない・ポデスタ制を利用し の門閥支配の形成 四 イギリス諸都市における・国王行政によって制約された名望家的寡頭制 五 北ヨーロッパにおける・参事会員資格をもった諸門閥ないしはツンフトの支配 六 古典古代における氏族カリスマ的王制 など
第四項 平民都市
一 都市市民の宜誓兄弟盟約による・門閥支配の打破 二 非正当的政治団体としてのポポロの革命的性格 三 中世イタリア都市における諸身分間の勢力の分配 四 古典古代におけるデーモスとプレーブスとの相似的発展、ローマの護民官職とスパルタのエフォロス 五 中世と対比しての古典古代の「民主制」の構造 六 古典古代および中世における都市僭主制 など
第五項 古典古代と中世の民主制
一 南北ヨーロッパの中世都市の類型相互間の関係、およびその古典古代の都市類型に対する関係 二 古典古代および中世における階級対立 三 古典古代および中世における都市制度、政治的組織の基礎としての地区共同体と職業団体 四 初期民主制の典型的な担い手、古典古代の都市における農民と中世都市における工業的市民層、ギリシアとローマとのその後の発展の相違 五 古典古代と中泄との都市民主制の経済政策、特殊古典古代的な都市における原理的に軍事的な関心方向 六 典型的な中世的・工業的内陸都市における原理的に経済的な関心方向 七 中世都市との対比における古典古代的ポリスの身分構成 など

経済と社会:支配の社会学2
創文社オンデマンド叢書
第2部第9章5~7節。政治と人間の問題をライトモチーフとして支配の構造を分析し、支配の正当性にもおよぶ。
【目次より】
第九章 支配の社会学
第五節 封建制、身分制国家および家産制
一 レーエンの本質と封建的諸関係の種類 二 レーエンとプッリュンデ 三 レーエン制の軍事的起源と正当性根 四 封建的権力分配とそのステロ化 五 レーエン団体から官僚制に至る過渡的諸形態、「身分制国家」、家産官僚制 六 経済との関係、家産制の発展に対する商業の意義 七 経済に対する固定化的影響 八 家産制の独占経済、「重商主義」 九 封建的支配の下における財産の形成と分配 一〇 家産制的独占主義の経済的結果 一一 支配の構造、「心情」と生活態度
第六節 カリスマ的支配とその変形
第一項 カリスマの本質と作用
一 カリスマ的権威の社会学的本質 二 カリスマ的権威の存立の基礎とその存立の不安定性 三 カリスマの革命的性格 四 カリスマの妥当領域 五 カリスマ的構造形式の社会的特質 六 カリスマ的共同体の「共産主義的」財貨給与
第二項 カリスマ的権威の成立と変形
一 カリスマの日常化 二 指導者選抜(後継者指定)の問題 三 カリスマ的歓呼賛同 四 民主制的選挙制度への移行 五 代議制におけるカリスマ的諸要素 六 カリスマ的・名望家的および官僚制的政党指溝 七 カリスマ的構造と共同社会生活の永続的組織 八 カリスマの「没主観化」、家カリスマと氏族カリスマ、「氏族国家」、長子相続制 九 官職カリスマ 一〇 カリスマ的王制 一一 没主観化されたカリスマは獲得可能であること、カリスマ的教育 一二 カリスマ獲得の金権制化 一三 現存秩序のカリスマ的正当化
第三項 支配形態の規律化と没主観化
一 規律の意義 二 軍事規律からの起源 三 経済的大経営の規律 四 規律とカリスマ
第七節 政治的支配と教権制的支配
一 政治的支配形態に対する祭司層と宗教的カリスマとの態度 二 皇帝教皇主義と教権制的支配、「教会」の概念 三 教権制的な教育と生活規律、「禁欲」に対する態度 四 修道生活の宗教的=カリスマ的事業と合理的事業 五 修道生活と皇帝教皇主義的支配およぴ教権制的官職カリスマとの関係 六 政治的カリスマと呪術的カリスマ、政治的権力と教権制的権力との関係 七 教権制的支配と宗教心との社会学的被制約性 八 経済的発展に対する教権制の意義、経済行為のステロ化・資本主義の阻止、西洋文化の独自性に対して与えた影響 九 資本主義および市民的民主制の時代における教権制の地位 一〇 西洋における信仰の分裂とそれが経済に及ぼした影響、ルターの態度、カルヴィニズムの倫理と教会 一一 ユダヤ教における教権制と経済意識 一二 ゼクテ・教会および民主制

経済と社会:支配の社会学1
創文社オンデマンド叢書
第2部第9章1~4節。政治と人間の問題をライトモチーフとして支配の構造を分析し、支配の正当性にもおよぶ。
【目次より】
凡例
目次
〔第二部経済と社会的・秩序および力〕
第九章 支配の社会学
第一節 支配の諸構造形態と諸機能様式
第一項 力と支配、過渡的諸形態
第二項 支配と行政、民主制的行政の本質と限界
第三項 「組織」による支配、支配の妥当根拠
第二節 正当的支配の三つの純粋型
支配の正当性、正当性の根拠
一 合法的支配
二 伝統的支配
三 カリスマ的支配
第三節 官僚制的支配の本質・その諸前提および展開
一 近代的官僚制の特殊的機能様式
二 官僚の地位
三 官僚制化の諸前提と諸随伴現象
1 貨幣経済的・財政的諸前提
2 行政事務の量的発達
3 行政事務の質的変化
4 官僚制的組織の技術的優秀性
5 行政手段の集中
6 社会的差別の水準化
四 官僚制的装謹の永続的性格
五 官僚制化の経済的・社会的結束
六 官僚制の勢力
七 合理的・官僚制的支配構造の発展段階
八 教養と教育との「合理化」
第四節 家父長制的支配と家産制的支配
一 家父長制的支配の本質と成立
二 名望家支配と純粋家父長制
三 家産制的支配
四 家産国家的支配構造
五 家産制的支配者の権力的地位、家産制的軍隊と家産制外的軍隊、伝統的・正当的な支配者権力にもとづく家産制的支配者の政治的支配権
六 家産制的需要充足。ライトゥルギーと連帯責任、強制団体
七 家産制的官職、家産制的官吏と官僚制的官吏との相違
八 家産制的官吏の給養、実物給与的プッリュンデと役得プッリュンデ
九 家産制的行政の分権化とステロ化、官職の占有と独占の諸結果、特権制国家
一〇 家産制的支配の崩壊に対するその統一性の擁護
一一 家産制的行政の機能の実例
1 古代エジプト
2 中国
一二 家産制的支配の分権化、ザトラピーと分国
一三 家産制的ヘルと地方的荘園制
一四 ジェントリー出身の治安判事によるイギリスにおける名望家行政、「ジェントルマン」の型の形成
一五 ツァーリズム的家産制
一六 家産制と身分的名誉

経済と社会:宗教社会学
創文社オンデマンド叢書
社会学の泰斗による著作第2部第5章。支配の社会学と並び宗教意識の問題は一貫して近代の意味を問うウェーバー社会学の要石である。
【目次より】
凡例
第五章 宗教社会学(宗教的共同体関係の諸類型)
第一節 諸宗教の成立
一 宗教的ないし呪術的に動機づけられた共同体行為の根源的此岸性 二 精霊信仰 三 「超感性的」な力の成立 四 自然主義と象徴主義 五 神々の世界と機能神 六 祖先崇拝と家 祭司制 七 政治的な集団神と地方神 八 一神教と日常的宗教性 九 普遍主義と一神教 一〇 神強制、呪術、神礼
第二節 呪術師 祭司
第三節 神概念。宗教的倫理。タブー
一 倫理的な神々。立法の神々 二 超神的、非人格的な力。神の創造としての秩序 三 タブー規範の社会学的意義。トーテミズム 四 タブー化、共同体関係、および類型化 五 呪術的倫理 宗教的倫理。罪意識、救済思想
第四節 「預言者」
一 「預言者」 祭司および呪術師に対するものとして 二 預言者と立法者 三 預言者と教説家 四 密儀師と預言者 五 倫理的預言と模範的預言 六 預言者的啓示の性格
第五節 教団
一 預言者、遵奉者、および教団 二 教団的宗教性 三 預言と祭司経営
第六節 聖なる知。説教。司牧
第七節 身分、階級と宗教
一 農民階級の宗教性 二 初期キリスト教の都市占住性 三 信仰戦士としての騎士 四 官僚制と宗教 五 「市民的」宗教性の多様性 六 経済的合理主義と宗教的─倫理的合理主義 七 小市民階級の非類型的な宗教的態度。職人の宗教性 など
第八節 神義論の問題
一 一神教的な神観念と世界の不完全性 二 神義論の純粋な諸類型 メシア的終末論 三 彼岸信仰、摂理信仰、応報信仰、予定信仰 四 世界の不完全性の問題に関するさまざまな解決の試み
第九節 救済と再生
第十節 救済方法と、生活態度へのそれの影響
一 呪術的宗教性と儀礼主義。儀礼主義的な帰依宗教性の諸帰結 二 日常倫理の宗教的体系化 三 忘我、狂躁、病的快感、および合理的宗教的な救済方法論 四 救済方法論の体系化と合理化、および生活態度 五 宗教的錬達者 六 現世拒否的禁欲と現世内的禁欲 七 現世逃避的、神秘主義的観照 など
第十一節 宗教的倫理と「現世」
一 宗教的心情倫理の現世に対する緊張関係 二 宗教的倫理の基盤としての隣人 三 利息取得に対する宗教的排斥 四 生の宗教的 五 宗教的な愛の無世界論と政治的な強圧行為 六 国家に対するキリスト教の態度の変遷 七 「有機的」な職業倫理 など
第十二節 文化宗教と「現世」
一 ユダヤ教の現世志向性 二 カトリック教徒、ユダヤ教徒、清教徒の営

経済と社会:法社会学
創文社オンデマンド叢書
第2部第1章・第7章。新しい法規範の成立、カリスマ支配と法発見など、合理化の問題が法を中心に論じられる。
【目次より】
凡例
〔第二部経済と社会的・諸秩序および諸力〕
第一章 経済と社会的諸秩序
第一節 法秩序と経済秩序
第二節 法秩序、習律および習俗
第三節 経済に対する法強制の意義と限界
第七章 法社会学
第一節 事項的な法領域の分化
第二節 主観的権利の設定の諸形式
第三節 客観的法の形態性格
第四節 法思考の諸類型と法名望家
第五節 法の形式的合理化と実質的合理化、神政政治的な法と世俗的な法
第六節 官権法と家産店主的法定立、法典編纂
第七節 革命によって作られた法の形式的な諸性質、自然法とその諸類型
第八節 近代法の形式的諸性質
訳者あとがき

経済と社会:支配の諸類型
創文社オンデマンド叢書
社会学の泰斗による著作。第1部第3~4章。支配の構造の社会学は、窮極において近代合理主義の解明をめざすウェーバー社会学の核心の一つである。
凡例
目次
〔第一部社会学的範疇論〕
第三章 支配の諸類型
第一節 正当性の妥当
一 支配の定義・条件および種類、正当性
二 正当的支配の三つの純粋型、合理的・伝統的・カリスマ的支配
第二節 官僚制的行政幹部を伴う合法的支配
三 合法的支配、官僚制的行政幹部による純粋型
四 〔続き〕
五 官僚制的=単一支配制的行政
第三節 伝統的支配
六 伝統的支配
七 〔続き〕
七a 長老制、家父長制、家産制
八 〔続き〕
九 身分制的=家産制的支配
九a 伝統的支配と経済
第四節 カリスマ的支配
一〇 カリスマ的支配、その特徴とその共同社会関係
第五節 カリスマの日常化
一一 カリスマの日常化とその影響
一二 〔続き〕
一二a 〔続き〕
第六節 封建制
一二b 封建制、レーエン封建制
一二c プフリュンデ封建制およびその他の封建制
一三 さまざまな支配類型の混合
第七節 カリスマの没支配的な解釈がえ
一四 カリスマの没支配的な解釈がえ
第八節 合議制と権力分割
一五 合議制と権力分割
一六 特殊化された権力分割
一七 政治的権力分割の経済に対する関係
第九節 政党
一八 政党の概念と本質
第一〇節 没支配的な団体行政と代議員行政
一九 没支配的な団体行政と代議員行政
二〇 名望家行政
第一一節 代表制
二一 代表制の本質と諸形式
二二 利益代表者による代表制
第四章 身分と階級
第一節 概念
一 概念
二 営利階級の意義
三 身分状況および身分の概念
付録
戦士身分
戦士身分
訳者あとがき

経済学と私
創文社オンデマンド叢書
時々の経済問題を論じた文章から、海外での研究生活と内外の著名な経済学者たちとの交流、さらに古典を踏まえた現代経済学への批評と熱い期待など、理論経済学の第一線で活躍してきた著者が贈る初のエッセイ集。
【目次より】
目次
記念講演五題
理論経済学の旅
現代経済学の潮流
小泉信三博士と理論経済学
マルクス没後百年
アダム・スミスと現代
機縁
小泉信三先生と私
高橋誠一郎先生の思い出
安井琢磨先生との出会い
サミュエルソン教授とのふれ合い
サミュエルソン教授との五日間
ジョーン・ロビンソン女史と私
レイヨンヒューブッド教授会見記
遊学雑記
ハーバードの経済学者たち
ケンブリッジ寸描
留学雑記
滞濠四ヵ月
オセアニアの旅
祝辞と追悼文
サミュエルソン経済学の功績
ヒックス、アロー両教授の貢献
ノーベル賞受賞のドブルー教授
ノーベル経済学賞のロバート・ソロー教授
追悼 サー・ジョン・ヒックス
カルドア教授を偲ぶ
やさしい経済学
社会的厚生関数論争
政治的景気循環
雇用理論の新展開
ロビンソン(二十世紀の巨人たち)
『一般理論』への道
フランク・p・ラムゼー
レオン・ワルラス生誕一五〇年
レオンチェフ教授の経済学
新著余瀝
経済学の混迷?
現代経済学の諸潮流 主流派批判の虚実
MISCELLANEA ECONOMICA
経済学と古典
経済学者の殺人
The Mystery of John Maynard Keynes
ケインズの伝記
ケインズ・ペーパーズ
性の深層意識 ローレンス『恋する女たち』
偶然と必然
マーフィーの法則
反ポパー主義の陥穽
歴史はくり返す
自然保護ということ
あとがき
初出一覧