創文社オンデマンド叢書作品一覧

浅野順一著作集4:詩篇研究
創文社オンデマンド叢書
牧師にして神学者の著者・浅野順一「著作集」11巻の第4巻「詩篇研究」。
【目次より】
《詩篇選釈》
まえがき(上巻)
まえがき(下巻)
旧約詩人の歌える神と自然 序説に代えて
義人の道と悪人の道 第一篇
メシアを待つ 第二篇
朝の祈り 第三篇
夕の祈り 第四篇
朝ごとに 第五篇
わが骨おののく 第六篇
人の子の栄光 第八篇
滅びざる望み 第九篇
鳥の如く 第一一篇
いつまで 第一三篇
愚かなる無神論者 第一四篇
福音的人格 第一五篇
神こそわが所領 第一六篇
創造の神と贖罪の神 第一九篇
戦勝の祈願 第二〇篇
「されど」 第二二篇
神こそわが牧者 第二三篇
栄光の王 第二四篇
一つの事 第二七篇
神鳴の歌 第二九篇
歓びの朝 第三〇篇
神の手にある時 第三一篇
愆赦され罪おおわれし者 第三二篇
神の国、神の民 第三三篇
汝の光によりて光を 第三六篇
御面の前にて 第四一篇
神への渇望 第四二篇及び第四三篇
神我らと偕にあり 第四六篇
くだける魂 第五一篇
神と肉体 第五六篇
一つの旗 第六〇篇
沈黙の信頼 第六二篇
心の磐なる神 第七三篇
神のみ審士 第七五篇
順礼の歌 第八四篇
己が日を数うる知恵 第九〇篇
感謝の歌 第一〇〇篇
王道の歌 第一〇一篇
自然と栄光 第一〇四篇
欠乏の恵み 第一〇六篇
ただ栄光のために 第一一五篇
われ山に向かいて目をあぐ 第一二一篇
涙をもって蒔く 第一二六篇
建築者なる神 第一二七篇
聖なる家庭 第一二八篇
あした待つ衛士 第一三〇篇
嬰児の如くに 第一三一篇
友情の祝福 第一三三篇
夜祭 第一三四篇
感謝の歌 第一三六篇
わが口の門守 第一四一篇
苦難と悔罪 第一四三篇
解説 木田献一

浅野順一著作集3:予言者研究II
創文社オンデマンド叢書
牧師にして、神学者の著者・浅野順一「著作集」全11巻の第3巻「予言者研究2」。
【目次より】
《予言書講解》
ヨナ書講解
一 第一章講解
二 第二章講解
三 第三章講解
四 第四章講解
イザヤ書講解
一 イザヤ書の構造
二 イザヤの人物
三 イザヤの召命
四 シリア・エフライム戦争とイザヤ
五 インマヌエル
六 アッシリヤの動静とイスラエル
七 イザヤの予言
八 セナケリブのパレスチナ侵入
九 エルサレムの包囲
アモス書講解
一 第一章講解
二 第二章講解
三 第三章講解 審判の必然
四 第四章講解
五 第五章講解
六 第六章講解
七 第七章講解 予言者と幻
八 第八章講解
九 第九章講解
《静穏なる信頼》
一つの予兆
静穏なる信頼
死とその克服
悲哀を担う者
神の思いと人の思い
神と世界 第二イザヤの世界史観
後記
《小説教・時論(一九二九年~一九四五年)》
神に頼りて歩む
エサウとヤコブ
石にて撃たるる者
信仰による新しき建設
書評 河合栄治郎著『時局と自由主義』
思うがままに
書評 天野貞祐著『道理の感覚』
繋がれざる神の言
造られたる人間
全体主義国家と信教の自由
中国をどうするか
学生と精神生活
机上(一)
牧会日誌
机上(二)
時代と基督教 世界史の転換とキリスト
信仰生活に於ける妥協と適応
病床雑感
狭き門 求道する友の為に
創造と模倣
義人は信仰によって活くべし ハバクク書二ノ一-四
新年の祈願
封印を開き給う者
草刈
生命の道と死の道 出陣学徒を送る為に
解説 木田献一 伊藤虎丸
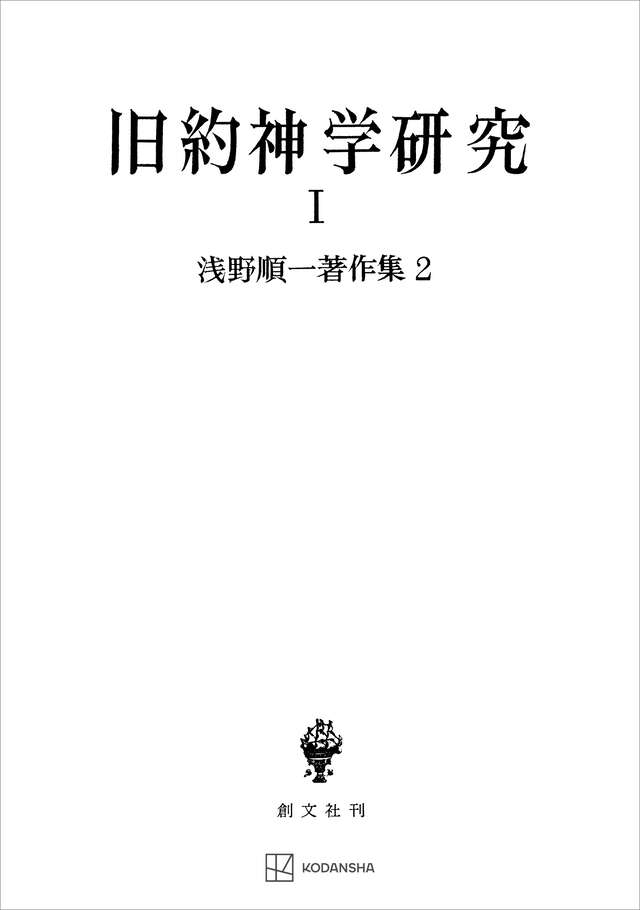
浅野順一著作集2:旧約神学研究I
創文社オンデマンド叢書
牧師にして、神学者の浅野順一「著作集」全11巻の第2巻「旧約神学研究』。
【目次より】
目次
《聖書と民族》
序
緒論
旧約聖書と基督教教会
第一部
モーセの十誡について
イスラエルに於ける王国の歴史とその性質
イスラエル予言者に於ける召命経験の特色
予言者の国家観
旧約聖書に於ける神の国
旧約時代のユダヤ人会堂について
第二部
聖書と民族
ナチスの宗教政策と旧約聖書
予言者と平和
予言者の国防
求道国日本
日本精神と基督教
《旧約神学の諸問題》
序
旧約神学の意義とその任務 最近に於ける旧約研究の傾向について
旧約聖書の神観
一 序言
二 神名
三 神の本質
四 神の業
五 結語
旧約聖書的人間、殊にその罪悪について
一 序言
二 創造と人間
三 罪悪と人間
四 結語
旧約聖書に於ける歴史の理解
一 序言
二 旧約聖書に於ける歴史の重要性 歴史化の問題
三 旧約聖書に於ける歴史の意義
四 契約思想と歴史
五 契約の二重性 律法と恩恵
六 審判としての歴史 賞罰の思想
七 救拯としての歴史 歴史に於ける神中心主義
八 予言者の宗教経験 殊にその召命
九 終末論 終末に関する予言者的理解
旧約聖書に於ける民族の意義
一 選民
二 国土・法制・国家
三 歴史と召命
四 律法と伝道
イスラエル予言者と政治
一 序言
二 歴史的検討
三 諸説
四 批評
五 結語
旧約聖書に於ける全体と個人
一 序言
二 旧約聖書に於ける個人
三 イスラエル宗教に於ける民族性
四 結語
附録 詩篇の宗教
一 序説
二 詩篇の宗教観
《旧約神学小論》
旧約聖書に於ける人間の身体的構造
一 人間の創造 「霊肉」
二 精神的諸器官 「肉」
三 「霊」と「魂」
四 人間に於ける霊肉の関係
教会の問題としての国家
解説 大内三郎 木田献一
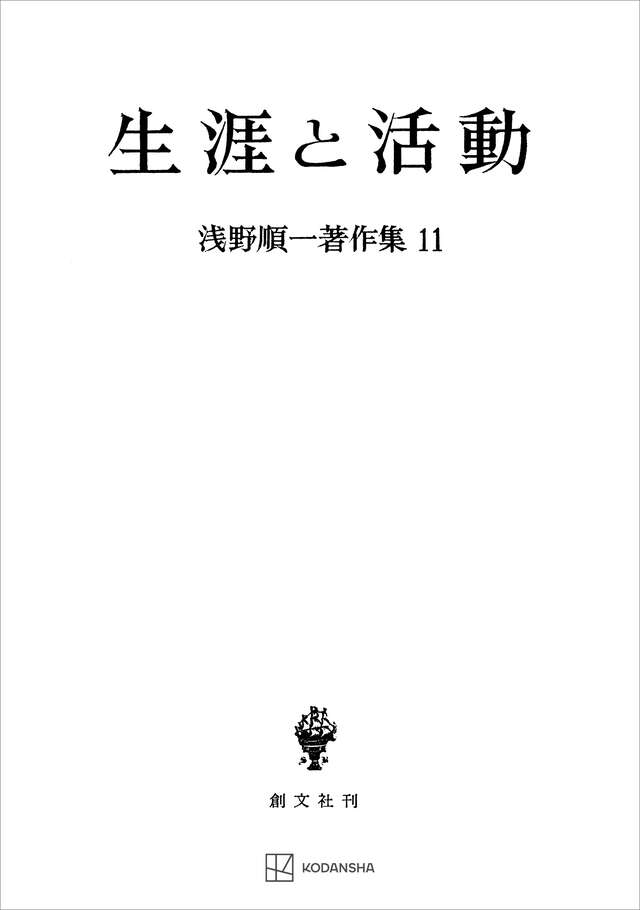
浅野順一著作集11:生涯と活動
創文社オンデマンド叢書
牧師、神学者の浅野順一「著作集」全11巻の第11巻「生涯と活動」。石謙謙(エッセイ)大内三郎・土屋虎男・伊藤虎丸(解説)収録。
【目次より】
《たましいの足跡》
半世紀に近い交友 石原 謙
たましいの足跡
幼い頃
クラマンさん
京城の記憶
府立一中入学
森明先生
三井物産入社
転期
その頃の東京神学社
森明先生の死
ヨーロッパ航路
留学 イギリス
留学 ドイツ
ヨーロッパ駆け足旅行
美竹教会の発足
軍隊生活
亡児追憶
恩師について
基督論に関する森明先生の手紙
書斎の森明先生
或る夏の高倉徳太郎先生
高倉徳太郎先生と旧約の予言者
アダム・C・ウェルシュ教授
石原謙先生と私
あとがき
《歴程(一九二六~一九八〇)》
エディンバラ通信
ハイランド雑記
祖国を思う心
ゼネヴァ回顧
逝ける愛国的国際主義者
上田丈夫君を弔う
日本神学校を辞す
公同教会運動について
エッチ・アール・マッキントッシュ教授の死
築山さんと私
独逸に於ける基督教の争闘
共助会と私
生命を得る者と失う者 故森明先生二十周年記念
古きと新しきもの 旧約聖書の現代的意義
世界平和と日本の教会
日本伝道の再構想
大村勇氏「日本伝道の問題」を読む
教会と平和問題
教界一九五三年の回顧 日本伝道一年を回顧
復活節と日本の習俗
日本伝道の将来 その神学の自立性について
感謝の辞(学位授与祝賀会)
教師検定試験を終えて
美竹教会を辞任する
一九六三年度秋季教師検定試験を終えて
旧約を学んで四十年
アメリカの友への手紙 ベトナム戦争について
ベトナム戦争、私の和平論
折にふれて
学生運動について
韓国の友へ
ご挨拶に代えて(新泉教会設立)
私の読書
老いと闘う
如何に春を迎えるか
祈り
解説
年譜
著作目録
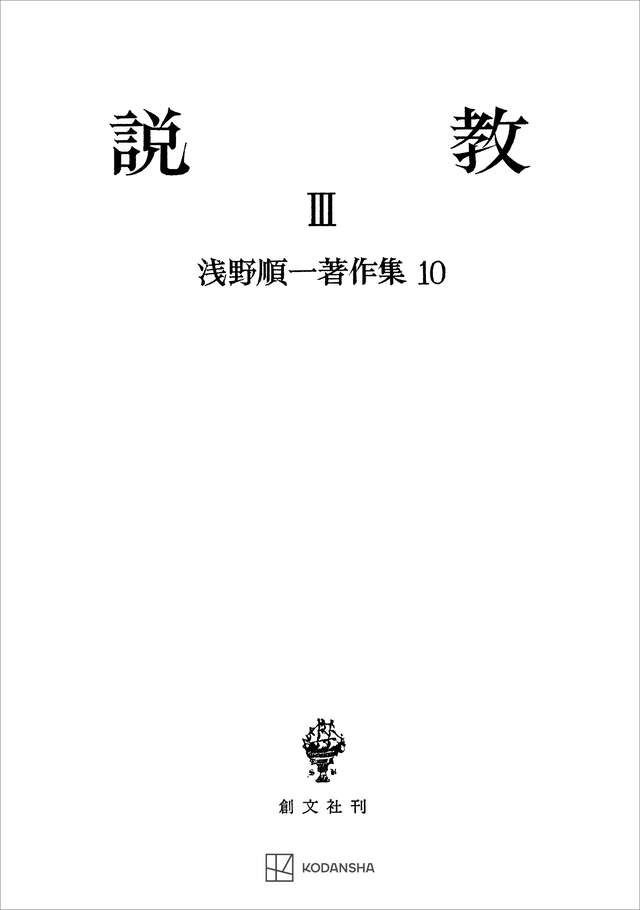
浅野順一著作集10:説教III
創文社オンデマンド叢書
牧師にして神学者の著者・浅野順一「著作集」全11巻の第10巻「説教3」。
【目次より】
《静かにして恐れるな 予言者イザヤ》
教会 主のぶどう畑
激動の中の静けさ
慎みて静かなれ
まつりごとはその肩に
「残りの者」とは何か
平和ならしめる者 日本の敗戦を記念して
二つのものを一つに 韓国に使いして
予言者の幻 永遠の平和
人はみな草である
この土台 イエス・キリスト
我のみ主、我のみ救う者
自らを隠す神
苦しみの炉
キリストのうちに自分を
主のしもべ われらの目ざすべき目標
人は何によって生きるのか
あとがき
《希望はどこにあるか》
I
旧約聖書における神話と歴史
旧約聖書における「審き」と「救い」 第二イザヤについて=歴史の予言者
旧約聖書における「言葉」
旧約聖書における「老い」の問題
旧約聖書における「空」の論理
旧約聖書における祖国観
旧約聖書における「法」と日本人の生活
旧約聖書における信仰告白 申命記第六章四―九節について
II
戦後二十五年・わたしの闘い 靖国法案反対の弁
信仰者はどう生きるか
現代にとってなぜ宗教なのか
信仰と自由 韓国の現状を見て
III
ヨブの教えるもの
宗教者と平和
闇の中に星の光を
教える者は学ぶ者
一老牧師の読者
隠れた神
希望はどこにあるか
なぜ生きるのか
言葉と言葉
この年をどう生きるか
あとがき
《説教について》
旧約聖書と説教
一 説教における旧約理解
二 イエス・キリストの証言としての説教
三 律法と福音
四 説教はいかに準備すべきか
解説 土屋虎男

浅野順一著作集1:予言者研究I
創文社オンデマンド叢書
神学者にして牧師の浅野順一の「著作集」全11巻の第1巻「予言者研究1」。
【目次より】
目次
序 高倉徳太郎
序(改版)
エリヤの宗教改革
一 序言
二 予言者エリヤの時代的背景
三 対カナン文化の問題
四 アハブ時代の宗教及び道徳問題
五 エリヤの宗教改革運動
六 結語
アモスの宗教
一 彼の人物
二 彼の時代
三 神観
四 宗儀の問題
五 罪観
六 審判
ホセアの宗教
一 彼の人物と時代
二 彼の家庭
三 神観
四 罪観
五 審判
六 結語
イザヤの贖罪経験 イザヤ書第六章の研究
一 彼の見たる幻
二 神観
三 贖罪
四 召命
五 審判
ミカの宗教思想
一 序言
二 彼の人物と時代
三 彼の神とイスラエルの罪
四 審判と希望
五 結語
エレミヤの召命経験 エレミヤ記第一章の研究
一 序言
二 彼の生い立ち
三 万国の予言者
四 巴旦杏の枝
五 沸騰る鍋
六 結語
神とエレミヤ
「主の僕」の歌 イザヤ書四二・一―四、四九・一―六、五〇・四―九、五二・一三―五三・一二の研究
一 序言
二 「主の僕」の歌の成立
三 異邦人の光
四 苦難の僕
五 「主の僕」とイエス・キリスト
六 結語
附録 旧約研究の方法論について
《旧約聖書》
序
第一章 旧約聖書の意義と価値
イ 一般文化的価値
ロ 旧約と新約との関係
ハ 旧約宗教の特質
二 旧約聖書に対する解釈
第二章 旧約聖書の正経性
第三章 律法の意義とその発達
イ 律法と契約
ロ モーセ五書の資料
ハ 律法の成立
ニ 天地の創造と始祖の信仰
ホ 出埃及とモーセ
第四章 旧約の歴史書
イ 歴史記述の意義と目的
ロ カナン侵入と定住
ハ 王国の建設
二 南北朝時代
第五章 予言者及び予言文学
イ 予言者の意義と使命
ロ アモスとホセア
ハ イザヤ
ニ ヨシアの宗教改革及びエレミヤ
ホ エゼキエル
へ 第二イザヤと「主の僕」の歌
第六章 詩歌、教訓及び黙示
イ エズラ、ネヘミヤとユダヤ教の発達
ロ 詩篇の宗教
ハ ヨブと苦難
ニ 知恵と懐疑
ホ 終末の書
参考書目
解説 大内三郎 木田献一

ヨブ記註解4
創文社オンデマンド叢書
ヨブ記は旧約聖書所収の書物。神の裁きと苦難の問題を扱う。特に、正しい人に悪いことが起こる「義人の苦難」の文献として知られる。
『旧約聖書』中の書物。執筆者はモーセとされているが、実際の作者は不明である。『ヨブ記』の中心テーマは、神の裁きと苦難であり、また「義人の苦難」が扱われている。つまり、なぜ良き人が苦しむということが起こるのかを問うている。「ヨブ記」には、神の前に出現するサタンが描かれてもいる。
【目次より】
序
ヘブル語アルファベット発音表
参考せる註解・翻訳・辞典
ダイアローグ(承前)
説教者の登場 (三二章)
神の霊、全能者の息(三三章)
邪悪より遠き全能者(三四章)
信仰 何の益か(三五章)
苦しみによる救い(三六章)
創造の神 自然の命令者(三七章)
雲に知恵、霧に悟り(三八章)
野の獣、空の鳥(三九章)
高ぶる者(四〇章)
契約を結び得ざるもの(四一章)
懺悔と結末(四二章一―六)
エピローグ(四二章七―一七)
繁栄の回復(四二章七―一七)
私訳

ヨブ記註解3
創文社オンデマンド叢書
ヨブ記は旧約聖書所収の書物。神の裁きと苦難の問題を扱う。特に、正しい人に悪いことが起こる「義人の苦難」の文献として知られる。
『旧約聖書』中の書物。執筆者はモーセとされているが、実際の作者は不明である。『ヨブ記』の中心テーマは、神の裁きと苦難であり、また「義人の苦難」が扱われている。つまり、なぜ良き人が苦しむということが起こるのかを問うている。「ヨブ記」には、神の前に出現するサタンが描かれてもいる。
【目次より】
序
ヘブル語アルファベット発音表
参考せる註解・翻訳・辞典
ダイアローグ(承前)
悪人の分 ゾパル(二〇章)
同一の死 ヨブ(二一章)
神との和らぎ エリパズ(二二章)
「隠された神」 ヨブ(二三章)
諸悪の社会 ヨブ(二四章)
人は蛆、人の子は虫 ビルダデ(二五章)
天を震わせ、海を静める者 ヨブ(二六章)
純潔の主張 ヨブ(二七章)
附記 ヨブ記二五、二六、二七章の関係について
知恵の讃歌(二八章)
幸いなる回顧 ヨブ(二九章)
現在の孤独 ヨブ(三〇章)
無罪の証言 ヨブ(三一章)
私訳
いわゆる「否定的告白」 ヨブ記三一章について
旧約聖書における目 主としてヨブ記

ヨブ記註解2
創文社オンデマンド叢書
ヨブ記は旧約聖書所収の書物。神の裁きと苦難の問題を扱う。特に、正しい人に悪いことが起こる「義人の苦難」の文献として知られる。
『旧約聖書』中の書物。執筆者はモーセとされているが、実際の作者は不明である。『ヨブ記』の中心テーマは、神の裁きと苦難であり、また「義人の苦難」が扱われている。つまり、なぜ良き人が苦しむということが起こるのかを問うている。「ヨブ記」には、神の前に出現するサタンが描かれてもいる。
【目次より】
ヘブル語アルファベット発音表
参考せる註解・翻訳・辞典
ダイアローグ(承前)
エリパズの発言 第二回の弁論(一五章)
ヨブの反論(一六章)
ヨブの保証者(一七章)
再びビルダデの抗弁(一八章)
ヨブの抗弁 「贖う者」(一九章)
私訳
説教者としてのジョン・カルヴィン
ヨブ記と内村鑑三

ヨブ記註解1
創文社オンデマンド叢書
ヨブ記は旧約聖書所収の書物。神の裁きと苦難の問題を扱う。特に、正しい人に悪いことが起こる「義人の苦難」の文献として知られる。
『旧約聖書』中の書物。執筆者はモーセとされているが、実際の作者は不明である。『ヨブ記』の中心テーマは、神の裁きと苦難であり、また「義人の苦難」が扱われている。つまり、なぜ良き人が苦しむということが起こるのかを問うている。「ヨブ記」には、神の前に出現するサタンが描かれてもいる。
【目次より】
序
ヘブル語アルファベット発音表
参考とせる註解書その他
プロローグ(ヨブ記一―二章)
ヨブの敬虔と幸福(一ノ一―五)
神とサタンとの対話(第一回)(一ノ六―一二)
最初の試練(一ノ一三―二二)
神とサタンとの対話(第二回)(二ノ一―六)
ヨブの病、再度の試練(二ノ七―一〇)
友人の訪問(二ノ一一―一三)
ダイアローグ(ヨブ記三章―四二章一ノ六)
ヨブの発言 その嘆き(三章)
エリパズの弁論(四章)
エリパズの弁論の続き(五章)
ヨブの答え(六章)
ヨブの嘆き(七章)
ビルダテの登場(八章)
ヨブの答え 皆同一(九章)
再び生の否定(一〇章)
ゾパルの登場(一一章)
三たびヨブの反論(一二章)
ヨブの道(一三章)
絶望の生(一四章)
私訳
旧約口語訳について
ヨブ記におけるサタン
Tur-Sinai の The Book of Jobなど

資本主義経済の変動理論(現代経済学叢書)
創文社オンデマンド叢書
資本主義経済は、なぜ好景気と不景気を繰りかえすのか? 恐慌はなぜ起こるのか? 人口の増加、生活水準の向上、技術革新を原動力に、資本主義は矛盾を景気循環と恐慌によってその矛盾を乗り越えながら、進歩していく。原動力となるうちの、人口増加と生活水準の向上は時としてインフレを喚起することになるが、技術革新により価格抑制効果が、インフレを抑える力となる。経済活動の根本原理をわかりやすく説く格好の入門書。
【目次より】
はしがき
序章 ケインズ理論の長期化
0.1 ケインズ理論の二つの貢献
0.2 ケインズ理論の発展
0.3 価格分析か所得分析か
0.4 本書の課題
第一章 静学的ケインズ理論
1.1 ケインズの均衡理論
1.2 有効需要の原理
1.3 ケインズの完全雇傭政策
第二章 ケインズ体系の安定条件
2.1 フリッシュ・サミュエルソン的動学化
2.2 変動過程の一時的均衡分析
第三章 ケインジアンの景気循環論
3.1 貨幣的蜘網景気論
3.2 ウィクセル的景気理論
3.3 カルドア的過少支出説
3.4 ヒックス的労働不足説
第四章 景気循環と経済成長
4.1 景気循環と成長
4.2 カルドア理論と成長
4.3 ヒックス理論と成長
4.4 マルクスの循環的成長理論
第五章 成長率による経済変動の分析 もう一つの所得分析的変動理論
5.1 はしがき
5.2 モデルの構成
5.3 成長率
5.4 諸成長率の間の関係
5.5 投資決意に関する仮定
5.6 景気変動
5.7 経済成長
5.8 長期的完全雇傭政策
第六章 価格分析的変動理論 一つのハードル理論
6.1 本章の課題
6.2 モデルの構成
6.3 景気の回復
6.4 景気の上昇
6.5 好況の崩壊
6.6 不況過程
6.7 静止的状態
6.8 趨勢の導入
引用文献

産業連関論入門
創文社オンデマンド叢書
1973年にノーベル経済学賞受賞者のレオンチェフが最初に作成した「産業連関表」とは、産業間のつながりを示すマトリックス。ある産業は、他の産業から原材料などを購入し、これを加工して別の財・サービスを生産する。そして、生産した財やサービスをまた別の産業部門に対して販売する。このような財・サービスの「購入→生産→販売」という連鎖をマトリックスとして表示するのが産業連関表である。産業連関表を利用すると、ある産業に新たな需要が発生した場合、どのようにその生産が波及していくのかを計量化可能になる。本書は、マクロ経済学の中の企業活動の領域の入門書。
【目次より】
はしがき
第一章 産業連関表と産業連関分析
緒言
産業連関論の概略
産業連関論と経済政策
第二章 産業連関の静学理論
物量的産業連関システムと価値的産業連関システム
均衡産出量の決定
均衡産出量の図形的説明
均衡産出量の正値条件
逆係数の図形的説明
波及構造の定性分析
波及構造の定量分析
産業連関システムと価格の決定
第三章 産業連関論と企業理論
I サミュエルソンの代替定理
代替の可能性
等生産量曲線
収穫不変性の仮定
生産方法の決定
サミュエルソンの代替定理の批判
II クープマンスの代替定理
新しい企業理論 線型計画論
労働の有効配置
クープマンスの代替定理の批判
III クラインの代替定理
クラインの代替定理
ヒックスの企業理論
価値的投入係数の固定性
規模に関する収穫の可変性
クラインの代替定理の批判
第四章 産業連関論と一般均衡理論
一般均衡論におけるワルラスとヒックス
一般均衡理論
利潤率均等の法則と代替定理
消費者の選択理論
産業連関論と一般均衡理論
第五章 産業連関論とケインズ経済学
ケインズ経済学とケインズ哲学
産業連関論における国民所得
産業連関論とケインズ経済学
第六章 産業連関の動学理論
動学的産業連関システム
産業の均等発展と不均等発展
国民所得分析と循環的成長
産業連関分析と循環的成長
第七章 産業連関論と外国貿易
輸出入を含んだ産業連関システム
国内産出額および輸入額の決定
線型計画論による輸入計画の編成

近代社会の経済理論
創文社オンデマンド叢書
「通常の経済原論ないし経済理論の教科書では、理想型の資本主義社会を前提として、企業や家計の生態が説明されるとともに、社会の機構と動態が分析されている。けれども現実の資本主義社会は理想型どおりではないし、また資本主義諸国は世界の一部をなしているにすぎない。もはや時代は、非資本主義的要素や勢力を無視ないし軽視すると、現実の社会の重要な現象を理解しえないばかりか、硬直的な視角から、かたくなに世の中を見るという羽目に陥ってしまうような段階にきている。
しかしながら勢力を増大しつつある非資本主義経済と、資本主義経済の間には、それらが共に近代的な経済体制であるがゆえの、多くの論理の共通点があるし、また現実の資本主義経済(たとえば日本経済)が理想型どおりでないといっても、「ずれ」は無原則的ではなく、「ずれ」には「ずれ」の論理がある。本書においては、対象を理想型の資本主義経済に限定せず、社会主義経済を含む近代社会に一貫する経済合理性を明らかにすると共に、他方において日本の経済が明治革命以後たどって来た特異な経済発展をも説得的に説明することを試みる。したがって本書は、広い意味での比較体制論の領域に属するであろうが、その領域の屁金的な研究よりも、さらに論理的・分析的である。それと同時に本書は、その視野が短期的であるという意味で不完全であり、一層大部の書物の上巻であるに過ぎないかも知れないということを指摘しておかねばならない。」(本書「はしがき」より)
本書は1967から68年に大阪大学で行われた講義をもとにしています。
【目次より】
はしがき
序論 近代国民経済
理想型としての近代国民経済 ー 本書の梗概
第1部 経済のミクロ的合理性
1.生産技術
生産の樹木図 生産関数 ー 総生産関数
2.技術の選択
異なる技術の併用 ー 総額崇拝の誤謬
3.利潤の分配
分配とイデオロギー ー イデオロギー的利潤分配の非合理性
4.計画の変更
企業者活動の相対性 ー ストルパー・サミュエルソンの定理とリブチンスキーの定理の拡張
5.家計の行動
家計の独立性 伝統的需要理論 ー 闇市場のある場合
第2部 市場機構と計画
6.伸縮価格経済
価格決定の二方式 ー 価格形成過程の分析
7.固定価格経済
ケインズ登場 ー 有効需要の原理
8.分権的計画経済
資本財および労働の最適配置 ー 価格公定の法則
第3部 国家による経済制御
9.財政と完全雇用
政府の経済行為 ー 完全雇用乗数
10.二重構造と失業
日本の潜在的失業 ー ケインズ政策と潜在的失業

近代日本の政治と人間
創文社オンデマンド叢書
丸山眞男に師事した著者の専門分野である近代日本政治思想史についての著作である。特に近世国学から明治期における政治思想と人間観について論じる。
【目次より】
一 明治思想における政治と人間
二 啓蒙期知識人の役割
三 加藤弘之の転向
四 明治前期の保守主義思想
五 「民本主義」の構造と機能 吉野作造を中心として
六 大山郁夫の政治思想 大正デモクラシー期における思想と言論
七 国民的使命観の歴史的変遷
あとがき

熊本藩法制史料集
創文社オンデマンド叢書
主に永青文庫所蔵の熊本藩法制史料の中から、「刑法草書」を中心に刑事関係の基礎的史料を選び、解題を付して編集。2部構成で、第1部では「刑法草書」の立法、第2部ではその運用に関する史料をそれぞれ翻刻収録した。
【目次より】
序
解題
第一部
1 宝暦四年捧呈、同五年施行の刑法草書
1 御刑法草書 一冊 2 御刑法草書 一冊
2 宝暦十一年施行の刑法草書の草案
1 堀平太左衛門起草の試案 一冊 2 第一次草案ならびに編纂委員意見 四冊 3 第二次草案ならびに編纂委員意見・付札例書 三冊
3 暦十一年施行の刑法草書 三冊
4 天保十年施行の御刑法草書附例 二冊
附録 刑法新律草稿 一冊
第二部
1 熊本藩刑律和解及御裁例 四冊 2 参談書抜 一冊 3 御刑法方定式 一冊 4 旧章略記 一冊(抄録) 5 死刑一巻帳書抜 一冊 6 除墨帳 一 冊(抄録) 7 小盗笞刑 一 冊 8 益田彌一右衛門上書堀平太左衛門返答之書付 一 冊 9 肥後経済録 一 冊(抄録) 10 隈本政事録 一 冊(抄録) 11 肥後物語 一 冊(抄録) 12 通俗徒刑解 一 冊(抄録) 13 銀台遺事 一 冊(抄録) 14 肥後熊本聞書 一 冊(抄録) 15 拷問図 一巻
第一部
1 宝暦四年捧呈、同五年施行の刑法草書
1 御刑法草書(宝暦四年捧呈) 2 御刑法草書(宝暦四年捧呈、同五年施行、施行中随時修正増補)
2 宝暦十一年施行の刑法草書の草案
1 堀平太左衛門起草の試案
律艸書
2 第一次草案ならびに編纂委員意見
御刑法例書 御刑法艸書 盜賊・人命 御刑法艸書 訴訟・詐偽・受贓・関津・捕亡・犯姦 御刑法艸書 闘殴・雑犯
3 第二次草案ならびに編纂委員意見・付札例書
御刑法例書 御刑法草書 盗賊・詐偽・奔亡・犯姦 御刑法草書 闘殴・人命・雑犯
3 宝暦十一年施行の刑法草書
刑法例書 刑法艸書 盗賊・詐偽・奔亡・犯姦 刑法艸書 闘殴・人命・雑犯
4 天保十年施行の御刑法草書附例
御刑法草書附例 乾 名例・盗賊・詐偽 御刑法草書附例 坤 奔亡・犯姦・闘殴・人命・雑犯 附録 刑法新律草稿
第二部
1 熊本藩刑律和解及御裁例 2 参談書抜 3 御刑法方定式 4 旧章略記(抄録) 5 死刑一巻帳書拔 6 除墨帳(抄録) 7 小盗笞刑 8 益田彌一右衛門上書堀平太左衛門返答之書付 9 肥後経済録(抄録) 10 隈本政事録(抄録) 11 肥後物語(抄録) 12 通俗徒刑解(抄録) 13 銀台遺事(抄録) 14 肥後熊本聞書(抄録) 15 拷問図

トマス・アクィナスのキリスト論(長崎純心レクチャーズ)
創文社オンデマンド叢書
イエス・キリストとは何か? トマス・アクィナスの「神学大全」の註解を通して、彼が独自な存在論の観点からイエス・キリストを存在と働きの両面から総合的に捉えていることを解明した、新たなキリスト論展望。
「我は誰なりと思うや」とのイエスの問いに、弟子たちは「生ける神の子キリストです」と答えた。「イエス・キリストは真の人間であり神である」という使徒伝承はキリスト論の原点であり、その教義(ドグマ)は4世紀から6世紀にかけて異端論争を通して形成されてきた。トマス・アクィナスは「神学大全」第3部でキリスト論の全貌を語っているが、著者はその註解の仕事を通して、トマスが独自な存在論の観点からイエス・キリストを存在と働きの両面から総合的に捉えていることを解明し、その独創性を高く評価する。近世以降に盛んになった歴史的実証的なイエス伝研究の限界を明らかにして、新たなキリスト論を展望し、さらに信仰と理性のあり方を平易にといた講演。
【目次】
「長崎純心レクチャーズ」について 片岡千鶴子
第一日
I キリスト論とは
1 キリスト論とイエス伝
2 連続講演のプラン
II 使徒的伝承
1 キリスト論のはじまり
2 「神の子」の意味
3 使徒的伝承
4 パウロ
5 ヨハネ
6 グノーシス
III 教理史から
1 アリウス派論争
2 ネストリウス派論争
3 キリスト単一性論
IV 東西教会の分裂
1 分裂以前の東西教会
2 アウグスティヌスとFilioque
第二日
1 ヨハネ福音書とロゴス
2 翻訳の問題
3 ロゴスと神の同一性と区別
4 ヒポスタシスという言葉
5 ギリシアの神秘主義の伝統
6 受肉とキリスト論
7 キリスト論の難問
8 ダマスケヌスによる総合
9 トマスの独創性
10 トマスの存在論
11 エッセと「いのち」
12 イエス伝の問題
第三日
1 トマス以後のキリスト論
2 ドグマ的キリスト論への批判
3 ハルナックの教理史
4 ドグマとは何か
5 ドグマを決定するもの
6 ドグマの言葉
7 聖書の問題
8 存在論とドグマ
9 イエス伝への反省
10 トマスの現代的意義
あとがき

理性と信仰(関西学院大学研究叢書)
創文社オンデマンド叢書
哲学者にしてキリスト教神学者である著者による「理性」と「信仰」をめぐる論考。時に、対立する「理性」と「信仰」はどのような関係にあるのか? 「信仰」は「理性」を超えるものなのかなどを、問い直します。
【目次より】
序
第一章 キリスト教哲学の根本問題
第一節 キリスト教哲学の可能性について
序
(一) 創造における理性と信仰
(二) 堕罪における理性と信仰(イ)
(三) 堕罪における理性と信仰(ロ)
(四) 新生における理性と信仰(イ)
(五) 新生における理性と信仰(ロ)
第二節 キリスト教哲学成立の歴史
序
(一) ギリシャ哲学における理性と信仰
(二) 教父哲学における理性と信仰(イ)
(三) 教父哲学における理性と信仰(ロ)
(四) アウグスチヌスの理性と信仰
(五) 中世哲学における理性と信仰
第二章 時と永遠について
序説
第一節 聖定における時と永遠の位置
第二節 創造における時と永遠
第三節 摂理における時と永遠
(一) 業の契約と時間の構造
(二) アダムの堕罪と時間
(三) 恵みの契約と時間の遠近法
第四節 新約の時と永遠
(一) 新約的時間の遠近法
(二) 終末における時と永遠
結語
「補論」一般史と救済史の関係について
第三章 自然の意味について
序
第一節
(一) ギリシャ的自然観
(二) 中世的自然観
附論 トーマス・アキーナスの自然観
(三) ルネッサンスの自然観
第二節 近世初頭における自然科学とプロテスタント信仰
(一) 予定論と科学(イ)
予定論と科学(ロ)
(二) 第二原因としての自然法則(一)
第二原因としての自然法則(二)
第三節 聖書の自然観
序
(一) 創造における自然
(二) 摂理における自然
(三) 終末における自然
第四章 知性の改善
序
第一節 理性の訓練
(一) プラトンの知識論
(二) 知識形成の基盤としての神と自己の存在認識
第二節 危機に立つ理性
(一) 史学的見方
(二) 社会学的見方
(三) 哲学宗教的見方
結論
「附論」ルネッサンスと宗教改革
附録(一) 自然的秩序と目的論的秩序 カントの目的論の構造と批判
附録(二) カントの目的論における普遍と個物の関係について

実存の真理を求めて
創文社オンデマンド叢書
「本質的存在」と「現実的存在(実存)」は、ギリシア哲学者プラトンのイデア論以来、哲学上の大きなテーマであり続けています。近代に入り、19世紀にはキルケゴールが改めて「実存」を問い直し、20世紀にはハイデガー、ヤスパース、サルトルとその系譜が引き継がれました。ヤスパースの実存哲学の専門家である著者が、「実存」を徹底的に問い直します。
【目次より】
まえがき
第一章 まことを求めて
一 本物の音色 二 真理と自由 三 現代の反省 四 母性について
第二章 アメリカ文化とドイツ精神
第三章 道徳教育の反省
第四章 ヤスパースの教育観
第五章 ヤスパースの歴史観
第六章 追憶
一 ヤスパース 二 ハイデッガー
第七章 カール・ヤスパース 生涯と思想
第八章 シェーラーにおける人間の地位
第九章 ヤスパース 『真理について』以後
第十章 ヤスパースの時代批判
第十一章 実存哲学の実践的性格
第十二章 ハイデッガーにおける存在と実存
第十三章 [附録]生きる力(カール・ヤスパース 斎藤武雄訳)

ツアラツストラを読む人のために
創文社オンデマンド叢書
永劫回帰とは? 超人とは? 京都学派の巨人による、寓意に溢れるニーチェの主著『ツアラスツストラ』を読む人のための手引き。
京都学派の巨人の一人である著者が、難解で知られるニーチェの『ツァラトゥストラ』を丁寧に読み解いていく。わかる人も、わからない人にとっても、有益な入門書。日々生きていく中の課題に新鮮な見方を与えてくれる一冊です。
【目次より】
序
緒言
第一章 ツァラツストラとニーチェ
第二章 ツァラツストラの誕生
第一節 「悦しき科学」との関係
第二節 ツァラツストラの成立過程
第三章 ツァラツストラの構造
第一節 序説について
第二節 「彩られし牛」と呼ばれる町での説教 第一篇
第三節 「幸福なる島々」における説教 第二篇
第四節 漂泊者の言葉と快癒者の言葉 第三篇
第五節 ツァラツストラの誘惑 第四篇
第六節 大なる正午とツァラツストラの死 書かれざりし第五篇と第六篇
第四章 教説としての超人
第一節 歴史的未来としての超人
第二節 歴史的批判者及び創造者としての超人
第三節 生の肯定者としての超人
第五章 実存としての超人
第一節 重力の精とは何か
第二節 嘔吐としての生 ワグネル、レー・ルー
第三節 ニヒリズムの最も極端な形式としての永劫回帰
第四節 肯定の最高方式としての永劫回帰
再刊にあたって 久山康

正法眼蔵の研究
創文社オンデマンド叢書
鈴木大拙に師事した禅の思想的研究者である著者が、道元の主著である『正法眼蔵』の成立とその内容を徹底的に解説する。
【目次より】
序
[第一部]
第一章 道元の遍歴 入宋参学の跡
第二章 正法眼蔵の成立に対する一私見
附・特に「嗣書」について
第三章 道元の眞筆本について
第四章 正法眼蔵の「示衆」とその各巻の題号
[第二部]
第五章 正法眼蔵私釈
全機
都機
諸法実相
見佛
古鏡
空華