創文社オンデマンド叢書作品一覧
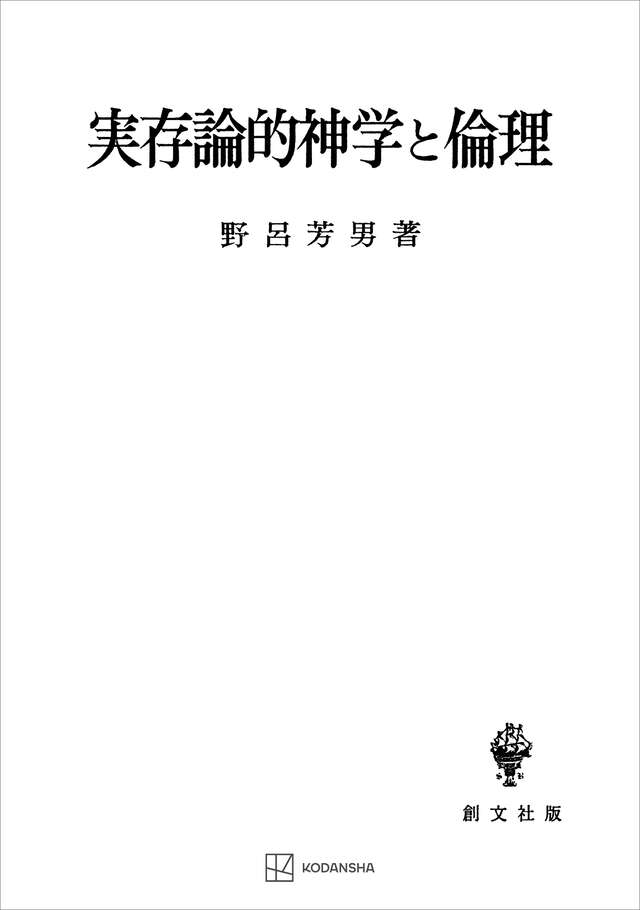
実存論的神学と倫理
創文社オンデマンド叢書
四つの論文から構成される。
本書の第一章「実存論的神学の展開方向」ではキリスト論を中心に論じる。第二章「神の死と実存論的神学」は、聖霊論を媒介にして神観を記述することで、著者の立場が明らかにされる。
第三章「神学と倫理」は実存論的神学を基礎する宿命倫理の構築を試みる。その際、援用されるのが、アメリカの自由主義神学者ニーバー(1892~1971)の思想である。第四章「ラインホルド・ニーバーの政治思想」では、ニーバーの思想を肯定的に叙述する。
キリスト教的な新しい倫理を模索する著作である。
【目次】
第一章 実存論的神学の展開方向
一 実存論的神学と弁証法的神学
二 実存と体験
実存論的神学と存在論、及びエーベリングの言葉の出来事 啓示と実存 実存論的神学と実存主義 その両者の話合いの可能性
三 史的イエスと信仰のキリストの問題についてのバルトの理解
四 マイケルソンの歴史としての神学
五 実存論的神学と神秘
イエスの服従 愛
第二章 神の死と実存論的神学
一 ニーチェ
二 ヴァン・ビューレン
ウィトゲンシュタインの言語ゲーム
三 ヴァン・ビューレン批判
四 ティーリケのニヒリズム批判
信仰とニヒリズム 不条理 コックスの非聖の都会の容姿と次元的思考 西谷啓治 ヴァハニアン 倫理についての二つの推論
五 聖霊論
第三章 神学と倫理
一 ブルトマンの新約の倫理
二 シュヴァイツァーの生への畏敬と倫理
三 バルトの倫理
四 ポール・レーマンの倫理
レーマンとジョン・ベネット 良心 ジョセフ・フレッチャーの倫理 フレッチャーのR・ニーバー批判
五 歴史と自然
第四章 ラインホルド・ニーバーの政治思想
一 ニーバーの政治思想について
二 ニーバーのエーリッヒ・フロム批判
三 ニーバーの共産主義批判
四 ニーバーの社会集団論
五 アジア・アフリカ諸国とデモクラシー
ハミルトンのニーバー批判
六 宗教的社会主義の問題
七 平和主義の問題
あとがき
事項・人名索引

近代日本経済史(現代経済学選書) パックス・ブリタニカのなかの日本的市場経済
創文社オンデマンド叢書
近世社会の多重国家体制の下で残された財産目録を丹念に分析し、中央集権国家への転換に見られる連続緒非連続の両面を総合的に考察するとともに、パックス・ブリタニカへの参入から第二次大戦の破局にいたる1世紀におよぶ経済社会の展開を解明した第一級の概説。
新しい市場社会のための法制度や経済共通基盤の整備、その時々の産業政策やマクロ経済など、日本型市場社会の形成に関わるさまざまな営為を、膨大な史料と最新の研究成果により実証的に分析する。社会史的な支店も導入して独自の歴史叙述を実現した本書は、今日における経済史研究の到達点を示すものに他ならない。
冷戦構造崩壊のさなかに身を置き〈日本近代〉の等身大の自画像を描こうとする著者の情熱は、経済学の分野をこえて人文・社会諸科学の研究者、そしてわが国の市場社会に関心を寄せる読者に共通理解の場を提供するとともに、定量分析のあり方など今後の社会研究に対しても多くの示唆を与えよう。
【目次】より
第I部 「開放体系」への移行 1859-90年
1 19世紀前半の日本経済 開港に際しての初期条件
2 開港と「価格革命」 外からの衝撃
3 近代国家の形成 多重国家体制から単一国家体制へ
4 工業化のための制度的枠組の形成 経済共通基盤の整備
5 近代経済発展の始動 在来部門の成長と再編成
第II部 工業化の始動と展開 1891-1913年
1 パックス・ブリタニカへの参入 日本の対内・対外経済政策
2 近代工業の発展 二つのリーディング・セクター,紡績業と造船業
3 工業化を支えたもの 貿易と技術移転
4 工業化の担い手 企業家・技術者・労働者
5 工業化と小規模家族農業 農業部門と非農業部門の関係
第III部 戦争景気から「慢性的不況」へ 1914-31年
1 動揺する世界政治・経済秩序と日本経済 第一次世界大戦から世界恐慌へ
2 工業化の新しい局面 動力革命と重化学工業化
3 金融再編成と産業合理化 大企業体制の成立
4 農業の停滞と不均衡成長 二重構造
5 都市化の進展と大衆社会化への動き 都市の変貌と生活様式の変化
IV部 戦争と統制経済の展開 1932-45年
1 国際金本位制の終焉 パックス・ブリタニカの解体と日本の孤立化
2 管理通貨体制下での景気転換 経済成長のメカニズム
3 15年戦争の開始と重化学工業化の進展 産業構造の変化
4 統制経済の展開 市場経済の変容
5 戦争拡大と日本経済の破局 太平洋戦争から敗戦へ
参考文献
あとがき
年表
索引

国民経済計算(現代経済学選書)
創文社オンデマンド叢書
ある国の、生産・消費・投資等のフローと資産・負債等のストック面を体系的に記録し、その国の経済状態を示す。GDP(国内総生産)はその代表的な指標のひとつである。本書は、マクロ経済学の基礎的な理論と実践を理解するための格好の手引きである。
【目次】
まえがき
一 フロー表
1 経済的数量の記録 2 生産勘定 3 所得支出勘定 4 資本調達勘定 5 貯蓄と投資の均等 6 問題 7 研究の手引き
二 国民貸借対照表
1 フロー量とストック量 2 調達勘定 3 統合勘定(国民貸借対照表) 4 問題 5 研究の手引き
三 産業連関表
1 多数の財・サービスを扱う勘定体系 2 2産業の産業連関表 3 多産業の産業連関表 4 国民経済的視点 5 新SNAと数量経済学の課題 6 問題 7 研究の手引き
四 計量経済学
1 計量経済学的実証研究の例示 2 計量経済学 3 マクロ・エコノメトリック・モデル 4 日本のマクロ・エコノメトリック・モデル 5 問題 6 研究の手引き
〔略〕
八 経済成長の要因分析
1 日本経済の経済成長 2 成長会計による要因分析の方法 3 計量経済学による要因分析の方法 4 成長会計による要因分析の結果 需要面 5 成長会計による要因分析の結果 供給面 6 計量経済学モデルによる要因分析の結果 需要要因 7 計量経済学モデルによる要因分析の結果 供給要因 8 成長の阻害要因 9 問題 10 研究の手引き
九 景気循環
1 好況と不況 2 景気変動の原因 3 最近の景気変動のパターン 4 為替レートと貿易収支 5 Jカーブ効果 6 為替レートと景気循環 7 問題 8 研究の手引き
十 産業構造の変化
1 産業構造:第1,2,3次産業 2 産業構造:製造業 3 産業連関分析 4 産業構造の変化の要因分析(1):方法 5 産業構造の変化の要因分析(2):実証的結果 6 多部門経済モデルへの道(1):生産物市場 7 多部門経済モデルへの道(2):資産市場 8 研究の手引き
十一 国民経済計算に関する補足
1 国際経済に関する勘定 2 銀行部門に関する勘定 3 政府部門に関する勘定 4 対家計民間非営利団体に関する勘定 5 国民経済計算におけるデフレータ 6 問題 7 研究の手引き
十二 産業連関表補論
1 生産者価格表と購入者価格表 2 部門分類と副産物・屑の取扱い 3 輸出・輸入の取扱い 4 家計外消費 5 新SNA方式による産業連関表
文献
問題解答
索引

一般均衡と価格(数量経済学選書)
創文社オンデマンド叢書
多数の財が取引される市場で、需要と供給、価格が決まるメカニズムを考察する一般均衡理論は、レオン・ワルラスが19世紀に創始した。その後、パレートがその理論を発展させ、20世紀半ばより整合的な価格分析の方法となった。一般均衡理論を理解するための格好の入門書。
【目次】
はしがき
第1章 経済循環図式
1 企業の経済活動
2 家計の経済活動
3 政府の経済活動
4 市場における財およびサービスの取引
5 国民所得勘定と産業連関表
第2章 消費関数の計測
1 消費者需要の理論
2 個別消費関数の計測
3 総消費関数の計測
4 個別産業に対する消費需要
第3章 生産理論の計測
1 生産者行動の理論
2 生産関数の計測
3 技術進歩率の計測
第4章 一般均衡モデルの計測
1 一般均衡理論
2 輸入関数
3 賃金決定方程式
4 財産所得方程式
5 計測された一般均衡モデル
第5章 比較静学
1 比較静学の理論
2 価格の変動
3 粗代替性・安定条件
4 雇用の変動
5 生産量の変動
6 国民所得の変動
第6章 実証的多部門経済モデルの比較
1 実証的多部門経済モデル
2 消費の内生化
3 コブ・ダグラス型生産関数
4 生産量の決定
5 価格の決定
第7章 一般均衡理論の実証性
1 価格変化に関するテスト
2 雇用の変化に関するテスト
3 生産量の変化に関するテスト
4 消費の変化に関するテスト
5 総括
第8章 価格変動の諸要因
1 価格形成と需要・供給・輸入
2 価格政策への応用
補論 クロス・セクション・データによる貯蓄関数の計測
1 序
2 予備的考察
3 方法上の問題点
4 所得効果と流動資産効果
5 所得効果の非線型性
6 年齢効果
7 過去の消費の影響
8 分布ラッグの推定
9 所得変動の影響
10 結論
付録A 統計データの出処および単位
付録B 産業連関表関係のデータ作成法
付録C 補論の統計データの出処
付録D 統計データ
引用文献
人名索引
事項索引

蟻の歌(フォルミカ選書)
創文社オンデマンド叢書
ラブレー研究で知られるフランス文学研究者・評論家であった著者による、随想集である。
【目次】
本郷三丁目
若い地質學者の變身
春日抄
「さぼてん」と僕
昔噺
羊の寓話
『櫻の園』を觀て
僕の芝居見物
『天井棧敷の人々』を觀て
『處女オリヴィヤ』を觀て
貝殻追放について
宿命とは因果律だといふことなど
「たまらん」こと
恐怖のドン底から
もつと先にしてほしいこと
感想一つ二つ
文化會長になつた僕
『インテリは生きてゐられない』を讀んで
所見
フランス人の言語教育
放言二つ三つ
フランス文學の流行は不十分である
アンドレ・ジードの死
感想的解説(『風俗小説論』を讀んで)
感想的解説(『晩歌』を讀んで)
フランス・ルネサンス文學について
後記

刑法紀行
創文社オンデマンド叢書
法学者・団藤重光による刑法をめぐってさまざまな場所や裁判などに遭遇したことを記したエッセイで、日本エッセイスト・クラブ賞を受賞した(1967年)。
【目次】
イタリア通信
イタリアの刑法教授の生活
ユーゴースラヴィアの三日間
ドイツ便り
オーストリアとスイスの旅
北欧の旅
イギリスの旅
オランダとベルギー
スペインとポルトガルのおもいで
ヨーロッパの矯正施設
北欧の矯正施設
フランスの矯正施設
アメリカのガス死刑と電気死刑
キャリフォーニアの医療矯正施設
カナダとメキシコの旅
アラブの国々を訪ねて
ソヴィエト旅行記(一九六五年)
ソヴィエト旅行記(一九六六年)

超越に貫かれた人間(長崎純心レクチャーズ) 宗教哲学の基礎づけ
創文社オンデマンド叢書
第6回長崎純心レクチャーズとして2002年に行った3日間の講演を再現。イエズス会神父であり卓越した哲学者であるリーゼンフーバー教授が、神学者、神秘思想家らとの対話を通じて導かれた「超越に貫かれた人間」の真実を語る。
人間は不可避的に問う存在である。自分自身の存在、根拠、意義を問うとともに世界の真理、意義、幸福をも探究する。人間の問いそのもののうちには、無制約的なもの、すなわち超越への開きが含まれているのである。知ることはなぜ可能か。人間はいったい何を経験するのか。この追究をとおして宗教性が人間の本質に深く根づいていることを確認し、人間と超越との関係を、超越に関わられ貫かれる人間という受動的観点から解明、さらに宗教的行為の基本構造へと考察を進め人間の存在と使命を浮き彫りにする。西洋中世哲学研究者として知られる著者が、長年の研究と思索の間に親しんだ哲学者、神学者、神秘思想家との対話にもとづき、磨かれた言語で宗教哲学の根本的考え方を明解にとく講演。
【目次】
「長崎純心レクチャーズ」について 片岡千鶴子
序言 稲垣良典
第一日 人間存在に見られる無制約性 未規定性と尊厳の間に
一 全体の問題提起
1 問題としての超越理解 2 人間からの出発
二 人間の予備概念
1 欠如性・未規定性と理性 2 個人の尊厳における無制約的なもの
三 超越への問いの精神論的可能根拠
1 自己意識と存在認識 2 像としての人間
四 精神における超越への本質的な関わり
1 問い 2 知識の要としての真理
第二日 超越経験の根本理解と諸形態 日常を意義づける無制約的なもの
一 精神的経験
1 経験の哲学的概念 2 感覚的経験と精神の経験 3 説明と理解 4 純粋な完全性の経験
二 聖書的信仰の地平のなかに見られる超越経験
1 神経験と神認識 2 感覚と存在把握 3 感覚を通して描かれる神経験 4 超越との関わりを示すいくつかのトポス
三 日常における潜在的超越経験
1 意義の発見 2 現実の承認 3 芸術的創造性における賛美 4 導きに対する信頼 5 責任における対面 6 当為の定言制 7 時間の贈り物と可能性における呼びかけ
四 意義の経験と神との出会い
第三日 宗教的行為の成立 自己実現としての脱自
一 宗教的行為の構造
1 人格的行為 2 無力と、超越による根拠づけ 3 受容と自発性 4 離脱と脱自 5 無制限の肯定と自己譲渡 6 合一と対話性 7 日常性と究極性 8 個人性と共同性
二 根本的宗教的行為の諸形態
1 言葉としての現実と神現としての根源語 2 超越への傾聴 3 黙想 4 祈り 5 信仰
あとがき

租税の経済理論
創文社オンデマンド叢書
国家など行政団体が、経費に充当するために、徴収する税金は経済理論的にどのような意味があるのか? 日経・経済図書文化賞受賞作。
財政学において、租税は重要なテーマである。本書では、公共経済学の視点から租税の経済分析を行う。より具体的には、租税帰着の理論と最適課税の理論が主題となる。本書は租税理論の研究者・専門家のみならず、財政問題に関心のある人々にとって必読書である。
総ページ数 330
判型 A5
【目次】
まえがき
第 I 部 租税帰着の理論
第1章 静学的租税帰着の理論
1.はじめに
2.静学的租税帰着モデル
3.モデルの因果律
4.比較静学分析
5.結び
数学付録
第2章 動学的租税帰着の理論
1.はじめに
2.動学的租税帰着モデル
3.予備的考察
4.比較動学分析
5.結び
数学付録
第3章 地域間租税帰着の理論
1.はじめに
2.地域間租税帰着モデル
3.比較静学分析
4.結び
数学付録
第4章 動学的階級間租税帰着の理論
1.はじめに
2.モデルの記述
3.長期均衡の諸性質
4.差別的帰着の評価
5.結び
数学付録
第 II 部 最適課税の理論
第5章 公共的競争均衡と租税体系
1.はじめに
2.公共的競争均衡モデル
3.一つの反例
4.公共的競争均衡と租税体系の両立可能性定理
5.両立可能性定理の証明
6.残された課題
第6章 住民の地域選択と分権的地方財政制度
1.はじめに
2.短期モデルの構造
3.住民の地域選択過程
4.ティブー的均衡の厚生上の意義
5.残された課題
第7章 ピグー的租税・補助金政策の有効性
1.はじめに
2.モデル、パレート効率性、ピグー的均衡
3.予想調整過程とその安定性
4.ピグー的料率の調整過程とその安定性
5.価格調整過程とその安定性
6.結び
第8章 通時的経済における租税政策の役割
1.はじめに
2.モデル
3.黄金律均斉成長経路の安定性
4.租税政策の役割
5.一つの応用例 年金制度
第9章 最適間接税の理論 展望
1.はじめに
2.最適課税問題の基本構造
3.最適課税ルールの相対的意義
4.最適課税問題の新展開
索引

東南アジア農業開発論(東南アジア研究叢書)
創文社オンデマンド叢書
農業経済学者の著者による、熱帯・亜熱帯に属する東南アジアの農業開発についての論考が本書である。
【目次より】
はしがき
序論 「南北対立」と「人口食糧」との問題
I 東西対立から南北対立へ
II 低開発国における人口と食糧とのアンバランス
III 農業開発問題の重要性
第1章 東南アジア農業開発にたいする日本の動き
第2章 東南アジアの地域的特質
I 東南アジアの地域設定
II 東南アジアの地理学的統一性
III 東南アジアの地理学的多様性
IV 東南アジアの流動性
第3章 東南アジアの経済開発戦略
I 低開発国経済開発戦略の基本問題
II 工業化論の経済理論的批判
III 東南アジア経済開発の戦略決定にかんする与件
第4章 東南アジア農業の特質
I 自然的基礎
II 人口寡少と可耕末墾地の存在
III 単一耕作的輸出農産物と多年生作物の地域的卓越性
IV 農業生産の二重構造 自給生産と商品生産、小生産者とプランター
V 米作の卓越性と食糧過不足国の分化
VI 農業における低位生産性と不完全雇傭
第5章 東南アジア農業開発の目的と目標
I 東南アジア農業開発における目的
II 東南アジア農業開発における目標
第6章 東南アジア農業開発の主体
I プランター
II 耕作農民
III 政府
第7章 東南アジア農業開発の条件
I 資本条件
II 社会経済的条件
III 技術的条件
IV 価格条件
V 交通条件
第8章 東南アジア農業開発と外国援助
I 低開発国にたいする外国援助
II 東南アジア農業開発にたいする外国援助
第9章 東南アジア農業開発における日本の役割
I 農業技術協力の重要性
II 農業技術協力の問題点
III 一次産品開発輸入の問題
補論 東南アジア農業開発の日本農業におよぼす影響
I 東南アジア農業開発の日本農業への影響の形態
II 東南アジア農業開発と日本農業保護主義

インドネシアの米(東南アジア研究叢書)
創文社オンデマンド叢書
農業の立ち遅れていたインドネシアの食料自給率を上げるために、1965年にビマス計画(食糧自給集団集約栽培計画)が開始された。インドネシア国民銀行は、農民にマイクロ・クレジットを与え、それを元手に、農民は種、肥料、農薬などの資材を供与し、政府の営農指導員が教育を行った。その成果により、米の増産が図られ、輸入量が減少した。その計画は、単なる増産にとどまらず、加工、調整、流通、農村開発も射程に入っていた。農業経済学の実例を記録した一冊である。
【目次より】
はしがき
序論 ビマス計画にかんする研究の過程と課題
1 研究の経過 ー 3 研究の目的と課題
第1章 インドネシア経済における米
1 インドネシアの経済安定と米 スハルト政権の米増産政策の直接的背景 2 インドネシア経済に占めるコメの重要性 スハルト政権の米増産政策の間接的背景
第2章 インドネシア米作の自然的基礎
1 インドネシアの位置・面積・地形 ー 3 インドネシアの地質および土壌
第3章 インドネシア農業の特質
1 インドネシア経済における農業の重要性 ー 7 家畜組制度
第4章 インドネシアの米の生産と流通
1 米の生産 2 米の流通と消費
第5章 スカルノ政権の経済開発計画と米増産計画
1 スカルノ政権下の米増産計画とスハルト政権下の米増産計画との関連 ー 6 ビマス計画
第6章 スハルト政権と米増産計画 ビマス計画の発展と「米危機」
1 ビマス計画の強化 ー 3 第1次開発5ヵ年計画と米増産計画
第7章 ビマス・ゴトンロヨン計画
1 ビマス・ゴトンロヨン計画の背景と動機 ー 6 ビマス・ゴトンロヨン計画の評価
第8章 改良ビマス計画
1 改良ビマス計画の背景 2 改良ビマス計画の発展
第9章 米増産計画の修正と第二の米危機
1 米増産計画の修正 2 第二の米危機と米増産目標の引上げ
第10章 ビマス計画の評価と教訓
1 岐路にたつビマス計画 ー 4 ビマス計画のありかた
第11章 インドネシア米増産の展望 農業の将来と関連して
1 至上命題としての米増産 ー 3 インドネシア米作の将来
補論 第2次開発5ヵ年計画と米増産
1 第2次開発5ヵ年計画 2 第2次開発5ヵ年計画における米の増産計画

日本のキリスト教
創文社オンデマンド叢書
神学者にして牧師の著者は、「神の痛みの神学」を提唱した。「神の痛み」とは、神が神の愛に反逆し、神にとって罪人となった人間に対して、神自身が怒りを自らに引き受け、その上で罪人を愛する神の愛のことである。また、著者は日本基督教団内部における、会派問題に対処したり、信仰告白の制定などにも貢献したことでも知られている。その著者による、日本のおけるキリスト教の存在と歴史の解説である。
【目次より】
I
日本のキリスト教
「日本の神学」ということ
II
『神の痛みの神学』について
「神の痛みの神学」をめぐる外と内
ヨーロッパ神学との対話のために
III
内村鑑三における「世界」と「日本」
小塩力著『高倉徳太郎伝』をめぐって
簡朴に静寂に重厚に 小塩力の神学
学生キリスト教運動(SCM)の歴史を回顧して
IV
エキュメニズムの理解
モントリオール通信
日本基督教団信仰告白について
宗教改革と日本基督教団
日本基督教団二十五年の歩み
教団二十五年
V
他宗教への態度
『維摩経義疏』の一節
日本の宗教哲学
田辺 元
田辺先生をしのぶ
田辺先生における師弟関係
VI
ヘブル書十一章三節についての一考案
キリスト論における苦難の問題
イエス・キリストの苦難と復活
キリスト教教育の神学的検討
山本新著『文明の構造と変動』について
『氷点』をめぐって
世俗の問題
発表年月

均衡理論の研究
創文社オンデマンド叢書
市場経済では,需要と供給が一致するように価格が決まるという前提に基づく理論。需要と供給が一致した状態が均衡である。ある産業や企業だけの均衡を扱うのが、「部分均衡論」である。市場のあらゆる財・サービスの均衡を扱うのが「一般均衡論」である。
【目次】
福岡正夫論文集刊行について
第1部 線型経済学の諸問題
完全雇用と固定的生産係数
柴田博士のカッセル批判をめぐって
カッセル一般均衡体系の再検討
線型経済学と伝統理論
投入産出モデルと市場機構
投入産出の不等式体系
動学的レオンチェフ体系における双対安定の非両立性について
ゲーム問題の若干の特殊な解法について
第2部 一般均衡理論の基礎をめぐって
均衡点存在問題の一考察
価格調整関数と存在定理 一つの注解
存在問題の再考察
安定条件と調整速度 一つの批判的覚書
ヒックス教授の需要理論
価格決定における需要の役割
均衡理論の進路
ケインズ経済学のミクロ理論的基礎 展望と評価
マクロ分析とミクロ分析
第3部 成長理論およびマクロ経済学
再生産表式と均衡成長
再生産表式モデルにおける双対安定性について
新古典派定理と2部門成長モデル
最適成長理論 展望
インフレーション理論の展望
貨幣的成長のケインズ・モデル
カルドアの成長理論
ケインズと現代経済理論
ケインズ経済学の現局面
あとがき
索引

イギリス革命思想史
創文社オンデマンド叢書
1642ー1649年に絶対王政を打倒すべく起こったのが、清教徒(ピューリタン)革命である。その当時の政治的主張は、国王派、議会派、中立派、盟約派、カトリック同盟など、さまざまな主張が入り乱れていた。本書では、革命に思想的バックボーンを与えた思想を明らかにする。
【目次より】
目次
はしがき
凡例
序説 ピューリタン革命の経済的背景
I 反独占運動の発展
[1] 王室独占の解体
[2] 自由貿易論の展開
[3] ギルド民主化運動
II 農業・土地問題
[1] 土地所有関係の変革
[2] 囲込みと農業改良思想
第一章 左翼民主主意義の成立 ジョン・リルバーンとレヴェラー運動
I 分析の視角
II リルバーンの思想的発展とその背景
III レヴェラー運動の展開とリルバーン
IV 『人民協約』の成立
V 『人民協約』の発展
VI レヴェラー運動の性格
第二章 社会主義ユートウピアの構想 ジェラード・ウィンスタンリとディガー運動
I 研究史的展望
II ウィンスタンリの神学的歴史・社会観の成立
III ディガー運動の実践へ
IV ユートウピアの構想とその特質
第三章 革命的無政府主義の先駆 第五王国思想の発展
I 問題の所在
II 「第五王国」思想の展開
III 第五王国派の成立
IV ジョン・ロジャーズの社会思想
V プロテクター政権と第五王国派
VI 第五王国派の性格
第四章 不服従運動とその思想 初期クェーカーの社会思想
I 問題の提起
II クェーカー主義の成立
III プロテクター政権とクェーカー運動
IV 「内なる光」と社会批判
V 初期クェーカーの社会思想
第五章 エピローグ 総括と展望

日本の方向(フォルミカ選書)
創文社オンデマンド叢書
戦後間もない1950年初期に、保守的な動きが強まった。当時は、敗戦の直後ということもあり社会主義的・民主的な思想が隆盛していた中で、保守的な思想が反動として復活したことに対し、日本の進むべき方向性を示した本書は、当時の日本の思想状況を知るための貴重な資料である。
【目次】
はしがき
第一部 民主主義のために
革命と道徳
革命と大学
革命と暴力
社会民主主義と国会の保守性
総選挙を顧みて
ひとごとではない
革命問答
反動問答
この数年間民主主義は日本において進歩しつつあるか
第二部 平和主義のために
民族主義と国際連帯主義
内乱
思想の争いは必らず戦争になるか
アメリカとソヴエトはどういうわけで協調できないのか
平和論争の盲点
私の愛国心
毛沢東と中国革命
日本・中国・ロシア

ロシヤ史入門
創文社オンデマンド叢書
ソヴィエト・ロシアは果たして天国なのか、地獄なのか?
ロシアの過去も現在もその賛美者と憎悪者の手によって甚だしく否曲されている。非科学的な感情論でなく、隣国ロシアを正しく理解することこそ、我々日本人に課せられた刻下の急務といいえよう。(原本帯より)
862年にノブゴロドにリューリクが都市を築き、882年にノブゴロド公国のオレグがキエフを征服し、キエフ大公国となった。988年には、ウラジーミル1世が東方正教会のキリスト教を受け入れ、スラヴ文化との統合を目指した。13世紀のモンゴルの侵攻による崩壊、16世紀のロシアツァーリ国建国、ロマノフ朝のロシア帝国成立、18から19世紀の拡大、ナポレオン戦争での勝利を経て、1917年のソヴィエト連邦の誕生までをまとめた格好の入門書。
【目次】
はしがき
第一章 キエフ時代
第二章 モスクワ時代
一 モスクワ公国の台頭
二 イワン三世
三 イワン四世(雷帝)
四 『混乱』
五 ピョートルまでのロマノフ王朝
第三章 ペテルブルク時代
一 ピョートル大帝
二 エカチェリーナ女帝(二世)
三 ツァーリズムの崩壊
四 ソヴエト政権の成立
ロシヤ史主要参考書
系譜
ロシヤ史年表

浅野順一著作集9:説教II
創文社オンデマンド叢書
牧師にして神学者の著者・浅野順一「著作集」全11巻の第9巻「説教2」。
【目次より】
《時は縮まる 「ローマ人への手紙」から》
まえがき
福音を恥とせず
神の慈愛と忍耐と寛容の富
かくれたユダヤ人
行ないの法則か信仰の法則か
信仰者は勝利する
約束の子孫
怒りの器、憐れみの器 神の選びについて
麗しき足
恵みの選び
時は迫る
誇りうる奉仕
甘言と美辞か、苦言と警句か
その根本のもの
神の義の新しき誕生
《人はひとりである 時代に対する一伝道者の告白》
偽り者の復活
低きに止まるな
汝、殺すなかれ
予言者の苦悩
勝つ者は神のみ
真理の霊と迷いの霊
神に栄光、人に平和
閉ざされた耳 対話なき世界
神は心を探り、思いを試みる
途中を歩む
主の神殿 愛国心とは何か
神の息と枯れたる骨
新しき酒・古き皮袋
石の心と肉の心
人はひとりである
あとがき
解説 雨宮栄一

浅野順一著作集8:ヨブ記研究・法の神学
創文社オンデマンド叢書
牧師にして神学者の著者・浅野順一「著作集」全11巻の第8巻「ヨブ記研究・法の神学」。
【目次】
《ヨブ記の研究》
まえがき
序説 予言者との対比
実存 その解釈
プロローグ ヨブの試練
生と死 人間の身体
論争 ヨブと友人
「贖う者」 キリスト
知恵の賛歌
説教 エリフ
自然 人間との関係
懺悔 その意味
エピローグ ヨブの回復
法と知恵と実存
信仰に何の益があるか ヨブの苦しみが示すもの
《知恵文学小論》
知恵文学
ユダヤ人の虚無感と日本人の無常観 伝道の書と徒然草との対比
《法の神学小論》
旧約聖書神学の意義
旧約聖書に於ける法の神学
申命記の一断面
解説 西村俊昭 木田献一

浅野順一著作集7:予言者研究III
創文社オンデマンド叢書
牧師にして神学者の著者・浅野順一「著作集」全11巻の第7巻「予言言者研究3」。
【目次より】
《イスラエル予言者の神学》
まえがき
序論
第一部 歴史
第一章 言
一 言の語義
二 言の歴史
三 言と自然
四 律法的な言と予言者的な言
第二章 時
一 「時」と「日」
一 「時」の意義
二 「日」殊に「ヤーウェの日」
二 時と永遠
一 「永遠」
二 過去・現在・未来
第三章 契約
一 契約の語義
二 予言者と契約
三 契約と旧約聖書
四 「新しき契約」
第四章 選び
一 恵みの選び
二 神と民
三 個人の選び
四 残れる者
五 異邦人の選び
六 結語
第五章 歴史
一 旧約聖書と歴史
二 歴史の意義
三 契約と歴史
四 歴史と予言者
第六章 終末
一 審判
一 律法と審判
二 「ヤーウェの日」
三 審判と救拯
二 回心
一 回心の語義
二 補囚前の予言者
三 補囚及びその後の予言者
第二部 祭儀と文化
第一章 祭儀 予言者との関係について
一 問題の所在
二 歴史的関係
三 儀式殊に犠牲
四 根本的相違
第二章 伝道
一 問題の提出
二 特殊より普遍へ
三 「主の僕」
四 苦難と伝道
五 結語
第三章 文化
一 遊牧生活とヤーウェ信仰
二 文化批判の原理としてのヤーウェ信仰
三 文化のヤーウェ化
四 結語
第四章 政治 旧約の王権を主として
一 イスラエルの王国
二 予言者と国家
三 結語
第五章 平和
一 旧約聖書と戦争
二 予言者と戦争
三 「平和」の意義
第三部 体験
一 予言者の語義及び起源
二 神の言
三 神の霊
四 幻
五 真の予言者と偽りの予言者
六 祈祷 主としてエレミヤについて
七 召命
略記号
参考文献
解説 木田献一

浅野順一著作集6:旧約神学研究II
創文社オンデマンド叢書
牧師にして神学者の著者・浅野順一「著作集」全11巻の第6巻「旧約神学研究2」。
【目次より】
目次
《旧約聖書の倫理》
序
旧約聖書の倫理
一 序言
二 契約と倫理
三 旧約倫理の団体的性格
四 予言者と社会及び国家
五 律法と神の義
六 罪・死・福祉
七 結語
旧約聖書に於ける神の義
一 義の意義
二 神の義
三 神の義と契約
旧約聖書に於ける死と生
一 序言 生死の意義
二 陰府の観念
三 死と身体
四 永生信仰の条件
五 死の克服 復活
六 神との交わり 永生
七 結語
イスラエル精神史概説
一 序言
二 父祖の時代
三 出エジプトとモーセ
四 カナン侵入と定住
五 王国の建設とその分裂
六 予言者の宗教
七 捕囚前の予言者
八 捕囚後の精神生活
九 律法と詩歌と知恵
十 結語
《苦難と虚無》
苦難と虚無
旧約聖書に於ける苦難
一 序言
二 苦難と審判
三 問題提出 エレミヤ
四 問題把握 ヨブ
五 問題解決 主の僕
六 苦難と死
七 結語
ヨブ記に於ける苦難と人間
一 序言
二 問題の所在
三 試練
四 問題の解決
五 結語
旧約聖書に於ける虚無思想 伝道の書を中心として
一 序論
二 本論(その一)
三 本論(その二)
四 結論
予言者エレミヤとその祈り
一 エレミヤの苦悩
二 予言者と祈り
エレミヤ哀歌(第三章講解)
望みある嘆き エレミヤ哀歌三・一―二一
静かに待つ エレミヤ哀歌三・二二―二八
手と共に心を エレミヤ哀歌三・二九―四一
深き穴の底より エレミヤ哀歌三・四二―五八
正しき審判 エレミヤ哀歌三・五九―六六
エレミヤ哀歌について
あとがき
《時論(一九四五年―一九六一年)》
権力と権威
真実ということ
平和祈願の動機
平和の君の誕生
「平和の問題に関して」を読みて
平和ならしむる者
共産主義国家と基督教
日本伝道の根本問題
日本と伝道 年頭の所感
これからのキリスト教
レーニンか聖書か
イスラエルの精神と今日の世界
政治家の慎重をのぞむ
重大なこと
静かなデモ
時局について基督者として感じたこと
政治の世界に於ける予言者の論理と倫理
素朴単純な血の声 私と愛国心
解説 西村俊昭 雨宮栄一

浅野順一著作集5:説教I
創文社オンデマンド叢書
牧師にして神学者の著者・浅野順一「著作集」全11巻の第5巻「説教1」。
【目次より】
《反省と出発》
第一部
省みて
神は唯一 モーセの第一誡
然りと否
撃ちて医す神
新しき夢
青年と召命
悪に勝つ善
信仰と個性
イエス一人の他
信仰者の戦い
世界と自己
神の安居処
第二部
旧約聖書より見たる民主主義
旧約聖書に於けるヒューマニズム
旧約学者エー・ビー・デビドソン
あとがき
《真実 予言者エレミヤ》
主の言葉 エレミヤ書一ノ一、二
聖別 エレミヤ書一ノ五
はじめの愛 エレミヤ書二ノ二
水 エレミヤ書二ノ一三
我々の自由 エレミヤ書二ノ三一
新田を耕せ エレミヤ書四ノ三
真実を求める一人 エレミヤ書五ノ一
別れ道 エレミヤ書六ノ一六
主の神殿 エレミヤ書七ノ四
知恵と真実 エレミヤ書八ノ八
神の真偽 エレミヤ書一〇ノ八、一〇
イスラエルの望みなる王 エレミヤ書一四ノ八
一心をもって エレミヤ書二九ノ一三、一四
神の口 エレミヤ書一五ノ一九
偽りなき心 エレミヤ書一七ノ九、一〇
神に欺かれた人 エレミヤ書二〇ノ七
愛と真実の神 エレミヤ書三一ノ三
良き無花果、悪しき無花果 エレミヤ書二四ノ一、二
健康と医しとを エレミヤ書三三ノ六
新しき契約 エレミヤ書三一ノ三一、三二
クリスマスと旧約の予言者 エレミヤを中心として
旧約予言者の愛国・平和の思想 エレミヤにおける「真実」ということ
あとがき
《新しき国 新しき教会 新中国に使いして》
はしがき
I
新しき国、新しき教会
中国教会に使して
中国の教会と宣教師問題
中国の教会と日本の教会
II
素朴健全な学生生活
朝の西湖
中国人の手
顔
附論 中国の教会と日本の教会との交わり
解説 戦後民主主義と浅野順一 伊藤虎丸