講談社学術文庫作品一覧

執権 北条氏と鎌倉幕府
講談社学術文庫
【2022年NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」 主演小栗旬が演じる北条義時のことがよくわかる!】
北条氏はなぜ将軍にならなかったのか。
なぜ鎌倉武士たちはあれほどに抗争を繰り返したのか。
執権政治、得宗専制を成立せしめた論理と政治構造とは。
承久の乱を制し、執権への権力集中を成し遂げた義時と、蒙古侵略による危機の中、得宗による独裁体制を築いた時宗。
この二人を軸にして、これまでになく明快に鎌倉幕府の政治史を見通す画期的論考!
【本書より】
・鎌倉北条氏は、そもそもどのような家であったのか。
・「得宗」とは、いったいどういう意味なのか。
・これは事実自体がほとんど知られていないが、鎌倉将軍には実は四人目の源氏将軍が存在した。第七代将軍源惟康がその人である。鎌倉幕府が空前の強敵蒙古帝国と対峙したこの時期、なぜ鎌倉幕府は源氏の将軍を戴いていたのであろうか。
―これらの問題を追究するためには、どのような方法が有効なのであろうか。
まず、鎌倉幕府の通史や北条氏歴代の伝記を書くつもりはない。なぜならば、この本は北条氏という「一族の物語」ではなく、「一族の物語」の底を流れる「基調低音」を書くことが目的だと思うからである。表面的に幕府や北条氏の歴史をなぞっても、我々が求める答には辿り着けないはずである。
そこで私は鎌倉北条氏歴代のなかからキー・マンとして二人の「執権」を選んだ。承久の乱で仲恭天皇を廃位し後鳥羽・土御門・順徳の三上皇を配流(流刑)した「究極の朝敵」、第二代執権北条義時と、蒙古帝国の侵略を撃退した「救国の英雄」第八代執権、北条時宗である。
世間一般の評価に極端な隔りのあるこの高祖父(ひいひいおじいさん)と玄孫(ひいひいまご)の人生に注目することにより、答に迫りたいと考える。
この試みが成功し、見事、解答に至れるかどうかは、わからない。「とりあえず付き合ってやるか?」と思った読者と共に旅に出るとしよう。
【本書の内容】
はじめに―素朴な疑問
第一章 北条氏という家
第二章 江間小四郎義時の軌跡―伝説が意味するもの
第三章 相模太郎時宗の自画像―内戦が意味するもの
第四章 辺境の独裁者―四人目の源氏将軍が意味するもの
第五章 カリスマ去って後
おわりに―胎蔵せしもの
※本書は2011年に講談社選書メチエより刊行された『北条氏と鎌倉幕府』を原本としています。

天皇陵 「聖域」の歴史学
講談社学術文庫
今年7月、大阪府の「百舌鳥・古市古墳群」が日本で23件目のユネスコ世界遺産に指定された。しかし、この世界遺産を構成する古墳の多くは、その被葬者さえ特定されていない。最大規模を誇る仁徳天皇陵や、履中天皇陵、允恭天皇陵などには、本当にその天皇が眠っているのだろうか。天皇陵は、いつ、どのように定められ、管理されているのか、近世・近代史を専門とする著者が、「天皇陵の歴史」と問題点を解き明かす。
江戸時代後期、各地の古墳を独自に探査した蒲生君平。幕末期、尊王思想の高まりの中で、陵墓の比定と修補を願い出た宇都宮の藩主・戸田忠至。こうした近世の研究成果の上で、明治政府は、全天皇と皇族の陵墓を決定していった。神話に語られる天皇の実在を「証明」するためにも、墓の確定は欠かせなかったからである。神武天皇陵や仁徳天皇陵はどのように決められたのか、明治天皇陵はなぜ京都にあるのか、大正天皇陵の参拝に大混雑した鉄道と町、昭和初年に新たに皇統に列せられた南朝第3代の長慶天皇の陵はどう探したのか、さらに天皇陵の祭祀の場としての意味、著者が発見した資料「陵墓参考地一覧」からわかること――など、あらゆる論点から天皇陵を検証し、今後の科学的・考古学的調査の必要性を訴える。
〔原本:『天皇陵論―聖域か文化財か―』 新人物往来社、2007年刊〕

菩薩 由来と信仰の歴史
講談社学術文庫
観音菩薩をはじめ、弥勒菩薩、文殊菩薩、地蔵菩薩、日光・月光菩薩・・・などなど、様々な姿で親しまれ、信仰の対象となっている菩薩とは、いったいなにか。それぞれの名前の由来や、役割と利益、形像の特徴、日本への伝来と信仰の歴史などを分かりやすく解説する。
菩薩とは、サンスクリット語のボーディ=サットバに由来し、「悟りを求める人」という意味を持つ。それも、ただ自分中心の修行ではなく、仏の慈悲行を通して一切衆生を救おうとする、大乗仏教の理想的修行者像を意味する。最初は釈迦菩薩だけだったのが、大乗仏教の発展の中で、弥勒、観音、勢至・・・など「十方世界」に多くの菩薩が修行につとめていると考えられるようになったという。なかでも観音菩薩は、ヒンドゥー教の影響も受けて、十一面、千手千眼、馬頭など、多様な変化観音に分化し、その性格や利益をそれぞれに示している。
写真や図版、イラストをまじえて、20以上におよぶ各尊の特徴も示した、仏教学の入門書。仏像鑑賞の手引きにも最適。
〔原本:『菩薩―仏教学入門―』 東京美術、1982年刊〕

東京のヤミ市
講談社学術文庫
新宿、渋谷、新橋、池袋、上野……焼け跡となった街に、ふたたび人とモノがあつまり、立ち上げられたマーケット。「戦後東京」の原風景を形づくったと語られ、いまや歴史の中に霞みつつあるヤミ市とは、いったい何だったのか。
食べるものも着るものも「あるべきところにあるべきものがない」敗戦直後、人々は統制経済の網の目をかいくぐり、生きるための商いを、そこで営んだ。ゴザの上に芋を並べた露店は、やがて電気ガス水道をそなえた商店となり、カストリと焼き鳥の飲み屋ができ、ありとあらゆる雑貨が流れ込んでゆく。そうして日々の暮らしを立て直そうとする庶民たちの「復興」は、テキ屋たちのプロデュースにより加速され、巨大な盛り場を生み出していった。
丹念なフィールドワークにより都市生活文化の探究を続けてきた著者が、ヤミ市のリアルな姿を蘇らせる!
【本書の内容】
第一章 望遠レンズでみるヤミ市
バルーンに乗って一九四七年の東京探訪/新宿はヤミ市のターミナル/渋谷―エネルギッシュな三角地帯/新橋―巨大な呑み屋街/銀座・有楽町―ヤミ市のできない都心/上野広小路―アメ横の母体/池袋―ボランタリーチェーンの理想と現実
第二章 覗きこむヤミ市
ヤミ市建築の変化―ヨシズ・バラック・マーケット/ヤミ市の地域・建築設計―新宿/ヤミ市建築の豪華版―新橋「新生マーケット」/ヤミ市の店舗建築とディスプレイ1―昼のマーケット/ヤミ市の店舗建築とディスプレイ2―バラック長屋の飲食店街/ヤミ市の店舗建築とディスプレイ3―三階建ての夜の街/インフラストラクチャーの構築
第三章 ヤミ市にひしめく人びと
第一世代の出自/初期ヤミ市商人からの脱却/ヤミ市地下活動へ/ヤミのプロ商人/ヤミ市を生き抜く
第四章 ヤミ市料理のレシピ
「国際的なメニュー」の登場―配給では食べられない時代/洋食編/韓国・朝鮮料理編/和食編/中華料理編/ドリンク編/デザート編
第五章 太陽の下のヤミ市
ブティック/荒物屋/日用雑貨・化粧品屋/パチンコ屋/生鮮食料品店/電気器具店
第六章 新宿ヤミ市・夜のシナリオ
夜のマーケット・それぞれの風景/酒場の作法
第七章 焼け跡再興のプロデューサー
テキ屋と焼け跡商売/「組」型経営管理法/東京のカポネ/土地をめぐるヤミ市の論理
第八章 ヤミ市の生活文化論
ヤミ市文化の闇/ヤミ市の生んだ食文化/ヤミ市パチンコ屋を逆照射する/カラオケと軍歌の相似性/ヤミ市の時代を駆け抜けて
主要参考文献
ヤミ市年表
ヤミ市キーワード集

平治物語 全訳注
講談社学術文庫
壊滅的な打撃を受けた源氏とこの世の春を謳歌する平氏――。やがて『平家物語』へとつづく、一族の明暗を分かつことになった平治の乱を題材にした『平治物語』の諸本のうち、劇的に構成された合戦や、個性を際立たせた巧みな人物造形が、流麗な文体によって描き出される四類本は、「もっとも面白い『平治物語』」と言われる。この四類本を底本に、本文と現代語訳に加え、校訂注、読解の助けとなる語釈と解説、補注も充実した、物語世界の隅々まで楽しめる一冊。
悪源太義平がわずか17騎で、500騎の平氏を蹴散らす痛快な合戦、牛若丸ら幼い息子を必死で守ろうとする常葉の哀切、そして運命の子頼朝……。個性豊かな登場人物が縦横無尽に躍動する合戦絵巻、いざ開幕!
時は平安時代の末、のちに「武者の世」の始まりと評された保元の乱から三年後、平治元年(1159)に平治の乱は勃発する。上皇・天皇の近臣同士の争いに端を発する政治闘争は、待賢門と六波羅での源平両軍の激突となって噴出した。その結果、源氏の棟梁である源義朝が敗走。東国へと落ち延びる途中で討たれ、子息たちも命を落とし、源氏は壊滅的な打撃を受ける。一方、見事勝者となった平清盛はこの世の春を迎え、それぞれの一族の明暗が決定的に分かれることになった――。
『平家物語』の舞台を用意したともいえる平治の乱を題材とした軍記物語、『平治物語』。時代を越えて語り継がれるうちに、筋立てが異なる異本が複数存在することもこの物語の大きな特色の一つである。そのなかでも、本書が底本とした「四類本」は、劇的に構成された合戦や、個性を際立たせた巧みな人物造形が、流麗な文体によって描き出される「もっとも面白い『平治物語』」になっている。本文と現代語訳に加え、校訂注、読解の助けとなる語釈と解説、補注も充実した、物語世界の隅々まで楽しめる。
義朝の息子、悪源太義平がわずか17騎で、500騎の平氏を蹴散らす痛快な合戦、義平とは対照的に不甲斐なくて滑稽な藤原信頼、牛若丸ら幼い息子を必死で守ろうとする常葉の哀切、そして運命の子頼朝の姿……。個性豊かな登場人物が縦横無尽に躍動する合戦絵巻、いざ開幕!

西洋占星術史 科学と魔術のあいだ
講談社学術文庫
「○○座生まれのあなたは……」などと始まる「星占い」――雑誌やテレビはもちろん、ネット上でも頻繁に見かけるおなじみの存在ですが、「○○座生まれ」というのはどういうことか、ちゃんと説明できる人は実はそう多くないでしょう。ましてや、星占いはいつ誕生したのか、はじめから今見るようなものだったのか、といった問いに答えられる人となると、もっと少ないに違いありません。
本書は、科学や科学技術の歴史に詳しい専門家が誰にでも分かるように、そして面白く読めるように占星術の歴史をコンパクトにまとめた1冊です。
占星術を生み出したのは、現在のバクダット南方に位置するバビロニアで紀元前9世紀頃から勢力を伸ばしたカルデア人でした。天文学に長けていたカルデア人は、日蝕や月蝕、彗星の出現などを地上に起きることの前兆として捉え、将来訪れる災厄を予言する技法として、占星術を開発したのです。この技法が、のちの紀元前4世紀に登場したアレキサンダー大王がバビロニアを征服したことをきっかけにしてギリシア世界に流入し、さらに古代ローマに継承されていくのが「西洋占星術」の発展につながっていきます。当初はもっぱら天下国家の運命を対象にしていた占星術は、やがて個人の運命を占うようになりました。個人といっても、はじめは皇帝や王だけがその恩恵にこうむることができましたが、時代が進むにつれて、一般の人たちも自分の運命を知るために占星術にアクセスするようになったのです。
当代随一の占星術師である鏡リュウジ氏が解説を書き下ろしたこの文庫版を手にすれば、何気なく触れてきた「星占い」も、ぐっと深みを帯びて、まったく違う魅力的なものに見えてくること間違いなし、です!
[本書の内容]
1 カルデアの知恵
2 ギリシャ人の科学
3 ホロスコープの技術
4 「占星社会」ローマ
5 ルネサンスの大論争
6 近代科学からの脱落
7 現代を生きる占星術
あとがき
解 説 鏡リュウジ

音楽の理論
講談社学術文庫
なぜベートヴェン「田園」は穏やかな感興をもたらすのか。
バッハの紡いだ旋律の根幹とはいかなるものか。
日本のクラシック音楽評論の泰斗が、楽曲をより深く愉しむための「楽理」を詳らかにし、
バロック以前から無調・多調音楽まで三七五もの名曲の譜例を採り、和声・リズム・旋律・対位法・形式・転調の真髄を説く。
空前絶後の音楽理論書!
-----------------------------------------
本書は和声とか対位法とか音楽形式とかの寄せ集めではなく、一つの体系的な音楽理論であって、その中に和声や対位法や音楽形式、そしてさらに旋律とリズム編までも含んでいるのである。その中心となる観点は、私が音楽史と音楽美学の研究から得た私自身のものである。──本書より
-----------------------------------------
【本書の内容】
第1部 基礎の理論
第2部 和声の理論
第3部 転調の理論
第4部 リズムと旋律の理論
第5部 対位法の理論
第6部 形式の理論

歌舞伎十八番集
講談社学術文庫
天保三年、市村座において七代目市川團十郎が4度目の『助六』を上演する際に「市川海老蔵流寿狂言十八番の内」と銘記したのに始まる歌舞伎十八番。以来、三百年にわたり庶民の人気を博してきた『鳴神』『暫』『勧進帳』『景清』『毛抜』などの原作脚本に、古典演劇研究の泰斗が詳細な註釈をつけた歌舞伎ファン待望の鑑賞ガイド。歌舞伎を深く味わうための必携の書。
毎日のように人気の歌舞伎役者がマスコミに登場する空前の歌舞伎ブーム。なかでも十三代目市川團十郎襲名で注目されるのが市川家代々の当たり狂言十八種目。いわゆる「歌舞伎十八番」は、天保3年(1832)3月、市村座において七代目市川團十郎が四度目の『助六』を上演する際に「市川海老蔵流寿狂言十八番の内」と銘記したのに始まる。本書では人気演目の『勧進帳』『助六』『暫(しばらく)』『景清』『毛抜』『鳴神』『外郎売』などの解題と、江戸時代以来の台本をもとに校訂した脚本に懇切な註釈をつけて歌舞伎研究の泰斗が解説。歌舞伎原作の魅力を堪能できる歌舞伎鑑賞手引きの決定版である。
原本:『評釈江戸文学叢書 歌舞伎名作集』(下巻)
〈内容〉
1 歌舞伎十八番解題
●歌舞伎十八番の意義
●演目とその由来
不破/鳴神/暫/不動/うわなり/象引/
勧進帳/助六/押戻/外郎売/矢の根/関羽/
景清/七つ面/毛抜/解脱/蛇柳/鎌髭
●人気演目の成立とあらすじ
『勧進帳』/『景清』/『矢の根』/『毛抜』
『鳴神』/『暫』/『助六』
2 歌舞伎十八番原作脚本と詳細註釈
●『勧進帳』
●『景清』
●『矢の根』
●『毛抜』
●『鳴神』
●『暫』
●『助六所縁江戸桜』
3 付録
●『暫』のせりふ・つらね集
●『外郎売』のせりふ
4 解説
児玉竜一・早稲田大学教授、演劇博物館副館長
「河竹繁俊と歌舞伎十八番集」
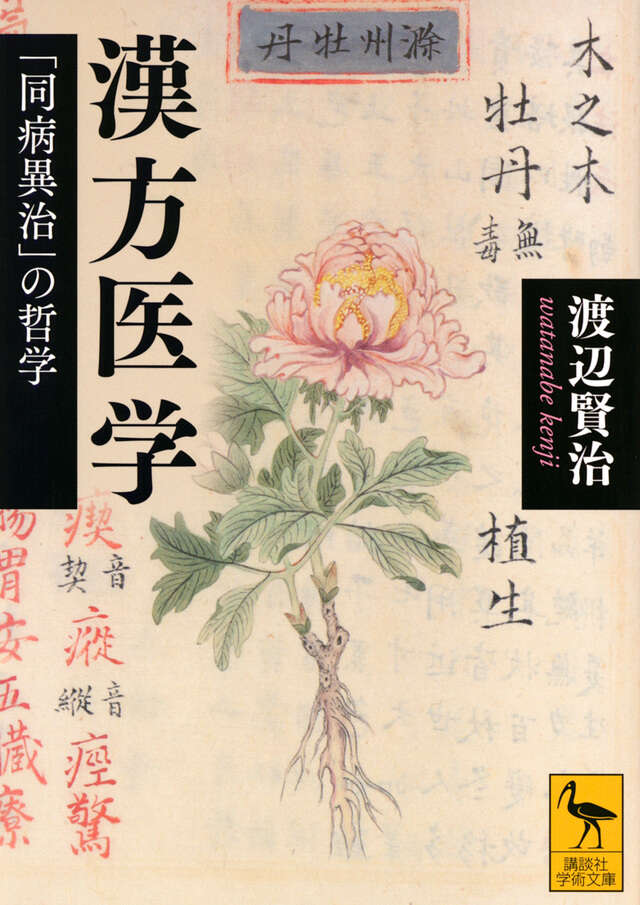
漢方医学 「同病異治」の哲学
講談社学術文庫
江戸時代に吉益東洞(一七〇二-一七七三)が礎をつくり、華岡青洲(一七六〇-一八三五)が西洋医学と融合させ、独自の進化を遂げた日本漢方医学。同じ病でも人次第で治療が変わる「同病異治」の哲学とは何か? 高齢化社会で多病を抱える患者への対応、200種を超える生薬を組み合わせ、がん治療の補助療法としての期待も高まる今、病との付き合い方を変える、東洋思想医学の可能性を考察する。
漢方では関節リウマチであっても一人一人、また昨日と今日ではその性質が違うと考える。こうした極めて東洋的な考え方は、これからの医療を考える上で重要であろう。西洋の文化が直線的で四角定規であるのに対し東洋の文化は曲線であり、円である。わが国が担うべきは、単に薬という物質的なものだけでなく、文化的・精神的な考え方もひっくるめた、真の東西医学の融合ではないだろうか――「まえがき」より
本書は2013年、講談社選書メチエより『漢方医学』の題名で刊行されました。

金魚と日本人
講談社学術文庫
1502年(文亀2年)、室町時代中期に中国から初上陸。元禄江戸で大ブームを起こして以来、金魚は日本人に愛され続けてきました。
しかし、いったいなぜ、欧米ではさほど流行らなかった金魚が、本家・中国をしのぐ勢いで、日本では深く広く浸透したのでしょうか。そもそも日本の金魚のルーツはどこにあるのか。当時の日本社会は、金魚をどう受け止めたのか・・・・・・。
金魚の飼い方や品種の解説ではなく、金魚と日本人の500年の歴史を、豊富な史料から検証。日本人の自然観や社会観を、金魚を通して考察します。
本書の原本は、一九九七年に三一書房より刊行されました。

方言の地図帳
講談社学術文庫
ゴミは、「なげる」? 「ほかす」? 「うっちゃる」?
「明後日の次の日」、あなたの町では「やのあさって」?「しあさって」?
全国2400箇所の調査記録をもとにした「お国言葉」の一大パノラマ。
さまざまな方言が列島に広がるさまを地図に表すと、そこから日本語の豊穣な世界が見えてくる!
辞典としても使えて方言の基礎知識も満載!
国立国語研究所が総力を傾けて製作した『日本方言地図』をもとに、言葉がいかに伝播し、姿を変え、生成していくのかを描き出す。懐かしい言葉の記録でもあり、日本の長い歴史の探究でもあり、あたらな言葉の動態を探る探究でもある、無二の地図帳。
「方言は日本人の心のふるさとであると同時に、日本語に新たな活力を与えるエネルギー源でもある。共通語は周囲の方言を吸収しつつ成長を続けてきた」(本書より)
【本書の内容】
第I部 自然
第II部 人間と生活
第III部 動植物
音韻編
方言の基礎知識

中世ヨーロッパの結婚と家族
講談社学術文庫
学術文庫ですでに、『中世ヨーロッパの城の生活』、『中世ヨーロッパの都市の生活』、『中世ヨーロッパの農村の生活』、『大聖堂・製鉄・水車』、『中世ヨーロッパの家族』、『中世ヨーロッパの騎士』が好評を博している、ギースの「中世ヨーロッパシリーズ」の7冊目。本作では、人間の社会を構成する最も基本的な単位、「家族」と、その核心をなす「結婚」から、中世の社会史を掘り下げる。初訳。
古今のあらゆる社会において、「家族」は、人が食べ、学び、経済生活を送る普遍的な場であったが、同時に、常に変化し続けるものでもあった。今日の家族は、ヨーロッパ中世が生み出した歴史の産物なのである。
古代には、貴族の一夫多妻は当然であり、ローマ時代の「ファミリア」は、血族だけでなく奴隷や召使いをも含んでいた。中世の1000年間に、「解消不能な一夫一婦制」という原則はどのように定着し、「夫婦と子どもたちが一つの家に住む」という家族観はなぜ生まれたのか。14世紀の大災厄、黒死病以降に、家族のあり方や、子どもへの接し方はどう変わったのか。貴族や中流階級、農民や職人など、様々な人々の「結婚」と「家族」の進化の道筋を丹念に描く。
[原著:Frances and Joseph Gies, Marriage and the Family in the Middle Ages,1987 ]
目次
第一部 起源
第一章 歴史家、家族を発見
第二章 原点――ローマ人、ゲルマン人、キリスト教
第二部 中世前期
第三章 ヨーロッパの家族――五〇〇―七〇〇年
第四章 カロリング朝時代
第五章 アングロ・サクソン時代のイングランド
第三部 中世盛期
第六章 十一世紀の家族革命
第七章 十二世紀――新しいモデル
第八章 黒死病以前の農民たち――一二〇〇―一三四七年
第九章 貴族の系譜――長子相続がもたらす危機
第一〇章 中世の子どもたち
第四部 中世後期
第一一章 黒死病の影響
第一二章 中世後期の農民の家族――一三五〇―一五〇〇年
第一三章 イングランドの土地持ち紳士階級の家族
第一四章 十五世紀のフィレンツェ――商人の家族
第五部 中世末期 中世の終わり
第一五章 遺産
訳者あとがき

アイヌの世界観 「ことば」から読む自然と宇宙
講談社学術文庫
動植物を神格化し、自然も神も人も、すべては平等である――! アトゥイ(海)、アペ(火)、コロ(支配)、カラ(創造する)、ウク(受取る)・・・・・・。驚くべき自然観察者であるアイヌ。その、名付けの意味、語源、語彙素構成や使用法を丹念に拾いながら、彼らの宇宙観、霊魂観、動植物観を言語学的に分析。認識人類学的アプローチで、”アイヌ文化”を旅します。
本書は1994年から長らく講談社選書メチエの一冊として刊行されてきました。今回、学術文庫に収録するにあたり、補章として「現代に生き続けるアイヌの世界観」を追加しています。
*コ「ロ」、カ「ラ」、ウ「ク」=「 」内字は小文字です
目次
プロローグ
第一章 アイヌの宇宙観
1 モシリ(世界)
2 アイヌ・モシリ(人間の世界)の誕生
3 カムイ・モシリ(神々の世界)
4 ポクナ・モシリ(下方の世界)
5 アイヌの他界観
6 相補二元的宇宙観
第二章 霊魂とカムイ
1 霊魂の観念
2 カムイの概念
3 語彙素構成からみる神性の認識
4 人間的なカムイ像
5 カムイとジェンダー
6 人間との関係
第三章 アイヌの植物命名法
1 植物名が語る認識のプロセス
2 基本名からみる命名のプロセス
3 対照名からみる命名のプロセス
4 類別的認識
5 植物観と神格化
第四章 動物の分類と動物観
1 動物の個別名と包括名
2 個別化の原理
3 類別カテゴリーの外延
4 類別化の原理
5 動物分類と空間分類の連繋
6 動物のシンボリズムと神格化の基盤
第五章 諸民族との比較
1 日本上代における世界観との比較
2 北方諸民族における世界観
3 アイヌの世界観
第六章 世界観の探究――認識人類学的アプローチ
1 言語と文化
2 イーミックな観点とエスノ・サイエンス
3 「もの」の名称から認識の体系へ
4 象徴体系としての世界観
5 メタファーとしての動物
6 言語の象徴表現と世界観
7 認識人類学の意義
補章 現代に生き続けるアイヌの世界観
あとがき
学術文庫版あとがき
索引

神主と村の民俗誌
講談社学術文庫
氏神から産土神、株神を祀る。集落や同族、一家で神々を招くたびに役割を果たす神主の仕事とは? 祈祷・祭りと村の暮らしを描く。

箴言集
講談社学術文庫
われわれの美徳とは、偽装された悪徳にほかならない――
17世紀フランスの激動を生き抜いた公爵にしてモラリストが、人間の本性を見事に言い表した「箴言」。
鋭敏な洞察と強靱な思考、そして豊かなユーモアによって紡ぎ出された一行が、神からの自立を果たした近代人の抱える「自己愛」という宿命を撃ち抜き、さらには現代のわたしたちの心に深く刺さる。原文が醸す空気までをも伝える新訳。
【訳者まえがきより】
彼の人間を見る目、そして自分自身を見る目は鋭く、個人的体験のいかんにかかわらず、神からの自立をとげ、人間中心主義を標榜する近代人の本質、本性を早くから見抜いていたと思われる。彼は、自分自身、そして自分の個人的運命さえも客観視できるだけの強靱な精神、心の余裕、ユーモアさえ備えており、だからこそ、彼の人間観察は現代にも通用する普遍性を獲得しているのである。
【主な内容】
書肆から読者へ
道徳的考察
削除された箴言
没後収録の箴言
さまざまな考察
ラ・ロシュフコー自画像

戦国時代
講談社学術文庫
大名はいかに戦ったか。
民衆はいかに生き抜いたか。
日本はいかに変容したか。
戦後日本史学の巨人が、戦国時代というものの全体像を描き出した決定的論考。
戦国大名たちはいかに統治し戦ったか。人々はいかにして戦乱の時代を生きたか。新技術によって木綿や鉄砲が普及し何が変わったか。
後北条氏の台頭から豊臣政権まで、時代の全体像と動因を、明晰かつ生き生きと描き出す!
―四つの「時代を見る目」で読み解く―
第一に、群雄だけでなく全社会層の動き構造的にとらえる。
第二に、動乱のもたらす社会変動を、もっとも深奥から考える。
第三に、革新と創造の時代として描く。
第四に、世界史的な視野の中で見通す。
解説(本郷和人・東京大学史料編纂所教授)より―
永原の研究成果は、対峙する人間を選ばない。どんな立場から歴史を研究するにせよ、それが実証的であれば必ず、彼の到達に直面する必要に迫られる性質のものである。研究者は永原の提示した推論に学ぶ。それを学んで、乗り越えるべく努力を重ねていく。ある研究者は、努力の末に、永原論のある部分を乗り越えることに成功するだろう。ある研究者は懸命に挑戦しても、永原論の確かさを追認するだけにとどまるだろう。ともあれ、彼の研究業績は、後からやってくる研究者のチャレンジを静かに待っている。乗り越えられることを待っている。この意味で永原は実にフェアーで、尊敬すべき先達なのだ。中世史の良心というべき偉大な研究者、それが永原である。
※2000年刊『戦国時代 16世紀、日本はどう変わったのか』(小学館ライブラリー)上下巻の合本復刊
【主な内容】
戦国時代の開幕
惣・一揆と下克上の社会状況
「世界史」の成立と新技術
関東・東北の争覇戦
中国・四国の戦い
軍事力の構成
領国経済体制
都市と商人
九州の情勢とキリシタン大名
畿内政権と京・堺
大名国家と日本国
織田信長の進出
一向一揆と本願寺
「天下布武」

満鉄全史 「国策会社」の全貌
講談社学術文庫
明治40年(1907)、「10万の生霊と20億の戦費」といわれる犠牲を払って獲得した南満洲の地に誕生した一鉄道会社は、「陽に鉄道経営の仮面を装い、陰に百般の施設を実行する」実質的な国家機関として大陸政策を牽引した。しかし必然的に政官軍の縄張り争いと対中・対ソ事情の変化、そして場当たり的な政策の影響が直撃する位置に置かれた組織は、図らずも近代日本を体現する存在として日本の支配政策のお粗末さを象徴する存在として現代に伝えられている。
日露戦争から敗戦まで「日本の生命線」の表舞台に立ち続けた組織の足取りを正確にたどり、「国策」という言葉が包含する曖昧さと無責任さを炙り出す。年表、首脳陣人事一覧、会社組織一覧付き。(原本:講談社選書メチエ、2006年刊)
プロローグ――「国策会社」満鉄とは何だったのか
第一章 国策会社満鉄の誕生
第二章 「国策」をめぐる相克
第三章 使命の終わりと新たな「国策」
終 章 国策会社満鉄と戦後日本
エピローグ――現代日本にとっての満鉄
関連年表
歴代満鉄首脳陣人事一覧
南満洲鉄道株式会社組織一覧

四字熟語の教え
講談社学術文庫
「その言葉の歴史の中には、人々の思いや経験や知恵がつまっています。辞書を調べれば言葉の意味は書いてありますが、そこにつまっているいろいろな歴史や人々の思いはなかなか書いてありません。そういう空白をこの本ではうずめようとしています」。
480点を春夏秋冬の四章に収録。気楽に読める・わかる・使える! 生きた四字熟語に出会える名著。

本能寺の変
講談社学術文庫
2020年大河「麒麟がくる」を100倍楽しむ!
なぜ光秀は信長を殺したか。研究最前線からの回答!
なぜ、明智光秀は、あのとき、織田信長を討ったのか――古来より数えきれぬほど繰り返し問われてきたこの問いに、本流の歴史学的思考が真っ向から取り組んだ画期的論考が、最新の研究を反映する大幅増補をくわえて文庫化。
信長は何と戦い、何に負けたのか。この日本史上最大の政変の核心を衝く試みは、"戦国時代とは/室町幕府とは/日本の中世・近世とは/何か"という根本的な問いへと至る。
本格的歴史学研究でありながら、歴史小説・大河ドラマファンも楽しめる、驚きと発見に満ちた知的挑戦!
【本書より】
連年の発見によって、本能寺の変を挟む約三週間における重要人物の動向の詳細が判明し、変に関する研究は格段に前進し、一定の方向へと収斂されつつある。現段階の研究状況は、二〇一四以前の百家争鳴的な段階を完全に脱却している――
【目次】
はじめに
プロローグ:1 「本能寺の変」の人脈/2 戦国時代
第一章 明智光秀が背いた原因はなにか?:1 足利義昭――将軍をめざす/2 明智光秀――栄達から危機へ/3 織田信長――「国王にして内裏」/4 政変への道
第二章 画策する足利義昭:1「西国公方」義昭/2 政変迫る/3 政変断行
第三章 「秀吉神話」を解く:1 備中高松城の水攻め/2 「奇跡」の中国大返し/3 山崎の戦い/4 信長を継ぐ者は誰か
エピローグ
おわりに
補章「本能寺の変」研究の現在:1 北国情勢と光秀与同勢力/2 政権を揺さぶる派閥抗争/3 光秀の政権構想
参考文献
文庫版へのあとがき
関連年表

ジャンヌ・ダルク 超異端の聖女
講談社学術文庫
痛快で、やがて悲しい――。ジャンヌ・ダルクの生涯を一言であらわすならば、このようになるでしょうか。
時は15世紀、英仏100年戦争の末期。フランスを二分する未曾有の国難のなか、パリを追われた失意の国王シャルル7世のもとに彗星のごとくあらわれたのが、ジャンヌ・ダルクです。甲冑を身にまとい馬上の人となった彼女は破竹の勢いで敵方を打ち破り、またたくまにシャルル7世をランスでの戴冠に導きます。しかし華々しい栄光もつかの間、ジャンヌはイギリス軍に引き渡され、異端者として生きたまま火あぶりにされてしまうのです。「声」に導かれるまま生まれ育った村を旅立ったのが16歳、火刑台に立たされたときには19歳でした。
本書は、100年戦争の政治的背景から、中世におけるお告げや聖女の系譜など、彼女が生きた当時の世界を浮かび上がらせることで、ジャンヌ・ダルクの全体像をあざやかに、しかも親しみやすい筆致で描きだします。
名もない羊飼いの娘だったジャンヌを突き動かした「声」、ついにはシャルル七世をも動かし、フランスを熱狂させたものとは、いったい何だったのでしょうか。カトリックの聖人は数多くいますが、異端者として火刑にまでなりながら、500年後に聖女として認定されたのは彼女だけです。「普通の女の子」が国を救い、国家意識を創ることを可能にしたヨーロッパ中世とは、そして彼女を「守護聖女」として今なお現役で生かしているフランス人の心性とはいったいどのようなものなのでしょうか。異端にして聖女、華やかで苛烈なジャンヌ・ダルクの世界に、あなたも飛び込んでみませんか?(原本:講談社現代新書、一九九七年)
【本書の内容】
プロローグ
序 章 ジャンヌ・ダルクとはだれか
第1章 ジャンヌ・ダルクの先駆者たち――カリスマと聖女
第2章 神の「声」を聞いた少女
第3章 中世の政治と宗教――少女戦士はいかにして誕生したか
第4章 戦場の乙女
第5章 ジャンヌの最期
エピローグ
あとがき
学術文庫版あとがき
おもな参考文献