健康ライブラリー作品一覧

血液のがんがわかる本 リンパ腫・白血病・多発性骨髄腫
健康ライブラリー
【ひと目でわかるイラスト図解】
【どんな病気?どう治す?治療期間は?】
血液のがんは、リンパ腫、白血病、多発性骨髄腫に大別されます。
中高年に多くみられる病気です。
社会の高齢化が進むにつれて、血液のがんにかかる人も増えています。
新たに診断される人の数は、最も多いリンパ腫だけで1年間に3万6千人超、
すべてあわせると6万人近くになります(2019年)。
ちなみに、リンパ腫は「悪性リンパ腫」ともいわれますが、
良性のリンパ腫というものはありません。
それぞれ何種類ものタイプがあり、タイプによって特徴も治療の進め方も違ってきます。
治療を急ぐべき場合がある一方で、無治療のまま様子をみていればよいもの、
ふだんの暮らしのなかで服薬しながらコントロール可能なものもあります。
血液のがんに対する治療は年々進歩しています。
がん細胞に的を絞った治療薬も登場し、移植治療を受けずとも落ち着く例も増えています。
本書では、血液そのものについての基礎知識をはじめ、病気のタイプ、
それぞれの特徴と治療の進め方、治療中・治療後の過ごし方を徹底解説。
血液のがんの患者さんが安心して治療を受けられるために役立つ一冊です。
【本書の内容構成】
第1章 「血液のがん」の基礎知識
第2章 リンパ腫の特徴と治し方
第3章 白血病の特徴と治し方
第4章 多発性骨髄腫の特徴と治し方
第5章 治療中、治療後の過ごし方

名医が答える! 変形性膝関節症 治療大全
健康ライブラリー
【こんな人は必読!】
ひざが痛い! 階段がつらい! 手術をするか、悩む!
【膝の痛みをラクにするQ&Aガイド】
膝の痛みの原因で最も多いのが、「変形性膝関節症」です。
変形性膝関節症は40歳以上で半数程度にみられるともいわれています。
加齢や生活習慣などの影響で膝関節の軟骨がすり減って、
痛みや動かしにくさといった症状が現れるのです。
困ったことに、すり減ってしまった軟骨や関節の変形は
自然に治ることはありません。
そのままにしておくと徐々に進行していきます。
変形性膝関節症は治療で痛みを軽減し、進行を食い止めることができます。
運動や生活改善など、日々の生活のなかでできることもあります。
病院で診断を受けたあと、何十年も自分で上手に膝の状態をコントロールしている人もいます。
治療法も進歩し、選択肢も多くなりました。
本書では、Q&A形式で変形性膝関節症や治療に関する疑問や悩みにお答えしながら、
膝の状態を改善する方法を解説しています。
気になるところだけお読みいただいてもけっこうです。
本書で疑問や不安を解消し、大切な膝を守って、
イキイキと自分らしい生活を続けていくお手伝いができれば幸いです。
(はじめにより)
【本書の内容構成】
プロローグ 膝の痛み よくある疑問を大解決!
1章 この痛み、どうして起こる? 進行するの?
2章 受診から治療方法を決めるまで
3章 うまく体を動かして、膝をラクにする
4章 生活の工夫と薬で暮らしやすく
5章 進行しても、手術で改善できる

発達障害グレーゾーンの子の育て方がわかる本
健康ライブラリー
【困りごとに向き合う 育て方のヒントが満載!】
発達障害の特性がみられるものの、
そこまでくっきりとは際立っていない、
いわゆる“ グレーゾーン” の子どもがいます。
発達障害の診断項目を満たすほど特徴的ではなくても、
発達に“でこぼこ”があり、そのために日常生活で困りごとがある状態です。
発達障害は目に見えにくい障害なので、なかなか周囲の理解を得にくいものです。
グレーゾーンならなおのこと。
発達のでこぼこを単なる「個性」と捉えて見過ごしてしまうと、
やがて周囲の環境とのミスマッチが高じて、本人が傷つき、
結果として、発達の遅れや二次障害につながることがあります。
毎日の生活では、理解と配慮、そして工夫が不可欠です。
本書では、声かけ、ほめ方、環境づくり、就学準備、学習支援など
幼児期から学童期までの子どもとの関わり方や工夫の仕方を紹介、
困りごとに向き合うヒントが満載の一冊です。
【本書の内容構成】
1 発達障害の“グレーゾーン”とは?
2 グレーゾーンの子の“発達支援”の基本
3 [幼児期]就学“前”にできること
4 [学童期]就学“後”にできること
【グレーゾーンの子育て方にはコツがある】
1 困っているなら、診断がなくても今すぐ支援を
2 専門機関への相談・受診は焦らなくていい
3 困りごとを整理して自分たちに合う方法を見つけよう
4 最初は手取り足取り、積極的に手伝ってOK
5 日常の小さな成功体験を積み重ねていこう

強迫症/強迫性障害(OCD) 考え・行動のくり返しから抜け出す
健康ライブラリー
【ひと目でわかるイラスト版】
【手洗い、確認…、一度始めると止まらない!】
100人のうち1~2人は、生涯のどこかで強迫症とされるような症状に悩まされるといわれます。いやな考えが浮かんで消えない、何度も同じことをせずにはいられないといった自分でコントロールできない症状に苦しみ、日々の生活にも影響しているようなら、そこから抜け出す手立てが必要です。
強迫症にみられるこだわりの強さから、「発達障害(生れながらの特性)」と診断されることもあります。症状に悩んでいても「発達障害だから」「そういう性格だから」などと考え、「治せない」とあきらめている人もいるでしょう。しかし、強迫症は治せる病気です。
ただし、強迫症を治すには、本人や周囲の人の深い理解が必要です。
すべて医師に任せていればいい、いやなことはせず、薬を飲んでゆっくり休もう、家族はできるだけ本人の望むとおりにふるまおう――こうしたほかの病気ならうまくいくようなやり方は、強迫症の場合、悪化につながってしまうのです。
強迫症をいかに改善していくか、家族はどう接していけば悪化を防げるのか、具体的な実践法を示していくのが本書です。強迫症の治療法として最も有効とされるERP(エクスポージャーと儀式妨害)を中心に、回復に向けた道筋を示していきます。
【強迫症の主な症状】
*不潔恐怖・疾病恐怖・不道徳恐怖 「汚れること」への嫌悪
*加害恐怖 他人に危害を与えたのではと悩み続ける
*不完全恐怖 理想と現実のギャップを埋めたい
*洗浄強迫 手洗い、消毒……一度始めると止まらない
*確認強迫 本当に確認したのか確認したくなる
*順序強迫・計画強迫「決まったとおり」でなければ許せない
*強迫性緩慢 行動は止まって見えるが頭の中は忙しい
*縁起強迫 儀式をするほど不吉な予感が増えていく

名医が答える! 不眠 睡眠障害 治療大全
健康ライブラリー
【名医が疑問に答える決定版!】
【こんな人は必読!】
ぐっすり眠りたい!
夜中に何度も目が覚める!
睡眠薬だけに頼りたくない!
【眠りの質を高めるQ&Aガイド】
なかなか寝つけない、途中で何度も目が覚める、朝早くに目が覚め、その後眠れない‥‥これらの症状のせいで睡眠不足の状態が続いていて仕事中に疲労感を感じやすかったり、作業効率が悪くなったり、ミスばかり続いて困ったりしていませんか。こうした状況は「不眠症」といえます。
不眠症をはじめ、睡眠にまつわることで悩んでいる人は、年齢を問わず多くいます。こうした眠りに関する悩みを甘く見てはいけません。「寝不足くらい」とか「気合でがんばれ」などと切り捨てる人もいますが、それは大きな間違いです。睡眠不足によって重大な病気を招くことがあるだけでなく、ぐっすり眠れない背景には危険な病気が潜んでいることもあるからです。
また、治療に用いられる睡眠薬に関する誤解も多く、そのことが適切な治療を阻む理由になっていることも見過ごせません。
本書ではQ&A方式で睡眠に関するさまざまな悩みや疑問にお答えしながら、睡眠の重要性と、眠りの質・量を改善する方法を解説しています。睡眠のメカニズムをはじめ、不眠症を含む睡眠障害とはいったいどういう病気なのか、理解が深まります。
【本書の内容構成】
第1章 不眠にはさまざまなパターンがある
第2章 睡眠のメカニズムを知っておく
第3章 睡眠障害ってなに?
第4章 睡眠障害の治療法
第5章 生活習慣を改善して睡眠の悩みを解消する

名医が答える! 緑内障 加齢黄斑変性 治療大全
健康ライブラリー
【名医が疑問に答える決定版!】
【こんな人は必読!】
健診で引っかかった!
進行を抑えたい!
眼圧は正常なのになぜ?
【見え方の不安を解消するQ&Aガイド】
緑内障と診断を受けた人、あるいは疑いがあるといわれた人は、不安でいっぱいかもしれません。緑内障は、眼圧などの影響で視神経が障害され、見えにくさや視野の欠けが生じる病気です。
緑内障では、治療をおこなうことで現状を維持することはできても、一度失った視野の欠けをもとに戻すことはできません。失明を防ぐには、定期的にチェックを受けて一刻も早く緑内障に気づき、緑内障と診断されたらすぐに対策や治療をすすめる必要があります。
また、緑内障のほかに失明に至ることもある深刻な病気には、中高年で急増している加齢黄斑変性もあります。特徴的な症状は、ものがゆがんで見えることです。中心部がはっきりしないので、人の顔が判別しにくい、本や新聞が読みづらい、などの症状で気づくケースもみられます。これらは、目の成人病ともいわれ、加齢とともに患者数は増加しています。
本書では、緑内障と加齢黄斑変性を中心にQ&A式で病気の原因から治療法まで解説。また、白内障や網膜の病気、ドライアイなども取り上げ、それぞれの治療法とともに発症後の日常生活の注意点などを解説します。正しい知識を身につけ、理解することで、治療を受けるときに役立ちます。
【本書の内容構成】
第1章 慌てないで! 今からでも目は守れる
第2章 視野が欠ける緑内障
第3章 ゆがんで見える加齢黄斑変性
第4章 白内障を治して快適に暮らそう
第5章 その他の目の病気
第6章 目の悩みを減らす生活術

発達障害の人が自己実現力をつける本 社会に出る前にできること
健康ライブラリー
【これから社会に出る人たちへ】
「自己実現」とは、自分らしさを生かして社会に貢献していくこと。
本書では、そのための力を「自己実現力」と表現しています。
自己実現力は、自立する力、豊かな人生をつくる力でもあります。
さまざまな特性をかかえた発達障害の人が、
社会に出てからの人生をいかに豊かにしていくか、
自己実現力のつけ方をわかりやすく図解します。
本書は、主に社会に出る前の、高校生や大学生を対象に向けて解説していますが、
保護者や支援者、成人当事者の方にも、ぜひ読んでほしい一冊です。
【内容構成と主なポイント】
1章 自己理解を深める
特性は理解と支援で個性にもなりえる/特性の現れ方をストレス耐性で考える/人からの評価にとらわれないで/自分を客観的にみる練習をしてみよう/「問題」行動を「氷山モデル」で考える/自分を認めて「真の自己肯定感」をもつ/ギフテッドと2E
2章 心身の安心感を得る
安全な環境なのに危険を感じてしまう/感覚、認知の調整とストレスケアを/疲れやすいと自覚して、しっかり休む/ストレスへ対処して、心の疲労を防ぐ/自分の「感じ方」を知っておこう/感覚過敏・鈍麻・渇望、それぞれの対処法
3章 自分をたいせつにする
不完全な自分を受け入れると楽になる/思いやりを、まず自分自身に向ける/感情に対処して今の自分を幸せに
4章 スキルを身につける
相手を怒らせない伝え方「Iメッセージ」/対人関係をなめらかにする「魔法の言葉」/自分もハッピーになれる「感謝の言葉」
5章 親が今できること
親子の間の誤解をといておこう/兄弟姉妹のわだかまりを解消しておく/自己決定させることにこだわらない

DCD 発達性協調運動障害 不器用すぎる子どもを支えるヒント
健康ライブラリー
【知られざる発達障害】
転びやすい、着替えができない、なわとびがとべない、自転車にのれないなどは、子どもと過ごす生活のなかで、日常的によくある光景です。
しかし、そうした動作のなかにとりわけ「極端なぎこちなさ」を伴う子どもたちがいます。
本人が努力しても、親がどんなに教えてもうまくできない子どもたち。
そのような子どもたちは「DCD:発達性協調運動障害」のある子どもなのかもしれません。
DCDは、極端に不器用で、日常生活にさまざまな困難さを抱える発達障害の1つです。
協調運動の不具合で起こるため、診断がつかずに困難さを抱えたまま学童期を迎えることが多く、周囲からは理解されず、生きづらさを抱えているケースも少なくありません。
本書では、DCDという疾患がどんな症状を呈し、どんな生きづらさを伴っているのかを解説するとともに、
実例を多くあげて本人・家族が抱える困難さの現状、支援方法やアドバイスを紹介していきます。
【本書の内容構成】
プロローグ「DCD」という発達障害を知っていますか?
第1章 「不器用」では片づけられない「極端なぎこちなさ」
第2章 まだ知られていない「DCD」という発達障害
第3章 幼児期の「極端なぎこちなさ」に気づいてほしい
第4章 学校でいちばんつらいのは体育の時間
第5章 学校生活のあらゆる場面で困りごとを抱えている
第6章 大人になっても就労や家事でつまずきやすい
第7章 自分なりのライフスタイルをみつける

摂食障害がわかる本 思春期の拒食症、過食症に向き合う
健康ライブラリー
【ひと目でわかるイラスト図解】
【太る恐怖、飢餓がまねく食への執着、過食の衝動】
摂食障害は、心にかかえている問題が「食べ方の問題」として現れる病気です。
現れ方の違いでいくつかのタイプに分けられますが、ストレスが大きくかかわっている点はみな共通しています。
近年、小中高校生の摂食障害、なかでも食べられずにやせていく「神経性やせ症(いわゆる拒食症)」が増えています。
本人は、やせたままでいることに大きなメリットを感じています。
どんなにやせていても太ることを恐れ、極端なカロリー制限を続けたり、食べても吐いたりして体重増加を抑えようとします。
家族が「なにかおかしい」と思い始める前に、学校生活のなかで、子どもの変化があらわになることも多いものです。
学校として対応を考えていかなければならないことも少なくありません。
食べる量が増えて体重が戻ったあとも食べ吐きが止まらず、「過食症」に転じていくこともあります。
高校生、大学生では、極端な低体重の時期はないまま「過食症」が始まる例も少なくありません。
摂食障害の患者さんを支える家族の負担はとても大きいですが、家族の支えは、摂食障害から回復する大きな力になります。
本書では、摂食障害の原因、経過、治療法などをわかりやすく解説。
周囲ができる回復に結びつく働きかけ、そこから抜け出すヒントを紹介します。
【本書の内容構成】
第1章 神経性やせ症の始まり方
第2章 やせてもやせても、まだ足りない
第3章 やせすぎからの回復をはかる
第4章 過食がみられる摂食障害
第5章 家族の悩みが深いとき
【主なポイント】
*摂食障害は、心にかかえている問題が「食べ方の問題」として現れる病気
*子どもの摂食障害は神経性やせ症(拒食症)がほとんど
*家族が「異変」に気づくのは遅れがち、学校は早期発見の場となりうる
*やせるほど強まる太る恐怖。過剰なまでに活動的になる
*家族が説得しようとするほど本人との対立は激しくなる
*医療機関への受診を考える状態の目安と、受診の促し方
*神経性やせ症の回復過程でみられる過食は正常な反応
*神経性過食症(過食症)、よくある「食べすぎ」とどう違う?
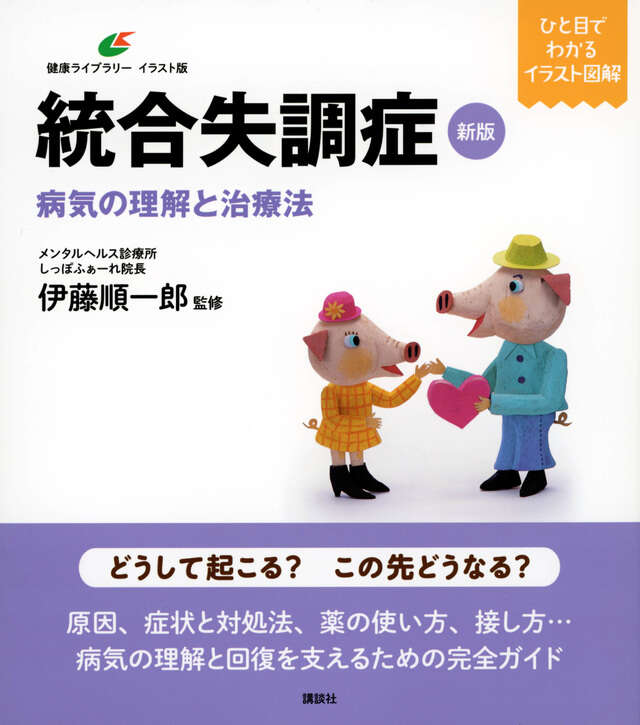
新版 統合失調症 病気の理解と治療法
健康ライブラリー
【どうして起こる? この先どうなる? 】
統合失調症について、きちんと理解されていないことは、まだまだたくさんあります。
なかには、患者さん本人や家族が誤解していることもあります。
統合失調症で起こる特徴的な症状には、対応に悩む人もいるでしょう。
本人にどう接すればよいか、いつになったら状況が変わるのか、
はたして回復するのかと、家族や周囲の人は悲観的になりがちです。
けれども幻覚、妄想などの症状が現れる時期は急性期のときだけ。
やがて精神的に落ち込み、身体的な活動性もグッと少なくなります。
そして病気の状態は少しずつ変わっていきます。
ほとんどのケースでは、ゆっくりと、波をうちながら確実に改善に向かっていきます。
また、近年、統合失調症に関する治療法が、だいぶ変わってきました。
なにより大きな変化は、患者さんを入院させるのではなく、
地域の中で暮らしていけるようにすることです。
そのための支援や福祉サービスが整理され、
社会とのつながりを保ったまま治療を進められるようになりました。
薬物療法や精神療法が進歩し、訪問診療も受けられるようになっています。
本書は、統合失調症の理解に役立つように図解でわかりやすく、
患者さんの回復を支える一助となる一冊です。
*本書は2005年発行の『統合失調症 正しい理解と治療法』に最新の情報を加えた新版です。
【本書の内容構成】
第1章 こんなときどうする? 症状とその対処法
第2章 どうして起こる? 病気のしくみを理解する
第3章 どうやって治療する? 薬の使い方を知る
第4章 これからどうする? 社会復帰に向けて
第5章 この先どうなる? 地域で暮らすために

女性の発達障害 困りごとにどう向き合うか
健康ライブラリー
【生きづらさをやわらげ自分を元気にする】
発達障害は、男子のほうが症状は目立ちやすく、発達障害と診断される子も多いです。大人になると、男性は会社など社会的に適応していても、家庭において発達障害のために、種々の問題が起こることがよくみられます。
一方、女子の症状は目立ちにくく、診断を受けないまま大人になる人が多いです。その後も、女性は相対的に環境への適応能力が高いために、問題なく大人になっていくとみられる例も少なくありません。
しかし、女性は男性より家事労働の時間が長く、出産、子育てでも大きな役割を担います。そのために、発達障害の女性は、たとえその程度が軽くても、妻として、母としての役割が大きな負荷となり、生きづらさが顕著となり、生活するうえでの困り感が重くのしかかるのです。
また、夫婦ともに、あるいは子どもにも発達障害の傾向があると、家族間に問題が起こりやすいのです。誰かに相談することもできず、つらく苦しい状況のなかで悩んでいる女性も多いです。
本書では女性の発達障害について基礎から解説し、あなたの生きづらさの原因をひも解き、あなたと家族が過ごしやすくなるための日常のアドバイスをしています。
本書が、あなたの日々の暮らしを少しでも楽にするための一冊になることを願っています。(まえがきより)
【「女性なのに」という視線が苦痛に】
発達障害の特性によって苦痛や生きづらさを感じるその背景には、「女性なのに」というかたよった視線も影響しています。特性による言動やふるまいは、社会で求められている「女性らしい」役割やイメージとはかけ離れていることが多いのです。そのギャップが、特性のある女性たちを苦しめています。
【本書の内容構成】
1 発達障害ってどういうもの?
2 プライベートでの困りごと――こんなとき、どうする?
3 職場や学校での困りごと――こんなとき、どうする?
4 自分をいたわり、励ます方法を身につける

名医が答える! 大腸がん 治療大全
健康ライブラリー
手術はどんな方法がある?術後の排便への影響は?人工肛門で人生は変わる? Q&A式で徹底解説、不安と疑問を解消できる決定版!

発達が気になる子の性の話 みんなでいっしょに学びたい
健康ライブラリー
【からだとこころの大切さがわかる!】
本書は、体の成長の変化での悩み、恋愛や性行為への疑問、性情報の選び方、SNSの危険……小学校高学年から高校を卒業する頃までには身につけたい、性や恋愛、人間関係についてイラストやマンガをふんだんに入れて解説しています。
発達がゆっくりであったり、凸凹があったりする発達障害やLGBTQなどの「発達が気になる子どもたち」にも理解しやすいよう、かなり易しい言葉でまとめています。さらに、もっと小さい頃に学んでおかなくてはならなかったような初歩的な内容の学び直しもできるようにしています。
また、人と適切な距離をとることや、周囲をみて自分の言動を判断することが苦手、からだの成長や変化にとまどいやすい特性がある子どもたちに向けて、巻頭や各ページに、どのように対応すればよいか、子どもへの伝え方や教え方のヒントを紹介しています。
まずは、子どもに学んでもらうことを念頭に、大人自身が学ぶことからはじめましょう。できればいっしょに読むことをおすすめします。それがむずかしい場合でも、子どもたちの質問は率直に受け止め、叱ったり、ごまかしたりせず、ていねいに答えていきましょう。
子どもたちが正しい性の知識を学び、自分自身や相手を大切にし、豊かな性行動がとれるよう子どもも大人も活用できる一冊です。
【本書の内容構成】
1 どうなっているの? わたしたちのからだ
2 人を好きになる気持ちはどんなもの?
3 好きな人にふれてみたい
4 心とからだを守るために

認知症といわれたら 自分と家族が、いまできること
健康ライブラリー
【イラスト図解で読みやすい】
【認知症でもなんとかなる!】
あなたはいま、「認知症といわれたらどうしよう」「認知症といわれたが、どうすればいいのか」と、不安や戸惑いでいっぱいかもしれません。
認知症をもたらす疾患の最大の危険因子(リスクファクター)は、年をとることです。高齢者が多い日本では、あなたと同じような不安や戸惑いをかかえている人が増えています。
ただ、認知症を心配する人や認知症と診断される人の数は増えているものの、重症化する人の割合はむしろ減っています。いまは医療も進んでいますし、介護に携わる人の意識も大きく変わってきています。認知症は進行する病気ではありますが、昔にくらべ、その進み方はゆるやかになっているといえます。
いまのあなたは、以前と同じようにはできず、失敗することが増えているかもしれません。しかし、できることもたくさんあるはずです。うまく言葉にしにくいかもしれませんが、いろいろなことを考えたり、感じたりもしているでしょう。なにもできない、なにも語らない認知症の人がいるとすれば、それは認知症そのものの症状というより、自信を失い、あきらめ続けた結果であることも多いのです。
失敗の増加と自信の喪失は、必ずセットになっているわけではありません。失敗しても、そばにいる人が目くじらを立てず、さりげなくサポートしてくれる環境のなかでなら、認知症があろうとなかろうと、自尊心を保ちながら幸せに暮らせます。「今度はこうしてみよう」などという、前向きな気持ちも生まれやすくなるでしょう。
本書は、家族の方だけでなく、認知症のある人自身にも役立つ情報をたくさん紹介しています。もの忘れの多さなど、症状への対処法を知りたいという方は、第3章、第4章など、途中から読み始めてもらってもかまいません。
あなたの「これから」にこの本がお役に立てば、とてもうれしく思います。(まえがきより)
【本書の内容構成】
第1章 認知症かもしれない
第2章 これからどうなる?
第3章 自分らしく暮らし続けるために
第4章 困りごとを減らすヒント
第5章 家族が認知症とわかったら

心不全がわかる本 命を守るためにできること
健康ライブラリー
【どんな病気? なぜ起こる、どう防ぐ?】
心不全は心臓がうまく働けなくなる状態のこと。予後はがんよりも悪いとされ、治療せずにいると、どんどん生命を縮めてしまう。生活習慣病があれば「リスクあり」、心臓病があれば「前段階」となり、すでに心不全の入り口にいる人は多く、患者数は今後さらに増えていくと予測されています。
しかし、症状があっても、「年のせい」「たいしたことはない」などと見過ごされるケースや、心不全の兆候があっても、健診ではひっかからないこともあります。
予後を改善するためには、生涯にわたって治療を継続する必要があります。心不全に対する一般向けの書籍は少なく、情報が集めにくいため「なにに気をつければいいのかわからない」と感じる方もいるでしょう。本書では、発症のサインとなる症状からステージごとの治療法、生活習慣の見直し方までを、イラストを使って解説。心不全に対する疑問が解消できます。
【主なポイント】
・心不全とは、心臓がうまく働かなくなる状態のこと
・代表的な症状は、息切れ・むくみ・だるさの3つ
・不整脈や弁膜症など、すべての心臓病が原因
・生活習慣病があるだけで、すでに予備軍
・一度発症したら、再発を防ぐ治療へ
・新たな薬が続々と登場している
・自分に合った病院を選ぶためのポイント
・心不全の予後改善には適度な運動が必要
【本書の内容構成】
第1章 心不全、どうやって気づけるの? ――息切れ・むくみ・だるさをチェック
第2章 なにが怖いの? 原因は? ――心臓がうまく働かなくなっていく
第3章 どんな治療があるの? ――急性心不全の発症や再発を防ぐ
第4章 それでも進んだら、どうしたらいいの? ――入院を経験したら
第5章 心臓に負担をかけないためには? ――心臓をいたわる習慣
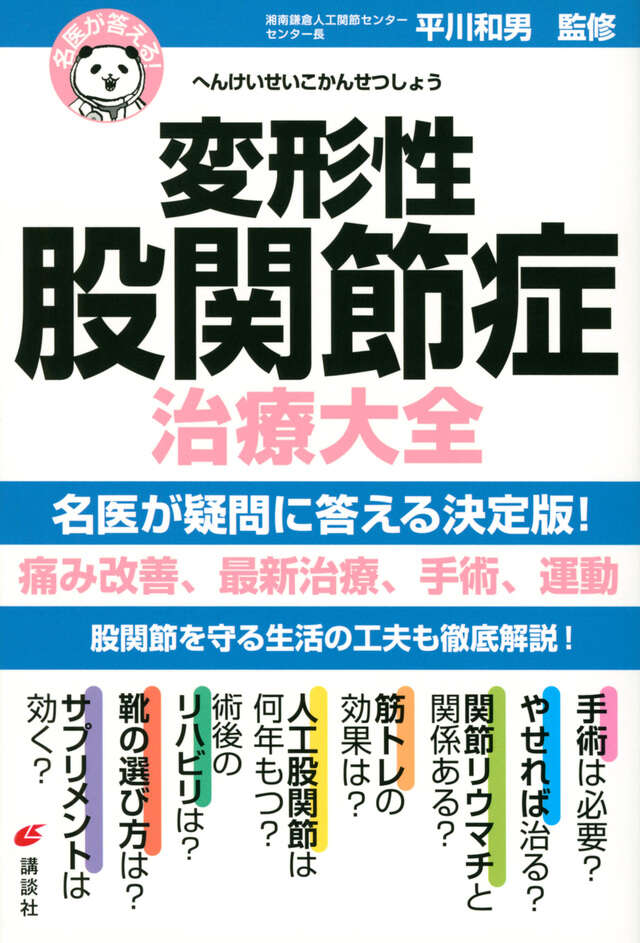
名医が答える! 変形性股関節症 治療大全
健康ライブラリー
腰や痛みの原因が関節? やせれば治る? 受診の目安は? 手術か保存療法か? Q&A式で徹底解説、不安と疑問を解消できる決定版

アタッチメントがわかる本 「愛着」が心の力を育む
健康ライブラリー
【「不安なときに守ってもらえる」という確信が心の力に】
アタッチメントのもともとの意味は「くっつく(アタッチする)こと」。「不安なとき、特定のだれかにくっついて安心する」という経験が子どものすこやかな発達のために、いかに大切なものであるか、改めて見直されるようになってきています。
幼い頃、どれだけ確実に、親をはじめとする養育者にくっついて安心できたかで、子どものアタッチメントの安定性は決まっていきます。安定したアタッチメントの経験がもたらす「守ってもらえる」という確信は、「心の力」となり、子どものすこやかな発達を促します。成長してからの対人関係のあり方にも影響すると考えられます。
だからこそ、子どもの困った行動や、大人がかかえる生きづらさのもとに何があるのか、アタッチメントという観点からみると理解しやすくなります。
本書では、アタッチメントに関する知識をわかりやすくイラスト図解します。子どもへのかかわり方を考える、また、生きづらさを感じる自分自身を見つめ直すためのヒントが詰まった1冊です。
●本書の内容構成
第1章 子どもの発達とアタッチメント
第2章 アタッチメントの個人差と問題
第3章 心の力を育む「基地」の役割
第4章 保育・教育の場でのかかわり方
第5章 大人にとってのアタッチメント

不登校・暴力行為に向き合う 小中学校で発達障害に気づいて・育てる支援ガイド
健康ライブラリー
【豊富なケーススタディで適切な支援を読み解く】
不登校、いじめ、校内暴力は、今や学校現場における大きな問題です。文部科学省も教育委員会も学校の先生方も、一生懸命解決に取り組んでいますが、年々数字は増えていくばかりです。
一つひとつに取り組むことも大切ですが、これらの難題はそれぞれ別のものではなく、根はひとつと考えられないでしょうか。もしかしたら、それは発達障害の子どもたちが、学校という社会的環境に適応できずに苦しんでいる姿かもしれません。すべてがそうだとは思いませんが、かなりの部分であてはまるのではないかと考えたとき、基本となる対応策が見えてきます。それは発達障害への支援であり、特別支援教育のさらなる充実です。
現在、先生方は、通常の授業の中で特別支援教育を行っています。発達障害の特性が強い子どもたちも、そうではない子どもたちも含めて対応していかなければならないのです。その先生方にもっていただきたいと思うのが2つの視点です。2つの視点とは発達障害の特性を把握する視点と子どもたちの行動を分析する視点です。この2つの視点を併せもって子どもを見たときに、本当に必要な支援は何かが見えてくるでしょう。(まえがきより)
【こんなケースにどう対処したらよい?】
●授業で叱られたことがきっかけで不登校
●登校してもなかなか教室に入れない
●席を離れて立ち歩いたり、教室を飛び出したりする
●すぐに「うるせえ」などと暴言をはく
●音楽など専科の先生に反抗的で授業が進まない
【本書の内容構成】
第1章 不登校と暴力的言動が増えている
第2章 発達障害の基礎知識をもとう
第3章 障害を個性に変えるために
第4章 支援には2つの視点をもって
第5章 不登校には、子どもの状態に合わせた支援を
第6章 暴力的言動には、複数の特性への対応を
第7章 さまざまな困難例に向き合う

40代から始めよう! 閉経マネジメント 更年期をラクに乗り切る、体と心のコントロール術
健康ライブラリー
40歳以降の女性は、女性ホルモンの変化によって、さまざまな心身の不調に悩まされます。
そして「閉経」は、それまで長い間、全身を駆けめぐって体を守ってくれていた女性ホルモンの働きが休止する、
女性にとっての一大事といえるでしょう。
本書で紹介する「閉経マネジメント」は、更年期前後の女性に忍びよる
「更年期症状」と、骨折にもつながる「骨粗しょう症」の不安を解消するための
「自分の体をマネジメントする方法」です。
その柱は2つ。
【1.女性ホルモンのコントロール】と、
【2.女性ホルモンの減少によって影響を受ける「骨の強さのマネジメント」】です。
どちらも、食事や運動など日常生活でできる対策に加え、適切な治療を行うことで、
不調から解放され、ラクに閉経前後の時期を乗り越えることができます。
また、閉経マネジメントで重要なのは、「いつ」「何を」するかです。
本書では、40代以降の女性のライフステージを「プレ更年期」「更年期」「ポスト更年期」の3つに分け、
それぞれのライフステージで、
【女性ホルモンのコントロール】や【骨強度マネジメント】のために何をすればいいかを
わかりやすく解説しました。
《閉経マネジメントを始める前に気になる、こんな疑問や不安も解消!》
◎私の閉経年齢はいくつでしょうか?
◎ホルモン補充療法のメリットとデメリット
◎サプリメントで女性ホルモンがコントロールできる?
◎骨強度を上げる食べ物ってある?
◎閉経前後にかかりやすい女性の病気って?
もっと知りたい人のためのQ&Aや、患者さんの体験記もたっぷり盛り込んだ、
いつまでも健康な女性でいるための方法がギュッとつまった1冊です。

子どもの目を守る本
健康ライブラリー
【スマホの使い過ぎで内斜視になることも】
視力がよくないのではないか、目つきが悪く見えにくそうにしている、黒目の向きが斜めになっているのではないかなど、小児眼科にはこうした心配をして訪れる親御さんがたくさんいます。気にしすぎではないかとか、早とちりかもしれないと思うかもしれませんが、それでよいのです。
というのも、人がものを見る機能は三歳ごろまでに急速に発達し、六歳から八歳、遅くとも一〇歳ごろまでにはほぼ完成し、視力が決まります。もし、なんらかの病気や異常があれば、視力が完成する前にできるだけ早く治療を開始して、見る力を育てるケアやサポートを受けさせる必要があります。
しかし、子どもは自分から目の異常や見え方が悪いと訴えることはまずありません。子どもと一緒にすごしている親や周囲にいる大人が、異変に気づいてあげるしかありません。ですから、なにかおかしいと感じたら、ためらわずに眼科を受診することが大切なのです。
また、三歳児健診や就学時健診は子どもの目の異常を早期に発見し、治療やサポートへつなげることを目的としています。子どもの目の異常を早期発見する重要な機会であることを理解し、必ず受けるようにしましょう。
本書では、異変に気づくためのポイントや、早期に見つけたい病気の知識などをできるだけわかりやすく解説しました。(まえがきより)
【子どもの目に関する疑問や不安に応えます】
*子どもの目の異常は、どうすればわかりますか?
*片目のみ視力が悪いのですが、なにか対処すべきですか?
*子どもでもめがねをかけさせないといけませんか?
*両親が近視だと、子どもも近視になりますか?
*子どもの目の病気で重症化するものはありますか?
*しきりに目をこすっていますが、大丈夫でしょうか?
*スマホやタブレットは使わせてもよいのでしょうか?
【本書の内容構成】
第1章 見逃したくない、気がかりなサイン
第2章 「見る力」の育ち方
第3章 弱視・近視・斜視……「見え方」の異常はなぜ起こる
第4章 知っておきたい子どもの目の病気
第5章 子どもの目に関するよくある質問