健康ライブラリー作品一覧

口・のどのがん 舌がん、咽頭がん、喉頭がんの治し方
健康ライブラリー
【舌や声、飲み込みの違和感は要注意のサイン!】
口やのどにがんができても、がんだと気づくのが遅くなりがちです。
部位によっては症状が現れにくく、症状が現れても口内炎やかぜに似ているためです。
口とのどのがんでは、がんのできた部位や種類、進み具合で治療法が変わります。
手術のほか、放射線や抗がん剤を使った治療も効果を発揮します。
しかし、がんが大きくなると治療の後遺症や副作用によって、生活が変化することは避けられません。
患者さんの体の状態や生活のしかた、環境などによって、治療方針が一人ひとり異なります。
自分のがんを正しく知り、治療後の生活をイメージすると、安心して治療に望めます。
本書では、診断の流れからリハビリの進め方まで徹底解説、
ベストな治療法を選ぶための完全ガイドです。
【主なポイント】
*口のがんの半分以上は舌にできる。口内炎に似ている
*のどのがんのサインは、声がれや飲み込みの違和感
*主な原因は喫煙と大量飲酒。舌やほおをよくかむ人も要注意
*舌がんはどの病期でも最初に手術を選択。同時に首のリンパ節も切除する
*舌を半分以上切除した場合は、再建で舌をつくり直す
*のどのがんは放射線療法が中心。最大のメリットは声を残せること
*がんが進行すると、声か食事かを選ぶ必要が出てくることも
*治療後は食事や発音・発声のリハビリで失った機能を補う
【本書の内容構成】
第1章 口やのどのがんを疑ったら
第2章 くわしい検査で治療法を選ぶ
第3章 口のがんの治し方
第4章 のどのがんの治し方
第5章 治療後のリハビリと日常生活

子どものトラウマがよくわかる本
健康ライブラリー
【トラウマに気づき、回復のためにできること】
「心の傷」ともいわれるトラウマ。トラウマが認識されないことによって、
事件や自死に発展したり、重篤な後遺症を残したりするケースもあります。
また、トラウマ体験の重なりによる「再トラウマ化」は、大きな問題です。
その裏には未だ表に現れていない、被害を受けた多くの子どもたちや苦しんでいる親もいるかもしれません。
子どものトラウマは、問題行動を引き起こすだけでなく、
その先の人生に大きな影響を及ぼすおそれがあります。
子どもの場合、「なにがあったか」という出来事の内容もさることながら、
その後のケアのあり方も、心の傷の残り方を大きく左右する要因になります。
子どもが自分から語ることは少ないからこそ、周囲がトラウマの存在に気づき、
子どもの回復のためになにができるかを考え、行動していくことが求められています。
本書は、トラウマインフォームドアプローチ(トラウマへの理解を深め、かかわっていくという姿勢)に基づいて編まれたもの。
支援者の方には適切な支援を進めていくために、当事者の方には自己理解と回復に役立つ一冊です。
【主なポイント】
*子どものトラウマは「問題行動」として現れる
*対人関係の傷つきで生じる「発達性トラウマ障害」
*トラウマ体験で「解離」が起こることもある
*「小児期逆境体験」のトラウマは長く影響し続ける
*「発達障害」と「発達期のトラウマ」の密接な関係
*「虐待」は複雑なトラウマを生じさせる最大の原因
*子どもだから生じやすい「性的虐待順応症候群」
*支援の基本は「トラウマインフォームドケア」
*「通告」したほうがよいとき
【内容構成】
第1章 子どものトラウマが特別な理由
第2章 虐待されてきた子どもに起こること
第3章 トラウマになりうる体験のいろいろ
第4章 子どもの回復を支えるためにできること
第5章 子どもを支える「しくみ」を活かす

大人の発達障害 グレーゾーンの人たち
健康ライブラリー
ここ数年、精神科や心療内科などでは、「発達障害かもしれない」と受診してくる人がたいへん多くなっています。しかし、受診しても診断がつかず、「傾向がある」と言われるだけの人がいます。こうした人たちが「グレーゾーン」です。
受診する動機に多いのは「対人関係」です。発達障害の特性のひとつに、コミュニケーションの障害があります。グレーゾーンの人たちは、ある程度の対人関係はつくれますが、うまく関係を続けることができず、孤立しがちになり、孤独感に苦しみます。自分の状況が客観的にみえるからこそ、良好な対人関係を求めて悩んでいます。
また職場ではミスや叱責を恐れて、一日中緊張しています。健常者と比べ、発達障害者と比べて、どちらにも合わない、はざまの葛藤に苦しみます。他者と比較して感じる不安もなくなることはありません。
このようにグレーゾーンの人には、特有のつらさがあります。ある程度社会に適応しているのに、ときにはうまくいかない経験があり、それを認識しているからこそ、つらいのです。
本書では、多くの大人の発達障害を診療している精神科医による解説と、当事者の思いと自分との向き合い方を紹介します。
【本書の内容構成】
1 発達障害のグレーゾーンとはなにか
2 発達障害の診断はどのようにおこなうか
3 グレーゾーンに関連する病気を治療する
4 今の自分と向き合っていく/当事者の声
5 職場の人へ/困りごとへの対応を

知的障害/発達障害のある子の育て方
健康ライブラリー
ひと目でわかるイラスト図解
《講談社 健康ライブラリースペシャル》
【これからに備えて、いまできること】
よそのお子さんはとっくにできていることが、うちの子はまだできない。「ママ」や「パパ」という言葉を口にしない。簡単な会話も成立しない。何度注意しても走り回る――親が育てにくさを強く感じているお子さんには、発達のかたより(発達障害の傾向)や、発達の遅れ(知的な遅れ)があると考えられる場合が少なくありません。
育てにくさの背景にあるのは、知的発達の遅れだったり、自閉症スペクトラムやADHDといった発達障害の特性だったりします。知的障害が認められても、程度が軽ければ、乳幼児期には「のんびりした子」などとして見過ごされていることもあります。また知的障害のお子さんのなかには、自閉症スペクトラムやADHDの特性がみられることも多くあり、子育ての困難さ、負担感がより一層高まりやすくなります。
本書では、知的障害や発達障害への理解を深めながら、保護者に求められるかかわり方を示していきます。今、お子さんが必要としていることはなにか、育ちを伸ばし支えるためにどう対応していけばよいか、具体的な働きかけ方を紹介します。
【主なポイント】
*「育てにくさ」と「言葉」に気がかりなサインが
*知的障害と自閉症スペクトラム・ADHD・LDの関係
*特性ごとに障害名は違うが重なり合うことも
*就学前は問題なくても就学後に「勉強」でつまずきやすい
*進学・就労への道筋はいろいろある
*言葉かけの基本、指示は「はっきり、短く、具体的に」
*制度や福祉サービスの活用は、子育て支援を担当する窓口で相談を
*パニック、じっとしていられない……。困った行動に対処するヒント
【監修者プロフィール】
■徳田克己(とくだ・かつみ)
筑波大学医学医療系教授、教育学博士、臨床心理士。専門は子ども支援学、子育て支援学、気になる子どもの保育。筑波大学発ベンチャー企業「子ども支援研究所」の所長として、各地で講演をおこない、育児に悩むお母さんやお父さんからの相談に応じている。『具体的な対応がわかる 気になる子の保育――発達障害を理解し、保育するために』(チャイルド本社)、『こうすればうまくいく!知的障害のある子どもの保育』(中央法規出版)など、著書、監修書多数。
■水野智美(みずの・ともみ)
筑波大学医学医療系准教授、博士(学術)、臨床心理士。「子ども支援研究所」副所長。『はじめよう! 障害理解教育――子どもの発達段階に沿った指導計画と授業例』(図書文化社)、『こうすればうまくいく!自閉症スペクトラムの子どもの保育』(中央法規出版)など著書多数。

大動脈瘤と大動脈解離がよくわかる本
健康ライブラリー
【内容紹介】
大動脈瘤や大動脈解離は、高齢化にともない年々増加しています。
大動脈は心臓から出て胸部、腹部にいたる、からだの中心を走る最も太い血管です。その太い血管で動脈硬化が進むと、血管壁の弾力性が低下し、さまざまな異常が起こりやすくなります。もろくなった血管壁に高血圧などの要因が加わり、血管がこぶのようにふくらんだ状態になるのが「大動脈瘤」。そして血管壁の一部に亀裂が入り、剥離を起こした状態が「大動脈解離」です。
どちらも危険な病気ですが、大出血を起こすまでは目立つ自覚症状がないため、なかなか気づきません。検診で偶然見つかり、「もし破裂したら……」とうつになる人も多くいます。本書では危険な病気の基礎知識から最新治療までわかりやすくイラストを使って解説、不安を解消する一冊です。
【監修者紹介】
大木隆生(おおき・たかお)
東京慈恵会医科大学外科学講座統括責任者、血管外科教授。1962年生まれ。東京慈恵会医科大学医学部卒業。同大附属病院、米国アルバート・アインシュタイン医科大学モンテフィオーレ病院血管外科部長及び同大血管外科学教授を経て、現職。専門は血管外科、特に大動脈瘤、閉塞性動脈硬化症。日本外科学会理事、日本心臓血管外科学会理事、日本血管内治療学会理事長などを務める。日本心臓血管外科学会他『大動脈瘤・大動脈解離診療ガイドライン(2011年改訂版、2020年改訂版)』作成に携わる。Best Doctors in NY、『Newsweek 日本版』の「米国で認められた日本人10人」「世界が尊敬する日本人100人」、『文藝春秋』の「日本の顔」などに選ばれた経歴と多数の特許を有する外科医。高知県観光特使。著書に『医療再生 日本とアメリカの現場から』(集英社新書)。
【主なポイント】
巻頭 Dr.に聞く 大動脈瘤・大動脈解離のQ&A
1 血管にこぶができる大動脈瘤大動脈瘤とは/見つけ方/原因/見つかったら/タイプ/治療の目的/治療の決まり方
2 血管が裂ける大動脈解離大動脈解離とは/原因/見つかり方/症状が似た病気/同時に起こりやすい病気/検査と診断/タイプ/治療の目的/治療の決まり方/入院スケジュール/退院したら
3 薬と生活の工夫で進行を防ぐ
手術か薬か/定期的な受診/薬での治療/日常生活の工夫/精神的ストレス/破裂の前兆
4 手術で破裂を防ぎ根本治療を
手術の方法/選び方/人工血管置換術/ステントグラフト治療/入院スケジュール/術後
の定期健診/手術後の生活/再発したら

ADHDの人の「やる気」マネジメント 「先延ばしグセ」を「すぐやる」にかえる!
健康ライブラリー
ひと目でわかるイラスト図解
《講談社 健康ライブラリースペシャル》
【やる気があるのにできないADHDの人へ】
周囲の人から見ると理解しづらいのですが、ADHDの人は、やる気はあるのになかなかやるべきことをできません。
やろうと思っているのに、できない。やる気はあるのです。サボっているわけではないし、怠けたいわけでもありません。
やる気はあっても、行動に移すのが難しい、日々続けておこなうのが難しい。ADHDの人は好きなことはがんばれるのに、興味のもてないことや普通のこと、毎日の決まったことに、なかなか取り組めません。
日常生活のいろいろなやるべきことを、めんどうと思いがちです。なんとかやる気を引き出して、やるべきことを実行したいのだけど、なかなかうまくいかなくて困ってしまいます。「やらなくちゃ」と思っていても、つい忘れてしまって、できないこともあります。ADHDの人の毎日には、「めんどう」と感じることがとてもたくさんあります。世の中のことは、「好き」か「めんどう」に二分されるようです。
けれど、めんどうでもやらないといけないのはわかっているし、できない自分はダメな人間だと感じ、悩んでもいます。
あなたのなかにある「やる気」を引き出し、行動に結びつけて持続させていければ、多くのことが改善して、生きやすくなる……。
本書では、そのためのマネジメント術を考えてみました。やる気を行動に移すスイッチをじょうずに入れて、やる気をうまくマネジメントしましょう。そうすればあなたに合った人生の進め方が見つかるでしょう。(まえがきより)
【監修者】
司馬理英子(しば・りえこ)
司馬クリニック院長。医学博士。1978年、岡山大学医学部卒。1983年に同大学大学院博士課程修了後、渡米。アメリカで4人の子どもを育てながら、ADHDについての研鑽を積む。1997年、『のび太・ジャイアン症候群』(主婦の友)を上梓。日本で初めて本格的にADHDを紹介した同書は、なじみ深いキャラクターになぞらえたわかりやすい解説により、ベストセラーに。同年帰国し、司馬クリニックを開院。子どもと大人の女性を専門に、治療を行う。主な著書に『大人のADHD』(講談社)、『のび太・ジャイアン症候群』『アスペルガー症候群・ADHD 子育て実践対策集』(ともに主婦の友社)など。
【主な内容】
1 やる気が行動につながらない
2 「やるべきこと」を「やりたいこと」に
3 マイ締め切りで時間を管理する
4 すぐやれるように準備しておく
5 努力に注目して自分をほめる

アルツハイマー病のことがわかる本
健康ライブラリー
ひと目でわかるイラスト図解
《講談社 健康ライブラリーイラスト版》
【進行を遅らせるために今、できること】
日本には、500万人を超える認知症の人がいます(2018年末)。
認知症をまねく最大の原因がアルツハイマー病です。
その発症は早く、認知症に至る20年以上前から発症しますが、
脳の働きのすべてが一度に失われていくわけではありません。
より早い段階で気づくことができれば
認知症の発症・進行を抑えられる可能性があります。
最近の研究で、加齢だけでなく、食事・運動・睡眠などの生活習慣が、
アルツハイマー病の進みぐあいを左右する要因になっていることがわかってきています。
生活改善に取り組むことは、アルツハイマー病の診断がついていても、
ついていなくてもできる有効な対策です。
本書では、アルツハイマー病について解明されている最新情報をもとに
病気の基礎知識から認知症に至るまでの経過や、症状が進んだ場合の対応まで
イラストを使ってわかりやすく解説。
今できることに取り組んでいこうと、前向きな気持ちになれる一冊です。
【主なポイント】
*認知症の6割はアルツハイマー病が原因で起こる
*アルツハイマー病のはじまりは無症状。20年以上かけてゆっくり進む
*脳にたまった「アミロイドβ」が神経細胞を壊れていく
*MRIで異常がみつかるのは脳の萎縮が始まってから
*「もとどおりに」は難しい。「進めないこと」が大切
*認知症の発症・進行リスクを高める9つの要因
*「生活改善」は認知症発症前でも後でも進行予防になる
*65歳未満で発症する「若年性アルツハイマー病」の問題とは
*認知症治療薬に期待できること
【本書の内容】
第1章 「アルツハイマー病」と「認知症」は同じもの?
第2章 脳の中でなにが起きているのか?
第3章 生活改善が進行を防ぐ鍵
第4章 脳の「予備能」を高める治療とリハビリ
第5章 この先も穏やかに暮らしていくために
【監修者プロフィール】
新井平伊(あらい・へいい)
1984年順天堂大学大学院修了。東京都精神医学総合研究所精神薬理部門主任研究員、順天堂大学医学部講師、順天堂大学大学院精神・行動科学教授を経て、2019年よりアルツクリニック東京院長。順天堂大学医学部名誉教授。アルツハイマー病の基礎と臨床を中心とした老年精神医学が専門。日本老年精神医学会前理事長。1999年、当時日本で唯一の「若年性アルツハイマー病専門外来」を開設。2019年、世界に先駆けてアミロイドPET検査を含む「健脳ドック」を導入した。

発達障害の子を育てる本 スマホ・タブレット活用編
健康ライブラリー
ひと目でわかるイラスト図解
《講談社 健康ライブラリースペシャル》
【すぐに使えて、一生役立つ“支援ツール”の徹底活用法!】
「発達障害」の子どもたちは、読み書きや計算、会話などを苦手としています。それが学校生活への不適応につながってしまうことが多く、徐々に自信を失い、学ぶことに意欲をもてなくなっていき、ときには不登校につながることもあります。
そうなる前に、その子に合った学び方を考えましょう。一般的な学び方では才能をなかなか発揮できない子がスマホやタブレットなどのツールを使うことで、学びやすい環境を手に入れ、力を発揮できるようになることがあります。
まずは、家庭で子どもといっしょに使ってみましょう。小学校入学以降で、子どもの生活や学習に困りごとが増えたときに、勉強以外の身近なことから使い始めるとよいでしょう。
本書では、音声読み上げ、音声教材、ノートアプリ、計算支援、思考整理、予定管理などのすぐに使えるソフトやアプリの紹介をはじめ、家庭での適切な使い方、学校での導入の流れや「合理的配慮」、進級・進学先への「移行支援」についても事例をまじえてくわしく解説します。
子どもの生活や学習の困難に対して、家庭や学校で何ができるのか。保護者の方だけでなく、ツールの支援を検討されている先生方にも役立つ一冊です。
【スマホ・タブレットを活用して“学べる環境”を整えよう】
*文字や文章の読みづらさは音声読み上げ・音声教材を使う
*文章の入力・画像の添付ができるノートアプリでノート代わりに
*作文や発表の前にマッピングアプリで考えを整理する
*書きとりが苦手なら、録音・撮影・音声入力で補う
*予定の管理に使えるアプリやツールで忘れ物や遅刻を減らす
*学校と「合理的配慮」を相談するときは
*「ひとりだけ特別扱い」と指摘されたら
【本書の内容構成】
第1章 今日からテクノロジーを活用しよう!
第2章 なぜ発達障害の子に役立つのか
第3章 まずは家庭で使ってみよう!
第4章 授業やテストにも使っていこう!
第5章 進学先でも将来も、ずっと使い続けよう!
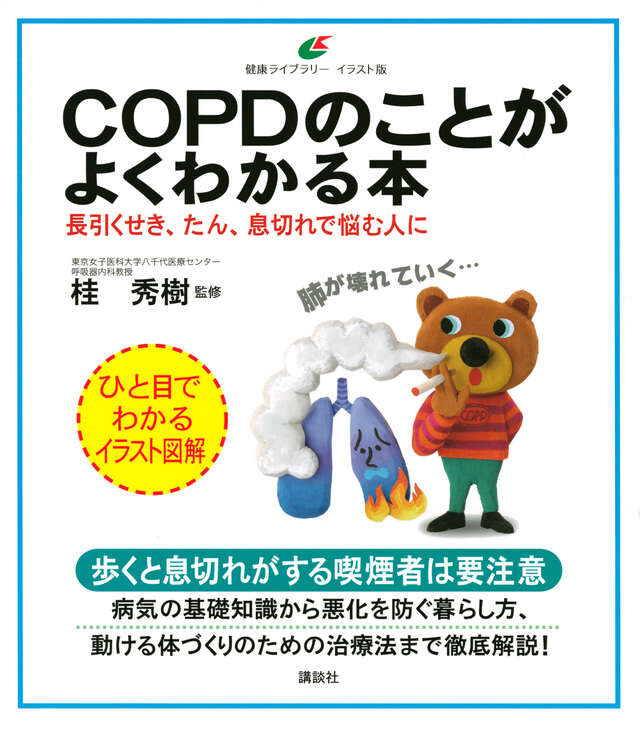
COPDのことがよくわかる本 長引くせき、たん、息切れで悩む人に
健康ライブラリー
ひと目でわかるイラスト図解
《講談社 健康ライブラリーイラスト版》
【歩くとすぐ息切れする喫煙者は要注意】
COPD(慢性閉塞性肺疾患)は、「肺の生活習慣病」といわれ、長年の生活習慣の結果として現れます。大きな原因は、タバコです。タバコの煙によって肺や気管支に炎症が起こって傷つき、咳や痰が出て呼吸がしづらくなります。喫煙者でふだんから咳や痰がよく出る、歩くとすぐ息切れがする、という方は、すでにCOPDが進んでいる可能性が高いと言えます。放置する期間が長いほど、危険度は高くなります。初めての検査で重度のCOPDと診断されることも珍しくありません。呼吸困難によって寝たきりになる危険性もあります。
病気の進行と生活の質(QOL)の低下をもたらす原因は、COPDへの知識不足です。本書では、病気の基礎知識から悪化を防ぐ暮らし方、動ける体づくりのための治療法まで徹底解説します。
【主なポイント】
*COPD(慢性閉塞性肺疾患)は肺胞や気管支で炎症が起こり、肺が壊れる病気
*咳や痰、息切れが代表的な症状で、ゆっくり現れるため気づきにくい
*風邪などで急激に症状が悪化し(「憎悪」)、命を落とすことも
*患者さんの約9割が喫煙者の「タバコ病」
*診断の決め手は「スパイロメトリー」、4段階の重症度がわかる
*禁煙は必須の治療法。新型タバコもNG、完全な禁煙を
*治療の目標は息苦しさを改善して動ける体をつくること
*息切れの重症度で使い分ける「気管支拡張薬」が基本の薬
*運動と食事を中心に「呼吸リハビリ」で動ける体をつくる
【本書の内容構成】
第1章 壊れた肺は元に戻らない――基礎知識
第2章 肺や体の機能を調べる――検査と診断
第3章 息苦しさを改善する――禁煙と薬物療法
第4章 動ける体をつくる――呼吸リハビリ
第5章 悪化のサインは見逃さない――緊急時の対処
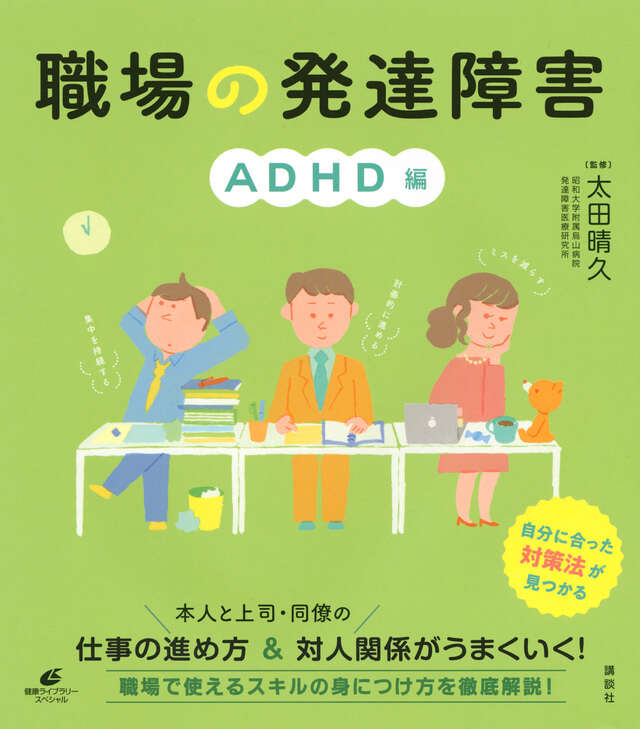
職場の発達障害 ADHD編
健康ライブラリー
ひと目でわかるイラスト図解
《講談社 健康ライブラリースペシャル》
【社会に出て困難に直面しているADHDの方へ】
ADHDは、正しくは注意欠如・多動症といいます。その名のとおり、不注意・多動性とそして衝動性が主な特性です。どの特性が強い状態になっているかは、人によって大きく異なりますが、社会に出てからの困難は、一般の人の想像以上です。
本書では昭和大学附属烏山病院の発達障害専門外来のデイケアで行われている成人のADHD向けのプログラムを参考に、実践的な内容を盛り込み、より具体的に図解しました。社会に出て困難に直面している方や、発達障害の人を受け入れている職場の方たちへの参考になるように、図解でポイントを示していて、 “ストレスなく読める”一冊です。
【職場で使えるスキルアップのヒント】
●ワーキングメモリの不足分をカバーする
●自分が集中できる時間を把握する
●全体像をつかめば、今やることが見える
●気分をもりあげて、先延ばしにしない
●時間を守れない原因をつきとめる
●「口にチャック」と「笑顔」で失言を防ぐ
●周囲と話のペースや量を合わせる
●「アンガーマネジメント」でトラブルを防ぐ
●多動性による言動をコントロールする
【本書の内容構成】
巻頭 自分を理解しよう
1 働きやすくするために 仕事の進め方
2 働きやすくするために 対人関係
3 働きやすくするために 自己管理
4 職場の人へ 特性を理解しよう
5 自分と医療ができること
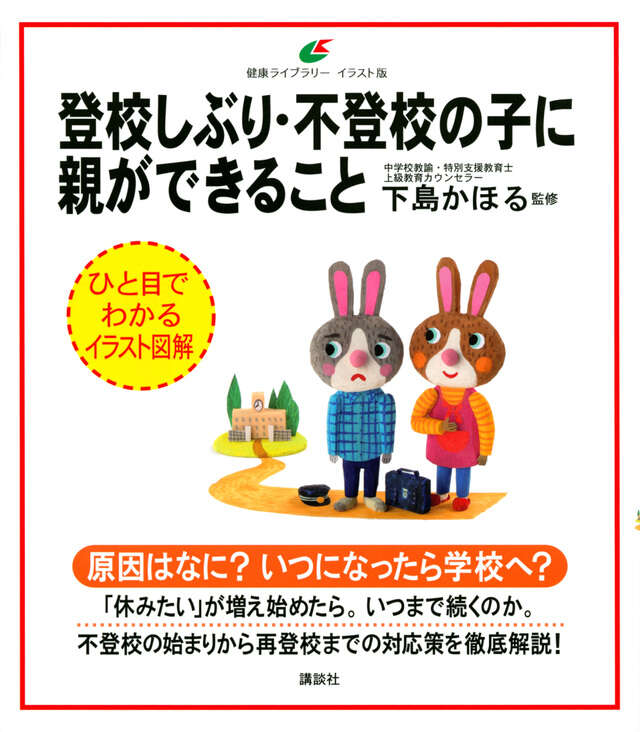
登校しぶり・不登校の子に親ができること
健康ライブラリー
ひと目でわかるイラスト図解
《講談社 健康ライブラリーイラスト版》
【時期を見きわめて働きかけ方を変えよう!】
不登校には「3つの時期」があります。
体調不良を訴えるなど、学校を休む日が増え始める「不登校開始期」、ほとんどを家庭で過ごすようになる、不登校まっただなかの「ひきこもり期」、学校や進路のことを気にするような発言や外出も増えてくる「回復期」。
時期によって子どもの状態は違います。不登校対策は、時期を見きわめて働きかけを変えることが必要です。本書ではその時期ごとに、子どもへの言葉がけや接し方をイラスト図解でわかりやすく紹介。さらに学校との関わり方、再登校・進学に向けての注意点、「元の学級・学校に戻る」以外の選択肢などこれからの見通しなども解説します。
子どもの不登校が長くなると失望が強くなったり、自分を責めたり、逃げ出したくなるときもあるかもしれません。親自身に余裕がないと、子どもに対してなかなかうまく対応できないもの。最終章では、こうした親の悩みも軽くするコツもアドバイスします。
【働きかけ方の主なポイント】
《不登校開始期》
*「行きたくない理由」を否定しない
*「しばらく休む」もの選択肢のひとつ
* 説得より、子ども自身に考えさせる
《引きこもり期》
*学校とのつながりは保ち続ける
*最低限のルール「起床時間」を守らせる
*ゲームやネットとのつきあい方は家族ぐるみで見直す
《回復期》
*新学期、進級時、進学時は登校再開のチャンス
*激励はプレッシャー。無理せずゆっくり復帰

脳卒中の再発を防ぐ本
健康ライブラリー
ひと目でわかるイラスト図解
《講談社 健康ライブラリーイラスト版》
【“二度目”を起こさないためにできること】
脳卒中は突然起こり、その後の生活を大きく左右します。
また、脳卒中は再発が多い病気です。再発すると初発よりも症状が重くなりやすく、脳の別の部位がダメージを受けて新たな症状が現れることもあります。発症後1年間が最も再発率が高く、この時期は治療を継続中であっても油断は大敵です。
本書は、急性期治療以降の脳卒中の再発予防に取り組むための指針を示した書です。なぜ脳卒中になったか、再発を防ぐためにどうしたらよいかをわかりやすく図解にしました。
脳卒中の多くは、若いころからの生活習慣の結果として起こってきます。脳卒中の治療は日々進歩し、死亡率は低下していますが、再発予防の治療を中断する人が多いことが問題になっています。自宅でも薬の服用と生活習慣の改善を、一生続ける覚悟が必要です。
退院後の「生活」が本当の勝負。二度と脳卒中を起こさず、安心して暮らすために、本書で今すぐできることから取り組みましょう。
【主なポイント】
*脳卒中[脳梗塞・脳出血・くも膜下出血]のタイプを知って対策をとる
*動脈硬化が進んだ血管は脳卒中の治療後も元に戻らない
*血圧・血糖値・血中脂質は薬と生活習慣の改善で徹底管理する
*脳梗塞は血栓を防ぐ薬[抗血小板薬・抗凝固薬]を生涯服用する
*再発可能性の高い未破裂の脳動脈瘤や心房細動は手術を検討
*再発をくり返すと脳神経細胞がダメージを受け認知症や寝たきりに
*安静にしすぎるのは禁物。積極的に歩いて体を動かすこと
*ストレスや疲れは血管の老化を進めるので、ためこまない
*初発とは違うことが多い、知っておくべき再発時のサイン「FAST」

新版 幼児期の発達障害に気づいて・育てる完全ガイド
健康ライブラリー
【対象】幼児期 4歳~就学前まで
【先生・保護者がすぐに使える記入式シートつき】
【発達障害の傾向と対応策がわかる!】
発達障害は、友達の気持ちを理解できない、ルールを守れないなど、社会性を含む心の機能の障害です。保育園・幼稚園や学校という集団社会の中にいるからこそ、問題点が明確になります。集団の中で起こる問題ですから、集団の中で解決しなければ、発達障害を改善することはできません。皆の中で育てることこそが、最善の治療法なのです。
幼児期には、基本的な生活習慣が身につき思考力が発達します。社会的にも心理的にも集団生活の準備が整う時期です。その段階で、発達に障害があることに気づかず小学校に通うようになると、授業についていけない、友達とトラブルを起こすなど、さまざまな問題に直面します。ですから、就学前の適切な対応が必要なのです。
発達障害への対応は、早ければ早いほど良いといわれます。それには気づきが大切です。
本書の特徴は、子どもの日常の行動を見るための「基礎調査票」と、その結果をグラフ化する「評価シート」です。結果をグラフ化することで、容易に支援計画をつくることができます。注意していただきたいのは、結果を見て発達障害だと即断しないこと。まわりの意識と働きかけで、子どもは大きく成長します。伸びる力を信じて、支えていってください。
なお本書は、2008年に発行した『幼児期の発達障害に気づいて・育てる完全ガイド』をDSM-5(精神疾患の診断・統計マニュアル)にあわせて見直した新版です。園の先生だけでなく、保護者、子どもにかかわるすべての大人に利用していただける一冊です。
【実例の一部紹介】
●Dくんの場合~衝動性と多動性がある
園では友達にちょっかいを出すことが多く、皆でなにかをするときも、ひとりだけずっとふざけていて、いくら言ってもまじめにできません。まわりからは、「Dくんと一緒にはやりたくない」という声があがり、それを聞くと本人はかっとしてつかみかかっていくので、トラブルが絶えません。
●Fくんの場合~自閉スペクトラム症傾向が強い
年長組のFくんは、なかなか人と視線を合わせることができません。大好きなのはレールをつないで電車ごっこをすること。それさえしていれば、機嫌よく遊んでいます。ただし、ほかの友達がレールに触ろうものなら、怒り出して大騒ぎになります。
●Hちゃんの場合~パニックを起こす
センターに来たときも、母親のひざから下りず、一緒に遊ぼうとしても「いや!」の連発でした。そんなにいやなら、帰るときはさぞうれしそうかというと、今度は帰りたくないと騒ぎ、通路に大の字になって大泣きです。

なかなか治らない難治性のうつ病を治す本
健康ライブラリー
ひと目でわかるイラスト図解
《講談社 健康ライブラリーイラスト版》
【不要な薬を整理し、心の回復力をつける】
うつ病の多くは数ヵ月から長くても2年以内に回復することが一般的ですが、
長年まじめに治療を受けているのに治らない方がいます。
しかも5年、10年どころか、20年以上も治らない難治のうつ病に悩む方は
少なくありません。なぜうつ病は治らない病気になったのでしょうか。
抗うつ薬、抗不安薬、睡眠薬……多くの薬を漫然と飲んでいないでしょうか。
不安や恐怖が消えない、眠れない……病気のせいと思っている症状のかなりが、
じつは飲んでいる薬や長期の療養生活のせいです。
一方で、多くの薬が悪いからと減薬や断薬に失敗して病状が悪化し、
苦しむ方も非常に多くなり、対策も必要になっています。
本書では、回復を妨げる心理から、治療法の見直し方、効果のない薬の
整理の仕方までイラストやチャートを使い、わかりやすく解説。
なんとか治ってほしいと願うご家族へのアドバイスも紹介します。
長引くうつ病で苦しむ患者さんを絶望から救う決定版!
【主なポイント】
*何年も何十年もうつ病が治らない理由
*うつ病から双極性障害と診断が変わることも多い
*薬がうつ病や双極性障害を治りにくくした
*休養をとりすぎることの悪影響も
*長引くうつ病は診たて直しでゼロから診断を
*長期投与・多剤投与を見直し、効果のない薬を整理する
*減薬、断薬は絶対に自己流でやらないこと
*家族だけで抱え込まない、対応のコツと注意点
*うつから抜けるための「五ヵ条」
【本書の内容構成】
ケース集 つらく苦しい日々から抜けられた
第1章 何年も何十年も治らない理由
第2章 絶望はどこからくるか
第3章 効果のない薬を整理する
第4章 心の回復力をつける
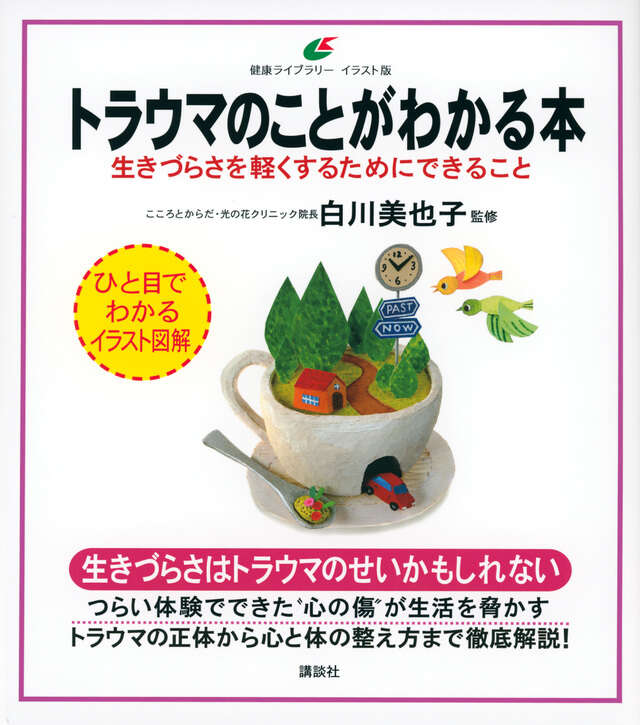
トラウマのことがわかる本 生きづらさを軽くするためにできること
健康ライブラリー
ひと目でわかるイラスト図解
《講談社 健康ライブラリーイラスト版》
【生きづらさはトラウマのせいかもしれない】
トラウマとは「心的外傷」のこと。なんらかの体験により、心が本来の役割を果たせなくなった状態を指します。
災害、犯罪被害、性暴力など、非日常的な恐怖体験がトラウマになることはよく知られていますが、虐待やネグレクト、子どもの面前でくり返されるDV、言葉の暴力など、日常的にくり返される出来事が心に傷を残し、より複雑な影響を与えることがあります。
非常につらい、危険な体験をしたことでできた心の傷は、心身にさまざまな影響を及ぼし、生きづらさのもとになることがあります。
本書はトラウマのでき方や症状の現れ方、トラウマの影響が長引く原因を解くとともに、最新の専門的治療法や多様な取り組み方を紹介します。
生きづらさを抱える人たちには、回復のための第一歩を踏み出すきっかけになる、また、ご家族やご友人、専門職の方には支援の手助けになる一冊です。
【本書の内容構成】
◆第1章 生きづらさをまねくトラウマの症状
◆第2章 トラウマの影響はなぜ長引くのか?
◆第3章 これからの目標と道のりを見定める
◆第4章 「今」への影響を変える心理療法
◆第5章 回復しやすい体をつくる毎日のケア

100歳まで自分の歯を残す4つの方法 改訂新版
健康ライブラリー
【ちょっと待って! その歯を抜くのはまだ早い】
歯科医の言われるままに歯を抜いてしまうと、次から次に歯を失う悪夢の連鎖が始まります。最後まで自分の歯を残そうと思ったら、できるだけ自分の歯を温存することが大切。最近はインプラント治療の普及に伴い、安易に抜歯に走る歯科医が多いので要注意ですよ!
TCH是正のため独自に考案した「歯を離せシール」(人気絵本作家ヨシタケシンスケ作)の新作を収録。
正しいブラッシング法を教える歯みがきポスターと併せ豪華3大付録付き。画期的解説書の改訂新版!
私たちはなぜ大事な歯を失ってしまうのでしょうか。歯を失う2大原因といわれるのが、虫歯と歯周病です。実に歯を失う原因はこの2つが90%近くを占めています。いずれも食習慣や歯みがきなどの生活習慣と密接不可分の関係にある、いわゆる「生活習慣病」です。逆説的にいえば、問題となる生活習慣を改善すれば、虫歯や歯周病とは無縁の生活を送ることができます。しかし、 なかなかどうして一度身体に染みついた生活習慣を正すことは簡単ではありません。
また、最近の歯科学の研究で、意外な生活習慣が歯の健康に悪影響を与えていることがわかってきました。従来はていねいなブラッシングと歯科医師による定期的な口腔ケアを励行しておけば、歯を失うことはないといわれてきましたが、実はそれだけでは不十分だったのです。鍵を握るのが、無意識のうちに上下の歯をつけるTCHという癖です。自分の歯を最後まで残そうこと思ったら、このTCHを是正しなければなりません。本書では虫歯や歯周病予防、そしてTCH是正を通じて、自分の歯を最後まで残すための実践的なテクニックを紹介します。
この改訂新版では、さらに治療効果を高めたTCH是正法、むし歯・歯周病予防法など最新情報をアップデートするとともに、人気絵本作家ヨシタケシンスケさんの協力で完成したTCH是正のための「歯を離せシール」新作を収録。正しいブラッシング法を教える歯みがきポスターなど豪華3大付録付きです。
【電子版にはシールやポスターは付属しません】

職場の発達障害 自閉スペクトラム症編
健康ライブラリー
ひと目でわかるイラスト図解
《講談社 健康ライブラリースペシャル》
【職場で使えるスキルの身につけ方を徹底解説!】
大人の発達障害のうち、近年受診が増えているのが自閉スペクトラム症(ASD)の人たちです。知的障害がなくIQも高い人たちは、社会に出るまで発達障害に気づかれず、働きはじめてから困難に直面します。このような発達障害者の急増にともない、医療機関の治療法として、近年注目されはじめたデイケア。発達障害の人が社会適応するスキルを身につけることができます。
本書は成人発達障害の専門機関の先駆けとして注目されている昭和大学烏山病院の発達障害専門外来・デイケアでのASD専門プログラムに実際に参加した当事者の声、支援者の声を参考に、職場でのリアルな困り事とその対応策をより具体的に紹介します。会話の仕方やコミュニケ―ションのとり方、仕事の進め方……、社会に出て困難に直面している場面で役立つように、図解でポイントを示した見開き100ページで“ストレスなく読める”一冊です。また本人に働きつづけてもらうためには職場の人の理解と支援は不可欠。雇用サイドへのアドバイスも紹介します。
【本書の内容構成】
巻頭 自分を理解しよう
1 働きやすくするために 対人コミュニケーション
2 働きやすくするために 仕事の進め方
3 働きやすくするために 自己管理
4 職場の人へ 特性を理解しよう
5 自分と医療ができること

新版 潰瘍性大腸炎・クローン病がよくわかる本
健康ライブラリー
くり返す下痢、腹痛、血便は異変を告げるサイン。正しい知識で取り組めば怖くない! 続々登場する新薬を詳しく解説した待望の決定版

発達障害の人の「就労支援」がわかる本
健康ライブラリー
発達障害の人は、知識や技術をいかして就職することはできても、人間関係などに悩んで職場になじめず、結果として、退職してしまう。そのような問題を防ぐために、職場定着までをみすえて支援するケースが増えている。本書では、就職活動から職場への定着、生活面まで就労支援のしくみと活用の仕方をイラスト図解。就労支援の全体像やポイントを手早くおさえられる。当事者だけでなく、受け入れる企業側にも参考になる一冊。
ひと目でわかるイラスト図解
《講談社 健康ライブラリースペシャル》
【1冊で丸ごとわかる!就労支援活用ガイド】
発達障害の人への就労支援が年々、広がりをみせています。
発達障害の人の場合、知識や技術をいかして就職することはできても、
人間関係などに悩んで職場になじめず、結果として、退職してしまうことがあります。
そのような問題を防ぐために、職場定着までをみすえて支援するケースが増えています。
就労支援にはさまざまな形式がありますが、基本的な内容や流れは共通しています。
本書では、就職活動から職場への定着、生活面まで就労支援のしくみと活用の仕方をイラスト図解。
本書を読んでいただければ、就労支援の全体像やポイントを手早くおさえていただけます。
就労支援を利用する当事者はもちろん、その当事者を受け入れる企業側にも、
参考にしていただける内容です。
発達障害の就労支援を知るための最初の一冊として、ぜひご活用ください。
【本書の内容構成】
1 発達障害の人の「働きづらさ」とは
2 働きづらさは「就労支援」で解消できる
3 本人も会社も利用できる「3つの就労支援」
支援1/適職をみつけて「就職」を成功させよう!
支援2/環境調整で「職場定着」をサポート
支援3/仕事を支える「生活」も大切に

リンパ浮腫のことがよくわかる本
健康ライブラリー
がん治療後の腕や脚の慢性的なむくみ。完治は難しいが適切な対応で生活に支障を来す状態は防げる。誰もがかかえる不安と悩みに応える