創文社オンデマンド叢書作品一覧

徳川時代の文学に見えたる私法
創文社オンデマンド叢書
法制史の淵源には法的淵源と非法的淵源がある。非法的淵源はその正確の度において、法的淵源には及ばないところがあるが、非法的淵源には前者の欠けている点を補ったり、その実際の意義を解明するのに効用があると思われる。本書は、徳川時代の私法を当時の非法的淵源である文学作品によって、説明するところにある。特に、浄瑠璃(とくに世話物)と小説(とくに浮世草子)をその史料として扱う。また、その扱う史料は当時の上方(大坂)が舞台となることが多いので、その私法の実態はその地方に特有のものが多いかもしれない。また、時代的には貞享ー安政年間を扱うが、元禄ー安永年間のものが多い。
【目次】
一 動産質
二 動産抵当
三 人質
四 家質
五 手打
六 手附
七 売買
八 家借
九 地借
一〇 借株
一一 借金
一二 入札
一三 為替手形、振手形、預り手形
一四 分散
一五 元服
一六 婚姻
一七 離婚
一八 夫婦財産制
一九 養子
二〇 親権
二一 相続
二二 遺言
二三 隠居
二四 後見
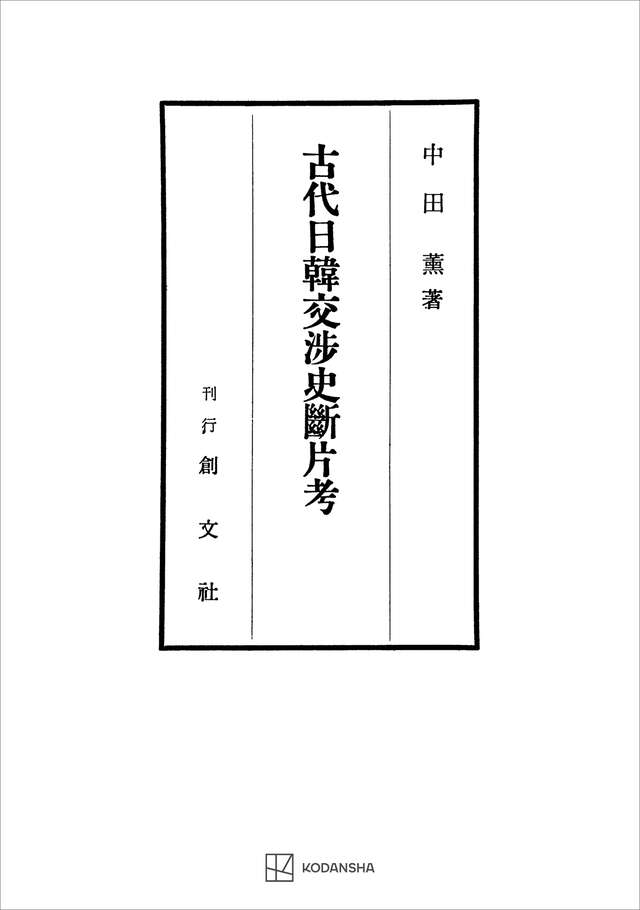
古代日韓交渉史断片考
創文社オンデマンド叢書
法制史家が、古代における、日本と朝鮮半島の国との交渉を巡る記録を読み、その意図や経緯、結果を探る。
【目次】
小序
第一 天日槍考
第二 蘇那曷叱知考
第三 神功皇后征韓年代考
第四 木満致考
第五 延烏細烏考
第六 八俣遠呂智考
第七 倭人考 緒言 (一)倭女王国成立前後 (二)奴国と狗奴国 (三)狗邪韓国 (四)邪馬台 (五)卑奴母離
第八 古代日韓航路考 緒言 (一)神代 (甲)南方航路 (乙)出雲航路 (二)倭人新羅侵入航路
補遺
引用書
索引
附図 1 朝鮮疆域誌上ノ巻首新羅図 2 大韓地誌百六十四、五間平安南道 3 大東輿地図慶州附近地図
附録 日本古代歴世年代考

アジアにおけるキリスト教比較年表
創文社オンデマンド叢書
アジア各国(日本、韓国、中国など)における、キリスト教に関連する出来事を年表形式にまとめたもの。対象期間は、1792年から太平洋戦争の終戦である1945年となる。
【目次】
まえがき
凡例
Appendix
アジアにおけるキリスト教比較年表

日本キリスト教文献目録(明治期)
創文社オンデマンド叢書
日本で明治期に刊行されたキリスト教関連の文献を詳細に分類して収録した貴重な基本図書。
【目次】
序文 (鵜飼信成)
刊行のことば (長 清子)
目次
凡例
図書館・文庫表
主要参考書
A キリスト教書
0 総記
書目・辞典
教理・神学
神・神の業
信条・教理問答
1 キリスト
キリスト論
聖家族
2 聖書
旧新約聖書
旧約聖書
新約聖書
3 聖書釈義
総記
旧約聖書
新約聖書
4 教会
教会論・聖職・修道会
教会史
5 典礼
ミサ・礼拝・公祷書
主日・教会暦
典礼
讃美歌
6 牧会
牧会学・説教学
宗教々育
伝道用書
7 信仰生活
B 対外活動
0 総記
宗教論・護教書
1 思想
哲学・論理
心理
倫理
2 歴史・地理
日本史
東洋史
西洋史
伝記
地理
3 社会
政治・法律
経済・社会
社会事業
矯風事業
家庭・婦人
4 教育
5 自然科学
6 産業
7 美術・音楽
美術
音楽
8 語学
9 文学
評論・随筆
日本文学
外国文学
C 関係書
0 総記
宗教総記
反キリスト教書
神道
仏教
1 思想
哲学・論理
心理
倫理・人生論
2 歴史・地理
日本史
東洋史
西洋史
伝記
地理
3 社会
政治・法律
経済・社会
社会事業
矯風事業
家庭・婦人
4 教育
5 自然科学
6 産業
7 美術・音楽
美術
音楽
8 語学
9 文学
評論・随筆
日本文学
外国文学
D 逐次刊行物
1 キリスト教関係誌
2 一般誌
追補
索引
1 書名索引
2 著訳者名索引

Christianity in Japan
創文社オンデマンド叢書
イエズス会の宣教師ザビエルによるキリスト教伝来から江戸末期までの日本と中国におけるキリスト教文献を紹介する貴重な資料集である。明治以前の日本とアジアにおけるキリスト教の状況を知るための重要な基本図書である。
【目次】
Preface
Foreword
Explanatory Notes
Abbreviations
List of Libraries
List of Sources
Abbreviations (Missions in Japan and China)
Table of Japanese and Chinese Era Names
CHRONOLOGICAL LIST OF BOOKS (1543-1858)
Appendix Alphabetical List of Collectanea
Index
(a) Title
(b) Author, Translator, Compiler and Others
(c) Subject

言葉の連合
創文社オンデマンド叢書
心理学者が考える言葉の本質とは? 言語習得において、「連合」はどのような役割をはたすのかに迫る。
【目次】
第I章 序論
1 研究方向の位置づけ
2 対連合学習の方法
3 問題提出
第II章 言語材料の諸次元
1 意味
2 有意味度(meaningfullness)
3 熟知性(familiarity)
4 情動性(emotionality)その他
5 明瞭さ (intelligibility)と発音しやすさ(pronunciability)
6 討論と結論
第III章 リスト構成の諸変数
1 類似性
2 項目間連想度(inter-item association)
第IV章 対連合学習の変数としての言語材料及びリスト構成の諸次元
1 有意味度
2 熟知度
3 感情性の諸次元
4 発音の容易さと認知しやすさ
5 リスト内類似度
6 孤立効果
7 総括
第V章 対連合学習の学説
1 Gibson説
2 対連合学習の過程の分析(著者の説)
3 文献展望
4 要約(著者の説との関係)
第VI章 弁別と習得(S弁別・R項目習得説の証明)
1 弁別学習と項目習得学習
2 弁別学習の諸変数
3 項目習得の諸変数
4 自由再生と系列再構成の関係
5 S弁別,R習得説の証明
第VII章 順逆再生勾配(S弁別説の証明)
1 有意味度
2 熟知度
3 リスト内類似度
4 孤立効果
5 順逆再認勾配
6 自由再生
要約
第VIII章 Sの偶発学習説の証明
1 逆またはS再生と偶発学習実験の結果との比較
2 選択仮説その他
第IX章 対連合の方向性
1 逆連合の性質
2 方向性因子の存在証明
3 逆再生のレミニッセンスと方向性禁止説
4 方向性連合と対材料の性質
第X章 対内関係と対間関係
1 対内関係I(媒介連合)
2 対内関係II(体制化の要因)
3 対内関係と対間関係の交互作用
4 総括
文献

国民所得分析(現代経済学叢書)
創文社オンデマンド叢書
マクロ経済学の重要なジャンルである国民所得の分析手法を紹介する。生産、分配、支出を統計的に分析し、国民経済活動の水準や規模を検証し、生産・分配・支出の相互関係や因果関係を解明する。
【目次】
序
第一章 経済循環のモデル
第一節 基本的モデルの構成
第二節 経済循環の構造
第三節 経済循環における貯蓄と投資
第四節 国民所得分析の意義
第二章 国民所得の概念とその測定
第一節 予備的説明一 国民所得概念の意義 二 富と所得 三 実質所得と貨幣所得
第二節 国民所得の概念
第三節 国民所得の測定
第四節 実質国民所得の評価
第五節 所得不平等度の測定
第三章 国民所得会計
第一節 企業の取引とその会計
第二節 国民生産物勘定
第三節 セクター勘定体系
第四節 国民経済計算
第四章 国民所得水準の決定
第一節 概説
第二節 消費と貯蓄
第三節 投資
第四節 所得水準の決定
第五節 貨幣と所得
第五章 国民所得水準の変動
第一節 消費及び貯蓄性向の変化と所得
第二節 貨幣供給の変化と所得
第三節 貨幣需要の変化と所得
第四節 投資と利子率との関係の変化
第五節 投資の変化と所得
第六節 国民所得と雇傭水準
第六章 国民所得水準の安定
第一節 安定政策の意義
第二節 財政政策と国民所得水準
第三節 財政政策による安定化の限界
参考文献
索引

人間・社会・歴史(フォルミカ選書)
創文社オンデマンド叢書
アメリカの自由主義神学者ニーバー(1892~1971)は、「正義を取り扱うことのできる人間の能力が民主主義を可能にする。しかし、不正義に陥りがちな人間の傾向が民主主義を必要とする」と主張した。ユートピア主義を批判し、リアリズムに基づき政治や社会問題にも積極的に発言を繰り返した。その影響力は大きく、キング牧師や歴代の大統領も重要性を認めている。
ニーバーの生涯と思想を紹介する格好の入門書。
【目次】
一 ニーバーの人と思想
道徳的人間と不道徳的社会 問題の提起
右への革命と左への革命 ニーバーという人
二 近代人間観の課題
二つの人間観の相克 ルネサンスとリフォメーション
二つの世界とキリスト教 デモクラシーとマルキシズムの人間観
三 近代歴史観の問題
革命に対する「イエス」と「ノー」
時の徴の見分け
四 キリスト教と今日の世界
光の子と闇の子
絶対平和主義と現実主義
アメリカ史のアイロニー
五 ニーバーに影響を与えた人々
ニーバー夫人
パウル・ティリッヒの歴史観
著作文献
あとがき

国際金融の政治経済学(数量経済学選書)
創文社オンデマンド叢書
国際金融論・ゲーム理論の分野で世界的業績をあげた著者は、バブル崩壊後の経済停滞の理由を金融政策の失策として、日本銀行の金融政策を批判した。著者の専門である、国際金融論・ゲーム理論の立場から、国際金融におけて政治と経済がどのような役割を果たすのかを解き明かす。
【目次】
はしがき
第I章 序説
1 はじめに
2 本書の方法と構成
第II章 国際通貨制度の選択
1 はじめに
2 国際通貨制度と国民的利害
3 国際通貨制度選択のゲーム論的分析
付論 ゲーム理論と寡占理論の基礎概念
第III章 通貨統合の政治経済学 公共経済学による接近
1 はじめに
2 通貨統合の便益と費用
3 政治的参加の理論 参加算術
4 歴史的観点からみた通貨統合
5 結び
付論 参加算術の数学的定式化
第IV章 ケインズ型モデルにおける貨幣政策の国際的連関
1 はじめに
2 政策の相互連関に関する諸研究
3 ケインズ型モデルにおける戦略的分析
4 固定為替制度における貨幣政策の連関
5 変動為替制度における貨幣政策の独立性
6 結び
第V章 貨幣政策連関の戦略的分析 価格伸縮モデル
1 はじめに
2 貨幣政策の相互依存関係の定式化
3 グラフと代数式による実例
4 長期的分析と準備通貨国の役割
5 結び
付論 微分ゲームとしての世界マネー・ゲーム
第VI章 為替制度と交易条件変動の効果
1 はじめに
2 基本的な枠組
3 固定為替制度
4 変動為替制度
5 変動為替制度における非貿易財の役割
6 結び
付論 貨幣保蔵と支出行動のミクロ的基礎
第VII章 為替制度とスタグフレーションの国際的波及
1 はじめに
2 二国モデルの枠組
3 変動為替制度
4 固定為替制度
5 モデルの一般化
6 要約と結論
数学付録
第VIII章 管理フロート制下における貨幣的連関
1 はじめに
2 モデルの枠組
3 価格伸縮経済における為替レートに関する政策の国際的相克関係
4 管理フロート制下における景気循環の波及
あとがき
参考文献
索引

現代哲学の系譜
創文社オンデマンド叢書
現代思想の出発点となる哲学・思想が登場したのが、19世紀後半である。新カント派、ドイツ観念論、マルクス主義、科学的唯物論、実存主義、プラグマティズム、功利主義、精神分析など、現代につながる哲学的な流れを解説する。
【目次】
序
第一章 現代哲学の源流としての十九世紀後半の哲学
第二章 近世精神史の動向と十九世紀前半の哲学
第三章 十九世紀後半の哲学の出発点としてのヘーゲル批判
シェリングのヘーゲル批判
トレンデレンブルクのヘーゲル批判
キェルケゴールのヘーゲル批判
ショペンハウァのヘーゲル批判
ブルクハルトのヘーゲル批判
ニィチェのヘーゲル批判
フォイエルバハのヘーゲル批判
マルクス・エンゲルスのヘーゲル批判
第四章 ヘーゲル批判を基盤として展開される新しい哲学思想
シェリングの積極哲学
キェルケゴールの実存哲学
ショペンハウァの意志哲学
ブルクハルトの歴史哲学
ニィチェの生の哲学
フォイエルバハの人間学
マルクス・エンゲルスの社会哲学
シュティルナァの自我哲学
ハルトマンの無意識の哲学
ワークナァの楽劇の哲学
マインレンダァの死の哲学
第五章 十九世紀後半の哲学の批判とその二十世紀の哲学との関係
十九世紀・二十世紀哲学思想史年譜表
註
人名索引

現代日本の政治意識
創文社オンデマンド叢書
戦後の1950年台における日本の左傾化を論じたもので、当時の日本の政治状況をめぐっての発言。当時の日本の政治を知るための史料として貴重である。
【目次】
はしがき
戦後右翼ナショナリズムの萌芽形態 日本革命菊旗同志会の場合
一 問題の所在と団体の歴史
二 イデオロギー的特質
三 団体の生理とその限界
四 心理とパースナリティの問題
むすび 戦後右翼の命運についての私見
右翼ナショナリズムにおける戦後的特質の所在 その思想的立場の問題
一 問題的視点
二 生理的反動グループ
三 戦後右翼の特徴
四 民族新生運動の思想
五 協和党の思想
むすび
民衆政治意識の基調
一 混迷と停滞のなかにあるもの
二 民衆意識の私的領域における分散と停滞
三 政治意識における多元的複合性と非分極化傾向
補
中間層指導者層の政治意識
一つの問題提起
一 地方指導者の発想方式の特色
二 集計全般にあらわれた共通の特徴点
三 階層別・学歴別・支持政党別集計等にあらわれた主要な特色
むすび
青年層の政治意識
総括的分析
一 世代の断層が意味するもの
二 生活感情の新しさと古さ
三 民族意識の分散と停滞
四 政治意識における連続と断絶
むすび
労働者層の政治意識
一 労働者意識の一般的傾向
二 問題別に分析した諸結果について
むすび
補論 ボス的政治指導者の問題
一 ボスとは何か
二 ボス的指導者の実力と機能
三 ボス的政治指導者を生む社会的背景になるもの
付記
付表

インドネシア民族主義研究(東南アジア研究叢書)
創文社オンデマンド叢書
社会の分断が進んでいるなかで、インドネシアが多民族国家であり続けるのはなぜだろうか? その理由を歴史的な経緯に探り、根源へと迫る力作。ナショナリズムについて考える際の必読書である。
タマン・シスワTaman Siswaとは「学童の園」という意味の私立学校の呼称で、1922年にジャワ島中部の古都ジョクジャカルタ市に誕生した。設立者はラデン・マス ・スルディ・スルヤニングラットという当時34歳の貴族であった。
「タマン・シスワは、1920年代を通じてジャワ各地に分校が相ついで設立され、1920年代末からはジャワのみならずスマトラやカリマンタン、スラウェシなどインドネシア各地に拡大していった。タマン・シスワは、たんに特異な私立学校として当時の植 民地社会で注目されただけでなく、それが持つ民族主義的性格と文化運動としての重要性によってインドネシア独立運動史上、まことに注目に値する教育活動であった。」(「タマン・シスワの成立と拡大」土屋健治より)
【目次】
はしがき
序 課題と方法
第一章 クビジャクサナアン概念
第二章 タマン・シスワ成立前史I(「原住民委員会」事件 一九一三年) ナショナリスト・インテリゲンツィアの登場
第三章 タマン・シスワ成立前史II(一九一三年~一九二二年) ジャワ知識人の西欧認識
第四章 タマン・シスワの成立と拡大(一九二二年~一九三〇年)
第五章 組織化I(東ジャワ会議 一九三〇年)
第六章 全国大会(一九三〇年)
第七章 〈人民主義〉と〈聖なる家族〉の思想 スディヨノとデワントロ
第八章 組織化II(全国大会以降 一九三〇年~一九三二年)
第九章 「私学校条令」闘争
結章 「民主主義と指導性」理念
資料一 『もし私がオランダ人であったならば』
資料二 『言語と民族』
資料三 『ラービンドゥラナート・タゴールとわれわれの関係』
資料四 タマン・シスワ学校の状況(一九三五・三六年)
引用文献
人名索引
事項索引

哲学論(フォルミカ選書)
創文社オンデマンド叢書
戦後日本にアメリカのプラグマティズムを紹介した哲学者・評論家による、「哲学」概論。
【目次】
目次
第一部 哲學の中で
哲學の反省
哲學批評について
哲學の言語
第二部 哲學の外に
日常の論理
日本思想の特色と天皇制
佐々木邦の小説にあらわれた哲學思想
あとがき

日本法制史講義
創文社オンデマンド叢書
日本法制史研究家の二大巨頭による講義。日本の法制が時代とともにどのように変化したのか、その背景にはどういった考え方があるのかをわかりやすく解説する。
【目次】
日本公法法制史
第一編 上古(建国より武家政治開始まで)
第一期 大化前代
序論
第一章 国初に於ける人種的関係
第二章 外国文化の輸入
本論
第一章 天皇
第二章 人民の階級
第三章 官位の制(中央管制)
第四章 地方制度
第五章 土地制度
第六章 財政
第七章 兵制
第八章 法源
第九章 刑法
第二期 大化後代
序論
第一章 大化の改新
第二章 律令の編纂
本論
第一章 天皇及皇族
第二章 中央官制
第三章 官吏法及位階法
第四章 氏姓制度の変遷
第五章 人民の階級
第六章 地方制度
第七章 戸籍、計帳
第八章 土地制度
第九章 財政
第十章 兵制
第十一章 庄園(荘園)
第十二章 法源
第十三章 刑法
第十四章 裁判所
第二編 中世(鎌倉幕府開設より関ヶ原合戦まで)
第一章 天皇及朝廷
第二章 将軍及幕府
第三章 人民の階級
第四章 庄園の変遷
第五章 封建制度の発達
第六章 地方制度
第七章 土地制度
第八章 財政
第九章 軍制(略)
第十章 法源
第十一章 裁判所(略)
第十二章 刑法
第三編 近世(徳川時代)
第一章 将軍及幕臣
第二章 天皇及朝廷
第三章 中央官制
第四章 人民の階級
第五章 地方制度
第六章 土地制度
第七章 財政
第八章 封建制
第九章 軍制(略)
第十章 法源
第十一章 裁判所(
第十二章 刑法
日本私法法制史
第一編 上古
第一期 大化前代
第一章 法源
第二章 私法
第二期 大化後代
第一章 法源
第二章 私法
第二編 中世
第一章 法源
第二章 私法
第三編 近世
第一章 法源
第二章 私法
附録
古在氏の想出
あとがき(石井良助)

アウグスティヌスからアンセルムスへ
創文社オンデマンド叢書
カトリック教会の司教、神学者・哲学者アウグスティヌス(354-430年)の思想は、後のカンタベリー大司教アンセルムス(1033-1109年)にどのような影響を与えたのだろうか? アンセルムスはアウグスティヌスから何を継承し、自らの思想として発展させたのか。知識をもって悟る、「知解」をめぐる神学思想史。
【目次】
まえがき
一 知解を求める信仰 序説として
二 アウグスティヌスの創造思想 無からの創造と言葉による創造
三 アウグスティヌスの三位一体論 『三位一体論』五―七巻
四 解釈学的トポスとしての〈神の像〉 『三位一体論』八―一五巻
五 神の遍在と永遠について 『モノロギオン』二〇―二四章
六 アンセルムスの三位一体論 『モノロギオン』三八章以下
七 『プロスロギオン』における神存在の論証について アンセルムス・カント・バルト
八 神のほまれ 『クール・デウス・ホモ』における贖罪論の根拠と目標
九 アンセルムスにおける‘Entplatonisierung’について
十 神と哲学 哲学史における神の問題
十一 ヘブライ・ギリシア・キリスト教思想
索引・文献表

福祉社会論(現代経済学選書)
創文社オンデマンド叢書
福祉国家批判を契機とした様々な議論は、既成の体制観や人間観あるいは党派性のために、冷静で包括的な検討を阻害しがちであった。本書の目的はそれら知的障害物を打破し、福祉国家を批判的に継承して〈あるべき福祉社会〉のヴィジョンを提出することである。
【目次】
まえがき
第I部 福祉社会の諸前提
1 歴史的諸前提
1.1 福祉国家の危機 福祉国家の再検討 経済危機と福祉国家 など
1.2 福祉国家から福祉社会へ 福祉国家の理念 福祉国家の成立 など
1.3 福祉国家と社会主義 経済体制と経済制度 民主的混合経済体制 など
1.4 経済体制の選択 国家の役割の理解 ケインズ理論の評価 など
2 理論的諸前提
2.1 効率と公平 資源配分の効率 市場経済と分配問題 ナショナル・ミニマムと再分配 など
2.2 経済成長と福祉 経済成長と所得分配 経済成長と完全雇用 など
2.3 資源と環境 人類の危機 持続的社会の条件 など
2.4 主体としての人間 産業社会と人間形成 など
第II部 福祉社会の諸制度
3 就業と職業生活
3.1 就業機会の保障 就業機会の保障の意義 経済政策の選択 など
3.2 雇用問題と社会政策 失業率と欠員率 失業率の目標水準の選択 など
3.3 教育と職業生活 職業と社会的地位 高等教育の規模の選 など
3.4 職業生活の人間化 職場の人間化と労働者参加 産業民主主義の要求 など
4 所得の分配と再分配
4.1 分配と再分配 分配状態の計測 分配状態の評価 など
4.2 財政と租税の制度 財政の機能 租税と公債 など
4.3 社会保障の給付と負担 社会保障の諸制度 所得税と社会保障給付 など
4.4 政府の規模の選択 政府の規模の検討 行政改革の意味 など
5 保健・医療と社会福祉
5.1 福祉社会と社会サービス 社会サービスの供給体制 など
5.2 保健・医療の制度と政策 医療費の給付と医療制度 など
5.3 社会福祉の制度と政策 社会福祉の機能と意義 など
5.4 社会政策と地域計画 地域計画の課題 など
第III部 福祉社会の諸条件
6 都市・家族・人間
6.1 福祉社会と都市政策 住宅問題と都市問題 など
6.2 国家・企業・家族 混合経済体制の再検討 など
6.3 教育と人間形成 教育の目標 など
6.4 福祉社会の展望 現代社会と自由 など
参考文献
索引

公家新制の研究
創文社オンデマンド叢書
「公家新制」は、平安中期から南北朝時代にかけて天皇・上皇の勅旨に基づいて制定された成文法典の呼称である。別名、制符(せいふ)ともされる。最古の新制は、947年に村上天皇が出した新制6ヶ条と呼ばれている。長保元年(999年)に一条天皇・藤原道長体制下で出された長保元年令11条は、後の新制の定形となった。「公家新制」の変遷に時代の変化を読み取る。
【目次】
序文
序章
はしがき
一 公家新制とは何か
二 平安・鎌倉時代の公家新制一覧表
第一章 公家新制の成立 天暦一・一一・一三新制
第二章 平安時代の公家新制
一 天延三年及び天元五年の新制
(一)天延三年新制の史料
(二)天元五年新制の史料
二 一条天皇と新制
(一)永延一・三・五新制
(二)永延一・三・七新制か
(三)永延一・五・五新制
(四)永延二・四・一四新制
(五)正暦年代の新制
(イ)正暦一・四・一新制
(ロ)正暦符
(六)長保年代の新制
(イ)長保一・七・二七新制
(ロ)長保二・六・五新制
(ハ)長保三・壬一二・八新制
三 長和二・四・一九新制
四 白河・鳥羽両院時代の新制
(一)永久四・七・一二新制
(二)庄園整理令
第三章 後白河上皇時代の公家新制
一 保元・治承の新制と建久の新制との関係
(一)保元一・壬九・一八新制(保元一年令と略称)
(二)保元二・一〇・八 新制(保元二年令と略称)
(三)治承二・壬六・一七新制
(四)治承二・七・一八新制
(五)治承三・八・三〇新制
(六)建久年代の新制と鎌倉時代の新制の関係
二 保元・治承年代の新制各説
(一)保元一年令
(二)保元二年令
(三)治承二・七・一八令
三 建久二・三・二二新制(建久I令と略称)
四 建久二・三・二八新制(建久II令と略称)
付録 興福寺の寺辺新制
第四章 鎌倉時代の公家新制
一 建暦二・三・二二新制
付録 「けちうのしんせい」
二 嘉禄一・一〇・二九新制
三 寛喜三・一一・三新制
四 延応二・三・一二新制
五 建長五・七・一二新制
六 弘長三・八・一三新制
七 文永一〇・九・二七新制
八 正応五・七・?新制
第五章 公家新制と武家新制の関係
一 鎌倉幕府施行の新制一覧表
二 延応二年の関東新制
三 弘長一年の関東新制
四 結び
索引

芸術の論理
創文社オンデマンド叢書
美学者、美術史家の著者による、「芸術」の本質をめぐる論考。芸術を成り立たせている論理は何かを大胆に剔出する。
【目次】
第一章 序説―視覚における三角形
第二章 美術家、美術作品の成立
第三章 美術における自然の位置
第四章 文芸の超実践性
一 文芸の思想
二 文芸の超実践性
第五章 宗教美術
一 宗教美術
二 園城寺、黄不動尊の美における位置
三 宗教美術の歴史的研究
第六章 藝術の高さ、大きさ、深さ
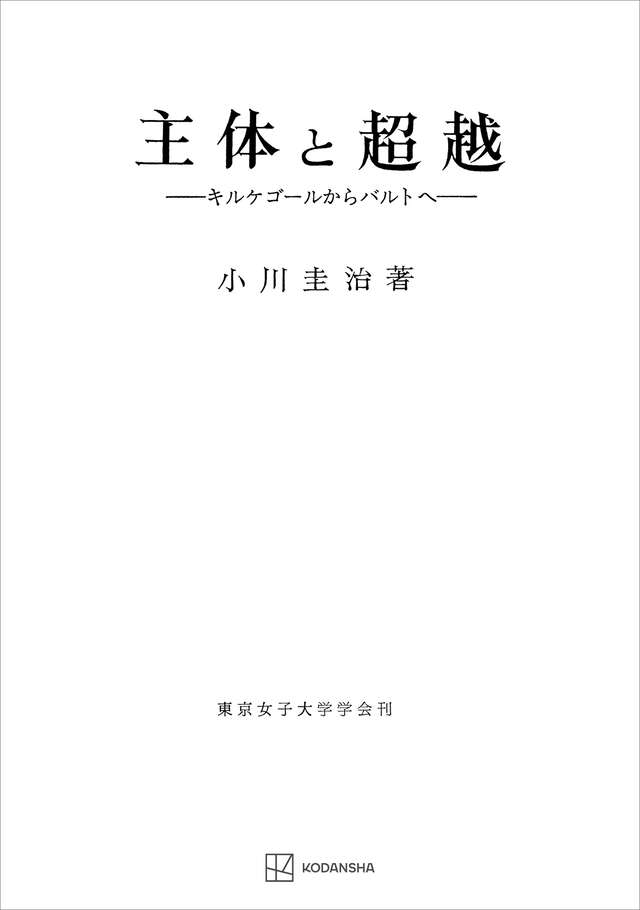
主体と超越
創文社オンデマンド叢書
「主体性」の確立を、主として宗教(キリスト教)的見地から詳細に究明する。宗教改革以後のキリスト教史・キリスト教思想史の展開を詳細に検討し、多くの神学者・哲学者の思想を批判的に検証する。特に、力を傾注したのが、キルケゴールとカール・バルトの思想である。彼ら二人思想の展開の必然性を明らかにする。
【目次】
序章 主題について
一 主体と主体性 二 キルケゴールからバルトへ 副題について 三 超越の事実性
第一部 問題状況
第一章 主観主義と客観主義
一 原理としてのincarnatio 二 ex opere operantisとex opere operato など
第二章 近代主観主義の問題
一 近代主観主義の展開 二 理想主義における主観主義原理の形成 三 自由主義神学における二焦点楕円の図式 四 「新しい思考」の待望
第二部 主体と主体性 S・キルケゴールについて
第一章 キルケゴール解釈の問題
一 問題の所在 二 H・ディームの問題提起 三 歴史的研究の限界 四 実存弁証法的解釈の方法 五 主体的解釈の立場
第二章 実存の三段階の構造
一 実存的人間学の視点 二 段階構造の二重性 三 段階の相互関係 四 実存弁証法的構造
第三章 主体性における内在と超越 『哲学的断片へのあとがき』の構成と主題について
一 『あとがき』の問題 二 『あとがき』の構成 三 『あとがき』の成立過程 など
第四章 神の前における主体
一 関係としての自己 二 キリスト像の問題 三 実存弁証法の問題性
第三部 超越の事実性 K・バルトについて
第一章 バルト解釈の問題
一 問題の所在 二 転向論と発展論 三 抽象性と具体性
第二章 神の言と実存
一 課題 二 神学におけるキルケゴール・ルネッサンス 三 バルトとキルケゴールの出会い など
第三章 神学における近代主義の克服
一 若きバルトと社会主義 二 ニヒリズムとの出会い 三 提起された課題
第四章 神学方法論の確立 アンセルムスの神の存在の証明をめぐって
一 新しい神概念の形成二 神の存在の証明 三 信仰と知解の弁証法 など
第五章 聖書解釈の方法 R・ブルトマンの問題
一 ケーリュグマ理解の問題 二 実存論的解釈の問題性 三 ブルトマンの神学史的位置づけ 四 聖書理解の姿勢について
第四部 展望 結論にかえて
一 実存の主体性から啓示の事実性へ 二 今日の神学的状況 三 与えられた課題
参考文献
あとがき
索引

大明律例譯義
創文社オンデマンド叢書
明代の中国の刑法典である「明律」とその追加法規の「條例」を和訳した書である。和歌山藩高瀬喜朴(1668~1749)が、8代将軍徳川吉宗の命によって享保5年(1720)に著した。江戸時代に数多くある明律注釈書のなかでも最重要書である。冒頭にある「律大意」は、高瀬が刑政の要諦ともいえる文を中国の諸典からまとめたもので、それだけでも価値が高い。また、『大明律例譯義』は、幕府や諸藩における法令の成立や実際の運用におおきく貢献した江戸時代の重要書である。
構成は、本文12巻、首末各1巻の全14巻となっている。
【目次】
首卷
律大意
譯義凡例
目録
卷之一
名例
〔1〕五刑
〔2〕十悪
〔3〕八議
〔4〕應議者犯罪
〔5〕職官有犯
〔6〕軍官有犯
〔7〕文武官犯公罪
〔8〕文武官犯私罪
〔9〕應議者之父祖有犯
〔10〕軍官軍人犯罪免徒流
卷之二
名例
卷之三
吏律
職制
公式
卷之四
戸律
戸役
田宅
婚姻
卷之五
戸律
倉庫
課程
卷之六
戸律
錢債
市廛
禮津
祭祀
儀制
兵律
宮衞
卷之七
兵律
軍政
關津
廐牧
卷之八
兵律
郵驛
刑律
賊盜
卷之九
刑律
人命
鬪毆
罵詈
卷之十
刑律
訴訟
受贓
卷之十一
刑律
許僞
犯姦
雜犯
捕亡
卷之十二
刑律
斷獄
工律
營造
河防
末卷
罪名
贖法
本宗九族五服