
マイページに作品情報をお届け!
日本の食と酒
ニホンノショクトサケ
- 著: 吉田 元

日本人は何を食べていたのか。本書は京都・山科家の日記や奈良・興福寺の文書をひもとくことで、中世の公家と僧侶の食生活を再現し、その背景をなす製法の歴史へと接近する。中世から近世にかけて日本酒としてのかたちを整えていく酒。醤(醤油)、味噌、納豆といった大豆発酵食品……。日本の食文化を最も特徴付ける発酵技術と発酵文化の歴史を追い、その原点に迫る。これが日本食の原型だ! (講談社学術文庫)
日本人は何を食べていたのか。本書は京都・山科家の日記や奈良・興福寺の文書をひもとくことで、中世の公家と僧侶の食生活を再現し、その背景をなす製法の歴史へと接近する。中世から近世にかけて日本酒としてのかたちを整えていく酒。醤(醤油)、味噌、納豆といった大豆発酵食品……。日本の食文化を最も特徴付ける発酵技術と発酵文化の歴史を追い、その原点に迫る。これが日本食の原型だ!
- 前巻
- 次巻
オンライン書店で購入する
目次
■【第一章】中世末の食物売りたち
歌合/狂言/供御人と食物
■【第二章】一五世紀公卿の食生活──『教言卿記』『山科家礼記』『言国卿記』
名字の地・山科/教言の晩年/応仁の乱/若き日の言国/供御人たち/惨劇/鞍馬参詣/食物の分類、貯蔵、調理法
■【第三章】一六世紀公卿の食生活──『言継卿記』『言経卿記』
『言継卿記』/言継の食生活/尾張下向/大洪水/子供たちの病気/駿府下向/東寺五重塔の焼失/信長の上洛と岐阜下向/『言経卿記』と言継の死/本能寺の変/京都追放/再び京都へ/東寺五重塔の再建/京都大地震/勅免/言経の食生活/『雍州府誌』と京都の食物
■【第四章】奈良興福寺の食生活──『多聞院日記』
はじめに/食物の種類/天災と飢饉/多聞院の献立/料理の内容とその他の食品/肉食・悪食
■【第五章】中世酒から近世酒へ
日本酒の製造法/京都の酒/僧坊酒/田舎酒とその他の酒
■【第六章】火入れの発展
はじめに/日本における火入れの成立//火入れの温度について/東アジア諸国における加熱殺菌法/日本の火入れの限界
■【第七章】大豆発酵食品
醤油と味噌の製造法/室町時代以後の大豆発酵食品/多聞院の大豆発酵食品/『料理物語』の醤油/ケンペル、ツュンベリーの見た醤油/『和漢三才図会』の大豆発酵食品/酢
あとがき
文庫版あとがき
参考文献
索引
書誌情報
紙版
発売日
2014年01月11日
ISBN
9784062922166
判型
A6
価格
定価:1,056円(本体960円)
通巻番号
2216
ページ数
288ページ
シリーズ
講談社学術文庫
電子版
発売日
2014年02月28日
JDCN
0629221600100011000E
初出
1991年9月に人文書院より刊行。(第1章―第3章および第5章は書き下ろし、その他収録作品参照)
収録作品
-
作品名初出
-
作品名
第4章
初出
「日記にみる一六世紀寺院の食生活」 仲尾俊博先生古希記念論集『仏教と社会』461―486頁、永田文昌堂(1990)
-
作品名
第6章
初出
「日本における低温殺菌法の発展」 『科学史研究』、169巻、25―31頁(1989)
-
作品名
第7章
初出
「一六世紀寺院の発酵食品づくり」 『日本醸造協会誌』、85巻、167―171頁(1990)に加筆
著者紹介
1947年、京都市生まれ。京都大学農学部水産学科卒業、京都大学大学院農学研究科農芸化学専攻博士課程修了。農学博士。専門は発酵醸造学、食文化史。種智院大学教授を経て、2013年に退職し、同大学名誉教授。 【著書】 『中世の光景』(共著)朝日選書、1994年。 『童蒙酒造記・寒元造様極意伝』(翻刻・現代語訳) 日本農書全書51、農文協、1996年。 『江戸の酒』朝日選書、1997年。 『近代日本の酒づくり――美酒探求の技術史』岩波書店、2013年。
オンライン書店一覧
関連シリーズ
-

地球上の中華料理店をめぐる冒険
-

生物学者と料理研究家が考える「理想のレシピ」
-

捨てられる魚たち 「未利用魚」から生まれた奇跡の灰干し弁当ものがたり
-
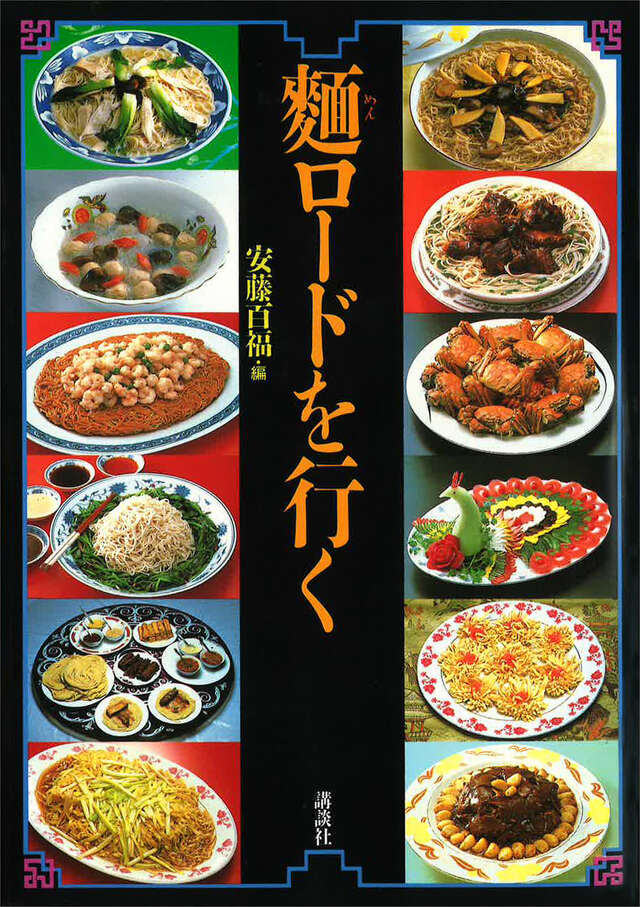
麺ロードを行く
-

「フーディー」が日本を再生する! ニッポン美食立国論
-

昭和天皇の料理番
-

美食・大食家びっくり事典
-

小泉式 食べ飲み養生訓108
-

そば学大全
-

食はイスタンブルにあり 君府名物考
-

とうがらしの世界
-

ハルカノイセカイ
-

たこやき
-

文化麺類学ことはじめ
-

「おいしさ」の科学
-

炎の牛肉教室!
-

おけいすし
-

食をめぐるほんとうの話
-
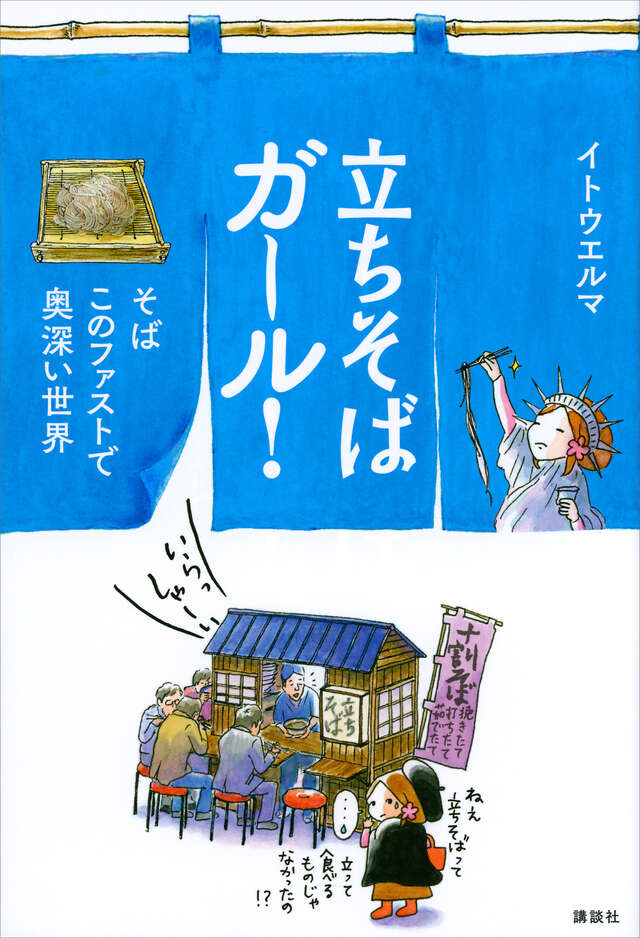
立ちそばガール! そば このファストで奥深い世界
-

憂食論 歪みきった日本の食を斬る!
-

食べ物としての動物たち
-

最後の職人 池波正太郎が愛した近藤文夫
-

すし物語
-

28歳からは「毒」になる食事
-

「食べもの神話」の落とし穴
-

「食べもの情報」ウソ・ホント
-

夜中にチョコレートを食べる女性たち
-

麺の文化史
-

明治洋食事始め――とんかつの誕生
-

日本料理の贅沢
-

日本料理の真髄
-

日本の「食」は安すぎる 「無添加」で「日持ちする弁当」
-

生姜免疫力
-

成功する人は缶コーヒーを飲まない
-

世界の野菜を旅する
-

世界の食べもの――食の文化地理
-

子どもの「パン食」は今日からおやめなさい! 栄養学不要論
-

江戸前鮨 伝統の技と真髄
-

江戸の食空間――屋台から日本料理へ
-

古代ローマの饗宴
-

蕎麦の事典
-

逸楽と飽食の古代ローマ―『トリマルキオの饗宴』を読む
-

フルーツひとつばなし おいしい果実たちの「秘密」
-

パンの文化史
-

とうがらし
-

チーズのきた道
-

しょうが
-

「賛否両論」笠原将弘の 口説きめし

















