講談社現代新書作品一覧

平将門と天慶の乱
講談社現代新書
■帝位「新皇」に就いて朝廷に刃向かった、唯一無二の「兵」■
鎌倉幕府を築いた源頼朝、南北朝時代を終わらせた足利義満、
三職推任を打診された織田信長、天下一統を成し遂げた豊臣秀吉……。
いずれも時代が認める改革者であったにもかかわらず、
古い王朝を改めて最上の地位を望まなかったのなぜなのか。
その背景には、武威によって坂東を従わせ、新皇を名乗りえて
京都の朝廷を争った末に、非業の最期を遂げた平将門の存在があったーー。
未だ謎の多い将門の実像に迫る。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
皇居の大手門のすぐ前側に位置する東京・大手町ーー
メガバンクや商社など名だたる巨大企業が本社を構える日本最大のオフィス街――に、
ぽつんと静かな霊場があるのをご存知だろうか?
10世紀に坂東(今の関東)を鎮定し、「新皇」に即位して、朝廷と争った平将門の首塚である。
都会の喧騒を払うように、清浄な気配を漂わせているが、
この地には見た目からちょっと想像できないような怨霊譚がいくつも伝え残されている。
はたしてそれらの伝説は本当なのか?
東京・大手町に存在する「日本史ミステリー」の真相解明にも挑む!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■本書のおもな内容■
序章 怨霊伝説を検証する 中世の将門怨霊譚/近現代の怨霊譚 ほか
第1章 蔭子・将門の少年期 蔭子なのに叙任されなかった将門 ほか
第2章 遺領が招いた争族 出世街道を外れた理由/「田畠」に隠れていた軍事施設 ほか
第3章 平良兼・良正の襲撃と源護の策謀 敵将を見逃す将門の甘さ ほか
第4章 追捕使・将門の勇躍と逆襲 旧私君・藤原忠平の厚意を得た将門/富士山の噴火 ほか
第5章 坂東独立の風雲 「天慶の乱」について/改元時期の京都と坂東の不安 ほか
第6章 将門、新皇に即位す 坂東の民意から生まれた新皇/弟と側近の諫言 ほか
第7章 誰が新皇を殺したのか 京都へ逃げ出す国司たち/京都滅亡の危機 ほか
第8章 敗者の声と勝者の宴 英雄なき勝利のあと/永続する朝廷と将門への鎮魂 ほか
終章 神田明神と将門塚の興起 なぜ神田明神と将門塚が都内にあるのか ほか
付録 平将門関連年表

続 昭和の怪物 七つの謎
講談社現代新書
【シリーズ累計22万部突破、第二弾!】
のべ4000人の元軍人らに取材を重ねてきた保阪正康氏が、昭和を代表する人物のエピソードを通じて昭和の闇=語られざる真実を語るシリーズ第二弾。本書では、三島由紀夫・近衛文麿・橘孝三郎・野村吉三郎・田中角栄・伊藤昌哉・後藤田正晴を取り上げる。
「これまでの私の取材を通して知り得たことは、確かに歴史の検証に必要な史実から、指導者の人間的エピソードに至るまで数多い。それらを歴史書として現すのではなく、人間学という枠内での書として刊行したいと私は考えるようになった。この系譜にある前著『昭和の怪物 七つの謎』(講談社現代新書)は、予想外の多くの人びとに手にとってもらい、これほどまでに昭和史の人間学が興味を持たれるのかと驚きを持った。歴史をもっと生身の人間の姿を反映したものとして表現したいという考えが受け入れられたようで、私には感慨ひとしおであった。
本書はこのシリーズの二冊目になる。(中略)私は古いノートをとり出しては、かつて聞いた歴史上の人物たちの証言が今はどのように受け止められるかを考えてみたかった。言うまでもなく、彼らの人物像を通して、日本の近現代史の流れを確認したかったのである。」(本書あとがきより)
【本書の構成】
第一章 三島由紀夫は「自裁死」で何を訴えたのか
第二章 近衛文麿はなぜGHQに切り捨てられたのか
第三章 「農本主義者」橘孝三郎はなぜ五・一五事件に参加したのか
第四章 野村吉三郎は「真珠湾騙し討ち」の犯人だったのか
第五章 田中角栄は「自覚せざる社会主義者」だったのか
第六章 伊藤昌哉はなぜ「角栄嫌い」だったのか
第七章 後藤田正晴は「護憲」に何を託したのか

社会学史
講談社現代新書
本物の教養がこんなに頭に染み込んで、ものの見方がすっかり変わる経験をあなたに!マルクスもフロイトもフーコーも、実は社会学者なんです。「社会学はもちろん、その周辺の学問を理解するためには、どうしても、社会学史全体を知っておく必要があります。それなのに、なぜか、社会学史の本がほとんどないのが現状です。だから、この仕事に私は、強い社会的な使命感を持っています」――大澤真幸
本物の教養が頭にどんどん染み込んで、ものの見方がすっかり変わる経験をあなたに。
「社会学はもちろん、その周辺の学問を理解するためには、
どうしても、社会学史全体を知っておく必要があります。
それなのに、なぜか、社会学史の本がほとんどないのが現状です。
だから、この仕事に私は、強い社会的な使命感を持っています」――大澤真幸
マルクスもフロイトもフーコーも、実は社会学者なんです。
アリストテレスからカンタン・メイヤスーまで、知の巨人が産み出した思想を、
網羅的に、平易な講義文体で学びましょう!
<本書の目次および登場する主な人物>
序 社会学に固有の主題
第1部 社会学の誕生――近代の自己意識として
1.古代の社会理論 アリストテレス
2.社会契約の思想 社会学前夜
グロティウス/パスカル/ホッブズ/ロック/ルソー/スミス
3.社会科学の誕生
コント/スペンサー
4.マルクス――宗教としての資本主義
エンゲルス/カント/フォイエルバッハ/ヘーゲル/フィヒテ
第2部 社会の発見
1.フロイト――無意識の発見
2.デュルケーム――社会の発見
3.ジンメル――相互行為としての社会
4.ヴェーバー――合理化の逆説
第3部 システムと意味
1.パーソンズ――機能主義の定式化
トマス/パーク/マートン
2.〈意味〉の社会学
ミード/シュッツ/ブルーマー/ガーフィンケル/ゴフマン/ベッカー
3.意味構成的なシステムの理論――ルーマンとフーコー
レヴィ=ストロース/デリダ/ブルデュー/ハーバーマス
4.社会学の未来に向けて
ボードリヤール/リオタール/ギデンズ/バウマン/トッド/メイヤスー

ふたつの日本 「移民国家」の建前と現実
講談社現代新書
日本はすでに「移民国家」だ。この30年間で在日外国人の数は94万人から263万人へと約3倍に増加し、永住権を持つ外国人も100万人を突破した。2019年春からは外国人労働者の受け入れがさらに拡大されることも決まっている。私たちは「平成」の時代に起きたこの地殻変動を正しく認識できているだろうか? いま必要なのは、この「遅れてきた移民国家」の簡単な見取り図だ。「日本」はどこから来てどこに向かうのか?
・本書のおもな内容
はじめに 「移民」を否認する国
第1章 「ナショナル」と「グローバル」の狭間
第2章 「遅れてきた移民国家」の実像
第3章 「いわゆる単純労働者」たち
第4章 技能実習生はなぜ「失踪」するのか
第5章 非正規滞在者と「外国人の権利」
第6章 「特定技能」と新たな矛盾
終章 ふたつの日本
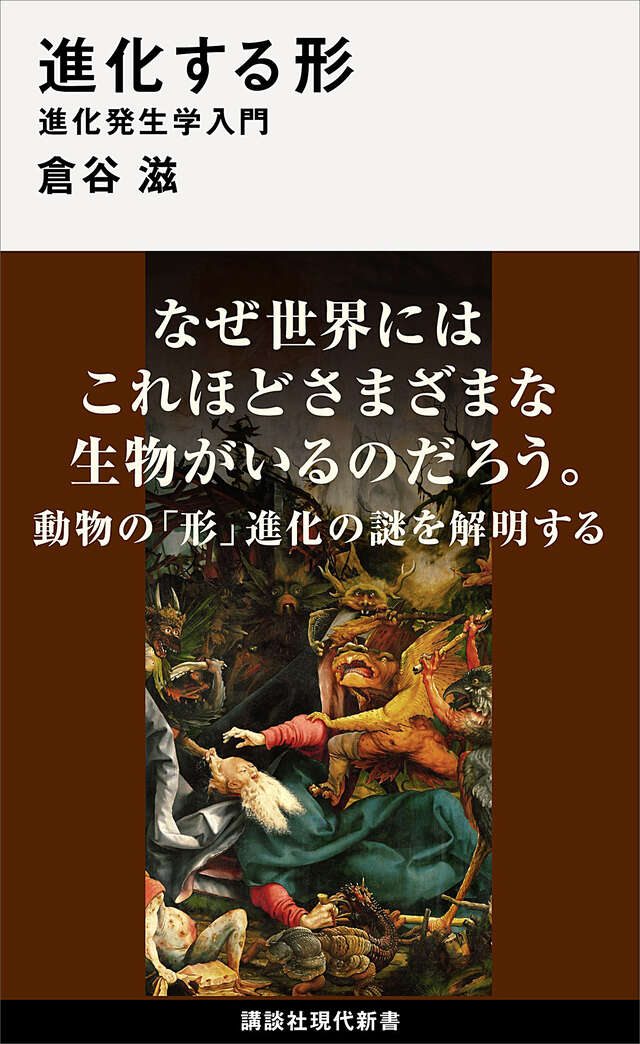
進化する形 進化発生学入門
講談社現代新書
なぜ生物は、多様な形をしているのか? その一方で、ペガサスやキングギドラのような、通常の形から逸脱した「怪物」は、なぜ現実には存在しないのか? その謎を解く鍵はゲノムにある。現代科学の最もホットな分野の1つである進化発生学の世界を、最先端の研究者がわかりやすく解説する。生物進化のメカニズムがわかる!!

科学と非科学 その正体を探る
講談社現代新書
本書は、科学と非科学のはざま、言うならば「光」と「闇」の間にある、様々な「薄闇」に焦点を当てた本である。「科学」と「非科学」は、そんなに簡単に区別できて、一方を容赦なく「断罪」できるのか? 「科学的な正しさ」があれば、現実の問題はなんでも解決できるのか? 生物学者が科学の可能性と限界を見つめ、私たちが生きる意味を問うサイエンスエッセイ。東大、北大をはじめ多くの入試問題で使用され、高校国語の教科書にも収録
■「科学的な正しさ」を疑い、「科学の存在意義」を問う■
何が「真実」で「異端」なのか。
分子生物学者が現代社会の「薄闇」に光をあてる。
はたして科学の可能性と限界とは?
私たちが生きる意味をも捉えなおした、極上のサイエンスエッセイ!
――
現代において、「非科学的」というレッテルは、中世の「魔女」のような
「異端」の宣告を感じさせる強い力を持っている。
社会に存在してはならないもの、前近代的なもの、というような響きである。
それは科学の万能性、絶対性が現代社会では無邪気に信じられているということの証でもある。
しかし、はたして科学という体系は、本当にその絶大な信頼に足るほど
強靭な土台の上に建っているものなのだろうか?
「科学的」なものと「非科学的」なものは、そんなに簡単に区別できて、
一方を容赦なく「断罪」できるものなのか?
「科学的な正しさ」があれば、現実の問題は何でも解決できるのだろうか?
科学と非科学の間に大きく広がる、そのはざまに一体、何があるのか?
本書は、複雑で、曖昧で、怪しげで、でもちょっと面白い、その辺土への誘い、である。
――
【本書のおもな内容】
第1話 デルフォイの神託/「神託」の謎に迫る科学のメス ほか
第2話 分からないこと/科学が持つ二つの顔 ほか
第3話 消える魔球/「正しい」こととは? ほか
第4話 無限と有限/農薬はなぜ「大体、安全」か? ほか
第5話 科学と似非科学/次々と現れる「新しい」生き物 ほか
第6話 科学は生きている/忍び寄る権威主義 ほか
第7話 科学と非科学のはざまで/カオスの縁 ほか
第8話 ドイツの滑空王/神々の領域 ほか
第9話 リスクととともに/新型インフルエンザ狂騒 ほか
第10話 アフリカ象と大学人/衰退する日本の科学と淘汰圧 ほか
第11話 「無駄」と科学/放射線に耐える奇妙な果実 ほか
第12話 閉じられたこと/グローバリゼーションのもたらすもの ほか
第13話 この世に「形」を生み出すこと/我が家の愚犬 ほか
第14話 確率の話/将棋と麻雀の日々 ほか

捨てられる銀行3 未来の金融 「計測できない世界」を読む
講談社現代新書
2019年4月から金融業界の「憲法」、検査マニュアルが大きく変わり始める。森信親金融庁長官から遠藤長官に代替わりして「捨てられる銀行」シリーズで明らかにしてきた改革路線の何が変わり、何が変わらないのか。そのすべてを明らかにする。今までの路線に安住する金融マンには何が待っているのか。どう変わらなければいけないのか。「計測できない世界」を制する者だけが生き残る。
2019年4月から20年間続いた金融のルールが本格的に変わり始める。
その変革は、森信親金融庁前長官が退任し、ほっと一息ついている地方銀行をはじめとする金融業界に衝撃を与えることになるだろう。
15万部のベストセラー『捨てられる銀行』で、著者はいち早く森改革路線の本当の狙いを明らかにした。
「予告の書」発売から3年、ついに金融界の「憲法改正」が本格的に始まる。
遠藤新長官の狙いは何なのか? それは森路線を覆すものなのか? 継承なのか? 金融業界に籍を置くならば、経営者から新入社員まで、この変化に乗り遅れることは「捨てられる」ことを意味する。
金融業界の大変革の全貌を見通し、その背景にあるビジネスモデルの世界的な大転換を明らかにする。
過去の計測できる数字に安住するものは、金融界では生き残れない。「計測できない世界」を制する者が未来の勝者となる。
金融マンは、どう未来を切り開けばよいのか? 答えは本書から導くしかない。
第1章 金融革命とポスト森金融行政
メインバンクを変える地方の雄/森金融革命とは何だったのか/地域金融革命と資産運用改革/現場主義者・遠藤新長官の頭の中/地域生産性向上支援チーム/何が変わり何が変わらないのか/「行かない革命」の脅威/銀行再編の限界/預金送金決済が銀行から消える日/アリペイが起こす信用革命
第2章 20年の金融ルールが変わる
検査マニュアルとは何だったのか/別表が招いた金融排除/引当が一変する/五味元金融庁長官の証言/「検査マニュアル」はどう変わるか
第3章 「共感」と金融
共感が世の中を動かす/保険の魔術師と呼ばれる男/飛騨から生まれた「育てる金融」/金融業者のクラウドファンディング/鶴岡を世界一にした金融マン
第4章 さよなら銀行
追い詰められた支店長/客を売ったメガバンク/衝撃の金融庁臨店/銀行は人に不幸を売る仕事?/相手にするのはAKとKK/商工中金の闇/
第5章 「計測できない世界」にどう対処するか
スルガ銀行が示すもの/本当のリスクとは何か/大きくなる誘惑/鎌倉投信・新井の新たな挑戦/リレーションシップ・インパクト論/「計測できない世界」に立ち向かう/捨てられない銀行員

神とは何か 哲学としてのキリスト教
講談社現代新書
科学万能の現代に、なぜこのような「時代遅れ」の問いが発せられなければならないのか? だがしかし、本当に、 「神」の問題は哲学的にはすでに解決済みなのか? 人間存在の根源に迫る、齢90の碩学からの、近代人への挑戦状。

中高生からの論文入門
講談社現代新書
大学入試改革もこれさえあれば怖くない! 有名中学高校が取り入れる「論文探究学習」。テーマ選びから文章術まで専門家が伝授する!
この一冊さえあれば、だれでも論文が書ける!
学校の探究学習、卒業論文、新・大学入試対策にも最適!
テーマ選び、図書館の使い方、文章の書き方、プレゼン――いまこそ必要なのは、自分の考えを組み立てる力だ。
●これだけはおさえておきたい論文の基本の基本
●タブレットではなくPCが必要な理由
●論文は書くから書けるようになる
●「1時間語れること」を探してテーマを考えよう
●論文にならないテーマとは?
●「テーマを変えたい」はよい知らせ
●本はどうやって読むか
●「感動詞」を「意見」に変える
●図書館の賢い使い方
●ネット検索のベーシック
●フィールドワークの進め方
●調査依頼の手紙の書き方
●実験・観察ってなに?
●書き方のきまり
●引用・参考・注釈のルール
●ホップ・ステップ・ジャンプの文章術
●パワポの基本の基本
【付録】論文チェックシート/論文相談室
探究力、構築力、表現力を磨くには? 論文論・図書館学習の第一人者がわかりやすく解説する
論文術の決定版。これさえあれば、大学入試改革も怖くない!

縄文時代の歴史
講談社現代新書
われわれの中にも縄文人は生きている!? 近年の発掘調査、および科学的な分析技術の飛躍的な発展により、旧来の縄文像は次々に塗り替えられることになった。最新の知見を元に、最も新しい縄文時代像を明らかにする。縄文ブームの今こそ必読。
縄文時代とは、日本列島において、土器が出現した1万6500年前から、灌漑水田稲作が開始される3000年~2500年前までの時代をさす用語です。
この時代には、狩猟・採集・漁労を主な生業とし、さまざまな動植物を利用し、土器や弓矢を使うなどして本格的な定住生活が営まれていました。1メートルにも及ぶ柱材を使用するような大型建物を作る技術や、クリ林の管理や漆工芸を始めとするきわめて洗練された植物利用技術を持ち、各地の環状列石や土偶に見られるように、複雑な精神文化がありました。また多数の集落が婚姻や交易などによってつながり合い、列島内には広範な社会的なネットワークがつくりあげられていました。
世界史上にも類例のないユニークな存在としても知られる縄文時代。最近のDNA分析によると、現代日本人の遺伝子にも、12パーセントほどは縄文人から受け継いだものが存在しているということです。著者によれば、日本人の円環的な死生観には、縄文人から受け継いだ要素が色濃く反映しているといいます。その意味において、縄文人は今もわれわれの中に生きている、そう言ってもよいのかも知れません。近年の縄文ブームも、もしかしたら、そのような親近感ゆえのことかも知れません。
近年の発掘調査、および科学的な分析技術の飛躍的な発展で新たな知見が次々に明らかにされたことにより、旧来の縄文像は一新されることになりました。千葉県佐倉市の国立歴史民俗博物館では、これら最新の研究の成果を元にして、縄文時代の展示をリニューアルしました。本書は、その責任者による、最も新しい縄文時代像を紹介するものです。

仕事と心の流儀
講談社現代新書
「問題が多いことを喜べ。それは懸命に生きている証だ」「能力や適性に大差はない。開花するかは『どれだけ努力したか』の違いだけだ」「空気は読んでも顔色は読むな」「情熱が人を動かし、金も動かす」「誰にだってチャンスはある。でも勉強しないとチャンスはつかめない」。幾多のビジネスの修羅場を乗り越えてきた大先輩から懸命に仕事するすべてのビジネスパーソンに贈るエール。
日々、ビジネスの現場で懸命に奮闘するすべての人へ。
幾多の修羅場を乗り越えてきた著者が贈る珠玉のメッセージ!
「勝者と敗者を分けるのは、心の強さと平常心」
「悲観的に考えて、楽観的に行動する」
「問題が多いことを喜べ。それは懸命に生きている証だ」
「金銭的報酬を追いかけて仕事をする人は、サラリーマンのプロになれない」
「能力や適性には差はない。開花するかどうかは『どれだけ努力をしたかの違い』だけだ」
「情熱が人を動かし、お金も動かす」
「部下の大半にやる気がないのは上司の責任」
「嫌な上司は反面教師にせよ」
「空気は読んでも顔色を読むな」
「人は三年権力を握ればバカになる」
「誰にだってチャンスはある。でも勉強しないとチャンスはつかめない」
人はなんのために仕事をするのか?
仕事の真の報酬とは何か?
新入社員から経営者まで共通する
働くことの本質をすべて語り尽くす。

0から1をつくる 地元で見つけた、世界での勝ち方
講談社現代新書
2018年冬季平昌五輪で、日本史上初の銅メダルを獲得した女子カーリング。チームを結成して率いた本橋氏による、ビジネス論!
2018年冬季平昌五輪で、日本史上初の銅メダルを獲得した女子カーリング。チームを結成して率いた本橋氏による、実践的ビジネス論!
・・・
ゼロは最強です。アイデアと体力さえあれば、何でも生み出すことができる。
0から始めることができれば、理想の10に向けた1をつくれると私は思っています。どこかの大都市で4まで進んでしまった事業を、理想の10までもっていくためには、一度、後退を迫られたりするかもしれません。
「地方だから」という言い訳は、私の中にはありません。地方だからこそ、前向きに、どんどん進めることができる。
田舎には無限の可能性があるということもまた、本書のテーマとなります。 (本文より)
・・・
<主な目次>
第1エンド はじめに
第2エンド 平昌五輪「銅メダル獲得」の裏で
第3エンド 何もない町に生まれ、トリノ五輪に出るまで
第4エンド バンクーバー五輪、チーム青森で学んだこと
第5エンド ロコ・ソラーレ結成、組織とは何か
ハーフタイム フォトギャラリー「私の愛するトコロ」
第6エンド 家族から成長させてもらったこと
第7エンド 結集した、それぞれの想い
第8エンド 綿密なコミュニケーションと観察眼
第9エンド 地元への感謝と、私たちの未来
第10エンド おわりに
楽しいはラクじゃない。でも、楽しさを失うわけにはいかなかった――。

「影の総理」と呼ばれた男 野中広務 権力闘争の論理
講談社現代新書
2018年1月に逝去した政治家・野中広務の生涯。政敵とは徹底的に闘う、強面のイメージが強かった。だが、その一方で、戦争を憎み、沖縄に寄り沿い、平和を愛した政治家でもあった。その素顔に迫る。

内戦の日本古代史 邪馬台国から武士の誕生まで
講談社現代新書
古代国家はいかに建設され、中世社会はいかに胎動したのか?倭王権に筑紫磐井が反乱を起こした理由は? 蘇我馬子と物部守屋の国際的な路線対立とは? 古代史上最大の戦乱「壬申の乱」勝敗の分岐点は? 桓武天皇の「征夷」を生んだ国家観「東夷の小帝国」とは? 天慶の乱はどのように中世へと時代を転換させたのか?――古代の戦いから日本のかたちが見えてくる、画期的な一冊。
古代国家はいかに建設され、中世社会はいかに胎動したのか?
倭王権に筑紫磐井が反乱を起こした理由は? 蘇我馬子と物部守屋の国際的な路線対立とは? 古代史上最大の戦乱「壬申の乱」勝敗の分岐点は? 桓武天皇の「征夷」を生んだ国家観「東夷の小帝国」とは? 天慶の乱はどのように中世へと時代を転換させたのか?――古代の戦いから日本のかたちが見えてくる、画期的な一冊。

老いた家 衰えぬ街 住まいを終活する
講談社現代新書
大量相続時代の到来とともに、注目され続ける「空き家問題」。2033年には3戸に1戸が空き家となる。これからの日本では、「住まいの終活」が最重要課題となってくるのだ。あなたが空き家を抱えた時、どうすればよいのか? あなたの子どもに自分の住まいについて、何をどう伝えておけばよいのか? 特別付録「書き込み式 住まいの終活(エンディング)ノート」に書き込みながら、あなたの住まいについて考えてみよう。
大量相続時代の到来とともに、注目され続ける「空き家問題」。2033年には約3戸に1戸が空き家となる。今すでに戸建ての4軒に1軒が「空き家予備軍」となっているのだ。
そんなこれからの日本で、最重要課題となってくるのが、住まいを「終活」することである。子供世代にとって、実家を相続した瞬間から、空き家問題は始まっている。親世代は、自分の子供に、所有する家や土地の何をどのように伝えておけばよいのかを考えておかねばならない。
特別付録「書き込み式 住まいの終活(エンディング)ノート」に書き込みながら、あなたの住まいについて真剣に考えてみよう。
全国の「空き家予備軍率ランキング」も一挙公開! あなたの家は将来、本当に大丈夫ですか?
<主な内容>
第1章 国民病としての「問題先送り」症候群
1・「問題先送り空き家」の実態
2・誰のものかわからない戸建て、分譲マンション
3・「空き家予備軍」は大量に控えている
第2章 他人事では済まされない相続放棄
1・相続放棄というサイレントキラー
2・相続放棄空き家への対応には限界がある
3・老いた分譲マンションと相続放棄
4・不動産のままで国庫に帰属できるのか?
第3章 世界でも見られる人口減少という病
1・アメリカ・ドイツ・韓国の人口減少都市
2・デトロイト市ランドバンクの取り組み
3・人口減少都市の土地利用転換に向けて
第4章 空き家を救う支援の現場から
1・住まいのトリアージとは何か
2・空き家バンクの最前線―島根県江津市の尽力
3・売り手支援の最前線―マッチングサイトの仕組み
4・空き家解体支援の最前線―和歌山県田辺市の先進性
第5章 さあ、「住まいの終活」を始めよう
1・住まいの終活、その手順
2・民間市場で流通性がある戸建ての選択肢
3・民間市場で流通性が低い戸建ての選択肢
4・分譲マンションの選択肢
5・「住まいの終活」への支援策の提言
特別付録 書き込み式「住まいの終活(エンディング)ノート」 (←ミシン目から切り取って保存できます)

ジャポニスム 流行としての「日本」
講談社現代新書
19世紀後半に西洋を熱狂の渦に巻き込んだ日本ブーム。そのインパクトは新たな美意識へとヨーロッパ人を開眼させた。印象派の画家たちは浮世絵の表現に西洋絵画の伝統にはない斬新な表現法の可能性を見いだし、色彩法、空間処理、線の技法など、「モダンアート」と称される、現代にまでつながってゆく表現法をその影響の元に生み出した。「近代」の感性を生み出した源流の一つとして、「日本」の存在を再評価する。
19世紀の西洋人にとって日本は「夢の国」でした。西洋のものとはまったく異なっていながらも洗練された文明があることを知り、鎖国による情報不足というミステリアスさともあいまって、西洋の日本への興味はこの時期に、これまでになく高まっていたのです。そしてついに日本が開国すると、その興味は「ジャポニスム」という日本ブームとして19世紀後半に西洋を熱狂の渦に巻き込むことになります。そのブームのインパクトは、現在の「クールジャパン」の流行をはるかに上回るものでした。おびただしい数の浮世絵を始めとする美術品、扇子を始めとする工芸品がヨーロッパ世界に流入し、人々はこぞって日本の美術工芸品をコレクションするようになったのです。
しかしそれは、単なるエキゾティシズムに止まることなく、それまでにはない、新たな美意識へとヨーロッパ人を開眼させることになりました。マネ、ゴッホ、ゴーギャン、ロートレック・・・印象派の画家たちは北斎、広重などの浮世絵の表現に、西洋絵画の伝統にはない斬新な表現法の可能性を見いだし、こぞって浮世絵をモデルにした作品を描きました。色彩法、空間処理、線の技法など、「モダンアート」と称される、現代にまでつながる美の感性の源流は、この、19世紀の「日本」にあるのです。
しかしブームにはかならず終わりがあるものです。「ジャポニスム」もその例外ではなく、日清戦争への勝利など、日本が「列強」の一角を占めるようになると、西洋人の「夢の国」へのあこがれは急速にしぼんで行きました。しかしそれでも、「ジャポニスム」の影響は「モダンアート」の中に流れ込み、見えないものになって残り続けました。現代、私たちが目にする「モダンアート」の中には、それゆえに、時間的にさかのぼっていけばジャポニスムにまでたどり着く要素をかならず見いだすことができるのです。
本書は、西洋の感性を変えた「19世紀のクールジャパン」とも言うべきインパクトを、美術の分野だけに止まらず、幅広く一つの文化現象として捉え直そうとするものです。

知ってはいけない2 日本の主権はこうして失われた
講談社現代新書
第二次大戦のあと、日本と同じくアメリカとの軍事同盟のもとで主権を失っていたドイツやイタリア、台湾、フィリピン、タイ、パキスタン、多くの中南米諸国、そしていま、ついに韓国までもがそのくびきから脱し、正常な主権国家への道を歩み始めているにもかかわらず、日本の「戦後」だけがいつまでも続く理由とは? 10万部を突破したベストセラー『知ってはいけない』の著者が、「戦後日本の“最後の謎”」に挑む!
かつて占領下で結ばれた、きわめて不平等な旧安保条約。
それを対等な関係に変えたはずの「安保改定」(1960年)が、
なぜ日本の主権をさらに奪いとっていくことになったのか?
「アメリカによる支配」はなぜつづくのか?
原因は、岸首相がアメリカと結んだ3つの密約にあった!
・・・・・・
PART1『知ってはいけない――隠された日本支配の構造』では、
戦後日本における、アメリカへの異様なまでの従属体制が
「なぜ生まれたのか」という謎については、
ひとまず解明と説明が終わったと考えています。
そこで最新作『知ってはいけない2――日本の主権はこうして失われた』では、
その異様な体制が70年たったいまも、
「なぜつづいているのか」という、戦後日本の“最後の謎”を解き明かします。
第二次大戦のあと、日本と同じくアメリカとの軍事同盟のもとで
主権を失っていたドイツやイタリア、台湾、フィリピン、タイ、パキスタン、
多くの中南米諸国、そしていま、ついに韓国までもがそのくびきから脱し、
正常な主権国家への道を歩み始めているにもかかわらず、
なぜ日本にだけはそれができないのか。
今後どうすれば私たちは、「自らが主権を持ち、
憲法によって国民の人権が守られる、本当の意味での平和国家」
として再生していくことができるのか。
10万部を突破したベストセラー『知ってはいけない』の著者が、
「戦後日本の“最後の謎”」に挑む!
・・・・・・
【目次】
第1章 日本は「記憶をなくした国」である
――外務省・最重要文書は、改ざんされていた
第2章 外務省のトップは、何もわかっていない
――三つの密約とその「美しき構造」について
第3章 CIAの金は、ロッキード社が配る
――「自民党」という密約がある
第4章 辺野古ができても、普天間は返ってこない
――軍事主権の喪失と「帝国の方程式」
第5章 米軍は、どんな取り決めも守らない
――国連憲章に隠された「ウラの条項」とは?
終章 外務省・最重要文書は、なぜ改ざんされたのか

改訂新版 新書アフリカ史
講談社現代新書
【アフリカ入門書の決定版が20年の月日を経て大改訂!】人類誕生から混沌の現代へ、壮大なスケールで描く民族と文明の興亡。新たなアフリカ像を提示し、世界史の読み直しを迫る必読の歴史書。変化の激しいアフリカ現代史を新たに書き加え、従来の記述も新しい知見や主張に基づいて内容を大幅に見直した改訂新版。
【アフリカ入門書の決定版が20年の月日を経て大改訂!】
人類誕生から混沌の現代へ、壮大なスケールで描く民族と文明の興亡。新たなアフリカ像を提示し、世界史の読み直しを迫る必読の歴史書。
変化の激しいアフリカ現代史を新たに書き加え、従来の記述も新しい知見や主張に基づいて内容を大幅に見直した改訂新版。

機密費外交 なぜ日中戦争は避けられなかったのか
講談社現代新書
リットン調査団への接待攻勢、諜報活動に努める杉原千畝ら外交官。満州国の正当化のためのメディア対策……。奇跡的に残存する1931~1936年の外交機密費史料。領収書の数々は何を語るか? インテリジェンス、接待、広報など、機密費史料から中国大陸での外交活動を復元し、満洲事変から盧溝橋事件へといたる道を描き出す一冊。
領収書が語る戦争への道――。
焼却されたはずの外交機密費文書が奇跡的に残されていた!
満州事変から日中戦争前夜までの史料の数々。
国際スパイ戦の舞台である上海、ハルビンで展開されたインテリジェンス活動。
領収書に残された杉原千畝らの活動や、蒋介石国民政府の内情を知るために雇われた
中国人、ロシア人ら内報者。
リットン調査団に対しおこなわれた日本と中国双方からの接待攻勢。
そして国の内外に向けて情報を発信するためのメディア対策費。
満洲事変によって亀裂の入った日中関係の危機を克服するために、奔走する現地の外交官たち。
それにもかかわらず、なぜ日中全面戦争への道を歩むこととなったのか?
戦争でも、平和でもない満洲事変後の日中関係を、知られざる機密費史料をもとに再現する。
話題作『戦争調査会』の著者による最新作!

ゆかいな認知症 介護を「快護」に変える人
講談社現代新書
認知症の人の思いや本音を聞いてみると、実は家族が持っている情報が間違っているために、自ら介護を大変なものにしているのではないかと思うことがよくありました。誤解の上に成り立った介護は、介護するほうにもされるほうにも、苦痛を与えるのは当然です。彼らの心の内側を知れば、認知症と診断された人だけでなく、介護に苦労している家族にとっても貴重な情報になるにちがいない、そう確信しました。――「はじめに」より