講談社選書メチエ作品一覧

享徳の乱 中世東国の「三十年戦争」
講談社選書メチエ
戦国時代は「応仁・文明の乱」より13年早く、関東から始まった――。 享徳3年(1454)、古河公方と上杉氏の対立に始まる仁義なき抗争。以降30年近くにわたる戦乱を著者は、「享徳の乱」と称すべきと学界に提唱した。本書はこの用語をメインタイトルとし、「戦国時代の開始=応仁の乱」という根強い「国民的常識」を正さんとする著者年来の宿願である。
日本列島での戦国時代の開幕は、一般的には応仁元年(1467)に始まる「応仁・文明の乱」が画期とされることが多い。この戦乱で京は焼け野原となり、下剋上があたりまえの新しい時代が訪れたというわけである。
最近でも、呉座勇一氏のベストセラー『応仁の乱』(中公新書)のサブタイトルは「戦国時代を生んだ大乱」となっている。新書などのタイトルは概して出版社や編集者の意向をうけて決まることが多いから、やはりこれは最大公約数的な見かたといっていいのだろう。
さて、のっけから恐縮だが、その見かたは、まちがっているとまでは言わないまでも大きな問題がある。
私の説は思いきって簡単にいうとこうなる。
◎戦国時代は応仁の乱より13年早く、関東から始まった
◎応仁の乱は「関東の大乱」が波及して起きたものである
「関東の大乱」というのは享徳3年(1454)12月、鎌倉(古河)公方の足利成氏が補佐役である関東管領の上杉憲忠を自邸に招いて誅殺した事件を発端として内乱が発生し、以後30年近くにわたって東国が混乱をきわめた事態を指す。
この内乱は、単に関東における古河公方と上杉方の対立ではなく、その本質は上杉氏を支える京の幕府=足利義政政権が古河公方打倒に乗り出した「東西戦争」である。しかし、これほどの大乱なのに1960年代初頭までまともな名称が与えられておらず、「15世紀後半の関東の内乱」などと呼ばれていた。
(中略)
関東で起こったこの戦乱は、戦国時代の開幕として位置づけるべきではないか、そのためには新しい名称・用語が必要ではないか。こう考えた私は「享徳の乱」と称すべきことを提唱した。1963(昭和38)年のことである。この歴史用語は、その後しだいに学界で認められて、今日では高校の歴史教科書にも採用されるようになっている。
しかし、いまだに「戦国時代の開始=応仁・文明の乱」という「国民的常識」は、根強く残っている。それを正すためにも、「享徳の乱」をメインタイトルとした書を世に問いたかったのである。本書は私の年来の宿願である。
(「はじめに」および「あとがき」より抜粋要約)

日本論 文字と言葉がつくった国
講談社選書メチエ
「日本語」があって、それを漢字・ひらがな・カタカナで「書く」ということと、「日本語」はなく、あるのは漢字語とひらがな語とカタカナ語、この混合物を「日本語」と呼んでいる、と考えることの違い、この飛躍はなかなか難しい。世界にも希な漢字仮名交じり文という表記法を有し、その下で文化を発展させてきた日本人の意識構造を変えることはできるのか。少なくとも、日本人がいかなる存在であるかを認識することはできるはず。
この世に日本語と呼べるようなひとつの言語がまずあって、その外側に、これを表記する道具としての文字として、漢字があり、ひらがながあり、カタカナがある――といった考えかた。これが大まちがいだと著者は言います。
それでは、ほんとうはどうだったか。「日本語」というのはなかった。実際にあるのは、漢字語とひらがな語とカタカナ語。三つの言葉があって、これらが入り混じった言語をわれわれは、大まかに日本語と呼んでいるにすぎない。こう考えれば、漢字語がなくならないかぎり漢字はなくなることはなく、ひらがな語がなくならないかぎりひらがなはなくならない。カタカナ語がなくならないかぎりカタカナはなくならない。だから漢字も、ひらがなも、カタカナも、そのまま生きつづけて現在にいたっている。そのしくみがよくわかるはずだというのです。
「日本語」があって、それを漢字・ひらがな・カタカナで「書く」ということと、「日本語」はなく、あるのは漢字語とひらがな語とカタカナ語、この混合物を「日本語」と呼んでいる、というふうに考えることとの違い、この飛躍はなかなかむずかしい。同じことではないかと一般には考えられてしまいそうですが、ほんとうに、なるほどわかったというふうに腑に落ちると、ものを見る見かたがガラッと変わって、いろんなものが今までと違うかたちで見えてきます。
世界にも希な漢字仮名交じり文という表記法を有し、その下で文化を発展させてきたわれわれの意識構造には何が刻みこまれているのか、変えることはできるのか……。少なくとも、われわれがいかなる存在であるかを認識することはできるはず。「文字と言葉」という観点から和辻哲郎『風土』、九鬼周造『「いき」の構造』、新渡戸稲造『武士道』、鈴木大拙『日本的霊性』、土居健郎『[「甘え」の構造』、ベネディクト『菊と刀』、中根千枝『タテ社会の人間関係』などの日本文化論の名著といわれる書物を読みなおすとき、思いがけない「この国のかたち」が見えてきます。

凱旋門と活人画の風俗史 儚きスペクタクルの力
講談社選書メチエ
古代ローマに倣うように、ルネサンス宮廷に甦る仮設建築の凱旋門。それは入市式における君主の行列を迎える舞台、またメッセージを伝える大道具として機能し、さらに「生きた人間による絵画」の展示を加えて、大がかりな演劇的空間を作り出した。束の間の宮廷祝祭を彩った凱旋門と活人画は、その後、国民国家の記憶装置あるいは上流社会の娯楽としての道を歩みやがて明治日本にも伝来し独自の変容を遂げてゆく。
古代ローマ時代に戦勝を記念して数多く作られた凱旋門。ローマの衰退とともに姿を消した凱旋門はルネサンス期に甦り、君主入市式に際して仮設建築の形で作られた。
一方、中世の教会で行われた典礼劇に端を発する活人画はその後アルプス以北の君主入市式を飾り、ルネサンス期には凱旋門を舞台に演じられるようになった。
両者は一体となってルネサンス宮廷の一大スペクタクルとして盛り上がりをみせたが、時代が下ると近代市民社会においてそれぞれ別の道をたどることになる。活人画は上流階級の夜会の余興として引き継がれ、凱旋門はやはり戦勝記念として国威の発揚を目的に作られ続けた。
さらにそうした文化は明治期のわが国にも流れ込み、国民統合の象徴として、祝祭の装置として、人集めの見世物として、高尚と下世話あい取り混ぜて浸透することになる。
両者ともエフェメラル(束の間)の存在として、一瞬間現れては消えてゆく。それ故に人々の期待と耳目を集める効果は大きく、その制作のためには美術・演劇はもとより音楽・文学といった芸術家たちの力が要請され彼らの腕の見せ所ともなったのである。
本書では、時を超え、洋の東西をまたいでさまざまなジャンルの芸術と触れあいながら、凱旋門と活人画がスペクタクルの力をいかに発揮してきたのかをたどる。

丸山眞男の憂鬱
講談社選書メチエ
戦後日本を代表する知識人・丸山眞男(1914-96年)は何に躓き、「憂鬱」に陥ったのか? 主著『日本政治思想史研究』(1952年)を読み解き、後年の論文「闇斎学と闇斎学派」(1980年)と山本七平(1921-91年)の『現人神の創作者たち』(1983年)を併置・対照することを通して、日本の近代化に潜む真実を明らかにする。これまで誰もなしえなかった不可欠の試みを実行する画期の書!
戦後日本を代表する知識人として知られる丸山眞男(1914-96年)。政治学の第一人者として「丸山政治学」と呼ばれる仕事を残し、多くの弟子と信奉者を生み出した丸山の主著は、しかし今日に至るまで真に読まれてはいない。
この紛れもない事実と向き合ってきた著者が、ついに丸山論を書き上げた。
ここで取り上げられる丸山の主著とは、『日本政治思想史研究』(1952年)である。大学院生の頃に小室直樹博士の自主ゼミナールでこの書を読んだ著者は、改めてこの書を取り上げるに際し、同じゼミナールで読んだ山本七平(1921-91年)の『現人神の創作者たち』(1983年)を併行して読む必要性に気づいた。この山本の著書で焦点をあてられているのは、山崎闇斎(1619-82年)とその学派であり、まさに闇斎と闇斎学派こそが丸山にとっての蹉跌となったことを著者は明確に認識する。
本書は、不可欠の準備作業として『日本政治思想史研究』を精読し、そこで取り上げられたものと取り上げられなかったものを綿密に腑分けすることから始められる。そこでは本格的に論じられずに終わった対象を、丸山は30年近くのちになって取り上げている。その長大な論文「闇斎学と闇斎学派」(1980年)を精読したあと、山本の『現人神の創作者たち』と対照させること。本書が実行しているのは実にシンプルな作業であるが、驚くべきことに、そのシンプルな作業がこれまでなされてこなかったことは厳然たる事実である。
闇斎学派に特徴的な正統な権威に対する絶対的な忠誠は、日本の近代化にとって不可欠なエートスとして機能した。その一方で、丸山を一躍スターにした論文「超国家主義の論理と心理」(1946年)で批判した、超越的な天皇への忠誠に駆動された「超国家主義」の淵源に闇斎学派があることもまた否定できない。このジレンマに気づいたあと、丸山と山本はいかなる道を選び、歩んだのか。後年の丸山に著者が見て取る「憂鬱」をもたらした真の理由とは何だったのか。
本書は、日本の近代化を考える上で避けて通れない主題に正面から取り組んだ画期の書にほかならない。

永田鉄山軍事戦略論集
講談社選書メチエ
「彼が生きていれば、太平洋戦争は起こらなかった」――近年再評価が進む、帝国陸軍の至宝・永田鉄山(1884-1935)。これまであまり世に出てこなかった永田自身の文書や発言録から、戦間期に残した論考6編を収録。その冷静かつ合理的な分析が訴える、あるべき国家の姿とは? 詳細な解説を加え、昭和の大日本帝国を支えた理論・思想の背骨を明らかにしてゆく。
第一次世界大戦の甚大な犠牲と破壊を受け、永田は戦争のあり方が様変わりしたと思い知る。それは短期かつあくまで局地的な戦いから、高度の工業生産力と膨大な資源を要する、長期にわたる国家総力戦への転換である。そして次なる大戦争は不可避と踏み、対応するには「国を挙げて抗戦する覚悟」をもって「国家総動員体制」を敷くべきであると説く。
永田は陸軍学校を優秀な成績で卒業後、長期のヨーロッパ駐在を経て軍の要職に就き、中堅幕僚の盟約「一夕会」を結成。東条英機、武藤章らとともに「統制派」を率いて国家総動員体制を推進、理論的支柱として満州事変以後は陸軍の実質的リーダーとなる。陸軍の革新を志し、政治進出にも大きな役割を果たすが、対立する皇道派により殺害される。二・二六事件はその翌年、日中戦争開戦はさらにその翌年。永田亡き後、日本は戦争とその結果としての破滅へ突き進むことになる。
来たるべきものである戦争に、いかに臨むか――にわかに国際関係の緊張が高まる現代、極めて誠実に、現実的に国防を考えた永田のロジックから、21世紀の我々は何を学べるだろうか。

浮世絵細見
講談社選書メチエ
◎大判、中判、間判、短冊……浮世絵のサイズはどう決まる?◎紙が貴重な時代の包紙……浮世絵を買ったらどう持ち帰る?◎役者絵と興行記録の違い……絵師は舞台を見て描いたのか?◎浮世絵師という仕事……収入、住まい、仕事の量とスピード◎贋作・剽窃・続編……江戸時代の認識はどう違う?――ほか、「そういえば知らない」浮世絵の謎を解き明かす!
浮世絵研究とは、紙の「折り跡」が謎を深め、制作年の一年の差が、謎を解く鍵になる世界。そこをちらりと覗いてみれば、絵を眺めるだけでは決して見えない浮世絵版画文化、そして江戸という時代の全体が立ち上がる。
浮世絵は誰もが身近に感じる日本美術の代表。欧米での人気もうなぎのぼり。が、こんなにわかっていないことが多かったとは。
そもそも洋画や日本画さえ西洋の美術をモデルに明治時代に作り出された。浮世絵の全盛期に「美術」という言葉はなかった。私たちが浮世絵を美術館で鑑賞するのと違い、もとは私的な楽しみのため市井で売り買いされるものだった。
そんなことは知っていると言うかもしれない。ところが、買い手が浮世絵をどのように持ち帰ったのかさえ、実はよくわかっていないらしい。展示や画集になれっこになっているから、いちいち想像などしない。しかしそれで本当に浮世絵を身近に楽しめていると言えるだろうか。
本書は、こうした謎を最新の知見にもとづき、現時点でわかるギリギリのところまで教えてくれる。親切な浮世絵の入門書は少なくない。けれども、わからないことをここまで教えてくれる本は初めてだ。
――椹木野衣氏書評(朝日新聞、2017年10月22日)
【目次】
はじめに
第一章 紙と判型の謎
その一 鈴木春信の死と判型
その二 歌川広重の花鳥画の大きさ
第二章 描かれた謎
その一 豆男春画の謎
その二 二種類の右図の謎
その三 写楽の見立と創造
その四 広重は東海道を歩いたか
第三章 どこまでが浮世絵か
その一 包紙――浮世絵はどのように売られたか
その二 絵半切――江戸時代の絵入用箋
その三 絵半切的絵本、絵入折手本、特製用箋
その四 千社札文化の謎
第四章 美術史の外側から読む
その一 春の清水寺の謎――文学・歌舞伎と浮世絵版画
その二 パリ万博の浮世絵画帖――浮世絵師の住居と報酬
終章 浮世絵研究をしたくなった方へ

セックス・イン・ザ・シー
講談社選書メチエ
2016年に出版され、大ベストセラーとなった話題の書、ついに邦訳刊行!
海の生物たちがどんなセックス・ライフを送っているのか、知っていますか? サンゴ礁の専門家が書いた本書では、さまざまな海中生物の性生活がドラマチックかつロマンチックに描き出されます。印象的なロブスターについてのくだりから。
「オスの前に立ったメスは、厳かにはさみを持ち上げ、オスの肩にそっと触れ、続いてもう片方の肩に対しても同じ動作を繰り返す。この合図は何らかのメッセージを伝えているように思われる――「今さら私を捨てたりしないでね」と。向かい合ったオスとメスは、互いに大量の「黄金シャワー」を浴びせる。その後、メスは隠れ家の奥に移動し、脱皮に移る。
メスの脱皮には最長で一時間あるいはそれ以上を要するが、メスが最後まで残った殻を脱ぎ捨ててからちょうど三〇分後、本番が始まる。ロブスターの交尾の様子は驚くほどロマンチックだ――ただし、時間は短い。メスの魔法にかかったかつての暴君は、心優しい恋人に変貌する。メスの脱皮が終わるとすぐ、オスは閉じたはさみを海底につけ、覆いかぶさるような姿勢でまだ体のやわらかい相手を守り、時には触角でそっとさすってやる」。
──人間の男女間で繰り広げられるドラマと見紛うばかりです。本書では驚きを誘う海中生物の姿が次々に紹介され、飽きることがありません。
しかし、著者は単に興味本位で本書を書いたわけではないことが徐々に分かってきます。
「私たちが魚を食することができるのは、その魚の餌になる微小な甲殻類が短い周期で繁殖してくれるおかげだ。……――その豊かさの源にあるのが、たくさんのセックスなのだ」。
そして、著者はこう断言するのです。
「海における性の営みが破綻すれば、人間も破綻する。水中で何が起きているのかを知ることが、地上の私たちにとって大切なのはそのためだ」。
興味を惹かれる「セックス」という入口から入って、とりわけ日本人にとっては欠かせない食物を提供してくれる海の大切さを認識すること。そして、海の生物たちを守ることに思いを致すこと。本書は、そんな大きなテーマにいざなってくれる、忘れられない1冊になるでしょう。

乱歩と正史 人はなぜ死の夢を見るのか
講談社選書メチエ
我々の現代性の黎明期、日中戦争の前/日米戦争の後、江戸川乱歩と横溝正史――二人は探偵小説の夢を創造する。個人の日常生活を成立させるリアリズムの場に深い〈穴〉があき、あるいはリアリズムの〈場〉が〈死者〉の声に触れて崩れるとき、人間に関わる真実が独特の顔をして垣間見えることがある。だが、この真実を表象する手段は限られている。乱歩と正史はこの真実を寓喩――殺人とその不可能図形によって描き出す。
我々の現代性の黎明期、日中戦争の前/日米戦争の後、江戸川乱歩と横溝正史――二人は探偵小説の夢を創造する。
個人の日常生活を成立させるリアリズムの場に深い〈穴〉があき、あるいはリアリズムの〈場〉が〈死者〉の声に触れて崩れるとき、人間に関わる真実が独特の顔をして垣間見えることがある。
だが、この真実を表象する手段は限られている。乱歩と正史はこの真実を寓喩――殺人とその不可能図形によって描き出す。

アーレント 最後の言葉
講談社選書メチエ
1975年12月4日にニューヨークの自宅で急逝したハンナ・アーレント。その机の上に置かれたタイプライターには数行が印字された1枚の紙が残されていた。ライフワークとなる三部作『精神の生活』の掉尾を飾るはずだった本のタイトルに続いて二つの銘が引用されて途絶えたアーレント最後の言葉は何を意味しているのか? わずかな手がかりを頼りに挑む探索の旅は、アーレントの出自と絡み合いながら、謎の真相に迫っていく。
1975年12月4日、ニューヨークの自宅で、ハンナ・アーレントが急逝した。享年69。死因は心臓発作だった。
自室の机に置かれていたタイプライターには1枚の紙がかかっており、そこに何行か印字されていることが、すぐに気づかれた。
その第1行には「判断(JUDGING)」とある。これはアーレントの遺著となった未完の三部作『精神の生活』の第三部の書名であることがヘッダーの部分に記されている。この大著の第一部「思考」と第二部「意志」は原稿がほぼ完成した形で残されていたため、死後出版された。しかし、第三部「判断」のためにアーレントが執筆した言葉は、この1枚だけである。
その紙片には、タイトルに続いて二つの銘が置かれ、そこで途絶えている。
第一の銘として引用されているのは、ローマ帝政初期の詩人ルカヌス(39-65年)の『内乱』の一節。表題のとおり、これはカエサルとポンペイウスの対立を軸とするローマの内乱を描いた作品である。そして、第二の銘として引用されているのは、ゲーテ(1749-1832年)の長編詩劇『ファウスト』の一節である。
タイトルと二つの銘だけから成るこの最後の言葉は、いったい何を意味しているのか? 二つの銘が並べて引用されていることの意味は何か? そして、このような始まりとともに執筆が開始されたライフワークの最終作は、どんな書物になるはずだったのか?
手がかりはあまりに乏しいように見える。しかし、著者はここにあるルカヌスの一節をアーレントが人生の中で何回も(少なくとも8回は)引用してきたことに気づく。その一つ一つを丹念に調査し、それぞれの箇所でこの一節に付与された意味を読み解いていくと、アーレントの出自と結びつく問題系に結びついていることが見出された。それは同時に、アーレントにとって決して消せない影響を与えた男たち──クルト・ブルーメンフェルト、カール・ヤスパース、そしてマルティン・ハイデガーの記憶と交錯し、ゲーテから引用された第二の銘とも関わっていることが明らかになっていく。
アーレントが残した謎を解き明かしていく本書は、その過程で通説とされてきた伝記上の事実をも鮮やかに覆し、これまで誰も知らなかったアーレントの姿を描き出す。気鋭の著者によるスリリングにして刺激的な論考!

モンゴル帝国誕生 チンギス・カンの都を掘る
講談社選書メチエ
13世紀にユーラシアの東西を席巻したモンゴル帝国。その創始者、チンギス・カンは、質素倹約、質実剛健なリーダーだった。それを物語るのが、著者が近年、発掘成果をあげているチンギスの都、アウラガ遺跡である。良質の馬と鉄を手に入れ、道路網を整備することで、厳しい自然環境に生きるモンゴルの民の暮らしを支え続けたチンギスの実像を、さまざまな文献史料と、自然環境への科学的調査を踏まえ、気鋭の考古学者が描く。
13世紀にユーラシアの東西を席巻し、その後の世界史を大きく転換させたモンゴル帝国。ヨーロッパが世界を支配する以前に現出した「パックス・モンゴリカ」時代の、人類史における重要性は、近年、広く知られるようになった。しかし、ではなぜ、ユーラシア中央部に現れた小さな遊牧民のグループ、モンゴルにそれが可能だったのか、また、その創始者、チンギス・カンとは、いったいどんな人物だったのか、まだ多くの謎が残されている。本書では、20年以上にわたってモンゴルの遺跡を発掘し続けている著者が、この謎に挑む。
著者がフィールド・ワークから実感するチンギス・カンは、小説などでよく描かれる、果てしない草原を軽快に疾駆する「蒼き狼」、あるいは金銀財宝を手にした世界征服者――というイメージとは異なり、むしろ質素倹約を旨とする質実剛健なリーダーだという。その姿を明らかにしつつある近年の著者の発掘成果が、チンギスの都と目されるアウラガ遺跡である。
チンギスは、ただ戦争に明け暮れるだけでなく、この都をひとつの拠点に、良質の馬と鉄を手に入れ、道路網を整備していった。つまり、産業を創出し、交通インフラを整えることで、厳しい自然環境に生きるモンゴルの民の暮らしを支え続けたのである。その「意図せぬ世界征服」の結果として出現したのが、イェケ・モンゴル・ウルス=大モンゴル国、いわゆるモンゴル帝国であった。
さまざまな文献史料と、自然環境への科学的調査を踏まえ、気鋭の考古学者が新たに描き出すモンゴル帝国とチンギス・カンの実像。

忘れられた黒船 アメリカ北太平洋戦略と日本開国
講談社選書メチエ
アメリカ海軍はペリーの他にもうひとつの艦隊を派遣していた。司令長官は海軍大尉ジョン・ロジャーズ。「ペリーとハリスのあいだ」の「ロジャーズ来航」は黙殺され、まさに「忘れられた黒船」といっていい。それはいったいなぜなのか? 本書は、これまでほとんど本格的に検証されることのなかった測量艦隊の、具体的な来日の経緯と国際環境について明らかにし、日本開国の事情をこれまでとは異なる観点で描きなおすことをめざす。
現在の日本史学は、ペリー来航を実際以上に過大評価しているといわざるをえない。これが、本書の立場です。ペリー来航が日本史にとって重大な歴史的事件であったとしても、それがそのままアメリカ外交の歴史にとっても重大な事件であったことを意味するわけではありません。にもかかわらず、日本人あるいは日本史の研究者は、ペリー艦隊の派遣がアメリカ外交史上でも重大事件であると思いこんでいたのではないでしょうか。
アメリカにとって最大の目的は、東アジア貿易でイギリスに対抗すること、その手段として太平洋蒸気船航路を開設することにありました。だからこそ、その航路上に位置する日本列島が、石炭補給地、遭難時の避難港、そして新市場として着目されたわけですが、それはいわば「点」にすぎません。ペリーがやったことは「点」の確保であり、続く「航路=線」の開拓の模索がなければなりません。そして合衆国はたしかに、ペリー艦隊の派遣以外にも手を打っていたのです。
アメリカ海軍は日本近海も含めた北太平洋海域一帯の測量を目的に「北太平洋測量艦隊」を派遣していました。司令長官は海軍大尉ジョン・ロジャーズ。この艦隊は1853年6月にアメリカ東海岸のヴァージニア州ノーフォークを出航しました(その7ヵ月前に、ペリー艦隊が日本へ向けてまさに同じ場所から出航)。さらに1854年12月には鹿児島湾、翌1855年5月には下田、そして6月に箱館を訪れています。しかも下田では、幕府に向けて日本近海測量の認可を求めるということもおこなっているのです。老中阿部正弘以下の幕閣は驚愕し、じつは開戦も辞せずという瀬戸際にまで追いこまれました。
日本開国にかかわる幕末外交史研究において、この艦隊について検討されたことはほとんどありません。ペリーおよび1856年に来日した初代総領事ハリスについては必ず言及されますが、まさに「ペリーとハリスのあいだ」の「ロジャーズ来航」はごく一部の研究者に知られるのみで黙殺されたかっこうであり、まさに「忘れられた黒船」といっていいのです。それはいったいなぜなのか……?
本書は、これまでほとんど本格的に検証されることのなかった測量艦隊の、具体的な来日の経緯と国際環境について明らかにし、日本近代外交の起点ともいうべき開国の歴史を、これまでとは異なる観点で描きなおすことをめざす。

フラットランド たくさんの次元のものがたり
講談社選書メチエ
2次元=平面世界(フラットランド)の住人に、3次元=空間世界(スペースランド)はどう映るのか? 4次元以上の世界は、どう想像できるのか?「次元」の本質をとらえた古典的名著、待望の新訳!アイドゥン・ブユクタシによる3次元の外へ誘う写真シリーズ《フラットランド》 特別収録
2次元=平面世界(フラットランド)の住人に、3次元=空間世界(スペースランド)はどう映るのか?
4次元以上の世界は、どう想像できるのか?
「次元」の本質をとらえた古典的名著、待望の新訳!
アイドゥン・ブユクタシによる3次元の外へ誘う写真シリーズ《フラットランド》 特別収録

ジャズ・アンバサダーズ 「アメリカ」の音楽外交史
講談社選書メチエ
本書は国際政治史のなかでジャズが果たした特異な機能を考察し、ジャズが国際政治と共振しながら織りあげた歴史の実像に迫ります。戦争、冷戦、デタント、平和運動、イデオロギー、民主化、脱植民地化、人種、異文化対話といった、アメリカ内外の政治的ダイナミズムが交錯するところにジャズはあり、それを問うことはジャズとアメリカとの関係を脱構築することになるでしょう。
ジャズは自由の母国としてのアメリカを象徴する音楽と理解されてきました。そして20世紀後半の国際政治を大きく規定した東西イデオロギー対立のなかでジャズには重要な位置が与えられたのです。アイゼンハワー政権下、米国務省はアメリカを代表するミュージシャンたちを「ジャズ大使」として世界各地に派遣。彼らは、アジア、アフリカ、南米や共産圏の各地で観客を熱狂の渦に巻きこみます。デューク・エリントン、ルイ・アームストロングやサラ・ヴォーンら多くのスターたちが参加したこの壮大な計画の目的は「アメリカ」を宣伝することにありました。
しかし、ジャズには同時に「アメリカ」批判、抵抗の音楽としての側面があります。人種隔離からみずからの解放と自由を求める人びとにとって、ジャズを演奏することはすなわち、抑圧的社会に抗議の意思を表明する象徴的行為でした。ジャズが重視する即興性は、譜面が求める規律に抵抗するものです。すなわちジャズにはこの二面性、つまり自由な自己表現を追求する側面と、抵抗の文化としての側面が内包されているのです。その抵抗の矛先がアメリカ自体に向かうとき、ジャズは反米の意思表明媒体となります。たとえば第二次世界大戦後のフランスがそうであったように。サルトルら実存主義の思想家は、思想を体現するものとしてジャズを捉え、アメリカ批判の論陣を張りながらジャズを積極的に受容しました。
さらにジャズは「連帯」をうながす媒体ともなります。アメリカから派遣される「ジャズ大使」たちは政府の思惑を超えてファンとのあいだに多様な共感を生んだし、共産圏に生きるミュージシャンやファンも国境横断的な連帯の輪を独自に広げました。今日のジャズに期待されているのも、異文化対話をうながし人びとのあいだのつながりを導く連帯の哲学です。
本書は国際政治史のなかでジャズが果たした特異な機能を考察し、ジャズが国際政治と共振しながら織りあげた歴史の実像に迫ります。戦争、冷戦、デタント、平和運動、イデオロギー、民主化、脱植民地化、人種、異文化対話といった、アメリカ内外の政治的ダイナミズムが交錯するところにジャズはあり、それを問うことはジャズとアメリカとの関係を脱構築することになるでしょう。
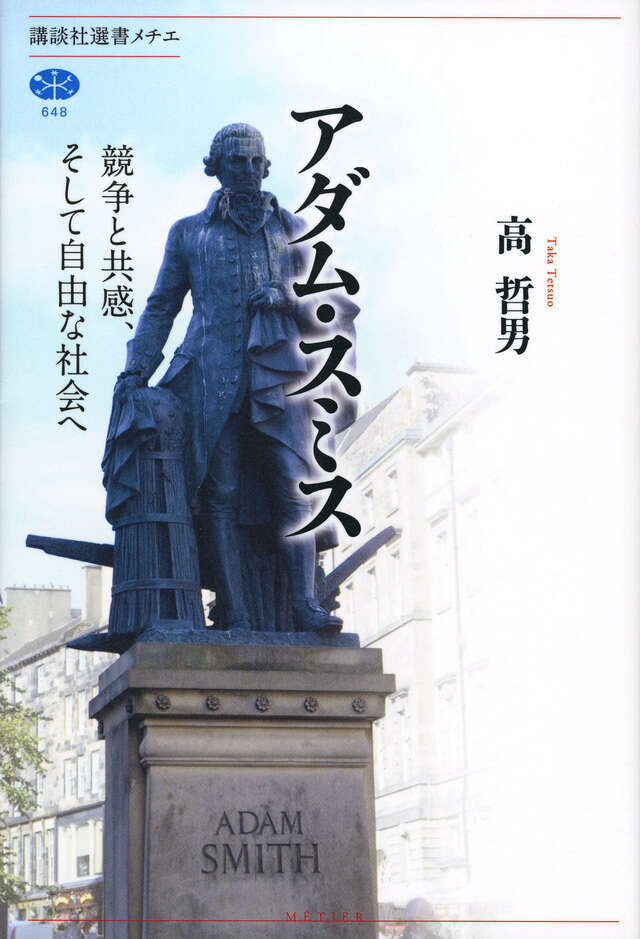
アダム・スミス 競争と共感、そして自由な社会へ
講談社選書メチエ
なぜ今、アダム・スミスなのか――。自由競争の理念を掲げて豊かさを追求する社会を論じる『国富論』と、他者への「共感」が社会形成にもたらす作用を説く『道徳感情論』。彼が残した二冊の主著を一貫した思想としてとらえ、両書の流れと呼応を俯瞰することで見えてくる、その思想の全体像。原典の新たな読み直しによって、誤解されてきた「近代経済学の父」の真の姿を明らかにし、閉塞する現代社会を超克する指針をしめす!

物語論 基礎と応用
講談社選書メチエ
動物もコミュニケーションを行うが、物語を語れるのは人間だけである。「物語」とは、人間の言語活動に特徴的かつ本質的なものである。では、ここでいう「物語」とはいったい何か――。フランス構造主義の物語論を中心に、その理論を紹介しつつ、カフカ、田山花袋、マルケスから、「シン・ゴジラ」「エヴァンゲリオン」「この世界の片隅に」まで、具体的なテクストを分析し、物語そのものの構造を論じ、設計図を明らかにしていく。
私たちは常に、物語に囲まれて生きている。小説や漫画などのフィクションが「物語」なのはもちろん、著者によれば、スポーツ中継や日々のニュース、歴史叙述も「物語」だという。では、ここでいう「物語」とは何か。どういう性質をもつものなのか――。これを論じてきた理論が物語論(ナラトロジー)である。
動物もコミュニケーションを行えるが、物語を語れるのは人間だけである。その意味では、物語とは、人間の言語活動に特徴的かつ本質的なものである。しかし、「物語」というと、これまでは往々にして、作者の意図や作品の社会的背景、歴史的意味の解釈にのみ、力点がおかれていた。本書でいう「物語論」はそうではなく、言語学や文体論を用いながら、物語そのものの構造を論じ、設計図を分析していく。
第一部では、フランス構造主義の物語論を中心に、その理論を紹介し、第二部では、カフカ、田山花袋、ボルヘスから、「シン・ゴジラ」「エヴァンゲリオン」「この世界の片隅に」まで、具体的なテクストを分析し、私たちの現実認識が、物語の仕方によっていることを明らかにしていく。

ヨハネス・コメニウス 汎知学の光
講談社選書メチエ
ヨーロッパの知られざる巨人ヨハネス・アモス・コメニウス(1592-1670年)。近代教育学の祖とされるこの人物が示した無限の広がりを一望する初の本格的概説書! 哲学者として、宗教家として、そして政治家として、ヨーロッパを舞台に縦横無尽の活動を繰り広げたコメニウスを支えたものは何か? 世界のあらゆる事象を把握しようとするコメニウスの「汎知学(パンソフィア)」の構想を「光」をキーワードにして読み解く。
本書は、ヨーロッパの知られざる巨人ヨハネス・アモス・コメニウス(1592-1670年)の全貌を明らかにする本格的概説書である。日常生活の中で知らないことに出会ったとき、私たちはインターネットを開いて検索する。その時その場のニーズに合わせて無数にある情報にアクセスできるが、この「参照」という行為を意識することはほとんどない。しかし、歴史を振り返れば、誰もがさまざまな情報を自由に参照できるようになったのは、つい最近のことにすぎないことに気づく。そして、それを可能にした人こそコメニウスだった。
『世界図絵』(1658年)を開けば、150項目に分類された多岐にわたる事象が取り上げられ、それぞれの項目に対応した絵が挿入されているのを目にする。コメニウスは言う。この書で示したのは「世界全体と言語のすべての概要」である、と。それを手軽に学べるようにすることこそ、コメニウスが実現したものである。それゆえ彼は近代教育学の祖とされるが、しかしコメニウスをある学問領域に押し込めては理解できない。
「世界全体と言語のすべて」を把握しようとした背景には、コメニウスがヤン・フス(1370頃-1415年)の系譜に連なる神学者だったという事実がある。自身の内面に向かう宗教を捉えるとき、コメニウスは社会への視点を忘れなかった。そうして内面と社会のあいだで揺れる姿を描き出したのが、小説『地上の迷宮と心の楽園』(1631年)である。「迷宮」としての「地上」の世界で、いかにして「心の楽園」を実現するのか。その問いに導かれて、コメニウスは実際にさまざまな社会の問題に関与していく。ヨーロッパを遍歴しながら数多くの君主との関係が生まれ、政治的活動を行った。こうした多様な活動を支えていたのが哲学である。ルネサンスの諸学問に取り組んだコメニウスは、あらゆる事柄を独自の世界観で再構成した知の体系を構想し、それを「汎知学(パンソフィア)」と呼んだ。それは『人間的事柄の改善についての総合的熟議』という大著に結実する。
このように多様で巨大な存在であるコメニウスを、著者は「光」をキーワードにして読み解いていく。人間は世界から光を受け取り、みずからもまた光を発する存在である。無数の光が飛び交うこの世界の中に「心の楽園」を築き上げること。困難に満ちた世界の中で、この偉人を知ることには絶大な意味がある。

氏神さまと鎮守さま 神社の民俗史
講談社選書メチエ
日ごろ意識することは少なくとも、初詣や秋祭り、七五三のお宮参りと、私たちの日常に神社は寄りそっている。我々にとって、神とは、そして日本とはなにか? 民俗調査の成果をふまえ、ごくふつうの村や町の一画に祭られる「氏神」や「鎮守」をキーワードに、つねに人びとの生活とともにあった土地や氏と不可分の神々や祭礼を精緻に探究。日本人の神観念や信心のかたちとしての神や神社の姿と変容のさまを、いきいきと描き出す。

コンスタンツェ・モーツァルト 「悪妻」伝説の虚実
講談社選書メチエ
音楽学者にして熱烈なモーツァルト崇拝者でもあったアルフレート・アインシュタイン(1880~1952)はモーツァルトの妻・コンスタンツェを、はっきりと「琥珀のなかの蠅」呼ばわりしました。ご馳走と見ればすぐさまそれにたかりにくる醜く、汚らわしく、うっとうしい存在。天才の妻として、なぜこれほどまでに、コンスタンツェは否定的なまなざしで受けとめられねばならなかったのか?
音楽学者にして熱烈なモーツァルト崇拝者でもあったアルフレート・アインシュタイン(1880~1952)はモーツァルトの妻・コンスタンツェを、はっきりと「琥珀のなかの蠅」呼ばわりしました。ご馳走と見ればすぐさまそれにたかりにくる醜く、汚らわしく、うっとうしい存在。そのような存在が、琥珀のようなモーツァルトと密接にかかわったからこそ、彼女は人びとの記憶に残るようになったのだというきわめて否定的な見解が、彼の言にはあらわれています。
なぜこれほどまでに、コンスタンツェは否定的なまなざしで受けとめられてきたのか?
この疑問を解くべく、本書ではまず、コンスタンツェの実家であるウェーバー家、および彼女の生涯を概観します。ただし、右の事柄についての資料はけっしてじゅうぶんとは言えず、まだ多くの点が謎に包まれていることは、先にお断りしておきましょう。またそのような状況に置かれている対象を前に、その人物の善し悪しに関して断定的な評価を下すつもりもありません。むしろアインシュタインの評伝を一例としてさまざまなバイアスがかけられた彼女の人生に関し、可能なかぎりその真実の足取りを再構成してみたいのです。
そして──ここからがこの本の真の目的となるのですが──、彼女が数あるモーツァルト伝やモーツァルト関係のメディアにおいて、どのように描かれ、どのように評価されてきたのかを追ってゆきます。なぜアインシュタインは彼女を「蠅」と呼んだのか、なぜ彼女はヨーロッパからみれば遥か東の島国においてさえ「悪妻」というレッテルを貼られるようになったのか。コンスタンツェに関する受容史を探るのが、じつは本書最大の狙いにほかなりません。
それにしても、人はコンスタンツェにいったいなにを見てきたのでしょう? またそのような視線のなかに、人はどのような想いをこめてきたのでしょう? 「悪妻」と呼ばれつづけてきたひとりの女性をめぐって、人間の抱える複雑な羨望と嫉妬、それぞれの置かれた時代相が解き明かされてゆくはずです。(序章を抜粋要約)

共同体のかたち イメージと人々の存在をめぐって
講談社選書メチエ
グローバル市場経済の秩序が政治に優先されるなか、人間は国民国家内部では表象されえず、市場の「リソース」となる。一方でそれと同期して現れる「エクスポジション」と呼ぶべきアート群。共同性を表象する効果を担ったイメージ(像)は失われたのか。結びつきの根拠が揺らいでいる状況のなか、共同体はどこに見出せるのか。アートの機能とナンシー、アガンベンなどの思想から、人間と共同性の関係を考察。
グローバル市場経済の秩序が政治に優先されるなか、人間は国民国家内部では表象されえず、市場の「リソース」となる。一方でそれと同期して現れる「エクスポジション」と呼ぶべきアート群。
共同性を表象する効果を担ったイメージ(像)は失われたのか。結びつきの根拠が揺らいでいる状況のなか、共同体はどこに見出せるのか。
イメージの機能やナンシー、アガンベン、エスポジトなどの思想を参照し、いまや「剥き出しの生」となった人間の存在様態を考察する。

意思決定の心理学 脳とこころの傾向と対策
講談社選書メチエ
生きるとは意思決定の連続だ。本書は心理学と脳科学の最新の研究から、さまざまな具体的事例や実験の結果を紹介しながら、意思決定のメカニズムを探る。情動と理性という対立する「こころのはたらき」に注目する二重過程理論。マシュマロテスト、損失回避性、疲労、ブドウ糖、依存症などなど、意思決定のメカニズムと影響を与える要因を徹底的に検証。わかっているようで実はよくわからない、自分の「こころ」を知るための必読書。
ケーキを食べるか? 休日に何をするか? 投資先をどこにするか? 人間関係を円滑にするためにどう行動するか?
生活は意思決定の連続です。あるときは上手く意思決定ができ、あるときは失敗する。あるときはすぐに決まるのに、あるときはなかなか決められない。なぜでしょうか?
本書は心理学と脳科学の最新の研究から、さまざまな具体的事例や実験の結果を紹介しながら、わたしたちの意思決定のメカニズムを探っていきます。
情動と理性というふたつの対立する「こころのはたらき」に注目する二重過程理論がバックボーンになっています。
マシュマロテスト、トロッコジレンマ、歩道橋ジレンマ、損失回避性、疲労、ブドウ糖、依存症などなど、意思決定のメカニズムと影響を与える要因を徹底的に検証します。
脳とこころの癖や傾向を知っておくことで、わたしたちはよりよい意思決定が可能になります。
わかっているようで実はよくわからない、自分の「こころ」を知るための必読書です。