講談社選書メチエ作品一覧

電鉄は聖地をめざす 都市と鉄道の日本近代史
講談社選書メチエ
小林一三神話を覆す! 私鉄黎明期の語られざる歴史
「阪急や阪神、東急や西武といった”電鉄”が、衛生的で健全な”田園都市”を郊外につくりあげた」
――よく知られたこの私鉄をめぐる物語の深層には、「寺社仏閣」を舞台とする語られざる歴史があった。初期の電鉄をめぐる世界では、神社仏閣とそれを取り巻く人々の、ある意味無軌道とも言える行動が郊外空間を作り出していったのである。それは、近代的な都市計画といった無機質なものでも、経済的な功利性のみだけでも説明のつくものではなかった。とくに、われわれが通常イメージするような鉄道が確立してくる以前の黎明期には、現在の視点からみると「怪しい」人々が蠢いていたのである。
そうした人々を突き動かしていたのは、寺院や神社を興隆させたいという熱情であった。「わが門前に鉄道を」……そのすさまじいまでのパワーが、電鉄を、ひいては日本の都市を作り出していったのである。本書は、「電鉄」と社寺を取り巻く「怪しい人々」に光を当てることで、都市と鉄道という近代化の物語の陰に隠された歴史を明らかにしようというものである。
近代の荒波を生き抜く希望を鉄道に見いだした寺社と、そこに成功栄達の機を嗅ぎつける怪しくも逞しき人々が織りなす、情熱と欲望、野望と蹉跌のドラマ。鉄道誘致と都市開発をめぐる、ダイナミックで滑稽で、そして儚い、無二の日本近代都市形成史。
【本書の内容】
序章 「電鉄」はいかにして生まれたか
第一章 凄腕住職たちの群像――新勝寺と成田の鉄道
第二章 寺門興隆と名所開発――川崎大師平間寺と京浜電鉄
第三章 「桁外れの奇漢」がつくった東京――穴守稲荷神社と京浜電鉄
第四章 金儲けは電車に限る――池上本門寺と池上電気鉄道
第五章 葬式電車出発進行――寺院墓地問題と電鉄
終章 日本近代大都市と電鉄のゆくえ

アンコール
講談社選書メチエ
ジャック・ラカン(1901-81年)は、「フロイトへの回帰」を唱えて精神分析の中興の祖となった分析家にして、第一級の思想家でもあった。サン=タンヌ病院などで臨床に専念したラカンは、独自の分析手法「短時間セッション」を開発したが、これがパリ精神分析協会の分裂を引き起こし、フランス精神分析協会に参加する。しかし、国際精神分析協会への加盟条件としてラカンの「教育分析家」資格取消を要求されたため、1964年にはパリ・フロイト派を創設した。
こうした四分五裂を経ながら精神分析を刷新し続けたラカンが自身の精神分析理論について生前に公刊した著作は、ただ1冊。それが『エクリ』(1966年)だが、これは難解な内容をもつ上、日本語訳には問題があると言わざるをえない。そのような状態が続く中、1953年から始められた「セミネール」は多くの聴衆を集めただけでなく、ラカン生前中の1973年から公刊され始め、聴衆を前に語られた貴重な記録となった。
そのセミネールの日本語訳は、1987年から着手されたが、パリ・フロイト派創設の時期にあたる1963-64年度の『精神分析の四基本概念』までの時期のものに限定されている上、価格も高く、また現在では入手できなくなっているものも多い。
そうした状況の中、選書メチエの1冊として、最も名高い『アンコール』をお届けする。これは1972-73年度のセミネールであり、既存の邦訳からはうかがうことのできない後期ラカンの真髄が語られている。「無意識はひとつのランガージュとして構造化されている」というテーゼから出発し、「想像界」、「象徴界」、「現実界」の分類を中心に練り上げられた前期の思想は、いかなる展開を遂げたのか? このセミネールで、ラカンは「愛」という主題を根底に据え、精神分析を新たな領域に飛躍させていく。「恍惚」や「美」など、さまざまな側面から「愛」に迫り、「無知」という領域が指摘される。そうして「女の享楽」という問題が提示され、以降、最晩年まで続けられたセミネールで展開される後期ラカンが幕を開く。
さまざまな仕掛けが凝らされたフランス語を「日本語のテクスト」として読みうるものにするべく、定評ある二人の訳者が全身全霊を捧げて完成させた待望のセミネール。誰もが待ち望んだ1冊が、ついに登場。
*お詫びと訂正
本書第1刷の著者略歴(266頁)に誤りがありました。心よりお詫びいたしますとともに、以下のとおり訂正させていただきます。なお、第2刷以降は訂正いたします。
【誤】
高等師範学校で哲学、のちに医学・精神病理学を学ぶ。学位取得後はサン=タンヌ病院などで臨床に専念。
【正】
パリ大学医学部などで学び、サン=タンヌ病院などで臨床に専念。

フランス史
講談社選書メチエ
フランク王国からミッテラン政権まで、これ一冊で見通せる!
フランス国内はもとより国外においても定番書として読まれ続けている碩学による通史、平易な訳文による日本語版がついに刊行。メロヴィング朝、カロリング朝、ルネッサンス、絶対王政、革命、世界大戦、第五共和政……一気通貫に見渡し、長大な歴史の要点がわかる! 政治・文化・経済ほかあらゆる面で、日本人の関心を強く引きつづけてきたフランスという国をより深く、明確に知るために必須の、背骨としての歴史を見渡す一冊。こうして、フランスはフランスとなった!
【本書の内容】
第一章 起源
第二章 メロヴィング朝
第三章 カロリング朝
第四章 カペー朝
第五章 カペー朝時代のフランスの諸相
第六章 百年戦争
第七章 近世の夜明け──一四六一~一五一五年
第八章 絶対王政の誕生──一五一五年~五九年
第九章 宗教戦争
第十章 国家の再建──アンリ四世とルイ十三世
第十一章 アンヌ・ドートリシュとマザラン
第十二章 ルイ十四世の内政
第十三章 ルイ十四世の外交政策
第十四章 ルイ十五世の治世──一七一五~七四年
第十五章 ルイ十六世とアンシャン・レジームの危機
第十六章 革 命──王政の崩壊
第十七章 フランス革命と第一共和政
第十八章 ナポレオン
第十九章 立憲王政
第二十章 第二共和政
第二十一章 第二帝政──内政
第二十二章 第二帝政──外交
第二十三章 第三共和政──保守党から急進社会党へ
第二十四章 第一次世界大戦
第二十五章 両大戦間の第三共和政──一九一九~三九年
第二十六章 第二次世界大戦
第二十七章 第四共和政
第二十八章 第五共和政
第二十九章 フランソワ・ミッテランの治世──一九八一~九五
監訳者あとがき(鹿島茂)

万年筆バイブル
講談社選書メチエ
「書き味」の良さとは、どこから来るのものなのか。ペン芯が“万年筆の心臓”と言われる理由は。“万年筆の頭脳”ペン先の精度の違いは、どう表れるのか。インク粘度と表面張力が、万年筆に及ぼす影響、 各社ブランドの、傾向と特徴は……。歴史から、構造、ブランド考まで、万年筆のプロ集団が、徹底解明。メールでは味わえない、極上の「書く愉しみ」へあなたを誘う、「万年筆」知識と教養の書!
空前のインクブームをきっかけに、近年人気復活中の「万年筆」。
その小さな1本には、いろんな秘密が隠されている。
「書き味」の良さとは、どこから来るものか。
“万年筆の頭脳”ペン先の精度の違いは、どう表れるのか。
ペン芯が“万年筆の心臓”と言われる理由は。
インク粘度と表面張力が、万年筆に与える影響、
各社ブランドの、傾向と特徴は……。
メールでは味わえない、極上の「書く愉しみ」を教えてくれる、万年筆の世界。
そんな運命の一本に出会い、存分に使いこなすための、知識と教養の書!
第1章 「自分だけの1本」の選び方
第2章 インクと万年筆の正しい関係
第3章 万年筆の構造
第4章 より広く、深く知るための、万年筆世界地図
年譜 万年筆の200年史
ドキュメント パイロット工場見学ツアー 万年筆ができるまで

いつもそばには本があった。
講談社選書メチエ
1冊の本には、たくさんの記憶がまとわりついている。その本を買った書店の光景、その本を読んだ場所に流れていた音楽、そしてその本について語り合った友人……。そんな書物をめぐる記憶のネットワークが交錯することで、よりきめ細かく、より豊かなものになることを伝えるため、二人の著者が相手に触発されつつ交互に書き連ねた16のエッセイ。人文書の衰退、人文学の危機が自明視される世の中に贈る、情熱にあふれる1冊!
1冊の書物には、それが大切な本であればあるほど、たくさんの記憶がまとわりついている。その本を買った書店の光景、その本を読んだ場所に流れていた音楽、そしてその本について語り合った友人……。そんな記憶のネットワークが積み重なり、他の人たちのネットワークと絡み合っていくにつれて、書物という経験は、よりきめ細やかで、より豊かなものになっていく──。
本書は、そんな書物をめぐる記憶のネットワークを伝えるために、二人の著者がみずからの経験に基づいて書いたものです。ただし、これは「対談」でも「往復書簡」でもありません。
キーワードは「観念連合」。ある考えやアイデアが別の考えやアイデアに結びつくことを示す言葉です。一人が1冊の本をめぐる記憶や考えを書く。それを読んだ相手は、その話に触発されて自分の中に生じた観念連合に導かれて新たなストーリーを綴る。そして、それを読んだ相手は……というように、本書は「連歌」のように織りなされた全16回のエッセイで構成されています。
取り上げられるのは「人文書」を中心とする100冊を越える書物たち。話題がどこに向かっていくのか分からないまま交互に書き継がれていったエッセイでは、人文書と出会った1990年代のこと、その後の四半世紀に起きた日本や世界の変化、思想や哲学をめぐる現在の状況……さまざまな話が語られ、個々の出来事と結びついた書物の数々が取り上げられています。本書を読む進めていくかたたちにも、ご自分の観念連合を触発されて、新たなネットワークを交錯させていってほしい。そんな願いを抱きながら、人文書の衰退、人文学の危機が自明視される世の中に、二人の著者が情熱をそそいだこの稀有な1冊をお届けします。

事故の哲学 ソーシャル・アクシデントと技術倫理
講談社選書メチエ
ディープラーニングしたAIの判断の責任は、だれがとればよいのでしょうか?人工物が複雑化すればするほど、事故の因果関係は不明瞭になります。被害は存在しても、加害者を特定できなくなります。また、小さな過失が、巨大事故を引き起こす可能性もますます大きくなっています。人工物が第二の自然になり、事故が第二の天災となる時代に、倫理はどうあるべきなのでしょうか。現在進行中の問題に深く切り込みます。
AI、iPS細胞、自動運転、IoT……。技術の発展は、とどまるところを知りません。身近な医療事故から超巨大な原発事故まで、事故もどんどん巨大化、複雑化しています。
産業革命以降、人工物(主に工学的に人間が作り出したもの)は、ますます大きなエネルギーを社会の中に出現させています。つまり、巨大事故の可能性も大きくなっているのです。
複雑な人工物の出現は、それを補完する社会制度を作ってきました。その制度の基本にある人間観、倫理観を考察します。すると明らかになってくるのが、事故と責任の関係です。
人工物が複雑化すればするほど、事故の因果関係は不明瞭になります。被害は存在しても、加害者を特定できなくなります。また、過失ともいえない過失が、巨大事故を引き起こす可能性がますます大きくなっています。
ディープラーニングしたAIの判断の責任は、だれがとればよいのでしょうか?
人工物が第二の自然になり、事故が第二の天災となる時代に、倫理はどうあるべきなのでしょうか。
現在進行中の問題に深く切り込みます。
【目次】
はじめに ソーシャル・アクシデントの時代
第一章 事故を考えるための技術論
第二章 安全は科学を超える
第三章 組織・システム・制度
第四章 無過失責任の誕生
第五章 人工物の存在論
最後に 天災化する事故
注
あとがき

創造と狂気の歴史 プラトンからドゥルーズまで
講談社選書メチエ
「創造」と「狂気」には切っても切れない深い結びつきがある──ビジネスの世界でも知られるこの問題は、実に2500年にも及ぶ壮大な歴史をもっている。プラトン、アリストテレスに始まり、デカルト、カント、ヘーゲルを経て、ラカン、デリダ、ドゥルーズまで。未曾有の思想史を大胆に、そして明快に描いていく本書は、気鋭の著者がついに解き放つ「主著」の名にふさわしい1冊である。まさに待望の書がここに堂々完成!
アップル社の最高経営責任者だったスティーヴ・ジョブズが「師」と仰いだ起業家ノーラン・ブッシュネルは、企業に創造性をもたらすには「クレイジー」な人物を雇うべきである、と説いている。ビジネスの世界でも「創造」と「狂気」には切っても切れないつながりがあることを、一流の企業人は理解していると言えるだろう。
だが、この「創造と狂気」という問題は、実に2500年にも及ぶ長い歴史をもっている。本書は、その広大にして無尽蔵な鉱脈を発掘していく旅である。
その旅は、「神的狂気」について論じたプラトン(前427-347年)から始まる。次いで、メランコリーと創造の結びつきを取り上げたアリストテレス(前384-322年)から《メレンコリアI》を描いた画家アルブレヒト・デューラー(1471-1528年)、そこに見出される創造性を追求したマルシリオ・フィチーノ(1433-99年)を経て、われわれは近代の始まりを告げるルネ・デカルト(1596-1650年)の登場に立ち会う。
デカルトに見出される狂気と不可分のものとしての哲学を受けて、あとに続いたイマヌエル・カント(1724-1804年)は狂気を隔離し、G. W. F. ヘーゲル(1770-1831年)は狂気を乗り越えようとした。しかし、時代は進み、詩人フリードリヒ・ヘルダーリン(1770-1843年)が象徴するように、創造をもたらす狂気は「統合失調症」としての姿をあらわにする。そのヘルダーリンの詩に触発された哲学者マルティン・ハイデガー(1889-1976年)が提示した問題系は、ジャック・ラカン(1901-81年)やジャン・ラプランシュ(1924-2012年)を通して精神分析の中で引き受けられる。そして、ここから現れ出た問題は、アントナン・アルトー(1896-1948年)という特異な人物を生み出しつつ、ミシェル・フーコー(1926-84年)、ジャック・デリダ(1930-2004年)、そしてジル・ドゥルーズ(1925-95年)によって展開されていく──。
このような壮大な歴史を大胆に、そして明快に描いていく本書は、気鋭の著者がついに解き放つ「主著」の名にふさわしい。まさに待望の堂々たる1冊が、ここに完成した。

小林秀雄の悲哀
講談社選書メチエ
「もう、終いにする」。戦後の知識世界に輝くビッグネーム・小林秀雄が、晩年、10年にわたって取り組んだ『本居宣長』は、執筆に難渋し、結論に達しないまま意外な一言で終わってしまった。日本が誇る知性は、なぜ最後の仕事で挫折したのか。彼がこの書物にかけた思い、そして小林がたどり着きたかった「ゴール」はどこにあったのか。小林の批評ぶりを多角的に検証しながら、批評とは何か、その原理について考える。
「もう、終いにする」
戦後の知識世界に輝くビッグネーム・小林秀雄が、晩年、10年にわたって取り組んだ『本居宣長』は、
執筆に難渋し、結論に達しないまま意外な一言で終わってしまった。
日本が誇る知性は、なぜ最後の仕事で挫折したのか。
彼がこの書物にかけた思い、企図、成果は?
そして小林がたどり着きたかった「ゴール」はどこにあったのか?
当代随一といわれた批評家のライフワーク『本居宣長』を丁寧に読み解き、
小林の批評ぶりを多角的に検討しながら、
批評とは何か、さらに批評を支える「原理」とは何かについて考える。
目次
序章
第2章 『本居宣長』という書物
第3章 外堀を埋める 『本居宣長』を読む・その1
第4章 源氏物語のほうへ 『本居宣長』を読む・その2
第5章 『古事記伝』を読む 『本居宣長』を読む・その3
第6章 『古事記伝』という仕事
第7章 小林秀雄の悲哀
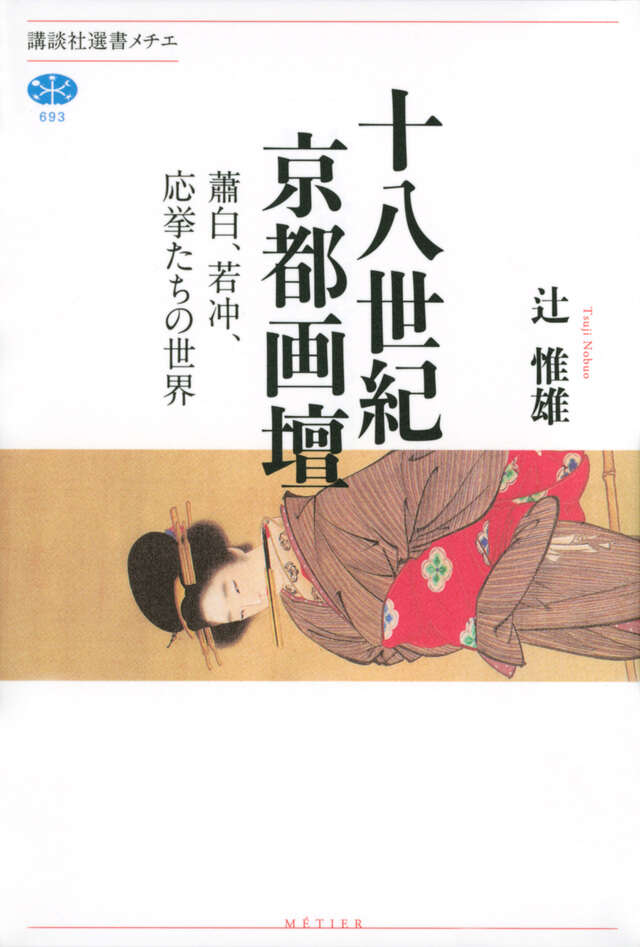
十八世紀京都画壇 蕭白、若冲、応挙たちの世界
講談社選書メチエ
蕪村や応挙、若冲、蘆雪に蕭白。ほぼ同時期、同じ地に豊かな才能が輩出した。旧来の手法から抜けだし、己の個性を恃んで、奔放に新しい表現を打ちだす。十八世紀の京都は、まさにルネサンスの地であった。「奇想」の美術史家・辻惟雄は、彼らの作品に向き合い、多数の論考を遺している。それらを抜粋し、作品の解釈から時代背景や人物像にも迫ってゆく。あの時代の京都を、彩りをもって甦らせる試みである。
蕪村や応挙、若冲、さらに蘆雪に蕭白。ほぼ同時期、同じ地に豊かな才能が輩出した。彼らは旧来の手法から抜けだし、己の個性を恃んで、奔放に新しい表現を打ちだす。多士済々、百花繚乱。十八世紀の京都は、まさにルネサンスの地であった。「奇想」の美術史家・辻惟雄は、彼らの作品に向き合い、多数の論考を遺している。それらを抜粋し、作品の解釈から時代背景や人物像にも迫ってゆく。あの時代の京都を、彩りをもって甦らせる試みである。

天然知能
講談社選書メチエ
2019年2月10日 「毎日新聞」書評 中村桂子さん
2019年2月27日 「朝日新聞」文芸時評 磯崎憲一郎さん
2019年3月9日 「日本経済新聞」書評 野家啓一さん
2019年3月9日 「朝日新聞」書評 野矢茂樹さん
2019年3月30日 「聖教新聞」書評
2019年4月21日 「読売新聞」書評 鈴木洋仁さん
2019年4月28日 「産経新聞」文芸時評 石原千秋さん
2019年6月24日 「公明新聞」書評 小川仁志さん
2020年1月21日 「毎日新聞」読書日記 西垣通さん
『ケトル』2019年4月号 書評 橋爪大三郎さん
『週刊朝日』4・19号 「ベストセラー解読」永江朗さん
*
「考えるな、感じろ」とブルース・リーは言った。計算を間違い、マニュアルを守れず、ふと何かが降りてくる。すべて知性の賜物である。今こそ天然知能を解放しよう。人工知能と対立するのではなく、想像もつかない「外部」と邂逅するために。
*
一見やさしく書かれていますが、バカにしてはいけません。世界の見方を変えてくれます。――養老孟司(解剖学者)
AIブームへの正しいカウンター。自然/人工の檻の外へ、知性を解き放つ! AIみたいな人間と人間みたいなAIにあふれる社会への挑戦状。――吉川浩満(文筆家)
*
「考えるな、感じろ」とブルース・リーは言った。
山の向こうにも同じように風景が広がることや、
太平洋でイワシが泳いでいることを信じられる。
今までのこだわりが、突然どうでもよくなる。
計算を間違い、マニュアルを守れず、ふと何かが降りてくる。
それらはすべて知性の賜物である。
生きものの知性である。
今こそ天然知能を解放しよう。
人工知能と対立するのではなく、
意識の向こう側で、想像もつかない「外部」と邂逅するために。
わたしがわたしとして存在するための哲学。

暗号通貨の経済学 21世紀の貨幣論
講談社選書メチエ
「お金とは何か」から暗号通貨を捉え直し、ブロックチェーンの可能性をゲーム理論で追究する。ビットコイン、イーサリアム、リップル……暗号通貨(仮想通貨)はいかにして「お金」になるのか。技術・経済・社会の大転換期、この革命的な技術が世界をどう変えるのか、総合的に把握するための一冊。暗号学×経済学=暗号経済学の誕生。ナンダ、そういうことだったのか!◎RSA暗号・楕円曲線暗号解説も収録。
「お金とは何か」から暗号通貨を捉え直し、ブロックチェーンの可能性をゲーム理論で追究する。
ビットコイン、イーサリアム、リップル……暗号通貨(仮想通貨)はいかにして「お金」になるのか。
技術・経済・社会の大転換期、この革命的な技術が世界をどう変えるのか、総合的に把握するための一冊。
暗号学×経済学=暗号経済学の誕生。
ナンダ、そういうことだったのか!
◎RSA暗号・楕円曲線暗号解説も収録。
*
第1部では、ビットコインを始めとする暗号通貨の基礎となるブロックチェーンの仕組みの要点を、数式など使わずにわかりやすく解説します。
ブロックチェーンという革新的な暗号技術は、世界をどう変えていくのか? オープンソースとプロプライエタリ、中央集権と分散化といったブロックチェーンが提起する哲学的な意味、そして通貨以外でのインパクトについても言及します。
第2部では、「お金とはなにか」を考えます。
価格の乱高下やセキュリティ問題など、いまだ暗号通貨を疑問視する声も強いのが現状ですが、これまで経済学が培ってきた貨幣理論を参照しながら、暗号通貨はいかにして「お金」たり得るのかを見ていきます。価格が安定する時とはすなわち、暗号通貨が「お金」になる時といえるでしょう。お金とはなにかという見識は、投資にも役立つかもしれません。
第3部は、ゲーム理論でブロックチェーンを検討します。
人間の行動は不合理すぎ、理論通りにいかないことが指摘されるゲーム理論ですが、アルゴリズムであるブロックチェーンの世界では、理論のままに均衡が実現されることになります。「囚人のジレンマ」などのゲーム理論をざっくりとおさらいしつつ、新しい世界を垣間見る章です。
補章として、公開鍵暗号とハッシュ関数の原理について、本文では簡略化した詳細部分を解説します。「そういうことだったのか!」と膝を打つこと間違いなし。数理暗号として、有名なRSA暗号と楕円曲線暗号の両方に言及しています。

オカルティズム 非理性のヨーロッパ
講談社選書メチエ
2019年3月1日「週刊読書人」書評 蔵持不三也さん〈書かれるべきテーマを書くべき研究者が書く〉
2019年3月2日「朝日新聞」書評 柄谷行人さん〈神なき時代をも貫く歴史的考察〉
2019年4月21日「毎日新聞」書評 鹿島茂さん〈理性と非理性を同じ「枠組み」で理解〉
2019年4月10日「読売新聞」著者インタビュー
『週刊金曜日』(2019年1月25日号)書評 永田希さん〈豊穣で危険な陰の思想史〉
ヘルメス文書、グノーシス、カバラー、タロット、黒ミサ、フリーメーソンやイリュミナティなどの秘密結社、そしてナチ・オカルティズムとユダヤ陰謀論……古代から現代まで、オカルトは人間の歴史と共にある。一方、「魔女狩り」の終焉とともに近代が始まり、その意味合いは大きく変貌する――。理性の時代を貫く非理性の系譜とは何か。世界観の変遷を闇の側からたどる、濃密なオカルティズム思想史!
【目次】
序章 毒薬事件――悪魔の時代の終焉と近代のパラドクス
第一章 オカルティズムとは何か
第二章 オカルティズム・エゾテリスムの伝統
第三章 イリュミニズムとルソー――近代オカルティズム前史
第四章 ユートピア思想と左派オカルティズム
第五章 エリファス・レヴィ――近代オカルティズムの祖
第六章 聖母マリア出現と右派オカルティズム
第七章 メスマーの「動物磁気」とその影響
第八章 心霊術の時代
第九章 科学の時代のオカルティズム――心霊術と心霊科学
第十章 禍々しくも妖しく――陰謀論を超えて
終章 神なき時代のオカルティズム

記憶術全史 ムネモシュネの饗宴
講談社選書メチエ
スマホをアップデートしたら、画面がガラッと変わって、お目当てのアプリや写真がどこにあるのか分からなくなった……そんな経験を思い出せば、「記憶」は「場所」と結びついていることが分かる。この特性を利用して膨大な記憶を整理・利用できるようにする技法が、かつてヨーロッパに存在した。古代ギリシアで生まれ、中世を経て、ルネサンスで隆盛を極めた記憶術の歴史を一望する書。最先端で活躍する気鋭の著者による決定版!
パソコンやスマホをアップデートしたら、画面がガラッと変わって、お目当てのアプリや写真がどこにあるのか分からなくなって呆然。あるいは、近所のコンビニが改装されて、棚の配置がすっかり変わってしまったら、お気に入りのお菓子や飲み物がどこに置いてあるのか分からなくなってイライラ。
──こんな経験は、きっと誰にでもあることでしょう。
このように、記憶というものは「場所」と結びついています。そして、ヨーロッパには、この特性を利用して、膨大な記憶を上手に整理し、必要な時にすぐ取り出せるようにする技法が存在していました。
それが本書のテーマです。
古代ギリシアで産声をあげた記憶術は、紙が貴重だった時代、長大な弁論を暗唱するために開発されました。キケロやクインティリアヌスといった一流の弁論家はもちろん、カエサルも会得していたとされるその技法は、中世には下火になるものの、やがてキリスト教の影響を受けて変容します。そして、15世紀に始まるルネサンスの中で華麗な復活を遂げ、指南書が陸続と出現しました。ところが、17世紀に入った途端、隆盛を極めたかに見えたこの技法は、忽然と姿を消すのです。いったい何が起きたのでしょう?
記憶術は、20世紀になって、パオロ・ロッシ『普遍の鍵』(1960年)と、フランセス・イエイツ『記憶術』(1966年)という記念碑的な著作によって、一挙に脚光を浴びるようになりました。いずれも邦訳が刊行され、日本でも話題になったのをご記憶のかたも多いことでしょう。それから半世紀を経て、記憶術は、文学、哲学、史学、美術史、建築史、音楽学、科学史、思想史、イメージ人類学、教育論、メディア論、記号論、医学など、実に多彩な領域の論客たちが名乗りをあげるようになり、新たなシーンが現れています。
本書は、その最先端で世界的に活躍する気鋭の著者が、記憶術の誕生から黄昏までを一望できるようにと願って執筆した、今後のスタンダートになること間違いなしの決定版です。

養生の智慧と気の思想 貝原益軒に至る未病の文化を読む
講談社選書メチエ
「酒は微酔にのみ、花は半開に見る」――儒者として医者として古典漢籍を総覧し本草学に通暁する貝原益軒が到達した「養生」の要諦である。人間が本来持っている「寿(いのちながき)」性質を、日常生活で現実のかたちにするにはどう生きたらいいのか。古代中国から日本へ連綿と続く「気」の世界観に支えられた未病を最善とする養生文化。江戸時代の貝原益軒『養生訓』に結実した大いなる智慧を読む。

〈海賊〉の大英帝国 掠奪と交易の四百年史
講談社選書メチエ
イギリスは貿易と戦争、そして「掠奪」で世界の海を制したのだった! 最強の海洋帝国と荒くれ者たちが動かした歴史を描く驚異的論考! 注目の若手研究者が、大きな歴史のうねりと、海の男たちの苦闘とを多層的に、鮮やかに描き出す。大海原の波濤の向こうに、誰も知らない世界史があった!
イギリスは貿易と戦争、そして「掠奪」で世界の海を制したのだった! 最強の海洋帝国と荒くれ者たちが動かした歴史を描く驚異的論考。
暴れまわる掠奪者たちを、法という鎖で縛り猟犬として飼い慣らしたイギリス政府は、新大陸・大西洋世界への進出競争や重商主義による貿易抗争を、「管理統制された掠奪」によって有利に進めんとした。海が世界史を転回させる舞台となった16世紀から、自由貿易が重商主義にとってかわる19世紀まで、軍人、海賊、政治家、商人たちの野望うずまく歴史のダイナミズムを活写する。
スペインの船や植民地を荒らしまわる「掠奪世界周航」をやってのけナイトの称号を得たフランシス・ドレイク、ジャマイカを根城にカリブ海で掠奪をくりひろげる「バッカニア」、インド洋や紅海への掠奪行を敢行する「紅海者」、北米の植民地と深く結びつく海賊たち……彼らはいかに「活躍」したか? 海軍や政府は彼らの力をどう利用したか? 注目の若手研究者が、大きな歴史のうねりと、海の男たちの苦闘とを多層的に、鮮やかに描き出す。大海原の波濤の向こうに、誰も知らない世界史があった!

なぜ私は一続きの私であるのか ベルクソン・ドゥルーズ・精神病理
講談社選書メチエ
オートポイエーシスという閉じた系の身体でありながら、意識が立ち上がるに際しては外部に連結する開口部を持たなければならないという矛盾。意識という現象はいったい何なのか。脳の働きとの関係はどうなっているのか。それは「私」という一続きの事態をどう成立させているのか。脳科学研究が「意識」の物質への還元を方向付ける趨勢に反駁したベルクソン、さらにドゥルーズの理論を参照し「私」の立ち上がる現場に迫る。
私の身体と私の意識。身体の生はオートポイエーシスという閉じた系であるのに、意識はそのつどの神経ネットワークを物質的基盤としつつも「私」が立ち上がるに際しては外部へと連結する開口部を持たなければならないという矛盾。脳科学研究が「意識」の物質への還元を方向付けるなか、20世紀初めにはベルクソンが反駁の理論を打ち立てた。
意識という現象はいったい何なのか。脳の働きとの関係はどうなっているのか。それは「私」という一続きの事態をどう成立させているのか。
精神病理学者である著者が、さまざまな症例を引き、ベルクソン・ドゥルーズの理論を参照しながら、「私」の立ち上がる現場を突き詰めていく。

胃弱・癇癪・夏目漱石 持病で読み解く文士の生涯
講談社選書メチエ
人間嫌いの厭世病。人の心の深い闇を描いた夏目漱石は、多病持ちだった。疱瘡、眼病、強度の神経衰弱、糖尿病、結核への恐怖、胃潰瘍……。次々襲う病魔と、文豪はいかに闘ったのか。医師との付き合い方、その診療にミスはなかったのか。そして病は、彼の生み出した文学にどんな影響を与えたのかーー。ままならない人生に抗い、嫉妬し、怒り、書き続けた49年。その生涯を、「病」をキーワードに読み解く!
人間嫌いの厭世病。人の心の深い闇を描いた夏目漱石は、多病持ちだった。
疱瘡、眼病、強度の神経衰弱、糖尿病、結核への恐怖、胃潰瘍……。
次々襲う病魔と、文豪はいかに闘ったのか。
医師との付き合い方にミスはなかったのか。
診察の中身は、本当の死因は何だったのか。
そして病は、彼の生み出した文学にどんな影響を与えたのかーー。
ままならない人生に抗い、嫉妬し、怒り、書き続けた49年。
作品、書簡、家族、知人の証言や、当時のカルテを掘り起こし、
その生涯を、「病」という切り口から読み解く!
内容
はじめに ミザンスロピック病
第一章 変人医者が生きかたのお手本
第二章 円覚寺参禅をめぐって
第三章 左利きの文人
第四章 朝日入社前後
第五章 新聞文士
第六章 神経衰弱の実相
第七章 胃が悲鳴をあげている
第八章 森田療法と漱石
第九章 修善寺の大患
第十章 急逝の裏に
むすびに 原稿用紙上の死
本文より)
漱石は頭を掻きむしるようにして、「頭がどうかしている。水をかけてくれ、水をかけてくれ」と唸るようにせきたてた。/見ると、夫は白目を剥いて、尋常ではない。/夫人は、ともかく水をと思い、そばのヤカンから水を口に含んでは口移しに水を与え、そして、漱石の求めに応じて、「貴方、しっかりしなさいよ、しっかりしなさいよ」と言いながら、ヤカンの水を植木鉢に水をやるように、夫の頭に勢いよくかけたのだった。「ああ、いい気持だ。ほんとうにいい気持だ」(「第十章」より)

「生命多元性原理」入門
講談社選書メチエ
なぜ生命は「多」を求めるのか?
遺伝、発生、進化の基本から最先端生命科学の肝まで、トップランナーが明快に解説する驚異の入門書
なんで地球にはこんなやたらに生き物がいるんだろう?
遺伝、発生、進化……なんでこんな複雑なシステムができたんだろう?
それには深いわけがある!
「多様性」をキーにして、DNA組換えやエビジェネティクス、進化や発生の原理など、最先端生命科学のキモを明快に解説。さらに、いま注目の新技術「CRISPR」や非コードDNAの科学的意味がジャック・デリダの思想と響き合うことの発見まで、最新の生命像と現代思想との共鳴させながら、根源的な「多元性」の原理へと読者を誘う。
【本書の内容】
第一章 地球生命史と生命多元性
第二章 DNAから考える
第三章 究極的目的から考える
第四章 「個体」と「発生」から考える
第五章 生命の多元性、人間の多元性

機械カニバリズム 人間なきあとの人類学へ
講談社選書メチエ
「シンギュラリティ」「IoTで豊かな未来」「鉄腕アトム」「ターミネーター」……私たちは、機械を愛し、憎んでいる。では機械のほうから「私たち」を見たらどうなる? テクノロジーと深く結びつく人間は、あらたな存在に生まれ変わっているのかもしれない。
人類学者カストロは、アマゾンにおける食人=カニバリズムを、「他者の視点から自らを捉え、自己を他者としてつくりあげるための営為」として描き出した。「機械カニバリズム」は、テクノロジーによって私たちが変容ゆくことを捉える試みである。将棋ソフトによってプロ棋士と将棋が、SNSによってコミュニケーションと社会が、いままさに変容しているなか、「人間」観そのものが刷新されていくべきなのだ。気鋭の人類学者が、「現在のなかにある未来」を探る、痛快かつ真摯な思考!
川上量生氏コメント――
わたしたちはAIが人間の能力を凌駕しつつある歴史的過程の中にいます。AIと人間とどちらが優れているのか、そういう問いが日常的に飛び交う世の中で過ごすのも、この時代に生を受けた運命としてはやむを得ないことでしょう。
しかしながら実際にはこの問いは、そもそも正しくなかったことが明らかになってきました。いったい「優れている」とはなにか? AIとはなにか? そしてなによりも人間とはなにか? という、より大きな疑問が頭をもたげてきたからです。人間とはそもそも優れているのか、機械とは、そしてAIとはなにが違うというのか。そして真実が明るみになったときに、人類ははたして結果を受け入れることができるのでしょうか。
いささか大袈裟ではありますが、人間社会がAIの時代を受け入れるための礎石にならん、という決意で始めた将棋電王戦を、本書はAI時代における社会的な役割から解き明かしてくれました。また、より大きな視点で、ニコニコ動画を含めたネット社会についても、人間と技術の関わりから、どう捉えるべきかを示してくれています。
こういう議論はまだまだ始まったばかりで、21世紀の人類の最大の哲学的テーマであると思う次第です。
【本書の内容】
現在のなかの未来
ソフトという他者
探索から評価へ
知性と情動
強さとは何か
記号の離床
監視からモニタリングへ
生きている機械

魅せる自分のつくりかた 〈演劇的教養〉のすすめ
講談社選書メチエ
「演劇」は役者が舞台で演じるものだけではない。一人でできる《発声》や《海の歩行》から、数人で行う《漫才》や《ものまね》、本格的なストーリーを展開する《ショート・ストーリーズ》まで、具体的なレッスンを手引きとともに紹介し、演劇の知恵を惜しみなく披露。硬くなった身体をやわらかくすれば、心もやわらかくなって、魅力的な「自分」を手にできる。第一線で活躍し続ける演出家が今の世の中に贈る大切な1冊。
「演劇」と聞いたとき、何をイメージするでしょう? 小学生のとき学芸会で取り組んだ記憶。興味をもって出かけた劇場で、いつもはテレビで見ているタレントが動きまわっているところ。あるいは、バイトをしながら劇団でがんばっている友達がいる、というかたもいるかもしれません。
でも、そのようなものは「演劇」のごく一部にすぎません。本書は、30年以上にわたってプロの劇団を率いてきた第一級の演出家が、長年あたためてきたアイデアを皆さんにお伝えするため、演劇から得た知恵を惜しみなく披露した1冊です。
ここには、一人でできる《発声》や《海の歩行》から、数人で行う《漫才》や《ものまね》、そして本格的なストーリーを展開する《ショート・ストーリーズ》まで、具体的なレッスンが数多く紹介され、実際にやってみるための手引きもつけられています。
これらの中から気軽にできるものを選んで実際にやってみれば、多くの人は自分の身体がいかに硬くなっているかに気づき、それは自分の心が硬くなっていることにつながっていることを理解するでしょう。硬くなった心と身体をやわらかくするための知恵──それが「演劇」であり、著者が〈演劇的教養〉と呼ぶものです。
この〈演劇的教養〉が教育の中に組み込まれていない日本はめずらしい国だ、と著者は言います。だからこそ、今こそ、この知恵を実際に取り入れてみましょう。
そこに生まれるのは、誰にとっても魅力的な「自分」に違いありません。
[主な内容]
〈演劇的教養〉とは何か
第一章 この世にない魂と出会う
第二章 台本から演劇を作る
第三章 発声練習と役作り
第四章 身体の不思議
基礎編
第一章 《マッサージ》と《柔軟運動》
第二章 《発 声》
第三章 《海の歩行》
第四章 身体の発掘
第五章 《歩行》と《寝返り》
第六章 さて、「演劇」とは何だろうか?
実践編
第一章 《ストリップ》
第二章 《漫 才》
第三章 《ものまね》
第四章 《ショート・ストーリーズ》
「演劇教育」の可能性
第一章 小中学生対象のワークショップ
第二章 「演劇教育」と自己アピール