講談社選書メチエ作品一覧

復元・安土城
講談社選書メチエ
わずか3年にして、灰塵に帰した幻の城。ヨーロッパにまで知られたその華麗なる姿。黄金の瓦・黒漆の壁・朱の八角円堂……。和様、唐様、南蛮風を總合した造形美は、近世の到来にふさわしい。戦国の世を「平安楽土」とすべく、「安土御構」に信長の託した夢とは?30年にわたる研究が、いま1冊となった――。

島の植物誌 進化と生態の謎
講談社選書メチエ
みずから移動できない植物は、海の彼方の島にどうやって渡るのだろうか?そこでどう生き、進化していくのだろうか?大洋の真中に突然誕生する火山島は、まさにこの疑問に答えてくれる実験室である。ガラパゴス諸島でダーウィンが観察し、指摘した植生の不思議。植物生態学は「島の植物」の精妙な生き方を解き明かす。
【目次】
序章 いまなぜ島の植物か
第一章 植物は海洋島へどうやって渡るのか
第二章 海洋島の上での進化のドラマ
第三章 植物の数は何によって決まるか
第四章 海洋島の植物生態系
第五章 島の植物の保全
参考文献
あとがき
索引

聊斎志異
講談社選書メチエ
狐、神仙、鬼、妖怪……。その裏側にかくされている「志異」の素顔。幻と現実のあわいに浮かぶロマンの世界。世を手玉にとる希有な手品、あるいは人を食った巧妙な魔術のようなその創造性。卓越したモラリストにして表現者・蒲松齢が描く、悲しくも美しい人間模様。冴えわたる筆が、われわれの精神を解放し、躍動させる。

神を殺した男 ダーウィン革命と世紀末
講談社選書メチエ
1859年11月24日、「神の死」を決定づける書が世に出た。初版1250部の『種の起源』は、即日完売となる。「進歩の夢」と「ニヒリズム」が、交錯する世紀末。マルクス主義・自然主義・帝国主義・社会ダーウィニズム……。あらゆる知の分野は、「進化論」のうえに再構築され、20世紀へと突入する。世紀末を飾ったテクストをとおし、ダーウィニズムの思想的磁場を考察した意欲作。
【目次】
第一章 神の殺害――個別創造説・思弁的進化論・ダーウィニズム
第二章 人類の黄昏――ユートピアニズム・マルクス主義・ダーウィニズム
第三章 コリンズ殺人事件――自然主義・決定論・ダーウィニズム
第四章 大英帝国の栄光と暗黒大陸――帝国主義・人種差別主義・ダーウィニズム
エピローグ
注
ブックガイド
「神を殺した男」年表
あとがき
索引

俳句のユ-モア
講談社選書メチエ
五七五の魅力はどこにあるのか一息に口ずさめる楽しさ。自由な読みを許す片言性。場のこわばりをほぐす機知の力。句会という共同の創造。「三月の甘納豆のうふふふふ」で知られる著者が、ユーモアを切り口に俳句の奥深さを解きあかす。

フランス現代思想
講談社選書メチエ
知の震源地、パリ。「実存」から「構造」へ、「構造」から「脱構築」へ……。1968年以後、めまぐるしく変貌する現代思想の原点はどこにあるのか?ラカン、アルチュセール、フーコー、デリダ……。彼らの哲学はどこから生まれてきたのか?ポスト・モダンのゆくえを見通す1冊。

ウマ駆ける古代アジア
講談社選書メチエ
6000年前、北アジアで人は野生のウマに出会った。草原の民の最高の伴侶となったウマは、騎馬・調教の方法と、馬車の技術とともにユーラシア全域に広まっていく。シュメルの戦車として、スキュタイの騎馬遊牧として、漢の軍馬として……。最新の考古学の発掘成果を駆使し、ウマと人の最古のつながりを探る渾身の書。
【目次】
序章 天馬以前の道を求めて
第一章 ユーラシア草原のウマとヒト――ウマ利用を開始したウクライナ草原
第二章 車輪と車両の発明――橇から馬車へ
第三章 馬車そして古代戦車の発生――草原とメソポタミアのあいだ
第四章 古代戦車中国へ――殷墟に埋れた馬と車
第五章 騎馬と遊牧と騎兵
第六章 馬と人の社会
終章 天馬
参考文献
あとがき
索引

日本という身体
講談社選書メチエ
文学者・思想家の「身体的なもの」をたどりつつ、「大」「新」「高」を手がかりに、大逆事件、経済新体制、高度成長など近代日本の生態のありように立ち向かった意欲作。筆者世代の72年体験をふまえた思想の可能性がここにある。

「鎖国」の比較文明論 東アジアからの視点
講談社選書メチエ
秀吉・家康の対明・対朝鮮外交を軸にした、キリスト教諸国への対抗策――ここから徳川幕府の鎖国への傾斜が始まる。『明史』『懲ひ録』『徳川実紀』などの文献を読みこみ、家光が鎖国令を出すに至るまでの為政者たちの心理を大胆にあぶり出す。17世紀初頭の複雑な東アジア情勢のなかで、鎖国の実相を鮮やかな切り口で描く力作。
【目次】
序章
第一章 徳川家康の全方位外交
第二章 文禄・慶長の役の国際環境
第三章 家康の対中国外交――鎖国への伏線
第四章 鎖国と林羅山の思想
第五章 徳川時代における開国の精神
終章 鎖国の比較文明論
註・参考文献
あとがき
索引

可能性としての「戦後」
講談社選書メチエ
焼けあとは、多くの思想の「現場」を生んだ。杉浦明平、花森安治、松田道雄……。彼らが立ちあがり、歩きはじめた場所はそのまま私たちの出発点であった。軍隊の消滅。国家没落のあとの明るさ。何もないがゆえの平等と自由。いま、あらためて「戦後」の意味を問いなおす。

フロイト
講談社選書メチエ
「無意識」「夢」「エロスとタナトス」「自我・超自我・エス」……。精神の深奥に分け入り、「こころ」の見方に革命を起こしたフロイト。いまなお、われわれは彼の「呪縛」から逃れることはできない。強迫的なパーソナリティーのもたらした膨大な著作。優れた洞察と過度の普遍化。死後半世紀のいま、この天才の思想と生涯を明らかにする。

プラントハンター
講談社選書メチエ
19世紀イギリス。誰も知らない珍しい花や樹々を求め、国中が沸きたっていた。この要求に応えて世界をかけめぐるプラントハンターたち。ラン、チャ、ユリ……。エキゾチックなあこがれを満たすべく、彼らはジヤワ、中国、そしてニッポンをめざす。豊富な文献渉猟から植物をめぐる文化交流をあざやかに位置づけた力作。(講談社選書メチエ)
19世紀イギリス。誰も知らない珍しい花や樹々を求め、国中が沸きたっていた。この要求に応えて世界をかけめぐるプラントハンターたち。ラン、チャ、ユリ……。エキゾチックなあこがれを満たすべく、彼らはジヤワ、中国、そしてニッポンをめざす。豊富な文献渉猟から植物をめぐる文化交流をあざやかに位置づけた力作。

風景の生産・風景の解放 メディアのアルケオロジー
講談社選書メチエ
柳田国男や今和次郎の仕事を継承しつつ、絵はがき、挿絵、鉄道旅行、街頭など風景の背後にある新しい事物やメディアの出現を通し、慣習や規範をとらえかえす。考現学を駆使して近代日本の視線を考察する「感覚」の社会史。
【目次】
序
第一章 絵はがき覚書――メディアのアルケオロジー
第二章 遊歩者の科学――考現学の実験
第三章 挿絵の光景から――交番の前のねずみたち
第四章 風景の生産――柳田国男の風景論
第五章 言語・交通・複製技術――近代風景意識の存立構造
注
資料
あとがき
索引

賭博・暴力・社交
講談社選書メチエ
「粗暴」で「不潔」な遊びにふける子供たち……。サイコロの一振りに、命を賭ける「悪魔の情欲」……。決闘を楽しみ、歌に、恋にあけくれる優雅な騎士と貴婦人たち。破天荒な遊びの数々がおりなす夢と現実。聖と俗、真面目と遊びを自由に横断するあたらしい中世像。

関ヶ原合戦
講談社選書メチエ
関ヶ原での東軍の勝利は「徳川の力」によるものではない。秀忠の軍勢3万の遅参、外様大名の奮戦。不測の事態が家康の計算を狂わせた。苦い勝利。戦後処理の複雑な陰翳。300年の政治構造がここに決定される。近世の幕藩体制の礎を築いた「天下草創」の戦いを描ききる。

大英帝国のパトロンたち
講談社選書メチエ
文化・芸術の後援者・保護者――パトロン。シェークスピア、ピール、ドライデン。
歴史に残る芸術家も、金と職を求めて屈辱的な日々を送った。きまぐれな大貴族、聖職者。貧困にあえぐ作家、詩人。
自由と孤立をめざして、彼らの選んだ道とは?
【目次】
プロローグ
第一章 パトロンとは
第二章 女王陛下の御手
第三章 宮廷人の文芸熱
第四章 パトロンに恵まれた男――マシュー・プライアー
第五章 独立を望む作家たち
第六章 「貧しき作家の安価な作品」
第七章 翻訳でもうけた男――アレグザンダー・ポープ
第八章 ジョンソンの独立宣言
エピローグ
参考文献
あとがき
索引
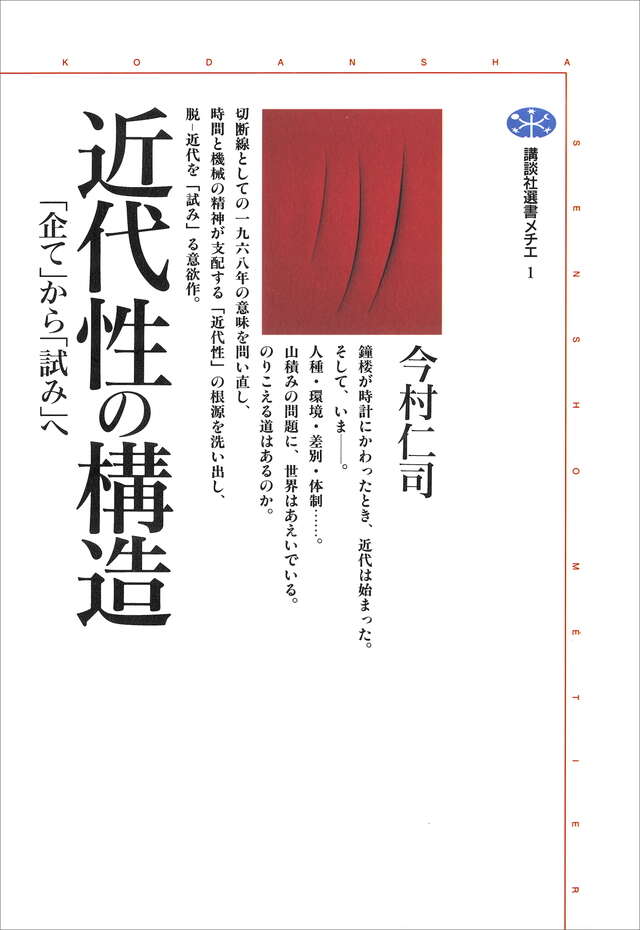
近代性の構造
講談社選書メチエ
鐘楼が時計にかわったとき、近代は始まった。そして、いま――。人種・環境・差別・体制……。山積みの問題に、世界はあえいでいる。のりこえる道はあるのか。切断線としての1968年の意味を問い直し、時間と機械の精神が支配する「近代性」の根源を洗い出し、脱-近代を「試み」る意欲作。(講談社選書メチエ)
鐘楼が時計にかわったとき、近代は始まった。そして、いま――。人種・環境・差別・体制……。山積みの問題に、世界はあえいでいる。のりこえる道はあるのか。切断線としての1968年の意味を問い直し、時間と機械の精神が支配する「近代性」の根源を洗い出し、脱-近代を「試み」る意欲作。