新刊書籍
レーベルで絞り込む :
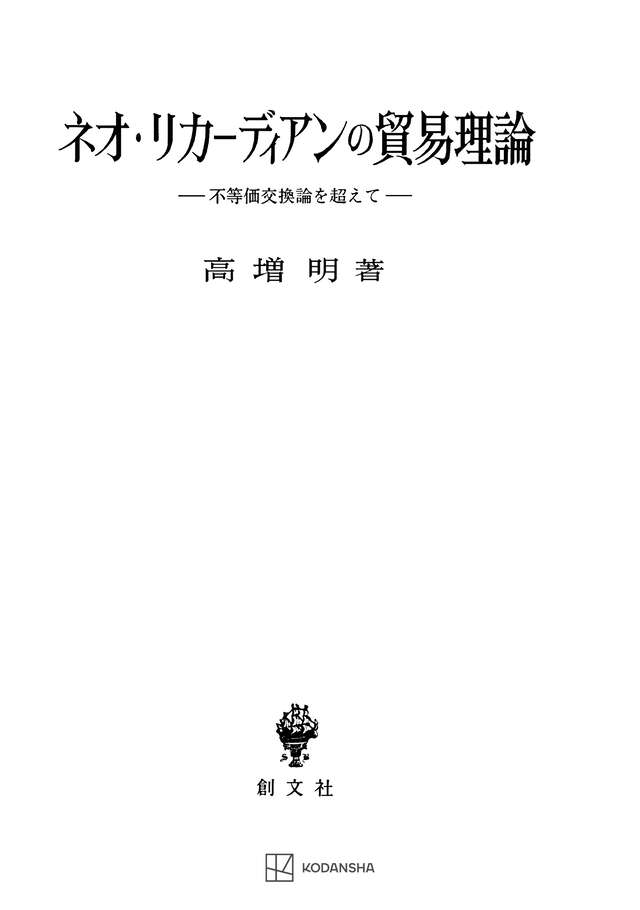
2022.02.25発売
ネオ・リカーディアンの貿易理論 不等価交換論を超えて
創文社オンデマンド叢書
不等価交換論を超えて 古典派から、新古典派、マルクス経済学、現代的アプローチまで主要な貿易論を検討、新しい理論の構築を試みる。
【目次より】
はじめに
序章 なぜネオ・リカーディアンか
1 ネオ・リカーディアンとは何か
2 新古典派 vs ネオ・リカーディアン
3 マルクス経済学 vs ネオ・リカーディアン
第1章 リカード比較生産費説について
1 序
2 リカードの比較生産費説
2-1 リカードの説明 2-2 リカードモデルの定式化
3 ミルの国際価値法則
3-1 ミルモデルの定式化 3-2 ミルをどう評価するか
4 多数の国,多数の商品
4-1 2国n商品 4-2 n国2商品 4-3 n国n商品
5 中間生産物
5-1 2国n商品 5-2 競争均衡と生産の有効性
6 時間のある経済(Sraffa-Leontief経済)
6-1 Steedman-Metcalfeによるリカード比較生産費説の批判 6-2 商品による商品の生産 6-3 より一般的な分析
7 自由貿易の通時的効率性
7-1 数値例による直観的理解 7-2 Smithによる一般的な証明
8 結論
数学注
補論1 貿易によって利潤率は上昇するか
補論2 Sraffa-Leontief 経済における生産可能性フロンティア
第2章 生産された生産手段としての資本とヘクシャー=オリーン=サミュエルソン(HOS)モデル
1 序
2 ヘクシャ ー= オリーン=サミュエルソン(HOS)モデル
2-1 閉鎖経済 2-2 開放経済
3 生産された生産手段としての資本
4 土地としての "K"
4-1 商品の価格 4-2 価格と生産量の関係 4-3 開放経済の一般均衡
5 結び
補論3 "normal" でないケースをどのようにして排除するのか
第3章 国際貿易における不等価交換:理論的展望
1 序
2 不等価交換とは何か
3 Emmanuel の不等価交換論
3-1 不等価交換の1次形態:等しい剰余価値, 異なった資本の有機的構成をもった国家間の不等価交換 3-2 厳密な意味での不等価交換:不均等な剰余価値率によって生じる不等価交換
4 Samuelson の Emmanuel 批判
5 Saigal による Emmanuel 理論の「発展」
6 Evans による Saigal モデルの修正
7 根岸隆による Saigal 批判
8 Roemer の不等価交換論
9 結び
参照文献

2022.02.25発売
市場の経済思想(現代経済学選書)
創文社オンデマンド叢書
市場活動をルールの下での競争というゲームとして統一的に考察。古代以来の反市場思想を歴史的・批判的に分析した問題作。各務賞受賞。
【目次より】
まえがき
1 経済と市場
1 稀少性の出現 2 余分なものとしての経済 3 稀少性への挑戦 4 稀少性に対処するための社会システム 5 競争 6 市場 7 市場をめぐる経済思想
2 交換・貨幣・市場ゲーム
1 交換 2 交易と市場の起源 3 交換ゲーム 4 交換に先立つもの 5 交換の正義 6 貨幣 機能主義的アプローチ 7 貨幣 経済人類学的アプローチ 8 貨幣 情報システム論的アプローチ 9 貨幣と市場ゲーム
3 反市場思想および経済的自由主義のプロトタイプ
1 アリストテレスの正義論 2 利得は不正であるという説 3 マネー・ゲームは不自然であるという説 4 利子の否定 5 司馬遷の経済的自由主義 6 国家独占をめぐる問題
4 市場ゲームと正義
1 トマス・アクイナスの正義論 2 「交換の正義」再論 3 「公正価格」 4 中世の商業 5 商業利潤の根拠 6 利子をめぐる議論 7 「分配の正義」 8 ゲームの 「公正」 と初期条件の問題
5 「搾取」と「剰余」
1 市場ゲーム と利得 2 マルクス的「搾取」の概念 3 「剰余」の概念 4 「剰余」としての人間 5 交換システムにおける「剰余」 6 マネー・ゲームと「利潤」
6 「見えざる手」 の世界と 「ユートピア」
1 『蜂の寓話』 のパラドックス 2 自生的な社会的秩序 3 「見えざる手」 4 自然的秩序形成のメカニズムと「共感」 5 「見えざる手」の失敗 6 「市場の失敗」 7 反市場社会としての「ユートピア」
7 市場と国家
1 国家とその経済的役割 2 プラトンの「国家」 3 市場ゲームの抑制者としての国家 4「富国強兵ゲーム」 のプレーヤーとしての国家 5 経済的自由主義と国家 6 再分配ゲームの仲介者としての国家 7 国家による市場の制御
8 資本主義というゲーム
1 「マネー・ゲーム」としての「資本主義」 2 「資本主義」は不公正なゲームか 3 「搾取」についての再論 4 「反資本主義」のモデル 5 「社会主義」という名の「国家独占資本主義」 6 資本主義の否定がもたらす「国家の失敗」 7 非資本主義的市場経済としての「市場社会主義」の可能性 8 資本主義の「精神」
9 経済思想のドラマ
1 古代・中世の反市場の思想 2 「重商主義革命」と「アダム・スミス革命」 3 正統・異端・無神論 4 「ケインズ革命」以後 5 主要なパラダイムの比較 6 市場の擁護と資本主義の擁護
参考文献

2022.02.25発売
アウグスティヌスの言語論
創文社オンデマンド叢書
言語哲学と解釈学の視点からアウグスティヌスにおける言葉の真相を文献学的に解明、彼の言語論の全貌を初めて本格的に示した問題作。
【目次より】
はじめに
序論 声の現象学へ
第一部 言語哲学的視点から 声とことば
アプローチ
第一章 声
I 意味の光
II 声
III 喚びかけの構造
IV 喚びかけの場所
第二章 ことば
I 沈黙と発語
II 根源語 讃美と呻き
III 光ることば
第二部 解釈学的視点から 経験と解釈
アプローチ
第一章 経験
I ホルテンシウス体験
II メロディア・インテリオル 『美と適合について』
III ミラノのヴィジョン 『告白』第七章における神秘経験
IV オスティアの経験 l’extase a deux
第二章 解釈
I 比喩的解釈
II 解釈の迂路
III ドケレの二重構造
第三部 『キリスト教の教え』の言語哲学 『キリスト教の教え』を読む
アプローチ
I いつだれのために書かれたか
II 伝達の回路
III 本論のアナリシス 表現と伝達
IV 結論
あとがき

2022.02.25発売
現代の租税理論 最適課税理論の展開
創文社オンデマンド叢書
最適課税理論の展開 望ましい租税制度の要請が強い今日、所得税と消費税に亙る最適課税理論を、最新の研究を踏まえて体系的に考察。
【目次より】
はしがき
序
第I部 最適課税理論:展望
第1章 展望 I:最適消費税理論 線形最適課税
1 最適消費税理論の展開
2 最適消費税問題の構造
3 最適消費税体系の構造
4 租税改革の理論
第2章 展望 II:最適所得税理論 非線形最適課税
1 最適所得税理論の展開
2 最適所得税問題の構造
3 非線形最適所得税
4 最適線形所得税
第II部 基礎理論の検討
第3章 最適消費税体系の存在問題
1 はじめに
2 モデル
3 再分配的な最適消費税体系
4 一般の場合の最適消費税体系
5 利潤が存在する場合の最適消費税体系の特徴
6 反例:最適消費税体系が存在しない場合
第4章 最適消費税ルールの一般化 生産者価格の可変性,利潤と最適課税ルール
1 はじめに
2 可変的生産者価格と最適消費税ルール
3 利潤の存在と最適課税ルール
付論1 不変生産者価格が意味する生産関数
付論2 最適消費税理論と租税改革理論
付論3 政府の徴税方式と課税ルール
補論 最適課税と効率的生産
1 はじめに
2 最適消費課税と非効率生産:反例
3 モデルと準備的議論
4 最適消費税経済における効率的または非効率的生産
5 要約
参照文献
第III部 最適課税のシミュレーション分析
第5章 わが国の最適線形所得税制
1 はじめに
2 分析の枠組み
3 計算の方法
4 わが国の最適線形所得税:結果と解釈
5 結語
第6章 わが国の最適消費税制
1 はじめに
2 分析の枠組みとモデル設定
3 計算の方法
4 わが国の最適消費税体系:結果とその検討
5 要約と展望
第IV部 最適課税理論の展開
第7章 貯蓄と最適課税
1 はじめに
2 モデル
3 貯蓄と最適課税:結果と検討
4 貯蓄課税の是非
第8章 脱税と最適課税
1 脱税と最適課税
2 経済の枠組み
3 脱税がない場合の最適課税体系
4 脱税と最適課税制度
5 最適な税務調査および罰則制度
6 結語:他の税の場合
第9章 最適課税理論の課題:新展開にむけて
1 税の包括化と総合的最適課税体系の考察
2 理論の枠組みの拡大
3 応用的数量分析の展開

2022.02.25発売
市場機構と経済厚生(現代経済学選書)
創文社オンデマンド叢書
厚生経済学の伝統を踏まえ、ゲーム論など最新の業績を取り入れて、均整のとれた市場機構の全体像を描いた中級テキストの決定版。
【目次より】
序
注意
1 序論 課題と方法
1 厚生経済学の分析上の立場 2 経済的厚生についての予備的考察 3 厚生経済学の形成
2 経済環境
1 財と価格 2 消費者 3 生産者 4 経済環境と政府
3 経済主体の最大化行動
1 市場の形態 2 効用最大化と需要関数 3 利潤最大化と供給関数 4 非協カゲームのナッシュ均衡
4 資源配分の効率性の条件
1 資源配分の効率性の基準 2 部分均衡型モデルと効率的資源配分の条件 3 生産物モデルと効率性の条件 4 端点解を許す場合の効率性の条件
5 価格機構と資源配分
1 競争市場と資源配分 2 競争市場の効率性 3 厚生経済学の第二基本定理 4 基本定理の経済的意義 5 市場の失敗
6 補償原理と分配問題
1 個人間効用比較 2 補償原理と厚生基準 3 個人間効用比較と公平性の原理 4 コルム=フォーリーの公平性
7 外部効果と市場機構
1 外部経済効果の概念 2 外部効果を含む経済モデル 3 外部効果の補正
8 公共財の最適供給
1 公共財の概念 2 公共財と効率性の条件 3 公共財と市場の失敗 4 公共財の自発的供給メカニズム
9 非凸性と価格形成
1 非凸性と競争機構 2 外部効果と非凸性 3 企業の参入と競合可能市場 4 公共料金 5 協カゲームによる料金決定
10 不確実性と経済厚生
1 不確実性の下での経済行動 2 アロー=ドブリューの条件付財の市場 3 保険市場 4 道徳的陥 5 逆淘汰 6 オークション
11 社会的選択の理論
1 社会的選択の方法 2 社会厚生関数 3 一般不可能性定理 4 単純ゲームと社会的選択 5 社会選択関数
12 国民所得と所得分配
1 実質国民所得の評価 2 所得分配の平等の華準 3 分配の不平等の尺度 4 所得分配の平等と現実
13 寡占市場と戦略的行動
1 単一生産物モデル 2 寡占市場と企業の参入 3 企業の合併 4 参入阻止行動 5 異質財生産と寡占市場 6 消費者行動の誘因両立性
14 次善理論と経済政策
1 ラムゼイの最適課税問題 2 リプシー=ランカスターの問題 3 価格の歪みの比例的変化の効果 4 次善最適点における経済厚生の変化の評価について 5 一般的モデルによる分析
参考文献

2022.02.25発売
日本財政の経済分析
創文社オンデマンド叢書
財政赤字、企業、住宅、年金、業種間負担、直間比率、地方税、税制改革など主要なトピックスに経済理論を適用、その説明力を実証。
【目次より】
まえがき
第1章 財政赤字と家計行動 中立命題の検証
I はじめに II 中立命題の理論的枠組とその限界 III 既存の実証分析 IV 中立命題の検証
第2章 企業税制と設備投資 投資のq理論からのアプローチ
A) 設備投資理論の展開
I はじめに II 設備投資理論の諸類型 III 設備投資と税制 IV アメリカの設備投資に関する実証研究 V 日本の設備投資の実証研究
補論
記号一覧
B) 設備投資の実証分析
I はじめに II モデル III データ IV 推定結果 V むすび
補論 理論モデルの説明
第3章 公的住宅政策と持家取得行動 資本コストの計測とシミュレーション
I はじめに II モデル III 時系列データによる分析 IV クロスセクションデータによる分析 V むすび
第4章 わが国財政運営のマクロ的評価 高雇用余剰と高雇用経常収支の計測
I はじめに II 自然失業率の理論と実証 III 自然失業率の計測とその吟味 IV GNPギャップの計測 V 高雇用余剰の計測 VI 高雇用経常収支,高雇用交易条件と高雇用為替レートの計測 VII むすび
第5章 業種間負担率格差の実態 「クロヨン」問題の推計
I はじめに II 所得税負担率格差の指標 III 所得階層分布と租税関数の推定 IV 税負担の業種間格差の実態 V 業種間格差の相対的意義
第6章 最適直間比率のシミュレーション分析 効率と公平のトレードオフ
I はじめに II 分析の方法 III 直間比率と経済的厚生
第7章 わが国税制改革の影聾分析
I はじめに II 竹下税制改革の概要 III 消費税と物価上昇 IV 世帯類型別の税負担の変化 V ライフサイクルの税負担の変化 VI 竹下税制改革の原生分析
補論
第8章 地方交付税:機能とその評価
I はじめに II 国と地方の財政関係と財政状況 III 地方交付税制度の概要と問題点 IV 地方交付税の財源保障機能 算定構造の分析 V 地方交付税の財政調整機能 VI 地方交付税の機能の評価と諜類
第9章 年金制度と高齢化社会 重複世代間モデルによるシミュレーション分析
I はじめに II 年金制度の現状とその問題点 III 戦後の経済成長と公的年金 IV 年金改革のシミュレーション分析(1):定常状態の比較 V 年金改革のシミュレーション分析(2):移行過程の比較 VI むすび

2022.02.25発売
六朝道教史研究(東洋学叢書)
創文社オンデマンド叢書
道教史上もっとも主要な時期である六朝期江南の天師道と葛氏道という代表的道流の歴史的変遷を独自の方法により解明した画期的業績。
【目次より】
まえがき
凡例
緒言
第一篇 葛氏道と霊寶経
序章 葛氏道と上清派
第一章 『太上霊寶五符序』の形成
第二章 『霊寶赤書五篇眞文』の思想と成立
第三章 霊寶経の形成
附 霊寶経の分類表
第二篇 天師道とその道典
序章 東晉・劉宋期の天師道
第一章 『九天生神章経』
第二章 『河上眞人章句』
附 『老子道徳経序訣』
第三章 『老子想爾注』
第四章 「大道家令戒」
第五章 『上消黄書過度儀』
補論一 『太上洞淵神呪経』と『女青鬼律』と『太上正一呪鬼経』の成書年代について
補論二 『玄妙内篇』の成立について
補論三 『千二百官儀』の思想と成立
第三篇 道教教理の形成
第一章 道教の終末論
第一節 東晉期の道教の終末論
第二節 上清経と霊寶経の終末論
第三節 劉宋・南齊期の天師道の終末論
第二章 劉宋期の天師道の「三天」の思想とその形成
補論 三教交渉における「教」の観念
参考文献目録
あとがき
索引
英文梗概

2022.02.25発売
近世初期の外交
創文社オンデマンド叢書
17世紀前半に確立した近世外交の特質をオランダ文書と日本語史料を駆使して本格的に分析し鎖国論の克服を試みた問題作。和辻賞受賞。
【目次より】
序
目次
第一部 近世初期の外交担当者
一 家康・秀忠の二元政治時代
1 本多正信と正純
2 将軍の買物掛と後藤庄三郎
3 以心崇伝と林羅山
4 小括
二 秀忠単独支配から秀忠・家光の二元政治
1 土井大炊頭利勝
2 酒井雅楽頭忠世
3 酒井讃岐守忠勝
4 伊丹播磨守康勝と松平右衛門正綱
5 秀忠の上意
6 小括
三 家光政権
1 綱紀粛清
2 異国之事
3 閣老の横ならびの時代
4 酒井讃岐守忠勝
5 榊原飛騨守職直
6 松平伊豆守信綱
7 井上筑後守政重
8 ポルトガル人追放の決定
9 小括
第二部 近世の外交儀礼の確立
一 拝謁
1 ポルトガル人
2 オランダ人
二 国書の形式
三 小括
第三部 オランダの台湾貿易
一 海賊とアドヴェンチュラー
1 李旦
2 許心素
3 一官(鄭芝龍)
二 日本貿易の基地としての台湾
1 通航許可証を得た中国人のタイオワン来航
2 在日華商の台湾貿易の排除
3 台湾貿易の拡大とタイオワン商館の資金不足
4 日本向け絹織物の買付
5 ハンブアンと一官
6 小括
むすびにかえて
あとがき
表
地図
註
貨幣換算表
参考文献

2022.02.25発売
権利と人格(現代自由学芸叢書) 超個人主義の規範理論
創文社オンデマンド叢書
脳の内容が複製可能であるならば人格の同一性は一体どのようにして証明が可能であるのか。個人の別個性と人格の不確定性――二つのモチーフを焦点とする、統一理論がいま求められている。恐れを知らず実定法学の領域へと越境して、権利に基礎をおく道徳および民事・刑事の法的責任の根拠に迫り、道徳を原始的個人の内面にかかわるものではなく他者との関係において現れる外面的世俗的な社会道徳をして再構成し、個人を超えるインパーソナルな開かれた規範理論を大胆に構築する、現代自由学芸の騎士による挑戦の書である。無批判な権利万能論と一線を画し、基本権間の衝突・統一的人格の虚構性・普遍的利己主義の不可避性等、従来の人権論が無視してきた権利論の根本問題に挑み、明快かつ論争的なスタイルで超個人主義の規範理論を提唱する。
【目次より】
序
第一部 道徳・権利・人格
第一章 狭義の道徳
第一節 道徳の広義と狭義 第二節 正義の「対他性」 第三節 「自然法の最小限の内容」 第四節 法とのオーバーラップと相違 第五節 狭義の道徳に含まれないもの
第二章 権利を基底におく道徳
第一節 目標基底的道徳(特に功利主義)および義務基底的道徳との相違 第二節 権利の衝突 第三節 権利の個人間比較 第四節 中間総括
第三章 権利とは何か、また何のためにあるのか
第一節 基本的な法的諸概念 第二節 選択説による権利の概念 第三節 権利の意義
第四章 権利の道徳では足りないもの
第一節 方法論上の問題 第二節 利己主義と行為者相対的考慮 第三節 公共的価値 第四節 未来の人々と動物
第五章 柔らかい人格と道徳的問題
第一節 序説 第二節 人格の同一性は程度の問題である 第三節 程度説批判の検討 第四節 自己利益 第五節 パターナリズム 第六節 功績と責任 第七節 約束 第八節 配分的正義 第九節 程度説と狭義の道徳
第二部 法的責任の基礎
第一章 序論
第二章 契約はなぜ、またどのように拘束するか
第一節 序説 第二節 信頼説 第三節 契約の法的保護の方法 第四節 手続的要件としての意志(思) 第五節 契約制度の意義 第六節 無償契約の拘束力の弱さ 第七節 自己拘束の可能性 第八節 契約における正義
第三章 刑事責任論における「自由意志」問題
第一節 問題の整理 第二節 決定論と非決定論 第三節 両立不可能論批判 第四節 責任の前提としての「自由意志」 第五節 「自由意志」ということば 第六節 結語
注
文献解題

2022.02.25発売
西ドイツの土地法と日本の土地法
創文社オンデマンド叢書
確固たる体系を持つ西ドイツ土地法を手がかりに、わが国現行土地法(公法)の持つ特徴と問題点を剔抉し、その克服の道を明示する。
【目次より】
はしがき
第一部 建築の自由と土地利用規制 西ドイツ法の場合
I 建築の自由と土地利用規制
I 西ドイツの国土整備計画法制 都市的土地利用と農村的土地利用との調整を中心として
III プロイセンの住宅地新開発規制立法AAnsiedlungsgesetzgebung)について 西ドイツ都市建設法制におけるAussenbereichの概念とその沿革
IV 財産権の保障とその限界 ボン基本法下三〇年の西ドイツ公法学におけるその一断面
第二部 土地と財産権保障 日本法の場合
I 日本国憲法と財産権保障 土地所有権を中心として
II 公共用地の強制的取得と現代公法 関連諸利益の取扱い方を中心として
III 残地補償と起業利益ならびに事業損失との関係について
IV 公共用地の任意買収と土地収用との相互関係について
V 土地区画整理制度と財産権保障 いわゆる「無償減歩」をめぐって
VI 土地所有権の制限と損失補償
II 我国地区計画制度の性格 西ドイツ地区詳細計画(Bプラン)制度との対比におけるその特色と問題点
VIII 不動産取引の公法的規制 土地売買の認可制度を中心として

2022.02.25発売
テオフラストスの形而上学
創文社オンデマンド叢書
テオフラストスの未検討テキスト『形而上学』を、序論・本文訳・詳細な註解を施して、初期アカデメイアの哲学的議論を解明する。
【目次より】
まえがき
目次
序論
1 テオフラストスの生涯
2 『形而上学』の構成
3 アポリアとしての哲学
4 著作時期について
5 テクストの歴史(伝承・写本・刊本)
本文訳
註解
文献

2022.02.25発売
四書学史の研究(東洋学叢書)
創文社オンデマンド叢書
南宋から清に至る思想史を四書学の継承とその批判克服を意図する新四書学の形成過程と捉え、新資料をも駆使して新生面を開いた力作。
【目次より】
序章
一 四書学史の概況
二 明代人と経書
一 朱子学的学習法の確立
二 明人の読書記誦
三 読書記誦による人格の陶冶
四 晩明における記誦
第一章 四書学の成立 朱子における経書学の構造
一 表裏精粗至らざるは無し
二 朱子学の論理
三 経書註繹の方法
四 四書学の構想
第二章 宋元代の四書学をめぐる政治的思想的状況
一 党禁から従祀に至る朱子学の黜陟
二 宋元思想界における四書学の位置
第三章 朱子以降における『大学』観の変遷
一 朱子の『大学』観
二 朱子以後の『大学』改訂
三 王陽明の『大学』観
四 明代末期の『大学』論議における二三の問題
五 清代の『大学』評価
第四章 四書註釈書の歴史
一 章句集注のテキストについて
二 註釈書の続成 集成書について
第五章 『四書評』の歴史
一 『四書評』について
二 『青雲堂四書評』について
三 『四書評』の余韻
第六章 晩明の四書学
一 周汝登の四書学
二 晩明の四書学
三 四書学の展開と方向性
第七章 科畢と四書学
一 講章の四書学 沿溟四書説をめぐって
二 八股文の四書学
附録 『四書正新録』姓氏・書目 『四書増補微言』新増姓氏・書目 『刪補微言』・『皇明百方家問答』引用書目

2022.02.25発売
ロシア近世農村社会史
創文社オンデマンド叢書
ロシア近代化の起点であるピョートル1世の諸改革と、農村がおかれた諸々の状況と変化の過程を基礎史料から描く、我国初の画期的研究。
【目次より】
まえがき
目次
序論 ピョートル改革の基本的性格
一 北方戦争の時代
二 軍事、行政改革
三 財政改革と工業化
四 教会改革と啓蒙
五 改革と民衆
第一章 戦時下の農村社会
第一節 世帯調査(一六七八─一七一〇)
第二節 兵士、労働者の徴用 「空白」の諸原因(その一)
第三節 逃亡と世帯隠し 「空白」の諸原因(その二)
第四節 ランドラート調査
第二章 農村社会の諸相
第一節 領主経営と農民経営
第二節 領主的諸規制
第三節 農民の日常的諸要求
第四節 『貧富の書』における農村社会像
補論 村の教会と聖職者について
第三章 人頭税の導入と農村社会
第一節 世帯税から人頭税へ
第二節 人口調査 人頭税の導入過程(その一)
第三節 軍隊と農村 人頭税の導入過程(その二)
第四節 農村の疲弊と政府の対応
終章 近世農村の成立
引用欧文文献目録

2022.02.25発売
不均衡理論と経済政策
創文社オンデマンド叢書
「不均衡下に於る望ましい経済政策とは何か」を追求して不均衡理論の有効性を示し、更に現実の経済に対する説明力を明らかにした力作。
【目次より】
序章
付論 最近の非ワルラス動学理論の展開と非ワルラス均衡理論
参考文献
第1章 不均衡理論の学説史的系譜
1 固定価格アプローチ 不均衡理論の第1世代
2 内生的価格決定分析 不均衡理論の第2世代
3 解明された問題と残された問題
第2章 不均衡経済における価格調整と数量調整
数学付録
第3章 不均衡経済における租税,財政支出および貨幣供給
1 不均衡経済における租税
2 不均衡経済における租税と財政支出
3 不均衡経済における貨幣供給
第4章 ケインズ的不均衡経済における期待,インフレーション及びスタグフレ-ション
数学付録
付論 賃金変動とスタグフレーション
第5章 不均衡経済における“bootstrap property"
第6章 非ワルラス経済における情報と合理的推測均衡
第7章 非ワルラス経済の動学分析について
1 研究史と残された問題
2 「せり人モデル」による非ワルラス経済の動学分析
第8章 マクロラショナリストの理論と不均衡経済
結章

2022.02.25発売
エンペドクレス研究
創文社オンデマンド叢書
ダイモーン・四根対応説という独自の見地からエンペドクレス思想を統一的に把握、初期ギリシア哲学研究の空隙を埋める。学士院賞受賞。
【目次より】
序言
引用方法・省略符号
第一章 『ペリ・ピュセオス』の宇宙円環(予備考察)
第二章 『ペリ・ピュセオス』と『カタルモイ』の関聯1(研究者諸氏の見解)
第三章 三つのイメージの対応
第四章 三人称人称代名詞の正体
付録 四根の分子
第五章 ダイモーンの正体
第六章 霊魂の特性と四根
付録一 アリストテレス『霊魂論』の証言
付録二 『ペリ・ピュセオス』の霊魂
第七章 二つの表現群の連鎖
付録 断片二七・三ー四行の四根‐擬人化の表現
第八章 愛憎の正体
第九章 ダイモーンの転生の円環と四根の転生の円環の対応
付録一 愛の可死者を生成させる性質
付録二 ヒッポリュトス『駁論』の証言
第一〇章 三つの障壁の除去
一 カーンの四根説批判
第一一章 ダイモーンの転生と四根の転生の齟齬
第―二章 『ペリ・ピュセオス』と『カタルモイ』の関聯2(結論)
付録 両作品の関聯の度合
補遺
1 エンペドクレスと血‐認識器官説
2 エンペドクレスと細孔説
3 〓の正体
一 研究者諸氏の見解
4 〓の正体
5 〓の正体
6 断片二六・五行の〓
7 断片一三一~断片一三四の帰属
8 両作品の規模
9 両作品執筆の年代と場所
跋語
引用文献

2022.02.25発売
政党支持の分析
創文社オンデマンド叢書
戦後わが国有権者の政党支持の特性と発展を、全国的規模の政治意識調査データをすべて収集し、長期視野に立って統一的に分析。
【目次より】
序
第1章 政党支持と社会構造・国際環境の変動
1 始めに 2 職業構成の変動 3 都市への人口移動 4 経済的生活意識と石油危機 5 新旧世代の交替 6 高学歴層と政治的シニシズム 7 国際環境の変化 8 時期区分によるまとめ
第2章 政党支持の類型とその特性
1 始めに 2 党派性の諸側面の尺度 3 政党支持の類型 4 政党支持の変動と支持の類型 5 政策に対する態度と政党支持の類型 6 投票における政党選択と政党支持の類型 7 1967年ミシガン調査データによる政党支持類型との比較 8 結び
第3章 政党支持の変動と支持の幅
1 始めに 2 政党支持の変動:長期的,短期的変動要因 3 政党支持の幅の仮説 4 政党支持の幅の尺度の構成 5 政党支持の幅の尺度の相対的安定性 6 政党支持の幅と政党選択 7 結び
第4章 政党支持の社会化過程
1 始めに 2 父親の支持政党の認知 3 両親と子の政党支持の一致 4 政党支持強度に対するグループの影響 5 政党支持をめぐる初期社会化と後期社会化 6 社会化効果の相対的ウェイト 7 結び
第5章 政党支持と職業利益
1 始めに 2 政党支持のデモグラフィック要因による多変量解析 3 政党支持の社会化過程と職業移動 4 職業カテゴリーと職業代表政党 5 職業代表政党から支持政党へ 6 職業代表政党なし層の政党選択 7 新中間層の政党支持と生活満足度 8 結び
第6章 「保守ー革新」イデオロギーと態度空間
1 始めに 2 「保守ー革新」イデオロギーのコンポーネント 3 「保守ー革新」次元の認知的前提 4 保革自己イメージ 5 政党空間における保革次元 6 政策空間における保革次元 7 政策イメージの変換機能 8 結び
第7章 政策争点・政党の政策イメージ・政党選択
1 始めに 2 政策争点と政党選択の関連モデル 3 政策争点と政策イメージの認知 4 政策イメージ尺度の構成とその分布 5 「政党の政策イメージ」と政党支持 6 「政党の政策イメージ」と投票における政党選択 7 結び
第8章 政党支持強度の消長
1 始めに 2 いくつかのモデルの検討 3 データと政党支持強度の尺度 4 政党支持強度に対する年功効果と時勢効果 5 政党支持強度と投票との一致 6 支持強度に及ぼすフォーマル・インフォーマルな集団の影響 7 政治不満の蔓延と政党支持強度の低下 8 結び
引用文献
調査一覧
補遺I
補遺II
あとがき

2022.02.25発売
ディースターヴェーク研究 その初等学校改革構想とプロイセン議会
創文社オンデマンド叢書
19世紀ドイツで活躍した教育家ディースターヴェークによる、初等学校改革とプロイセン議会=近代以降の公教育が孕む教育と政治の緊張関係を解明した力作。
【目次より】
はしがき
序章 研究の課題と方法
第一節 先行研究と目的
第二節 考察の方法と構成・資料
第一章 「三月以後」五〇年代における初等学校政策の推進とディースターヴェーク教育構想との対立
第一節 三月革命の終焉とプロイセン名望家政治体制の創出
第二節 議会における党派形成とブルジョアジーの教育的思惟 一八五三年の工場法制定をめぐって
補論 一八三九年規程の制定とブルジョアジーの対応 一八五三年法の成立前史
第三節 プロイセン三規程とディースターヴェーク教育論
補論 一八五三年工場法と三規程 初等学校の学習内容の制限をめぐって
第二章 「新時代」の議会における初等学校論議とディースターヴェークの対応
第一節 「新時代」のディースターヴェーク・自由派・衆議院
第二節 初等学校教育改善の請願と審議
第三節 初等教師の待遇改善・学校運営参加の請願と審議
第四節 宗派混合学校問題とディースターヴェークの対応
第三章 六〇年代における初等学校管理体制の再編政策とディースターヴェークの改革構想
第一節 ドイツ進歩党の結成とディースターヴェークの参画
第二節 学校行政分権化の模索 学校共同体制度の廃棄
第三節 ドイツ進歩党の改革案とディースターヴェークの指導的役割
第四節 「自由な国の自由な学校」構想とその周辺 学校共同体の再生と解体
結章 「三月以後」プロイセン名望家政治体制における初等学校政策とディースターヴェーク改革構想の意義と役割
資料・文献
ディースターヴェークの議会活動年表

2022.02.25発売
古代キリスト教思想家の世界 教父学序説
創文社オンデマンド叢書
オリゲネス、エウセビオス、アウグスティヌスなどの古代キリスト教思想家を、聖書・伝承・哲学・異端・神学・司牧との関わりのうちに概観し、信仰と愛に生きたその姿を描く。
【目次より】
序言
目次
序言 ペテロ・ネメシェギ
序章
第一章 教父とは
第二章 教父と聖書
第三章 教父と伝承
第四章 教父と哲学
第五章 教父と異端
第六章 教父と神学
第七章 教父と司牧
第八章 教父・信仰の人
索引・地図

2022.02.25発売
ヘーゲル宗教哲学の研究 ヘーゲルとキリスト教
創文社オンデマンド叢書
ヘーゲルのキリスト教肯定の立場を保守的とする従来の解釈を吟味し、その革新的性格を明かにする本邦初の業績。
【目次より】
凡例
目次
緒論
第一章 ヘーゲル研究史展望
第二章 宗教哲学の位置
一 問題の所在
二 『宗教哲学講義』テキストの問題
本論
はじめに
第一部 宗教の概念
第一章 宗教哲学の概念
一 信と知
二 和解
三 宗教と哲学
四 宗教哲学と哲学
五 宗教哲学と既成宗教
付論 経典(正典)化の問題
解釈
六 時代の原理
第二章 宗教の概念
1 予備問題
2 内容区分
一 ヘーゲルの神観
二 宗教論
三 宗教的意識の諸形式
1 直接知
2 感情
3 直観
4 表象
四 思惟の形式における宗教
1 表象の弁証法
2 宗教的意識の自己自身における媒介
A 直接知と媒介
神の存在証明
(a) 一般論
(b) 宇宙論的証明
(c) 自然神学的証明
(d) 存在論的証明
(e) 存在証明の評価
B 媒介知 有限・無限関係
3 宗教の思弁的概念
五 儀式
1 信仰論
2 儀式形態
3 国家論
第二部 規定的宗教
第一章 自然宗教
一 直接的宗教
1 魔術
2 その客観的規定
3 その儀式
二 意識の自己内分裂
形而上学的概念
1 中国の宗教
2 想像の宗教
3 自己内存在の宗教
三 自由の宗教への移行段階にある自然宗教
1 ペルシアの宗教 善の宗教、光の宗教
2 シリアの宗教 苦の宗教
3 エジプトの宗教 謎の宗教
第二章 精神的個別性の宗教
移行とこの宗教の形而上学的概念
一 崇高性の宗教
二 美の宗教
三 合目的性の宗教
第三部 絶対的宗教
総論的に
第一章 父の国
三一論
第二章 子の国
一 罪責論
二 和解論
三 神の死
第三章 霊の国
結論
あとがき
付録
I グロックナー版 ヘーゲル宗教哲学講義総目次
II ラッソン版 ヘーゲル宗教哲学講義総目次
参考文献

2022.02.25発売
習慣の哲学
創文社オンデマンド叢書
古代・中世の習慣概念の形成と展開を歴史的に跡づけ、さらに習慣の体系的考察により今日閑却されている習慣の復権を主張した問題作。
【目次より】
再版への序言
初版はしがき
目次
第一部 序論
第一章 習慣の概念
第二章 経験主義と習慣の問題
第二部 習慣論の歴史的研究
第三章 トマスの習慣論
はじめに
第一節 歴史的源泉
第二節 習慣の本質
第三節 習慣の原因
第四節 習慣と徳 トマスの人間論
第五節 トマス以後の展開
第四章 パースの習慣論 経験主義と形而上学
第五章 デューイの習慣論 経験と習慣
第三部 習慣論の体系的研究
第六章 習慣と価値
第七章 習慣と自由
第八章 習慣と意志
第九章 意志と徳
第十章 習慣と法
第十一章 習慣と因果性
第十二章 習慣と確実性
第十三章 習慣と形而上学
あとがき