新刊書籍
レーベルで絞り込む :

2022.02.25発売
神学大全22 第II-2部 第151問題~第170問題
創文社オンデマンド叢書
13世紀になった、聖書解釈や神学者の注解を体系的に集大成した全45巻の中世キリスト教神学の金字塔。第II-2部 第151問題~第170問題を収録。
【目次より】
凡例
目次
第百五十一問題 貞潔について
第百五十二問題 純潔について
第百五十一二問題 淫蕩という悪徳について
第百五十四問題 淫蕩の種類について
第百五十五問題 自制について
第百五十六問題 自制のなさについて
第百五十七問題 寛容ならびに穏和について
第百五十八問題 怒りについて
第百五十九問題 苛酷について
第百六十問題 節度について
第百六十一問題 謙遜について
第百六十二問題 高慢について
第百六十三問題 最初の人間の罪について
第百六十四問題 最初の罪の罰について
第百六十五問題 人祖に対する誘惑について
第百六十六問題 学ぶべきものに専念することについて
第百六十七問題 好奇心につして
第百六十八問題 外に表われた身体の立ち居振る舞いにおける節度について
第百六十九問題 外見の服装における節度について
第百七十問題 節制に関する掟について
訳者注
あとがき

2022.02.25発売
神学大全6 第I部 第75問題~第89問題
創文社オンデマンド叢書
全45巻からなる中世キリスト教神学の金字塔。
第75問題~第89問を収録。
【目次より】
第七十五問題 霊的実体と物体的実体から成る人間について──ここではまず魂の本質に関すること
第七十六問題 魂の身体に対する合一について
第七十七問題 魂の能カ一般に属する諸般のことがらについて
第七十八問題 魂の諸能力について──個別的に
第七十九問題 知性的諸能力について
第八十 問題 欲求の諸能力一般について
第八十一問題 感能について
第八十二問題 意志について
第八十三問題 自由意思について
第八十四問題 身体と結合された魂は如何なる仕方でその下位にある諸々の物体的なるものを知性認識するのであるか
第八十五問題 知性認識の仕方と序列について
第八十六問題 我々の知性は質料的な諸事物において如何なるものを認識しうるか
第八十七問題 知性的魂は如何にして自己を、そして自己のうちなる諸般のことがらを認識するのであるか
第八十八問題 人間の魂は如何にして自己の上位にあるところのものを認識するか
第八十九問題 分離された魂における認識について
訳者注

2022.02.25発売
神学大全5 第I部 第65問題~第74問題
創文社オンデマンド叢書
中世になった、全45巻からなる中世キリスト教神学の金字塔。第65問題~第74問題を収録。
【目次より】
第六十五問題 物体的被造物の創造の業について
第一項 物体的被造物は神に基づくか
第二項 物体的被造物は神の善性のために造られたのであるか
第三項 物体的被造物の神による産出は天使たちを媒介とするものであったか
第四項 諸物体の諸々の形相は天使たちに基づくか
第六十六問題 「創造」に対する「区別」の位置について
第一項 質料の「かたちなきさま」が、それの「かたちづくり」に、時間的に先立ったのであるか
第二項 すべての物体的なるものについて、単一な無形相の質料が存在するか
第三項 浄火天は無形相の質料と同時に創造されたのであるか
第四項 時間は無形相の質料と同時に創造されたのであるか
第六十七問題 区別の業そのものについて──最初の日の業
第一項 「光」は霊的なるものの領域でその固有の意味において語られるか
第二項 光は物体であるか
第三項 光は質であるか
第四項 光の産出が最初の日のこととされるのは適切であるか
第六十八問題 第二日の業について
第一項 蒼弯は二日目に造られたか
第二項 蒼弯の上に水が存在するか
第三項 蒼弯が水を水から分つのであるか
第四項 ただ―つの天が存在するのみであるか
第六十九問題 第三日の業について
第一項 水を集めるわざが三日目に行なわれたとされているのは適切であるか
第二項 諸々の植物の産出が三日目に行なわれた旨の読まれるのは適切であるか
第七十問題 装いの業について──第四日の業
第一項 諸々の光体は四日目に産出さるべきであったか
第二項 諸々の光体の産出の因は適切な仕方で叙述されているか
第三項 天の諸々の光体は魂あるものであるか
第七十一問題 第五日の業について
第七十二問題 第六日の業について
第七十三問題 第七日に属する諸般のことがらについて
第一項 神の諸々の業の完了は第七日に帰せらるべきであるか
第二項 神は七日目にそのすべての業を離れて休らい給うたのであるか
第三項 祝福や聖化が第七日という日に与えられるのは当然であるか
第七十四問題 全七日一般について
第一項 以上の日々を挙げれば充分であるか
第二項 これらの日々は実はすべてが一日なのであるか
第三項 聖書は六日の業を表わすのに適切なことばを用いているか

2022.02.25発売
経済と社会:音楽社会学
創文社オンデマンド叢書
社会学の泰斗による「経済と社会」シリーズの付論である。一貫して近代の意味を問うウェーバー社会学の重要著作シリーズの冊。
【目次より】
凡例
緒論(テーオドール・クロイヤー)
音楽社会学 音楽の合理的社会学的基礎
解説
マックス・ウェーバーと音楽
音楽理論の基礎について
訳者後記
第二刷あとがき
音楽用語集

2022.02.25発売
刑法綱要総論(第三版)
創文社オンデマンド叢書
戦後刑法学の泰斗による、刑法についての基本中の基本の図書な長年にわたって改定され続けた。『刑法要綱 各論』もあわせて読みたい。
第三版のはしがき 初版のはしがき 初版第六五刷のはしがき 改訂版のはしがき 改訂版第一四刷のはしがき
凡例
文献
第一編 刑法
第一章 刑法の意義、性格および機能
第二章 刑法理論
第三章 刑法の法源およびその適用範囲
第一節 罪刑法定主義
第二節 刑法の法源
第三節 刑法の時間的適用範囲
第四節 国際刑法 ことに刑法の場所的適用範囲
第二編 犯罪
第一章 犯罪論の体系
第二章 構成要件
第一節 総説
第二節 構成要件要素
第三節 構成要件該当性
第三章 違法性
第一節 総説
第二節 一般的正当行為
第三節 緊急行為
第四章 責任
第一節 総説
第二節 責任能力
第三節 故意
第四節 過失
第五章 未遂罪
第一節 未遂罪(狭義)
第二節 中止犯
第六章 共犯
第一節 共犯の本質
第二節 共同正犯
第三節 教唆犯
第四節 幇助犯
第五節 共犯に関する諸問題
第七章 犯罪の成立、個数および競合
第一節 犯罪の成立と個数
第二節 犯罪の競合
第三編 刑罰および保安処分
第一章 刑罰制度
第一節 刑罰および刑罰法律関係
第二節 刑罰の種類
第二章 観念的刑罰法律関係(刑の適用)
第一節 総説
第二節 刑の加重・減軽
第三節 累犯
第四節 刑の量定
第三章 現実的刑罰法律関係(刑の執行等)
第一節 総説
第二節 刑の執行猶予
第三節 仮釈放
第四章 少年に関する特則
第五章 保安処分
追補

2022.02.25発売
刑法綱要各論(第三版)
創文社オンデマンド叢書
戦後刑法学の泰斗による、日本刑法の最重要基本図書である。『刑法綱要 総説』とあわせて読みたい。
【目次より】
第三版のはしがき 初版のはしがき 改訂版のはしがき 改訂版第三刷のはしがき
凡例
文献
緒論
第一編 国家的法益に対する罪
第一章 国家の存立に対する罪
第一節 内乱に関する罪 第二節 外患に関する罪 第三節 破壊活動防止法の罪
第二章 国家・地方公共団体の作用を害する罪
第一節 公務員・公務所の意義 第二節 公務の執行を妨害する罪 第三節 逃走の罪 第四節 犯人蔵匿および証憑湮滅の罪 第五節 偽証の罪 第六節 誣告の罪 第七節 涜職の罪 第八節 経済関係罰則の整備に関する法律の罪
第三章 国際社会に対する罪
第一節 総説 第二節 国交に関する罪
第二編 社会的法益に対する罪
第一章 社会的秩序に対する罪
第一節 騒擾の罪 第二節 放火および失火の罪 第三節 爆発物取締罰則の罪 第四節 溢水および水利に関する罪 第五節 往来を妨害する罪 第六節 アヘン煙に関する罪 第七節 飲料水に関する罪
第二章 経済的秩序に対する罪
第一節 通貨偽造の罪
第二節 有価証券偽造の罪 第三節 文書偽造の罪 第四節 印章偽造の罪 第三章 道徳的秩序に対する罪
第一節 猥褻および重婚の罪 第二節 売春防止法の罪 第三節 賭博および富籤に関する罪 第四節 礼拝所および墳墓に関する罪
第三編 個人的法益に対する罪 付・コンピューター犯罪
第一章 生命・身体に対する罪
第一節 殺人の罪 第二節 傷害の罪 第三節 過失傷害の罪 第四節 決闘に関する罪 第五節 堕胎の罪 第六節 遺棄の罪
第二章 自由に対する罪
第一節 逮捕および監禁の罪 第二節 脅迫の罪 第三節 暴力行為等処罰に関する法律の罪 第四節 略取および誘拐の罪 第五節 強制猥褻の罪
第三章 私生活の平穏を害する罪
第一節 住居を侵す罪 第二節 秘密を侵す罪
第四章 名誉・信用に対する罪
第一節 名誉に対する罪 第二節 信用および業務に対する罪
第五章 財産に対する罪
第一節 総説 第二節 窃盗および強盗の罪 第三節 詐欺および恐喝の罪 第四節 横領および背任の罪 第五節 賍物に関する罪 第六節 毀棄および隠匿の罪
第六章 コンピューター犯罪

2022.02.25発売
神学大全24 第II-2部 第183問題~第189問題
創文社オンデマンド叢書
13世紀、聖書解釈や神学者の注解を体系的に集大成した全45巻からなる中世キリスト教神学の金字塔。第II-2部 第183問題~第189問題を収録。
【目次より】
まえがき
第一八三問題 人間の職分及び身分一般について
第一項 身分はその本質に自由または隷属の条件を含むか ~ 第四項 身分の区別は初歩者、進歩者、完全者に従って認められるか
第一八四問題 完全性の身分について
第一項 キリスト教的生活の完全性は特に愛に従って認められるべきか ~ 第八項 主任司祭と助祭長は修道者に優る完全性を有するか
第一八五問題 司教の身分の所属事項について
第一項 司教職を志望することは許されるか ~ 第八項 司教に登用の修道者は修道規律の遵守義務を負うか
第一八六問題 修道者の身分の主要構成事項について
第一項 修道者の身分は完全性の身分を含意するか ~ 第十項 罪の種類が同一の場合、修道者は世俗者よりも重罪を犯すか
第一八七問題 修道者の専属事項について
第一項 修道者は、教授、説教、その他これに類する役務の遂行が許されるか ~ 第六項 修道者は他の人々よりも粗衣を着用することが許されるか
第一八八問題 修道会の多様性について
第一項 修道会は単一であるか ~ 第八項 共住生活者の修道会は独住生活者の修道会よりも完全であるか
第一八九問題 修道会入会について
第一項 掟の錬成者以外は修道会に入会すべきでないか ~ 第十項 多数者との相談及び先行の長期間の熟慮を欠く修道会入会は、称賛すべきであるか
訳者注
解説

2022.02.25発売
六朝文学への思索(東洋学叢書)
創文社オンデマンド叢書
斯波六郎の中国文学研究の全体像がわかる遺稿集。 幅広く中国文学を探究し、かつその深遠に迫る必読書である。教育論も併録する。
【目次より】
序言
I 文選学研究
解題 文選
解題 昭明太子
一 李善文選注引文義例考
二 読文選札記
三 文選訳注
II 文心雕龍研究
解題 文心雕龍
一 文心雕龍札記
二 文心雕龍范注補正
III 六朝唐代文学研究
一 六朝人の作品に見える二三の語に就いて
二 「為当」考
三 文筆考
四 「賦得」の意味について
五 後漢末期の「談論」について
六 陶靖節詩箋補正
七 杜詩札記
八 中國の人生詩人達
九 雑纂
一 漢の文学
附篇
一 中等教育に於ける漢文の訓読について
二 随筆
斯波六郎博士 年譜
あとがき
斯波六郎博士 著作目録

2022.02.25発売
アリストテレス哲学の研究 その基礎概念をめぐって
創文社オンデマンド叢書
紀元前4世紀、プラトンの弟子として「フィロソフィア」を確立した西洋古代哲学者の巨人。「万学の祖」の功績を丹念に解き明かす。
【目次より】
まえがき
著作名略記一覧
第一章 実体概念
一 実体概念についての通念的解釈の問題性
二 第一の範疇の呼称
三 属性の主語としての実体
四 自己規定的述語 本質述語としての実体
五 実体的述語と定義的述語
第二章 現実態と可能態の概念
一 「エネルゲイア」をめぐる問題
二 可能態、現実態とはどういうことか
三 述語としての「現実態・可能態」
A 「運動」(キーネーシス)の定義
B 「魂」(プシューケー)の定義
四 「可能態から現実態へ」の二つのパターン
第三章 「実体」再論 その諸問題の検討
一 実体の特徴 あるこれ性と離在性
二 実体原理としての形相と質料
三 実体は可認識であるか
四 実体的一性と種的一性
第四章 自然論
一 自然学は観想か
二 アリストテレスにおける生成のプラトン的三分類
三 目的設定よりする必然性・必須条件
四 生成の内的原理としての自然
五 秩序ある世界としての自然
第五章 存在概念
一 先駆的存在思想
二 「存在」と「一」の概念
三 範疇と存在・一の関係
四 超越的述語としての「存在」と「一」
第六章 アリストテレス哲学の諸問題
I 「第三の人間」論 イデア論批判の一問題
II 「範疇論」真作性の問題
III 「至福者の島」思想 初期作品の一問題
注
あとがき
使用文献表
主要訳語表

2022.02.25発売
カントの実践哲学 その基盤と構造
創文社オンデマンド叢書
『純粋理性批判』『実践理性批判』『判断力批判』の三批判書を著した18世紀のドイツ哲学の巨人の思想を、実践哲学の視点から読む。
【目次より】
まえがき
凡例
第一章 カントの人格性とエートス
第一節 カントの人格性とエートスの形成
一 生い立ち
二 幼少・大学時代
三 家庭教師時代
四 私講師時代
五 ピエティスムスと啓蒙思想
第二節 人格とエートスの表現
一 生活と人格
二 責務の原則
三 人間本性の美と尊厳の感情
第二章 批判的倫理学への道
第一節 道徳性の原理の探求
一 先人の道徳体系
二 道徳性の原理
第二節 責務と帰責
一 責務と自由
二 帰責
第三節 義務論
一 自己自身に対する義務
二 他人に対する義務
第三章 批判哲学の諸問題
第一節 超越論的哲学の構造
一 『批判』における超越論的哲学
二 『遺稿』における超越論的哲学
三 知恵の学としての超越論的哲学
第二節 物自体の諸相
一 われわれの感性を触発するもの
二 超越論的対象
三 可想的存在
四 超越論的理念
第四章 自由と道徳法則
第一節 超越論的自由
一 第三二律背反とその解決
二 超越論的自由と必然性
第二節 超越論的自由と実践的自由
一 純粋理性の自由
二 帰責可能性の根拠としての自由
第三節 自我と自由
一 自我と実体
二 自我と自由
三 超越論的統覚としての自我
第四節 道徳法則
一 定言命法の根拠
二 定言命法の構造
第五節 技術的命法と定言命法
一 仮言命法の特性
二 技術的命法と定言命法
第五章 人間性尊重の道徳
第一節 人間的義務
一 責務と義務
二 法義務と倫理的義務
三 徳と徳義務
四 自己自身に対する義務と他人に対する義務
第二節 人間性の発展
一 人間観
二 人間本性における根源的素質
三 人間性の理想とその展開
第六章 倫理的価値思想
第一節 善意志の価値
第二節 行為の倫理的価値
第三節 人格的価値
あとがき
参考文献

2022.02.25発売
(訳注)中国歴代刑法志(続)(補)
創文社オンデマンド叢書
本書は、「隋書刑法志」「晉唐書刑法志」「新唐書刑法志」を原文と訳と注とを一書に収めたものである。
【目次より】
序
解題
目次
譯注 隋書刑法志
凡例
譯注 晉唐書刑法志
凡例
譯注 新唐書刑法志
凡例
『譯注績中國歴代刑法志』への補記 梅原郁
あとがき 梅原郁
英文レジュメ

2022.02.25発売
(訳注)中国歴代刑法志(補)
創文社オンデマンド叢書
本書は、「漢書刑法志」「晋書刑法志」「魏書刑法志」の原文、訳文、注を収録したものである。
【目次より】
序
解題
譯注 漢書刑法志
譯注 晋書刑法志
譯注 魏書刑法志
解説 冨田至
索引
英文レジュメ

2022.02.25発売
論語私感
創文社オンデマンド叢書
『論語』の章句を選び出して、言葉の意味をできるだけ正確に読み解いていく。武者小路実篤『論語私感』に触発されて書かれているが、目指す方向は逆である。詩、書、礼、楽を軸に据えて、学問的に取り扱う。そして最重要ともいえる、「道」と「天命」へとその考察は至る。汲めども尽きせぬ『論語』を味読する一冊。
【目次より】
序
封建制度と孝
孝と礼
礼と楽(音楽)
詩
詩と礼と楽と書 易と春秋
「学を好む」(学問を愛する)ことと「道」
隠逸と天命

2022.02.25発売
フランス法制史概説
創文社オンデマンド叢書
フランスの法制度をその起源からフランス革命までを通観する。フランスの法制を知るための基本図書である。
【目次より】
凡例
序言
新刷への序言
序論 ローマ的伝統とゲルマン的伝統との出会い(四世紀ー九世紀末)
史的概観
第一章 法源および法の記念碑
第二章 古代世界と新世界との媒介者としてのカトリック教会
第三章 ランク王国の政治制度
第四章 軍事、司法、行政の諸制度
第五章 社会構成と私法の精神
第六章 封建制の直接的な諸先行物
第一巻 フランス的諸制度の出現(一〇ー一三世紀)
史的概観
第一章 中世社会の一般的特徴
第二章 法源
第三章 中世社会の基礎としての領主領
第四章 都市と商工業活動
第五章 教会と霊的奉仕
第六章 王権と秩序構成
第七章 社会構成と私法
第二巻 王権の伸張と君主制の安定(一四ー一八世紀)
史的概観と叙述計画
第一章 王
第二章 組織された国民
第三章 顧問会議、輔弼官団〔即ち内閣〕および公職
第四章 諸宗教の一体制
第五章 陸軍と海軍
第六章 司法
第七章 行政と財政
第八章 二大社会的役務、即ち、扶助と教育
第九章 経済政策
第十章 社会構成と私法
結章 アンシャン・レジムの衰退と瓦解
附図
訳者あとがき

2022.02.25発売
離婚(東南アジア研究叢書) 比較社会学的研究
創文社オンデマンド叢書
離婚は文化に依存するのか。親族構造、宗教、法との関係は。欧米やアジア諸国そして日本における離婚の特徴を解明する。
【目次より】
まえがき
I 序論
A 研究の目的
B 親族構造と離婚発生との関係
C 宗教の離婚に対する態度
D 法的手続きとしての離婚
E 親族構造,宗教的価値観,法的手続きの間における相互依存性と独立性
F 近代化および都市化の影響
II 欧米の離婚
A 欧米諸国の離婚統制におけるキリスト教の役割
B 若干の国における離婚法と離婚傾向の変化
C ヨーロッパ諸国の離婚率
D フランスにおける離婚率の地域的分布
E 西ドイツにおける離婚率の地域的分布
F カナダにおける離婚率の地域的分布
G 米国における離婚率の地域的分布
H ヨーロッパ諸国における離婚率の変化とそのパターン
I 東西ベルリンにおける離婚率の変化
J ヨーロッパ以外の西欧文化圏における離婚率の変化
K 結論
III マレーシア・インドネシアにおける離婚
A 対象の規定と問題点
B スマトラ バタクとミナンカバウを中心として
C ジャワ ジャワ人の場合
D ボルネオ シー・ダヤクの場合
E マレー半島およびシンガポール マレ一人,ヌグリ・スンビランのミナンカバウ系住民,およびジャクンを中心として
F マラヤにおけるイスラム教徒の離婚の地域的分布
G マラヤ・シンガポール・インドネシアにおけるイスラム教徒の離婚傾向の変化
H マラヤ・シンガポール・インドネシアにおけるイスラム教徒の離婚傾向とアラブ諸国を中心とするイスラム教国における離婚傾向との比較
I 結論
IV 日本の離婚
A 日本の離婚をとり扱う場合の問題点
B 日本における離婚率の変化
C わが国の離婚と「家] 追出し離婚について
D 武士の「家」と離婚
E 農民における離婚とその背景 武士の社会との対比において
F 地域による農民家族の類型の相違とその離婚率への反映
G 離婚率の地域的分布における特殊例
H 婚姻をめぐる諸状況の変化と離婚率の変動
I 中国人の離婚 日本人の離婚との対比において
J 結論
V 総括
引用文献
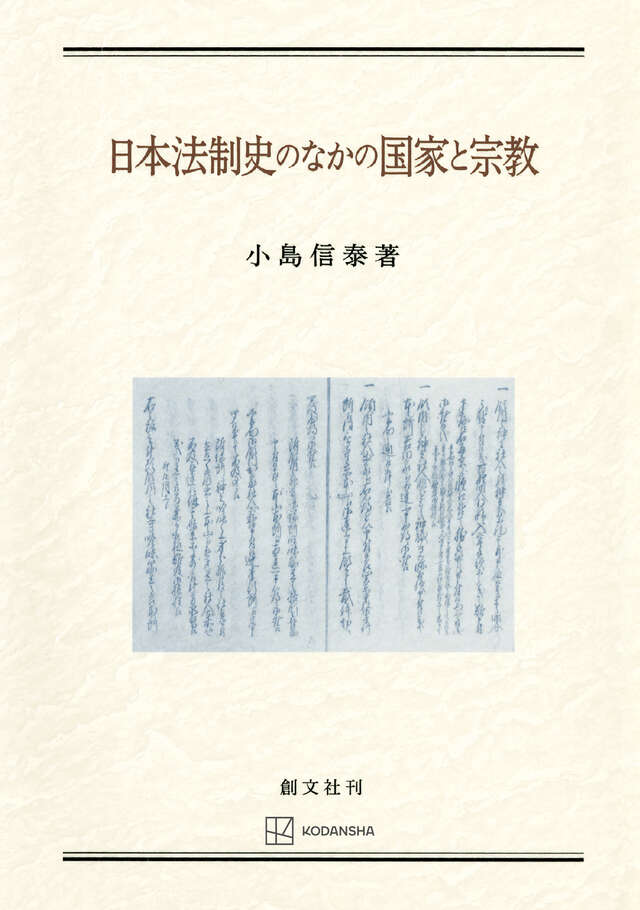
2022.02.25発売
日本法制史のなかの国家と宗教
創文社オンデマンド叢書
宗教集団に注目して、それが各時代の国家の中にあっていかに自治・自律を保持できたかを歴史的に探り、国家・法・宗教を考える。
【目次より】
凡例
第一編 古代・中世
第一章 古代の国家と仏教
はじめに
第一節 前史 釈迦の生涯と原始仏典
第二節 大乗仏典と日本への仏教公伝
第三節 古代国家の成立
第四節 古代国家の仏教制度
第二章 中世の国家と仏教
第一節 王法と仏法
第二節 鎌倉幕府と仏教
第三節 鎌倉仏教の展開と室町幕府
結び 近世の始まり
第三章 最澄・日蓮と国家
はじめに いま最澄・日蓮に学ぶ意味
第一節 最澄・日蓮と聖俗の関係
第二節 国家と宗教
第三節 『立正安国論』と鎌倉幕府
第四節 聖と俗の行方
おわりに 国家と宗教の新時代に向けて
補論一 自著紹介『最澄と日蓮 法華経と国家へのアプローチ』
第二編 近世
第四章 近世の国家と仏教
はじめに
第一節 近世史研究と国家・法・宗教
第二節 近世の仏教統制
第三節 国家と仏教
おわりに
第五章 江戸時代の公家に関する裁判権
はじめに
第一節 近世の公家の地位
第二節 公家のその領地に対する裁判権
第三節 公家に対する裁判権の所在
おわりに
補論二 江戸時代の公家と裁判 現在の研究状況と今後の課題
はじめに
第一節 文献紹介と本稿の課題
第二節 公家の処罰
第六章 江戸時代の文人が描いた僧侶 その法的側面を中心として
はじめに
第一節 江戸時代の寺院と僧侶
第二節 僧侶と借金
第三節 僧侶改革
おわりに
〔コラム1〕 借金の始末 江戸時代の法の階層構造
〔コラム2〕 江戸時代寺院研究の新視点
第三編 歴史を見る眼
第七章 法制史から見る江戸と現代
第八章 「公」について
第九章 歴史の中に法を見る 遺失物取得・生殺与奪・動産と不動産
■結語
あとがき
本書収録論文初出一覧

2022.02.25発売
人間学 その歴史と射程
創文社オンデマンド叢書
哲学・思想を超えて、人間とは一体何者なのか? 古今東西の重要思想を渉猟した著者は、総合的な人間理解の学としてのが人間学である。
【目次より】
0 人間学とはいかなる学問か
第 I 部 人間学の歴史的展開
1 ギリシア哲学の人間観
1 古代ギリシアの人間観の素地 2 ソクラテス 3 プラトン 4 アリストテレス 5 結びにかえて
2 聖書の人間観
1 人間についての聖書の語り方 2 人間の条件 3 契約団体と預言者 4 愛と自由
3 中世における人間観
1 アレクサンドリアのフィロン 2 初級キリスト教の人間論 3 中世初期の人間論 4 スコラ哲学の人間論
4 近代ヒューマニズムの人間観
1 ヒューマニズムとはなにか 2 フマニタスの理念と理想的人間像 3 ヒューマニズムの人間観 4 具体的人間への志向 5 人間観の変容
5 啓蒙主義の人間学
1 デカルト 2 ヴィーコ 3 ディドロ 4 カント
6 ドイツ観念論,その完成と解体における人間学
1 ヘーゲルの人間学 2 フォイエルバッハの人間学 3 マルクスによる〈関係としての人間〉論の再構築
7 実存哲学の人間学
1 キルケゴールの単独者的人間学 2 ブーバーの対話的人間学 3 まとめ
8 現代における哲学的人間学の成立
1 近代主観性の哲学と実存哲学 2 シェーラーの間主観性の現象学 3 『宇宙における人間の地位』の人間学的特徴 4 プレスナーの哲学的人間学 8.5 ゲーレンの人間学 8.6 現象学的人間学の意義
第 II 部 人間学の体系的展開
1 人間と文化
1 人間と文化との一般的関連 2 人間の「話す」行為と文化 3 人間の「作る」行為と文化 4 人間の「行なう」実践行為と文化
2 人間と言語
1 人間と言語 2 音と声 3 叫びと声 4 結論
3 現代心身論
1 デカルトの心身問題 2 スピノザの心身平行論 3 ライプニッツによる心身の予定調和論 4 現代生命論 5 現代生命論における心身関係
4 人間と宗教:仏教
1 仏教と人間学 2 ブッダの悟り 3 親鸞の立場 4 二種深信について 5 唯識思想について 6 末那識の発見
5 人間と宗教:キリスト教
1 宗教と人間学.2 キリスト教人間学 3 人間と神
6 人間と政治
1 現在の政治状況と人間 2 自由主義と共同体論との論争 3 アーレントの価値ヒエラルキー転倒論 4 むすび
7 人間と歴史
1 人間と歴史の相互関係 2 歴史と科学 3 歴史と物語 4 歴史のパースペクティヴ理論 5 歴史的理解の可能性 6 おわりに

2022.02.25発売
ウルトラ特撮 PERFECT MOOK vol.40ウルトラマンZ
全「ウルトラマン」シリーズと円谷プロが制作した特撮作品をすべて網羅した大全集ムック!
「ウルトラマンZ」を大特集
◎ウルトラマンゼット全能力
◎STORAGE隊員、特殊装備、特空機1~4号
◎登場する宇宙怪獣、怪獣、宇宙人を徹底紹介
◎特別インタビュー
平野宏周(ナツカワ ハルキ役)
「ポテンシャルを上げながら演じていかなければ!」
◎スタッフインタビュー
辻本貴則(映画・テレビドラマ監督)
◎特別企画
「ウルトラ ロボット名決戦」
「ヒーローの帰還」
◎好評連載
切通理作/野中剛

2022.02.25発売
決定版 侍戦隊シンケンジャー ひみつ超百科
講談社の絵本
天下御免の侍戦隊シンケンジャー参上! 三途の川からあらわれる外道衆を倒すため、現代のサムライたちが立ち上がる。モヂカラをあみだした志葉家の18代目当主、志葉丈瑠と仲間たち5人が一筆奏上! シンケンジャーに変身して戦うぞ。さらにシンケンゴールドが加わった6人の強さのひみつを大研究。スーパーロボ、シンケンオーものっているよ。キミのまだ知らないひみつがいっぱい!

2022.02.25発売
決定版 ウルトラヒーロー 135大決戦超百科
講談社の絵本
ウルトラマン対大怪獣! バトル炸裂! 歴代ウルトラヒーローがくりひろげてきた激戦のすべてがここに! 厳選された名バトルがよみがえるぞ。ウルトラマンからウルトラマンメビウスまでの歴代ウルトラヒーローと強敵怪獣・宇宙人との名決戦。そして『ウルトラギャラクシー 大怪獣バトル ネバーエンディングオデッセイ』まで展開された大怪獣たちのレイオニクスバトルを超特集。キミのまだ知らない情報が満載!
1)ゴモラvsゴメス(S)、マグラー 12)ゴモラvsエレキング 14)メビウス、ヒカリvsコダイゴン ジアザー 23)ウルトラマンマックスvsバグダラス 31)ウルトラマンネクサスvsバグバズン 38)ウルトラマンコスモスvsカオスバグ 43)ウルトラマンネオスvsザム星人 47)ウルトラマンガイアvsメザード 57)ウルトラマンダイナvsグロッシーナ 66)ウルトラマンティガvsスタンデル星人 アボルバス 74)ウルトラマンパワードvsダダ 78)ウルトラマングレートvsリュグロー 79)ウルトラマン80vsガビシェール 85)ウルトラマンレオvsケットル星人 90)ウルトラマンタロウvsパンドラ 99)ウルトラマンAvsブロッケン 109)ウルトラマンジャックvsマグネドン 119)ウルトラセブンvsベル星人 135)ウルトラマンvsキーラ