新刊書籍
レーベルで絞り込む :

2024.09.30発売
近世法制史料叢書3:武家厳制録・庁政談
創文社オンデマンド叢書
「武家厳制録」は、慶長3年より元禄16年に至る幕府法令集で、内容からみて元禄宝永期前後になった私選であるとされる。評定所に対して、幕府がその指針として提示している。
「庁政談」は、評定所定書の系統にあり、「国群境論」から始まり、地方を含む全国を対象とした法令を集めたものである。
【目次】
武家嚴制録
卷一
禁裏院中並公家中御條目
卷二
武家御條目之部
卷三
御陣中、付御上洛並日光 御成御條目之部
御陣中御條目
御上洛之時御條目
日光御成御條目之上
卷四
日光御成御條目之下
卷五
所々御番城御條目之部
卷六
所々御番城御條目之部下
卷七
諸宗寺院僧中御條目之部
卷八
諸宗寺院中御條目之部並臨時之御判物
卷九
諸宗寺院御條目之部
卷十
髙野山御條目之部
卷十一
神社御條目之部
卷十二
神社領御寄進状付知行目録之部
卷十三
寺領御寄附状、付知行目録部
卷十四
寺社方公事御裁許御下知状部
卷十五
髙野山公事御裁許御下知状部
卷十六
諸大名代替之時御條目之部
御改易衆有之時御條目之部
卷十八
福嶋左衛門太夫領國被 召上候時御制法部
卷十九
京極丹後守御預之節御掟之次第
卷二十
卷二十一
御役人衆御條目部
卷二十二
雜部
卷二十三
萬札之部
卷二十四
萬札之部
卷二十五
萬札之部
卷二十六
萬札之部
卷二十七
萬札之部
卷二十八
萬札之部
卷二十九
雜部
卷三十
雜部
卷三十一
雜之部
卷三十二
雜之部
卷三十三
雜部
卷三十四
雜部
卷三十五
雜部
卷三十六
雜部
卷三十七
關所女手形之部
卷三十八
服忌令部
卷三十九
雜部
附、御側衆御下知條々
卷四十
家綱公御本丸御移徙之時御條目部
卷四十一
卷四十二
卷四十三
卷四十四
卷四十五
御清之部
卷四十六
所々御番所之次第
卷四十七
所々御名代、付上使之次第
卷四十八
雜部
卷四十九
公帖並御内書之次第

2024.09.30発売
近世法制史料叢書2:御当家令条・律令要略
創文社オンデマンド叢書
「御当令状」は、1597(慶長2)年から1696(元禄9年)まで,江戸幕府の法令約600通を収録したもの。慶長以前の法令も数通を含んでいる。1711(正徳1)年付けの藤原親長の序があるが、どのような人物であったかは不明である。
「律令要略」とは、「公事方御定書」を制定するにあたり、当時私撰の幕府の法律書である。
【目次】
御當家令條
卷一
(一)一諸大名連判條々 慶長十六辛亥四月
(二)一同斷 慶長十七壬子正月
(三)一武家諸法度 元和元乙卯七月
(四)一御旗本諸法度 寛永九壬申九月
(五)一武家諸法度 寛永十二乙亥六月
(六)一御旗本諸法度 同年十二月
(七)一武家諸法度 寛文三癸卯五月
(八)一同口上之覺 殉死 同斷
(九)一御旗本諸法度 同年八月
(一〇)一武家諸法度 天和三癸亥七月
〔以下、各巻の詳細は省略〕
卷二
卷三
卷四
卷五
卷六
卷七
卷八
卷九
卷十
卷十一
卷十二
卷十三
卷十四
卷十五
卷十六
卷十七
卷十八
卷十九
卷二十
卷二十一
卷二十二
卷二十三
卷二十四
卷二十五
卷二十六
卷二十七
卷二十八
卷二十九
卷三十
卷三十一
卷三十二
卷三十三
卷三十四
卷三十五
卷三十六
卷三十七
律令要略

2024.09.30発売
近世法制史料叢書1:御仕置裁許帳・厳牆集・元禄御法式
創文社オンデマンド叢書
御仕置裁許帳は、小伝馬町の牢獄の囚人名とその罪状を記した史料から、1657(明暦3)年から1699(元禄12)年の裁判例となる974件の事件を採録した史料。18世紀初頭に、江戸町奉行所の役人によって作成されたとされている判例集。
また、元禄御法式は、上記、御仕置裁許帳を元に、法令の条文の形に編纂しなおしたもの。公事方御定書の先駆けとなるものとして、重要な史料である。
その他、厳牆集も収録。
【目次】
御仕置裁許帳
一
一 主人弑者並從類
一 主人之妻を殺者之類
一 主人之子を殺者之類
一 主人之娘を殺者之類並切付ル者之親類
一 主人を弑、致欠落者之請人之類附、主人を切付ル者宿仕者
一 主人に爲手負者之類並亂心之者
一 主人並妻子に慮外、附、手向者之類
一 主人に毒を飼致巧者之類
一 主人に脇指刀を拔、手向仕者之類並亂心者
一 主人之弟に致手向者並慮外仕、被切付、請人方え逃歸ル者
一 主人之甥を切付ル者並打擲仕者
一 古主を弑者
一 古主に爲手負者之類
一 古主に慮外仕者、附、脇指を拔、あたけ申者
一 父を弑者之類、同疵付る者之類並亂心之者
一 母を殺者之類、同打擲仕者、附、夫母を可殺と仕者之妻並亂心之者
一 酒狂にて祖母を切付る者
二 以下は、詳細省略
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
嚴牆集
一
二
元祿御法式
上 一―七〇
中 七一―一三三
下 一三四―一九八

2024.09.30発売
藩法史料集成
創文社オンデマンド叢書
江戸期の諸藩の法令をまとめた史料集である。
対象となる藩は、中村藩、新発田藩、和歌山藩、弘前藩、盛岡藩、亀岡藩、熊本藩、仙台藩、岡山藩である。
【目次】
序
解題
凡例
弘前藩
御刑法牒
盛岡藩
文化律
中村藩
罪案
新発田藩
新発田御法度書
御家中欽之覚
在中御条目
新令 二冊
新令取扱頭書
新律
徒罪規定書
名古屋藩
盗賊御仕置御定 二冊
寛政盗賊御仕置御定 附録
盗賊之外御仕置御定
和歌山藩
国律 乾
国律 坤
亀岡藩
議定書 乾
議定書 坤
熊本藩
御刑法草書 附例 上
御刑法草書 附例 中
御刑法草書 附例 下
仙台藩
刑法局格例調
岡山藩
新律

2024.09.30発売
初期キリスト教ラテン詩史研究
創文社オンデマンド叢書
ローマ時代、ギリシア文学の影響のもとに発展したラテン詩。なかでもキリスト教関連のラテン詩を選んで、その歴史を解説する。
【目次】
はしがき
第一章 初期キリスト教ラテン詩の起源
第一節 一~三世紀の原始キリスト教賛歌
一 一世紀の賛歌
二 二世紀の賛歌
三 三世紀の賛歌
第二節 原始キリスト教賛歌の問題
一 賛歌の類型
二 新約的なキリストへの賛歌の位置づけ
第三節 アフリカにおけるキリスト教ラテン詩の発生
一 キリスト教ラテン語発生の問題
二 アフリカにおけるキリスト教ラテン文学発生の問題
三 アフリカにおけるキリスト教ラテン詩発生の問題
第四節 最初のキリスト教ラテン詩人コンモディアヌス
一 コンモディアヌスの著作の日附の問題
二 コンモディアヌスの詩の文体的特色
三 コンモディアヌス以後の民衆詩の代表者アウグスティヌスの詩
第二章 キリスト教ラテン賛歌の先駆者たち
第一節 アンブロシウスの先駆者ヒラリウス
一 ヒラリウスの生涯と賛歌の写本
二 ヒラリウスの賛歌
第二節 アンブロシウス
一 アンブロシウスの生涯
二 アンブロシウスの賛歌
第三節 テ・デウムの問題
一 ニケタス説
二 カジンの説をめぐって
第三章 ある古典詩人とキリスト教詩人との友情
第一節 アウソニウス
一 アウソニウスの生涯
二 アウソニウスのキリスト教詩
三 アウソニウスとノラのパウリヌス
第二節 ノラのパウリヌス
一 ノラのパウリヌスの生涯
二 「殉教者の誕生日」論
第四章 キリスト教ラテン詩最大の詩人プルデンティウス
第一節 プルデンティウスの生涯
一 生涯
二 ローマ巡礼の意義
第二節 プルデンティウスと古典ラテン詩人たち
一 オウィディウスとプルデンティウスの詩「シュンマクス駁論」
二 ホラティウスとプルデンティウスの詩「日々の賛歌」
三 ウェルギリウスとプルデンティウスの詩
第三節 プルデンティウスのアレゴリー詩
一 キリスト教的アレゴリーの発生
二 「霊魂をめぐる戦い」におけるアレゴリー詩
結び
人名・書名索引

2024.09.30発売
救済史の神学
創文社オンデマンド叢書
長年にわたる著者の救済史研究をまとめたもの。牧師としての神学的実存をかけた、誤りに満ちた日本の神学への挑戦の書である。実存と歴史、実存と社会、主観と客観、科学と実践のギャップを超える「救済史の神学」を探究する。
【目次】
序
序論
第一部 主題と方法
第一章 神学的思惟の基礎概念
一 神学的思惟の問題点 二 その対象の秩序 三 釈義的思惟 四 批判的思惟 五 実践的思惟
第二章 救済史 その解釈と論争
一 神学における歴史の問題 二 神話と歴史 三 救済史 教会史と世界史 四 救済史をめぐる論争
第三章 救済史と世界史
一 両歴史の関連 二 救済史の現代史的地平 三 救済史のキリスト論的構造 四 救済史の例証
第二部 過程と展望
第四章 恩寵の選びと救済史
一 日本神学の未済の課題 二 救済史の始源 イエス・キリストの選び 三 教団の選びと異邦人問題
第五章 救済史の展望
一 現代神学における歴史と救済史 二 教義学の主題 救済史の線と方向 三 救済史の展望
第六章 摂理と歴史
一 歴史の意味 二 《歴史の目的》の登場 三 キリスト教歴史観の構造(1) 四 キリスト教歴史観の構造(2) 五 摂理信仰と世界観 六 摂理論と歴史観
第七章 イスラエルの民と諸民族
一 契約の民と自然の民 二 現代神学における民族論論争 三 救済史と民族史 四 聖書における民と諸民族
第八章 救済史の時
一 解釈学的方法論 二 時間論のアポリア 三 時間論の構造 四 救いの時
第九章 キリストとアダム 神学的人間学
一 神学における人間観の問題 二 キリストとアダム 三 救済史と人類史 四 人間構造論
第十章 救済史の成就
一 時の充満 二 イエスの実存と歴史 三 十字架の下に立つ人間 四 復活節の時と歴史
第十一章 救済史の認識
一 歴史と神学 現代神学の一争点 二 歴史認識の基本形式 三 パウロの回心
第十二章 未来学としての終末論
一 世界の未来 世俗的および聖書的終末論 二 世界の未来の天的背景(黙示録四章) 三 世界の未来の秘密を解く鍵
第三部 応用と展開
第十三章 現代における教会と世界
一 現代世界とキリスト教会 二 世界のなかの教会 三 救済史と’世界図式’ 四 世界のための教会
第十四章 世界宣教論
一 世界宣教の歴史的前提 二 世界宣教の神学的前提 三 世界宣教神学の提唱 四 《世界宣教神学》の諸課題
第十五章 人間形成論
一 人間形成の課題 二 福音と人間形成
第十六章 カルヴィン神学の現代的意義
索引

2024.09.30発売
バブーフとその時代 フランス革命の研究
創文社オンデマンド叢書
バブーフ(1760~1797)は、フランスの革命家・思想家である。彼は、私有財産制廃止を主張し、共産主義的独裁政権の樹立を目ざしてクーデタを企てるが、逮捕・処刑された。後のマルクス、ブランキらはバブーフの影響下にある。バブーフが登場した時代背景と彼の思想とフラン史革命の関係を詳細に探究する。
【目次】
目次
序論 バブーフ研究の意義と方法
一 フランス革命と陰謀
1 テーヌの革命観
2 オーラールの革命史 環境説の誕生
3 陰謀説か環境説か
二 フランス革命と社会主義
1 フランス社会主義の二つの流れ
2 フランス革命と社会主義
第一篇 バブーフの人間形成とフランス革命
一 バブーフの出自と初期の思想
1 家系・職業・環境
2 バブーフの初期の思想
二 初期の革命行動(一七八八―一七九四)
1 革命の勃発とバブーフ(一七八八・七―八九・一〇)
2 ピカルディにおける革命行動(八九・一〇―九二・八・一〇)
3 パリでの試煉(九二・八・一〇―九四・九)
三 テルミドール国民公会下におけるバブーフ
1 バブーフとテルミドール九日
2 バブーフとテルミドール反動
3 アラスの牢獄
第二篇 総裁政府時代の社会 バブーフの陰謀の前提
一 総裁政府時代の権力構造
1 憲法の制定とその基本的性格
2 中央における権力構造 立法・行政・司法各部の性格
3 地方における権力構造
二 総裁政府時代の国家財政
1 インフレーション下の社会の諸相
2 総裁政府の財政政策とアシニアの死滅
3 土地手形と国有財産の掠奪
第三篇 バブーフの陰謀事件
一 陰謀の発酵
1 総裁政府の政策と共和主義者の動向
2 バブーフの思想と左派共和主義者の団結
二 陰謀の組織と目的
1 陰謀の中核と細胞組織
2 革命のプロパガンダ 宣伝方法と組織
3 人民軍の創設
4 陰謀の目的と蜂起への歩み
三 陰謀の挫折とその反省
1 陰謀の挫折
2 革命裁判
3 挫折に対する反省
第四篇 バブーフの思想
一 バブーフの共産主義
1 歴史家達(マティエ、ルフェーブル、ゲラン)の見解
2 バブーフとロベスピエール
3 バブーフと共産主義について
二 バブーフと階級闘争
1 バブーフの階級国家観
2 バブーフの歴史的階級闘争観とその限界
結語
あとがき
参考文献
索引

2024.09.30発売
説教集 イエスは主なり
創文社オンデマンド叢書
教会の牧師であった著者による実際の説教をまとめたもの。
【目次】
まえがき
泥まみれの救い主 青木敬和
ただ、この一事のために 中村民男
もう一つの可能性 奥田和弘
東方で見た星 関田寛雄
神は恵みの主 佐竹 明
お言葉どおりに 川島貞雄
いと小さき者 荒井 献
虚無の克服 野呂芳男
イエスの見たもの 八木誠一
キリストのうちに自分を見いだす W・G・クレーラ
十字架の恵み 岩村信二
天に向かって開かれた窓 木田献一
「全き人」と「完全な人」 小田垣雅也
私について来なさい 井上洋治
美しき献げもの 大沼 隆
神の受容に応えて 金丸澄雄
ゆるし、そしてゆるされて 宮島新也
愛の業にはげむ教会 吉田良行
主が信じてくださるから 丹羽清治
人生の題名を 丹羽清治
別の基準 鈴木邦彦 青木敬和
鼎談 説教集「イエスは主なり」 関田寛雄 丹羽清治

2024.09.30発売
財政支出の経済分析(増補版)(数量経済学選書)
創文社オンデマンド叢書
「一言にしていえば、財政支出を厚生経済学的な観点から分析し、その分析を現実の財政支出の経済効率の評価にまで応用する」のが本書の狙いである。基本的に経済学は、市場メカニズム重視であるが、本書では公共経済学を扱い、その格好の入門書である。
【目次】
はしがき
第I部 財政支出の純粋理論
第1章 能力説の系譜とその再定式化
1 利益説と能力説の素朴な定義
2 能力説の多様化(1) ミルとエッジワース
3 能力説の多様化(2) ワグナー
4 能力説の多様化(3) ピグー
5 能力説の再定式化
第2章 利益説の系譜とその再定式化
1 イタリアにおける利益説の系譜 マツォーラとド・ヴィティ
2 北欧における利益説の系譜(1) ヴィクセル
3 北欧における利益説の系譜(2) リンダール
4 利益説の再定式化 サミュエルソンの公共財
5 能力説と利益説 再論
第3章 公共財の理論をめぐる問題
1 ストロッツの提言とその問題点
2 公共財と生産の分権化
3 初期の議論 超越的な批判とそれに対する反論
4 公共財の概念の再検討 最近の議論の検討
補論 公共支出の純粋理論からみた均衡予算の原則
第II部 財政支出の経済効率の評価 費用便益分析を中心に
第1章 便益費用評価の有効性
1 財政支出の分類
2 便益評価の仕方
3 便益評価の有効性
補論 公共財の存在とセカンド・ベストの問題
第2章 投資基準の問題
1 異時点間の資源配分における消費者主権
2 市場機構の不完全性
3 最適成長論におけるとり扱い
4 公共投資の割引率
5 公共投資の機会費用
第3章 宅地開発の費用便益分析 一つのケース・スタディー
1 費用便益比率
2 千里ニュー・タウン建設の費用便益分析
3 泉北ニュー・タウンの場合
4 おわりに
補論1 千里ニュー・タウンの開発費用
補論2 千里ニュー・タウン開発費用の費用負担について
補論3 費用便益表について
参考文献
索引

2024.09.30発売
興隆期のパクス・ブリタニカ 一つの歴史認識論
創文社オンデマンド叢書
ナポレオン戦争後から第一次世界大戦までの100年間、イギリスは「世界の工場」として、世界経済を牽引し、大英帝国として「世界の警察」として、世界平和を実現した。産業革命、資本主義の発展、海軍力と海運力で、英国はどうやって総人口4億人の大帝国を築くことができたのかを解き明かす。
【目次】
まえがき
第一章 第二代リヴァプール伯と自由貿易
第一節 経済観と政治システム
第二節 穀物法廃止の萌芽
むすび
第二章 リチャード・コブデンと自由貿易運動
はじめに
第一節「横の線のイメージ」の形成
一 パーソナリティ
二 アメリカ
三 ロシア
第二節 反穀物法協会(同盟)の成立
一 組織・運動
二 妥協
第三節 穀物法の廃止
一 最後の努力
二 勝利
(一)閣議
(二)議会
むすび
第三章 リチャード・コブデンとクリミア戦争
第一節 「自由放任」と平和
第二節 参戦の阻止
第三節 不干渉
むすび
第四章 リチャード・コブデンと英仏通商条約(一八六〇年)
第一節 背景
第二節 交渉
第三節 遅引
むすびにかえて 妥結
第五章 ジョン・ブライトと南北戦争
はじめに
第一節 状況と反応
第二節 トレント号事件
第三節 戦争と綿花
第四節 アラバマ号事件
むすび
第六章 グラッドストーンと植民地
第一節 植民地の保全 求心的イメージ
一 奴隷制
二 移民
三 自治
第二節 植民地の分離 遠心的イメージ
一 オーストラリア自治政府
二 自治植民地からのイギリス軍の撤退
むすびにかえて 求心的イメージの再現
第七章 サー・チャールズ・ディルクと英帝国
はじめに
第一節 イギリス・アメリカによる支配
第二節 遠心的イメージ
第三節 求心的イメージ
むすびにかえて 帝国統合のイメージ
あとがき
事項索引・人名索引
参考文献

2024.09.30発売
日本経済のモデル分析 国民経済計算からの接近
創文社オンデマンド叢書
数理経済学、計量経済学の手法で、経済主体と市場の関係を数理的なモデルに置き換えて理解するものである。大きく分けて、民間経済モデル、国民経済モデル、国際経済モデルがあり、マクロ経済学の一ジャンルである。本書は、このモデル分析で、日本の経済を解き明かす。
【目次】
まえがき
序章
国民経済計算とモデル分析 本書の構成
第1章 国民経済計算の基本的構造
1.1 国民経済の一般均衡論的枠組
需給均衡式と予算制約式 生産における分配式(物的資本への帰属式)
1.2 国民所得統計の要約
6基本勘定と三面等価の原則 国民所得と国富
1.3 要約と結論
付論 国連新SNAの概要
第2章 マクロ生産性の計測 1952~1971年
2.1 集計問題I(部門集計)
投入・産出体系から正統化されたマクロ生産性 生産可能曲線から正統化されたマクロ生産性 説明されない産出成長の部分
2.2 集計問題II(生産要素・産出物集計)
2.3 民間・政府企業統合部門の生産勘定
生産額=要素所得 産出の価格と量 要素所得=投入サービスの価値 投入資本の価格と量 投入労働の価格と量 付論・耐久消費財に関するデータ
2.4 民間・政府企業統合部門の生産性
ディビジア生産性指数 資本・労働・産出の質指数 成長のソース分析 資本に体化した技術進歩
2.5 要約と結論
第3章 民間諸勘定の統合体系 1952~1971年
3.1 生産・所得・貯蓄
生産と要素支払 所得と支出 要素支払対所得 労働支払(労働所得)の価格と量 資本支払(財産所得)の価格と量 生産対支出
3.2 蓄積・再評価・富
蓄積(貯蓄・資本形成)と再評価 民間国富 要約的指標
3.3 要約と結論
第4章 計量モデルとシミュレーション分析 1952~1980年
4.1 新古典派成長論タイプの計量経済モデル
モデルの構造 生産函数 モデルの適合度(goodness of fit)
4.2 シミュレーション分析I(財政政策)
静学および動学の弾性値 成長モデル対有効需要モデル
4.3 シミュレーション分析II(予測)
外生変数とパラメーター値の選択 成長潜在力の長期的(新古典派成長論的)分析
4.4 要約と結論
付論 援助のTwo-Gap分析について
A.1 チェネリー=ストラウト・モデルの特質
A.2 社会的厚生の最大化
A.3 要約と具体例
参考文献
人名索引

2024.09.30発売
日本法制史における不法行為法
創文社オンデマンド叢書
故意または過失によって他者に損害を与えるのが、「不法行為」である。日本の法において、不法行為と捉えられる行為がどのように変遷してきたのかを跡づけるものである。
【目次】
緒論
第一編 記紀・古風土記における不法行為法
第一章 贖(アガナフ)と償(ツグナフ)
第二章 記紀・古風土記に見える贖銅制
第二編 律令法における不法行為法
第一章 律令法の条文解釈について
第二章 律令法における過失法
第三章 贓及び自首と不法行為法
第四章 廐庫律における不法行為法
第五章 雑律における不法行為法
第六章 結論
第三編 武家法における不法行為法
第一章 武家法における不法行為法と律令法(公家法)
第二章 武家法における不法行為法の成立
第三章 御成敗式目における不法行為法
第四章 分国法(戦国諸家法)における不法行為法
第四編 徳川幕府法における不法行為法
第一章 徳川幕府法における不法行為法の成立
第二章 徳川幕府法における不法行為法
第三章 徳川幕府判例法における不法行為法
第五編 現行不法行為法の史的発展
第一章 権利侵害と違法性の史的発展
第二章 民事責任と刑事責任の史的発展
第三章 不法行為責任と契約責任の分化発展
第四章 損害賠償請求権の史的発展
第五章 故意過失の史的発展
第六章 不法行為法と時効制の成立

2024.09.30発売
徳川幕府と中国法
創文社オンデマンド叢書
武家諸法度、公事方御定書など江戸時代の幕府が定めた法や裁判の運営の際の基準が、中国の法律とどのような関係にあったかを探究する。
【目次】
はじめに
第一 白石の勉強のやりかた
第二 白石と人の記憶力
第一編
第一 我が国において刊行されたる明・清法制書目 序
第二 我が国において刊行されたる明・清法制書目
第三 我が国において刊行されたる明・清法制書目 続編
第二編
第一 徳川家康と明律
第二 吉宗と御定書並びに明・清律例
一 吉宗と御定書
二 吉宗と明律(御定書と明律)
三 吉宗と大清会典
第三 新井白石と明・清法制書目(附 通典・文献通考・通雅・東雅・経邦典例・明律・明律例等)
序論
一 新井白石の性向乃至学風
二 白石の学識(経邦典例等の関係)について
本論一 「新井白石日記」に見える明・清法制関係書目
一 「新井白石日記」の刊行
二 「新井白石日記」に見える白石が幕府より借用したる明・清法制関係書目
三 通典類
四 文献通考・続文献通考類
五 九通・十通
六 文献通考の註釈本
本論二 「新井白石日記」に見える明・清法制関係書目 続編
一 明律
二 明・清律例の註釈本
三 新井白石と大明集礼・大明会典
四 新井白石と大唐六典
第四 大唐六典・大明会典・大清会典について(吉宗・白石と大唐六典・大明会典・大清会典)
一 吉宗と大唐六典・大明会典・大清会典
二 大唐六典・大明会典・大清会典の歴史的考察
三 大明会典と大清会典(諸官衙の構成)
第五 新井白石について
一 新井白石に対する諸家の見解
二 諸家の見解に対する論評
三 追記
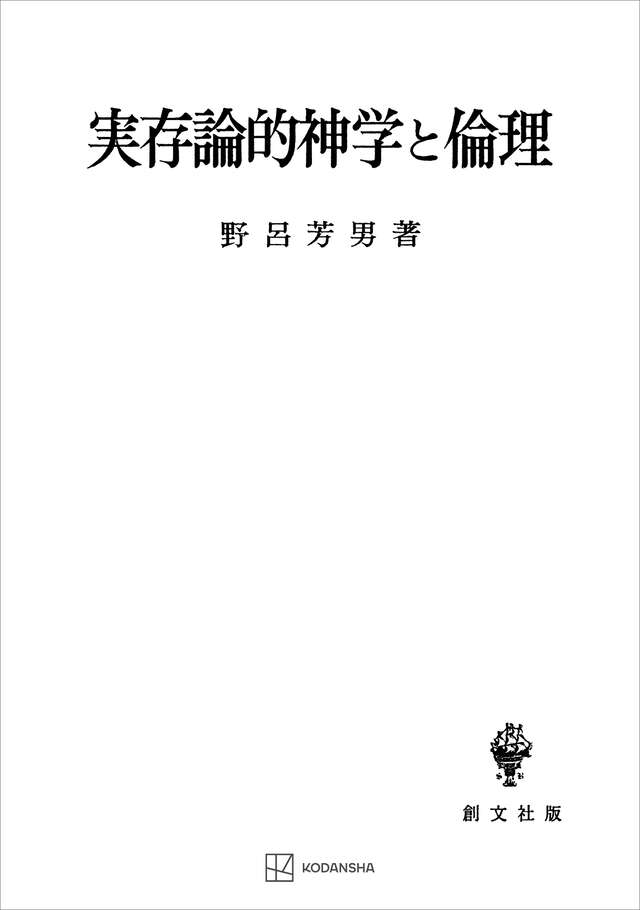
2024.09.30発売
実存論的神学と倫理
創文社オンデマンド叢書
四つの論文から構成される。
本書の第一章「実存論的神学の展開方向」ではキリスト論を中心に論じる。第二章「神の死と実存論的神学」は、聖霊論を媒介にして神観を記述することで、著者の立場が明らかにされる。
第三章「神学と倫理」は実存論的神学を基礎する宿命倫理の構築を試みる。その際、援用されるのが、アメリカの自由主義神学者ニーバー(1892~1971)の思想である。第四章「ラインホルド・ニーバーの政治思想」では、ニーバーの思想を肯定的に叙述する。
キリスト教的な新しい倫理を模索する著作である。
【目次】
第一章 実存論的神学の展開方向
一 実存論的神学と弁証法的神学
二 実存と体験
実存論的神学と存在論、及びエーベリングの言葉の出来事 啓示と実存 実存論的神学と実存主義 その両者の話合いの可能性
三 史的イエスと信仰のキリストの問題についてのバルトの理解
四 マイケルソンの歴史としての神学
五 実存論的神学と神秘
イエスの服従 愛
第二章 神の死と実存論的神学
一 ニーチェ
二 ヴァン・ビューレン
ウィトゲンシュタインの言語ゲーム
三 ヴァン・ビューレン批判
四 ティーリケのニヒリズム批判
信仰とニヒリズム 不条理 コックスの非聖の都会の容姿と次元的思考 西谷啓治 ヴァハニアン 倫理についての二つの推論
五 聖霊論
第三章 神学と倫理
一 ブルトマンの新約の倫理
二 シュヴァイツァーの生への畏敬と倫理
三 バルトの倫理
四 ポール・レーマンの倫理
レーマンとジョン・ベネット 良心 ジョセフ・フレッチャーの倫理 フレッチャーのR・ニーバー批判
五 歴史と自然
第四章 ラインホルド・ニーバーの政治思想
一 ニーバーの政治思想について
二 ニーバーのエーリッヒ・フロム批判
三 ニーバーの共産主義批判
四 ニーバーの社会集団論
五 アジア・アフリカ諸国とデモクラシー
ハミルトンのニーバー批判
六 宗教的社会主義の問題
七 平和主義の問題
あとがき
事項・人名索引

2024.09.30発売
近代日本経済史(現代経済学選書) パックス・ブリタニカのなかの日本的市場経済
創文社オンデマンド叢書
近世社会の多重国家体制の下で残された財産目録を丹念に分析し、中央集権国家への転換に見られる連続緒非連続の両面を総合的に考察するとともに、パックス・ブリタニカへの参入から第二次大戦の破局にいたる1世紀におよぶ経済社会の展開を解明した第一級の概説。
新しい市場社会のための法制度や経済共通基盤の整備、その時々の産業政策やマクロ経済など、日本型市場社会の形成に関わるさまざまな営為を、膨大な史料と最新の研究成果により実証的に分析する。社会史的な支店も導入して独自の歴史叙述を実現した本書は、今日における経済史研究の到達点を示すものに他ならない。
冷戦構造崩壊のさなかに身を置き〈日本近代〉の等身大の自画像を描こうとする著者の情熱は、経済学の分野をこえて人文・社会諸科学の研究者、そしてわが国の市場社会に関心を寄せる読者に共通理解の場を提供するとともに、定量分析のあり方など今後の社会研究に対しても多くの示唆を与えよう。
【目次】より
第I部 「開放体系」への移行 1859-90年
1 19世紀前半の日本経済 開港に際しての初期条件
2 開港と「価格革命」 外からの衝撃
3 近代国家の形成 多重国家体制から単一国家体制へ
4 工業化のための制度的枠組の形成 経済共通基盤の整備
5 近代経済発展の始動 在来部門の成長と再編成
第II部 工業化の始動と展開 1891-1913年
1 パックス・ブリタニカへの参入 日本の対内・対外経済政策
2 近代工業の発展 二つのリーディング・セクター,紡績業と造船業
3 工業化を支えたもの 貿易と技術移転
4 工業化の担い手 企業家・技術者・労働者
5 工業化と小規模家族農業 農業部門と非農業部門の関係
第III部 戦争景気から「慢性的不況」へ 1914-31年
1 動揺する世界政治・経済秩序と日本経済 第一次世界大戦から世界恐慌へ
2 工業化の新しい局面 動力革命と重化学工業化
3 金融再編成と産業合理化 大企業体制の成立
4 農業の停滞と不均衡成長 二重構造
5 都市化の進展と大衆社会化への動き 都市の変貌と生活様式の変化
IV部 戦争と統制経済の展開 1932-45年
1 国際金本位制の終焉 パックス・ブリタニカの解体と日本の孤立化
2 管理通貨体制下での景気転換 経済成長のメカニズム
3 15年戦争の開始と重化学工業化の進展 産業構造の変化
4 統制経済の展開 市場経済の変容
5 戦争拡大と日本経済の破局 太平洋戦争から敗戦へ
参考文献
あとがき
年表
索引

2024.09.30発売
国民経済計算(現代経済学選書)
創文社オンデマンド叢書
ある国の、生産・消費・投資等のフローと資産・負債等のストック面を体系的に記録し、その国の経済状態を示す。GDP(国内総生産)はその代表的な指標のひとつである。本書は、マクロ経済学の基礎的な理論と実践を理解するための格好の手引きである。
【目次】
まえがき
一 フロー表
1 経済的数量の記録 2 生産勘定 3 所得支出勘定 4 資本調達勘定 5 貯蓄と投資の均等 6 問題 7 研究の手引き
二 国民貸借対照表
1 フロー量とストック量 2 調達勘定 3 統合勘定(国民貸借対照表) 4 問題 5 研究の手引き
三 産業連関表
1 多数の財・サービスを扱う勘定体系 2 2産業の産業連関表 3 多産業の産業連関表 4 国民経済的視点 5 新SNAと数量経済学の課題 6 問題 7 研究の手引き
四 計量経済学
1 計量経済学的実証研究の例示 2 計量経済学 3 マクロ・エコノメトリック・モデル 4 日本のマクロ・エコノメトリック・モデル 5 問題 6 研究の手引き
〔略〕
八 経済成長の要因分析
1 日本経済の経済成長 2 成長会計による要因分析の方法 3 計量経済学による要因分析の方法 4 成長会計による要因分析の結果 需要面 5 成長会計による要因分析の結果 供給面 6 計量経済学モデルによる要因分析の結果 需要要因 7 計量経済学モデルによる要因分析の結果 供給要因 8 成長の阻害要因 9 問題 10 研究の手引き
九 景気循環
1 好況と不況 2 景気変動の原因 3 最近の景気変動のパターン 4 為替レートと貿易収支 5 Jカーブ効果 6 為替レートと景気循環 7 問題 8 研究の手引き
十 産業構造の変化
1 産業構造:第1,2,3次産業 2 産業構造:製造業 3 産業連関分析 4 産業構造の変化の要因分析(1):方法 5 産業構造の変化の要因分析(2):実証的結果 6 多部門経済モデルへの道(1):生産物市場 7 多部門経済モデルへの道(2):資産市場 8 研究の手引き
十一 国民経済計算に関する補足
1 国際経済に関する勘定 2 銀行部門に関する勘定 3 政府部門に関する勘定 4 対家計民間非営利団体に関する勘定 5 国民経済計算におけるデフレータ 6 問題 7 研究の手引き
十二 産業連関表補論
1 生産者価格表と購入者価格表 2 部門分類と副産物・屑の取扱い 3 輸出・輸入の取扱い 4 家計外消費 5 新SNA方式による産業連関表
文献
問題解答
索引

2024.09.30発売
一般均衡と価格(数量経済学選書)
創文社オンデマンド叢書
多数の財が取引される市場で、需要と供給、価格が決まるメカニズムを考察する一般均衡理論は、レオン・ワルラスが19世紀に創始した。その後、パレートがその理論を発展させ、20世紀半ばより整合的な価格分析の方法となった。一般均衡理論を理解するための格好の入門書。
【目次】
はしがき
第1章 経済循環図式
1 企業の経済活動
2 家計の経済活動
3 政府の経済活動
4 市場における財およびサービスの取引
5 国民所得勘定と産業連関表
第2章 消費関数の計測
1 消費者需要の理論
2 個別消費関数の計測
3 総消費関数の計測
4 個別産業に対する消費需要
第3章 生産理論の計測
1 生産者行動の理論
2 生産関数の計測
3 技術進歩率の計測
第4章 一般均衡モデルの計測
1 一般均衡理論
2 輸入関数
3 賃金決定方程式
4 財産所得方程式
5 計測された一般均衡モデル
第5章 比較静学
1 比較静学の理論
2 価格の変動
3 粗代替性・安定条件
4 雇用の変動
5 生産量の変動
6 国民所得の変動
第6章 実証的多部門経済モデルの比較
1 実証的多部門経済モデル
2 消費の内生化
3 コブ・ダグラス型生産関数
4 生産量の決定
5 価格の決定
第7章 一般均衡理論の実証性
1 価格変化に関するテスト
2 雇用の変化に関するテスト
3 生産量の変化に関するテスト
4 消費の変化に関するテスト
5 総括
第8章 価格変動の諸要因
1 価格形成と需要・供給・輸入
2 価格政策への応用
補論 クロス・セクション・データによる貯蓄関数の計測
1 序
2 予備的考察
3 方法上の問題点
4 所得効果と流動資産効果
5 所得効果の非線型性
6 年齢効果
7 過去の消費の影響
8 分布ラッグの推定
9 所得変動の影響
10 結論
付録A 統計データの出処および単位
付録B 産業連関表関係のデータ作成法
付録C 補論の統計データの出処
付録D 統計データ
引用文献
人名索引
事項索引

2024.09.30発売
蟻の歌(フォルミカ選書)
創文社オンデマンド叢書
ラブレー研究で知られるフランス文学研究者・評論家であった著者による、随想集である。
【目次】
本郷三丁目
若い地質學者の變身
春日抄
「さぼてん」と僕
昔噺
羊の寓話
『櫻の園』を觀て
僕の芝居見物
『天井棧敷の人々』を觀て
『處女オリヴィヤ』を觀て
貝殻追放について
宿命とは因果律だといふことなど
「たまらん」こと
恐怖のドン底から
もつと先にしてほしいこと
感想一つ二つ
文化會長になつた僕
『インテリは生きてゐられない』を讀んで
所見
フランス人の言語教育
放言二つ三つ
フランス文學の流行は不十分である
アンドレ・ジードの死
感想的解説(『風俗小説論』を讀んで)
感想的解説(『晩歌』を讀んで)
フランス・ルネサンス文學について
後記

2024.09.30発売
刑法紀行
創文社オンデマンド叢書
法学者・団藤重光による刑法をめぐってさまざまな場所や裁判などに遭遇したことを記したエッセイで、日本エッセイスト・クラブ賞を受賞した(1967年)。
【目次】
イタリア通信
イタリアの刑法教授の生活
ユーゴースラヴィアの三日間
ドイツ便り
オーストリアとスイスの旅
北欧の旅
イギリスの旅
オランダとベルギー
スペインとポルトガルのおもいで
ヨーロッパの矯正施設
北欧の矯正施設
フランスの矯正施設
アメリカのガス死刑と電気死刑
キャリフォーニアの医療矯正施設
カナダとメキシコの旅
アラブの国々を訪ねて
ソヴィエト旅行記(一九六五年)
ソヴィエト旅行記(一九六六年)

2024.09.30発売
超越に貫かれた人間(長崎純心レクチャーズ) 宗教哲学の基礎づけ
創文社オンデマンド叢書
第6回長崎純心レクチャーズとして2002年に行った3日間の講演を再現。イエズス会神父であり卓越した哲学者であるリーゼンフーバー教授が、神学者、神秘思想家らとの対話を通じて導かれた「超越に貫かれた人間」の真実を語る。
人間は不可避的に問う存在である。自分自身の存在、根拠、意義を問うとともに世界の真理、意義、幸福をも探究する。人間の問いそのもののうちには、無制約的なもの、すなわち超越への開きが含まれているのである。知ることはなぜ可能か。人間はいったい何を経験するのか。この追究をとおして宗教性が人間の本質に深く根づいていることを確認し、人間と超越との関係を、超越に関わられ貫かれる人間という受動的観点から解明、さらに宗教的行為の基本構造へと考察を進め人間の存在と使命を浮き彫りにする。西洋中世哲学研究者として知られる著者が、長年の研究と思索の間に親しんだ哲学者、神学者、神秘思想家との対話にもとづき、磨かれた言語で宗教哲学の根本的考え方を明解にとく講演。
【目次】
「長崎純心レクチャーズ」について 片岡千鶴子
序言 稲垣良典
第一日 人間存在に見られる無制約性 未規定性と尊厳の間に
一 全体の問題提起
1 問題としての超越理解 2 人間からの出発
二 人間の予備概念
1 欠如性・未規定性と理性 2 個人の尊厳における無制約的なもの
三 超越への問いの精神論的可能根拠
1 自己意識と存在認識 2 像としての人間
四 精神における超越への本質的な関わり
1 問い 2 知識の要としての真理
第二日 超越経験の根本理解と諸形態 日常を意義づける無制約的なもの
一 精神的経験
1 経験の哲学的概念 2 感覚的経験と精神の経験 3 説明と理解 4 純粋な完全性の経験
二 聖書的信仰の地平のなかに見られる超越経験
1 神経験と神認識 2 感覚と存在把握 3 感覚を通して描かれる神経験 4 超越との関わりを示すいくつかのトポス
三 日常における潜在的超越経験
1 意義の発見 2 現実の承認 3 芸術的創造性における賛美 4 導きに対する信頼 5 責任における対面 6 当為の定言制 7 時間の贈り物と可能性における呼びかけ
四 意義の経験と神との出会い
第三日 宗教的行為の成立 自己実現としての脱自
一 宗教的行為の構造
1 人格的行為 2 無力と、超越による根拠づけ 3 受容と自発性 4 離脱と脱自 5 無制限の肯定と自己譲渡 6 合一と対話性 7 日常性と究極性 8 個人性と共同性
二 根本的宗教的行為の諸形態
1 言葉としての現実と神現としての根源語 2 超越への傾聴 3 黙想 4 祈り 5 信仰
あとがき