
マイページに作品情報をお届け!
ドグラ・マグラの世界/夢野久作 迷宮の住人
ドグラマグラノセカイユメノキュウサクメイキュウノジュウニン
- 著: 鶴見 俊輔

巻頭に置かれるのは、夢野久作が読書界から顧みられることのほとんどなかった1962年に鶴見俊輔が雑誌「思想の科学」に発表した「ドグラ・マグラの世界」である。この評論により、日本の戦後期には忘れられた存在となっていた夢野久作は「再発見」される。
「ドグラ・マグラの世界」の発表がきっかけとなり、鶴見と夢野久作の長男である杉山龍丸の交流が生ずる。やがて杉山龍丸の著書や杉山が編纂した夢野久作の日記などを資料としてじゅうぶんに咀嚼したうえで、鶴見は夢野久作論『夢野久作 迷宮の住人』を執筆する。
夢野久作について少年期の鶴見俊輔が出会った夢野久作の『犬神博士』の紹介から、『夢野久作 迷宮の住人』の第一部は始まる。そして『氷の涯』という日本軍のシベリア出兵をモチーフにした作品、さらに異色の長篇推理小説『ドグラ・マグラ』へ。そして、これらの作品が昭和初期の読者にどのように受けとめられたのかと問いが生まれる。
第二部では作家夢野久作の本名である杉山泰道の側からその生涯が辿られる。泰道の伝記的事実の多くは、さらにその長男杉山龍丸の著書によるが、伝記的事実と時代背景を結びつけて読み解くことで、より作品世界に深くわけ入ることができる。
第三部では、夢野作品受容の変遷が綴られる。江戸川乱歩ほか同時代の探偵作家たちにはやはり異形のものとして解されている。しかし年少の読者だった福永武彦や中井英夫たちには強烈な印象が残っていた。敗戦後、占領期に夢野久作が思いおこされることはなかったが、1960年を境にふたたび関心が寄せられるようになり、作品研究・分析が進む。そこで見えてきたものは、中央から遠い地方で、土地の日常言語を駆使して人間の根本問題に迫る、きわめて独創的な作家の姿であった。
本書により、夢野久作というきわめて独自性に満ちた作家に多角的に光が当てられ、読者にとってもそのイメージが鮮明となることが期待される。
- 前巻
- 次巻
オンライン書店で購入する
目次
目次:
ドグラ・マグラの世界
夢野久作 迷宮の住人
はじめに
第一部 夢野久作の世界
第二部 杉山泰道の生涯
第三部 作品の活動
あとがき
夢野久作年譜
解説 安藤礼二
書誌情報
紙版
発売日
2024年01月15日
ISBN
9784065342688
判型
A6
価格
定価:2,200円(本体2,000円)
ページ数
288ページ
シリーズ
講談社文芸文庫
電子版
発売日
2024年01月12日
JDCN
06A0000000000749850K
初出
本書は『鶴見俊輔書評集成1 1946-1969』(2007年7月、みすず書房刊)と『鶴見俊輔集・続 3 高野長英・夢野久作』(2001年2月、筑摩書房刊)を底本としました。
著者紹介
鶴見俊輔(1922・6・25~2015・7・20) 哲学者。東京生まれ。15歳で渡米しハーバード大学で学ぶ。在米中にアナキスト容疑で逮捕されたが、留置所で論文を書き上げ卒業。交換船で帰国。戦後、丸山眞男らと「思想の科学」を創刊。京都大学、東京工業大学、同志社大学で教鞭を執る。70年、警官隊導入に反対して同志社大学教授を辞任。著書に『鶴見俊輔集』全12巻・続全5巻(筑摩書房)、『鶴見俊輔座談』全10巻(晶文社)ほか多数。稀代の読書家として文芸評論や書評も多く執筆。82年に『戦時期日本の精神史』で大佛次郎賞、90年に『夢野久作 迷宮の住人』で日本推理作家協会賞、94年に朝日賞、2007年に『鶴見俊輔書評集成』全3巻で毎日書評賞をそれぞれ受賞した。講談社文芸文庫の既刊として、埴谷文学と『死霊』論を集大成した『埴谷雄高』がある。
オンライン書店一覧
関連シリーズ
-
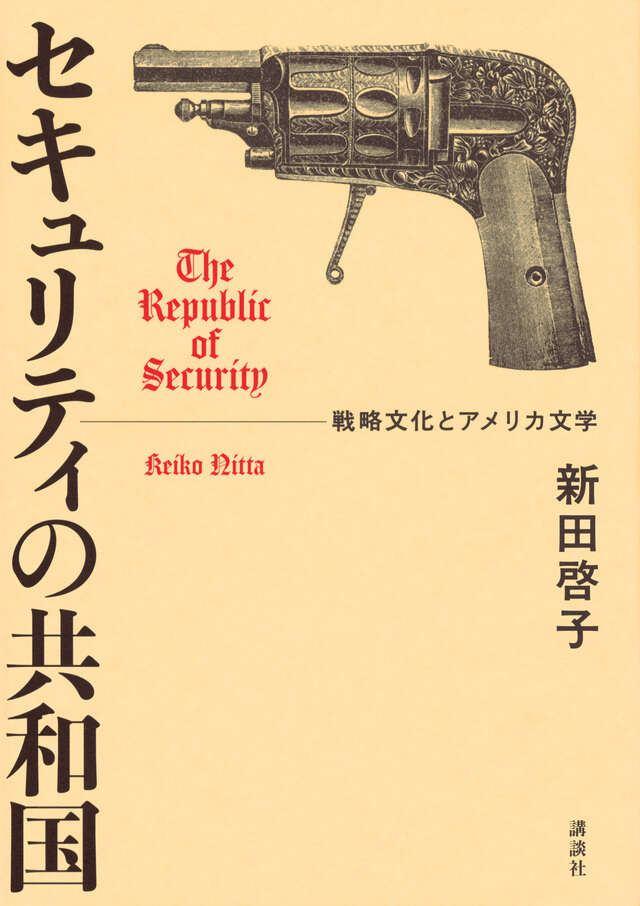
セキュリティの共和国 戦略文化とアメリカ文学
-

文学を探せ
-

文学ノート*大江健三郎
-

系譜なき難解さ 小説家と批評家の対話
-

ほんとうのカフカ
-

新旧論
-

チャンドラー講義
-

『別れる理由』が気になって
-

文学のエコロジー
-

二つの東京物語
-

事務に踊る人々
-

柄谷行人の初期思想
-

春秋の花
-

小説の未来
-

藍色の福音
-

羊のレストラン
-

一冊に名著一〇〇冊がギュッと詰まった凄い本
-

薄れゆく境界線
-

ウェブ小説30年史 日本の文芸の「半分」
-

大江健三郎の「義」
-

日本探偵作家論
-

今日よりもマシな明日 文学芸能論
-

大江健三郎と「晩年の仕事」
-

クヌギ林の妖怪たち 童話作家・富安陽子の世界
-

慶応三年生まれ 七人の旋毛曲り
-

新古今の惑星群
-

それを小説と呼ぶ
-

人間とは何か 偏愛的フランス文学作家論
-

村上春樹の世界
-

私の『マクベス』
-

詩とは何か
-

石坂洋次郎の逆襲
-

生きつづけるキキ ひとつの『魔女の宅急便』論
-

異邦の香り ネルヴァル『東方紀行』論
-

花づとめ
-

與謝蕪村
-

山本健吉 柿本人麻呂
-

事実と創作
-

わがスタンダール
-

イロニアの大和
-

変身放火論
-

小林秀雄の悲哀
-

この百年の小説 人生と文学と
-

物語批判序説
-

スカトロジア(糞尿譚)
-

志賀直哉私論
-

芥川龍之介と太宰治
-

立原道造の世界
-

作家は行動する
-

日本人の自伝
-

自伝の世紀
-

日本の文学論
-

読書の極意と掟
-

新美南吉の世界
-

現代詩人論
-

大衆文学論
-

大江健三郎柄谷行人全対話
-

「文学の言葉」を恢復させる
-

歴史小説の懐
-

小林秀雄と中原中也
-

筒井康隆入門
-

新しい小説のために
-

文芸的な、余りに文芸的な/饒舌録 ほか
-

乱歩と正史
-

現代詩試論/詩人の設計図
-

写生の物語
-

柄谷行人インタヴューズ
-

成熟と喪失 “母”の崩壊
-

世界の読者に伝えるということ
-

神々の闘争 折口信夫論
-

光の曼陀羅 日本文学論
-

テクストから遠く離れて
-

「私小説」を読む
-

恋と日本文学と本居宣長・女の救はれ
-

堀辰雄覚書・サド伝
-

柄谷行人蓮實重彦全対話
-

柄谷行人中上健次全対話
-
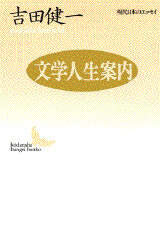
文学人生案内
-

文学概論
-

文学の楽しみ
-

文学のプログラム
-

風俗小説論
-

反文学論
-

俳人蕪村
-

日本浪曼派批判序説
-

二葉亭四迷伝
-

内部の人間の犯罪 秋山駿評論集
-

東西文学論・日本の現代文学
-

転々私小説論
-

中原中也
-

対談・文学と人生
-

対談 文学の戦後
-

折口信夫文芸論集
-

正宗白鳥 その底にあるもの
-

常識的文学論
-

小林秀雄全文芸時評集
-

江藤淳 小林秀雄
-

女の子を殺さないために解読濃縮還元100パーセントの恋愛小説
-

書物の解体学
-

坂口安吾と中上健次
-

斎藤茂吉ノート
-

近代日本の批評
-

畏怖する人間
-

意味という病
-

われもまた おくのほそ道
-

マス・イメージ論
-

ハイスクール・ブッキッシュライフ
-
アレゴリーの織物
-

1946・文学的考察
-

日本近代文学の起源

















