
マイページに作品情報をお届け!
ウェブ小説30年史 日本の文芸の「半分」
ウェブショウセツサンジュウネンシニホンノブンゲイノハンブン
- 著: 飯田 一史

文芸市場の「半分」を占めるまでに成長した、ウェブ小説の歴史。
多くの人がウェブ小説に漠然とした印象を持ってはいる。しかしその歴史を扱った書物はほとんどない。2022年現在、世間的には、ウェブ小説といって真っ先に思い浮かぶものは「なろう系」「異世界転生」というイメージだろう。実際にはウェブ小説は、1990年代には「分岐する物語」「集団創作」志向を持ち、「自費出版」「ケータイ小説」などのかたちでも展開、小説家になろうや他の思想の異なる「ウェブ小説投稿サイト」の隆盛といった数多の試みと多様化を経て現在に至る。本書は「ウェブ小説の書籍化の歴史」を主に扱う。今や日本の文芸市場の「半分」を占めるまでに成長したウェブ小説の歴史を、ネットビジネス史と出版産業史的な視点から紐解く。
*以下、本書目次より抜粋
はじめに
第1章 1990年代ウェブ小説の書籍化
―分岐・集団創作・マルチメディアの夢
第2章 2000年代前半のウェブ小説書籍化
―自費出版・掲示板文化・ガラケーサイト
第3章 2000年代後半
―第二次ケータイ小説ブーム
第4章 2000年代年代後半
―アルファポリス、エブリスタ、小説家になろう
補章 2000年代までの隣国のウェブ小説動向
第5章 2010年
―初の異世界転生書籍化と「ウェブから書籍へ」の流行の波及
第6章 2011年
―「新人賞からウェブ投稿へ」という投稿先変化の萌芽
第7章 2012年
―なろう系文庫レーベルと複数のテキスト系サービスの出現
第8章 2013年(1)
―MFブックス、ビリギャル、櫻子を当てたKADOKAWA
第9章 2013年(2)
―多様化する女性向けウェブ小説と出版社系サイト/電子小説誌の苦戦
第10章 2014‐2015年
―なろう系がラノベになり、ライト文芸にウェブ発が合流する
第11章 2016‐2018年(1)
―なろうダイジェスト版禁止、成年向けと児童への広がり
第12章 2016‐2018年(2)
―SFと純文学におけるウェブ小説書籍化の明暗
第13章 2019‐2022年
―日本式の「ウェブ小説書籍化」は終わらない
おわりに
ⒸIchishi Iida
- 前巻
- 次巻
オンライン書店で購入する
書誌情報
紙版
発売日
2022年06月22日
ISBN
9784065284049
判型
新書
価格
定価:1,980円(本体1,800円)
通巻番号
223
ページ数
560ページ
シリーズ
星海社新書
電子版
発売日
2022年06月21日
JDCN
06A0000000000524204U
初出
本書は、Webサイト「monokaki」(https://monokaki.ink/)での連載「Web小説書籍化クロニクル」を、改稿、加筆修正して出版したものです。
著者紹介
ライター。1982年青森県むつ市生まれ。中央大学法学部法律学科卒。グロービス経営大学院経営研究科経営専攻修了(MBA)。出版社にてカルチャー誌や小説の編集者を経て、独立。マーケティング的視点と批評的観点からウェブカルチャー、出版産業、子どもの本、マンガ等について取材、調査、執筆している。単著に『いま、子どもの本が売れる理由』『ウェブ小説の衝撃』(筑摩書房)『マンガ雑誌は死んだ。で、どうなるの?』(星海社)『ライトノベル・クロニクル2010ー2021』(Pヴァイン)など。
オンライン書店一覧
関連シリーズ
-

文学ノート*大江健三郎
-
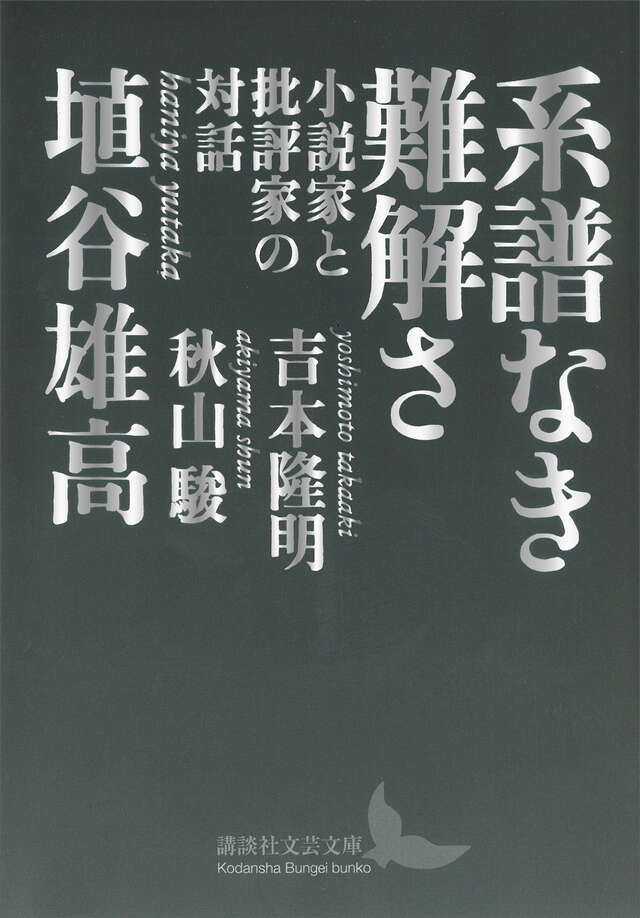
系譜なき難解さ 小説家と批評家の対話
-

ほんとうのカフカ
-

新旧論
-

チャンドラー講義
-

『別れる理由』が気になって
-

ドグラ・マグラの世界/夢野久作 迷宮の住人
-

文学のエコロジー
-
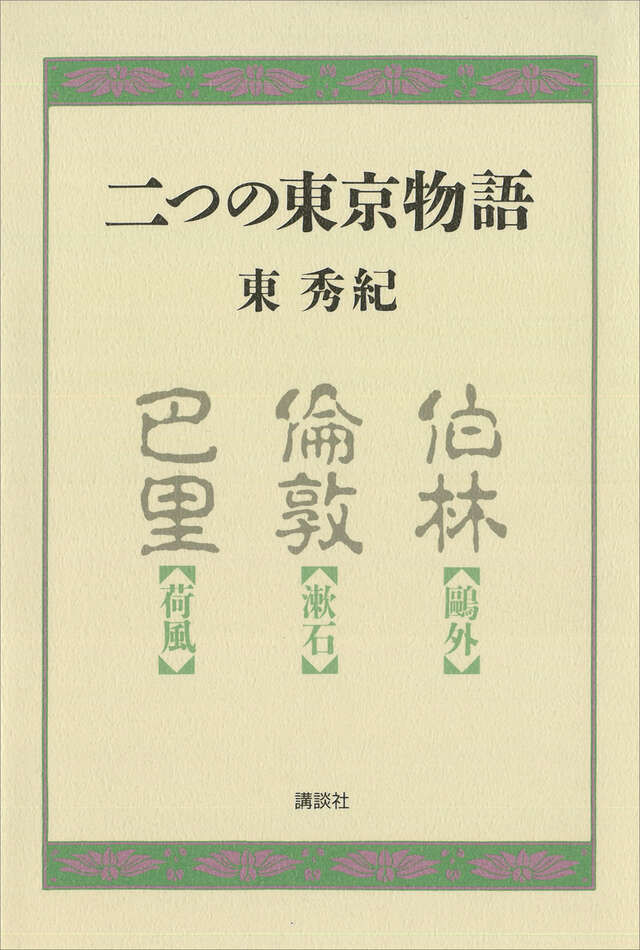
二つの東京物語
-

事務に踊る人々
-

柄谷行人の初期思想
-

春秋の花
-

小説の未来
-

藍色の福音
-

羊のレストラン
-

一冊に名著一〇〇冊がギュッと詰まった凄い本
-

薄れゆく境界線
-

大江健三郎の「義」
-

日本探偵作家論
-

今日よりもマシな明日 文学芸能論
-

大江健三郎と「晩年の仕事」
-

クヌギ林の妖怪たち 童話作家・富安陽子の世界
-

慶応三年生まれ 七人の旋毛曲り
-

新古今の惑星群
-

それを小説と呼ぶ
-

人間とは何か 偏愛的フランス文学作家論
-

村上春樹の世界
-

私の『マクベス』
-

詩とは何か
-

石坂洋次郎の逆襲
-

生きつづけるキキ ひとつの『魔女の宅急便』論
-

異邦の香り ネルヴァル『東方紀行』論
-

花づとめ
-

與謝蕪村
-

山本健吉 柿本人麻呂
-

事実と創作
-

わがスタンダール
-

イロニアの大和
-

変身放火論
-

小林秀雄の悲哀
-

この百年の小説 人生と文学と
-

物語批判序説
-

スカトロジア(糞尿譚)
-

志賀直哉私論
-

芥川龍之介と太宰治
-

立原道造の世界
-

作家は行動する
-

日本人の自伝
-

自伝の世紀
-

日本の文学論
-

読書の極意と掟
-

新美南吉の世界
-

現代詩人論
-

大衆文学論
-

大江健三郎柄谷行人全対話
-

「文学の言葉」を恢復させる
-

歴史小説の懐
-
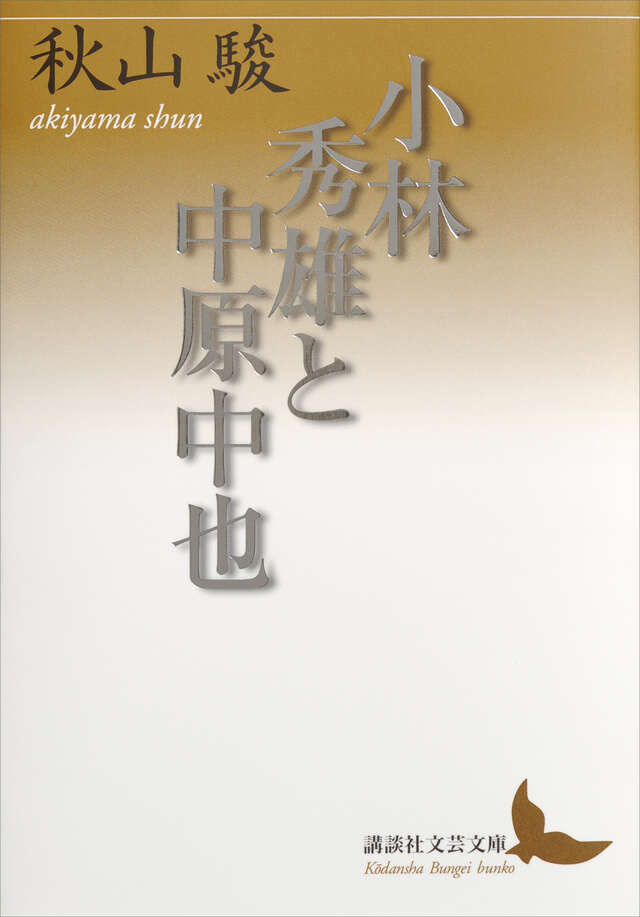
小林秀雄と中原中也
-

筒井康隆入門
-

新しい小説のために
-

文芸的な、余りに文芸的な/饒舌録 ほか
-

乱歩と正史
-

現代詩試論/詩人の設計図
-

写生の物語
-

柄谷行人インタヴューズ
-

成熟と喪失 “母”の崩壊
-
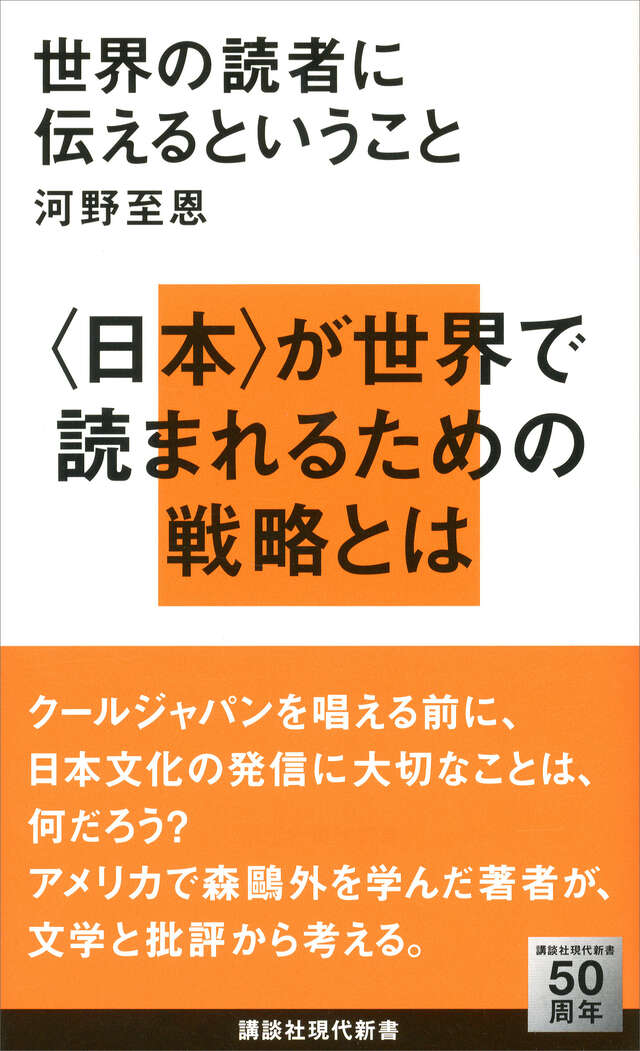
世界の読者に伝えるということ
-

神々の闘争 折口信夫論
-

光の曼陀羅 日本文学論
-

テクストから遠く離れて
-

「私小説」を読む
-

恋と日本文学と本居宣長・女の救はれ
-

堀辰雄覚書・サド伝
-

柄谷行人蓮實重彦全対話
-

柄谷行人中上健次全対話
-
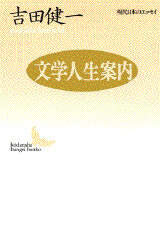
文学人生案内
-

文学概論
-

文学の楽しみ
-

文学のプログラム
-

風俗小説論
-

反文学論
-

俳人蕪村
-

日本浪曼派批判序説
-

二葉亭四迷伝
-

内部の人間の犯罪 秋山駿評論集
-

東西文学論・日本の現代文学
-

転々私小説論
-

中原中也
-

対談・文学と人生
-

対談 文学の戦後
-

折口信夫文芸論集
-

正宗白鳥 その底にあるもの
-

常識的文学論
-

小林秀雄全文芸時評集
-
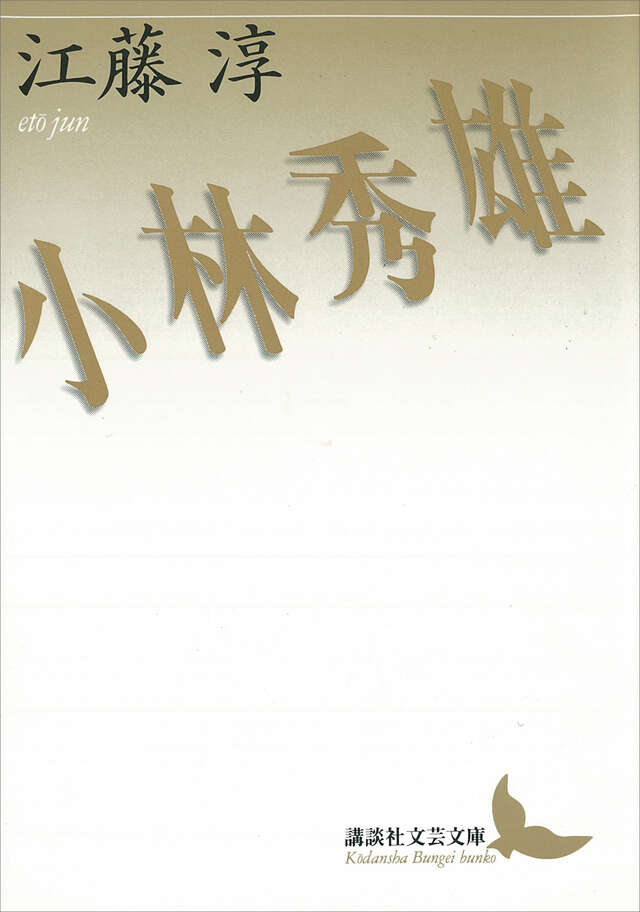
江藤淳 小林秀雄
-

女の子を殺さないために解読濃縮還元100パーセントの恋愛小説
-

書物の解体学
-

坂口安吾と中上健次
-

斎藤茂吉ノート
-

近代日本の批評
-

畏怖する人間
-

意味という病
-

われもまた おくのほそ道
-

マス・イメージ論
-

ハイスクール・ブッキッシュライフ
-
アレゴリーの織物
-

1946・文学的考察
-

日本近代文学の起源

















