ブルーバックス作品一覧
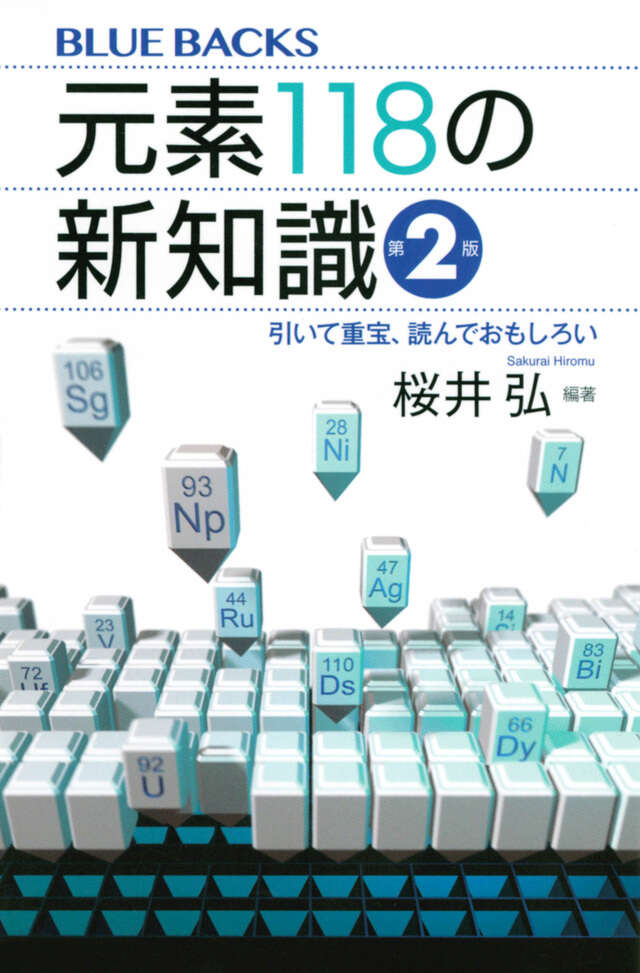
元素118の新知識〈第2版〉 引いて重宝、読んでおもしろい
ブルーバックス
累計18万部突破! 「読む元素事典」の決定版が、〈国際標準の最新元素周期表〉に完全対応!
元素とはなにか──?
・各元素の性質の違いはどう決まる?
・周期性があるのはなぜ?
・天然の元素と人工元素の違いとは?
・元素の数はどこまで増える?
・元素発見ランキングの第1位は誰?
・原子量などの重要データはなぜ変動する?
……ほか、元素番号1番「水素」から118番「オガネソン」まで、「万物の根源」をなす全元素を徹底詳説!
本書が支持される4大理由とは?
1:「元素の本質」をいきいきと描き出す。
事典的要素が充実していることはもちろん、読み物としても面白い。具体的なエピソード満載で、各元素の個性を紹介。
2:全118元素の特性や用途など、重要ポイントが一目瞭然。
化合物や現象の列挙にとどまらず、その原因やメカニズムを掘り下げて解説。
3:生命と元素の関わりがよくわかる。
生命活動に必須の元素から、いまだその存在が謎に包まれている元素まで、健康や病気にどう影響するかを詳述。意外な元素に、生命との関係があった。
4:充実した元素データ。
同位体の種類や存在比、半減期から電子配置、原子量まで。元素に関する最新数値を網羅。

宇宙検閲官仮説 「裸の特異点」は隠されるか
ブルーバックス
すべての物理法則が破綻する「特異点」は、ふつうの宇宙であれば必ず発生する。物理学者にとってショッキングな
この事実を証明したのが、ロジャー・ペンローズの「特異点定理」だった。
しかし彼は、一方ではこんな「仮説」も提唱したーー本当に厄介な「裸の特異点」は、宇宙検閲官がブラックホール
で覆い隠してくれている、だからきっと大丈夫だ!
はたしてこの仮説は、定理となりうるのか、それとも願望にすぎないのか? 物理学の存亡をかけた検証が始まった!
2020年ノーベル物理学賞の対象となった「特異点定理」を一般書で初めて解説し、一般相対性理論はみずから破綻する「宿命」であることを示しながら、宇宙検閲官仮説が本当に成立するか否かをスリリングに検証! そこからは、宇宙創成の謎解きにつながる数々の最先端の理論も「副産物」として生まれてくる! 映画『インターステラー』に描かれたブラックホールと特異点のリアルな姿がここにあります。
(本書の内容)
第1章 一般相対性理論とは
第2章 アインシュタイン方程式の解
第3章 特異点定理
第4章 宇宙検閲官仮説
第5章 特異点定理と宇宙検閲官仮説の副産物

カラー図説 生命の大進化40億年史 中生代編 恐竜の時代ーー誕生、繁栄、そして大量絶滅
ブルーバックス
本書は、40億年にわたる生命の進化史を綴る全3巻企画の二冊目、中生代編です。進化の新たなステージに登場した特徴的な種を特に取り上げ、豊富な化石写真と美しいカラー復元画とともに解説していきます。
中生代は、約2億5200万年前から約6600万年前まで、約1億8600万年続いた時代です。その間、一般的にも注目され人気の高い恐竜が誕生し、繁栄し、絶滅しました。
恐竜が誕生した三畳紀、恐竜が巨大化し、種類を増やし、さらには空にも進出を始めたジュラ紀、さらに多様化し、多くの羽毛恐竜が現れ、大繁栄の末、巨大隕石の衝突と共に絶滅した白亜紀。
本書では、これら三つの時代を、恐竜をはじめとした様々なグループ、約110種の生き物を紹介しながら概観していきます。登場する生物を追っていくだけで、生命の進化の流れが理解できる構成になっています。
目次
第1章 爬虫類時代の始まり 三畳紀
第2章 恐竜時代がやってきた! ジュラ紀
第3章 繁栄は続く 白亜紀
著者紹介
土屋 健
オフィス・ジオパレオント代表。サイエンスライター。埼玉県生まれ。金沢大学大学院自然科学研究科で修士号を取得(専門は地質学、古生物学)。その後、科学雑誌『Newton』の記者編集者、サブデスク(部長代理)を経て2012年に独立し、現職。近著に『機能獲得の進化史』(みすず書房)、『地球生命 水際の興亡史』(技術評論社)、『恋する化石 「男」と「女」の古生物学』(ブックマン社)など多数。

「心の病」の脳科学 なぜ生じるのか、どうすれば治るのか
ブルーバックス
【最新研究から見えてきた精神疾患のしくみと治癒への道筋】
・うつ病の脳では炎症が起きている?
・遺伝要因と環境要因、どちらの影響が強いのか
・統合失調症の幻覚は脳の神経回路の配線障害が原因?
・ロボットが自閉スペクトラム症の患者を支援する
・ゲノムの中を飛び回る遺伝因子が統合失調症を引き起こす?
・認知症薬でPTSDのトラウマ記憶を消せるかもしれない
・精神疾患の根治薬を実現するには …など
うつ病、自閉スペクトラム症・ADHDなどの発達障害、PTSD、統合失調症、双極性障害…
多くの現代人を苦しめる「心の病」は、脳のちょっとした変化から生まれます。
誰にでも起こりうるこの病は、何が原因で、
どのようなメカニズムで生じるのでしょうか?
様々な角度から精神疾患の解明に挑む研究者たちが、研究の最前線をわかりやすく解説。
そのしくみから「治る病」にするための道筋まで。
■主な内容
第1章 シナプスから見た精神疾患 ~「心を紡ぐ基本素子」から考える:林(高木)朗子
第2章 ゲノムから見た精神疾患 ~発症に強く関わるゲノム変異が見つかり始めた:久島周
第3章 脳回路と認知の仕組みから見た精神疾患 ~脳の「配線障害」が病を引き起こす?:那波宏之
第4章 慢性ストレスによる脳内炎症がうつ病を引き起こす? ~ストレスと心と体の切っても切れない関係:古屋敷智之
第5章 新たに見つかった「動く遺伝因子」と精神疾患の関係 ~脳のゲノムの中を飛び回るLINE-1とは :岩本和也
第6章 自閉スペクトラム症の脳内で何が起きているのか ~感覚過敏、コミュニケーション障害…様々な症状の原因を探る:内匠透
第7章 脳研究から見えてきたADHDの病態 ~最新知見から発達障害としての本態を捉える:岡田俊
第8章 PTSDのトラウマ記憶を薬で消すことはできるか ~認知症薬メマンチンを使った新たな治療のアプローチ:喜田聡
第9章 脳科学に基づく双極性障害の治療を目指す ~躁とうつを繰り返すのはなぜか:加藤忠史
第10章 ニューロフィードバックは精神疾患の治療に応用できるか :柴田和久
第11章 ロボットで自閉スペクトラム症の人たちを支援する :熊﨑博一
第12章 「神経変性疾患が治る時代」から「精神疾患が治る時代」へ :勝野雅央
・ビッグデータ解析から精神疾患に迫る:橋本亮太
・計算論から精神疾患を捉える方法:磯村拓哉、高橋英彦
・脳神経系のエピジェネティクスと「心の病」のつながり
・ヒトiPS細胞を使って精神疾患を研究する方法:中澤敬信
・複雑性PTSDとは
・適応障害とうつ病の間

新しいゲノムの教科書 DNAから探る最新・生命科学入門
ブルーバックス
DNAという言葉は誰でも知っているし、日常会話のなかでもよく口にする言葉です。しかし、DNAが生命の設計図であることはなんとなくわかっていても、それが具体的にどんな形で私たちの体の構造の「情報」になっているのか、想像するのは簡単ではありません。また、ニュースで毎日のように取り上げられる、PCR検査やゲノム編集、遺伝子組換え、クローンといった話題が、DNAとどう結びついているのかを正確に理解している人も少ないでしょう。
本書では、中学や高校で習う原子や分子といった知識があれば理解可能なように、DNAに基づく生命科学の大枠を、DNAに書かれた生命情報という観点から解説を試みました。少ない予備知識の読者でも最初から順を追って読めば基本を理解でき、少し知識がある読者なら、基本を確認しながら最新の解析技術まで深めることができる1冊。
第1章 生命の情報~なぜDNAという分子が重要なのか
1生命の単位としての細胞 /2原核細胞と真核細胞 /3細胞の多様性と分化 /4クローン生物とはなにか /5ES細胞、iPS細胞と再生医療 /6すべての細胞に同じ「ゲノム情報」 /7DNAの構造
第2章 遺伝子とはなにか
1遺伝子という概念の変遷 /2RNAとセントラル・ドグマ /3転写――RNA合成/4mRNAを成熟させるRNAプロセシング /5タンパク質の基本構造 /6タンパク質の多様性 /7翻訳―ータンパク質の生合成/8翻訳後のタンパク質の成熟 /9非コードRNA遺伝子 /10 DNAの複製
第3章 ゲノムDNAの全体像
1ヒトゲノム計画 /2いろいろな生物のゲノム /3すべての生命に必要な代謝システム /4ヒトゲノムDNA の中身をのぞいてみると/5 トランスポゾン とはなにか/6 ウイルスとゲノム /7 遺伝情報システムとしてのゲノム /8ゲノムの不安定化とDNA修復/9ヒトゲノムの個人差と多様性
第4章 クロマチンとエピゲノム~ゲノムに追記される情報
1DNAのヌクレオソームとクロマチン構造 /2細胞記憶を担うエピジェネティクス /3エピゲノムの片腕――DNAメチル化/4もう一方の片腕――ヒストンコード /5遺伝子のスイッチ /6転写を増やす働きをするエンハンサー /7エンハンサーの謎 /8インスレーター の二つの構造/9核構造と相分離
第5章 生命科学を大きく発展させるDNA解析技術
1 DNAを扱う基本操作 /2遺伝子のクローニング /3すっかりおなじみになったPCR /4DNA塩基配列決定法の基本/5「次世代」のDNA塩基配列決定法 /6遺伝子の発現解析法 /7クロマチン構造の解析法/8DNA解析に変革をもたらすゲノム編集技術/9新次元のゲノム情報をもたらすメタゲノム解析

はまると深い! 数学クイズ 直感力・思考力を磨く
ブルーバックス
・128チームが参加するトーナメント大会。引き分けがなかった場合の試合数は?
・定規でサッカーボールの直径を測るには?
・新幹線の座席は、なぜ通路を挟んで2席と3席になっている?
ふだん何気なく目にしているものの裏側には、かならず「数学」がある!
クイズ形式の傑作問題に挑戦しながら、その奥に潜む数学的思考をくわしく解説。
あなたにも数学の奥義を伝授します!
フロベニウスの硬貨問題、フェルミ推定、鳩の巣原理、ユークリッドの『原論』、オイラーグラフ、最長片道切符問題、古代の三大作図問題……。
古今東西さまざまな大数学者を悩ませたパラドックスや図形の問題などなど。
考えだしたら止まらない、やみつき「数学クイズ」をもとに、大人気・数学のお兄さんといっしょに数学世界の旅へ!

量子力学の多世界解釈 なぜあなたは無数に存在するのか
ブルーバックス
あなたが本を読んでいるとき、居眠りをしているあなたも同時に存在する!
世界は無数に分岐していて、あなたはそれぞれの世界に無数に存在している!
これはSFでも疑似科学でもない。第一線の理論物理学者たちによって真剣に議論され、現在では多くの
支持を集めている考え方である。人間の直観に大きく反する量子力学をどう理解すべきかを考えたとき、
標準的な解釈とされているコペンハーゲン解釈ではなく、この多世界解釈こそが、じつは最も「自然」で、
最も「真面目に」量子力学に向きあう考え方であるといわれている。それはいったいなぜなのか?
さらに多世界解釈では「シュレーディンガーの猫」のパラドックスも取るに足らない問題として説明され、
「量子もつれ」「遅延選択」「量子消しゴム」「Qビズム」などの新時代のテーマにも明快に答えられる。
量子力学で最もエキサイティングな「解釈問題」を誰にでもわかる平易なロジックの積み重ねで説明し、
衝撃的な世界像を描き出すとともに、誤解されがちな量子力学の根本原理も正しく知ることができる、
量子力学に興味のあるすべての人が必ず読んでおくべき一冊!
(本書の内容)
第1章 原子の世界
第2章 量子力学の誕生
第3章 光は波か粒子か
第4章 波の収縮と確率――コペンハーゲン解釈
第5章 状態の共存から多世界解釈へ
第6章 同時進行する複数の状態
第7章 ボーア=アインシュタイン論争からエンタングルメントへ
第8章 光子の干渉実験
第9章 デコヒーレンス─ 干渉性の喪失
第10章 世界の分岐
第11章 確率則
第12章 多世界解釈の世界像

人体最強の臓器 皮膚のふしぎ 最新科学でわかった万能性
ブルーバックス
皮膚はさまざまな能力を併せ持った「スーパー臓器」です。有害な化学物質や病原体の侵入を防ぐ物理的バリアであるともに、人体最大の免疫器官であり、無数のセンサーが埋め込まれた感覚器官です。
皮膚組織の分子レベルでの解明が進んだことで、これまでからだを覆う「薄皮」のように思われてきた皮膚には、生命活動にかかわるさまざまな精緻なしくみが備わっていることがわかってきました。21世紀に入ってからの皮膚医学の進展は目覚ましく、毎年のように教科書を書き換えるような発見が相次いでいます。本書は、人体最強の臓器と呼ばれる皮膚の謎に、最新の科学的知見を元に迫ります。
ここまでわかった万能の臓器「皮膚」の謎
・人が温度を体感できる「からくり」がわかった
・皮膚をかくと、かゆみが静まる驚きの理由
・ヒトが「裸のサル」になった必然的理由とは?
・アトピー性皮膚炎の原因遺伝子がわかった
・いかに皮膚は老化するのか?
・喘息などのアレルギー発症も、アレルゲンの皮膚侵入が引き金になる
・AIの診断能力はすでに一流の皮膚専門医をしのぎうる
(本書の内容)
はじめに
第1章 そもそも皮膚とはなにか?
第2章 皮膚がなければ、人は死ぬ
―生体防御器官としての皮膚
第3章 なぜ「かゆく」なるのか? 感覚器官としての皮膚
第4章 動物の皮膚とヒトの皮膚
―生き物が変われば皮膚も変わる
第5章 皮膚の病気を考える
―どんな病気があるのか?
第6章 アトピー性皮膚炎の科学
―現代人を悩ます皮膚の難病
第7章 皮膚は衰える
―皮膚の老化とアンチエイジング
第8章 未来の皮膚医療はどう変わる?
番外編 研究者になるための体験的・人生ガイド

宇宙の終わりに何が起こるのか 最新理論が予言する「5つの終末シナリオ」
ブルーバックス
この宇宙は必ず終わる。──いつ、どうやって!?
「万物が究極的に破壊される」瞬間を描く5つのシナリオとは?
19ヵ国で翻訳!
話題の最新宇宙論
2021年9月刊行、同名書籍の新書化
〈最新理論が予言する「5つの終末シナリオ」〉
1:ビッグクランチ──急激な収縮を起こし、潰れて終わる
2:熱的死──膨張の末に、あらゆる活動が停止する
3:ビッグリップ──ファントムエネルギーによって急膨張し、ズタズタに引き裂かれる
4:真空崩壊──「真空の泡」に包まれて完全消滅する突然死
5:ビッグバウンス──「特異点」で跳ね返り、収縮と膨張を何度も繰り返す

量子の世界をみる方法 「スピン」とは何か
ブルーバックス
電子の「スピン」といわれたときに、皆さんはどんなイメージを持ちますか?
「地球が自転をしながら太陽のまわりを回るように、電子が自転しながら原子核のまわりを回っているようなイメージ」や「電子がコマのように回っている」「フィギュアスケートの選手のように回っている」などのイメージが頭に浮かんでいるのではないでしょうか?
実は、この答えは正しくないのです、といったら皆さんは驚くでしょうか。
「スピン」は私たちの暮らしているマクロな世界の「回転」とは異なり、なかなか感覚的に掴みにくく、それが「スピン」への理解を難しくしているのではないかと思います。
本書は、「スピン」をもっと深く、そして正しく理解してほしいという思いから、物理学者とサイエンス分野の広報関係者、そして素人!? がチームを組んで執筆しました。
この本は、多様な読者を想定したものです。物理に興味のある高校生から「スピン」をきちんと理解したい大学生。学生時代に量子力学の授業で「スピン」の話を聞いたことがあるけど、もう一度、きちんと理解したいと思っている方などなど。さまざまな人に本書をとおして「スピン」の不思議さやおもしろさ、凄さを知ってもらいたいと考えています。
「スピン」の正体とは? 量子力学の誕生からスピンの発見までの歴史的な背景。さらに「スピン」はどのように記述され、捉えればいいのか? 本書では、できるだけ具体的に理解できるように「シュテルン=ゲルラッハの実験」を紹介しながら解説していきます。
さらに、電子だけでなく、陽子、素粒子のスピンまでを取り上げ「量子」の世界をみていきましょう。
そして、2022年度のノーベル物理学賞の受賞でニュースでも話題になっている「量子もつれ」を利用する量子コンピューターや生き物の特殊な能力について、そのほかにも超伝導や永久磁石など社会の様相さえ劇的に変えつつあるスピンを利用した技術最先端までをていねいに解説していきます。
本書を片手に「量子」と呼ばれる摩訶不思議な世界に飛び込み、「スピン」をめぐる冒険に出かけましょう。

宇宙を解くパズル 「真理」は直観に反している
ブルーバックス
ハーバード大学で300年近い歴史がある「ホリス数学・自然哲学教授」にして、「超弦理論」などの研究で理論物理学をリードしてきたカムラン・バッファ氏が、1年生向けの講義で使っているパズル満載の型破りなテキストを書籍化!
ブライアン・グリーン氏、エドワード・ウィッテン氏が驚きつつも絶賛した(文末に記載)類のない一冊の日本語版!
「宇宙はどうなっているのだろう?」この素朴な問いにとりつかれた人類が宇宙の謎を解明してきた結果わかったのは、宇宙はあまりにも人類の直観に反しているということだった。なにしろ空間や時間は歪んでいて、光は波でも粒でもあり、物質の最小単位は「ひも」かもしれないというのだ! このような宇宙をどう理解すればいいのか?
バッファ氏は言う。「理論物理学者の仕事は、宇宙の難解な問題を、単純なパズルに分解して解くことだ」
トランプやコイン、アリやカメらが繰り出す問題に悩むうち、物理学はどう進歩してきたのか、対称性やその破れがなぜ重要なのか、さらにいま注目の概念「双対性」の本質までが見えてくる。バッファ氏の盟友・大栗博司氏が監訳者として随所で注釈をほどこした、楽しみながら物理学の「真髄」に迫れる本!
【たとえば、こんな問題があります】
缶が2つあって、一方には緑のペンキが、もう一方には白のペンキが入っている。缶は同じ大きさで、入っているペンキの量もまったく同じだとしよう。ここで緑のペンキを少量すくって、白の缶に入れる。次にその混ざったペンキの缶から同じ量をすくって、緑の缶に戻す。
そこで問題。白の缶に入っている緑のペンキの濃度と、緑の缶に入っている白のペンキの濃度、どちらのほうが高いか?
※バッファさんの本書刊行記念講演と、大栗さんとの対談をこちら↓からご覧いただけます!
https://www.youtube.com/watch?v
【理論物理学の大家たちも絶賛!】
「現代の物理学と数学の中核をなす概念を、パズルを通してひととおり説明するというすばらしい本。私が知る中でももっとも風変わりで魅力的なアプローチで、初学者も専門家も頭の体操に楽しく取り組みながら学べる。世界屈指の物理学者から、最先端の本質的な考え方を楽しみながら効果的に吸収できる」――ブライアン・グリーン
「簡単で愉快なパズルを解きながら、物理学と数学の高度な概念の数々を楽しく巡っていくという独特な本。たくさん楽しんで、たくさん学べるはずだ」――エドワード・ウィッテン
【監訳者の大栗博司さんより】
「本書は、完成した成果ではなく、そこのいたる過程をパズルを解くことで体験できるようになっているのが斬新です」

カラー図解 脳の教科書 はじめての「脳科学」入門
ブルーバックス
脳の複雑で不思議なしくみを、豊富なカラー図版と共に、わかりやすく徹底的に解説しました。脳の進化や構造、1000億個を超えるといわれる神経細胞の不思議、神経細胞以外にも重要な働きをするグリア細胞、脳はどのように世界を見て、聞いて、認識しているのか? 記憶はどのようにつくられ、どこに蓄えられているのか? など、「脳」の謎や不思議をあますところなく、丁寧に解説しています。
主な内容
第1章 脳の全体像
第2章 脳の細胞
第3章 外の世界を知る
第4章 体の中の世界、体の外の世界にはたらきかける
第5章 記憶・思考・言語など 脳の高次の機能
第6章 脳の発達
第7章 脳の病気
医学生やコメディカル関係者はもちろん、「脳」に興味があるすべての人必読の一冊です。

ブルーバックス科学手帳2023
ブルーバックス
日々の生活にもっと「サイエンス」を!
365日の科学の出来事や元素周期表、ノーベル賞受賞者の一覧など、役立つ情報満載の科学ファン必携のスケジュール手帳です。

時計遺伝子 からだの中の「時間」の正体
ブルーバックス
体内時計とは何か? 生体リズムはどのように生まれるのか?
時計遺伝子は、様々な体の機能に関わっていた!
・生体リズムの乱れが、生活習慣病を引き起こす
・深夜にコンビニに行くと元気になるのはなぜか
・「朝日を浴びると良い」「寝る前のスマホは良くない」理由とは
・「寝る子は育つ」の本当の意味
・時差ぼけを解消する薬ができる?
・ブルーライトはなぜ体に良くないのか?
・朝型・夜型を決める遺伝子があった
・分子レベルでみた「規則正しい生活」が大切なわけ
――遺伝子レベルで体内に何が起きている?
睡眠、血圧、体温、ホルモン分泌……
体の中で起きているほとんどの生理現象は24時間の生体リズムを示します。一体なぜか。
その謎に答えを出したのは、2017年のノーベル生理学・医学賞のテーマにもなった「時計遺伝子」でした。
37兆個の全細胞に存在する時計遺伝子が臓器のリズムを作り、脳の視交叉上核という小さな部位が司令塔となって、全身の「時間」を司っていたのです。
哺乳類における生体リズム研究の第一人者が、その分子機構から、睡眠障害・生活習慣病の関係までを解説。
【主な内容】
第1章 からだのリズムを作る時計遺伝子
第2章 生体リズムはどこで作られるのか? ――時計中枢の発見
第3章 時間情報の送信ルートを特定せよ ――脳から全身の臓器に至るまで
第4章 時計遺伝子は細胞分裂の時間も決める
第5章 光と時計遺伝子の深い関係 ――「朝日を浴びると良い」理由
第6章 生活習慣病と時計遺伝子 ――高血圧を分子レベルで解明する
第7章 時差ぼけはなぜ起こるのか? ――生物が初めて直面したリズム異常
第8章 視交叉上核の謎を解く ――朝型・夜型遺伝子の発見と睡眠障害治療薬の可能性
第9章 睡眠と時計遺伝子 ――霊長類の時計と睡眠覚醒リズム
第10章 なぜ生物は体内時計を持つようになったのか ――からだの「時間」を作る様々なメカニズム

日本の気候変動5000万年史 四季のある気候はいかにして誕生したのか
ブルーバックス
日本の気候は、5000万年前の超温暖期から3000万年前の寒冷化、2300万年前のモンスーン開始による梅雨の誕生、エルニーニョ多発の時代、260万年前の氷期など、さまざまな変化を経験してきた。そうしたなかで、日本は列島を形成し、日本特有の温暖湿潤で美しい四季をもつ気候となってきた。5000万年前には大陸の一部だった日本が、大陸から分かれ始めたのは約4000万年前、日本列島が現在の位置になったのは約1500万年前だが、その長い時代の変遷の中で、日本の気候はどのように変化してきたのだろうか? 気候は、日本だけでは語ることはできない。日本の気候の成立には、ヒマラヤ山脈の誕生によるモンスーンの開始や黒潮と対馬海流の成立も大きく関わっている。本書では、地球全体の気候変動、日本列島の地質学的な変化と気候の変化を関連づけて明らかにしていく。
主な内容
第1章 超温暖期とその後の寒冷化 日本列島以前の気候
第2章 モンスーン時代の到来 梅雨の始まり
第3章 日本列島誕生と気候への影響
第4章 地球温暖化アナロジーの時代
第5章 第四紀氷河時代の日本
第6章 日本特有の気候の成立

1日4分 世界標準の科学的トレーニング 今日から始める「タバタトレーニング」
ブルーバックス
ジムに通ってコツコツ運動しても、ストイックに追い込んだトレーニングをしても、なかなか思うような効果が出ないと感じる人も多いなか、「高強度、短時間、間欠的」のシンプルなタバタトレーニングが世界じゅうで人気です。欧米のアスリートや俳優やモデルなども、タバタトレーニングを取り入れて効果を実感しているコメントが寄せられています。
もともとは、アスリートのチームで経験的に組まれたプログラムが基本になったものですが、著者はさまざまなデータを取り、実験や研究を重ね、科学的に裏づけを取り、プログラムを確立しました。
アスリートから高齢者まで、それぞれに合った「高強度、短時間、間欠的」な運動であれば、体力をつけ、パフォーマンスを出すことができる理由を徹底解説。10代から高齢者まで年齢別に、また「趣味のスポーツのパフォーマンスを上げたい」「体力をつけたい」「筋肉を増やしたい」「健康維持」など目的別のトレーニングを紹介します。
第1章 誰でもすぐできる! 世界が認める、タバタトレーニングとは
海外では超有名! タバタトレーニングが認められた理由/たった4分で完結! 気軽にできるシンプルなトレーニング/有酸素性運動と無酸素性運動のどちらも最大効果が得られる/運動が苦手な人でも、追い込まなくても、効果は出せる/大きな筋肉を使って効率よく/ウォーミングアップ、クーリングダウン、メディカルチェックで身体をケア/生活習慣病の予防や肥満解消効果/タバタトレーニング実践法 ほか
第2章 身体とトレーニングの科学
身体活動を数値化する/有酸素性運動とはなにか/最大酸素摂取量と持久力/最大酸素借と筋の無酸素性体力/有酸素性運動と無酸素性運動のバランス/骨格筋の科学――筋量と筋力/運動における疲労の科学 ほか
第3章 科学的視点で組み立てるトレーニング
トレーニングの原則/トレーニングの原理/科学的トレーニングの要素/効果はトレーニングによってなぜ変わるのか/トレーニングと生体反応
第4章 分子生物学的タバタトレーニング

天変地異の地球学 巨大地震、異常気象から大量絶滅まで
ブルーバックス
日本が世界有数の地震大国であることは知られていますが、ほかにも火山噴火に台風、そして近年の線状降水帯による異常な大雨と、いったいなぜ、この国にはこれほど自然災害が集中するのでしょうか? じつは地球科学によれば、それは必然であり、日本は世界でも稀な「災害が束になってやってくる国」だというのです。災害が束になると、それはもう「天変地異」です。
しかし地球46億年の歴史をたどれば、もっとすさまじい天変地異の連続でした。日本列島の体積の6倍ものマグマが海底から噴き出し、すべての大陸が一つに合体してはまた分裂し、地球全体が凍りついて一個の雪玉になったこともありました。この間に、生物は何度も大量絶滅を繰り返してきました。
じつは、天変地異にはサイクルがあります。そのサイクルは、より大きなサイクルに呑み込まれ、そのサイクルもまた、さらに巨大なサイクルの歯車の一部となっています。
では、最も大きなサイクルとは何でしょうか? 地球を動かしている究極の原動力とは、いったい何なのでしょうか?
その答えは、宇宙にあるのかもしれない! 「しんかい6500」で深海底に50回以上潜った地球を知り尽くす筆者が、回転木馬に乗りながら考えてたどりついた推論とは? 天変地異を軸に46億年をとらえなおす、かつてないスケールの地球科学!
序 章 天変地異とは何か
第1章 人類が経験した天変地異
第2章 空、海、陸と天変地異
第3章 生物を襲った天変地異
第4章 究極の天変地異
終 章 銀河と天変地異

最小にして人類最大の宿敵 病原体の世界 歴史をも動かすミクロの攻防
ブルーバックス
私たちのおよそ2000万分の1の大きさのウイルス。ゲノムのサイズもヒト全ゲノムが約62億塩基対、2万2千個のタンパク質をコードすると言われているのに対し、新型コロナウイルスはたった29種類のタンパク質しかもたず、遺伝情報の量も非常に少ない、シンプルな存在。なのに私たちはなぜ新型コロナウイルス翻弄されるのでしょうか。
人類誕生から現在までの人の死因の累計第一位である感染症を引き起こす、ウイルスや細菌などの病原微生物(病原体)は、その小さな体と限られた遺伝情報量の中に、ヒトなどに感染して自らの子孫を効率よく増やして広めるための、巧妙で狡猾な生態を持つものばかりです。
本書では、そんな病原体たちが進化の過程で身に付けた、さまざまな感染戦略、生存戦略を紹介します。宿主に寄生することに特化した構造や機能、生態などの高度な進化は、いずれも驚くほどうまくできたしくみで、なかなかエキサイティングな世界です。恐ろしいものであると同時に、その「見事な」までの病原体について知っておくことが、次なる病原体との戦いの備えになるかもしれません。

生物を分けると世界が分かる 分類すると見えてくる、生物進化と地球の変遷
ブルーバックス
すべての生物学の土台となる学問こそが、分類学だ!
なぜ、我々は「ものを分けたがる」のか?
人類の本能から生まれた分類学の始まりは紀元前。
アリストテレスからリンネ、ダーウィン……と数々の生物学の巨人たちが築いてきた学問は、
分子系統解析の登場によって大きな進歩を遂げている。
生物を分け、名前を付けるだけではない。
分類学は、生命進化や地球環境の変遷までを見通せる可能性を秘めている。
生命溢れるこの世界の「見え方」が変わる一冊!
地球上で年間1万種もの生物が絶滅しているという。
その多くは、人類に認識すらされる前に姿を消していっている。
つまり私たちは、まだこの地球のことをこれっぽっちも分かっていない。
それどころか、「分かっていないことすらも分かっていない」のである。
だが、分類学を学ぶことで、この地球の見え方は確実に変わる。
奇妙な海洋生物・クモヒトデに魅せられ、
分類学に取りつかれた若き分類学者が描き出す、新しい分類学の世界。
◆主な内容
プロローグ 分類学者の日常
第1章 「分ける」とはどういうことか ~分類学、はじめの一歩
第2章 分類学のはじまり ~人は分けたがる生き物である
第3章 分類学のキホンをおさえる ~二名法、記載、命名規約とは?
第4章 何を基準に種を「分ける」のか? ~分類学の大問題
第5章 最新分類学はこんなにすごい ~分子系統解析の登場と分類学者の使命
第6章 生物を分けると見えてくること ~分類学で世界が変わる
エピローグ 分類学の未来
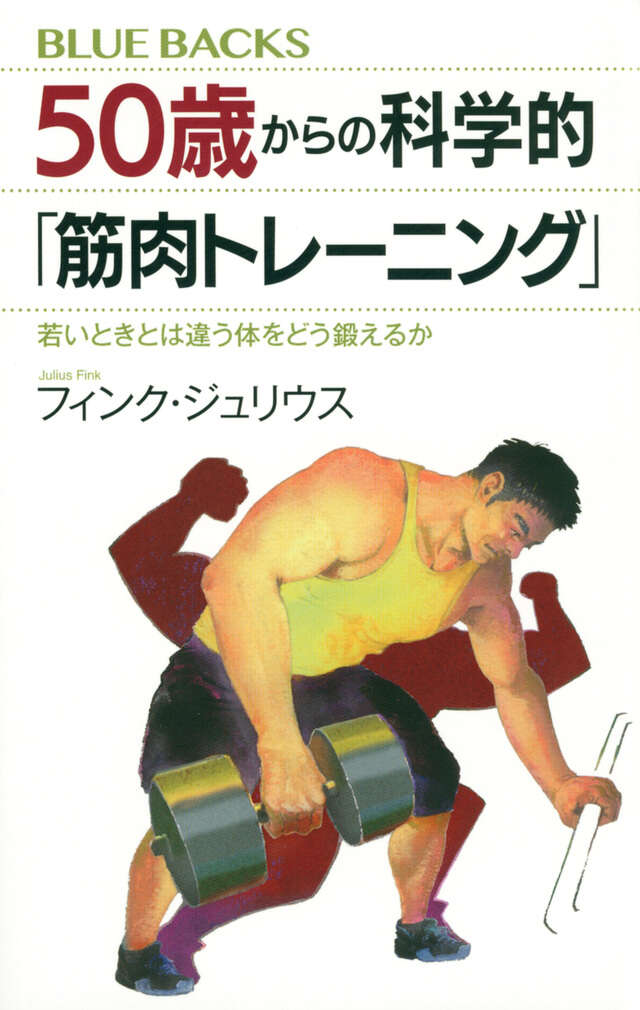
50歳からの科学的「筋肉トレーニング」 若いときとは違う体をどう鍛えるか
ブルーバックス
筋トレこそ最強のアンチエイジングだった
男性更年期を乗り切り、肥満、生活習慣病を防ぐ方法
「贅肉が気になるので、痩せたい」「若い時のように筋肉をつけたい」「以前のように持久力を戻したい」
中年になって、そんな思いでスポーツジムに行っても、なかなか思い通りになりません。とくに、若い頃にハードにスポーツをしていた人は、だれもが経験しますが、その頃と同じハードなトレーニングをしても、効果はほとんど現れません。ダイエットしても、若いときのようには痩せません。
これは、男性にも更年期があり、テストステロン(男性ホルモン)が減少するからです。テストステロンは、筋肉の形成と肥満の解消に大いにかかわっています。気力やチャレンジ精神、精力の源泉ともいわれる男性ホルモンのひとつです。
これを無視して激しいトレーニングをすると、中枢神経系の働きが阻害され、テストステロンは生産されにくくなり、運動しても筋肉がつかず、また痩せにくい体になってしまいます。
男性の更年期(男性ホルモンの減少と性ホルモンのアンバランス化)と、それによるトレーニングと身体の関係は今では詳しく解明されています。本書では、テストステロンの減少を抑え、筋肉を増やし贅肉を減らすのに効果的なトレーニング方法・メニュー、食生活の注意点、睡眠法などを紹介。筋トレ未経験の初心者から中級・上級者まで、レベル別にガイドしているので誰でも今日から始められます。
【間違い 1】中高年になって腹が出てくるのは不摂生が原因? → ◯太りやすいのは男性ホルモンが減ってくるから
【間違い 2】男性ホルモンの減少は仕方ない? → ◯筋トレと食事で男性ホルモンの分泌を増やすことが可能
【間違い 3】年を取ったら筋肉はつかなくなる? → ◯中高年向けのメソッドで誰でも筋肉はつく
【間違い 4】筋トレは最低半年はやらないと効果が出ない? → ◯初心者なら1ヵ月で体が変わる