講談社文芸文庫作品一覧

甲乙丙丁(上)
講談社文芸文庫
64年春、日本統計資料社に勤める津田貞一に、出勤停止、アカハタ配布停止がもたらされる。貞一と、30年代からの交流のある、もう1人の主人公、党中央委員、田村榊は、嘗て参議院議員でもあり、作家である。合法、非合法、半合法、戦前・戦中・戦後を、時代の良心として、精一杯生きぬいた中野重治が、党および人との諸問題を、良心の底をもつき貫いて語った巨大な文学的記念碑。

かくれ里
講談社文芸文庫
世を避けて隠れ忍ぶ村里――かくれ里。吉野・葛城・伊賀・越前・滋賀・美濃などの山河風物を訪ね、美と神秘のチョウ溢(チョウイツ)した深い木立に分け入り、自然が語りかける言葉を聞き、日本の古い歴史、伝承、習俗を伝える。閑寂な山里、村人たちに守られ続ける美術品との邂逅。能・絵画・陶器等に造詣深い筆者が名文で迫る紀行エッセイ。

一個・秋・その他
講談社文芸文庫
野間文芸賞、芸術院賞両賞受賞の短篇集『一個その他』から、世評高い作品集『カレンダーの余白』『青梅雨その他』『雀の卵その他』、そして川端賞受賞の『秋その他』に至る短篇の名手・永井龍男。その晩年の短篇集の中から、「一個」「蜜柑」「杉林そのほか」「冬の日」「青梅雨」「雀の卵」そして名品中の名品「秋」など14篇の短篇の冴えを集成。

宮沢賢治覚書
講談社文芸文庫
大正13年4月『春と修羅』上梓――賢治28歳、この夏、それを手にした心平21歳。至純な天性が、もう1つの“異数”の天性に“出会い”、画期的な“言葉の宇宙”に鋭く感応する。日本近代詩史の勃発的事件――「宮沢賢治」。賢治評価の第1ページを拓き、その全集を編集した草野心平の限りなく深い理解と熱意溢れた“讃歌”。

語り物の宇宙
講談社文芸文庫
伊吹山の天狗に妻を掠われ、山々を遍歴する「甲賀三郎」。地獄巡りの「小栗判官」。ギリシャ神話に通う「しんとく丸」。浄瑠璃、歌舞伎、説経節等に深く息づく庶民の英雄たち。柳田国男、折口信夫らの先駆的業績を踏まえつつ、遥かな神話、伝説に始源する「語りの世界」の魅力を豊饒な自立した言語表現として初めて本格的に論究する。現代文学の地平を新たな視点から照射する画期的文学論。

一草一花
講談社文芸文庫
道元、明恵、良寛などから日本人の自然観・宗教観をさぐり、その美意識の根底には哀しみを帯びた東方の虚無思想が存在すると説くノーベル賞受賞記念講演「美しい日本の私」、芥川龍之介の「末期の眼」を引き、あらゆる芸術の極意は“末期の眼”にあるとして芸術家の恐ろしい“業”を示唆する「末期の眼」など、川端文学の本質を貫く生死一如の観を清冽に表出するエッセイ群26篇。

高村光太郎
講談社文芸文庫
敗戦後の岩手の山中に、己を閉塞させた高村光太郎。彼の留学体験に、父・光雲への背反、西洋文化の了解不可能性を探り、閉塞の〈実体〉を解明する。著者の文学的出発の始めに衝きあたった巨大なる対象――その生涯、芸術、思想を論じ、高村光太郎の思想的破綻を自ら全戦争体験をかけ強靱な論理で刳り出す初期の代表的作家論。

もう一つの修羅
講談社文芸文庫
常に現在を超えインターナショナルであり続けること。強靱な思考とダイナミックな論理の滲透力──そして何よりも明晰・華麗なレトリック。忌憚のない鋭い批評ゆえに同時代に敬遠された文学者花田清輝が、時間の流れの雲間から、今再び輝き出す。血と暴力を象徴する“修羅”を転倒し、“もう一つ”の言葉の“修羅”の世界を開示する知的快感溢れる力業!

忘れ得ぬ人々
講談社文芸文庫
鋭く柔軟な美的感覚と傑れた鑑識眼。学問への深い愛。自由濶達、磊落、率直な人柄のもとに、多くの俊才を輩出させた仏文学界の先駆者・辰野隆。その崇敬・讃嘆する、幸田露伴、夏目漱石、寺田寅彦、長谷川如是閑、谷崎潤一郎ほか、多彩な人々と著者との“交流”が渾然一体となる。エッセイ文学に1つの時代を画した名随筆集。

みずから我が涙をぬぐいたまう日
講談社文芸文庫
天皇に殉じて割腹、自死を遂げた作家の死に衝撃を受けた、同じ主題を共有するもう1人の作家が魂の奥底までを支配する〈天皇制〉の枷をうち破って想像力駆使し放つ“狂気を孕む同時代史”の表題作。宇宙船基地より逃走する男が日本の現人神による救済を夢見る「月の男」。──全く異なる2つの文体により、現代人の危機を深刻、ユーモラスに描く中篇小説2篇。

われ逝くもののごとく
講談社文芸文庫
太平洋戦争により崩れゆくサキ一家の変転の歳月と多くの庶民の、生きて死に逝く、“生死一如”の世界。かつての青春放浪の地、山形県庄内平野を舞台に人情味ある土地言葉を駆使しつつ、雄渾に物語る。生涯を賭けて深めた独自の仏教・東洋思想の視座から日本の風土と宗教を余すところなく描き尽した著者畢生の長篇大河小説。野間文芸賞受賞。

記憶の蜃気楼
講談社文芸文庫
辰野隆と共訳『シラノ・ド・ベルヂュラック』の名翻訳をはじめ、日本のフランス文学隆盛を先導した鈴木信太郎。詳細緻密な実証的研究、正確澄明な名文。友人、知己、学問を洒脱に語る滋味溢れるエッセイ集。「シラノ」ほか「記憶の蜃気楼」「君子有酒」「遊びの人生」「黄金伝説」「人工的時間」を収録。

蝸牛庵訪問記
講談社文芸文庫
蝸牛庵・幸田露伴と若き日の出会いから、その凄絶、荘厳な終焉の日までの“日常”の比類なき記録。該博な知識、不羈の精神、巨大な文学空間を展開する“文豪”露伴の、慈父のごとき姿をあざやかに捉える、小林勇のエッセイ文学の名著『蝸牛庵訪問記』。

鹿鳴館の系譜―近代日本文芸史誌
講談社文芸文庫
日本近代の“欧化”の象徴としての鹿鳴館――。その華やかさのうしろにある“悲哀”を見出す著者が、近代日本100年の歩みを、そのヴァリエーションとして、再構成しながら、社会・風俗・建築・音楽など、文化の全領域に“欧化という伝統”を発掘。既成の文学史観を覆す知的スリルに満ちた長篇。磯田光一の代表的エッセイ。読売文学賞受賞。

幕が下りてから
講談社文芸文庫
「悪い仲間」「陰気な愉しみ」で芥川賞を受賞、「海辺の光景」で野間文芸賞、芸術選奨両賞を受賞した著者が、新たに挑戦した長篇秀作。敗戦による価値の混乱と青春の惑乱を共にした、一主人公の「やましさ」の根源を、底深く洗いただし、極めてモラリッシュな文学世界を創造した長篇。毎日出版文化賞受賞作品。

都築ヶ岡から
講談社文芸文庫
小林秀雄、中原中也、そして吉田健一等との親交が語る人間的信頼の絆の純粋さ。文学的半生への深い省察。ピアノ、旅、愛犬との狩猟の話を高雅に綴る身辺の記。近代批評の確立者にして自由なる精神の持ち主、名著『吉田松陰』(野間文芸賞受賞)の評論家河上徹太郎の独創的、多彩なエッセイ。

幼年
講談社文芸文庫
幼い時期の記憶の断片――女になり替りたい願望、金を盗んだ罪の意識、父との確執と、母への思慕。それらを、主情的な回顧としてではなく文献、再訪、知人らの証言で修復し、確認しつつ幼い精神の形成されゆく一過程として提示した自伝。死者への鎮魂の名著『レイテ戦記』の著者の透徹した知性、清冽なる精神の拠ってきたる源泉。
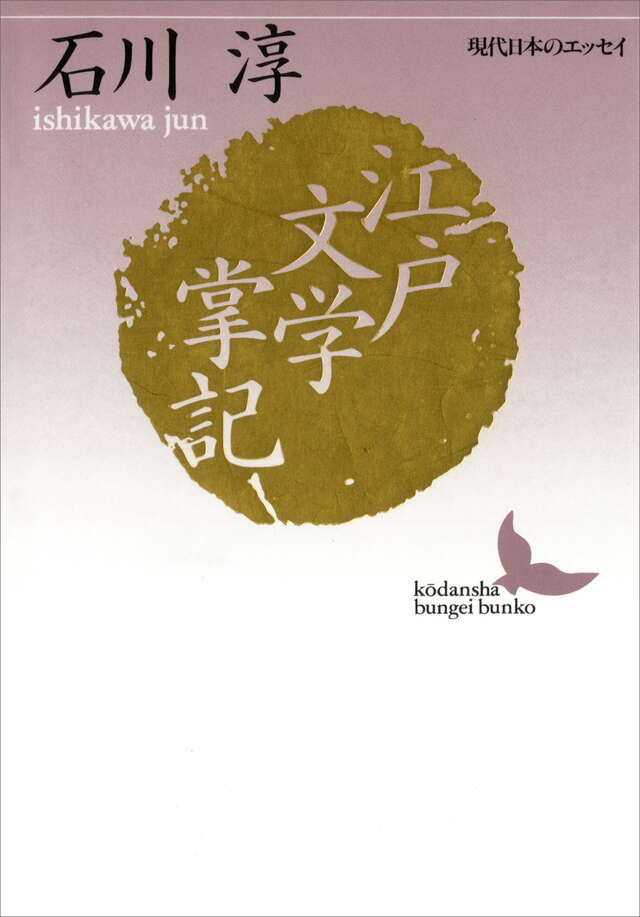
江戸文学掌記
講談社文芸文庫
狂歌師・宿屋飯盛はその族籍を四民の外の「遊民」に区分けられたという。名称に潜む軽侮、対する反骨。文学の毒を練り風雅の妙を極めた「遊民」たる江戸文人たちの人、生活、作品を論じ、江戸文学の根幹に迫って精髄を伝える石川淳の真骨頂8篇。「山東京伝」「横井也有」「其角」「長嘯子雑記」ほか。読売文学賞受賞。

金沢・酒宴
講談社文芸文庫
金沢の町の路次にさりげなく家を構えて、心赴くまま名酒に酔い、九谷焼を見、程よい会話の興趣に、精神自由自在となる“至福の時間”の体験を深まりゆく独特の文体で描出した名篇『金沢』。灘の利き酒の名人に誘われて出た酒宴の人々の姿が、40石、70石入り大酒タンクに変わる自由奔放なる想像力溢れる傑作『酒宴』を併録。

天才について
講談社文芸文庫
夢は“二塁手”だった。ささやかな日常、文学、師友、旅、読書、観劇──。著者の“詩魂”が、人生のさまざまな機微を掬い取る。英文学界を領導した第一級の学殖──学問と人間への愛に支えられた秀れた感性が語る真のユーモア溢れる格調高いエッセイの世界。