講談社学術文庫作品一覧

中国の歴史9 海と帝国 明清時代
講談社学術文庫
学術文庫版「中国の歴史・全12巻」の第6回配本・第9巻は、明朝と清朝、ふたつの大帝国を1冊で通観する。出口治明氏(立命館アジア太平洋大学学長)が「名著ぞろいのシリーズの中で、まさに名著中の名著。内藤湖南に匹敵するのでは」とイチオシする話題作。
2003年3月、雲南省昆明の空港で、著者は不思議な一行に出会う。聞けば彼らは、台湾の港町・花蓮から、海の女神「媽祖」を奉じて、雲南省の麗江を訪ねた帰路だという。台湾の海の女神が、なぜ中国内陸の観光地を?――この謎から、海に囲まれた東ユーラシア500年の歴史が浮かび上がってくる。
14世紀半ば、朱元璋が開いた明朝は、万里の長城の修築や、鄭和の南海遠征など、古代的な性格の色濃い王朝だった。それに対し、16世紀に登場したヌルハチに始まる清朝は、少数の満洲族のもとでさまざまな人々が闊達に生き、近代的な活気に満ちていた。古代的な明代から、近代的な清代への跳躍はなぜ可能だったのか。それを解明するには、「海に向かい合う中国」を見ることで、従来の中国史の枠を超える必要がある。倭寇と朝貢、銀の流通と世界経済、清朝皇帝とチベット仏教。地球規模の視点から、ふたつの帝国を描き出す。そして19世紀、アヘン戦争や太平天国を経験し、中国社会は近代への脱皮に備えて大きく変化していく。〔原本:2005年8月、講談社刊〕
目次
はじめに 大海に囲まれた二つの帝国
第一章 出来事の時空間
第二章 明朝の成立―一四世紀1
第三章 海と陸の相克―一四世紀2
第四章 海と陸の交易者―一五世紀
第五章 商業の時代―一六世紀1
第六章 社会秩序の変容―一六世紀2
第七章 王朝の交替―一七世紀
第八章 産業の時代―一八世紀1
第九章 伝統中国の完成―一八世紀2
第一〇章 環球のなかの中国―一九世紀
おわりに 媽祖と明清の歴史
学術文庫版のあとがき
主要人物略伝
歴史キーワード解説
参考文献
年表
索引

異端審問
講談社学術文庫
――皇帝ジギスムントが宮中伯ルートヴィッヒに向かって命令する。「囚人を受け取り、よろしく異端者として扱え」。今度はルートヴィッヒがコンスタンツの帝国代官に向かって命令する。「我ら双方によって断罪されたる者としてこの者を受け取り、よろしく異端者として焼け」。――
1415年に異端として裁かれた宗教改革の先駆者、ボヘミアのヤン・フス処刑の克明な描写にはじまる本書は、中世のヨーロッパで異端審問がどのようにして生まれ、そして制度として定着していったのかを、具体的なエピソードを丁寧に積み重ねながら、当時の人々の息遣いもあざやかに描き出す。法も手続きも無視して「すべて殺せ」という13世紀の異端狩りの熱狂から、ウンベルト・エーコの小説『薔薇の名前』にも登場した、世界で最も有名な異端審問官ベルナール・ギーによって組織化・マニュアル化された14世紀の冷徹無比な異端審問を経て、15世紀末スペインでの過酷な弾圧に至る、その道のりの背後には、いかなる時代精神が見いだせるのか。
西洋中世史不朽の名著『異端カタリ派の研究』(岩波書店、1989年)の著者が、多彩な史料を駆使して知られざる中世世界への扉を開く!(原本:講談社現代新書、1996年)
【解説(轟木広太郎・ノートルダム清心女子大学准教授)より】
本書は、一三、一四世紀における異端審問の成立と制度的確立の経緯を、およそ関連するすべての種類の史料を博引旁証しながら描き切った労作である。……ヨーロッパ中世という日本人にはどこか掴みどころのない、しかしそれでいて魅惑的な個性を放つ時代の雰囲気を初学者に感得させると同時に、このテーマに興味を持つ専門家にとってもいまだ探求のヒントを数多く掘り出すことのできる鉱脈たり続けていると思う。(本書「解説」より)
【本書の内容】
第一章 薪と硫黄の匂い――異端審問とは何か
第二章 剣と火と異端者――異端審問の誕生まで
第三章 異端審問創設の頃
第四章 異端審問の制度化
第五章 審問官ベルナール・ギー
第六章 裁かれる者たち
第七章 スペインの火刑台
あとがき
参考書目抄
解説「異端審問と交差する四つの歴史の道筋」(轟木広太郎)

物理学の原理と法則 科学の基礎から「自然の論理」へ
講談社学術文庫
■世界の真理は、単純明快! てこの原理からE=mc2、量子力学まで全部わかる!■
中学校理科から量子力学まで物理学全体を見渡し、歴史のエピソードや文学作品を引きながら「基本の基本」をわかりやすく伝授。さらに、人間の思考は自然の論理をどこまで捉えられるのか、という根源的問いにまで誘う。宇宙物理学の先端で研究に取り組み、科学とは何かを深く問い続けてきた名手が放つ、画期的入門テキストにして深遠なメッセージ。
「文系のための物理学入門」の決定版!
□単純、簡明、統一、原理主義□
物理学者は、多様で複雑に見える自然だが、真理は意外に単純明快であり、論理を忠実にたどっていけば必ず真理に到達できると信じている。アインシュタインが述べたように、「神は老獪だが、意地悪ではない」のである。そのための自然を解剖していく手法は、本書に書いたような原理・法則・原則に則っている。どのような建築物もレンガ一つひとつの積み重ねから成り立っているように、壮大な物理学の成果も、最も基本的な原理の上に構築されているのである。―本書より
(本書は2011年にPHPサイエンス・ワールド新書より刊行された『物理学の原理と法則』を大幅に改稿・加筆し文庫化したものです)

〈イスラーム世界〉とは何か 「新しい世界史」を描く
講談社学術文庫
ジャーナリズムで、また学問の世界でも普通に使われる用語、「イスラーム世界」とは何のことで、一体どこのことを指しているのだろうか? ムスリムが多い地域のことだろうか、それとも、支配者がムスリムである国々、あるいはイスラーム法が社会を律している地域のことだろうか。ただ単に、アラビア半島やシリア、パレスチナなどの「中東地域」のことを指しているのだろうか? 本書は、高校世界史にも出てくるこの「イスラーム世界」という単語の歴史的背景を検証し、この用語を無批判に用いて世界史を描くことの問題性を明らかにしていく。
前近代のムスリムによる「イスラーム世界」の認識、19世紀のヨーロッパで「イスラーム世界」という概念が生み出されてきた過程、さらに日本における「イスラーム世界」という捉え方の誕生と、それが現代日本人の世界観に及ぼした影響などを明らかにする中で、著者は、「イスラーム世界」という概念は一種のイデオロギーであって地理的空間としては存在せず、この語は歴史学の用語として「使用すべきではない」という。そして、地球環境と人類史的視点から「新しい世界史」を構想し叙述する方法の模索が始まる。
本書は刊行当時、歴史学者・イスラーム学者の間に議論を引き起こし、アジア・太平洋賞特別賞を受賞した。文庫化にあたり、原本刊行後の議論を踏まえて「補章」を加筆。〔原本:『イスラーム世界の創造』東京大学出版会、2005年〕

中国の歴史8 疾駆する草原の征服者 遼 西夏 金 元
講談社学術文庫
「中国の歴史・全12巻」の学術文庫版、第5回配本の第8巻は、中原の「中華王朝」を脅かし続けた北方遊牧民の興亡史。
8世紀半ば、唐王朝を揺るがした「安史の乱」は、600年におよぶ大変動の序奏だった。耶律阿保機のキタイ、李存勗ひきいる沙陀、李元昊の西夏、完顔阿骨打の金。多極化と流動化のはてに、歴史の統合者たる大モンゴル国が浮上する。13世紀に世界史を大きく転回させた「大モンゴルの時代」は、突然訪れたわけではなかった。
中国王朝史のなかで忘れられた英雄・耶律阿保機が、10世紀初頭に建国した「キタイ帝国」すなわち大契丹国は、中華風には「遼」と呼ばれる。現在の中国東北部から東モンゴルを領域とし、北宋を圧迫したが、1125年、金により滅亡する。その後、耶律大石が中央アジアに建国した「第二次キタイ帝国」は、「西遼」「カラ・キタイ」と呼ばれる。タングト族の李元昊が1038年に建国した大夏は、中華からは西夏と呼ばれ、1227年、モンゴルにより滅ぶ。ジュシェン族(女真族)の完顔阿骨打が建国し、北宋を滅ぼした金も、1234年、モンゴルにより滅ぼされる。
そして、チンギス・カンに始まる大モンゴル国は、5代皇帝・クビライの時代にユーラシアの海陸を覆う世界帝国となった。この超域帝国の宗主国を、中華風には「元」と呼ぶ。グローバル化の扉を開き、現代へと続く巨大帝国誕生のドラマ。〔原本:2005年10月、講談社刊〕

貞観政要 全訳注
講談社学術文庫
1300年以上読まれた「統治の教科書」不朽の古典、全文完全新訳。
とても読みやすい平明な訳文と、背景となる歴史がよくわかる解説でおくる、決定版!
□よき君主は諫言に傾聴する□
唐王朝(618-907年)の第二代皇帝にして、王朝の最盛と謳われる七世紀「貞観の治」をなした皇帝・太宗が、広大な版図を治め、王朝を栄えさせるために、臣下と議論を交わし、ときには痛烈な諫言を受け入れた様を描いたのが、この『貞観政要』全十巻四十篇です。
「私の非が明らかにならない理由は、官僚たちが従順で、皇帝の機嫌を損うのを憚かっているためだろうか。そうならないように、私は虚心に外からの忠告を求め、迷いを払いのけて反省しているのである。言われてそれを用いないのであれば、その責任を私は甘んじて受け入れよう。しかし、用いようとしているのにそれを言わないのは、いったい誰の責任であるか。今後は、各自が誠意を尽くせ。もし私に非があれば、直言して決して隠さないように」(本書 巻二「任賢」より)
□「人の上に立つ者」のために書かれた□
太宗が死して60年余が過ぎ、国史編纂に携わる歴史家の呉兢によって編纂されたこの書物は、唐王朝が変革のときを迎えようとする時代にあって、貞観の治世を手本とするよう、当時の皇帝に上進されたものでした。
□日本人も古代から読み継いだ□
平安時代の日本にも伝わると、以来江戸時代を経て現代に至るまで、統治者の心構えを説く必読書として読まれ続けてきました。
徳川家康も明治天皇も読んだと言われる、「主君のための教科書」です。
□ビジネスの智恵として□
現代にも通じる、人材育成、組織統治、コミュニケーション術の要諦を説く一冊として注目されています。
□歴史学の眼で「全文」を読み解く□
『貞観政要』が描くのは「理想の君主」像だけではありません。
長く皇帝の座にあった太宗は、やがて怒りやすくなり、傲慢で贅沢になり、直言を嫌がるようにもなっていきます。
・なぜ編者・呉兢は、そのようなことまで記したのか
・唐王朝はいかなる歴史の中で築かれたか
・実像の皇帝・太宗はどのような人物であったか
歴史学者ならではの鋭い分析とわかりやすい解説で、本書の「本当の意義」を読み取ることができます。
【本書は訳し下ろしです】

ヴァレリー 芸術と身体の哲学
講談社学術文庫
習慣として早朝の数時間、一日のうちいちばん「非社会的」な時間に書き続けられたというヴァレリーの言葉。
膨大な量のそれは人間の生の実相へと肉迫する。作品が装置であるとはどういうことか。時間と行為の関係とは? 詩が身体を解剖するとは?
ヴァレリーのテクストを丹念に読み込み、そこから描き出された芸術と身体と生の関係。
著者の美学・身体論の出発点となった記念碑的力作。解説・細馬宏通。

日本人の原風景 風土と信心とたつきの道
講談社学術文庫
山に富み、森林に覆われ、海に囲まれた列島。そこに棲む日本人は自然の恵みを享受し、生計を立て、カミに礼を尽くしては人生の節目とした。また、参詣・巡礼に言寄せた遊山や漂白・旅の渡世は、楽も苦も味わう深さをもたらした。
近世に固まったそうしたスタイルは、しかし高度経済成長期を境に変容を余儀なくされる。見失われた日本人の暮らしと人生の豊穣はどんな形だったのか。民俗学者がフィールド観察と研究の蓄積をもとに語る。

〈名奉行〉の力量 江戸世相史話
講談社学術文庫
時代劇でおなじみの名奉行や悪代官の意外な実像から、驚くほど便利な江戸の暮らしまで、研究者ならではの視点で江戸の風もあざやかに切り取った短編集。
桜吹雪で知られる「遠山の金さん」の父は、とある試験を転機に異例の大出世を遂げた名官吏だった!?
「おれがわるかつた」、「ゆるせゆるせ」とざっくばらんに詫びる「暴れん坊将軍」吉宗の肉声に、文字通り女房を「借金のカタ」に差し出してしまった旗本、年利一二〇〇%の超高金利金融「烏金」利用者の実態に、宛名に記された「殿」と「様」の格付けをめぐるひと悶着……。
読めばもっと江戸が好きになる。第一人者の篋底から取り出された珠玉の掌編の数々!
(原本:『大江戸世相夜話』中公新書、2003年)
【本書の内容】
はしがき
遠山金四郎の入墨
遠山金四郎の入墨/遠山金四郎父子/江戸の受験参考書/名奉行の「条件」/官職名の由来/銭形平次と目明/親の歳を間違える金四郎
お代官様――悪の代名詞
将軍吉宗の肉声/遊芸を許す田沼意次/お代官様――悪の代名詞/秘薬「熊胆」の値段/「謙譲の美徳」の裏側
二十二時間・二十三日間・三年間/白いカラスは吉兆か/殿と様はどちらが偉いか
大御所の犯罪
大御所の犯罪/無 尽/談合体質の根深さ/拾った金は誰のものか/象をめぐる暗闘/国民の生命の重み/女房を借金のカタに置いても
女髪結い繁盛記
便利すぎて困る/女髪結い繁盛記/江戸の贈答事情/江戸の高利貸し/江戸の女性と証文の怖さ/地獄の沙汰も金次第
放蕩息子の矯正
読み書き算盤/放蕩息子の矯正/「うろたえる」老人たち/天明七年のポスター/上流女性をどう呼ぶか
初出一覧
あとがき
学術文庫版あとがき

中国の歴史7 中国思想と宗教の奔流 宋朝
講談社学術文庫
講談社創業100周年企画「中国の歴史・全12巻」の学術文庫版、第4回配本。この巻では、唐宋変革期から南宋滅亡までを政治史を概観するとともに、思想文化に焦点を合わせて宋代中国を考察する。著者によれば、中国四千年の歴史のなかで、日本人にもっともなじみやすいのは宋代であり、日本の生活習慣や伝統文化の奥底に「宋」は居着いているという。
大唐帝国を揺るがせた安史の乱から200年、五代乱離のあとを承けて宋朝が建てられた。太宗の下、中央集権的官僚国家が確立、科挙制度の改革により広範な階層から科挙官僚が輩出した。文治主義をとったことの功罪はいかなるものだったか。
なかでも、朱子学の公認は宋という王朝を象徴する出来事だったが、それはどのような背景、環境から生まれ、受容されていったのか。その過程と、そこに関わる士大夫たちの精神について詳述する。
北方の異民族王朝に対し絶えず軍事的劣勢にありながらも、後世まで規範となる政治・社会・経済システムを作り上げた宋朝は、文化の華がひときわ咲き誇った時代だった。宋代に起源をもつ文化の新潮流、陶磁、喫茶、書画、文学などにも目を向け、宋代像を描き出す。〔原本:2005年7月、講談社刊〕

パリ歴史探偵
講談社学術文庫
景色にまぎれた不自然な段差、小さな抜け道。かすかな違和感に導かれ、古地図を広げて一九世紀のガイドブックや文学作品を繙けば、モーパッサン、ランボー、ゾラが暮らした時代の空気がみるみる立ち上る! 当時の風習や世相までをも、ユーモラスな視点で活写。中世から一九世紀を自在に飛び回る旅へ、中世・ルネッサンス研究の泰斗が貴方を誘う。
(一部抜粋)
本書は、パリの街角のさりげない光景のなかに、この都市の記憶を、あるいはこういってよければ、パリという馥郁(ふくいく)たる香りの酒瓶の底に沈んだ澱のようなものをたどろうとした試みである。「神々は細部に宿れり」をモットーにして、半ば意識的に、モニュメントとはいいがたい些細な「モノ」をめぐるささやかなる探偵紀行を展開してみた。――「プロローグ」より
目次
プロローグ
1章 三つの壁、三つの時代・
1 中世に飛ぶ
2 古地図のなかのパリ
3 入市税関の時代
●コラム『タブロー・ド・パリ』
2章 パサージュを渡り歩く
「昔の香りただようショワズール小路よ」/ヴァリエテ座の楽屋口
/パサージュ対ギャルリー/ジュフロワ小路からヴェルドー小路へ
/「ソルボンヌ小路」を発見!/セピア色のパサージュ
●コラム『ナナ』
3章 昔のガイドブックから
1 『パリ= ディアマン』一八六七年版 ●コラム『居酒屋』
2 局留め便、ひとむかし前のメール ●コラム『肉体の悪魔』
3 写真館の時代
「小さな肖像」/ランボーを撮った写真家/「立体写真」ブーム
4章 まぼろしの公衆トイレを求めて
5章 記憶の場としてのマルヌ川
1 『居酒屋』の時空間
2 マルヌ川の岸辺で思うこと
3 思いがけず廃線歩き
6章 印象派の散歩道
学術文庫版付録「青春のカルチエ・ラタン」
あとがき
本書は2002年、講談社現代新書より刊行された『パリ歴史探偵術』を改題、一部、加筆修正したものです。

《英雄》の世紀 ベートーヴェンと近代の創成者たち
講談社学術文庫
ベートーヴェンはナポレオン戴冠の知らせを聞いて作曲中の第三シンフォニーの楽譜を床にたたきつけたといいます。「ボナパルト」なるタイトルを持つはずだったこの交響曲は標題をあらため、英雄交響曲《シンフォニア・エロイカ》として発表されました。ナポレオンに落胆したものの、革命の時代に終止符をうつ「英雄」を待望していたのです。
ドイツ人作曲家ルートヴィヒ・ファン・ベートーヴェン(1770-1827年)の生きた18世紀から19世紀にかけてのヨーロッパは、革命の進行する激動の世紀でした。この時代の人々にとって、自前の代表者をもちえないドイツですら、「英雄」とは実在する観念でした。どのようにして英雄像はリアリティを持ったのでしょうか。
馬上のナポレオンを目撃したヘーゲル。皇帝となったナポレオンに謁見したゲーテ。
ナポレオンという「英雄」は幻想にすぎなかったのか。ベートーヴェンの生涯をたどりつつ同時代の偉人たちをとおして、「英雄の世紀」を臨場感あふれる筆致で描きます。
西洋史の泰斗が達意の文章でおくる近代創成のロマン!!
【本書の内容】
はじめに
第一章 英雄(エロイカ)の世紀
第二章 啓蒙の賢人から普遍の天才へ
第三章 啓蒙都市民の誕生
第四章 ヨーロッパ国際関係のなかのドイツ
第五章 ナポレオン革命
第六章 ナポレオン・ショック
第七章 市民と英雄
第八章 古典主義からロマン主義へ
第九章 静穏の一八二〇年代
主要参考文献
学術文庫版あとがき
関係年表

中国の歴史6 絢爛たる世界帝国 隋唐時代
講談社学術文庫
講談社創業100周年企画「中国の歴史・全12巻」の学術文庫版。第3回配本、第5巻と同時発売の第6巻は、古代東アジアに君臨した隋唐帝国の興亡史。
後漢末以来、400年にわたった分裂は、589年、隋によって統一された。2代皇帝・煬帝は大運河を開鑿するなど強権を発動したが、高句麗遠征に失敗して求心力を失う。煬帝の死後、3代恭帝から禅譲された李淵は唐王朝を樹立。2代太宗は、均田制・租庸調・府兵制を中心とする律令体制によって国力を充実させ、国際都市・長安を中心とする当時世界最高の文明国を現出させた。唐は一時、中国史上唯一の女帝・則天武后の周朝により中断するが、第6代玄宗により中興を果たすと、唐詩の李白・杜甫、書の顔真卿らを輩出して文化面でも繁栄を極めた。しかし、8世紀半ば、突厥の母とソグドの父を持つ安禄山の反乱、さらに9世紀後半の黄巣の乱へと混乱の度を加え、907年、朱全忠の簒奪により唐王朝は滅亡する。
シルクロードと都市の発展、女性たちの進出、日本からの遣唐使と円仁の求法の旅、朝鮮・ウイグル・チベットなど周辺諸国の動向もまじえ、世界帝国の300年を鮮やかに描き出す。
〔原本:2005年6月、講談社刊〕

中国の歴史5 中華の崩壊と拡大 魏晋南北朝
講談社学術文庫
講談社創業100周年企画「中国の歴史・全12巻」の学術文庫版。第3回配本の第5巻は、220年の後漢滅亡から隋の天下統一(589年)にいたる大分裂の時代を取り上げる。
前漢・後漢の400年の大帝国は、後漢末期の混乱の中に崩壊し、魏・蜀・呉が争う三国時代を経て、晋の司馬炎による再統一をみるが、まもなく匈奴・鮮卑・羯・羌など異民族の大侵攻を招いていわゆる「五胡十六国」の大混乱時代に突入する。
華北はやがて鮮卑が建てた北魏が統一し(439年)、東魏、西魏、北斉、北周と興亡を繰り返す。一方、江南には漢民族の王朝である宋に続き、斉、梁、陳と次々に王朝が交替する。胡漢の勢力がたがいにしのぎを削るなかで、華北では雲岡や龍門の壮麗な石窟寺院が営まれ、江南には建康(現在の南京)を中心に陶淵明、顧ガイ之らで名高い六朝文化が栄える。
この魏晋南北朝時代は、日本列島には邪馬台国や倭の五王が登場し、朝鮮半島には高句麗・百済・新羅が興って、東アジアの「世界秩序」が形成された。その中心をなす「中華」も分裂と融合を繰り返し、非漢民族が漢化(中国化)するなかで拡大し、新たな中華世界を形作っていったのである。現代に続く中華意識と民族問題を視野に、東アジア世界の秩序の源流へとさかのぼる一冊。〔原本:2005年2月、講談社刊〕

渋沢栄一「青淵論叢」 道徳経済合一説
講談社学術文庫
〈渋沢栄一が"怒濤の人生"を振り返り、後世の私たちに語りかける〉
〈「最後の肉声」に込められた希望のメッセージ〉
時勢が緊迫する昭和のはじまりにあって、人生の黄昏を迎えていた「日本資本主義の父」は、後世に何を言い遺こそうとしたか。
「家訓」にはじまり、倫理観、経済観、政治観、人生観など広汎なテーマについて32項目にわたって、幕末維新の経験をふまえ、日本の明日を憂いながら語り尽くした談話集「青淵論叢」を、渋沢という人物を知り尽くした鹿島茂が読みやすく現代語訳し、さらに懇切に解説。
「金というものは社会の力を表彰している役にたつ道具ですから、これを貴ぶのは正当なことですが、しかし、必要な場合にはよくこれを消費しなければなりません。消費はもちろんよいことなのです。よく集めてよく散じ、もって社会を活発にし、それによって経済界の進歩を促すのはまさに有為の人が心がけなければならないことなのです。真に経済のよくわかった人は、よく集めてよく散じるようでなければなりません。よく散じるとは正当に支出することです。金を善用することです」(本書「富者の要務」より)
「江戸の封建主義に代わって明治・大正の資本主義が登場しても、官は官のもの、民は民のものという疎外的分担体制はよりひどくなっている。
これは、自分にも責任があるのだから、なんとしても最終解決しなければならない。
では、どうすればいいのか?
これが、日本の資本主義をほとんどゼロから独力で作り上げた渋沢が古希にあたって再度、自分に問いかけた疑問だったのである」(本書「編訳者解説」より)
【本書の主な項目】
立身出世の秘訣/信用を得る人得ない人/叱言(こごと)の云い方/真の成功とは何か/予の人物鑑識法/大国民は斯う有り度い/外来思想と咀嚼消化の力/国家観念と世界主義/政治経済と道徳観念/道徳と経済の合一説/事業経営に必須の条件 ほか

古代哲学史
講談社学術文庫
本書は、20世紀の日本を代表する哲学者・田中美知太郎(1902-85年)による生前最後の単行本です。
古代ギリシア哲学の専門家として、数々の著作や翻訳を送り出すとともに、日本西洋古典学会の設立に携わるなど、日本の哲学界の大きな礎を築いた著者が最後に残したのは、「古代哲学史」という単刀直入なタイトルを冠した1冊でした。全三部から成る本書の第I部では、万物の始源は「水」だと説いたタレス(前585年頃)に始まり、アナクシマンドロス、アナクシメネス、ヘラクレイトス、エンペドクレス、アナクサゴラスなどを経て、ソクラテス、プラトン、アリストテレスに至る哲学史の流れを大づかみにしてみせる「西洋古代哲学史」が収録されています。文庫版で100頁にも満たない分量で要点を的確に押さえた思想史を描く力量は、まさに出色です。
第II部では、古代哲学をより深く知りたいと願う読者のために碩学がアドバイスをする、という趣きを帯びています。残された哲学者たちの著作に触れる時に注意すべきこと、そして参考書や研究書を含めた読書案内まで、実践的な哲学ガイドとして役立つことでしょう。
そして、第III部には、著者が何度も改訂を繰り返してきたヘラクレイトスの残された断片の日本語訳が収録されています。ここに読むことのできる言葉は、時に謎めき、時に不思議な魅力を放つ、古来、多くの人たちを惹きつけてきたものです。
著者がその最期に読者に向けて贈った本書には、長年月にわたる研鑽の果実が惜しみなく凝縮されています。近年は政治論や文明論などに光をあてられることの多い偉大な学者の神髄に触れられる絶好の1冊です。学術文庫版には、田中美知太郎に思い入れを抱いてきた國分功一郎氏の解説を収録し、文字どおりの決定版となります。
[本書の内容]
I
西洋古代哲学史
古代アトム論の成立
II
古代哲学 一
古代哲学 二
III
ヘラクレイトスの言葉
あとがき
解 説(國分功一郎)

経済学の思考法 稀少性の経済から過剰性の経済へ
講談社学術文庫
格差拡大、雇用不安、デフレ、グローバリズムの停滞……。「構造改革」以降、実感なき好景気と乱高下する日本経済。過剰な貨幣発行がもたらす問題、「複雑な”経済現象”」と「理論重視の”経済学”」の乖離など、現代資本主義が直面する困難を徹底的に検証。
アダム・スミスから金融理論、リーマンショックからアベノミクスまで、経済学の限界と誤謬を提示する。
内容抜粋
「経済学」がひとつの思想でありイデオロギーであるとすれば、今日の支配的な経済学の考え方とは異なった「経済」についての見方はできないか。「稀少な資源の配分をめぐる科学」というような経済学の典型的な思考方法ではない、別の思考様式はないのか、ということだ。―――学術文庫版「はじめに」より
目次
学術文庫版「はじめに」
第1章 失われた二〇年――構造改革はなぜ失敗したのか
学術文庫付論
第2章 グローバル資本主義の危機――リーマン・ショックからEU危機へ
学術文庫付論
第3章 変容する資本主義――リスクを管理できない金融経済
第4章 「経済学」の犯罪――グローバル危機をもたらした市場中心主義
第5章 アダム・スミスを再考する――市場主義の源流にあるもの
第6章 「国力」をめぐる経済学の争い――金融グローバリズムをめぐって
第7章 ケインズ経済学の真の意味――「貨幣」の経済学へ向けて
第8章 「貨幣」という過剰なるもの――「稀少性」の経済から「過剰性」の経済へ
第9章 「脱成長主義」へ向けて――現代文明の転換の試み
あとがき――ひとつの回想
学術文庫版あとがき
2012年刊行、講談社現代新書『経済学の犯罪』を改題、
大幅加筆修正したものです

中国の歴史4 三国志の世界 後漢 三国時代
講談社学術文庫
講談社創業100周年企画「中国の歴史・全12巻」の学術文庫版。第2回配本、第3巻と同時発売の第4巻は、後漢末期から魏・呉・蜀の三国時代に焦点を当てる。
日本人にもっとも長く、広く親しまれてきた外国文学、『三国志』に語られる歴史は、どれほど史実を伝えているのだろうか。中国文学の研究者である著者が、小説『三国志演義』を手掛かりに、大抗争時代の戦乱と外交、文化と社会を解き明かす。
著者によれば、この時代は、現代にいたる中国の歴史を知るうえで、見逃せない重要性を持っているという。たとえば、小説では悪役の魏の曹操は、卓越した改革者であり、その子の曹丕、曹植は優れた詩人だった。曹操父子を中心とする文学運動が、後の唐詩の原点となったのである。また、広大な中国に、統一帝国を強く指向する理念が確立したのは、この時代だった。さらに、中国思想の骨格を成す儒教・仏教・道教が定着し、三教の間で論争と交流が行われるようになったのも、後漢末から三国時代のことだった。
また、陳寿の正史『三国志』や羅貫中の『三国志演義』では脇役だった呉こそが、実はこの時代を演出した影の主役だという。邪馬台国と朝鮮半島を含む東アジアの動乱は、現代に何をもたらしたか。文学から歴史を読む、中国通史シリーズとしては異色の一巻。〔原本:2005年、講談社刊〕
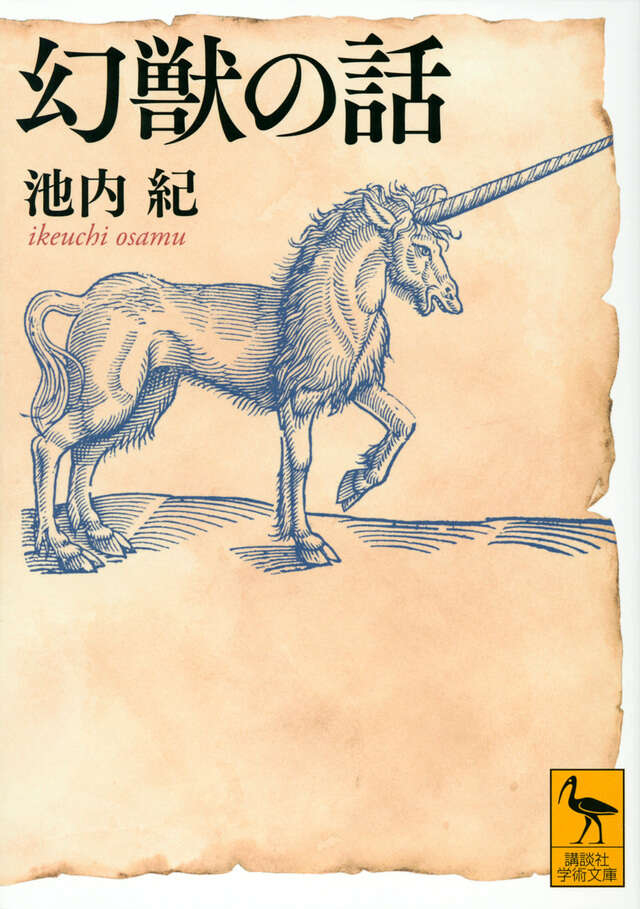
幻獣の話
講談社学術文庫
「むだで横道にそれた知識には一種のけだるい喜びがある」。ホルヘ・ルイス・ボルヘス(1899-1986年)は、『幻獣辞典』の序でそう語る。
マルコ・ポーロがスマトラで目にした一角獣、フランスの教会の壁面に刻まれた大耳人間、日光東照宮を彩る幾多の霊獣に、目まぐるしく姿を変える千変万化のバルトアンデルス.......。古今東西の書物に記された、不思議で興味深い生きものたちをめぐるエッセイは、まさにボルヘスが語る「喜び」に満ちている。
龍のように、洋の東西を超えて同じような想像上の生きものが生み出されるのはなぜか。人間はなぜ、くり返し、異様なもの、奇妙なもの、ときにはグロテスクなものを生み出したがるのか――。軽妙洒脱な語り口で繰り広げられる世界に引き込まれていくにつれて、私たちの意識に、あるいは無意識のうちにこそひそむ「幻の獣」の姿が浮かび上がる。
古代中国の『山海経』から、二十世紀にカレル・チャペックが生み出したロボットに至るまで、書物を広く深く愛した著者ならではの幻獣奇譚集。
1 一角獣――マルコ・ポーロが見たもの
2 アジアとヨーロッパ――幻獣という知の遺産
3 不思議な生きもの、不思議な人――狂気と文学のあいだ
4 幻獣紳士録1
5 幻獣紳士録2
6 百鬼の奇――日本の幻獣
7 霊獣たちの饗宴――日光東照宮の場合
8 中国の宝の書――『山海経』入門
9 私という幻の獣――寺山修司の夢
10 ゴーレムからロボットへ――二十世紀の幻獣

語りえぬものを語る
講談社学術文庫
哲学の魅惑!
「相対主義の言わんとするところはまったく正しい。ただ、それは語られえず、示されている。」
相貎論、懐疑論、ウィトゲンシュタインの転回、過去、隠喩、自由――スリリングに展開する著者会心の「哲学的風景」。【解説:古田徹也氏】
●猫は後悔するか
●世の中に「絶対」は絶対ないのか
●霊魂は(あるいは電子は)実在しうるのか
●相対主義はなぜ語りえないのか
●意味はない、しかし相貎はある
●懐疑論にどう答えればよいのか
●私にしか理解できない言葉
●何が語られたことを真にするのか
●自由という相貎
●科学は世界を語り尽くせない
――本書目次より