講談社現代新書作品一覧

黒田官兵衛 作られた軍師像
講談社現代新書
来年の大河ドラマの主人公黒田官兵衛。その有能さは豊臣秀吉、徳川家康をも恐れさせたと言われています。本能寺の変では有名な中国大返しを実現させたなど多くのエピソードが残っていますが、それらは主として江戸時代に作られたものです。官兵衛には「軍師」という言葉がついてまわりますが、この「軍師」という言葉も戦国時代にはなく、後世につくられたものでした。本書は信頼できる史料をもとに、黒田官兵衛の実像に迫ります。
来年の大河ドラマの主人公黒田官兵衛。その有能さは、豊臣秀吉、徳川家康をも恐れさせたと言われる、戦国から江戸前期にかけての大名です。本能寺の変で、信長が斃れ悲嘆にくれる秀吉に、「天下を取る好機です」とささやき、有名な中国大返しを実現させたなど、多くのエピソードが残っています。しかし、それらは主として江戸時代に作られたものがほとんどです。官兵衛といえば、「軍師」という言葉がついてまわりますが、この「軍師」という言葉も、戦国時代にはなく、後世につくられたものだったのです。本書は、信頼できる史料をもとに、黒田官兵衛の実像に迫る一冊です。

絆の構造 依存と自立の心理学
講談社現代新書
変質する「標準家族」、変貌する「結婚制度」。揺らぐ「男性稼ぎ主型」社会の中で、専業主婦は少数派となり、単独世帯も増加を続ける。日本の家族と社会の関係は大きく変化をしているようだ。人生九〇年時代を迎えた日本の「人間関係」の現在を、「絆」というキーワードを軸に生涯発達心理学から読み解く。個人が自分らしいネットワークを築き新たなつながりをつくる一歩を踏み出すための好著。(講談社現代新書)
変質する「標準家族」、変貌する「結婚制度」。
揺らぐ「男性稼ぎ主型」社会の中で、専業主婦は少数派となり、単独世帯も増加を続ける。日本の家族と社会の関係は大きく変化をしているようだ。
人生九〇年時代を迎えた日本の「人間関係」の現在を、「絆」というキーワードを軸に生涯発達心理学から読み解く。
「絆」は、東日本大震災以降、日本中で再注目されている。特に家族の「絆」、地域の「助け合いの絆」を、政府をはじめ、メディアも人々に訴えている。
しかし、我々日本人は、血縁、家族縁、地縁、社縁などに縛られすぎていないだろうか。他人とうまくコミュニケーションをとれることを高く評価し、他人との会話がないことを問題視するような、対人行動についての社会通念に翻弄されすぎていないだろうか。
この伝統的な縛りを解き、通念をひとまず無視し、無理に人とつながることを一端止めてはどうだろう。自分が生きる上で大切な人々を選択し、納得できるやり方でつきあえるように、人生を見直す時期にきているのではないだろうか。
本書では現在の日本の家族関係、仲間・友人・恋人との関係など、「人間関係」の構成や愛情のネットワークをわかりやすく解説し、これからの人と人がつながる仕組みを考察する。
その上で、個人が自分らしい人間関係のネットワークを築く必要性を説く。
新たなつながりをつくる一歩を踏み出すための一冊。

僕がメディアで伝えたいこと
講談社現代新書
実は、いじめを受けていた小中学校時代。就職活動では民放の入社試験に落ちまくり、なんとか入れたNHK時代、街中では「嘘つき」と怒鳴られ、社内では「給料泥棒」呼ばわりされた。会議では「黙って原稿を読めばいい」「打ち合わせにないことはやるな」と叱責されたこともあった。それでもくじけず、あきらめなかった理由とは何か。元NHKアナウンサー、堀潤の発想と行動の「原点」――。(講談社現代新書)
NHKのアナウンサーの多くはあらかじめ決められた段取りに従い、リハーサルを何回もしてから本番に臨むというように、決まりきったことしかやらないし、台本に書かれていないことはまず話さない。
そのため、番組では生放送が発するようなハプニング感は感じられないし、中継番組もどこか漂白された感を否めない。
僕にとっては、それがおもしろくなかった。
(中略)
あるお祭りの中継で、実行委員会のAさんに話を聞くシーンでのこと。
彼は、途中までは台本を覚えていたのだろう。
ペラペラと話すことができたが、ある時点で言葉に詰まり、続くはずのコメントが出なくなってしまった。
通常、NHKのアナウンサーならこんな時、「つまり、○○ということですよね?」などと言って必死に取り繕おうとする。
結果、その場には微妙な空気が漂う。
その気まずい雰囲気は、テレビの前のみなさんにも伝わってしまうものだ。
だからその時、僕はこうフォローした。
「Aさん、台本を一緒に読みましょうか。リハーサルしていても、生放送はやっぱり緊張しますよね」
とにかく楽しい放送をしたかった。
嘘をつき、取り繕い、いいように見せかける放送ではなく、正直な放送をしたかった。
だからこそ、こんなふうにテレビの裏側を「ド正直」に流す手法を僕は心がけてきた。(「第1章」より)
---------------------------------
いじめを受けていた小学校時代のあだ名は、「なんでやねん君」。
バイオリンを習わされていた著者は半ズボンを履き、襟付きのシャツを着ていた大人しい「お坊ちゃん」でしかなかった。
就職活動では民放の入社試験に落ちまくり、なんとか入れたNHK時代、街中では「嘘つき」と怒鳴られ、社内では「給料泥棒」呼ばわりされたことがあった。
会議では「黙って原稿を読めばいい」「打ち合わせにないことはやるな」と叱責されたこともあった。
それでもくじけず、あきらめなかった理由とは何か。
元NHKアナウンサー、堀潤の発想と行動の「原点」――。

フルーツひとつばなし おいしい果実たちの「秘密」
講談社現代新書
単に空腹を満たす食べ物としてだけでなく、健康を守るふしぎな力を宿しているフルーツ。しかし、現代人の多くは、その効用や魅力については無知である。本書は、何気なく口にしているフルーツの品種、効用、果実生成のしくみ、品種改良など広範な知識を網羅した、現代人のための『フルーツの教科書』というべき作品。「ミスター植物学」として知られる田中修・甲南大教授が、フルーツの面白知識を軽妙な文章で巧みに解説する。
単に空腹を満たす食べ物としてだけでなく、健康を守るふしぎな力を宿しているフルーツ。しかし、現代人の多くは、その効用や魅力については無知である。本書は、何気なく口にしているフルーツの品種、効用、果実生成のしくみ、品種改良など広範な知識を網羅した、現代人のための『フルーツの教科書』。 「ミスター植物学」として知られる田中修・甲南大教授が、フルーツの面白知識を軽妙な文章で巧みに解説する。「ふじリンゴの名前の由来は育成者が山本富士子のファンだった」「温州ミカンを食べるとγGTPの値が改善する」など、興味深いエピソード満載。新宿高野の全面協力で、豊富なカラー写真を収録しており、見ているだけでも楽しい。『植物はすごい』(中公新書)の著者による書き下ろし新作
本書で取り上げる主なフルーツ
温州ミカン 種なしミカンの秘密
イチゴ 品種改良で誕生した新品種「スカイベリー」
リンゴ 「自家不和合成」とは?
ブドウ フレンチパラドックスの謎
モモ 「魔よけの果実」とは?
ナシ 英語名は「砂のようなナシ」
カキ なぜカキは品種改良されないのか
オウトウ 「佐藤錦」のタネを育てたら?
メロン マスクメロンとマスカットの関係は?
スイカ 英語名は、「水分の多い瓜」
パイナップル パイナップルは、リンゴ味?
バナナ メモに使えるバナナの皮 収穫されるのは、緑色
レモン 橘類で生産高1位
キウイ 1本では、実がならない果樹
ブルーベリー 目にやさしいアントシアニン
クリ ブランドは接ぎ木で増やす
ビワ 「タネなしビワ」の誕生
イチジク 世界最古の栽培作物

歌舞伎 家と血と藝
講談社現代新書
当代の役者はいかなる歴史を背負って舞台に立っているのか? 明治から現在まで、血と家と藝が密接にからみあう歌舞伎の世界には、波瀾万丈の人間ドラマがあった。歌舞伎座の頂点を目指す七大名家の興亡を描きつくした大著。歌舞伎を観るのが、もっと面白くなる! (講談社現代新書)
当代の役者はいかなる歴史を背負っているのか?
明治から現在まで、歌舞伎の世界には、
世襲と門閥が織りなす波瀾万丈のドラマがあった――。
歌舞伎を観るのがもっと楽しくなる本。
○市川團十郎家はなぜ特別なのか?
○松本幸四郎家は劇界の毛利三兄弟?
○中村勘三郎の死は何を意味するか?
○偶数系片岡仁左衛門の悲劇とは?
○栄華を極めた二人の中村歌右衛門の戦略とは?
○尾上菊五郎家の歴史は繰り返す?
○新しい歌舞伎座を担うのは誰か?
「二〇一三年四月二日、歌舞伎座新開場柿葺落の初日に出かけた。この日、いちばん盛り上がったのは、人間国宝や藝術院会員たちの重厚な演技ではなく、中村勘九郎の息子・七緒八が花道を歩いて出てきた時だった。セリフを言うわけでもなければ見得を切るわけでもない。ただ歩いて出てきただけだ。……それなのに、「中村屋」との掛け声と万雷の拍手――こういう光景は歌舞伎ならではのものだろう。こういう世界は、たしかに入りにくい。だが、入ってしまえば、ひとりの幼児の背後にいる何世代にもわたる歴史が見えて、それだけで面白い。」(あとがきより)

仏教の真実
講談社現代新書
釈迦がほんとうに伝えたかったこと。●釈迦は霊魂の存在をいかにとらえたか?●「人生は苦」とはどういうことか?●往生、仏滅、渡世の本来の意味とは? 神と仏の違いとは? 愛とは、苦とは、煩悩とは? 現代日本で常識のように考えられている思想、習慣、言葉の本来の意味を平易に解説。(講談社現代新書)
釈迦がほんとうに伝えたかったこと
●釈迦は霊魂の存在をいかにとらえたか?
●「人生は苦」とはどういうことか?
●往生、仏滅、渡世の本来の意味とは?
神と仏の違いとは? 愛とは、苦とは、煩悩とは?
現代日本で常識のように考えられている思想、習慣、言葉の本来の意味を平易に解説。

宇宙はなぜこのような宇宙なのか――人間原理と宇宙論
講談社現代新書
かつて科学者の大反発を浴びた異端の考え方――「人間原理」。この宇宙は人間が存在するようにできている、という一見宗教のような見方が、21世紀に入った今、理論物理学者のあいだで確実に支持を広げている。なぜか? 宇宙をめぐる人類の知的格闘の歴史から最新宇宙論までわかりやすく語る、スリリングな科学ミステリー。科学書の名翻訳で知られる青木薫の初の書き下ろし! (講談社現代新書)
科学書の名翻訳で知られる青木薫、初の書き下ろし!
「この宇宙は人間が存在するようにできている!?」
かつて科学者の大反発を浴びた異端の考え方は、なぜ今、支持を広げているのか。
最新宇宙論の世界で起きつつあるパラダイム・シフトの全貌をわかりやすく語る、
一気読み必至のスリリングな科学ミステリー。
【目 次】
第1章 天の動きを人間はどう見てきたか
第2章 天の全体像を人間はどう考えてきたか
第3章 宇宙はなぜこのような宇宙なのか
第4章 宇宙はわれわれの宇宙だけではない
第5章 人間原理のひもランドスケープ
終 章 グレーの階調の中の科学

会社を変える分析の力
講談社現代新書
いまやビジネスの世界では、「データ分析が競争を制す」と言われる時代。しかしその一方で、高い分析ソフトを買ったものの、宝の持ち腐れで終わっているという会社も少なくない。では、分析力を武器にできる会社は何が違うのか? また分析力を武器にできる個人は何が違うのか? 第一人者が丁寧にその違いを解き明かす。(講談社現代新書)
いまやビジネスの世界では、「データ分析が競争を制す」と言われる時代。
そのために必要なのが「データ分析」。
データ分析は、たしかに使いようによっては、仕事の効率化、売上大幅アップなど、企業を変革するくらいのインパクトを持つ。
しかしその一方で、高い分析ソフトを買ったものの、宝の持ち腐れで終わっているという会社も少なくない。
また、いくら分析の得意な人間を増やしてもそれだけで実績が上がるわけでもない。
では、分析力を武器にできる会社は何が違うのか?
また分析力を武器にできる個人は何が違うのか?
第一人者が丁寧にその違いを解き明かす。
著者河本氏は2013年8月、日経情報ストラテジーが選ぶ第1回データサイエンティスト・オブ・ザ・イヤーを受賞!

ヒゲの日本近現代史
講談社現代新書
江戸時代中期には、ヒゲありが幕府によって禁止されたことがあります。しかし、明治時代になると、一転してヒゲありが大流行し、欧米のさまざまな型が取り入れられていきます。だが大正時代になると、今度はヒゲなしが増え、日中戦争が始まると、またヒゲありが増え……、と、ヒゲのある/なしだけでも時代性を窺い知ることができるのです。つまり、ヒゲが時代を映す鑑とも考えられるのです。ヒゲに見える興味深い日本近代史。
当たり前のことですが、ヒゲは基本的に男性にしか生えません。ここ10年ぐらいでこそ、ヒゲのある/なしは、ファッションのひとつとしてみなされるようになりましたが、それこそ第二次世界大戦後の現代にあっても、ヒゲありはビジネスマナーに反すると認識されていました。さらに時代を遡れば、江戸時代中期に「大ヒゲ禁令」が出され、ヒゲありは幕府によって禁止されました。しかし、明治時代になると、一転してヒゲありが大流行し、欧米のさまざまな型(スタイル)が取り入れられていきます。だが大正時代になると、今度はヒゲなしが増え、日中戦争が始まると、またヒゲありが増え……、と、ヒゲのある/なしだけでも時代性を窺い知ることができるのです。
すなわち、ヒゲを蓄えることは男らしさや権威の象徴と考えられるわけですが、ある時代には公権力によってヒゲが禁止・抑制されたこと、またある時代には公権力自らが権力性を誇示するために利用したことなどを知ることで、ヒゲが時代を映す鑑とも考えられるのです。
ヒゲに見える興味深い日本近代史。

まんが 哲学入門――生きるって何だろう?
講談社現代新書
「生きるってなんだろう?」――誰もが一度は考えたことのある問いに、「時間」「存在」「私」「生命」の4つのテーマから迫っていく。難しいことばをほとんど使わず、「まんまるくん」と「先生」の二人の掛け合いの形から、哲学の根本問題をゆっくりと解きほぐしていく哲学入門書。(講談社現代新書)
どうして時間は過ぎていくの?
「ある」ってどういうこと?
どうして人は死ぬの?
「私」って何?
誰もが一度は考えたことのあるような哲学の疑問を、「まんまるくん」と「先生」の楽しい対話から考える。
「生きるってなんだろう?」──誰もが一度は考えたことのある問いに、「時間」「存在」「私」「生命」の4つのテーマから迫っていく。難しい言葉を使わず、「まんまるくん」と「先生」の二人の掛け合いの形から、哲学の根本問題をゆっくりと解きほぐしていく哲学入門書。
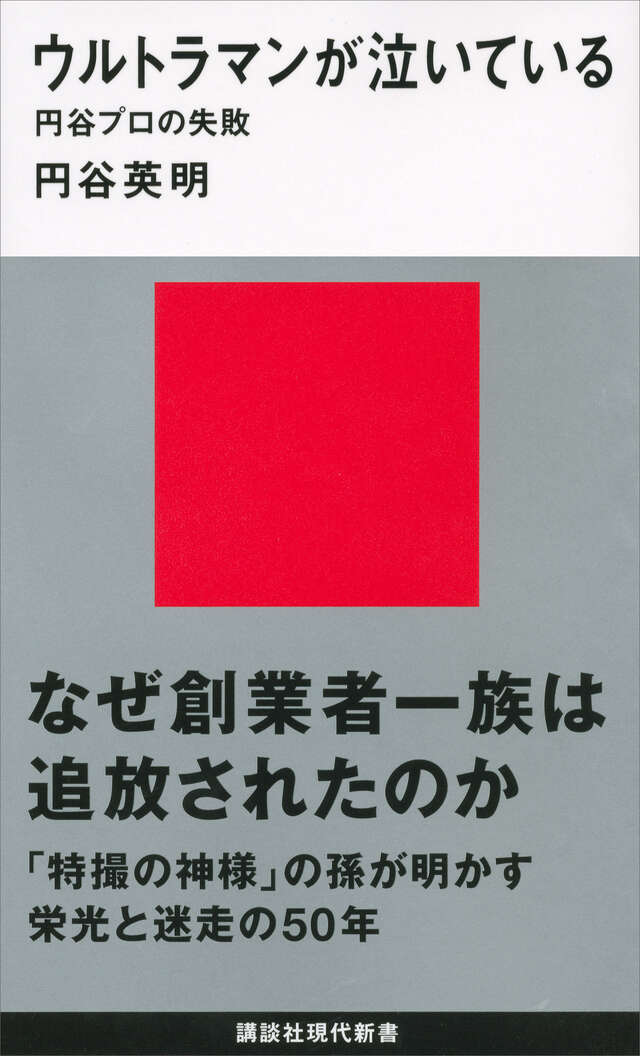
ウルトラマンが泣いている――円谷プロの失敗
講談社現代新書
1960年代から80年代にかけて、多くの子どもたちが夢中になったウルトラシリーズ。ミニチュアや着ぐるみを駆使して、あたかも実写のように見せる独自の特撮技術を有し、日本のみならず世界の映像業界をリードしてきたはずの円谷プロは、なぜ、乗っ取られてしまったのか。(講談社現代新書)
1960年代から80年代にかけて、多くの子どもたちが夢中になったウルトラシリーズ。
ミニチュアや着ぐるみを駆使して、あたかも実写のように見せる独自の特撮技術を有し、
日本のみならず世界の映像業界をリードしてきたはずの円谷プロから、
なぜ、創業者一族は追放されたのか。
「特撮の神様」と呼ばれた円谷英二の孫にして、
「円谷プロ」6代社長でもある円谷英明氏が、
「栄光と迷走の50年」をすべて明かします。
----------------------------------------------------------------------
われわれ円谷一族の末裔は、祖父が作った円谷プロの経営を
全うすることができませんでした。
現存する円谷プロとは、役員はおろか、資本(株式)も含め、
いっさいの関わりを断たれています。
これから、約半世紀にわたる円谷プロの歩み、真実の歴史を明かそうと思います。
その中には、今もウルトラマンを愛してくださる皆さんにとって、
あまり知りたくないエピソードも含まれているかもしれません。
成功と失敗、栄光と迷走を繰り返した末に、会社が他人に渡ってしまった背景には、
一族の感情の行き違いや、経営の錯誤がありました。
私も含め、どうしようもない未熟さや不器用さがあったことは否めません。 (「はじめに」より)

ツール・ド・フランス
講談社現代新書
世界最大の自転車レース「ツール・ド・フランス」のはじまりは、1903年。新聞の拡販キャンペーンとして実施されたことに由来する。そして、2013年6月29日から開幕する大会でちょうど100回目を数える。本書では、歴史を積み重ねてきたツール・ド・フランスのスポーツとしての魅力を、これまでの名勝負・名選手にまつわるエピソードから抽出し、歴史を育んできたフランス、ひいては欧州文化の土壌を紹介する。
ここ数年、ヘルシー志向の高まりやエコの観点から、自転車に乗るサイクリストたちが急増、自転車ブームが到来している。実は、これが日本におけるブームの3度目で、高度経済成長期において青春を満喫する「銀輪サイクリングブーム」が最初、1985年にNHKが特集で放送したことがきっかけで「ロードレーサーブーム」が起きたのが2回目である。
その2回目のブームを巻き起こした放送というのが、世界最大の自転車レース「ツール・ド・フランス」である。「ツール」とは「一周する」という意味のフランス語で、文字どおりフランス全土を約3週間にわたって自転車で一周する。途中、数々の名場面の舞台となったアルプスやピレネーの山々を駆け上ったりし、総距離はじつに3600kmにも及ぶ。
そんな壮絶なレースのはじまりは、1903年。スポーツ新聞の拡販キャンペーンとして実施されたことに由来する。以後、二度の世界大戦による中断をはさんだものの、今年2013年6月29日から開幕する大会でちょうど100回目を数える。
本書では、100回を数えるまで歴史を積み重ねてきたツール・ド・フランスのスポーツとしての魅力を、これまでの名勝負・名選手にまつわるエピソードから抽出し、同時に、歴史を育んできたフランス、ひいては欧州文化の土壌を紹介する。
近年、南米や東欧の選手たちの躍進が目覚ましいなか、日本人選手の活躍も記憶に新しい。アームストロングのドーピングによる7連覇剥奪といった事件もあったが、新たな世紀に突入するツール・ド・フランスの魅力を一冊に。

ラノベのなかの現代日本 ポップ/ぼっち/ノスタルジア
講談社現代新書
気がつくと、ラノベ出身作家がメジャーシーンで活躍していたり、作品がハリウッドで映画化されたり。日本文化にもじわじわと影響をもたらしている。その巨大で寡黙なラノベ作品群だが、読者層が限られているからこそ、内容の変容をたどっていくと、日本社会の変化が確実に刻み込まれている。その変化とはどのようなものなのか。注目の批評家が読み解く。(講談社現代新書)
文芸評論とは無関係ながら、ある一定の世代に黙々と消費され続けるライトノベルの世界。
気がつくと、ラノベ出身作家がメジャーシーンで活躍していたり、作品がハリウッドで映画化されたり。日本文化にもじわじわと影響をもたらしている。
その巨大で寡黙なラノベ作品群だが、
読者層が限られているからこそ、内容の変容をたどっていくと、
日本社会の変化が確実に刻み込まれている。
その変化とはどのようなものなのか。
上の世代との断絶。ポップかライトへ、そしてぼっちへ。むかしオタク、いまはフツー。ドラえもんの来なかったのび太たち。
注目の文芸批評家が読み解く。

明治国家をつくった人びと
講談社現代新書
福沢諭吉宛の世界的大学者からの手紙、幕末の使節団がみたアメリカのデモクラシー、初代帝大総長がヨーロッパで接した知の精神――。伊藤博文、山県有朋、井上毅から旧幕臣知識人まで、この国のかたちを築いた骨太な指導者たちの幕末明治の文明受容の旅を辿りながら、彼らの思想と行動を読む。『本』好評連載、待望の新書化!
福沢諭吉宛の世界的大学者からの手紙、幕末の使節団がみたアメリカのデモクラシー、初代帝大総長がヨーロッパで接した知の精神――。
伊藤博文、山県有朋、井上毅から旧幕臣知識人まで、この国のかたちを築いた骨太な指導者たちの幕末明治の文明受容の旅を辿りながら、彼らの思想と行動を読む。『本』好評連載、待望の新書化!

うつ病の現在
講談社現代新書
うつ病は患者100万人の国民病。誰がかかってもおかしくないこのこころの病とどうつきあうか、何を知っておくべきか。現代型うつ病や、従来型のうつ病。そして周辺の病気・双極性障害についても、信濃毎日新聞の医療記者が丹念に取材、うつ病に関して知っておきたいことを読みやすく解説。巻末には野村総一郎氏&鷲塚伸介氏の専門家対談。
うつ病は患者数100万人の国民病。誰がかかってもおかしくないこのこころの病とどうつきあうか、何を知っておくべきか。
現代型うつ病や、従来型のうつ病。そして周辺の病気・双極性障害(そううつ病)についても、信濃毎日新聞の医療記者が丹念に取材、うつ病に関して知っておきたいことを読みやすく解説。
巻末には野村総一郎氏&鷲塚伸介氏の専門家対談。

騎手の一分――競馬界の真実
講談社現代新書
2012年秋のマイルチャンピオンシップ。レースの後、勝利騎手インタビューが行われたウイナーズサークルの中央には、久しぶりの笑顔があった。ユタカさん(武豊騎手)が、約2年ぶりにG1を勝ったんだ。「お久しぶりです」俺はもう家に帰っていたから、そのインタビューはテレビで見たんだけど、何だかとてもさびしく感じた。あの武豊をこんな状態にしたのは誰なのか――。(本書より) (講談社現代新書)
プロの世界で長く生きてきたのだから、いつ、どこで、どういう形で引退しようかという
「引き際」は、この2~3年、常に頭の片隅にあった。
(中略)
これまで競馬界を支えてきたジョッキーたちが、実は2012年だけで23人もターフを去っている。
これは過去15年でもっとも多い数字だという。
1982年には252人いた騎手が、いまや半分近くにまで激減している。
厳しい試験をくぐり抜けて、ようやく憧れの騎手になったはずなのに、
なぜ、次から次へとこうもみんな、騎手を辞めてしまうのか。(序章より)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2012年秋のマイルチャンピオンシップ。
レースの後、勝利騎手インタビューが行われたウイナーズサークルの中央には、
久しぶりの笑顔があった。
ユタカさん(武豊騎手)が、約2年ぶりにG1を勝ったんだ。
「お久しぶりです」
俺はもう家に帰っていたから、そのインタビューはテレビで見たんだけど、
何だかとてもさびしく感じた。
あの武豊をこんな状態にしたのは誰なのか――。(第4章より)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ダービー、宝塚記念、有馬記念など、数々のG1を制してきた
藤田伸二が明かす、「伝えておきたいこと」。

今を生きるための現代詩
講談社現代新書
詩は難解で意味不明? 何を言っているのかわからない? いや、だからこそ実はおもしろいんです。技巧や作者の思いなどよりももっと奥にある詩の本質とは? 谷川俊太郎、安東次男から川田絢音、井坂洋子まで、日本語表現の最尖端を紹介しながら、味わうためのヒントを明かす。初めての人も、どこかで詩とはぐれた人も、ことばの魔法に誘う一冊。あなたが変わり、世界が変わる。(講談社現代新書)
詩は難解で意味不明? 何を言いたいのかわからない?
いや、だからこそ、実はおもしろいんです。
そもそも詩とは何か。
詩を読むとはどういうことか。
「技巧」や「作者の思い」などよりももっと奥にある詩の本質とは?
谷川俊太郎、安東次男から川田絢音、井坂洋子まで、日本語表現の最尖端を紹介しながら、詩を味わうためのヒントを明かす。
初めての人も、どこかで詩とはぐれた人も、ことばの魔法に誘う一冊です。
「詩は謎の種であり、読んだ人はそれをながいあいだこころのなかにしまって発芽をまつ。ちがった水をやればちがった芽が出るかもしれないし、また何十年経っても芽が出ないような種もあるだろう。そういうこともふくめて、どんな芽がいつ出てくるのかをたのしみにしながら何十年もの歳月をすすんでいく。いそいで答えを出す必要なんてないし、唯一解に到達する必要もない。」(本文より)

非社交的社交性 大人になるということ
講談社現代新書
人間は一人でいることはできない。といって、他人と一緒にいると不快なことだらけ――。「人間嫌い」のための、居心地のいい人間関係のつくり方とは。哲学者が、カントの言葉「非社交的社交性」を手がかりに、哲学、日本、若者を考えるエッセイ。(講談社現代新書)
人間は一人でいることはできない。といって、他人と一緒にいると不快なことだらけ――。「人間嫌い」のための、居心地のいい人間関係のつくり方とは。哲学者が、カントの言葉「非社交的社交性」を手がかりに、哲学、日本、若者を考えるエッセイ。

「動かない」と人は病む――生活不活発病とは何か
講談社現代新書
「体がだるくてボーっとする」「なかなか病気が治らない」のは年のせい? 定年後に元気がなくなってしまうのはなぜ? 実は「動かない」だけでかかる生活不活発病という病気があります。これは誰にでも起こる可能性があり、またうっかりしていると寝たきりにまでなりかねないこわい病気です。年を重ねてもいきいきと充実した生活を送るために知っておきたいことを、生活不活発病を中心に介護の専門家がやさしくかたります。
「動かない」から「動けない」。高齢化時代の新しい常識!
誰の身にも起こりうる病気を徹底解明
「体がだるくてボーっとする」「なかなか病気が治らない」のは年のせい? 定年後に元気がなくなってしまうのはなぜ?
実は「動かない」だけでかかる生活不活発病という病気があります。これは誰にでも起こる可能性があり、またうっかりしていると寝たきりにまでなりかねない怖い病気です。
年を重ねてもいきいきと充実した生活を送るために知っておきたいことを、生活不活発病を中心に介護の専門家がやさしくかたります。

頭が良くなる議論の技術
講談社現代新書
「楽しい議論」で生産性も人間関係も急上昇。著者自ら「議論の花咲かじいさん」を名のるが、そのコツを初公開する。一回の発言は一五秒以内、席を変えてみる、反論するときは対案を提出する、後戻りしない、自分の議論に反論をする、など役に立つ情報が満載。職場でも、学校でも、家庭でもすぐに始められ、議論の場の空気がグーンと良くなること間違いなし。組織が活性化され、仲が良くなる会話力を身につけたい人必読の書である!
日本人は議論が苦手といわれている。が、しかし、近年のマイケル・サンデルブームをみると、議論の必要性は学校や職場などで広く認識されているようだ。
日本人特有の相手の立場や感情をくみ取って、おだやかに議論を進めようとする気遣いをベースにこれからの「議論の技術」を齋藤孝が伝授する。
「論理の作法」を「ルール化」し、個人の能力を高める。それが生産性を向上し、参加者の満足感を高め、議論の場に活気をもたらす。モットーは「柔よく剛を制す」。
「ロジカル・エモーショナル・ディスカッション」のすすめでもある。