講談社現代新書作品一覧

和解という知恵
講談社現代新書
人間関係がぎくしゃくして悩んでいる方、遺産分割や離婚等のトラブルを抱えている方へ。人間関係がうまくゆかなくなって落ち込んでしまうことは、いつの時代でも、誰でもあることなのでしょう。とりわけ近年は、遺産分割等を機にこれまでうまくいっていた親族との人間関係がぎくしゃくし、深く悩んでいる人は多いと思います。本書は、弁護士としての46年の経験に基づき、紛争を避けるための「和解」のコツについて論じた本です。
【「仲直り」のヒント】
人間関係がぎくしゃくして悩んでいる方、遺産分割や離婚等のトラブルを抱えている方へ。「妥協」「譲歩」をせずに紛争を避けるコツを第一人者の弁護士が伝授します。
宮澤賢治が「ヤメロ」と言った「ソショウ」はどうすればやめられるのか。
家庭で、職場で、ご近所で―。
人間関係に悩むみなさんに贈る「和解」という「幸せの処方せん」。
--------------------------------------------------------
近年、遺産分割や離婚等を機に、これまでうまくいっていた親族との人間関係がぎくしゃくし、深く悩んでいる人はかなり多いと思います。
そうしたトラブルが起こった時、解決策はいろいろありますが、私が推奨するのは断然「和解」です。この『和解という知恵』は、弁護士としての46年の経験に基づき、紛争を避けるための「和解」のコツについて論じた本です。「和解」といえば、「妥協」「足して2で割る」というようないい加減なもの、と思われるかもしれません。しかし本書では「和解のメカニズム」を解明するとともに、和解の方法について、具体例をもとにまとめました。
【本書の主な内容】
序章 訴訟をやめて和解を
第1章 和解とは何か
譲歩と和解/因果律と共時性の原理/ワキガを理由に離婚? ほか
第2章 和解のしくみ
過去に左右される「訴訟」と未来を志向する「和解」/
金銭の貸し借りを巡る和解の方法 ほか
第3章 和解の扉を開く鍵
紛争解決規範の定義/ゲーム理論/言葉を引き出す工夫 ほか
第4章 和解へのスタート
身体と心の状態に光を当てる
そこに「経済的な安心感」はあるか ほか
第5章 和解をやり遂げる方法
遺産分割協議における利害の調整法
土地の交換に見るウィン・ウィンの和解
先妻の子の「今」を知るための情報収集法 ほか
第6章 和解の源泉と二つの源流
第7章 和解の深さ

デジタル・ワビサビのすすめ 「大人の文化」を取り戻せ
講談社現代新書
スティーブ・ジョブズとジャック・ドーシー、デジタル世界の巨人たちも日本の「ワビサビ」に傾倒していた。デジタルをいちばん享受できるのは、時間があって、人生経験を積んだ「大人」たち。SNSで趣味の輪を広げ、音楽でも写真でもアートでも、デジタルを使い倒して、生活を楽しもう。リタイア世代の地域デビューの技術書。(講談社現代新書)
スティーブ・ジョブズとジャック・ドーシー、デジタル世界の巨人たちも日本の「ワビサビ」に傾倒していた。
酸いも甘いも噛み分けた「大人」だからこその、豊かなデジタル生活を目指そう!
最近ではおバカな写真を自ら投稿して炎上する「アホッター」やら、
LINE殺人事件やら、ダメな部分が強調されることの多いSNS。
もともと、どんどん人と繋がれることが魅力であったはずなのに、
あらゆる罵詈雑言が幅をきかせるこの世界を嫌い、
いまではLINEの村社会に避難する人びとも多い。
さらにデジタルであらゆる文化が安っぽくなったという声も聞こえる。
でもそれは、デジタルがそれだけ誰もが使える当たり前の道具になってきたという裏返しでもある。
道具であるからには、要は使い方次第。
デジタルというと、若者のものという印象を持つ人もまだ多いが、
じつはデジタルをいちばん享受できるのは、時間があって、人生経験を積んだ「大人」たち。
フェイスブックなどのSNSで趣味の輪を広げ、音楽でも写真でもアートでも、デジタルを使い倒して、生活を楽しもう。
そのための方法を、デジカメ、デジタル・オーディオなどで人気の筆者が指南する。
リタイア世代の地域デビューの技術書。

万葉びとの宴
講談社現代新書
新元号「令和」の由来がわかる!
『万葉集』研究の第一人者が「梅花の宴」を読み解く決定版
宴はなぜ大宰府で行われたのか?
歌はどのように披露されたのか?
そもそもなぜ梅の花だったのか?
…
* * *
かくも素晴らしき「宴会」ニッポンの原点
古代人の雅に学ぶ酒宴の神髄
主人と客はお互いを気遣って称え合う。
盛り上げ上手の芸達者はあちこちでお座敷がかかる。
途中で抜ける時はマナー違反につき下手に出たり…。
思わず親近感が湧いてくる古代の人びとの宴会を、
注目の万葉学者がおもしろ実況・解説!

歴史家が見る現代世界
講談社現代新書
「現代」はいつから始まったのか? 「近代」と「現代」は何が変わったのか? そもそもどのようにして「時代区分」をするのか? 近年、歴史学の潮流は急速に変化してきた。視野の狭い国別の歴史にとらわれて、世界規模で進む大きな歴史のうねりを見逃してはならない。ハーバード大・歴史学部の名誉教授が書き下ろした、「現代世界」を考えるための手引き書。(講談社現代新書)
【目次】
第1章 歴史をどうとらえるか
第2章 揺らぐ国家
第3章 非国家的存在の台頭
第4章 伝統的な「国際関係」はもはや存在しない
第5章 普遍的な「人間」の発見
第6章 環地球的結合という不可逆の流れ
結 語 現代の歴史と記憶

プロ野球 名人たちの証言
講談社現代新書
王貞治が川上哲治から学び、金田正一から教えられ、イチローに驚かされたこととは。梨田昌孝、西山秀二、高橋慶彦、得津高宏、高橋善正、荒川博、黒江透修、高田繁、広岡達朗、関根潤三ら、球界で一時代を築き上げてきた名手たちが、彼らだからこそ知りえる世界を明かす。(講談社現代新書)
【「一流が一流たる理由」と「プロの極意」がわかる貴重な証言の数々】
田中将大、大型契約の背景とは。
王貞治が川上哲治から学び、金田正一から教えられ、イチローに驚かされたこととは。
広岡達朗「長嶋茂雄を見てください。『どうやって打つんですか?』と聞いても、明確な答えは返ってきません。なぜなら現役時代、彼は無意識でプレーしていたからなんです。そして、これが本物のスーパースターなんですよ。無意識でプレーできなければ一流とは言い難い」
黒江透修「ミスターが四タコだったような日は特に大変でしたよ。遠征先の宿舎に戻ってくるなり、ミスターは全裸になり、僕たちはパンツ一丁になって打撃練習のお手伝い」
高橋善正「王さんと長嶋さんはキャンプでも率先して練習し、紅白戦もオープン戦もフル出場する。ONがあれだけ真剣に練習していたら、誰も手を抜くことなんてできないよ」
【主な内容】
序 章 メジャーリーグと日本野球
田中将大、大型契約の背景 ほか
第1章 王貞治かく語りき
第2章 極意の証言
1 梨田昌孝:コンニャク打法の真実 ほか
2 西山秀二:桑田真澄のコントロール/イチローの究極スイング ほか
3 高橋慶彦:江夏豊の逆算、古葉竹識の器 ほか
4 得津高宏:金田正一監督の遺産 ほか
5 究極を見た打者たち:内川聖一/青木宣親 ほか
第3章 投手という世界
1 小谷正勝:山口鉄也を作った男 ほか
2 高橋善正:澤村拓一と大学野球 ほか
3 スライダーとフォーク:成田文男/上原浩治
第4章 V9巨人とその遺産
1 荒川博:一本足打法のルーツ ほか
2 黒江修透:牧野茂コーチの力 ほか
3 高田繁:ONのすごみ ほか
補論 野村克也の川上哲治論
第5章 達人たちの視点
1 広岡達朗:ヤクルト、西武の優勝の裏で ほか
2 関根潤三:大谷翔平は面構えがいい/根本陸夫との縁
3 村上孝雄:仰木、古葉、長嶋、稲尾…… ほか
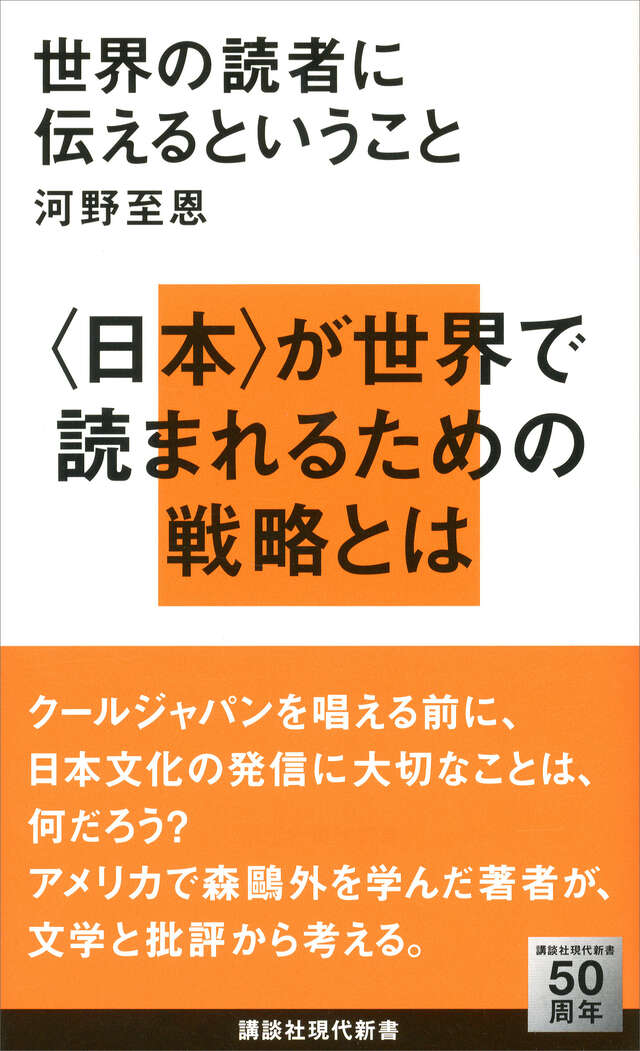
世界の読者に伝えるということ
講談社現代新書
日本文化が世界で人気があると聞くとうれしい。コンテンツ輸出も大切だ。ただ、いま大事なのは「日本発の文化を日本以外の世界の読者の視点から見る」ことではないだろうか? アメリカで森鴎外を学び、大学で教えた経験も持つ著者が、文学と批評を例に、比較文学と地域研究というアプローチを通して考える画期的論考。(講談社現代新書)
日本文化が世界で人気があると聞くとうれしい。コンテンツ輸出も重要だ。ただ、日本文化の発信にあたって、いま求められているのは、「日本発の文化を、日本以外の世界の読者の視点から見てみる」ことではないだろうか?
アメリカで森鴎外を学び、大学で教えた経験も持つ著者が、文学と批評を例にして、比較文学と地域研究というふたつのアプローチを通して考える。
【目次】
序章 「世界の読者」の視点
第1部 ひとつめのレンズ 比較文学篇――世界文学としての日本文学
第1章 アメリカで学んだ、日本文学の大切なこと
第2章 「世界の読者」から読みかえる村上春樹
第3章 「世界文学」という読みかた
第4章 海外の大学から見る「日本文学の発信」
第2部 ふたつめのレンズ 地域研究篇――日本研究からみる日本文化・ポピュラーカルチャー・現代日本の批評
第5章 日本研究という視点
第6章 日本研究で「日本らしさ」を語ることのむずかしさ
第7章 日本のポピュラーカルチャーを研究する
第8章 海外の日本研究から読む、現代日本の批評
終章 すべての文化は「世界の財産」である

教育の力
講談社現代新書
「ゆとり」か「詰め込み」か、「平等」か「競争」かなど、教育を巡る議論ほどに対立と齟齬が起こっている問題はないと言っても過言ではありません。しかしそれらは、論者の個人的な感想や思い込みによる独りよがりである場合がほとんどです。みんなが善意と熱意を持って教育を論じるのだけれど、ある種、独りよがりな「思い入れ」や「思い込み」が先走ってしまい、不毛な対立が至るところで引き起こされてしまっている……それが教育を巡る言説の現実ではないでしょうか。
しかし、この種の「対立」は冷静に考えてみれば錯覚であることが少なくありません。「ゆとり」か「詰め込み」かと二項対立で問われると、人はつい、どちらかの立場に与してしまいます。しかしそれは実は「問い方のマジック」に陥っているだけなのです。こういった偽の問題による不毛な対立を避けた、本当に意義のある教育を巡る議論が、いまこそ必要とされているのではないでしょうか。
こうした混乱に終止符を打つためには教育、とりわけ公教育はそもそも何のために必要なのかをまず定義しなければなりません。著者の考えによるなら、それは一人一人の子供が近代社会のルールを身につけその中でより自由に生きられるようになることということになります。個々の子供の自由の感度こそが社会に対する信頼の土台となり、みんなでよりよい社会を作るという真の意味での市民参加型の民主主義社会の礎となるのです。
では、どうすればそのような〈よい〉教育を作ることができるのでしょうか。著者の提案は様々ですが、その一つは、一方的に教師の授業を聞くという受け身の授業を改め、子供たちがある一つのテーマに関して自ら調べ、お互いに教え合う、授業の「プロジェクト化」です。日本ではあまりなじみのない方法ですが、すでにフィンランドやオランダなどでは成果を上げたメソッドです。競争よりも協力の方がそれぞれの子供の学力を上げることはすでに様々なデータで証明されています。
〈よい〉教育をつくるためには学校の物理的な「構造」はどうなっているのがいいのか? 〈よい〉教育を行うための教師の資質とは何か? そしてその実現のための〈よい〉社会とは?
本書は、義務教育を中心に、どのような教育が本当に〈よい〉と言えるのか、それはどのようにすれば実現できるのかを原理的に解明し、その上でその実現への筋道を具体的に示してゆくものです。

社会保障亡国論
講談社現代新書
消費税が増税されると本当に社会保障は充実するのか。現在わが国の社会保障給付費は、GDPの約4分の1にあたる110兆円を超える規模に達しており、年間3~4兆円というペースで急増している。消費税率の引き上げの効果は3~4年で消失する計算となる。年金・医療・介護・子育て支援など、「少子高齢化」日本を暮らす人々の不安は拡がる一方だ。社会保障財源の現状を具体的に改善する議論と給付の抑制・効率化策も提言する。
消費税が増税されると本当に社会保障は充実するのか。
現在わが国の社会保障給付費は、GDPの約4分の1にあたる110兆円を超える規模に達しており、年間3~4兆円というペースで急増している。消費税率の引き上げの効果は3兆~4年で消失する計算となる。
年金・医療・介護・子育て支援など、「少子高齢化」日本に暮らす人々の不安は拡がる一方だ。社会保障財源の現状を具体的に改善する議論と給付の抑制・効率化策も提言する。

銀行問題の核心
講談社現代新書
日本金融システムの中心メンバーであるメガバンクが好業績を続ける一方で、中小企業への融資がなかなか進まないのはなぜか? 銀行と金融庁との関係とは? 銀行と反社会勢力との関係とは? 資金繰りで苦労するまじめな中小企業を潰す検察の失敗とは? 日本の銀行のいまについて、現場の支店長を経験した作家と、日本の企業社会に精通する弁護士のふたりが議論する。(講談社現代新書)
銀行員を主人公としたドラマ『半沢直樹』が大ヒット。銀行の仕事に改めて世間の注目が集まる中で起きた、みずほの反社融資問題。
日本金融システムの中心メンバーであるメガバンクが好業績を続ける一方で、中小企業への融資がなかなか進まないのはなぜか?
銀行と金融庁との関係とは?
銀行と反社会勢力との関係とは?
資金繰りで苦労するまじめな中小企業を潰す検察の失敗とは?
現場の支店長を経験した人気作家と、企業の危機管理問題の第一人者である弁護士のふたりによる大議論。
日本の銀行のいまに迫る!

憲法改正のオモテとウラ
講談社現代新書
【憲法改正とは「政治」そのものである】参議院の圧力、省庁の縄張り争い、政官業癒着勢力の暗躍……。小泉政権時に「新憲法起草委員会」事務局次長を務めた著者がはじめて明かす、改正議論の舞台裏。前文に歴史観や思想は必要なの? 天皇を元首ごときにしていいの? 憲法改正を利用して、既得権益を守ろうとする省庁や族議員が存在する!
【憲法改正とは「政治」そのものである】
参議院の圧力、省庁の縄張り争い、
政官業癒着勢力の暗躍……。
小泉政権時に「新憲法起草委員会」事務局次長を務めた
著者がはじめて明かす、改正議論の舞台裏。
--------------------------------------------------
前文に歴史観や思想は必要なの?
天皇を元首ごときにしていいの?
憲法改正を利用して、既得権益を守ろうとする
省庁や族議員が存在する!
--------------------------------------------------
〈本書の主な内容〉
第1章 参議院への配慮と自民党内の政治力学
・ 改正論議の裏で繰り広げられた権力闘争
・ 読売新聞にスクープさせる「暴挙」
・ 「こんなふざけた案は絶対に認めない」
・ 秘密を守れない政治家たち
・ 反発する参議院への配慮と自民党内力学 ほか
第2章 どうすれば国民に支持されるかを考える
・ 安倍氏が全面書き換えを主張した理由
・ 前文に価値観はそぐわない
・ 天皇は元首なのか
・ 「元首ごときにするには畏れ多い」という意見
・ 自衛軍か国防軍か
・ 目先の問題解決策を憲法に求めてはならない
・ 「個人」の重要性をわかっていない「第2次草案」
・ 封殺された一院制論
・ ポピュリズムの危険性が高い首相公選制
・ 最高法規を愚弄する行為
・ 財務省 vs. 総務省
・ 理論武装させられた族議員によるバトル ほか
第3章 政治の荒波に翻弄された条文化作業
・ 諮問会議メンバーを固辞する学者たち
・ これが政治力学
・ 「総理は今、それどころではないんだ」
・ 失敗に終わった「軽井沢工作」
・ 自然描写や歴史に触れるのは中国憲法と同じ ほか

絶望の裁判所
講談社現代新書
裁判官というと、少し冷たいけれども公正、中立、優秀といった印象があるかもしれない。しかし、残念ながら、そのような裁判官は、今日では絶滅危惧種。近年、最高裁幹部による、思想統制が徹底し、良識派まで排除されつつある。 三三年間裁判官を務めた著名が著者が、知られざる、裁判所腐敗の実態を告発する。情実人事に権力闘争、思想統制、セクハラ・・・、もはや裁判所に正義を求めても、得られるものは「絶望」だけだ。
裁判所、裁判官という言葉から、あなたは、どんなイメージを思い浮かべられるのだろうか? ごく普通の一般市民であれば、おそらく、少し冷たいけれども公正、中立、廉直、優秀な裁判官、杓子定規で融通はきかないとしても、誠実で、筋は通すし、出世などにはこだわらない人々を考え、また、そのような裁判官によって行われる裁判についても、同様に、やや市民感覚とずれるところはあるにしても、おおむね正しく、信頼できるものであると考えているのではないだろうか?
しかし、残念ながら、おそらく、日本の裁判所と裁判官の実態は、そのようなものではない。前記のような国民、市民の期待に大筋応えられる裁判官は、今日ではむしろ少数派、マイノリティーとなっており、また、その割合も、少しずつ減少しつつあるからだ。そして、そのような少数派、良識派の裁判官が裁判所組織の上層部に昇ってイニシアティヴを発揮する可能性も、ほとんど全くない。近年、最高裁幹部による、裁判官の思想統制「支配、統制」が徹底し、リベラルな良識派まで排除されつつある。
33年間裁判官を務め、学者としても著名な著者が、知られざる裁判所腐敗の実態を告発する。情実人事に権力闘争、思想統制、セクハラ……、もはや裁判所に正義を求めても、得られるものは「絶望」だけだ。

「若作りうつ」社会
講談社現代新書
年の取り方がわからない! ――どこもかしこも若さ志向、加齢の手本となるべき年長者も見つからない社会で、我々はどのように年を重ねていくべきか。いま出版界で熱い注目を集めるオタク出身の精神科医が、「成熟消失」の時代を読み解く。(講談社現代新書)
年の取り方がわからない!――どこもかしこも若さ志向、加齢の手本となるべき年長者も見つからない社会で、我々はどのように年を重ねていくべきか。いま出版界で熱い注目を集めるオタク出身の精神科医が、「成熟消失」の時代を読み解く。
<目次>
序章 年の取り方がわからない
どこもかしこも若さ志向/終わりなき思春期 ほか
第一章 「若作りうつ」に陥った人々の肖像
若さにしがみつかせる強迫観念/自己中心的な結婚願望、その袋小路
不惑になっても自分探し/孤独死に恐れおののく現代人 ほか
第二章 誰も何も言わなくなった
昭和のお年寄り/「日本的成熟」のリセット
メディアは教えてくれない/“成熟の無重力空間” ほか
第三章 サブカルチャーと年の取り方
少年向けコミックの移り変わり/「父親なきアニメ」へ
「かわいい」の世代間伝達/「中二病」は僕らの宗教 ほか
第四章 現代居住環境と年の取り方
「誰にでも好かれる子ども」/パーソナリティの格差社会
社会的加齢のための刺激/自由な居住環境の副作用 ほか
第五章 二十一世紀のライフサイクル
乳児期「基本的信頼 vs. 不信」~ 老年期「統合性 vs. 絶望」
老いや死を前提とした人生の再設計 ほか
終章 どのように年を取るべきか
年の取り方のニューモデル/私達一人一人にできること ほか

城を攻める 城を守る
講談社現代新書
「この時代小説がすごい!」作家別ランキング1位の著者が、戦国時代から幕末にかけて城郭攻防戦が展開された26の「戦う城」を徹底分析。国内最後の城郭攻防戦を耐え抜いた名城中の名城「熊本城」、栄光と没落の分岐点となった東海一の堅城「高天神城」、外交的駆け引きに敗れ去った難攻不落の巨城「大坂城」、謙信が手塩にかけて造り上げた戦国最強の山城「春日山城」、関東平野を睥睨する巨大山城「八王子城」ほか。
本書を手に取った方々は、一過性の趣味として城めぐりをしているわけではないはずだ。おそらく城好きが高じて、その歴史的背景までも知りたいと思っているのではないだろうか。本書は、そうした方々を対象としている。「日本百名城」ブームを一過性のものとして終わらせないためにも、その城で過去にあった攻防戦に目を向けてもらい、その城の経てきた歴史に興味を持っていただく必要がある。本書は、そうしたことを念頭に置いて書いた「戦う城本」である。
【白河城】 東北戊辰戦争の行方を左右した城郭攻防戦
【会津若松城】 幕末最大の悲劇の舞台となった白亜の名城
【五稜郭】 箱館戦争の舞台となった欧州式稜堡型城郭
【新井城】 武士の時代の終わりを告げた海城
【河越城】 新旧交代の舞台となった武蔵国の要衝
【箕輪城】 孤高の奇才・長野業政の築いた城郭網
【鉢形城】 戦国時代の黎明から終焉まで、激戦の舞台となり続けた要害
【八王子城】 関東平野を睥睨する巨大山城
【水戸城】 血で血を洗う同士討ちの舞台となった名城
【川中島合戦と海津城】 信玄の高速道路を支えた一大兵站拠点
【一乗谷朝倉館】 現代によみがえる中世城郭都市
【七尾城】 北陸有数の巨大山城を攻略した謙信の軍略
【春日山城】 謙信が手塩にかけて造り上げた戦国最強の山城
【桶狭間合戦をめぐる城郭群】 伊勢湾経済圏支配をめぐる織田・今川両家の熾烈な攻防戦
【懸河城】 今川家の駿遠防衛構想の切り札となった要害
【二俣城攻防と三方ヶ原合戦】 巨匠武田信玄が最後の筆を揮った会心の一戦
【長篠城】 戦国時代の流れを変えた山間の城
【高天神城】 栄光と没落の分岐点となった東海一の堅城
【山中城】 緒戦の大切さを教えてくれた戦国山城の最終型
【韮山城】 四万四千の豊臣軍を翻弄した北条家創業の城
【小谷城】 戦国時代を代表する難攻不落の大要害
【有岡城】 戦国有数の悲劇の舞台となった怨念の城
【賤ヶ岳合戦と陣城群】 天下の帰趨を決めた陣城戦
【大坂城】 外交的駆け引きに敗れ去った難攻不落の巨城
【原城】 泰平の世を震撼させた宗教戦争
【熊本城】 国内最後の城郭攻防戦を耐え抜いた名城中の名城

国際メディア情報戦
講談社現代新書
中国・北朝鮮・イラン・アルカイダ……いまや大国も小国もテロリストも続々参戦している「国際メディア情報戦」。それは「どれだけ多くの人に、自分に有利な情報を到達させ、その心を揺り動かすか」をめぐる戦いである。急拡大する戦いの現場でいま何が起きているのか? 日本はどう戦うのか? 稀代のメディアスター、ビンラディンの驚愕のメディア操縦法から、オバマの逆襲まで、世界各地で起きている新しい「戦場」を読み解く。
【あの名著『戦争広告代理店』から12年、待望の最新刊!】
情報戦というと、CIAやらMI5やらの情報機関が水面下で暗躍する、
「ごく一部の人しか知らない情報」をいかにゲットするかの戦いのことだと思われるかもしれない。
しかし、いま世界を動かしているのは、自らに有利な情報を多くの人の目と耳に届け、その心を揺り動かすこと、いわば「出す」情報戦である。
情報は、自分だけが知っていても意味はない。
現代では、それをいかに他の人に伝えるかが勝負になっているのだ。
国際メガメディアの情報空間で生まれる巨大なイメージのうねりをめぐって、大国も小国もテロリストも争っている。
それはいかなるテクニックによるのか?
急拡大する新しい「戦場」で、いま何が起きているのか?
そして、日本はいかに戦えばよいのか?
今世紀をサバイバルするための必読書!
【朝日・日経・読売・毎日ほか絶賛の嵐!】
あらゆる局面の背後にプロの仕事師たちが暗躍している。本書はその知られざる現場を活写して、テレビのスペシャル特番のごとく読者の関心を一気にわしづかみにする。 ――福岡伸一氏
ビンラディンが殉教者として崇められないように採られた措置は何だったかなど、ページをめくる楽しみがあった。――加藤陽子氏

校長という仕事
講談社現代新書
杉並区立和田中学の元民間人校長が、5年間の公立中学の校長体験、学校経営、教育委員会・校長・教員の関係などについて持論を語る

呼鈴の科学 電子工作から物理理論へ
講談社現代新書
呼鈴が鳴る、その仕組を初歩の電子工作と、著者の創案になる独自の装置を駆使して論じていく。数式を用いず、法則に頼らず。部品を集め、回路を作って、物の働きを実際に見て感じて考える。相対性理論も量子力学も、呼鈴の中で働いている。
本書はファラデーの名著「ロウソクの科学」の精神に倣い、一つの主題から湧き出てくる様々な問題を、簡単な実験を通して体感できるように工夫して、電磁気学解説の新生面を開いたものである。

日本軍と日本兵 米軍報告書は語る
講談社現代新書
日本軍というと、空疎な精神論ばかりを振り回したり、兵士たちを「玉砕」させた組織というイメージがあります。しかし日本軍=玉砕というイメージにとらわれると、なぜ戦争があれだけ長引いたのかという問いへの答えはむしろ見えづらくなってしまうおそれがあります。本書は、戦争のもう一方の当事者である米軍が軍内部で出していた広報誌を用いて、彼らが日本軍、そして日本人をどうとらえていたかを探ります。(講談社現代新書)
私たちは、日本軍、とくに日本陸軍というと、空疎な精神論ばかりを振り回したり、兵士たちを「玉砕」させた組織というイメージがあります。しかし、実際には、「玉砕」ばかりしていたわけではありません。孤島で追い詰められた場合はともかく、ニューギニア、フィリピンなどの大きな島では、徹底抗戦、持久戦がとられましたし、沖縄でも、最後に出された指令は、組織的抵抗を最後まで継続せよ、というものでした。
もちろん、だからといって、日本軍が玉砕をしなかった、あるいは合理的な組織だったということではありません。ただ、日本軍=玉砕というイメージにとらわれると、なぜ戦争があれだけ長引いたのかという問いへの答えが見えづらくなってしまうのです。
日本軍、とくに日本陸軍の実像をどうとらえるべきなのか、本書は、戦争のもう一方の当事者である米軍が軍内部で出していた広報誌『Intelligence Bulletin(『情報広報』)を用いて、彼らが、日本軍、そして日本人をどうとらえていたかを探ります。
『情報広報』には、例えば、日本人はLとRの区別がつかないので、戦場で日本人か中国人か判別がつかない場合には、それらが入った文章を言わせることといったことが書かれています。また、日本兵個人の特徴として、規律は良好、準備された防御では死ぬまで戦う、とある一方で、予想していなかったことに直面するとパニックに陥る、自分で物を考えないといった分析がされています。
さらに、日本の兵士らがじつはさまざまな不平不満を抱えていて、投降させることもできた、といったことが書かれているのです。
本書は、気鋭の研究者が、米軍内部の資料をもとに、従来の日本軍イメージをとらえなおす一冊です。

孤独な日銀
講談社現代新書
【凋落するエリート集団の「存在意義」を問う】本書では、他の日銀本のように、日本経済の長期低迷と金融政策運営の関係を直接的に取り扱うことはしていません。本書の目的は、金融政策論やマクロ経済論を展開することではなく、日銀という組織を論じることにあるからです。組織としての日銀の描写によって、机上や紙上の金融政策論には現れてこない、実際の政策運営の躍動感を感じていただければと思います。(講談社現代新書)
【金融政策運営の失敗は、誰の責任なのか】
【凋落するエリート集団の「存在意義」を問う】
本書では、他の日銀本のように、日本経済の長期低迷と金融政策運営の関係を直接的に取り扱うことはしていません。
日銀とはどういう組織でどのような業務を行っているのか。政府との関係はどのようになっているのか。そして、日銀という組織は将来的にどうあるべきなのか――。
本書の目的は、金融政策論やマクロ経済論を展開することではなく、日銀という組織を論じることにあるからです。
組織としての日銀を描写することによって、机上や紙上の金融政策論には現れてこない、実際の政策運営の躍動感を感じていただければと思います。
【おもな内容】
第1章 日銀マンとは何者か―大組織に潜む「エリート意識」の構造
半官半民/組織に潜むエリート意識/個性豊かだけど変人が多い/採用試験は面接だけ/『小説日本銀行』と実際の日銀/日銀マンの一生/減点方式ではない人事査定方法 ほか
第2章 日銀という組織―なぜ人々は「過度な期待」を寄せるのか
罰則のない日銀考査/明示されていない「経済成長」と「物価安定の達成」/「時代の要請」と新日銀法の大きなギャップ/なぜ人々は「過度な期待」を寄せるのか/日銀の最重要局/別格の大阪支店 ほか
第3章 日銀の歴史と総裁たち―「財政・金融の分離」と「独立性」への疑問
デフレ・ファイターとしての日銀/総裁として必要な資質/歴代総裁考/傑出していた国際派総裁/人間味溢れていた平成の鬼平/実力派大蔵官僚と激動の日本経済/敬虔なクリスチャン ほか
第4章 最高意思決定機関への懸念―問われる審議委員の存在意義
完全に担保されていない独立性/正副総裁と審議委員の力関係/透明性と説明責任/経済調査能力が低下する危惧 ほか
第5章 日銀の孤独と悲劇―「独立性」と「共同責任」の狭間で
スケープゴートにされる日銀/日銀不要論を免れるための独立性/流れを変えた安倍政権/失敗の責任は誰が取るのか?/共同責任体制の死角/日銀のジレンマ ほか
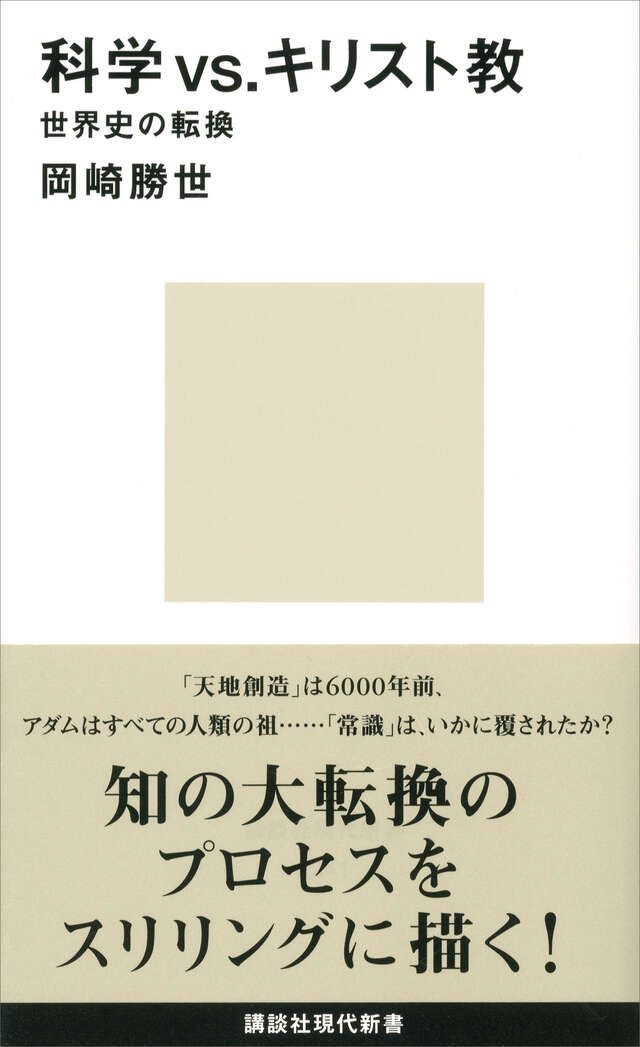
科学vs.キリスト教 世界史の転換
講談社現代新書
「天地創造は六千年前」「アダムはすべての人間の祖」──聖書が教える「常識」は、科学によっていかに書き換えられたのか? 科学的知見の発展のもと、ヨーロッパの人々の世界認識が根底から覆されてゆくその葛藤のプロセスを、デカルト、ニュートン、ビュフォン、リンネ、ダーウィンなど著名な科学者、哲学者から、ガッテラー、シュレーツァーなど今では忘れられてしまった歴史家の仕事なども追いながら、スリリングに展開する。
「天地創造は六千年前」──それが、聖書の記述こそが正当な歴史とされてきたヨーロッパにおける、古代から中世に至る長い間の「常識」でした。逆に言えば、彼らの感覚にとって、「六千年」というのは恐ろしく長い時間と見なされていたと言うことでもあります。ところが、ルネサンスおよび大航海時代の始まりにより科学的な探求が始まり、地理上の知見がこれまでになく大きな広がりを見せるようになると、様々なところで聖書の記述と齟齬をきたす事実が発見されるようになります。たとえば中国の歴史が知られるようになると、それがどうやら「六千年」よりも古いことが明らかになり、「天地創造は六千年前」というそれまでは自明と思われていた「常識」が揺らぎ始めます。また、地質学の知見によっても、地球の歴史が六千年よりも実はかなり長いのではないかと考える学者たちが現れるようになります。例えばダーウインは、当時としては大胆なことに地球の歴史を三億年前までさかのぼらせます(もっとも、この説は非難を浴び、結局ダーウインは後に撤回することになるのですが)。かくして「普遍的」と思われていた聖書をベースとした歴史(これを普遍史と呼びます)は、至る所で綻びを見せ始め、ついには深刻な危機に陥ります。神の存在の元、意味ある統一体をなしていたと思われていた宇宙は、デカルト・ニュートンによって単に機械的な運動をする物体の集まりに他ならないとされ、アダムはすべての人類の祖としての地位を失い、またリンネによって、人間も動物の一種へと「降格」されてしまいます。またその一方では、この「革命」のおかげをもって歴史が聖書から「独立」し、現在のような歴史学としての出発点を築くことにもなりました。本書では、「科学」の発展によってヨーロッパの人々の世界認識が根底から覆されてゆくプロセスを、デカルト、ニュートン、ビュフォン、リンネ、ダーウィンなど著名な科学者、哲学者から、ガッテラー、シュレーツァーなど今では忘れられてしまった歴史家の仕事なども追いながら丹念にたどってゆきます。

会社を変える会議の力
講談社現代新書
今日も日本中の多くの会社で、会議に対するボヤキが聞こえてくる。「時間のムダ」「資料づくりで一日が終わる」「何も決まらない」などなど。しかし実際、会議と名の付くもので、本当の会議の名に値するものは1割程度。あとはダメな会議や会議モドキだらけ。本当の会議とは問題解決の結論を出す(決める)会議のこと。会議を変えて組織を活性化させるためのヒント満載、これであなたの会議観も変わる! (講談社現代新書)
今日も日本中の多くの会社で、会議に関するボヤキが聞こえてくる。
「時間のムダ」「資料づくりで一日が終わる」「何も決まらない」などなど。
しかし実際、会議と名の付くもので、本当の会議の名に値するものは1割程度。
あとはダメな会議や名ばかり会議の会議モドキだらけ。
本当の会議とは問題解決の結論を出す(決める)会議のこと。
会議を変えて組織を活性化させるためのヒント満載、
これであなたの会議観も変わる!