新刊書籍
レーベルで絞り込む :

2014.07.25発売
経済学の歴史
講談社学術文庫
『経済表』を考案したケネーはルイ15世寵妃の侍医であり、『国富論』の著者・スミスは道徳哲学の教授だった。興味深い経済学草創期からリカード、ミル、マルクス、ワルラスを経てケインズ、シュンペーター、ガルブレイスに至る12人の経済学者の評伝と理論を解説。彼らの生きた時代と社会の発展をたどり、現代経済学を支える哲学と思想を再発見する。(講談社学術文庫)
スミス以降、経済学を築いた人と思想の全貌創始者のケネー、スミスからマルクスを経てケインズ、シュンペーター、ガルブレイスに至る12人の経済学者の生涯と理論を解説。
『経済表』を考案したケネーはルイ15世寵妃の侍医であり、『国富論』の著者・スミスは道徳哲学の教授だった。興味深い経済学草創期からリカード、ミル、マルクス、ワルラスを経てケインズ、シュンペーター、ガルブレイスに至る12人の経済学者の評伝と理論を解説。彼らの生きた時代と社会の発展をたどり、現代経済学を支える哲学と思想を再発見する。
経済学の歴史を学ぶ理由の1つは、現代理論を盲信する危険性を防ぐことにあると思われる。例えば、スミスは、本来、絶妙なるバランス感覚の持ち主であり、決して極端な自由放任主義者ではなかったが、いつの間にか自由放任主義哲学の元祖として「自由至上主義者」たちに学問的にも政治的にも利用されるようになった。だが、それがわかるには、そもそもスミスが何を考えていたのか正確に知っておかなければならない。経済学史の効用の1つがここにある。――<本書「プロローグ」より>

2014.07.25発売
物理のための数学入門
本書は『講談社基礎物理学シリーズ』の第10巻であり、物理学で使う数学を詳説するものです。
一般に物理学の教科書では、数学的な内容は既知のものとして、あまり詳しく説明されません。そのため、つまずいてしまう学生さんが多く出てしまいます。本書では、大学の1~3年生までに出てくる物理における数学を、例題を多くあげて丁寧に解説しています。本書を読めば、数学でつまずくことはなくなるでしょう。解答も、(省略)や(略解)を使わず全て書くようにしました。
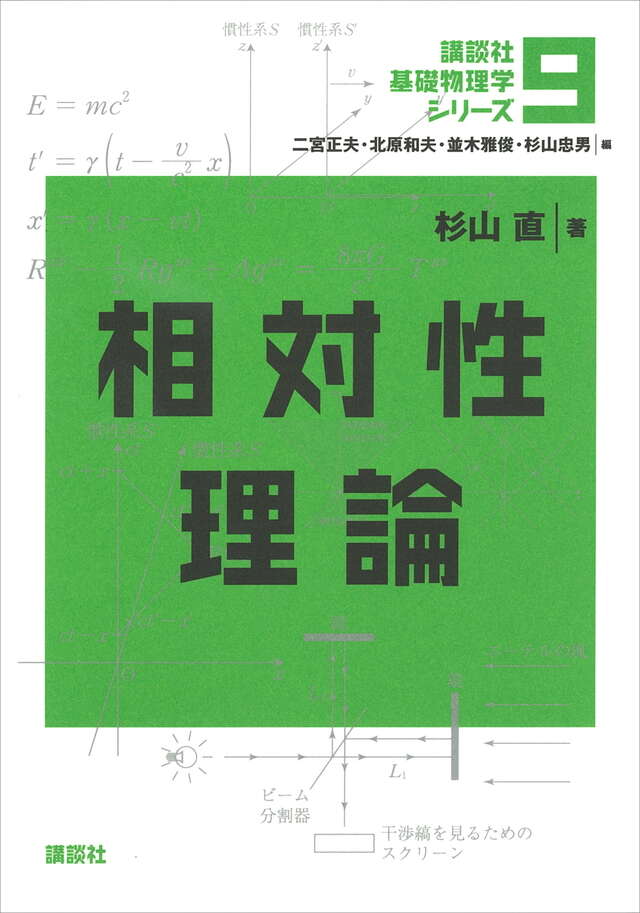
2014.07.25発売
相対性理論
本書は『講談社基礎物理学シリーズ』の第9巻であり、相対性理論という物理学分野を詳説するものです。
相対性理論とは、有名なアインシュタインが1905年(特殊相対性理論)と1916年(一般相対性理論)に提唱した理論です。光の速さや宇宙全体の構造といった壮大なスケールの物理現象を扱う、物理学の中でも特にエキサイティングな分野です。本書は、普通の力学の常識と異なった面白い現象が現れることを、例題とその解説で示し、読者に魅力を感じていただける本になっています。
本書は、「特殊相対性理論」で終わってしまう教科書が多い中、「特殊相対性理論」と「一般相対性理論」の両方を解説しています。一般に難解といわれる「一般相対性理論」をかみくだいて易しく説明しましたので、ぜひチャレンジしてみてください。
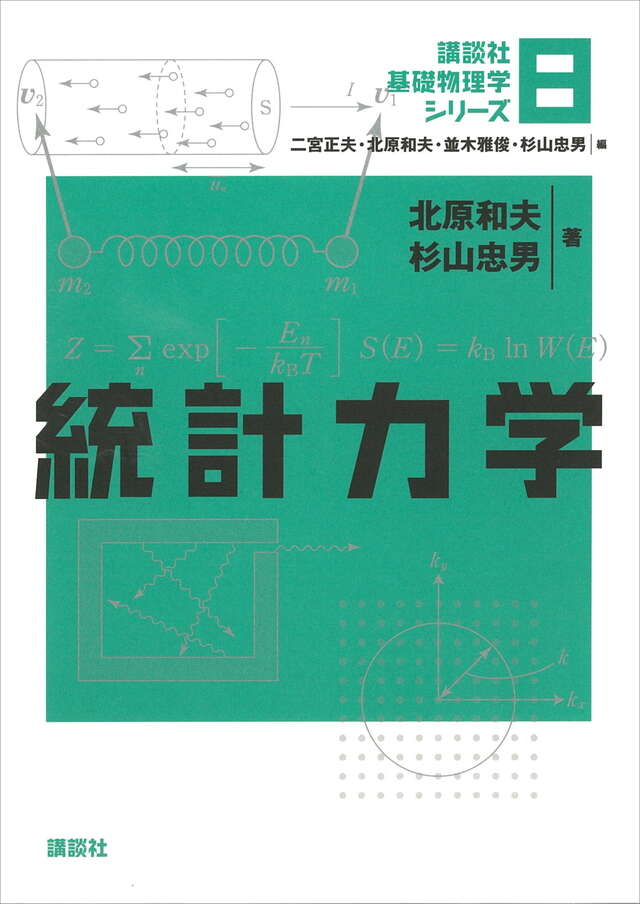
2014.07.25発売
統計力学
本書は『講談社基礎物理学シリーズ』の第8巻であり、統計力学という物理学分野を詳説するものです。
統計力学は、熱力学の親戚筋にあたります。熱の正体は物質を構成する分子の運動の激しさなのですが、分子はとてつもなく小さくて数が多いので、1 個 1 個の分子の動きを追うことは不可能(であり無意味)です。そこで、分子の集団の振る舞いを統計的に観察するのが統計力学です。
しかし、統計力学は熱力学にもまして数式が抽象的でわかりにくく、初学者には特に不評な科目です。本書は確率論や数理統計の前提知識は一切必要なく、統計力学に初めて触れる初学者が理解できるようにした教科書です。難解な数式に惑わされず、物理的な意味をしっかり理解できるように、具体的な例題を大いに活用しました。
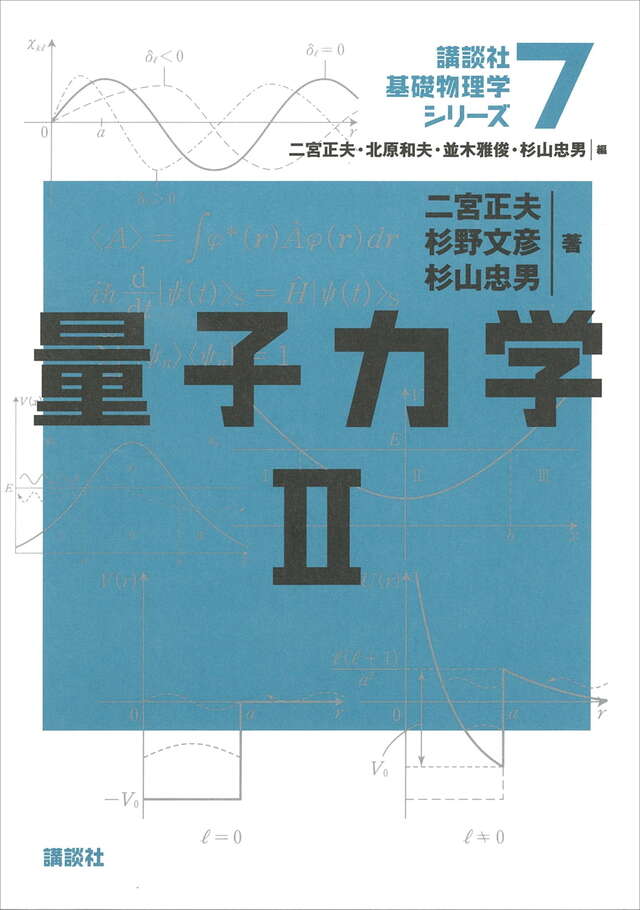
2014.07.25発売
量子力学2
本書は『講談社基礎物理学シリーズ』の第7巻であり、本シリーズ第6巻『量子力学I』の続巻です。量子力学は範囲が広く、通常1セメスターですべて終了するものではありません。『II』はおもに量子力学の発展的内容を扱います。量子力学の基本的性質から、摂動論、WKB近似、経路積分などを解説。内容の多くを例題を通して詳解します。解答付き章末問題を充実させました。

2014.07.25発売
量子力学1
本書は『講談社基礎物理学シリーズ』の第6巻であり、量子力学という物理学分野を詳説するものです。
量子力学とは、字面からはイメージが湧かないのですが、原子や電子といったミクロの粒子の運動を論じる学問です。量子力学は物理学として興味深いのはもちろんのこと、我々の身の回りにあるほとんど全ての電気製品が、実は量子力学の法則の応用によって動いており、実用的な学問です。
本書では、例題とその丁寧な解説を通じて、「何が問題なのか、これを習得するとどのような物理現象が理解できるのか」を明確にしてゆく教科書です。それにより、初学者が電子や原子の運動を実感し、量子力学を理解していただけます。
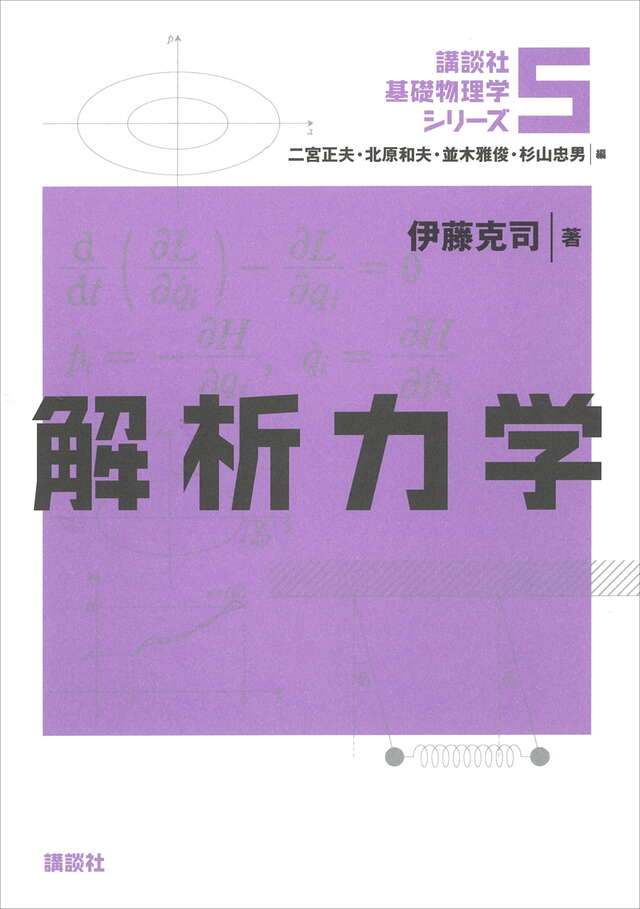
2014.07.25発売
解析力学
本書は『講談社基礎物理学シリーズ』の第5巻であり、解析力学という物理学分野を詳説するものです。
解析力学とは、力学の探究を押し進めて理論的に構築しなおしたものです。多くの教科書類は、学習者がそれまで見たこともないような難しい数学的記述で占められているので、非常に難解な分野と感じられています。
しかし、解析力学を学ぶことによって、力学の多くの問題が統一的に解けるようになるほか、統計力学や量子力学などのさらに進んだ分野で必要な道具を手に入れることができ、その効用は小さくありません。
本書は、初等力学からギャップなく知識が繋がるように、解析力学とは何かを初歩から学ぶ教科書です。

2014.07.25発売
振動・波動
本書は『講談社基礎物理学シリーズ』の第 2 巻であり、振動波動論という物理学分野を詳説するものです。
振動と波動は、振り子の運動に始まり、水の波、音の波、光の波、果ては電子や原子核の波(電子のようなミクロの粒子の正体は、実は波であることが知られています)に至るまで、ありとあらゆる物理分野で見られる普遍的な現象です。振動と波動を知らないことは、物理を知らないことと同じです。
しかし、振動と波動は、「微分方程式」「フーリエ変換」といった高等数学に頼って説明されることが多いので、重要でありながら初学者には学びにくい傾向があります。
本書は、高等数学の理解を蔑ろにしないのはもちろんながら、例題に重点を置くことにより、振動と波動を物理現象として実感をもって習得できるようにしました。

2014.07.25発売
力学
本書は『講談社基礎物理学シリーズ』の第 1 巻であり、「力学」という物理学分野を詳説するものです。
力学とは、「物体は、どのような力が働くときにどのように運動するのか」を明らかにする物理学の一分野であり、ガリレイやニュートンによって確立されました。
力学は、「ボールを投げたら何秒後にどこに落下するか」から「惑星はなぜ太陽の周りを回るのか」まで実に様々な問いに答えを与えることができるので、物理学を学ぶためには不可欠の分野です。大学に入っても必ず 1 年次で履修することになっており、主要な物理学シリーズでも第 1 巻に据えられています。
本書は、基礎的な力学をわかりやすく、かつ、理工系として必要な分を不足なく習得できる本です。

2014.07.25発売
今度こそわかるくりこみ理論
重要だが、いざ勉強すると難解だ――。多くの人の「学ぼうとしても、たどり着く前に挫折する」という経験を熟知した著者が、物理的イメージを重視して読者を導く。現代の素粒子論や物性論の“急所”であるくりこみ理論の勘どころが、この一冊で基礎から理解できる。
物性物理から素粒子物理まで、幅広い物理現象の本質をとらえる「くりこみ理論」を丁寧に解説。多くの人の「学ぼうとしても、たどり着く前に挫折する」という経験を熟知した著者が、物理的直観を重視して読者を導く一冊。

2014.07.25発売
今度こそわかるP ≠ NP予想
計算機科学の最重要難問に挑む! わかりやすい具体例と図表をふんだんに取り入れ、P≠NP予想の背後にある考え方を実感できるように工夫した。計算機科学の独特の記法や言い回しもしっかりと説明し、初学者がスムーズに理解を進められるように記述。近年の新しい発見も解説し、最先端の研究への架け橋となる一冊。
計算機で解けない問題は存在するか?計算機科学の奥深くに控えた重大な未解決問題が、学部生レベルの数学を超えない予備知識で理解できる。今までのどの本を読んでもよくわからなかった読者に贈る、平易な「再入門書」。

2014.07.25発売
今度こそわかるゲーデル不完全性定理
ゲーデルは、何を証明しようとしたのか? 不完全性定理を初学者が一歩ずつ着実に理解できるように、平易な言葉遣いで説明。初学者がつまずくところを熟知した著者が丁寧に解説した。この難解な定理を、「ふつうの言葉」で説き明かす!
ゲーデルは、何を証明しようとしたのか? 数理論理学を初学者に教えれば右に出る者のない著者が、わかりやすい言葉遣いで説く。初学者が不完全性定理を一歩ずつ着実に理解できるように心がけた、新しい入門書。

2014.07.25発売
単位が取れる微積エッセンス
超人気講師・さいとう先生の鬼わかりやすい解説をよんで勉強すれば、単位もラクに取れる! 微積の勉強が楽しくなる! 微積に困った学生に朗報の一冊。多変数も詳しく解説。

2014.07.25発売
単位が取れる微分方程式ノート
欲しいもの、汝の名は単位なり。
受験数学界にその名を轟かせた人気講師が、“最重要ポイント”をズバリ解説。すらすら読めてらくらく使える!
大学生向け試験対策本
予備校生に人気の実力派講師・齋藤寛靖先生が、大学生のために特別講義!丹念な説明と選りすぐりの問題で、単位取得を着実にアシスト。それに微積の基礎から高階の微分方程式まで、大事なところを素早く学べる工夫がいっぱい。効率的に勉強したいアナタに。

2014.07.25発売
イラストで学ぶ 機械学習 最小二乗法による識別モデル学習を中心に
最小二乗法で、機械学習をはじめましょう!! 数式だけではなく、イラストや図が豊富だから、直感的でわかりやすい! MATLABのサンプルプログラムで、らくらく実践! さあ、黄色本よりさきに読もう!
【目次】
第I部 はじめに
第1章 機械学習とは
第2章 学習モデル
第II部 教師付き回帰
第3章 最小二乗学習
第4章 制約付き最小二乗学習
第5章 スパース学習
第6章 ロバスト学習
第III部 教師付き分類
第7章 最小二乗学習に基づく分類
第8章 サポートベクトル分類
第9章 アンサンブル分類
第10章 確率的分類
第11章 系列データの分類
第IV部 教師なし学習
第12章 異常検出
第13章 教師なし次元削減
第14章 クラスタリング
第V部 発展的話題
第15章 オンライン学習
第16章 半教師付き学習
第17章 教師付き次元削減
第18章 転移学習
第19章 マルチタスク学習
第VI部 おわりに
第20章 まとめと今後の展望

2014.07.25発売
完全独習現代の宇宙論
高校レベルの予備知識から出発し、読者が独力で現代宇宙論のエッセンスを理解できる独習書。無からの宇宙誕生から、元素の合成、天体の形成、そして宇宙の未来まで、宇宙の進化の歴史
に沿ってわかりやすく解説する。

2014.07.25発売
今度こそわかる場の理論
ていねいに説く「量子場」の基礎の基礎。学部1年生から「量子場の理論」に慣れ親しむための入門書。予備知識を最小限度に抑えて,ゼロから学んでいく。場の理論はむずかしくない!
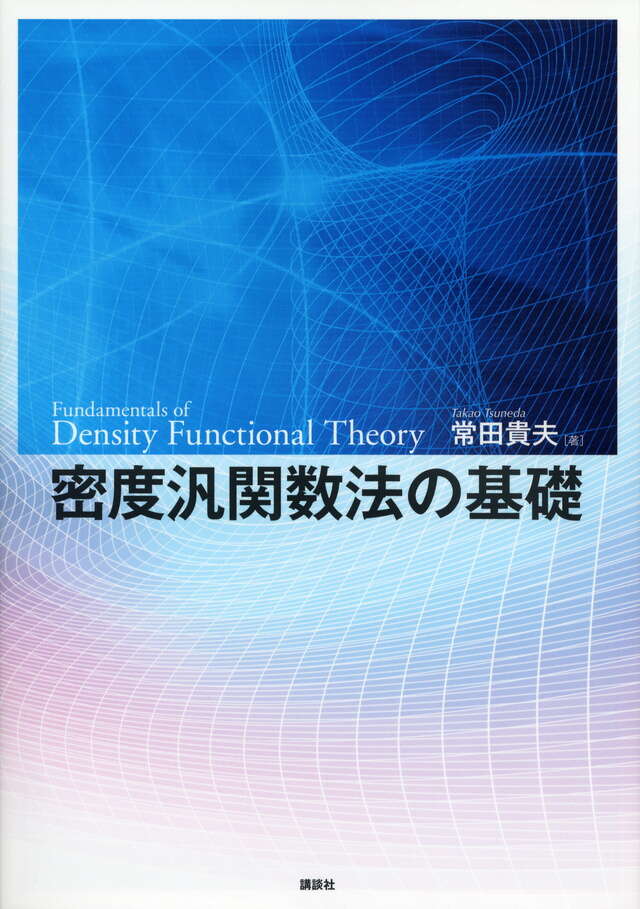
2014.07.25発売
密度汎関数法の基礎
コーンシャム方程式から様々な汎関数の種類まで詳しく解説。最新の研究も紹介。密度汎関数法に関わる理論・実験研究者に必携の一冊。世界的に見てもこれまで詳しく解説した本はない。

2014.07.25発売
大学院生のための基礎物理学
学部レベルの物理基礎科目を、一歩高い立場に立って俯瞰する。大学院生ならば知っておきたい物理学の基礎=「力学」「電磁気学」「熱学・統計力学」「量子力学」を網羅した一冊。それぞれの科目の重要事項を「ポイント」にまとめ、170題を超える例題・演習問題を付することで、学習と理解を助ける。学部生よりも一歩高度な立場に立って、物理学の基礎を着実に身につける。
学部レベルの物理学基礎科目を一歩高い立場から網羅!
専門の研究に進むために必要な素養を確実に身につける。
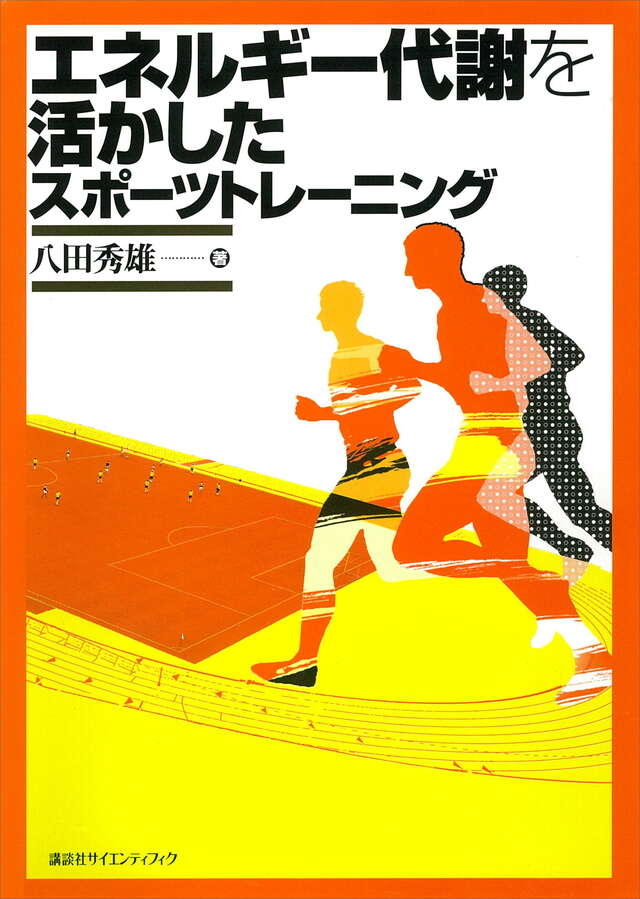
2014.07.25発売
エネルギー代謝を活かしたスポーツトレーニング
すべての運動は有酸素運動である。体を動かすエネルギーはどう作られどう使われるのかを、生化学的に探った一冊。理論的な背景を、実際の運動や競技に即して考察。疲労回復や持久力アップの秘策がわかる。『乳酸を活かしたスポーツトレーニング』の姉妹版。
すべての運動は有酸素運動である。
試合の途中でバテないために、必要なトレーニングとは何か。クレアチンリン酸が運動の決め手ではないか。ダイエットに有効な運動は何か。新たな見方で運動を考える。
無酸素運動なんてあり得ない。
20分運動しなくても、脂肪は使われているのですか?マラソンで、スパートについていける選手といけない選手の違いは?
運動時に体内がどうなっているのかを、運動生理生化学的に考える。理論的な背景を、実際の運動や競技に即して考える。