新刊書籍
レーベルで絞り込む :

2022.02.25発売
明清の戯曲(中国学芸叢書) 江南宗族社会の表象
創文社オンデマンド叢書
中国の演劇は社会と深く結びつきつつ独自の表現様式を生み出した。本書は明清期の江南の伝奇戯曲に光を当て、この地域特有の宗族社会の組織理念が演劇空間でいかに表現され、多くの作品群を性格づけたかを問う。著者は宗族組織の内部構造を分析し、五十以上に及ぶ作品の梗概を通して、中国人の生活感情と演劇の社会的機能を明らかにする。
【目次より】
序説 元明間の祭祀演劇の変化とその社会背景 農村の宗族構成から見た展望
第一章 明代江南宗族の祭祀体系
序節 外神系祭祀と内神系祭祀の関係 安徽省徽州府歓県渾渡黄氏 第一節 外神祭祀 第二節 内神祭祀 第三節 小結
第二章 明代江南宗族の演劇体系
序節 祭祀演劇の環境 安徽省徽州府休寧県老洲呉氏 第一節 外神祭祀 第二節 内神祭祀 第三節 演劇統制 第四節 小結
第三章 清代江南宗族による外神祭祀演劇の再編成
序節 清代江南同族村落の祭祀組織の再編成 第一節 郷村の社廟演劇組織の再編成 第二節 市鎮の社廟演劇組織の再編成 第三節 文武科挙神に対する演劇組織の形成 第四節 小結
第四章 清代江南宗族による共同体規制演劇の強化
序節 江南宗族の共有地支配の発想 第一節 水源地保全禁約の演劇 第二節 貯水池保全禁約の演劇 第三節 墳山竹木保全禁約の演劇 第四節 宗祠・墓祠保全禁約の演劇 第五節 小結
第五章 清代江南宗族による宗祠演劇の拡大
序節 宗祠演劇拡大の背景 第一節 個別祖先に対する寿誕祭祀演劇 第二節 祖先群に対する季節祭祀の演劇 第三節 進主(祖先神位入祀)の演劇 第四節 科挙及第者の祀祖謝恩演劇 第五節 超幽追薦演劇 第六節 小結
第六章 社祭演劇における宗族の戯曲選好
序節 社祭演劇に対する宗族の期待 第一節 節婦類 第二節 孝子類 第三節 忠臣類 第四節 功名類 第五節 風情類 第六節 遊賞類 第七節 超幽類 第八節 小結
第七章 宗祠演劇における宗族の戯曲選好
序説 宗祠演劇に対する宗族の期待 第一節 頌類 第二節 大雅類 第三節 小雅類 第四節 風類 第五節 超幽類 第六節 小結
第八章(上)宗族演劇の戯曲世界 宗族内部の戯曲世界
序節 宗族の内部統制に関わる戯曲世界 第一節 慶寿類 第二節 伉儷類 第三節 誕育類 第四節 訓誨類 第五節 激励類 第六節 分別類 第七節 思憶類 第八節 捷報類 第九節 小結
第八章(下)宗族演劇の戯曲世界 宗族外部の戯曲世界
序節 宗族の対外交流に関する戯曲世界
第一節 訪詢類 第二節 遊賞類 第三節 宴会類 第四節 邂逅類 第五節 風情類 第六節 忠孝節義類 第七節 陰徳類 第八節 栄会類 第九節 小結
終章 宗族演劇の現段階
注引文献

2022.02.25発売
開発経済学(新版)(現代経済学選書) 諸国民の貧困と富
創文社オンデマンド叢書
諸国民の貧困と富 先進国の技術導入を柱に、市場・共同体・国家の適切な統合により途上国を発展軌道に乗せる政策を示す。日経賞受賞。新版では「アジアの金融危機」の実証分析と、説明の改良とりわけ内政的経済成長論に新たな解説を加えた。資料も全面的に最新のデータへ更新した。
【目次より】
新版に寄せて
序論 開発経済学の課題
「開発経済学」と「開発途上国」 本書の構成
1 経済発展の理論的枠組
1.1 社会システムの発展過程
1.2 誘発的革新の理論
1.3 理論的枠組と途上国の現実
2 開発途上国の発展展望
2.1 国際比較へのアプローチ
2.2 経済成長と構造変化
2.3 投資・貯蓄・物価
2.4 人的資本の向上
2.5 人ロ・資源・食料
3 人口成長と天然資源の制約
3.1 経済発展と人口成長
3.2 人口成長の経済理論
3.3 資源制約説の系譜
4 資源の制約を打破するには
4.1 科学的農業の可能性
4.2 「緑の革命」の展望
4.3 誘発的革新への障害
4.4 余剰資源にもとづく発展
5 資本蓄積と経済成長
5.1 アダム・スミスからマルクスヘ
5.2 第2次大戦後の開発論と開発政策
5.3 新古典派的生産関数と成長モデル
5.4 成長会計による検証
5.5 成長パターンの変化
6 技術進歩とその源泉
6.1 成長パターンの様式化
6.2 成長パターン変化の技術的基礎
6.3 技術進歩の源泉を求めて
7 所得分配と環境問題
7.1 経済成長と所得分配
7.2 不平等化の要因
7.3 停滞と貧困
7.4 経済発展と環境問題
8 市場と国家
8.1 市場と国家の経済機能
8.2 幼稚産業保護論をめぐって
8.3 開発モデルの盛衰
8.4 開発理論のパラダイム転換
8.5 アジア金融危機が意味するもの
9 共同体の役割
9.1 共同体の機能
9.2 途上国農村の構造
9.3 共同体と経済合理性 フィリピンでの観察
9.4 共同体の失敗とその補正
付論 技術進歩に関する理論的補足
参考文献

2022.02.25発売
現代マクロ経済学(現代経済学選書)
創文社オンデマンド叢書
マクロ経済学はその姿を一変させ、今や新古典派理論の全盛となり、アメリカを中心とする学界もそれを「進歩」として支持する。著者はこれに断固として反対し、過去二五年間のマクロ経済学を批判的に検討し、理論の基礎をケインズの天才が見抜いた需要不足(=有効需要)に据えて、新しいマクロ経済学を試みる。中級レベルの学習のための道先案内を務める本書を通して、読者は実際的で豊かな可能性に満ちたマクロ経済学を見出すに違いない。
【目次より】
まえがき
図表一覧
序論
1 マクロ経済学の「新古典派化」
2 「新しい」ケインズ経済学
3 新しいマクロ経済学を求めて
景気循環の理論
1 Ramseyモデル
2 リアル・ピジネス・サイクル理論
3 ケインズ的アプローチ
4 金融政策と景気循環
経済成長論
1 Old Growth Theory
2 New Growth Theory 内生的成長モデル
3 経済格差の縮小
新しいマクロ経済学
1 価格と数量
2 生産要素の「不完全雇用」と生産性の部門間不均等
3 ルイス・モデル
4 需要と経済成長
5 残された課題 オープン・エンド
TFPと技術進歩の需要創出効果 技術進歩はいかにして生み出されるのか 技術進歩と不完全雇用
4章付論
文献表

2022.02.25発売
エネルゲイアと光の神学 グレゴリオス・パラマス研究
創文社オンデマンド叢書
14世紀の後期ビザンティンの神学者グレゴリオス・パラマス(1296―1359)の思想を神学の領域を超えて、人間の普遍的な神認識の問題として考察したわが国初の本格的研究。パラマスの神認識と彼の修道霊性を重視する態度から東方神学の特質を浮かび上がらせるとともに東方キリスト教に特徴的な霊的感覚を一種の認識論として捉え、霊と身体との調和をはかるパラマス思想の中に、反グノーシス的な身体・感覚の復権があることを明らかにする。
【目次より】
凡例
まえがき
序論 グレゴリオス・パラマスの生涯と著作
第一部 東方神学の特質
第一章 パラマスの「神認識」をめぐって
第二章 パラマスと哲学 ヘシカズムの伝統との関連において
第三章 ギリシア教父の遺産 人間の神化
第四章 光と闇の神学(変容の光とシナイの神の闇)
第二部 エネルゲイア論
第一章 パラマスにおける神の本質と働きの区別の問題(一)
第二章 パラマスにおける神の本質と働きの区別の問題(二)
第三章 パラマスにおける神の本質と働きの区別の問題(三)
第四章 エネルゲイア、ヒュポスタシス、エンヒュポスタトス
第五章 エネルゲイアとウーシアの区別の哲学的源泉
第三部 人間の神化と光の神学
第一章 ヘシカズムにおける神化の思想
第二章 「霊的感覚」
第三章 身体もまた祈る パラマスの身体観への試み
第四章 光の神学と否定神学
第四部 神のエネルゲイアと光の神学 東方の論理に向けて
第二章 光としての神
第三章 神化の神学
第四章 超否定神学 東方の論理
あとがき
初出一覧
参考文献
欧文要旨
欧文目次
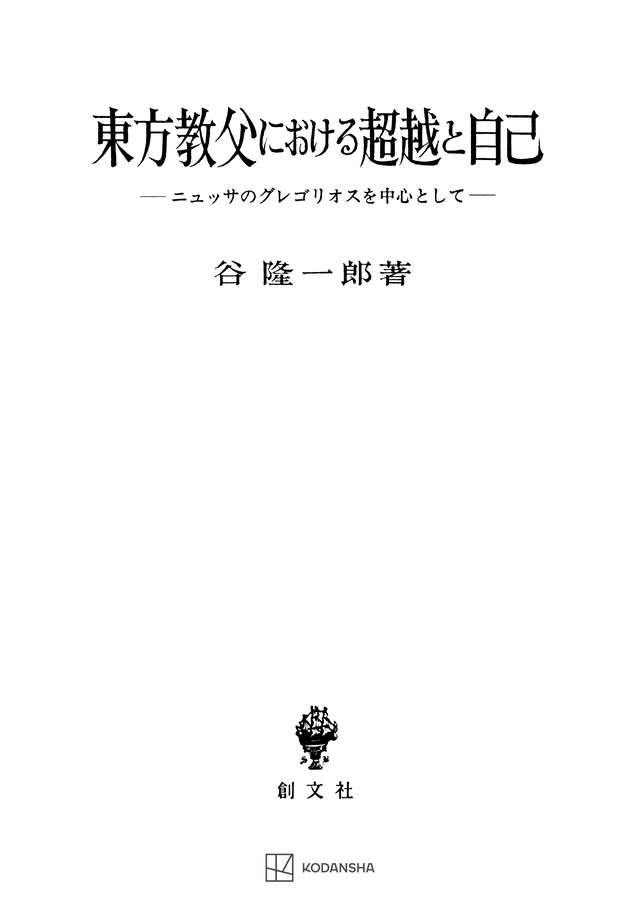
2022.02.25発売
東方教父における超越と自己 ニュッサのグレゴリオスを中心として
創文社オンデマンド叢書
東方ギリシア教父の伝統は、ヘブライ・キリスト教と古代ギリシア哲学という二大潮流の邂逅のうえに成立し展開した。それは思想史上、後世にとって規範ともなり源泉ともなった。本書は教父哲学の祖アレクサンドリアのクレメンスと哲学面での代表者ニュッサのグレゴリオスにおける愛智=哲学の中心に息づく存在論的ダイナミズムに視点をおいて、哲学や倫理学の根源的位相を明らかにし、研究の少ない未開拓な分野に本格的な鍬をいれた画期的業績。
【目次より】
はしがき
序章 教父の愛智とその指し示すところ
第一部 信と知との探究 アレクサンドリアのクレメンスに即しての展望
第一章 知を求める信 その動的な構造
第一節 クレメンスの人と時代
第二節 根源の出会いと信
第三節 創造の場に
第二章 敬神と愛智
第一節 信と知との開かれたかたち
第二節 否定の道
第三節 自然・本性と自由
第四節 神性の交わりと他者
第二部 ニュッサのグレゴリオスにおける超越と自己
第一章 愛智の基本的構造
第一節 神的ロゴスの現存の場に向かって
第二節 愛智の発動
第二章 神の名と否定神学
第一節 生の範型としてのモーセ
第二節 神の名の顕現
第三節 否定神学と象徴
第三章 エペクタシスの道行き
第一節 闇のうちなる神の顕現
第二節 自己超越の論理
第三節 絶えざる生成
第四章 存在の次元における自由の問題
第一節 創造と罪
第二節 自由意志と自己
第三節 欲望の問題
第五章 善の超越性と不断の創造
第一節 自由と行為と善の連関をめぐって
第二節 不断の創造
第三節 人間的自由と神性の働きとの共働
第六章 肉体・質料の復権と他者
第一節 人間的自由と悪
第二節 内的な砂漠
第三節 肉体・質料の復権
第七章 神性の全一的交わり
第一節 エクレシアとその動的な姿
第二節 神の宿り・顕現の機微
第三節 全一的交わりの成立
第四節 キリストの受苦と栄光 没薬と乳香
第八章 内なる根拠・キリストの発見
第一節 信と知との緊張
第二節 使徒的経験の場に
第三節 教理的文脈の吟味
第四節 人間的自由と新しい創造
註
あとがき

2022.02.25発売
ロシア・ナショナリズムの政治文化 「双頭の鷲」とイコン
創文社オンデマンド叢書
20世紀ロシアの国家・民族・ナショナリズムを、その深層に流れる政治文化に焦点を当て解明、歴史を貫く「ロシア的なもの」を剔出する。
【目次より】
はしがき
第一部 ロシア・ナショナリズムの政治文化
第一章 ロシアにおける国家と民族 歴史的、政治文化的考察
第二章 ロシア・ナショナリズムの歴史と政治文化
第二部 ソヴィエト体制下のロシア・ナショナリズム
第三章 「ユーラシア主義」とロシア国家像の転換 スラブ国家からユーラシア国家へ
第四章 ロシア革命と国家 「ナショナル・ボリシェヴィズム」の系譜
第五章 非スターリン化政策とロシア・ナショナリズム ヴェ・オーシポフをめぐって
第六章 グラースノスチ下のロシア・ナショナリズム運動
第三部 ロシア正教会とナショナリズム
第七章 ゴルバチョフ政権下のロシア正教会とナショナリズム
第八章 宗教とナショナリズム 西ウクライナの「ギリシア・カトリック教会」をめぐって
第九章 ソヴィエト体制崩壊後のロシア正教会とナショナリズム 自由の背理とアイデンティティ危機
第十章 二〇世紀のロシア正教会 チーホンからアレクシー二世へ
註
あとがき
初出一覧

2022.02.25発売
ハイデガー哲学の射程
創文社オンデマンド叢書
『存在と時間』の真の射程がギリシア哲学(プラトン・アリストテレス)の存在への問いにあることを示しその根本構想を解明、ハイデガーの思惟の道、さらには西洋哲学の根底に潜む問題地平(形而上学・存在論)を鋭く描いた意欲作。
【目次より】
序 ハイデガー哲学の射程
凡例
第一章 形而上学
第一節 存在論 神学としての形而上学とその一性
第二節 形而上学の二重性と基礎的存在論の理念
第三節 『存在と時間』の書き換えと形而上学の問題
第二章 存在論
第四節 存在論的差異とイデア論
第五節 存在の意味への問いとアナロギアの一性(プロス・ヘン)
第六節 存在を超えて
第三章 現象学
第七節 現存在の現象学
第八節 真理
第九節 解釈学
第四章 現存在の分析論
第十節 道具分析の存在論的射程
第十一節 終りとしての死と時間性
第十二節 良心と現存在の分析論
註
あとがき

2022.02.25発売
十字架のヨハネ研究
創文社オンデマンド叢書
一六世紀スペインの神秘家で詩人であった十字架のヨハネに関する初めての本格的研究。人間の魂が神との合一に向かう過程を入念に叙述・分析したヨハネの作品は、心理分析の精緻さと的確さ、さらには哲学的・人間学的な洞察の鋭さにおいてスペイン文学史上の至宝ともいえる古典である。著者は独自の方法により宗教言語論的特性を解明するとともにその解釈学的構造を分析、ヨハネ神秘思想の全貌を明らかにして、従来の神秘主義理解の視野を拡大する。
【目次より】
序文
略記号表
第I部 序論
一 生涯と時代
二 作品
(1) 造形作品 (2) 主著(3) 詩 (4) その他 (5) テクスト
三 思想の源泉
(1) 聖書 (2) カルメル会の伝統 (3) 教父、正統神学者 (4) スペイン神秘主義 (5) 世俗文学 (6) ドイツ系神秘主義 (7) ルネサンス思潮 (8) ユダヤ教神秘主義 (9) イスラム神秘主義
四 方法と視点
第一節 視点・関心・方法 第二節 本書の構成
第II部 道程
一 神への翻案/人への翻案 『ロマンセ』の位置
二 愛にみちた観念 『カルメル山登攀』における否定神学とそれを破るもの1
三 見ることと触れること 『カルメル山登攀』における否定神学とそれを破るもの2
四 夜の構造 『カルメル山登攀』・『暗夜』の根本イメージ
五 魂の受動性 『暗夜』の根本問題
第III部 合一
一 合一を語る言葉 『愛の生ける炎』における神秘的合一のイメージ1
二 魂の中心/神の中心 『愛の生ける炎』における神秘的合一のイメージイメージ2
三 甘美な接触 『愛の生ける炎』における神秘的合一のイメージ3
四 神のかげ 『愛の生ける炎』における神秘的合一のイメージ4
五 私の胸で恋人は目覚める 『愛の生ける炎』における神秘的合一のイメージ5
六 合一の人称 『霊の讃歌』における神秘的合一把握
あとがき

2022.02.25発売
十九世紀英国の基金立文法学校 チャリティの伝統と変容
創文社オンデマンド叢書
有名パブリック・スクールの多くは、チャリティ(市民公益活動)によって創設された基金立学校である。19世紀教育改革期、国民教育全体の原資として再編が期待されたにも拘わらず、基金立学校はなぜ中流階級の中等教育機関として、国家統制を回避し独立セクターの中にその公益性を閉じ込めることになったのか。その過程を階層統合の挫折として捉える本書は、王立委員会報告書など公文書からその実態を解明する。教育理念・教育内容を巡る問題を、従来看過されてきた財政基盤との関わりで法制史的に論じた教育史の労作。
【目次より】
はしがき
序論 問題の所在と研究課題の設定
第I部 一九世紀初期基金立学校の実態と再編課題
第一章 基金立学校の基本的形態
第二章 基金立文法学校における「エルドン判決」の意義
第三章 基本財産(endowment)をめぐる論争
第II部 チャリティの監督機関の創設と基金立学校の改組構想
第四章 産業社会におけるリベラル・エデュケーション論争
第五章 チャリティ監督機関の設立と中流階級教育の高揚
第六章 基金立学校の改革構想
第III部 基金立学校の再編過程と二元的セクターの形成
第七章 基金立学校委員会(一八六九─七四年)の政策執行とその性格
第八章 基金立学校への公費補助
第九章 中等教育における公的セクターの成立
結論
あとがき
年表
文献一覧

2022.02.25発売
神学的言語の研究
創文社オンデマンド叢書
ケーベル博士は西洋文化の理解のために神学の基礎知識が不可欠であると力説したが、いまだ神学は学問として認知されていない。本書はトマス・アクィナスが厳密な意味で「学」である神学を構築した事実を言語学的側面から論証、特に彼の神学が聖書と結びつくことにおいて「学」として確立することを明らかにし、学問領域の拡張を試みた問題作。
本書はトマス・アクィナスが厳密な意味での「学」としての神学をいかに構築したかを、“神”と呼ばれる神秘に関わる認識的・学問的言語としての神学的言語であるアナロギア、神の像、悪などに注目しつつ『神学大全』の分析をとおして論証する。とくに聖書的神学と対立するとされたトマスの神学が、むしろ徹底して「聖書的」であり、聖書と結びついてはじめて「学」として確立したことを明らかにした。さらに近代の人間中心主義的な理性観の限界を越えて、学としての神学が既存の学問だけではなく、われわれ自身にも知られていない認識能力の可能性を拓き、理性の自己超越性を洞察するうえでいかに有効であるかを、信仰告白や神秘経験の表現である宗教言語とは区別された神学的言語を考察することにより解明している。
【目次より】
まえがき
序論
第一章 「学」としての神学
I 「学」としての神学の可能性 II 「学」としての神学をめぐる問い など
第二章 トマス・アクィナスと神学的言語
I 神学と聖書 II 神学的言語について など
本論
第三章 神学的言語としてのアナロギア
I トマス神学とアナロギア II トマスの「アナロギア」理解 など
第四章 神学的言語としての「神の像」(1) 「神の像」再考
I 問題 II 「人間の尊厳」をめぐる問題 I など
第五章 神学的言語としての「神の像」(2) トマス・アクィナスにおける神学的言語としての「神の像」
I 問題 II 「神の像」の概念 III 「神の像」としての人間 IV 結び
第六章 トマスにおける神学的言語としての「悪」(1)
I 問題 二つの「悪」言語 II 欠如(privatio)としての悪 Iなど
第七章 トマスにおける神学的言語としての「悪」(2)
I 問題 II キリストにおける悪 III キリストの罪 など
第八章 キリスト論と神学的言語
I 問題 「学」としての神学 II アンセルムスにおける「学」としての神学 III 神学的言語としての「適わしさ」 など
第九章 受肉と神化
I 序論 問題 II 見神と神化(1) III 見神と神化(2) など
付論
一 トマス・アクィナス『神学大全』の基本的構想
二 神学的言語について
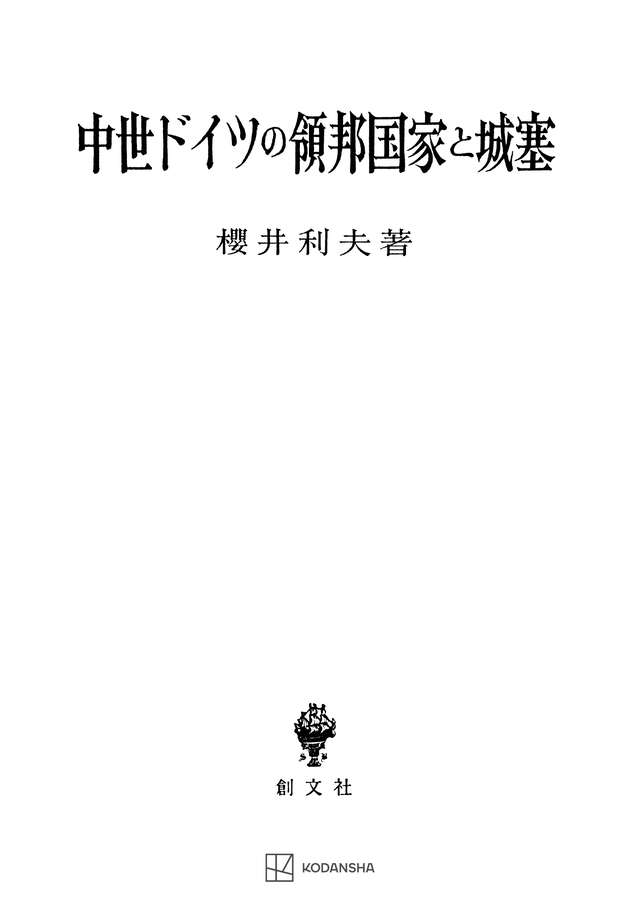
2022.02.25発売
中世ドイツの領邦国家と城塞
創文社オンデマンド叢書
中世ドイツには一万以上もの城塞が遍在した。それは村落や都市と並ぶ第三の定住形態として、教会と共に中世の決定的要素をなした。人格的結合関係たるレーエン制国家から官僚制国家への移行期にあたる一四世紀前半という中世後期にあって、城塞レーエン制は領邦支配権の拡大と強化を促す機能を果たす。領邦の生成と発展の上で城塞がいかなる法制史的国制史的意義を有したのか、本書はトリール大司教領を対象として原史料に基づき論じた我が国初の城塞史研究。
【目次より】
序
目次
第一章 一四世紀トリール大司教領における城塞とランデスヘルシャフト 城塞レーエン政策の視角から
一 はしがき
二 築城高権と自由所有城塞
三 城塞レーエン政策とランデスヘルシャフト
四 むすび
第二章 トリール大司教バルドゥイーンの城塞政策と領邦国家 レーエン制の視角から
一 はしがき
二 城塞レーエン政策
1 マイエン城塞
2 マールベルク城塞
3 キルブルク城塞
4 モンタバウアー城塞
三 レーエン城塞
1 ビショフシュタイン城塞
2 フェーレン城塞
3 エルレンバッハ城塞とデールバッハ城塞
四 むすび
第三章 トリール大司教領国における城塞と領域政策
一 はしがき
二 大司教バルドゥイーンと文書主義
三 第一次シュミットブルガー・フェーデ
1 はじめに
2 前史
3 経過
四 第二次シュミットブルガー・フェーデ
五 第三次シュミットブルガー・フェーデ
六 むすび
第四章 トリール大司教領国における城塞とアムト制 大司教バルドゥイーンの治世(一三〇七ー五四年)を中心として
一 はしがき
二 アムト制
三 アムトの中心としての城塞区
(i) 大司教の自由所有城塞 (ii) 大司教が質権に基づいて専有する城塞 (iii) 大司教が授封したレーエン城塞 (iv) 大司教と同盟した城塞(都市)
四 むすび
引用史料・文献一覧

2022.02.25発売
柳宗元研究(東洋学叢書)
創文社オンデマンド叢書
柳宗元文学の根幹である寓言を対象に敗北・蘇生の意味を解き明かし、彼の否定への意志とその反語性を考察した力作。
【目次より】
序
第一編 敗者の美学
第一章 左遷の中の文学
一 柳宗元の生涯
二 〈柔外剛中〉と道への希求
三 絣文から古文への転換
四 困窮と文学
第二章 敗北の逆説 寓言論
一 社会への憤激
二 自戒のために
三 愚者の文学
四 理想と敗北
第二編 自然との対峙
第一章 「永州八記」について
一 「永州八記」の源流
二 「永州八記」と『水経注』
三 「永州八記」の構造
四 「滸黄渓記」の誕生
第二章 山水詩 宗教から文学への転回
第一節 永州前期の山水詩
一 不遇な現実と山水遊覧
二 慰めの世界を求めて
三 消えない憂愁
四 高所からの眺め
第二節 永州後期の山水詩
一 表層と深層の逆説
二 孤高の思索者 「寂霙」をめぐって
三 「漁父歌」の系譜
四 宗教感情の変容
五 低所からの眺め
第三章 草木を植えるうたの位相
一 永州時代について
二 柳州時代について
三 草木を植えるうたの変遷(一) 漢魏六朝時代
四 草木を植えるうたの変遷(二) 唐代
五 『楚辞』の継承と超克
第三編 古文家の絆
第一章 文学論のめざすもの
第一節 柳宗元の文学論
一 文学の理念
二 文学の機能
三 文学の効用 「社会教化説」と、芸術性の追求
四 文学の動機
五 文学の地位 「代償行為論」「文学自立論」
六 創作論
七 文学の評価
第二節 唐代古文家の文学論
第二章 韓柳友情論
一 がまを食べるうた
二 師道のあり方
三 ユーモア文学礼讃
四 仏教との関わり
五 韓愈「順宗実録」の成立とその意義
第四編 否定の深層
第一章 「非国語」について
一 「文采」と「大中の道」 思想と文学の本質
二 「非国語」の内容
三 『国語』批判の根拠
四 文学の源泉としての『国語』
五 「非国語」と陸淳『春秋微旨』
第二章 自己処罰の文法
一 柳宗元の弁明(一) 許孟容への手紙
二 受難者の群像
三 柳宗元の弁明(二) 楊憑への手紙ほか
四 自責の文学
五 劉萬錫の弁明
六 柳宗元の設論
第三章 飛べない鳥
一 『詩経」と「楚辞』について 加害者の視点から被害者の視点へ
二 漢魏六朝詩について
三 唐詩について
四 柳詩の飛べない鳥
結

2022.02.25発売
中国古代の「謡」と「予言」(東洋学叢書)
創文社オンデマンド叢書
謡を通して中国古代社会の予言がいかに大きな意味をもち、それが現実の政治と社会への鋭い批判であったかを明らかにした初の本格的業績。
【目次より】
第一章 「謡」とは何か
第一節 「謡」の研究史
第二節 「謡」の起源とその定義
第三節 「謡」の政治的・社会的意味
第四節 「謡」と「予言」
第二章 前漢初期の「歌」とその予言性
第一節 呂后をめぐって
第二節 「淮南民歌」について
第三節 「穎川兒歌」について
第四節 「淮南民歌」と「穎川兒歌」の深層 准南王安と田紛、王太后、そして武帝
第五節 前漢初期の「歌」の「予言」 『漢書』の解釈
第三章 前漢の「謡」と「予言」
第一節 娃弘と夏侯勝の「予言」について
第二節 元帝の時の「謡」
第三節 成帝の時の「謡」
第四節 前漢末の「謡」 王非をめぐって
第四章 後漢の「謡」と「予言」
第一節 順帝の時の「謡」
第二節 桓帝の時の「謡」
第三節 鴬錮の禍をめぐる「謡」
第四節 後漢末の「謡」
第五章 「童謡」と焚惑
第一節 焚惑
第二節 「童謡」と焚惑
第六章 古代中国の予言
第一節 詳瑞と災異
第二節 予言「秦を亡ぼす者は胡なり」について
第三節 予言「始皇帝死して地分かれん」と予言「今年、祖龍死せん」について
第四節 「予言」の後
第五節 「予言」の政治性と「謡」
注
あとがき
漢代外戚関係網

2022.02.25発売
ニヒリズムの思索
創文社オンデマンド叢書
ハイデッガーと西谷啓治を手がかりに仏教において「始源的なもの」がいかに追究されてきたかを論じ、新たな自己の成立を明らかにする。
【目次より】
序
第一部 ニヒリズムの思索の境位に向けて
第一章 ニヒリズムの問い方
1 ニーチェのニヒリズムの思索 2 主観ー客観構造と実存 3 第四の歴史哲学的立場 4 「体験」と「実在の自覚」
第二章 西谷啓治の空の立場
1 ヨーロッパのニヒリズム・日本のニヒリズム 2 「空」の立場 3 パースペクティヴ主義と回互的相入 4 永遠の今即歴史的今、歴史的今即永遠の今 5 西谷の空の立場の意義
第三章 ハイデッガーの始源への遡行
1 ハイデッガーの歴史の思索 2 思索の歴史の始源 3 存在歴史の思想 4 存在歴史的思索 5 超克の否定 6 ハイデッガーの思索のもたらすもの
第二部 始源的な思索に向けて
第一章 大乗経典制作と解釈学
1 大乗仏説非仏説論争の発生 2 真理と仏説 3 言葉と聖典制作 4 聖典と解釈 5 ガダマーの解釈学の視点から
第二章 伝統を創出する視点
1 伝統への視座 2 ガダマーの伝統の思想 3 宗教経験における伝統 4 釈尊における古道との同定 5 伝統とテクスト 6 伝統とニヒリズム
第三章 死後の他界の観念
1 文化の内に沈殿する宗教的観念 2 他の世界としての他界 3 霊魂の在所 4 方向としての他界 5 生存の外を指し示す方向 6 他界の表象
第三部 自己の思索に向けて
第一章 近代の自己の変容
1 現代における「自己」の状況 2 キェルケゴールの「内面性」 3 罪の主体としての自己 4 無に面した自己 5 世界からの自己の理解
第二章 世界像とリアリティ
1 科学的世界像と神話的世界像 2 世界像と科学 3 現代技術と世界像の解体 4 世界のリアリティ 5 ヴァーチャル・リアリティ
第三章 布施と供犠
1 ヴェッサンタラ太子本生話 2 布施と所有 3 贈与と布施 4 アプラハムとイサクの物語 5 布施における「私」の成立
あとがき
註

2022.02.25発売
エックハルト ラテン語説教集 研究と翻訳
創文社オンデマンド叢書
アリストテレスを初め多くの権威や当代の説教理論に基づいたエックハルトの高度な思想が平易に説かれた貴重な全五六編の邦訳と註。
【目次より】
凡例
聖書略号
はじめに
第1部 研究篇
I 聖書解釈について
II 愛について
III 神愛について
IV 恩寵について
V 秘蹟について
VI 三位一体について
第2部 翻訳篇
ラテン語説教の概要
ラテン語説教および註(全56篇)
あとがき(初出一覧)
文献一覧(聖書,古典引用文献,参考文献)

2022.02.25発売
北朝鮮の経済 起源・形成・崩壊
創文社オンデマンド叢書
1930年代の経済統制期から近年の崩壊までの北朝鮮経済を、国内外を通じて初めて一貫した論理で説明する。
1945年8月8日に対日参戦したソ連軍は、その直後に朝鮮半島に進攻し、同月20日すぎには北朝鮮(38度線以北)のほぼ全域を支配下においた。これが北朝鮮における共産主義(金日成)政権の始まりであった。本書の課題は、この政権下の北朝鮮経済を実証的および理論的に解明することである。
【目次より】
凡例
北朝鮮概観図
はしがき
図表目次
序章 戦時期朝鮮の経済統制
1 農業統制 2 工業統制 3 むすび
前編 生成期の北朝鮮経済
第1章 農業制度の変革
1 土地改革の準備 2 土地改革の実施 3 国家統制 4 総括
第2章 穀物の徴収と生産・消費
1 穀物徴収 2 穀物生産 3 農民の穀物消費 4 むすび
第3章 工業
1 基本政策 2 国営沙里院紡織工場 3 生産の検証と考察 4 まとめ
第4章 労働者
1 公表文献にみる労働者 2 捕獲文書にみる労働者 3 職場離脱の要因 生活・労働条件 4 労働需給と労働者の性格 むすびに代えて
補論1 8・15前後の北朝鮮産業施設の破壊と物資搬出
補論2 1947年貨幣改革
後編 金日成体制下の北朝鮮経済
はじめに
第5章 農業の実態
1 協同農場
2 機械化,化学化
3 むすび
第6章 経済の構造と特質
1 構造 農業と工業
2 特質
3 総括
第7章 金日成体制の理論分析
1 独裁モデル
2 金日成体制
3 理論化
4 結論
補論3 援助と貿易
補論4 1990年代の食糧危機
補論5 農業崩壊のモデル分析
終章 結論
付表
あとがき
参考文献
重要事項略年表

2022.02.25発売
新社会哲学宣言
創文社オンデマンド叢書
新社会哲学とは、何よりも、「ポスト専門化」時代におけるトランス・ディシプリナリーな哲学と社会科学の統合態を意味している。著者は、社会認識の方法として、個人の存在を軽視する全体論(ホーリズム)も、アトミスティクな個人を暗黙に想定する個人主義も採らない。その代わりに、自己と他者と世界の了解がそれぞれ区別されつつも、切り離せないという前提の下、全体論的で対話論的で生成論的な「自己-他者-世界」了解を社会認識の中核に据える。社会科学のトランス・ディシプリナリーな基礎概念を再定式化し、公共世界という観点から政治と経済の世界を架橋する、現代自由学芸の騎士による新社会哲学宣言。
【目次より】
序
第一部 社会理論の学問史的論考
第一章 プレ専門化時代(一九世紀前半まで)の社会理論:その諸潮流の再構成
第二章 専門化時代(一九世紀中葉から二〇世紀中葉)における社会諸科学と哲学:その再考
第三章 ポスト専門化時代(二一世紀)の哲学と社会科学:その理念
第二部 新社会哲学の論理とヴィジョン
第四章 相関社会科学的問題群・基礎概念の定式化:社会科学基礎論の試み
第五章 政治哲学の現代的再構想
第六章 経済哲学の復権
第七章 新社会哲学のアクチュアリティ
注
参考文献

2022.02.25発売
宋学の形成と展開(中国学芸叢書)
創文社オンデマンド叢書
宋学における道問性と尊徳性という共通認識と思考枠組の変遷を、「礼」の解釈を軸に分析した画期的業績。
【目次より】
はしがき
I 天
一 天譴論
二 郊祀論
三 天理による統合
四 朱熹による展開
五 天譴論の再現
六 郊祀論の再現
II 性
一 北栄の性説
二 朱熹の定論
三 心身情性
四 無善無悪
五 朱陸の異同
六 非難と調停
III 道
一 主題の構成
二 理学の開山
三 虚像の成立
四 従祀の昇降
五 唐宋の変革
六 道統の後継
IV 教
一 聖人の教え
二 礼学の意義
三 冬官の補亡
四 教化の職官
五 家礼と郷礼
六 漢字と宋学
参考文献
あとがき
年表

2022.02.25発売
海外直接投資の経済学
創文社オンデマンド叢書
80年代に本格化したわが国の海外直接投資の決定要因とその経済効果の相互連関を、マクロ計算モデルを用いて本格的に分析した成果。
【目次より】
はしがき
第1章 日本の海外直接投資の計量分析に関する基礎的考察
はじめに
第1節 日本の海外直接投資の一般的特徴
第2節 直接投資の定義と実際の統計
第2章 日本の海外直接投資の決定要因と経済的効果の計量分析
はじめに
第1節 直接投資の決定要因の分析
第2節 直接投資の貿易効果の分析
付論 直接投資の雇用への影響
第3章 海外直接投資のマクロ計量モデル
はじめに
第1節 モデルの基本的特徴
第2節 海外生産活動のモデル化
第3節 海外直接投資の経済的効果のモデル化
第4章 国内経済活動部門のマクロ計量モデル
はじめに
第1節 国内経済活動部門の枠組み
第2節 主要な構造方程式の推定結果
第5章 マクロ計量モデルの動学的性質
はじめに
第1節 モデルの相互依存関係と現実説明力
第2節 モデルの動学的性質
第6章 日本経済の環境変化と海外直接投資・海外生産
はじめに
第1節 為替レートの変動による直接投資・海外生産の変動
第2節 世界貿易の拡大と直接投資・海外生産
第3節 海外直接投資・海外生産の変動と貿易効果
第4節 海外生産活動の変化と貿易取引
補論1 世界輸出価格指数,世界貿易数量の作成についてのデータ
補論2 ファイナル・テストについて
付表 方程式体系一覧
参考文献

2022.02.25発売
六朝道教思想の研究(東洋学叢書)
創文社オンデマンド叢書
上清派道教と「太平経」の思想および祭祀・祈祷や道教像を通して道教信仰の具体相とそれを支える宗教意識を解明する。
中国の思想文化の一環としての道教思想について六朝時代を中心に考察し、道教が仏教の思想や儀礼を受容して、ひとつのまとまりを持った宗教として実質を整えていく過程を追う。
【目次より】
序論
第一篇 六朝時代の上消派道教の思想
第一章 『真詰』について
はじめに
一 茅山における神仙の降臨
二 仙・人・鬼の三部世界
三 真人への道
四 真人の世界
第二章 方諸青童君をめぐって
はじめに
一 方諸について
二 東海小童について
三 方諸青童君と終末論
おわりに
第三章 上清経の形成とその文体.
はじめに
一 上清経の形成
二 上清経の文体
おわりに
第四章 魔の観念と消魔の思想
はじめに
一 鬼と魔と魔王
二 消魔の思想 『洞真太上説智慧消魔真経』について
おわりに
第五章 上清経と霊宝経
はじめに
一 霊宝経の思想
二 上清経と霊宝経
三 五ー六世紀の上清派
おわりに
第二篇 『太平経』と六朝道教思想
第一章 『太平経』の承負と太平の理論について
はじめに
一 理想としての古
二 承負 積み重なる罪
三 循環の思想
四 承負と太平の理論の歴史的位置
おわりに
第二章 『太平経』における「心」の概念
はじめに
一 「天心」
二 「五臓の主」
三 心と善悪 「心神」「司命」
四 五臓神存思と守一
五 個人の養生と太平の世
おわりに
第三章 開劫度人説の形成
はじめに
一 緯書の天地観
二 「太平の気」「道気」の到来と天地再生
三 劫運思想の成立
四 河図洛書
五 石室の道経
六 天宮の道経
七 開劫度人説の成立
おわりに
付章 空海の文字観 六朝宗教思想との関連性
一 「自然の文」
二 六朝仏教の文字論
三 六朝道教の文字論
第三篇 六朝時代の道教信仰
第一章 六朝道教における祭祀・祈祷
はじめに
一 儒教の祭祀・祈祷観
二 神仙思想と祭祀・祈祷
三 六朝道教の斎
第二章 六朝時代の道教造像 示教思想史的考察を中心に
はじめに
一 道教造像の始まりとその様式
二 造像記の内容
三 造像を通して見た道教と仏教
おわりに
あとがき
英文目次・梗概