新刊書籍
レーベルで絞り込む :

2022.02.25発売
ドイツにおけるキルケゴール思想の受容 20世紀初頭の批判哲学と実存哲学
創文社オンデマンド叢書
20世紀初頭の批判哲学と実存哲学に初期フランクフルト学派による受容に光を当て受容の歴史的真相を系統的かつ総合的に解明した意欲作。
【目次より】
凡例
略記一覧
目次
序論
第一部 初期批判哲学のキルケゴール思想の受容
はじめに
第一章 初期ルカーチのキルケゴール論
第二章 初期マルクーゼの受容
第三章 初期ブロッホの受容
第四章 初期アドルノのキルケゴール論
第一節 「本来性の隠語」から見た批判の視点
第二節 批判の核心
第一部 要諦
第二部 初期実存哲学のキルケゴール思想の受容
はじめに
第一章 ヤスパースとハイデガーの初期論争点
第二章 『存在と時間』におけるキルケゴール思想の軌跡
第一節 「瞬間」の概念
第二節 「反復」の概念
第三節 「本来性」と「死」の概念
第四節 「不安」の概念
第三章 『存在と時間』以前の受容の軌跡
第一節 ヤスパースの『世界観の心理学』への『論評』
I ヤスパース批判の概要
II キルケゴール解釈の視点
第二節 初期「草稿」
I キルケゴール像の影
II キルケゴール受容の真相
第四章 ハイデガーの受容の問題
第一節 思考様式の異同性
第二節 K・レーヴィットの報知
第二部 要諦
結論
あとがき
註
引用・参考文献

2022.02.25発売
グローバル経済の産業連関分析
創文社オンデマンド叢書
今日の世界は,貿易や直接投資あるいは自然環境を通じて経済的な相互依存関係にある。それらの実態を分析する上で産業連関分析は成熟した分析手法として多くのエコノミストに利用されてきた。本書は新たに開発された最新の手法を紹介しつつ、経済のグローバル化に伴ってますます重視されてきたエネルギー消費と環境汚染物質の排出の関連といった環境問題をはじめ、アジアNIEsや米国との産業構造、費用構造の国際比較、消費税導入の経済効果、さらには地域間の産業構造格差や輸入財を除いた国産化率など、多岐にわたる実証分析の応用を通してその可能性を明らかにする。
【目次より】
はしがき
第1章 産業連関表と産業連関分析
産業連関表とは 産業連関分析 産業連関分析のミクロ経済的基礎と多部門経済モデル的発展
第2章 日本の産業構造の変化とその要因
はじめに 比例成長からの乖離モデル 日本の産業構造の変化とその要因 まとめ
第3章 韓国・台湾・米国の産業構造の変化とその要因
はじめに 韓国の産業構造変化とその要因 台湾の産業構造変化とその要因 米国の産業構造変化とその要因 まとめ
第4章 産業構造の地域間格差の要因分析
はじめに:日本の産業構造と国土政策 地域産業連関表での比例拡大からの乖離モデル 地域格差の要因分析 まとめ
第5章 環境問題と産業連関分析 産業別環境汚染物質発生量の予測
エネルギーと環境問題 持続可能な経済開発 エネルギー消費と二酸化炭素・硫黄酸化物排出量 産業別二酸化炭素・硫黄酸化物の排出量 日中の産業別二酸化炭素・硫黄酸化物排出量 二酸化炭素排出量の削減と技術移転 まとめと今後の課題
第6章 国産化率の推定
はじめに 産業連関表と国産化率の定義 国産化率の計測 多国間国際産業連関表を使った国際分業率 まとめと今後の課題
第7章 費用構造の国際比較 日本, アメリカ, 西ドイツを例にとって
問題意識と分析方法 価格決定モデルと国際間での価格格差 購買力平価による価格格差 ジョルゲンソン・黒田モデルの産業連関分析への応用 拡大ジョルゲンソン ・ 黒田モデルによる価格の日米比較 まとめと今後の課題
第8章 戦後日本の費用構造変化の要因分析
はじめに 費用構造変化の要因分解モデル 戦後日本の費用構造変化 まとめと今後の課題
第9章 消費税導入の経済効果 1990年産業連関表を用いた予測とその評価
はじめに 価格決定の基本モデル 伝票方式 帳簿方式 帳簿方式間接税(現行方式「消費税」)の経済効果 伝票方式間接税(中曽根内閣「売上税」)との比較 第6節 本章の分析の限界と今後の課題
参考文献

2022.02.25発売
カール・シュミットとカトリシズム 政治的終末論の悲劇
創文社オンデマンド叢書
“政治神学”“友と敵”“決断”“例外状況”“代表”。本書は、カール・シュミットの政治思想の特質を、彼の諸著作の徹底的な検証や他のカトリック知識人との比較考察を通して明らかにしたものである。近代合理主義・個人主義をプロテスタンティズムの産物と見做し、カトリシズムの教会論や終末論に依拠して痛烈に批判しつつも、遂に世俗化の犠牲となり、超越の契機を失い、ナショナリズムそしてナチズムと妥協していくシュミットの思考のプロセスが、克明かつ鮮やかに描き出される。
【目次より】
序
第一章 初期シュミットの終末論
シュミットの歴史観 シュミットの人間観 シュミット教会論 シュミット国家論
第二章 ドノソ・コルテスの政治神学
ドノソ・コルテスの生涯 歴史観 人間観 教会論 政治神学 ドノソの政治思想
第三章 シュミットの政治神学の展開 カール・シュミットとドノソ・コルテス
シュミットのドノソ継承 独裁論 自由主義批判 カトリック自然法論とシュミット ドノソとシュミットの相違点
第四章 シュミットの教会論
ヴァイマール期におけるカトリシズムの教会論 シュミットの教会論 シュミットの教会論に対する賛美 シュミットの教会論に対する批判 代表原理の衰退
第五章 ドイツ・カトリシズムにおける二つの道 カール・シュミットとフーゴ・バル
表現主義をめぐるシュミットとバル カトリシズムをめぐるシュミットとバル ナショナリズムと国家主義をめぐるシュミットとバルの対立 バルの禁欲的カトリシズム シュミットのバル評価
第六章 カトリシズムと世俗化 カール・シュミットとヴァルデマール・グゥリアン
決断主義と反自由主義 「世俗化されたカトリシズム」批判 ファシズムに対する態度 第三帝国におけるグゥリアンのシュミット批判
第七章 シュミットと政治的カトリシズム カトリシズム・ナショナリズム・国家
保守的カトリシズム ナショナリズム 国家主義 シュミットと中央党との対立
第八章 カトリシズムとナチズム K・エッシュヴァイラー、H・バリオン、W・グゥリアンの選択
K・エッシュヴァイラー H・バリオン W・グゥリアン
第九章 二つの終末論 カール・シュミットとエーリック・ペーターゾン
E・ペーターゾンの生涯 シュミットとペーターゾンの思想的関係 ライヒ・イデオロギー ペーターゾンの政治神学批判 ペーターゾンの終末論の展開 政治神学をめぐるシュミットとペーターゾン
第十章 シュミットの反ユダヤ主義
シュミットの反ユダヤ主義の展開カトリシズムと反ユダヤ主義
おわりに
シュミットの生涯と著作
あとがき

2022.02.25発売
アウグスティヌスの懐疑論批判
創文社オンデマンド叢書
本書はアウグスティヌスが回心後、最初に着手した初期の代表作で難解をもって知られる『アカデメイア派論駁』の世界でも初の総合的な研究成果であり、研究/翻訳/註解の三分より構成される。アウグスティヌスはアカデメイア派懐疑論の論駁を通して真理論や知識論に関する新たな理解を示したが、著者はそれがヘレニズム期のものともデカルト以降の近代の懐疑論とも異なり、命題の真偽、真理と善という価値をわれわれの生のあり方にどのように位置づけるかに核心があることをはじめて解明した。原著は19世紀以来、デカルト懐疑論との比較や新プラトニズム研究の視点などから考察されてきたが、未だその全体像は明らかになっていない。本書はアウグスティヌスの戦略的論法を読み解いて原著の意図を分析し、真理と行為の問題性を摘出した画期的作品。
【目次より】
まえがき
第1部 『アカデメイア派論駁』研究序説
第2部 『アカデメイア派論駁』
第3部 『アカデメイア派論駁』註解
第I巻
第1章1~4節 ロマニアヌス宛て書簡 第2章5~6節 討論の開始 第2章5節:全体的問題の提示 第2章5~6節:第I巻の問題の提示 第3章7節~第4章12節 知者 第3章7~8節:キケロと懐疑論の紹介 第3章9節:人間のfinis 第4章10~12節:誤謬の定義 第5章13節~第8章23節 知恵 第5章13~15節: 道 第6章16節:知恵の定義 など
第II巻
第1章1節~第3章9節 ロマニアヌス宛て書簡 第4章10節~第6章15節 アカデメイア派の紹介 第4章10節:設定 第5章11~12節:アウグスティヌスによるアカデメイア派の紹介 第6章14~15節:アリピウスによるアカデメイア派の紹介 第7章16節~第8章21節 ジュニアメンバーとの討論 第7章16節~第8章21節:父親似のたとえ など
第1章1節~第2章4節 序 第1章1節:導入 第1章1節~第2章4節: fortuna 第3章5節~第6章13節 シニアメンバーの討論(その2) 第3章5~6節:問題の提示 第4章7~10節:自分は知っていると思う
第5章11節~第6章13節:assensio 第6章13節:締めくくり 第7章14節~第9章21節 連続講話 第7章14節:モノローグの導入 第7章15節~第8章17節:アカデメイア派の評判 第9章18~21節:ゼノンの定義 第10章22節~第13章29節 認識 第10章22節:カルネアデス登場 第10章23節~第11章26節:自然学 哲学者の不一致 感覚・夢・狂気 第12章27~28節:倫理学 第13章29節:論理学 第14章30節~第16章36節 同意と行為 など
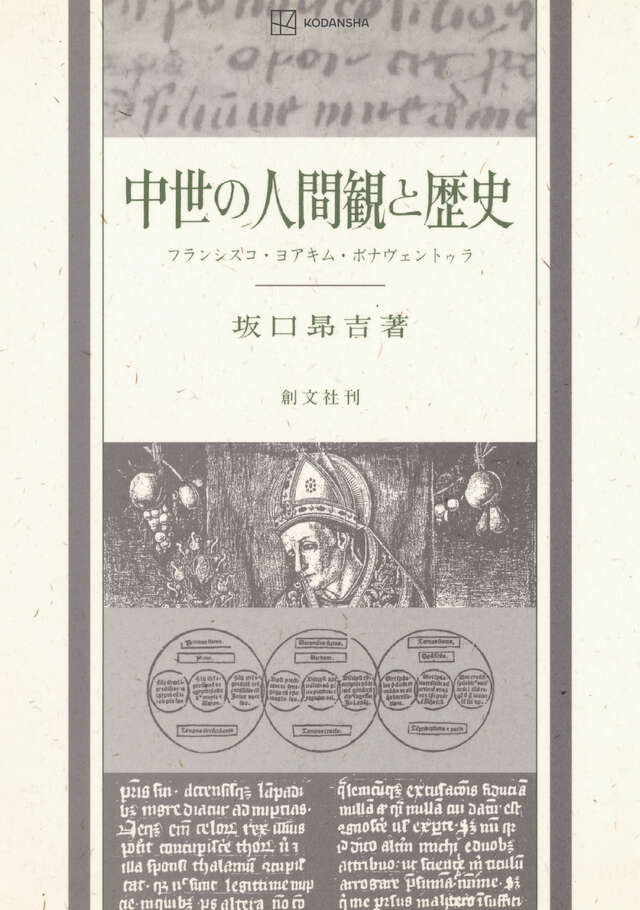
2022.02.25発売
中世の人間観と歴史 フランシスコ・ヨアキム・ボナヴェントゥラ
創文社オンデマンド叢書
人間の尊厳、歴史の進歩の肯定―ルネサンス思想の基盤をなすこの二つの近代的精神は、中世キリスト教世界の中で徐々に形成された。本書は十二・十三世紀の三人の宗教思想家、フランシスコ・ヨアキム・ボナヴェントゥラに焦点を当て、彼らの思想がフランシスコ会の設立、発展を通じて如何に融合し、近代的精神の宗教的母型を作り出したかを探る、著者四十年の研究の集大成。
【目次より】
まえがき
序論
I 中世における人間観の発展
II 中世における歴史観の発展
第一章 フランシスコ会の創立をめぐって
第二章 アシジのフランシスコと宗教運動
第三章 アシジのフランシスコとカタリ派
第四章 フランシスコ会の教団組織について
第五章 フランシスコ会における党派対立の原因について
第六章 ボナヴェントゥラとアリストテレス哲学の関係
第一節 若き日のボナヴェントゥラとアリストテレス哲学の関係
第二節 晩年のボナヴェントゥラとアリストテレス哲学の関係
第七章 ボナヴェントゥラのフランシスコ伝について
第八章 ヨアキムの歴史神学とスコラ学者
第九章 ボナヴェントゥラの歴史神学とフィオレのヨアキム
第十章 ボナヴェントゥラの歴史神学におけるキリストの位置
あとがき
初出一覧
註(略語一覧)
文献表

2022.02.25発売
フラクタル社会の経済学
創文社オンデマンド叢書
心理や文化という生きた現実的人間を前提に人間と経済のダイナミズムを解明、新しい経済理論の創造を目指した画期的業績。
【目次より】
はじめに
序章 新しいパラダイムをめざして
第I部 経済の変化と人間の内面世界における可変性
第1章 フラクタル社会の構造と変化
1 経済的「マシン」論からの脱却
2 フラクタル社会の基本モデル
3 現実世界と内面世界の相互依存的変化
第2章 「持つ様式」から「ある様式」へ 内面世界における可変性の例証(1)
1 進歩史観の終焉と「疎外された社会」
2 「持つ様式」から「ある様式」へ
3 「新しい人問社会」への改革
第3章 「清貧」の思想と「遊び」の哲学 内面世界における可変性の例証(2)
1 忘れられた「清貧の生きかた」
2 「遊び」の哲学と自己実現
3 人間を「マシン」と見る侮蔑的価値観を超えて
第II部 フラクタル社会のダイナミズムと可能性
第4章 ポリモルフィック・システムとしての経済
1 フラクタル化と「場の情報」
2 意味解釈システムの崩壊
3 ハードの危機とソフトの危機
第5章 意味解釈システムと自己超越プログラム
1 情報圧縮と無意識化された深層世界
2 自己超越プログラムの発動
3 「超・意味の体系」としての文化
第6章 経済のグローバル化と意味の体系の対立
1 グローバル化と内面世界の構造変化
2 情報場の変化と深層世界の「意識化」
3 技術的同質化と意味体系の対立
第7章 意味を革新する創造的社会をめざして
1 主体性の回復と内面的世界の豊かさ
2 主体性と社会システム
3 意味を革新する創造的社会をめざして
第III部 フラクタル社会の経済学:その論理と意義
第8章 新たなる論理と哲学
1 理論的前提としての人間観
2 社会科学の「豊かさ」
3 経済と文化を見る新たな視点
第9章 関連する諸研究
1 非営利セクターの経済学について 新古典脈アプローチの困難性を考えるために
2 センの『福祉の経済学』について フラクタル社会の「望ましさ」を考えるために
3 日本型システム論について 主体性のダイナミズムを考えるために
要約
参考文献
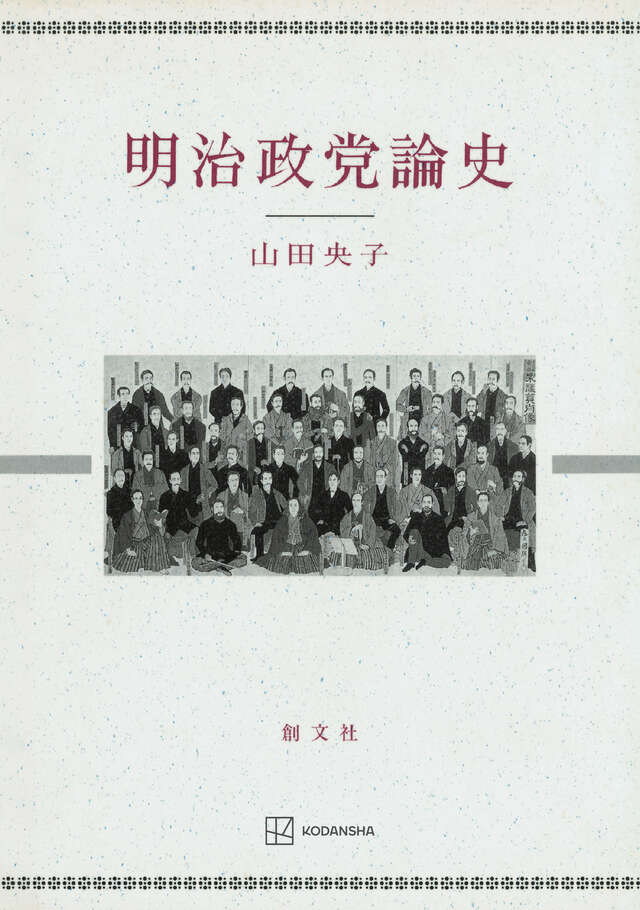
2022.02.25発売
明治政党論史
創文社オンデマンド叢書
政党をめぐる福沢諭吉・井上毅・陸羯南たちの思想的営為を、文化接触の問題として同時代の世界的文脈において考察し、明治政党論が含む豊かで多様な論点を鮮やかに提示する、政治思想史からの挑戦の書。
【目次より】
目次
凡例
序章
第一章 明治前半期における政党観の形成
第一節 明治十年代初頭における政党観 西欧の政党観の紹介
第二節 自由党における政党イメージ 伝統と西欧モデル
第三節 井上毅における政党観 「政党」と「政社」の別
第二章 福沢諭吉における政党内閣論の形成 明治一四年政変前後におけるイギリス政体論の変容と分岐
第一節 明治前半期における立憲政体論と政党の評価 「政党なき立憲政体」論の広がり
第二節 政党解釈における福沢の変化と『民情一新』以降の位置づけ 徒党から政党へ
第三節 イギリス政体論の変容と政党論 福沢諭吉と「イギリス派」の分岐
I 「イギリス派」における政体構想の分岐
II イギリス政体論の変容と政党の位置
III イギリスにおける政体論の再定義の試み
IV 福沢における政党内閣論と「近時文明」論の対応
第四節 明治政党論における福沢の位置
第三章 陸羯南における政党観の特質 初期議会前後を中心に
第一節 国民主義と政党
第二節 立憲政体における政党
第三節 政党内閣と内閣的政党
註
明治前半期政党関連翻訳著作一覧
あとがき
明治前半期政党関連年譜

2022.02.25発売
レッシングとドイツ啓蒙 レッシング宗教哲学の研究
創文社オンデマンド叢書
十八世紀啓蒙主義を代表する文学者レッシングの根本思想を初めて本格的に分析、『人類の教育』の訳を付す。十八世紀の「ドイツ啓蒙主義」の重要な一断面を、「世俗的敬虔」の原型をつくり出した、ゴットホルト・エフライム・レッシングという一人の思想家に即して解明する。
【目次より】
凡例
はしがき
序論 レッシング研究の意義と課題
1 レッシングの精神史的意義 2 レッシングと近代プロテスタント神学 3 レッシング研究の課題 4 レッシング研究の方法
第一章 レッシングとキリスト教
はじめに 1 レッシングの修業時代 2 レッシングと「断片論争」 3 レッシングの神学的立場 4 レッシングと「真理探求の道」 5 レッシングの神学思想 むすび
第二章 若きレッシングの宗教思想
はじめに 1 若き自由著作家の軌跡 2 若きレッシングの宗教的懐疑 3 若きレッシングの神学批評 4 喜劇『ユダヤ人』と普遍的人間性の理想 5 『理性のキリスト教』におけるレッシングの思弁 むすび
第三章 レッシングとゲッツェの論争
はじめに 1 論争の背景とその経緯 2 ゲッツェの攻撃 3 レッシングの弁明 4 レッシングの『反ゲッツェ論』 むすび
第四章 レッシングの「厭わしい広い濠」
はじめに 1 霊と力の証明 2 歴史の真理と理性の真理 3 宗教の「内的真理」 4 真のキリスト教的な愛 5 「レッシングの濠」の真正性 6 レッシングの問題とペテロの問題 むすび
第五章 『賢者ナータン』とレッシングの「人間性の思想」
はじめに 1 『賢者ナータン』の成立の背景とその主題 2 三つの指環の譬喩 3 中間時における歴史的宗教の真理性 4 ナータンと人間性の教育 5 ナータン的理性の本質 むすび
第六章 『人類の教育』におけるレッシングの根本思想
はじめに 1 『人類の教育』の基本的特質 予備的考察 2 『人類の教育』の基本構造 3 レッシングの歴史的境位 4 人類の教育としての啓示 5 啓示と理性の関係(1) 旧約聖書の時代 6 啓示と理性の関係(2) 新約聖書の時代 7 「新しい永遠の福音」と人類の完成 8 再受肉の思想 9 結論的考察 むすび
第七章 レッシングの「スピノザ主義」
はじめに 1 「汎神論論争」の発端 2 レッシングとヤコービの会話 3 ヤコービとスピノザ主義 4 メンデルスゾーンと「純化された汎神論」 5 レッシングの「ヘン・カイ・パーン」 6 レッシングの万有在神論 7 結論的考察 むすび
附録 レッシング『人類の教育』(全訳)
あとがき
参考文献

2022.02.25発売
コミュニティの法理論(現代自由学芸叢書)
創文社オンデマンド叢書
日本とドイツの地域社会や自治体調査の比較から、著者は《一社会の決定権限がコミュニティ・レベルまで分散している》との理論的着想を得て、生活世界からの法創造を試みる。本書は、現代のコミュニティは、単なる行政の下請けでもなく、地域福祉などのボランティア活動の担い手にもとどまらず、社会的決定の主体でもありうることをラディカルに主張する、現代自由学芸の騎士による時代診断・時代予測の書である。公共的決定とその執行を国家にゆだね、自らは身軽になって私的利益の追求に主たる関心をおいている現代社会の人間達は、いかなるきっかけで、地域社会の公共性に自ら携わるようになるのか。
【目次より】
はしがき
第一章 決定権限の分散現象についての問題提起 真野まちづくりと神戸市まちづくり条例
一 なぜ真野地区からはじめるか
二 神戸市まちづくり条例の概要
三 まちづくり条例における決定権限の分散
四 真野まちづくりの展開
五 決定権限の分散の理論的諸相
(1) 決定権限の分散の概念 事実上の公共的意思の制度上の公共的意思への転換
(2) 決定権限の分散概念の拡張
第二章 ドイツにおける決定権限の分散 ドイツの「自治体内下位区分」とブレーメン市の地域評議会
一 ドイツにおける決定権限分散=自治体内下位区分制度
二 「地域事務所」 「地域評議会」制度の形成
三 区域割り
四 地域評議会の組織
五 地域事務所
六 地域評議会の任務と権限
第三章 コミュニティ制度の日独比較は可能か
一 政党を基礎とする住民組織
二 地域評議会活動における「政治的なるもの」の概念
三 地域評議会は住民組織といえるか
第四章 決定権限の地域分散の構造
一 基礎的地域組織の諸問題 町内会を問う
二 住民組織の職務ないし権限の対象範囲と性格
三 住民組織の構成員
四 住民組織の組織エリア
五 住民組織の意思表明 多数決か全員一致か
六 決定権限の諸類型と強弱
第五章 コミュニティヘの道
一 あるコミュニティ形成過程 横浜市ドリームハイツ地区
二 コミュニティの源泉について 幼児教室すぎのこ会の歩み
三 コミュニティの共同性の実体について
四 コミュニティヘの道
註
文献解題

2022.02.25発売
中国の道教(中国学芸叢書)
創文社オンデマンド叢書
「道教とは何か?」この問いについて世界の道教学者の共通理解を見出すのは困難である。著者は道教の成立を後漢時代とする従来の通説を根底から批判し、5世紀中葉の天師道を母胎に成立したとして、儒・仏・道の三教の一つとして歴史的、具体的に道教についての明確な概念を初めて提示する。道教の宗教としての構造と教理、教団組織と信奉者の宗教意識、さらには道教の歴史を思想史的、体系的に一貫した視点から解説した画期的な概説である。思想研究のみならず歴史、文学をはじめ中国の基層文化と社会を理解するための必読書。
【目次より】
凡例
はしがき
目次
序章 「道教」の構造
一 「道教」の成立
二 「道教」の構造
三 「道教」と天師道
第一章 神仙道の形成
一五斗米道
二 太平道
三 葛氏道
四 上清派
第二章 「道教」の成立
第一節 天師道の成立とその思想
一 「三天」の思想
二 正一盟威の道
三 老子と『老子道徳経』
四 三洞説と「道教」
五 四輔説と道士の位階
第二節 教団の組織と教徒の生活
I 教団の旧制度 治と祭酒の制度
一 祭酒と道民
II 教団の改革
一 祭酒の戒の設置
二 道民の生活倫理
三 道士の職位の整備
III 教団の新制度 道館(道観)と出家道士の制度
一 道館の設置
二 道館での道士の生活
三 出家道士の位階制度
第三節 「道教」の世界観と修道法
I 世界観
一 天上界
二 人間界
三 三塗
四 南宮
五 洞天福地
II 修道法
一 護身法
二 滅罪法
三 長生法
第三章 「道教」の歴史
一 南朝の「道教」
二 北朝の「道教」
三 隋の「道教」
四 唐の「道教」
五 北宋の「道教」
六 南宋・金の「道教」
七 元の「道教」
八 明・清の「道教」
終章 「道教」の役割
注
あとがき
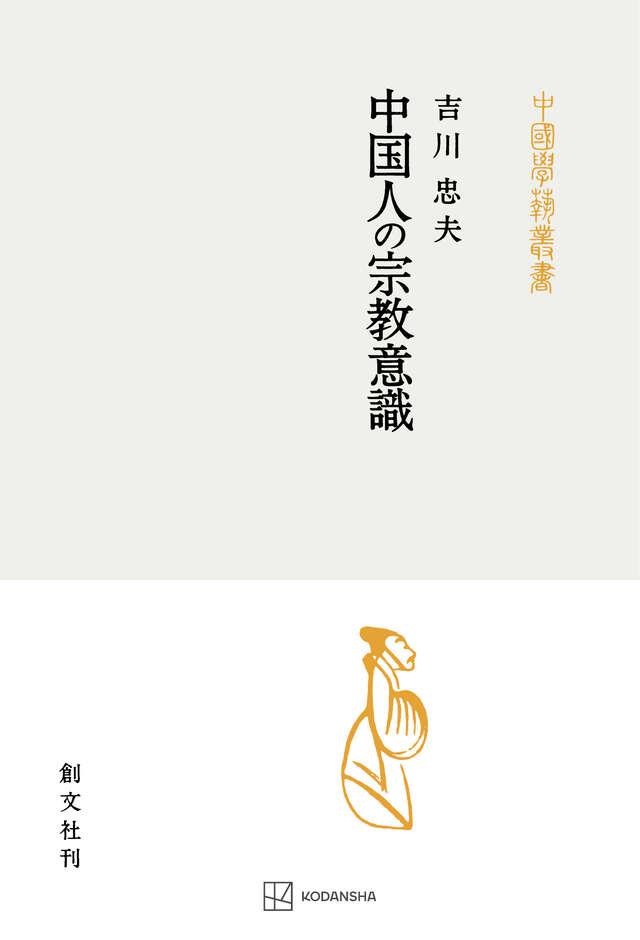
2022.02.25発売
中国人の宗教意識(中国学芸叢書)
創文社オンデマンド叢書
六朝隋唐期の中世600年に及ぶ時代を対象に、人々の日常に息づく「罪の意識」に光をあて、幅広く多様な中国人の宗教意識を見事に描き出す。儒・仏・道の三教に亙る広範な文献を渉猟しつつ、罪意識と贖いの儀礼を通して、中国社会に通底する宗教の深層構造を初めて本格的に明らかにした問題作。
【目次より】
序章 『後漢書』楚王英伝から
I 静室 懺悔の場
一 静室の諸相とその展開
二 静室内のしつらえ
三 静室における儀礼
四 精舎と静室
五 請室と静室 俗から聖ヘ
II 罪の懺悔
一 罪目
二 道教徒の懺悔 とくに王義之の場合
三 仏教徒の懺悔 とくに沈約の場合
四 王微の「告霊文」
III 償債と謫仙
一 輪廻応報の思想
二 禅録のなかの償債
三 『高僧伝』のなかの償債
四 道教における償債
五 謫仙
六 『高僧伝』神異篇
七 全真教の場合
IV 宗教に傾斜する心性
一 漢代人の遺言・遺書と沐並の「終制」
二 遺言・遺書のなかの仏教
三 皇侃の『論語義疏』
四 出家の動機
注
あとがき

2022.02.25発売
悲の現象論序説 日本哲学の六テーゼより
創文社オンデマンド叢書
西田幾太郎に始まる日本哲学を、現代哲学のコンテクストのもとで、局処世界、ノエシス的超越、種のアフォーダンスなど六つのテーゼに集約し、新たな第七の「悲のテーゼ」を導き出す。
【目次より】
緒論 「悲の現象論」の構想
一 問題概念としての「日本哲学」
二 「悲の現象論」の予備概念
1 「局処世界」テーゼ 西田哲学あるいは「場所」と論理
一 第一テーゼとその意味
二 ゲーテの詩より
三 西田のハイデッガー批判
四 ザインのトポロギー
五 局処世界
2 「ノエシス的超越」テーゼ 続・西田哲学あるいは「行為的直観」と現象学
一 第二テーゼとその意味
二 自我の反省可能性 フッサールとの対峙
三 「無の場所」の現象学
四 自覚と世界 ハイデッガーとの対決
五 行為的直観の現象学
3 「種のアフォーダンス」テーゼ 田辺哲学あるいは「種の論理」と行為
一 第三テーゼとその意味
二 田辺哲学の「再考」
三 種の論理の論郭づけ
四 「行為」の意味
五 行為的瞬間としての無
六 種の概念の修正
七 種の論理の隠れた動揺
八 種のアフォーダンス
4 「語黙通底」テーゼ 久松真一の禅思想あるいは「覚の哲学」と言語
一 第四テーゼとその意味
二 覚の宗教
三 覚の哲学(一)
四 覚の哲学(二)
五 語り得ないものの語り
5 「自他の回互」テーゼ 西谷哲学あるいは「空の立場」と他者
一 第五テーゼとその意味
二 「負」の大きさ
三 西田と西谷の「近さ」
四 ノエシス的合一
五 西田と西谷の対決点
六 「回互」の構造
6 「超近代」テーゼ 京都学派の思想あるいは「世界史の哲学」と物語行為
一 第六テーゼとその意味
二 京都学派の「世界史の哲学」
三 絶対の「無」と歴史世界の「有」
四 西田・田辺論争
五 超近代 近代との非連続の連続
7 「悲」のテーゼ
一 第七テーゼとその意味
二 「悲」の場所としての局処世界
三 「悲」の通路としての「ノエシス的超越」
四 「悲」の行為的生成としての「アフォーダンス」
五 「悲」の表現としての言語行為
六 「悲」の他者開示
七 「悲」の歴史開示
付論 「悲」と「哄笑」 『ツァラトストラはかく語った』と禅
一 宗教批判の着手点としての「笑い」
二 『ツァラトストラはかく語った』に出てくるさまざまの「笑い」
三 「笑い」の諸解釈
四 ツァラトストラの憧憬
五 禅の「笑い」とキリスト教の「悲」
結語

2022.02.25発売
ドイツにおける大学教授の誕生 職階制の成立を中心に
創文社オンデマンド叢書
職階制の成立を中心に 16世紀に成立する正教授職=職階制と随伴現象を解明、中世から現代に至る大学の歴史を初めて統一的に示す。
【目次より】
まえがき
序章
第一節 基本的問題意識
第二節 先行研究の検討
第三節 本書の方法、構成と概要、本研究の性格
第一章 中世大学の教師と運営機関
第一節 中世大学における学位と教授内容 ヴィーン大学の事例
第二節 中世大学における教師の種類(有給教師と無給教師)と講義との対応関係
第三節 大学教師にたいする経済的援助の形態
第四節 聴講料
第五節 大学教師への道と任命方法
第六節 中世大学の意思決定・運営機関とその構成
第七節 中世大学における教師の序列
第八節 中世ドイツ大学におけるカンツラーと事務職員
第九節 ドイツ大学の構造的二重性
第二章 一六世紀における教授職をめぐる各大学の動向 個別大学史的考察
第一節 ヴィーン
第二節 ハイデルベルク
第三節 インゴルシュタット
第四節 テュービンゲン
第五節 ヴィッテンベルク
第六節 マールブルク
第七節 ヘルムシュテット
第八節 ヴュルツブルク
第三章 正教授職の成立とその随伴現象
第一節 正教授職の成立
第二節 正教授職成立の随伴現象
第三節 寡頭的組織の成立とその特性
第四節 教授職からみたドイツ大学の特徴
第四章 宗教改革期における大学をめぐる状況
第一節 大学教師の独身制の崩壊
第二節 俸給の性格
第三節 授業の形態と学生生活
第四節 教養学部の名称、講義目録、学位
第五節 大学の予備教育機関
第六節 カンツラーと事務職員
第七節 領邦国家による査察
第八節 ドイツ大学史における一六世紀の位置
第五章 大学教師の職階制の歴史的展開とその影響
第一節 一七世紀の「私的教師」をめぐる状況
第二節 職階制成立の影響
第三節 職階制からみた時代区分
終章 ドイツ大学の歴史的性格 「公」と「私」のアスペクトから
序 本章のねらい
第一節 先行研究による性格規定
第二節 大学内部における公と私
第三節 大学と国家との歴史的関係
結語
あとがき
ドイツ大学の発展地図
ドイツ大学史年表
ドイツ語要約

2022.02.25発売
宋代中国の国家と経済 財政・市場・貨幣
創文社オンデマンド叢書
財政・市場・貨幣 国家の経済活動を重視する立場から、当時の貨幣流通の実態を実証的に分析し、市場と国家の関係を明らかにする。
【目次より】
図表一覧
序論 中国貨幣経済論序説
緒言
一 自然経済・貨幣経済の捉え方に関する諸学説
二 中国経済史における貨幣経済をどう捉えるか
小結
第一部 宋代の国家と市場
第一章 北宋の財政と貨幣経済
緒言
一 複合単位と北宋財政
二 北宋財政と全国的流通
三 新法期の貨幣財政
小結
付表
第二章 北宋の都市市場と国家 市易法
緒言
一 市易条文の内容 市易法の本旨
二 市易三法の成立と変遷
三 市易法の性格変化と廃止
小結
第三章 宋代の商工業者の組織化 行
緒言
一 免行法施行の前提 宋初の行役
二 免行法と行
三 南宋の行 免行銭廃止後の行
四 同業組織としての行
小結
第四章 宋元時代の牙人と国家の市場政策
緒言
一 牙人の機能
二 宋朝と牙人
三 元代の牙人
四 元朝の市場政策
小結
第二部 宋代貨幣論
第一章 唐宋時代の短陌と貨幣経済の特質
緒言
一 国家財政に関わる短陌 省陌
二 銅銭と紙幣の交換レートとしての短陌
三 商品流通と短陌
四 短陌対策の変遷
小結
第二章 唐宋時代における銅銭の私鋳
緒言
一 鋳造貨幣の生産費
二 唐五代の私鋳銭
三 宋代の私鋳銭
小結
第三章 宋代陜西・河東の鉄銭問題
緒言
一 陜西の鉄銭
二 河東の鉄銭
小結
第四章 宋代四川の鉄銭問題
緒言
一 宋初の通貨問題
二 新法期以後の鉄銭事情
三 鉄銭の私鋳問題
小結
第五章 宋代の価格と市場
緒言
一 市価の変動と地域差
二 宋代価格の特性
小結
終章 貨幣経済の時期区分
緒言
一 非統一的貨幣経済の時代
二 統一的貨幣経済の時代
結語
あとがき

2022.02.25発売
家郷を離れず 西谷啓治先生特別講義
創文社オンデマンド叢書
京都学派を代表する西谷啓治が、自らの思索を説きあかした最晩年の特別講義と、西谷哲学を解説する著者論文とを収録。
【目次より】
凡例
目次
第一部 「空と即」 西谷啓治先生特別講義
第一景 「空と即」の背景
第二景 住処としての世界
第三景 事々無礙と信の世界
第四景 空と即 海と小波
第五景 科学と禅
第六景 イマジネーション
付録 ハイデッカーと西谷
第二部 家郷を離れず
第一章 考えるということ
第二章 問わるべきこと
第三章 家郷を離れず
第四章 感覚の根源性
第五章 開けへの道
第六章 言葉と有の内景
参考文献
あとがき

2022.02.25発売
睡虎地秦簡よりみた秦代の国家と社会(東洋学叢書)
創文社オンデマンド叢書
第一級の史料を用いて、秦帝国の支配構造と統一過程にみられる法治主義の特質を明らかにする。
凡例
序章 睡虎地秦簡と中国古代社会史研究
第一章 内史の再編と内史・治粟内史の成立
第一節 睡虎地秦簡にみえる内史の問題点 第二節 睡虎地秦簡にみえる内史の構成 第三節 内史の変遷と再編
第二章 秦の都官と封建制
第一節 先学の解釈とその問題点 第二節 秦簡にみえる都官の構造 第三節 都官設置の歴史的背
第三章 秦の領土拡大と国際秩序の形成
第一節 秦の属邦と道制 第二節 前漢における属国と道 第三節 後漢における属国と道 第四節 秦簡における属邦と臣邦真戎君長 むすび
第四章 睡虎地秦簡「日書」の基礎的検討
第一節 「日書」の形態とその内容 第二節 「日書」の占法原理と問題点 第三節 日者と「日書」の関係 第四節 その他の「日書」について
第五章 「日書」を通してみた国家と社会
第一節 語彙分析よりみた甲種と乙種の用字傾向 第二節 「日書」の占辞における地域性をめぐる問題点 第三節 「日書」の語彙分析よりみた国家の諸相 第四節 「日書」の語彙分析よりみた官制の諸相
第六章 先秦社会の行神信仰と萬
第一節 漢代の行神と祖道 第二節 「日書」における行神と祖道 第三節 出行における吉凶の時日とその構造 第四節 帰家の吉凶と通過儀礼
第七章 「日書」における道教的習俗
第一節 中国古代の行旅第二節 放馬灘秦簡「日書」にみえる「律書」と納音 第三節 禁呪の形式 第四節 禹歩と四縦五横
第八章 萬の変容と五祀
第一節 嫁娶日の吉凶にかかわる禹 第二節 治癒神としての禹 第三節 アジールの神としての禹 第四節 行神祭祀と五祀
第九章 「日書」に反映された秦・楚のまなざし
第一節 「玄戈」における秦・楚の占法原理の差異 第二節 「稷辰」・「秦」における楚のまなざし 第三節 建除における楚のまなざし 第四節 「歳」における秦のまなざし
第十章 戦国秦の嗇夫制と県制
第一節 県邑を主管する嗇夫 第二節 県令と県嗇夫・大嗇夫 第三節 「語書」と県・道嗇夫
終章 睡虎地秦簡よりみた戦国秦の法と習俗
第一節 秦律にたいする楚暦の影響 第二節 「封診式」毒言における悪口のタブー 第三節 「封診式」にあらわれた国家と家族・共同体 第四節 「語書」と六国の統一 第五節 戦国秦における法治主義の転換
あとがき
欧文目次

2022.02.25発売
ヘーゲルのギリシア哲学論
創文社オンデマンド叢書
「哲学史講義」の未公刊資料の解読により、ヘーゲルの古代哲学理解を理性の問題を中心に解明し、人文主義的ヘーゲル像を初めて明らかにする。
【目次より】
序論
第I篇 ヘーゲル研究史から見た古代ギリシア哲学問題
第一章 日本のヘーゲル研究史と古代ギリシア哲学問題
第二章 ドイツのヘーゲル研究と古代ギリシア哲学問題
第三章 『哲学史講義』筆記録研究の現状
第II篇 思弁哲学の源泉
第一章 『精神現象学』から『哲学史講義』へ
第二章 ヘーゲルと観想の幸福
第三章 理性をめぐって
第四章 理性の根源
第五章 ヘーゲル元素論と推論の中項 『ティマイオス』篇三二a-b解釈への註釈
第六章 ソクラテスの彫塑的問答法
第III篇 ヘーゲルの新プラトン主義理解
第一章 若きヘーゲルにおける概念と全一論
第二章 ヘーゲルと新プラトン主義の伝統
第三章 ヘーゲルから見た新プラトン主義
第四章 純粋概念の新プラトン主義的根源 『精神現象学』序言の一節への註釈
あとがき
欧文要旨
主要参考文献一覧
資料一 ヘーゲル『霊魂論』翻訳断片
資料二 ヘーゲル「アリストテレス講義」
資料三 ベルリン期ヘーゲル未公刊講義筆記録一覧
資料四 ヘーゲル 古代ギリシア関係研究文献目録
資料五 『精神現象学』日本語文献目録

2022.02.25発売
ノヴァーリスと自然神秘思想 自然学から詩学へ
創文社オンデマンド叢書
ノヴァーリスの主として理論的著作を取り上げ、ノヴァーリスの自然思想を十八世紀末の思想状況において明らかにする。第一に、ノヴァーリスの自然思想を、ルネサンス以来のヨーロッパの「自然神秘思想」の伝統の受容と変奏として検討、第二に、ノヴァーリスの思想における「自然」の問題を体系的にとらえ、とくに、哲学や自然科学をふまえた「自然学」が、なぜ、いかにして「詩学」となるのかを考察する。
【目次より】
はじめに
引用について
第一部 超越と自然
第一章 「ノヴァーリス」の誕生
1 「熱狂の擁護」
2 体験と哲学
第二章 ガイストの顕現としてのこの世界
1 「制約なきもの」と「物」
2 エクスターゼと知的直観
3 「ガイスト」の運動
4 神性への媒介者 宗教
5 表象 哲学
6 森羅万象の相互表象説と新プラトン主義的な世界像 自然学
第三章 世界の意味の喪失と回復
1 世界の意味の喪失
2 黄金時代
3 回復の方法 ロマン化
4 伝統との関わり
第二部 自然学
第四章 マクロコスモスとミクロコスモス 自然と人間
1 マクロコスモスとミクロコスモス
2 自然と人間
3 自然の救い
4 自然とわざの愛の関係
5 魔術師としての人間
第五章 魔術
1 魔術史への興味
2 魔術と観念論哲学の重ね合わせ
3 「未来のシェーマ」としての魔術
第六章 万物の共感の学
1 伝統のなかの共感の学
2 ガルヴァニズム、電気、磁気
3 ブラウン医学
4 動物磁気
5 「ラヴォワジェの革命をこえるもの」
第七章 しるしの学 しるし・記号・象徴
1 自然神秘思想の伝統における「シグナトゥール」
2 近世の記号の学
3 自然の文献学としての自然学
4 しるしとその意味 「外なるもの」と「内なるもの」
第三部 詩学
第八章 心情の表現としてのポエジー
1 自然と人間の内的空間としての心情
2 心情のあり方
3 心情とポエジー
第九章 高次の自然学としてのポエジー
1 自然哲学との関連と相違
2 ゲーテの自然学とノヴァーリス
3 自然と精神のアナロジー
4 光の問題
第十章 文学の理論としての詩学
1 ロマン的ポエジー
2 芸術とポエジー
3 自然とポエジー
第十一章 シンボルとアレゴリー
1 シンボル
2 アレゴリー
おわりに
あとがき
註
引用テクストおよび参考文献

2022.02.25発売
トマス・アクィナスの知性論
創文社オンデマンド叢書
トマスの知性論の特徴である、能動知性の内在の提唱、人間知性としての可能知性の非質量性の提唱に注意を向け、トマス哲学における人間知性の問題を考察する。アヴェロエス主義やアリストテレス的認識を批判し、中世独自の認識論を展開したトマスの知性論を分析する。
【目次より】
序
第一章 真理認識に対する欲求と節度 "naturaliter scire desiderant"の解釈
第二章 『エチカ注解』におけるアヴェロエス説批判
第三章 『デ・アニマ注解』における可能知性の問題
第四章 可能知性単一説に対する論駁
第五章 『存在しているものと本質』序文における《エッセ》の認識
第六章 本質の二義性と知性の《エッセ》
第七章 認識者としての魂の《エッセ》
第八章 魂の不死に関するトマス説とカエタヌス説
第九章 生命を与える魂 存在を与える形相 "Vivere viventibus est esse"の解釈
第十章 第四の道と『存在しているものと本質』
第十一章 第一に認識されるもの
第十二章 トマスのイデア論 神の観念としてのイデア
第十三章 トマス哲学における能動知性の問題
第十四章 トマスの知性論における存在認識
あとがき
註
文献表

2022.02.25発売
熊本藩の法と政治 近代的統治への胎動
創文社オンデマンド叢書
熊本藩の統治機構と官僚制の発達の経過、刑法史、商工業活動に対する規制と庶民の生活上の諸規制、横井小楠を中心とする肥後実学党の実像を明らかにする論文集。
【目次より】
はじめに
序章 熊本藩概況
一 領地と領民 二 家臣団 三 財政状況
第一部 統治機構と官僚制の整備
第一章 藩庁中央機構
一 時代区分および軍事機構と政治機構の関係 二 第一期 寛永九年から延宝八年まで四九年間 三 第二期 天和元年から宝暦元年まで七一年間 四 第三期 宝暦二年から寛政八年まで四五年間 五 第四期 寛政九年から明治元年まで七二年間 六 小括
第二章 町方、特に熊本城下町の統治機構
一 熊本藩における諸町の行政的位置づけ 二 熊本城下町の形成と発展 三 熊本城下町の統治機構 四 小括
第三章 郡村統治機構
一 郡村統治機構の変遷の概要 二 宝暦改革後の郡村支配機構の概要
第四章 統治機構の合理化と官僚制の整備
一 宝暦改革前の機構整備 二 宝暦改革およびその後の機構整備と官僚制の整備
第二部 近代的刑法の誕生と行刑史
第一章 熊本藩刑政の変遷
一 初期の刑政 二 中期の刑政 三 宝暦の改革と刑政 四 後期の刑政 五 小括
第二章 刑罰と行政罰の分離
一 仕置から刑罰の分離独立 二 郡方処罰権と行政罰体系 三 町方処罰の実態 四 小括
第三章 拷問について
第三部 藩民統制
第一章 商工業活動に対する規制
一 商札・職札制 二 問屋制 三 運上 四 藩内流通規制 五 藩外流通規制と国産仕立 六 物価・手間賃・給銀の規制 七 個別業種についての規制例
第二章 都市生活上の規制
一 取り締まり機構 二 種々の生活諸規制
第三章 農村生活上の規制
第四部 幕末政治史の一斑 肥後実学党をめぐって
第一章 天保期熊本藩政と実学党の誕生
一 伊藤石之助・大塚仙之助の乱 二 天保期藩政の実態 三 実学党誕生前夜 四 実学党の誕生 五 むすびにかえて
第二章 横井小楠と長岡監物
第三章 横井小楠覚書
おわりに
付 町方法令集
解題
凡例
「市井式稿」
「市井雑式草書 乾」
「市井雑式草書 〓」