講談社文芸文庫作品一覧
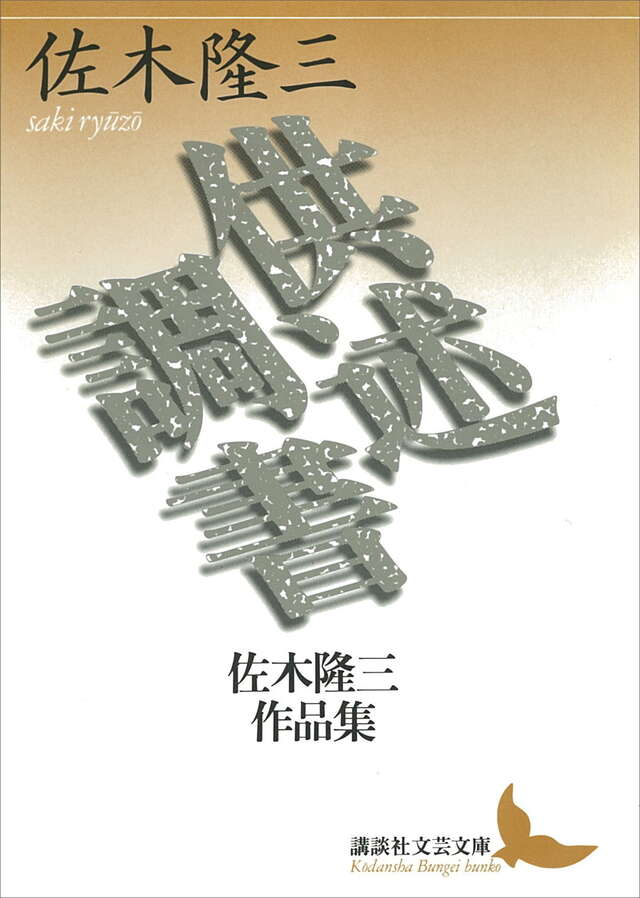
供述調書 佐木隆三作品集
講談社文芸文庫
ジャンケンで決めるという奇抜な発想で、企業の首切りを痛烈に諷刺した「ジャンケンポン協定」(新日本文学賞)、ダム建設に反対し1人で国家権力と闘った男がモデルの実録的小説「大将とわたし」、著者の沖縄生活が生んだ基地の街の男女の生態を描く「シャワー・ルーム」等、作家の軌跡の節々の作品に、犯罪を主題に現代の若者の精神の崩れを衝く「供述調書」を加えた代表作5篇。
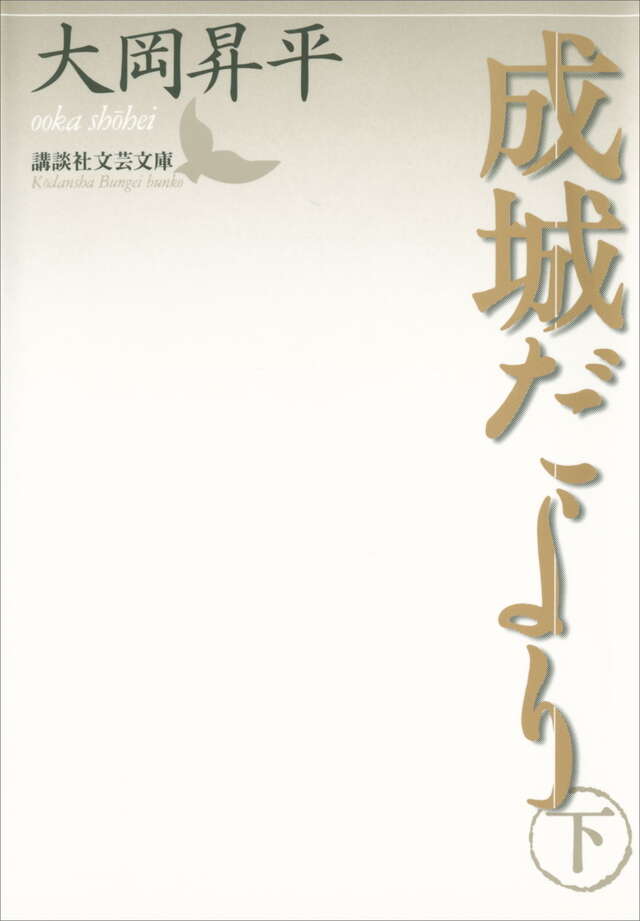
成城だより 下
講談社文芸文庫
毎月の文芸誌に目を通し、文壇のみならず時代と社会現象一般に眼を向け、自分を老生と呼びつつ、好奇心を躍動させ、文学、映画、音楽等を批評する。ランボーがスタンダールとともに自己の中に在ると感じ、また「事件」のゲラを読む。心臓、体力の限界を心配しつつ堺事件調査の旅行にも出る。「文学界」1986年2月号まで書き継ぎ大岡昇平を雄弁に語る、知的刺激と人間味溢れる好エッセイ。上下2巻。

女獣心理
講談社文芸文庫
美術学校を出、銀座の店頭装飾を仕事にした女性征矢(ソヤ)は、やがて伯爵のパトロンのサロンで、男達の憧憬の的となり、突然に失踪。巷では堕落した街の女になったとの噂が出る。澄みとおる程美しい目をし、ギリシャ神話の白鳥の姿のゼウスと交わった女神に擬えて「レダ」を呼ばれた神秘の女が奔放に生き永遠の美と自己愛に殉じ狂おしく果てる姿を、「私」の眼を通し描く。日本文学に希れな、鮮烈な女性像。
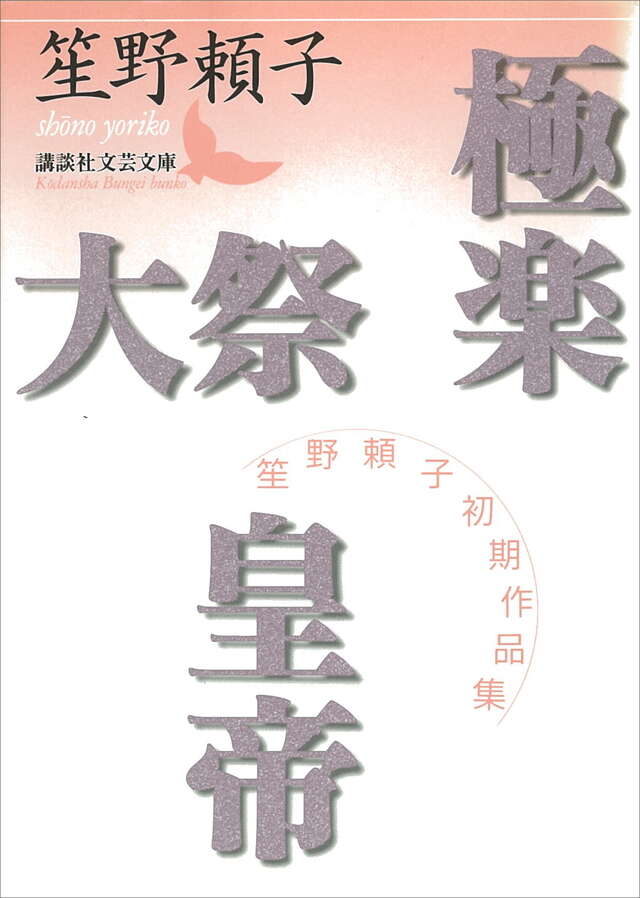
極楽・大祭・皇帝 笙野頼子初期作品集
講談社文芸文庫
群像新人賞「極楽」を含む最初期の作品三篇。地獄絵を描くことを人生の究極の目的とした男の心象を追求した「極楽」、現実からの脱出を願う七歳の子供の話「大祭」、初期の代表作「皇帝」。著者の原点三篇を収録。
輪切りの地獄、鼠硝子、自閉帝国……究極の地獄絵を求める密室画家、「地獄変」の書き変えを志した「極楽」。祝祭の日、父親殺しの妄想へと走る小学生「大祭」。自閉帝国を求める白衣の殺人者、長篇「皇帝」。25歳で群像新人賞を受賞した芥川賞、三島賞、野間文芸新人賞作家が、暗黒の80年代を注ぎ込んだ引きこもり・憎悪小説集。
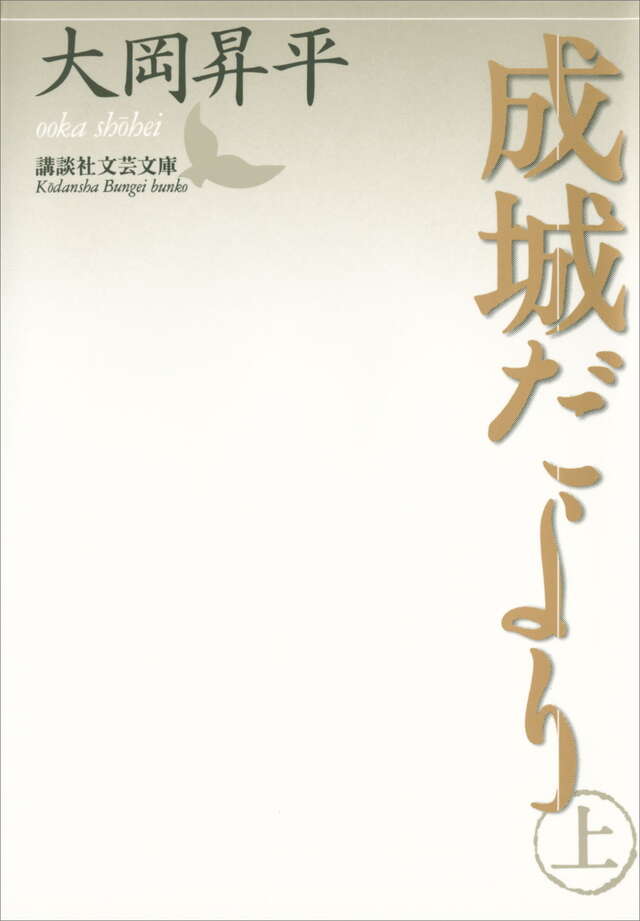
成城だより 上
講談社文芸文庫
成城に越して来て11年、運動は駅まで15分の片道だけ。体力の衰えに抗しつつ、富永太郎全集に集中、中原中也「山羊の歌」の名の由来を追い、ニューミュージック、映画、テレビ、劇画、広汎な読書、文学賞選考会等、80年代前半の文化、文壇、世相を俎上に載せ、憤り、感動する。70歳にして若々しい好奇心と批評精神で「署名入り匿名批評」と話題を呼んだ日記体エッセイ。上下2巻。

ドイツ悲哀劇の根源
講談社文芸文庫
メランコリーの現象学とアレゴリーの力学。[新訳]
ベンヤミンは本書の文章の組み立て方をモザイク画にたとえた。描き出された事象は20世紀という夜を背景に浮かびあがった星座さながらである。星は暗くなければ目に見えない。本書の対象であるドイツのバロック時代もまた夜であった。ベンヤミンは暗がりの中に埋もれた未完結な現象を、さらに深い闇から観察することによって、20世紀の根源的な意味を明るみに出す。
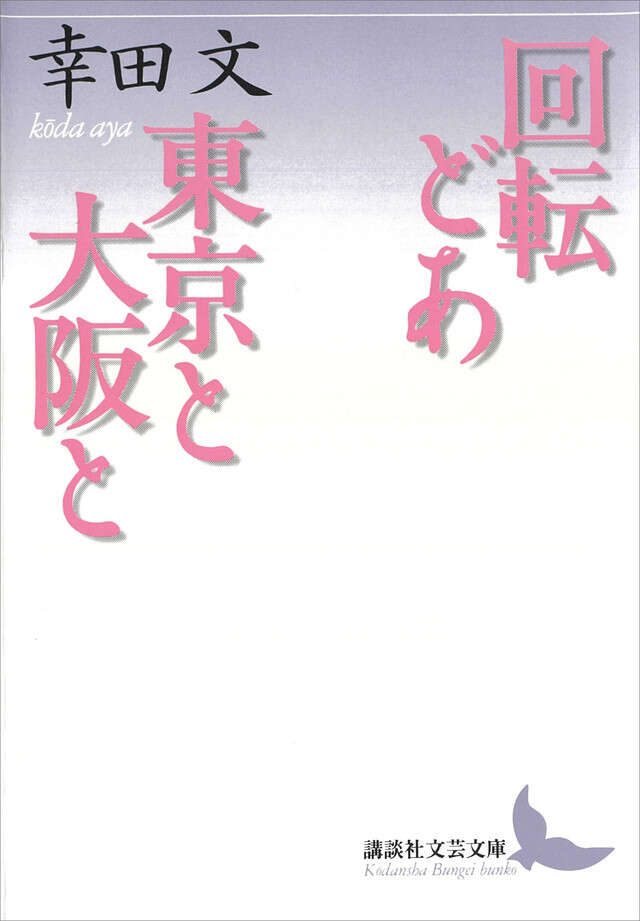
回転どあ・東京と大阪と
講談社文芸文庫
「いったい涼しげというのは、すっきりと線が立っている趣をいい、すっきりとは或る鋭さを含んでいるとおもう。……。げというのは力量である。」(『回転どあ』「あじさい」)ーー父・幸田露伴の思い出を綴った文章で世に出た著者は、東京下町・向島に生まれ育った。気性の激しさ、繊細鋭利な感性、強靱な文体で身辺を語り、日々の発見を精妙に記す。庶民生活を清新に描いた、単行本未収録エッセイ101篇。

現代詩人論
講談社文芸文庫
大正末期から戦後まで、混迷の時代の中で輝かしい光を放った詩人たち――西脇順三郎、金子光晴、中野重治、中原中也はじめ、「四季」の三好達治、立原道造、戦後「荒地派」の鮎川信夫、田村隆一さらに清岡卓行、谷川俊太郎に及ぶ、23人の魅力の源泉に迫る。「詩」と「批評」という二筋道を、一筋により合わせ得る道を自らの内に探求してきた著者の、刺激に満ちた詩人論。現代詩を語る上で、必読の詩人論が誕生した!
達治、重治、中也、俊太郎など23人の詩人の本質!
大正末期から戦後まで、混迷の時代の中で輝かしい光を放った詩人たち――西脇順三郎、金子光晴はじめ、“四季派”の三好達治、立原道造、戦後“荒地派”の鮎川信夫、田村隆一さらに清岡卓行、谷川俊太郎に及ぶ23人の魅力の源泉に迫る。「詩」と「批評」という二筋道を一筋により合わせ得る道を自らの内に探求してきた著者の刺激に満ちた詩人論。

うるわしき日々
講談社文芸文庫
『抱擁家族』の30年後の姿 老いと家族をテーマの長篇ーー80を過ぎた老作家は、作者自身を思わせて、50過ぎの重度アルコール中毒の息子の世話に奮闘する。再婚の妻は、血のつながらぬ息子の看病に疲れて、健忘症になってしまう。作者は、転院のため新しい病院を探し歩く己れの日常を、時にユーモラスなまでの開かれた心で、読者に逐一説明をする。複雑な現代の家族と老いのテーマを、私小説を越えた自在の面白さで描く、『抱擁家族』の世界の30年後の姿。

南回帰線
講談社文芸文庫
クリスマスの翌日の12月26日に生まれてしまった《遅れてきたキリスト》のぼくは29歳、ニューヨークで電信会社の雇用主任の職につく。ぼくは《卵巣の市電》という固定観念にとりつかれ、人間実存の根源を探るべく混沌とした性の世界を彷徨する。“20世紀最大の危険な巨人”と呼ばれたミラーが1939年パリで刊行した自伝的作品。
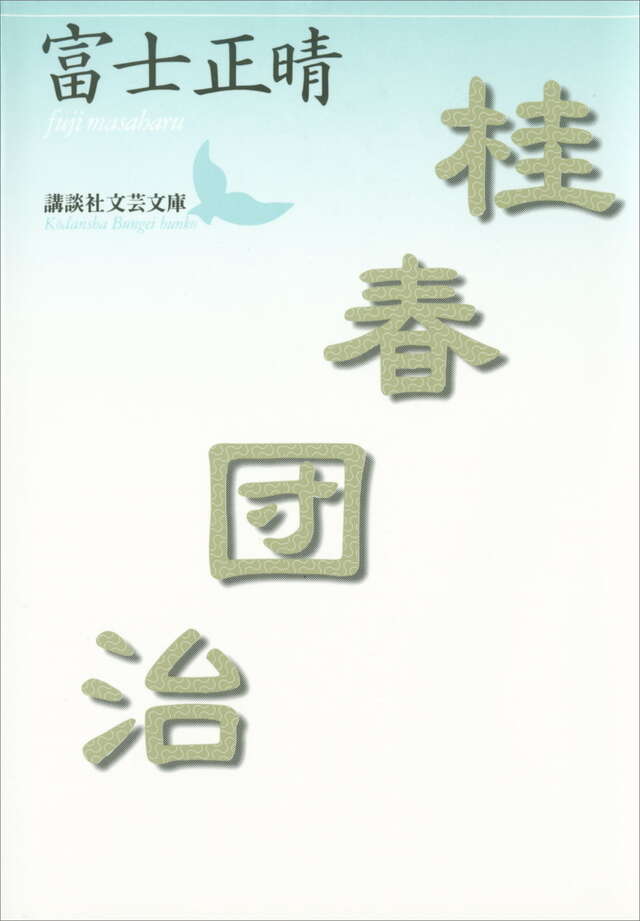
桂 春団治
講談社文芸文庫
独創的話術と奇行で知られ一世を風靡した奇才桂春団治。〈微妙猥雑〉な上方弁を駆使し落語界を席巻、上方落語の全盛期を築いた春団治の一代記を、出生から57歳の死まで、詳細綿密な調査と多彩な資料で裏付け書下ろした傑作評伝。「桂春団治年譜」「上方落語年表」などを付すほか「紅梅亭界隈」「東松トミの半生――桂春団治外伝の一つ」を併録。毎日出版文化賞受賞。
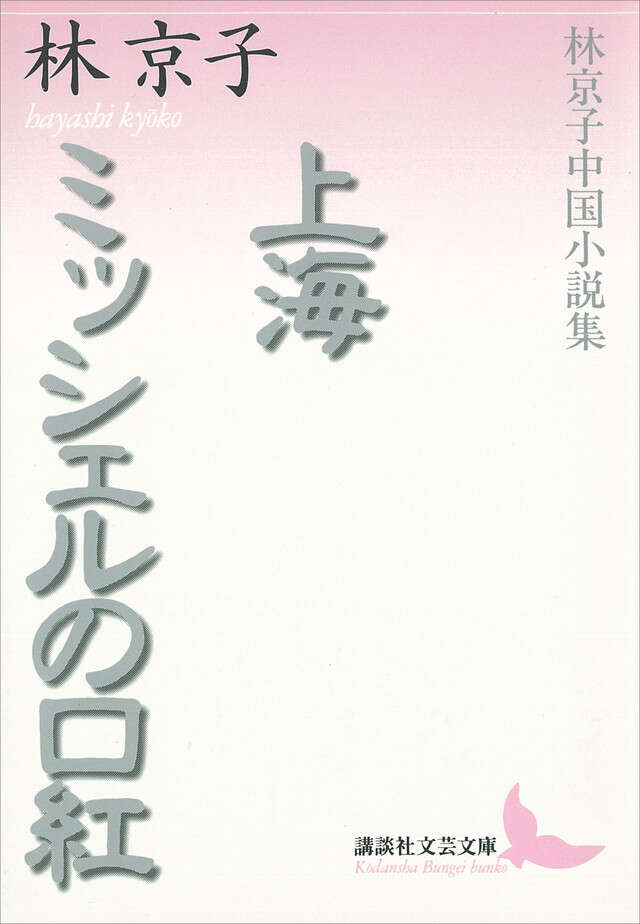
上海・ミッシェルの口紅 林京子中国小説集
講談社文芸文庫
戦争の影迫る上海の街で、四人姉妹の3番目の「私」は、中国の風俗と生活の中で、思春期の扉をあけ成長してゆく。鮮烈な記憶をたどる7篇の連作小説「ミッシェルの口紅」と、戦後36年ぶりに中国を再訪した旅行の記「上海」。長崎で被爆して「原爆」の語り部となる決意をした著者が、幼時を過ごしたもう一つの文学の原点=中国。

アメン父
講談社文芸文庫
“父は肩肘はらないで大マジメだった”明治末にアメリカで久布白直勝牧師により受洗、昭和3年広島・呉市に十字架のない独立教会を創設、70余で没した父。呉の三津田の山に父が建てた上段・中段と呼ぶ集会所(教会)、住居での懐かしい思い出や父の日記・著作等から“アメン”に貫かれている父の生涯の軌跡を真摯に辿る。息子から父への鎮魂歌。長篇小説。

死の床に横たわりて
講談社文芸文庫
「生きてるのは、つまりは、長いあいだじっと死んでいれるようにと準備する為じゃ」という父の言葉にとりつかれたアディは、夫に、自分の遺体を父の眠るジェファソンまで運んで埋めるように遺言を残して死ぬ。家族6人は洪水で橋が流失した川を棺桶と共に渡る。15人の59回にわたる内的独白から成るこの小説は、南部の貧農一家を立体的に描き出す。
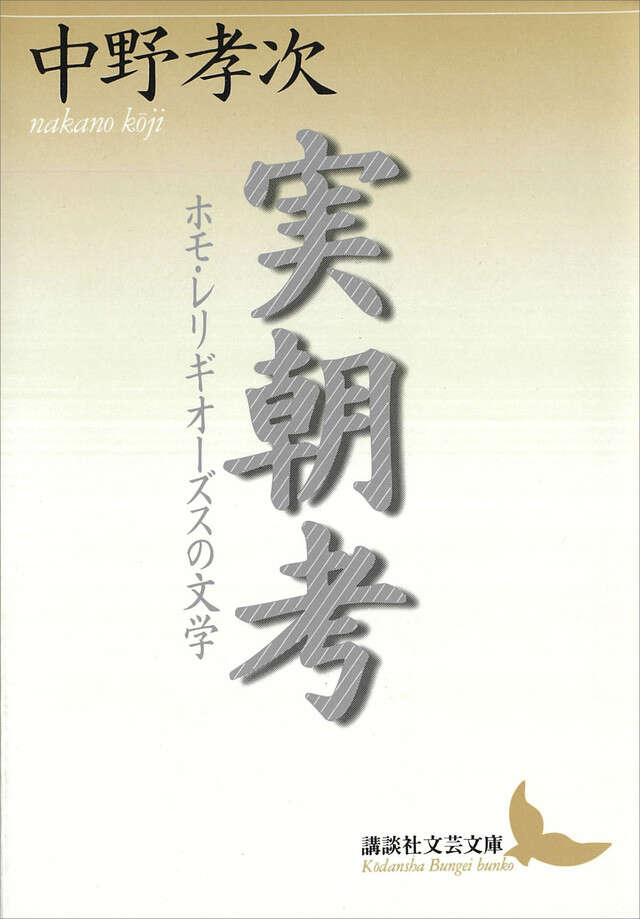
実朝考 ホモ・レリギオーズスの文学
講談社文芸文庫
宮廷文化に傾倒し、武芸軟弱を以て侮られた、鎌倉三代将軍・源実朝は、庶民に共感する単純強靱な歌を詠んだ。それなぜ生まれたのか。その実体に迫る過程で、著者が見たものは〈絶対的孤独者〉の魂だった。死と直面し、怨念を抱えて戦争の日々を生きぬいた著者が、自己を重ね、人間の在り方と時代背景を鋭く考察。時を越えて共有する問題点を、現代の視点で深く追究した、画期的第一評論。

但馬太郎治伝
講談社文芸文庫
“私”は1930年、2度目のパリで、日本学生会館、通称メーゾン・タジマに宿泊し、設立者・但馬太郎治の名を知る。戦後、再三の奇縁から、当時、若く快男子で、日本人としてケタ違いの栄華を生きた彼の過去と現在に興味を感じる。レジオン・ドヌール勲章を胸に、パリ社交界で巨額の富を蕩尽した国際的大パトロン薩摩治郎八をモデルに真の教養人の比類なき生涯をエスプリ豊かに描く長篇小説。

海冥 太平洋戦争にかかわる十六の短編
講談社文芸文庫
戦犯として刑死した父の冤罪を晴らすため、現地P――島のジャングルの奥へ入ってゆく、その息子の新聞記者吉田。「玉砕」につぐ「玉砕」、ひとつの島全体が餓える――“餓島”。南海の果て、また戦後の横浜港の氷川丸を発端に、それぞれ独立した空間と時間を生きる海の戦争に関わる登場人物達の生と死の挿話が重なり、大きなうねりとなって、苛酷な戦争の真実を伝えてゆく。歴史に埋もれた死者を悼む16の短篇。
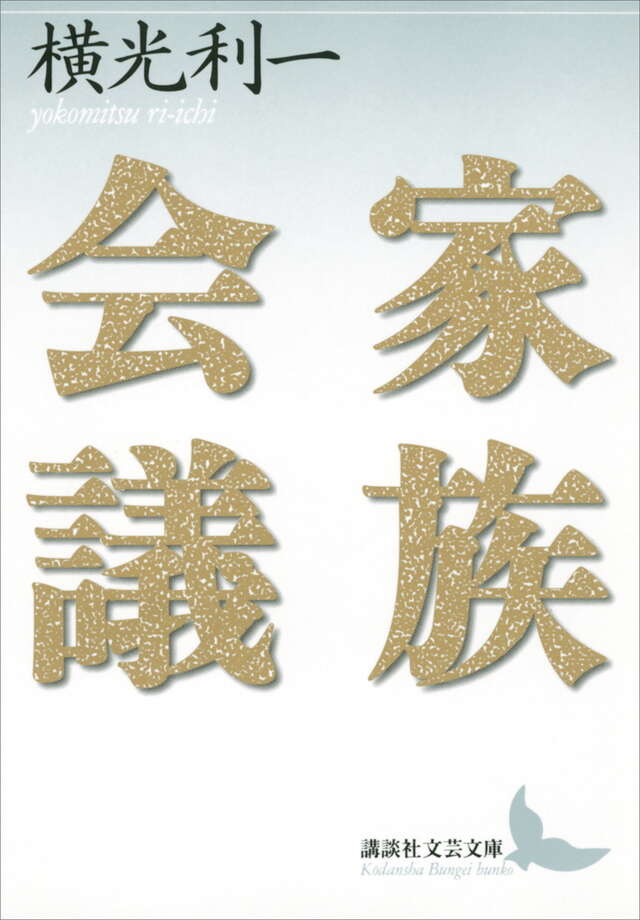
家族会議
講談社文芸文庫
東京の兜町で株式売買をする重住高之は、大阪の北浜の株のやり手仁礼文七の娘泰子に心惹かれている。だが、――文七はあくまで高之に熾烈な仕手戦をしかけて止まない。金の絡みと高揚する恋愛の最中、悲劇は連続して起こる。資本が人を動かし個人が脅かされる現代に人間の危機を見、「純粋小説論」を提唱実践した横光利一が、その人間崩壊を東と西の両家の息づまる対立を軸に描いた家庭小説の傑作。

たいくつな話・浮気な女
講談社文芸文庫
1860年南ロシアに生まれたチェーホフは短篇小説作家として頂点を極め、晩年には「桜の園」「かもめ」など劇作に力を注いで演劇の新時代を画した。本書には、功成り名とげた老教授の寒々とした日常を綴った名作「たいくつな話」、夫がありながら奔放な恋にふける人妻を描いた「浮気な女」の他、「アリアドナ」「殻にはいった男」「たわむれ」「コーラス・ガール」を収録。
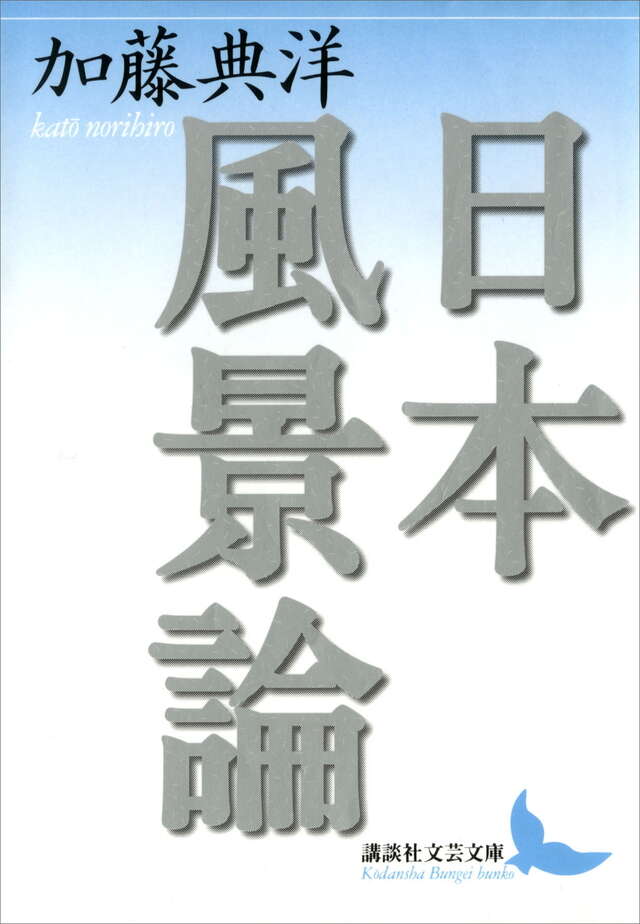
日本風景論
講談社文芸文庫
常に斬新な批評を展開する著者が“風景”と呼ぶ微妙な位相。村上春樹の小説を中心に「まさか」と「やれやれ」論、坂口安吾、田中角栄、北一輝に共通性を見る「新潟の三角形」、“ディスカバー・ジャパン”と国木田独歩、志賀重昂を対比する「武蔵野の消滅」ほか、三島由紀夫、深沢七郎、吉本ばなな、大島弓子等、時代をとりまく日本的文化現象に焦点をあてた独創の8篇。著者の批評の資質と方向を示す初期評論集。