講談社文芸文庫作品一覧
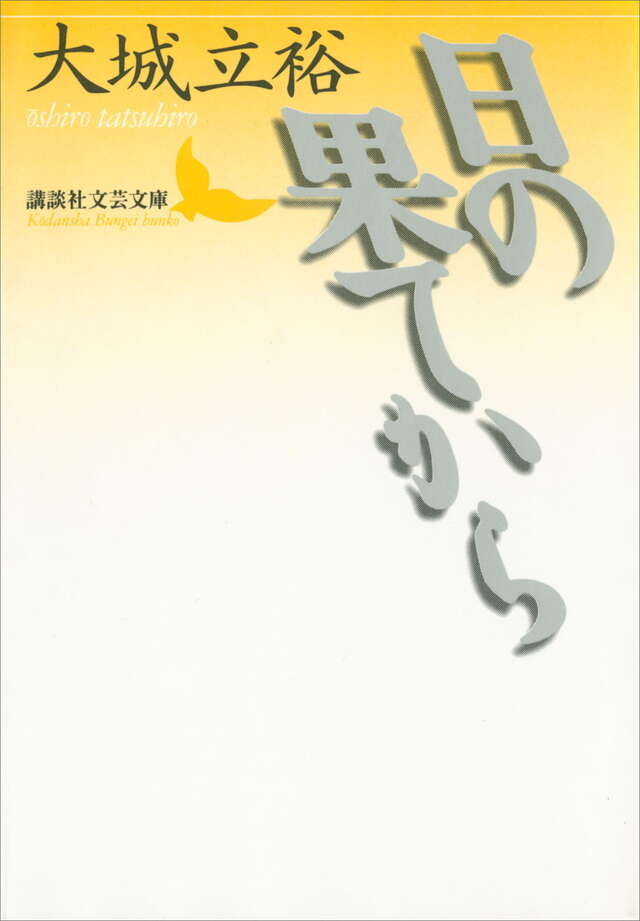
日の果てから
講談社文芸文庫
1945年4月、アメリカ軍沖縄本島に上陸。凄絶な地上戦の〈地獄絵〉の中、逃げ惑う住民。刑務所も遊廓も、そこに縛られる人々も何もかも、沖縄は死の渦のなかで回転しやがて敗戦とともに浄化される。神女殿内(のろどんち)の家柄である神屋家を絡め、文化、歴史、風土を背景に太平洋戦争末期の沖縄戦を神話的世界にまで昇華させた傑作長篇。平林たい子賞受賞。
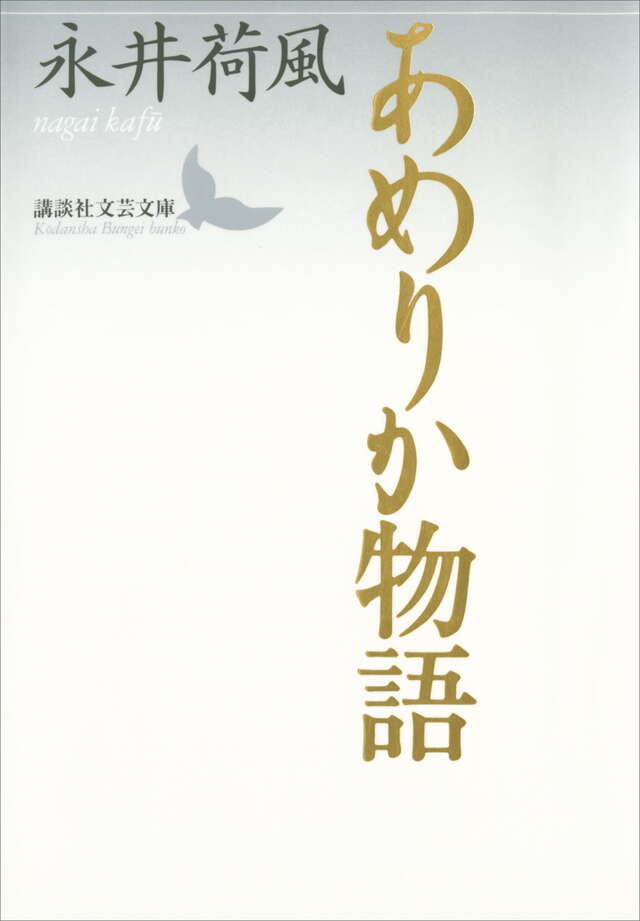
あめりか物語
講談社文芸文庫
明治36年荷風24歳から明治40年28歳まで4年間のアメリカ見聞記を24篇の小説に収める。渡航中の情景を描いた「船房夜話」、癲狂院に収容された日本人出稼ぎ労働者の無惨な話「牧場の道」など。異国の風物に対峙した荷風の孤独感、鋭い感性と批評精神溢れる新鮮な感慨は、閉塞した時代に憧憬と衝撃を与えた。『ふらんす物語』と併称される初期代表作。

神戸・続神戸・俳愚伝
講談社文芸文庫
“東京の何もかも”から脱出した“私”は、神戸のトーアロードにある朱色のハキダメホテルの住人となった。第二次世界大戦下の激動の時代に、神戸に実在した雑多な人種が集まる“国際ホテル”と、山手の異人館〈三鬼館〉での何とも不思議なペーソス溢れる人間模様を描く「神戸」「続神戸」。自ら身を投じた昭和俳句の動静を綴る「俳愚伝」。コスモポリタン三鬼のダンディズムと詩情漂う自伝的作品3篇。

白鯨 モービィ・ディック 上
講談社文芸文庫
灯油の原料を求めて大海に出た捕鯨船の船長エイハブの壮絶な白鯨との死闘。それを物語る唯一の生き残りの乗員イシュメールの魅力的な語り口。苛酷な宿命の下での自然と神、卑俗と聖性、博愛と弱肉強食等の混沌とした人間的葛藤の奥に、男だけの世界の濃密な関係が息づく。近代の文明の行き詰った危機に改めて注目される古典を朗唱にふさわしい平明な新訳とした文庫版。全2冊。
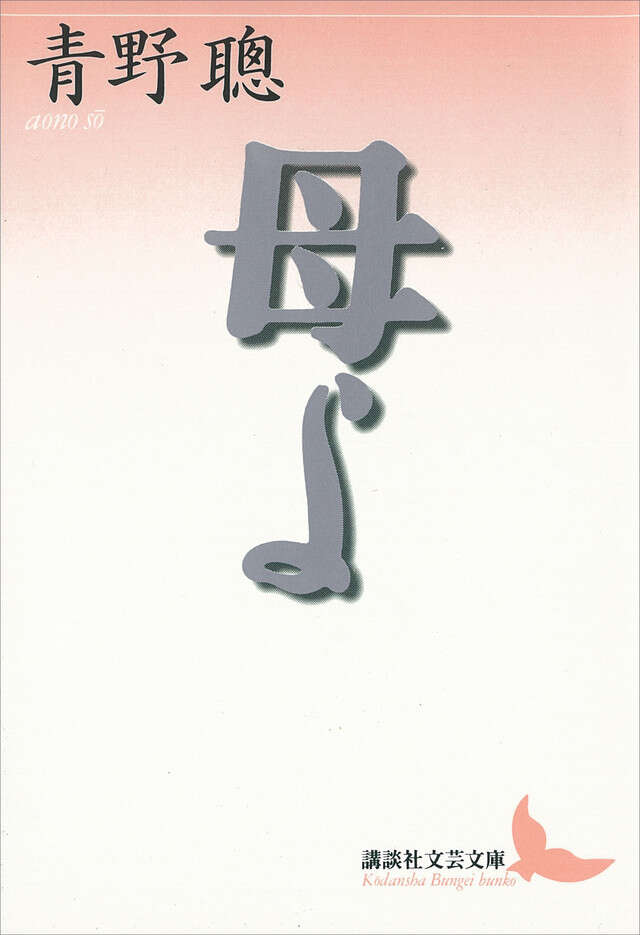
母よ
講談社文芸文庫
母よ、あなたの素顔を見たい、どのような顔をしていたのでしょう。現存している写真はたったの1枚、「ひんやりとした感じの、きれいな人だったのよ」と、少年のぼくに語ってくれた姉。──実母への切実な想いと、別居している理英との間に生まれた保育園にかよう男の子の成長ぶりを、清澄なことばで綴った秀作。第43回読売文学賞受賞作。

王道
講談社文芸文庫
かつてインドシナの地にアンコールワットやアンコールトムを造営し繁栄を誇ったクメールの王国──〈王道〉とはそこに存在した道路である。巨万の富を求めて密林の奥深く古寺院を探して分け入るクロードとペルケン。悪疫、瘴気、そして原住民の襲撃。マルロー自身の若き日のインドシナ体験を基に、人間存在と行為の矛盾を追求した不朽の冒険小説。

私の古寺巡礼
講談社文芸文庫
「自分の道は発見できたといえるかも知れません」昭和39年の「西国巡礼」の旅を第一歩に、「かくれ里」「十一面観音巡礼」等の清新な名著を著わした著者が、創作力旺盛な昭和50年前後に、若い人たちに向けて書いた「お水取りの不思議」「熊野の王子を歩く」「近江の庭園」等の13篇を収録。失われゆく日本の風土・文化を愛惜し日本人の自然観や信仰を共に考え歩む“私の”巡礼紀行。
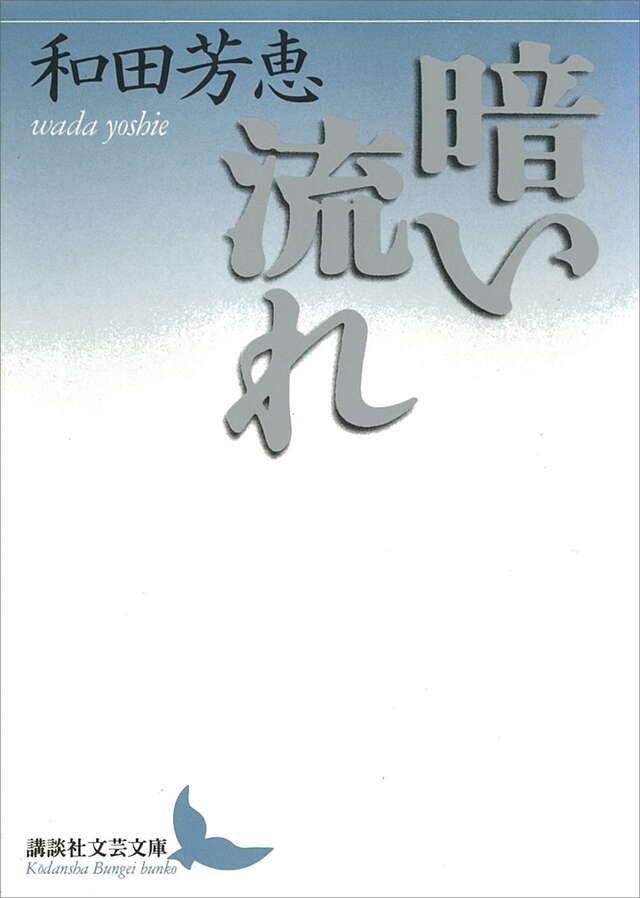
暗い流れ
講談社文芸文庫
ハレー彗星が地球に大接近し、湯河原で幸徳秋水が逮捕された明治43(1910)年、著者5歳から書き起こし、関東大震災の翌年、田舎の代用教員を辞し東京に出て地元の有力者の書生となった大正13年20歳を目前にする頃までを、北海道の原野を背景に描く自伝小説。抗し難い性の欲望に衝き動かされた青春の日々を独得の語り口で淡々と綴る傑作著篇。日本文学大賞受賞。

井伏鱒二対談選
講談社文芸文庫
滋味溢れる小説と共に座談の名手でもあった井伏鱒二が、折りおりに出会った人びとと交わす楽しい会話のひと時。安岡章太郎「昭和初期の作家たち」/伊馬春部「憎めない“演技の人”太宰治」/三浦哲郎「書くのは愉し」/五木寛之「戦後と漂流の行方」/新井満「生きとし生ける者へのまなざし」今村昌平「「黒い雨」を語る」/開高健「釣る話」/中西悟堂「野鳥の話」の8篇収録。

愛の砂漠
講談社文芸文庫
高名な医師クーレージュとその18歳になる息子が同時に、町の有力者の愛人になっている美しい未亡人マリア・クロスを愛してしまう──地方都市ボルドーを舞台に、男と女を決定的に隔てる「愛の砂漠」、絶対的に孤立した人間の心の暗部をえぐり出した傑作。遠藤周作が深い共感を覚えつつ翻訳したこの作品は1925年のアカデミー小説大賞を受賞した。

一茶随想
講談社文芸文庫
目出度(めでた)さも中位也(ちゅうくらゐなり)おらが春 一茶
生涯を通して自由律俳句を唱導した井泉水は、また俳句研究にも大きな業績を残した。俳諧史上最大の存在の芭蕉と対蹠的な一茶、この2人を常に研究し続けた著者の多くの著述から、一茶を軸として、「芭蕉と一茶」「一茶の句境」「一茶と子規」「日記の一茶」等7篇収録。近代文学の視座で一茶を評価発見した著者ならではの珠玉の随筆集。

流離譚 下
講談社文芸文庫
戊辰戦争で死ぬ藩士を軸に安岡一族の歴史を書く長篇
安岡文助の次男嘉助は天誅組に入り京都で刑死するが(上巻)、一方長男覚之助は勤王党に関わって、入牢、出獄の後、討幕軍に従って戊辰戦争に参戦、会津で戦死する。戦いの最中に覚之助が郷里の親族に宛てた書簡を材に、幕末維新の波に流される藩士らの行く末を追って、暗澹たる父文助の心中を推し測りつつ物語る。土佐の安岡一族を遡る長篇歴史小説。全2冊完結。
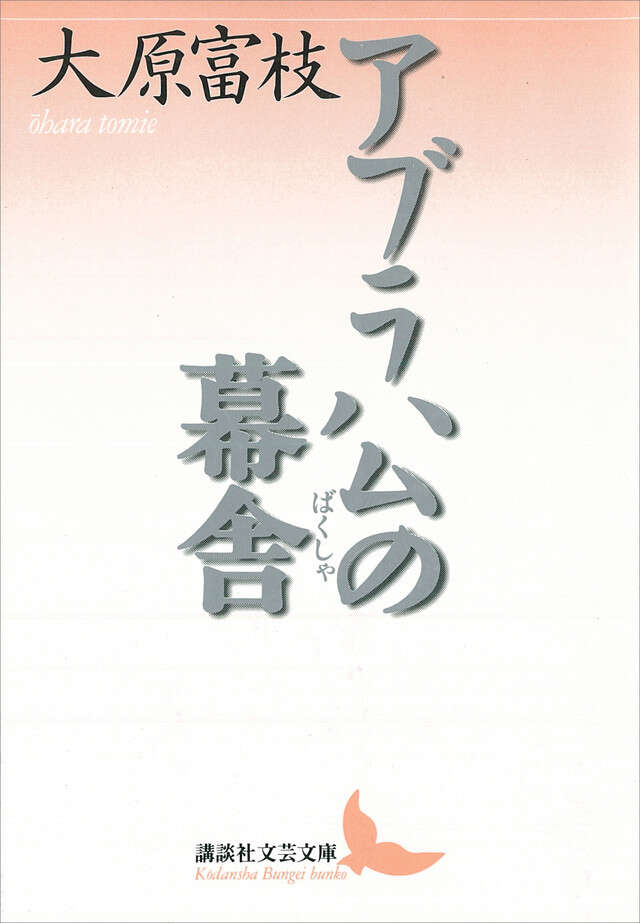
アブラハムの幕舎
講談社文芸文庫
主人公・田沢衿子は20代後半の独身女性。母親の言動に振りまわされ苦痛を感じているが、断ち切ることができない。ある日、彼女の15階だてのアパートで、祖母を殺した少年が投身自殺した。強者に支配される少年と自分とを重ね合せ、彼女は母親から逃れるため行動をおこす。〈イエスの方舟〉を背景にして、弱者の生き方を追究、魂の漂流をいきいきと描いた、著者の代表長篇小説。
主人公田沢衿子は20代後半の独身女性、母親の言動に振りまわされ苦痛を感じているが断ち切ることができない。或る日、彼女の15階だてのアパートで、祖母を殺した少年が投身自殺した。強者に支配される少年と自分とを重ね合わせ、彼女は母親から逃れるため行動をおこす。〈イエスの方舟〉を背景にして弱者の生き方を追究、魂の漂流をいきいきと描いた著者の代表長篇小説。

夏服を着た女たち
講談社文芸文庫
人情の機微、男と女のきわどい心理の綾を洗練された筆致で浮き彫りにした名手アーウィン・ショーの短篇からニューヨークを舞台にした秀作10篇を常盤新平が精選。「夏服を着た女たち」「街をさがし歩いて」「80ヤード独走」「ニューヨークへようこそ」「未来に流す涙」「モニュメント」「街の喧騒」「アメリカ思想の主潮」「ストロベリー・アイスクリーム・ソーダ」「愁いを含んで、ほのかに甘く」を収録。

流離譚 上
講談社文芸文庫
父親を主題に名作「海辺の光景」を書いた安岡章太郎が、土佐の安岡一族のルーツを遡って、幕末の藩士達に辿り着く。その1人安岡嘉助は文久2年、蕃の参政吉田東洋を刺殺、脱藩、天誅組に入って京に上るが、志半ばにして刑死する。(上巻)日記や書簡を手掛かりに、自分の実感を大切にしながら臨場感あふれるスリリングな語り口で、歴史のうねりに光を当てる長篇歴史小説。日本文学大賞受賞。全2冊。

山梔
講談社文芸文庫
山梔(くちなし)のような無垢な魂を持ち、明治時代の厳格な職業軍人の家に生まれ育った阿字子の多感な少女期を書く自伝的小説。著書の野溝七生子は、明治30年生まれ、東洋大学在学中の大正13年、特異な育ちを描いた処女作の「山梔」で新聞懸賞小説に入選、島崎藤村らの好評を博す。歌人と同棲、後大学で文学を講じ、晩年はホテルに1人暮す。孤高の芸術精神が時代に先駆した女性の幻の名篇の甦り。
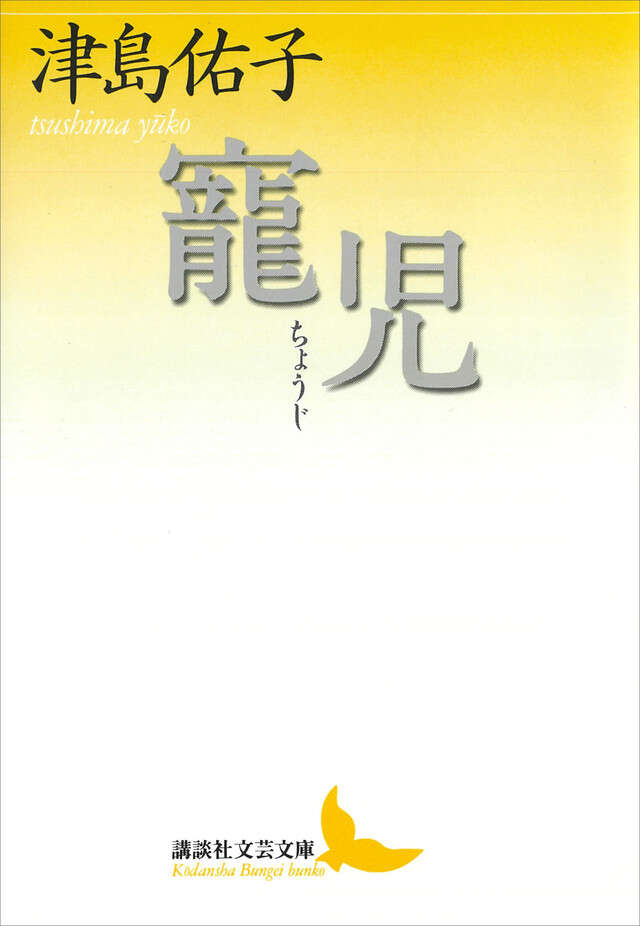
寵児
講談社文芸文庫
ピアノ教室の講師をする女は、離婚して娘と暮している。娘は受験を口実に伯母の家に下宿して母親から離れようとしている。体調の変化から、ある日女は妊娠を確信する。戸惑う女が男たちとの過去を振返り自立を決意した時、妊娠は想像だと診断され、深い衝撃を受ける。自立する女の孤独な日常と危うい精神の深淵を〈想像妊娠〉を背景に鮮やかに描く傑作長篇小説。女流文学賞受賞作品。
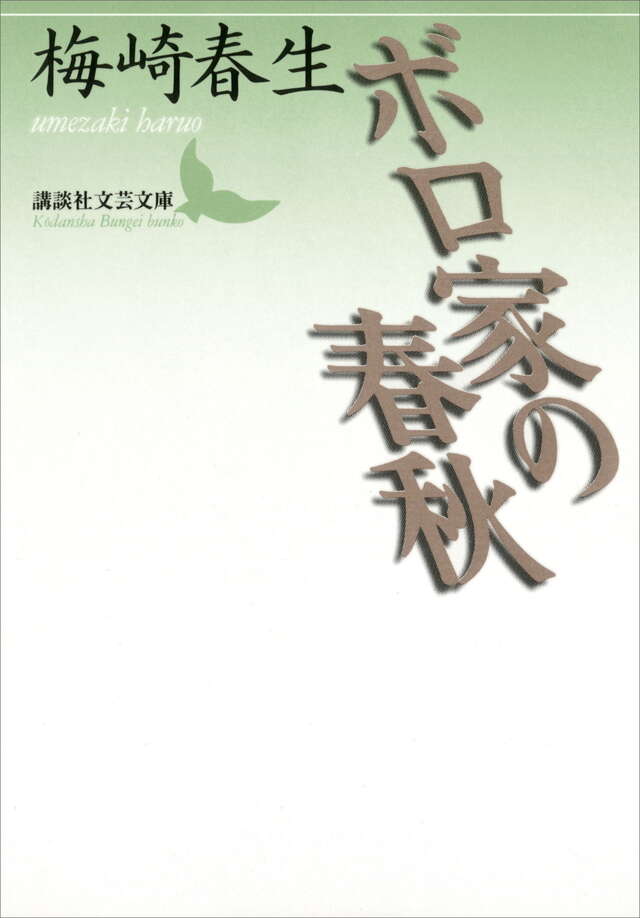
ボロ家の春秋
講談社文芸文庫
「桜島」「日の果て」などの戦争小説の秀作をのこした梅崎春生のもう1つの作品系列、市井の日常を扱った作品群の中から、「蜆」「庭の眺め」「黄色い日日」「Sの背中」「ボロ家の春秋」「記憶」「凡人凡語」の計7篇を収録。諷刺、戯画、ユーモアをまじえた筆致で日常の根本をゆさぶる独特の作品世界。

ペテルブルグ(下)
講談社文芸文庫
政府高官の息子ニコライ・アポローノヴィチはテロリストから託されたいわしの缶詰の時限爆弾にスイッチを入れてしまう──爆弾がいつ爆発するかという緊迫感につつまれて、物語はスリリングに展開する。20世紀ロシア象徴主義の鬼才ベールイが、豊かな想像力を駆使して、混迷する現実の完全な抽出とその変革をめざした言語革命的実験小説。

若山牧水随筆集
講談社文芸文庫
「白鳥はかなしからずや空の青海のあをにも染まずただよふ」「幾山河越えさり行かば寂しさのはてなむ国ぞ今日も旅ゆく」広く愛誦される牧水の歌は、明治末年、与謝野晶子等「明星」派の歌人とは異質の歌風によって世に迎えられた。旅・自然・漂白の歌人と評された彼の代表的短歌120首と紀行文「山旅の記」、父母のことや自らの生い立ちを綴った「おもいでの記」のほか「石川啄木の記」などを収録。