講談社文芸文庫作品一覧

上海游記・江南游記
講談社文芸文庫
大正10年3月下旬から7月上旬まで、およそ4ヵ月に亘り、上海・南京・九江・漢口・長沙・洛陽・大同・天津等を遍歴。中華民国10年目の中国をつぶさに見た芥川龍之介が、政治、文化、経済、風俗ほか、当時の中国の世相を鮮やかに描写。芥川独特の諧謔と諦観で綴った大正10年の中国印象記。表題作をはじめ「長江游記」「北京日記抄」及び、絵葉書に象徴的に記した各訪問地の感想「雑信一束」の5篇を収録。

われよりほかに 谷崎潤一郎最後の十二年(上)
講談社文芸文庫
文豪の知られざる実像に出会う驚き
【日本エッセイスト・クラブ賞】受賞作
京都で生まれ育った伊吹和子は24歳の時、下鴨の潺湲亭(せんかんてい)で当時66歳の谷崎潤一郎と会い「潤一郎新譚源氏物語」の原稿の口述筆記者となる。「谷崎源氏」の仕事が終わったあとは、中央公論社の谷崎担当の編集者として引き続き口述筆記に従事し、「瘋癲老人日記」や「夢の浮橋」など、晩年の傑作の誕生の現場に親しく立ち会う。

戦後短篇小説再発見5 生と死の光景
講談社文芸文庫
刻々と近づいてくる老いと死――
日常の中での避けがたい死との関係を通して、生きている現在を直視する12篇
・正宗白鳥「今年の秋」
・島比呂志「奇妙な国」
・遠藤周作「男と九官鳥」
・結城信一「落葉亭」
・島尾ミホ「海辺の生と死」
・高橋昌男「夏草の匂い」
・色川武大「墓」
・高井有一「掌の記憶」
・川端康成「めずらしい人」
・上田三四二「影向」
・三浦哲郎「ヒカダの記憶」
・村田喜代子「耳の塔」

齋藤史歌文集
講談社文芸文庫
〈稀有の才質〉と謳われる史の代表的歌文集。
2・26事件に連座した歌人齋藤瀏の長女・史が「近世から近代を経て熟成された」見事な日本語を、歌・小説・随筆に表出。屈指の理解者樋口覚編纂による代表的短歌と散文の集成。
「ひたくれなゐの人生」収録の短歌に近作37首を加えた「1 齋藤史歌集」、ちゃぼとの交歓を綴った「2 ちゃぼ交遊記」、父齋藤瀏の歌人としての交流や軍人としての日常のでき事、それにまつわる史自身のことなどを記す「3 遠景近景」、2・26事件叛乱幇助で入獄した父のことを語った「4 おやじとわたし」の4部構成。

金色の盃(下)
講談社文芸文庫
~「眺めのいい部屋」のジェイムズ・アイヴォリー監督作品~
2002年1月ロードショー「金色の嘘」原作
アメリカの大富豪ヴァーヴァー氏は、ロンドンで美術品の収集に余念がない。1人娘のマギーはアシンガム夫人の仲介でイタリアの貴族アメリーゴ公爵と結婚する。そしてヴァーヴァー氏は娘の友人のシャーロットを妻に迎える。シャーロットとアメリーゴはかつて愛し合っていたが、貧乏ゆえに結婚できなかったという過去がある。図らずも義母と娘婿の関係になった2人を待ちうけるものは――

戦後短篇小説再発見4 漂流する家族
講談社文芸文庫
日々繰りかえされる我儘、甘え、反発――夫婦、親子の心理の葛藤を深く掘り下げ、人と人の絆に迫る12篇
・安岡章太郎「愛玩」
・久生十蘭「母子像」
・幸田文「雛」
・中村真一郎「天使の生活」
・庄野潤三「蟹」
・森内俊雄「門を出て」
・尾辻克彦「シンメトリック」
・黒井千次「隠れ鬼」
・津島祐子「黙市」
・干刈あがた「プラネタリウム」
・増田みず子「一人家族」
・伊井直行「ぼくの首くくりのおじさん」

金色の盃(上)
講談社文芸文庫
~「眺めのいい部屋」のジェイムズ・アイヴォリー監督作品~
2002年1月ロードショー「金色の嘘」原作
アメリカの大富豪ヴァーヴァー氏は、ロンドンで美術品の収集に余念がない。1人娘のマギーはアシンガム夫人の仲介でイタリアの貴族アメリーゴ公爵と結婚する。そしてヴァーヴァー氏は娘の友人のシャーロットを妻に迎える。シャーロットとアメリーゴはかつて愛し合っていたが、貧乏ゆえに結婚できなかったという過去がある。図らずも義母と娘婿の関係になった2人を待ちうけるものは――

鳴るは風鈴 木山捷平ユーモア小説選
講談社文芸文庫
〈桜桃忌〉に出られなかった事から太宰治を回想する「玉川上水」、敗戦直後郷里に疎開した頃の日常を描き飄逸味を漂わせた「耳かき抄」。表題作をはじめ「逢びき」「下駄の腰掛」「山つつじ」「川風」「柚子」「御水取」など身辺の事柄を捉えて庶民のうら哀しくも善良でしたたかな生き方を綴った諧謔とペーソス溢れる木山文学の真骨頂、私小説的作品を中心に新編集した傑作11篇。

戦後短篇小説再発見3 さまざまな恋愛
講談社文芸文庫
情熱、せつなさ、歓び、迷い……ひかれ合う男と女の微妙な心の種々相を鮮明に映し出した恋の名篇12。
・山川方夫「昼の花火」
・檀一雄「光る道」
・岩橋邦枝「逆光線」
・丸谷才一「贈り物」
・大庭みな子「首のない鹿」
・瀬戸内晴美「ふたりとひとり」
・野呂邦暢「恋人」
・高橋たか子「病身」
・大岡昇平「オフィーリアの埋葬」
・山田詠美「花火」
・宇野千代「或る小石の話」
・高橋のぶ子「浮揚」

やわらかい話 吉行淳之介対談集
講談社文芸文庫
対談の名手といわれた吉行淳之介が残した多くの対談の内から、とびきり楽しく、そして人生の奥深い味わいをかもし出す12篇を精選。巻末に“あとがき的対談”として吉行淳之介の人となりを彷彿とさせる和田誠と丸谷才一の新対談を収録。〈ゲスト〉金子光晴/和田誠/淀川長治/加山又造/山口瞳/寺山修司/開高健/田村隆一/桃井かおり/大村彦次郎/徳島高義/丸谷才一
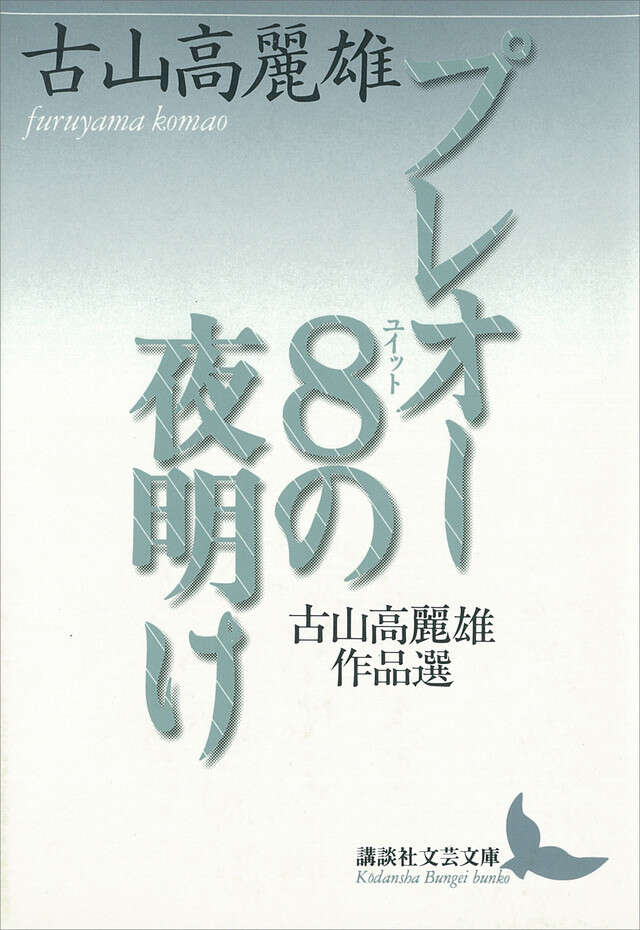
プレオー8の夜明け 古山高麗雄作品選
講談社文芸文庫
「生きていればこんなめにもあう」。理不尽なことも呑み込まなければ「普通の人間」は生きていかれない。22歳で召集、フィリピン、ビルマ、カンボジアなどを転戦、ラオスの俘虜収容所に転属され敗戦となり戦犯容疑で拘留。著者の冷徹な眼が見た人間のありようは、苛烈な体験を核に、清澄なユーモアと哀感で描かれた。芥川賞受賞の表題作ほか「白い田圃」「蟻の自由」「七ヶ宿村」など代表作9篇。

子規人生論集
講談社文芸文庫
「余は今迄禅宗の所謂悟りという事を誤解して居た。悟りという事は如何なる場合にも平気で死ぬる事かと思って居たのは間違いで、悟りという事は如何なる場合にも平気で生きて居る事であった」(「病牀6尺(抄)」より)
34歳で逝った子規の厖大な創作活動から「墨汁一滴(抄)」「仰臥漫録(抄)」等7篇、漱石宛書簡他を収録。子規独自の個性と文学革新の気概溢れるエッセイ集。

戦後短篇小説再発見2 性の根源へ
講談社文芸文庫
全10巻117篇の秀作ここに!!
人間の内奥に潜む性の魔力――戦時下の性から現代の突端の光景まで、エロスとしての人間に肉迫する11篇
・坂口安吾「戦争と1人の女〔無削除版〕」
・田村泰次郎「鳩の街草話」
・武田泰淳「もの喰う女」
・吉行淳之介「寝台の舟」
・河野多恵子「明くる日」
・野坂昭如「マッチ売りの少女」
・田久保英夫「蜜の味」
・中上健次「赫髪」
・富岡多恵子「遠い空」
・村上龍「OFF」
・古山高麗雄「セミの追憶」
●編纂委員=井口時男/川村湊/清水良典/富岡幸一郎

戦後短篇小説再発見1 青春の光と影
講談社文芸文庫
全10巻117篇の秀作ここに!!
鬱屈した心情と爆発するエネルギー――いつの時代にも変わらぬ若者たちの生態を鮮やかに描いた11篇
・太宰治「眉山」
・石原慎太郎「完全な遊戯」
・大江健三郎「後退青年研究所」
・三島由紀夫「雨のなかの噴水」
・小川国夫「相良油田」
・丸山健二「バス停」
・中沢けい「入江を越えて」
・田中康夫「昔みたい」
・宮本輝「暑い道」
・北杜夫「神河内」
・金井美恵子「水の色」
●編纂委員=井口時男/川村湊/清水良典/富岡幸一郎

生き急ぐ スターリン獄の日本人
講談社文芸文庫
旧満州哈爾濱(ハルビン)学院を卒業し、25歳の敗戦直後ソ連軍に不当逮捕されて、11年のラーゲリ生活を体験した著者が、極寒の大地での苛酷な日常と精神の葛藤を逐一記録する。戦争と革命の歴史の巨大なうねりの凝縮された1点に立ち国家と権力悪とに抗して人間の誇りと尊厳を守り通す姿は、ロシア民衆魂の底深さと人類の偉大さ、卑小さを共に示す。ソ連崩壊を予見した識者の20世紀に刻した記念碑的名著。
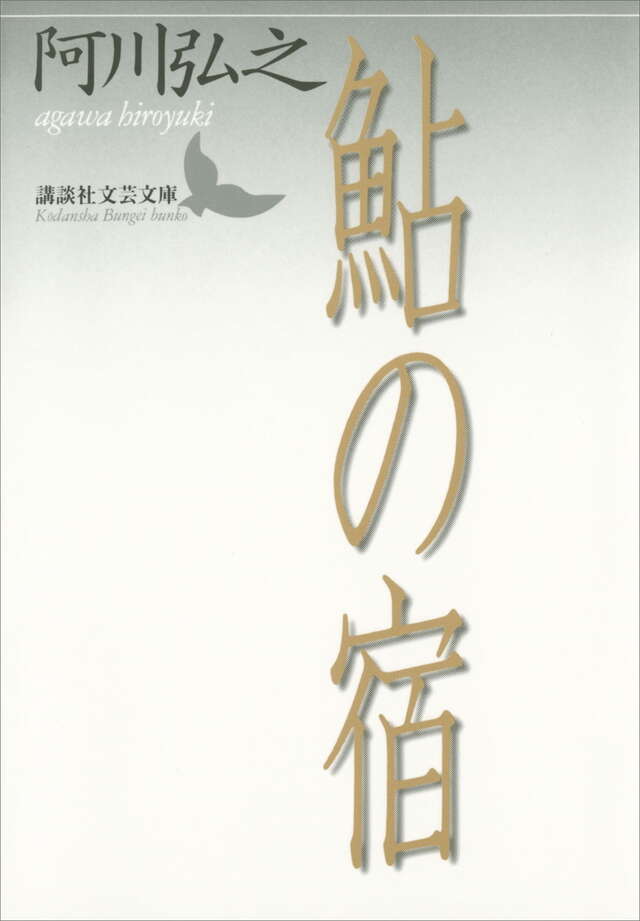
鮎の宿
講談社文芸文庫
志賀直哉門下の著者が師にまつわる様々な出来事を中心に綴った滋味溢れるエッセイ集。志賀の臨終を描いた「終焉の記」をはじめ、滝井孝作、尾崎一雄ら同門の作家や「白樺」同人の里見、梅原龍三郎のこと。志賀と前後して亡くなった三島由紀夫、川端康成、文壇仲間吉行淳之介、遠藤周作との交流、親しかった人々や食、旅をめぐる話などを清澄な文章で記した初期のエッセイ59篇。

大衆文学論
講談社文芸文庫
白井喬二、菊池寛らを論じ、先行する大衆文学論を詳細に考察した第一部「大衆文学の理論」。吉川英治、山本周五郎、松本清張らの、作家と作品を論じた第二部「作家の年輪」。時代小説の挿画、落語、浪曲など、大衆文化・芸能を掘り下げた第三部「大衆文学の周辺」。独自の視点で大衆文学を検証し、芸術性偏重の従来の文学観に新たな文学論を提示した画期的評論集。芸術選奨受賞作。
白井喬二、菊池寛らを論じ、先行する大衆文学論を詳細に考察した第1部大衆文学の理論。吉川英治、山本周五郎、松本清張ら作家と作品を論じた第2部作家の年輪。時代小説の挿画、落語、浪曲等大衆文化、芸能を掘り下げた第3部大衆文学の周辺。独自の視点で大衆文学を検証し芸術性偏重の従来の文学観に新たな文学論を提示した画期的評論集。芸術選奨受賞。人名索引を付す。
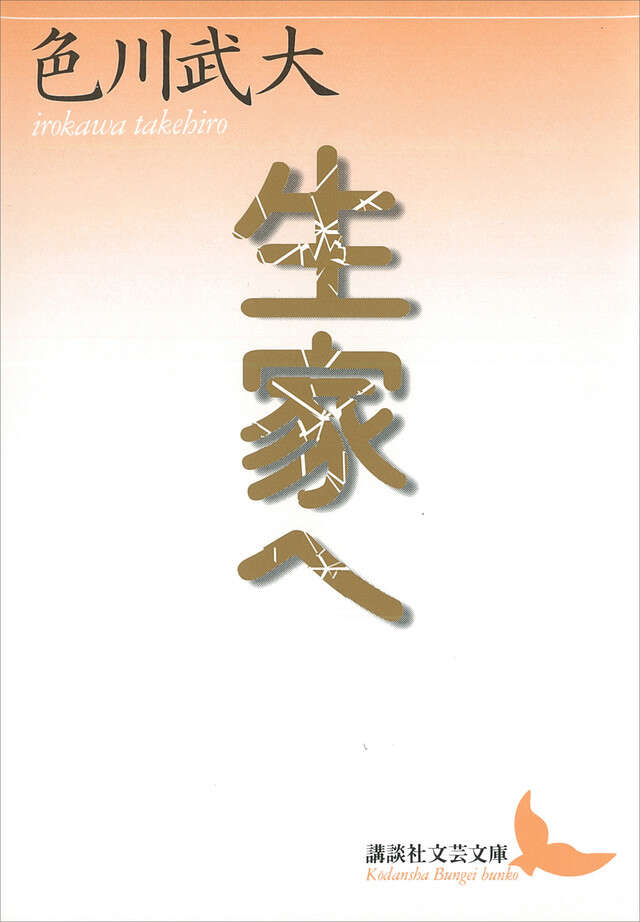
生家へ
講談社文芸文庫
生まれ育った生家へ、子どもの頃のままで帰りたい――戦時中、家の下に穴を掘り続けた退役軍人の父が、その後も無器用に居据っていたあの生家へ。世間になじめず、生きていることさえ恥ずかしく思う屈託した男が、生家に呪縛されながら、居場所を求めて放浪した青春の日々を、シュールレアリスム的な夢のイメージを交えながら回想する、連作11篇。虚実織り交ぜた独自の語りで、心弱き庶民の心情に迫った、戦後最後の無頼派の名作
生まれ育った生家へ、子どもの頃のままで帰りたい――戦時中、家の下に穴を掘り続けた退役軍人の父が、その後も無器用に居据っていたあの生家へ。世間になじめず、生きていることさえ恥ずかしく思う屈託した男が、生家に呪縛されながら、居場所を求めて放浪した青春の日々を、シュールレアリスム的な夢のイメージを交えながら回想する、連作11篇。書き留め続けた純粋な生の光景、虚実織り交ぜた独自の語りで、心弱き庶民の心情に迫った、戦後最後の無頼派の名作!

新編「在日」の思想
講談社文芸文庫
済州島の武装蜂起を描く大長篇小説「火山島」の小説家が、文学、ことば、変化する戦後日本で生きる原点の思想と国籍の問題や民族統一の課題等を論ずる20篇のエッセイ。
1 「「在日」の思想」「天皇制とチマ・チョゴリ」
2 「私にとってのことば」「日本語で「朝鮮」は書けるか」
3 「済州島と私」「自分と出会う」「私の好きな歌」他、日常の暮らしの想いや歓びまでを綴る新編成の文庫版。

漱石人生論集
講談社文芸文庫
「小生は何をしても自分は自分流にするのが自分に対する義務であり且つ天と親とに対する義務だと思います。天と親がコンナ人間を生みつけた以上はコンナ人間で生きて居れと云う意味より外に解釈しようがない」(書簡より)屈指の漱石の読み手である出久根達郎が、厭世家ではあるが決して人生を悲観しない漱石の生き方の真髄を全集の中から選んで編集した、今に新しい人生論集。