講談社学術文庫作品一覧

親鸞と一遍 日本浄土教とは何か
講談社学術文庫
無の深淵が口をあけ虚無の底に降り立った中世日本に日本浄土教を大成した二人の祖師がいた。定住型の親鸞と漂泊型の一遍という、全く対照的な生き方と思索を展開した両者の思想を、原典に現代語訳を付して緻密に読みこみ比較考量、日本文化の基層に潜む浄土教の精髄を浮き彫りにする。日本人の仏教観や霊性、宗教哲学の核心に鋭く迫った清新な論考。

馬賊の「満洲」 張作霖と近代中国
講談社学術文庫
日露の脅威がせまる清朝末期の混沌に、馬賊は生まれた。混乱の中、軍閥の長となり中原への進出をうかがい、覇権を目指した「東北王」張作霖もそんな一人だった。虚飾にとらわれた従来の張作霖像を解体し、中国社会が包含する多様性にねざす地域政権の上に馬賊を位置づけ、近代へと変貌する激動の中国と日中関係史を鮮やかに描き出した意欲的な試み。

浮世絵の歴史 美人絵・役者絵の世界
講談社学術文庫
独特の魅力を放つ「浮世絵」は、いかにして生まれ、江戸期の象徴的芸術とまでなったのか? 庶民出の町絵師によって、庶民の興味を引く「美人・役者・風景」を題材にし、庶民の購買力によって支えられた浮世絵。本書は浮世絵を日本の近世から現代の美術史として通観する試みである。浮世絵とは、そもそも何だったのか――これを読めば、浮世絵のすべてがわかる、入門編にして決定版。
独特の魅力を放つ「浮世絵」は、いかにして生まれ、江戸期の象徴的芸術とまでなったのか? 庶民出の町絵師によって、庶民の興味を引く「美人・役者・風景」を題材にし、庶民の購買力によって支えられた浮世絵。版技術の発達、鳥居・勝川・歌川各派の興亡、「蔦重」と歌麿・北斎・写楽の登場を経て大きな世界を築き、ブームが去ると今度は海外から注目を集め、多くが流出する。本書は浮世絵を日本の近世から現代の美術史として通観する試みである。成立から隆盛に至る江戸期から、幕末の衰退、「低俗」と偏見にさらされた明治以降の研究と海外からの再評価まで、壮大な潮流を俯瞰してゆく。浮世絵とは、そもそも何だったのか――これを読めば、浮世絵のすべてがわかる、入門編にして決定版。
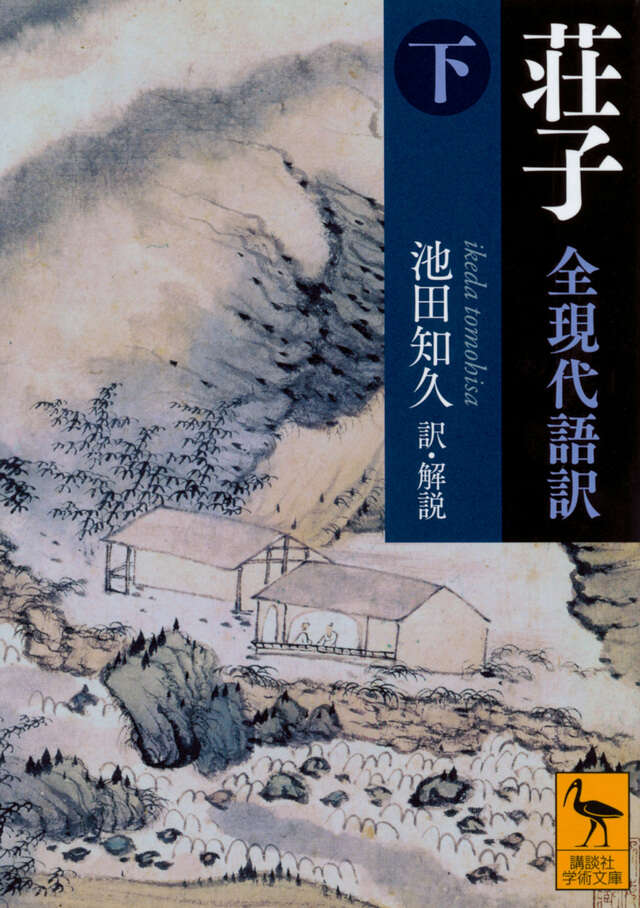
荘子 全現代語訳(下)
講談社学術文庫
「胡蝶の夢」「朝三暮四」「知魚楽」「万物斉同」「庖丁解牛」「寿(いのちなが)ければ則ち辱多し」「無用の用」などがよく知られているが、それだけではない、西洋哲学を凌駕する深い哲学・思想がある。最重要である「道」が「一」であり、また結局は「無」であり、人間には決して把えられないものであるという根本テーゼを定立した。宇宙論、生き方、処世、芸事まで、幅広い哲学を展開した、汲めども尽きぬ名著。
『荘子』は現在三十三篇本として確立しています。、内篇のみが荘子の自著であり、外篇・雑篇は荘子の弟子・後輩あるいは亜流の作であり、内篇は成立が最も早く価値も最も高く、外篇は成立がやや新しく価値も低くなり、雑篇ともなれば成立が最も新しく価値も最も低いというのが通説です。しかし、訳注者はその内容はどれも興味深いものであるとの立場をとります。
『荘子』には、よく知られた「胡蝶の夢」「朝三暮四」「知魚楽」「万物斉同」「庖丁解牛」「寿(いのちなが)ければ則ち辱多し」「無用の用」などがありますが、西洋哲学を超えるような大変に深い哲学・思想をふくんでいます。
「斉物論」は、中国古代の道家にとって最重要である「道」が「一」であり、また結局は「無」であり、人間の知恵によっては決して把えられない何ものかであるという根本テーゼを始めて定立しました。
宇宙論から人間の生き方、処世から芸事まで、幅広い哲学を展開した、汲めども尽きぬ面白さをもった『荘子』を全編、【総説】【現代語訳】【原文】【解説】を付し、達意の訳文と丁寧な解説で読み解いていきます。
『荘子 全訳注 下』(講談社学術文庫 2014年5月刊)の簡易版です。

新版 平家物語(三) 全訳注
講談社学術文庫
「おごれる人も久しからず」――勢いづく木曾義仲の前に、平家は僅か二十余年の栄華の末、都落ちを余儀なくされる。九州から瀬戸内へ落ち延びながら雪辱を期するも、源義経等の攻勢に一族は次々に無念の最期をむかえ――。宇治川の先陣、鵯越の坂落などおなじみの名場面の連続で、平氏転落の加速を格調高く語ってゆく。講談社学術文庫『平家物語』全12巻を4冊にまとめ、新版として刊行。第三巻は巻第七から第九までを収録。
12世紀末、日本が古代から中世へと大きく転換した時代に頭角を現した平家は、たちまちに権力の座に就くものの永く維持できず、東国の源氏勢によって急速に滅ぼされる。この平家一門の栄華と滅亡を軸に、歴史過程を物語ったのがこの『平家物語』である。
「おごれる人も久しからず」――平氏一門の運命はいよいよ、滅亡へと転回してゆく。勢いを増す木曾義仲の前に、平家は僅か二十余年の栄華の末、都落ちを余儀なくされる。九州から瀬戸内へ落ち延びながら雪辱を期するも、源範頼、義経等の攻勢に一族は次々に無念の最期をむかえ――。宇治川の先陣、鵯越の坂落などおなじみの名場面の連続で、平氏転落の加速を格調高く語ってゆく。
かつて刊行された講談社学術文庫『平家物語』全12巻を4冊にまとめ、新版として刊行。第三巻は巻第七から第九までを収録。

自然魔術
講談社学術文庫
イタリア・ルネサンス後期に活躍した自然探求者・技術者の著作。古代ローマの学者プリニウスの『博物誌』と並び称される。動植物の生成、磁石、女性美、蒸留、芳香、火薬、料理、狩猟、光学など、見聞と著者自身による実験観察をもとにした知識の万華鏡。黒魔術と言われる錬金術についても否定的に言及している。本書は博物誌としての歴史的意義とルネサンスから近代への思想的転換期を現している書物の抄訳。
デッラ・ポルタは16世紀から17世紀、イタリア・ルネサンス後期に活躍した自然探求者・技術者である。自然魔術師とも呼ばれる。その著書『自然魔術』は、古代ローマの学者プリニウスの『博物誌』と並び称される、自然に関する知識と観察・実験の成果をまとあげた書物である。
内容は、当時の自然観が率直に語られる一方で、動植物の生成、磁石、医術、女性美、蒸留、芳香、火薬、料理、狩猟、光学(レンズ研究)などについて、見聞と著者自身による実験観察をもとに詳細に語られている。いわば自然に関する知識の万華鏡とも言える。
デッラ・ポルタの近代科学への貢献は大きいと言われるが、その反面、黒魔術と呼ばれる錬金術についても言及されており、その技術は改良されることによって明るい見通しがつくとしている。ただし、錬金術師たちが吹聴しているようには「金」も「賢者の石」も「不老不死の妙薬」も作り出すことは不可能と断言している。
本書は博物誌としての歴史的意義とルネサンスから近代への思想的転換期を現している書物の抄訳。

荘子 全現代語訳(上)
講談社学術文庫
「胡蝶の夢」「朝三暮四」「知魚楽」「万物斉同」「庖丁解牛」「寿(いのちなが)ければ則ち辱多し」「無用の用」などがよく知られているが、それだけではない、西洋哲学を凌駕する深い哲学・思想がある。最重要である「道」が「一」であり、また結局は「無」であり、人間には決して把えられないものであるという根本テーゼを定立した。宇宙論、生き方、処世、芸事まで、幅広い哲学を展開した、汲めども尽きぬ名著。
『荘子』は現在三十三篇本として確立しています。内篇のみが荘子の自著であり、外篇・雑篇は荘子の弟子・後輩あるいは亜流の作であり、内篇は成立が最も早く価値も最も高く、外篇は成立がやや新しく価値も低くなり、雑篇ともなれば成立が最も新しく価値も最も低いというのが通説です。しかし、その内容はどれも興味深いものである。
『荘子』には、よく知られた「胡蝶の夢」「朝三暮四」「知魚楽」「万物斉同」「庖丁解牛」「寿(いのちなが)ければ則ち辱多し」「無用の用」などがありますが、西洋哲学を超えるような大変に深い哲学・思想をふくんでいます。
「斉物論」は、中国古代の道家にとって最重要である「道」が「一」であり、また結局は「無」であり、人間の知恵によっては決して把えられない何ものかであるという根本テーゼを始めて定立しました。
宇宙論から人間の生き方、処世から芸事まで、幅広い哲学を展開した、汲めども尽きぬ面白さをもった『荘子』を、【総説】【現代語訳】【原文】【解説】を付し、達意の訳文で読み解きます。
『荘子 全訳注』(講談社学術文庫 2014年5月刊)の簡易版です。

中世ヨーロッパの騎士
講談社学術文庫
鎧を着けて馬にまたがり、「サー」と呼ばれた戦士たち。平時は城に住み、騎馬試合と孤独な諸国遍歴に生涯を過ごす。本書は、中世騎士の登場から、十字軍での活躍、吟遊詩人と騎士道物語の誕生、宗教に支えられたテンプル騎士団、上級貴族にのしあがったウィリアム・マーシャルや、ブルターニュの英雄ベルトラン・デュ・ゲクランの生涯、さらに、『ドン・キホーテ』でパロディ化された騎士階級が、近代の中に朽ちていくまでを描く。
学術文庫ではすでに、『中世ヨーロッパの城の生活』(2005年刊)、『中世ヨーロッパの都市の生活』(2006年刊)、『中世ヨーロッパの農村の生活』(2008年刊)、『大聖堂・製鉄・水車』(2012年刊)、『中世ヨーロッパの家族』(2013年)が刊行されて好評を博している、ギースの「中世ヨーロッパシリーズ」の6冊目。本作では、中世ヨーロッパの軍事を担った「騎士」の実像に光をあてる。
世界の歴史上、さまざまな兵士が世界の戦場で戦ってきたが、活動期間の長さといい、歴史、社会、文化に及ぼした影響の大きさといい、中世ヨーロッパの騎士の右に出るものはない。「騎士」と聞いて思い浮かぶのは、鎧を着けて馬にまたがり、「サー」と呼ばれる戦士の姿だろう。平時は城に住み、野外の騎馬試合と孤独な諸国遍歴に生涯を過ごす――こんな通俗的なイメージは、歴史上に実在した騎士とまったくかけ離れているわけではない。そして重要なことに、彼らは強い連帯意識を持つ階級の一員でもあった。
本書では、中世騎士の登場から、十字軍での活躍、吟遊詩人とアーサー王物語に代表される騎士道物語の誕生、テンプル騎士団などの宗教騎士団、遍歴の騎士から上級貴族にのしあがったイングランドのウィリアム・マーシャルや、ブルターニュの英雄ベルトラン・デュ・ゲクランの生涯、さらに、衰退を迎えた騎士階級が、小説『ドン・キホーテ』に最後の一撃を加えられ、近代社会の中に朽ちていくまでを描く。

岡倉天心「茶の本」をよむ
講談社学術文庫
茶道を通じて、日本文化の真髄と日本人の美意識を西洋に広めるために、岡倉天心が英語で著し、1906年にニューヨークで刊行された『茶の本』を、大日本茶道学会の新会長である著者が、新たに日本語訳し、わかりやすく解説。難解な名著をやさしく読み解く工夫として、本書は 『茶の本』を最終章からさかのぼって読んでいく。西洋文明に対峙し続けた天心の「日本」への想いは、世界と向き合う現代の日本人へのエールでもある。
『茶の本』は、茶道を通じて日本の文化の真髄を西洋に広めるために、岡倉天心が英語で著し、1906年にニューヨークで刊行された。東洋の伝統的精神文化を説く文明論として、『東洋の理想』『日本の覚醒』とならぶ天心の代表作である『茶の本』は、茶に関する名著というだけでなく、茶道を嗜まない人々にも、日本文化の美意識を伝えるものとして読み継がれており、学術文庫でも桶谷秀昭氏の訳でロングセラーになっている。
本書は、本年、大日本茶道学会の会長に就任した著者が、この天心の名著『茶の本』の新しい日本語訳と、それに対する解説を試みたものである。とかく難解といわれる『茶の本』を、現代の茶道の実践者であり、芸術社会学者として大学の教壇にも立つ著者が、わかりやすく読み解いていく。
『茶の本』の難しさは、100年前の西洋人に向けて書かれていること、英語によるレトリックを駆使した文体などにあるが、もう一つは、巻頭から茶道の本質や哲学、道教とのつながりなど、思想的な議論に踏み込んでいることが上げられる。そこで本書は、『茶の本』の最終章から遡って読むという工夫をしている。第一章から読み始めるより、最終・第七章の「茶人」、第六章の「花」という具体的なことに言及する章から読み始めるのが親しみやすく、また後ろの章の内容を先に知って読むと、天心が前の章で用意した伏線に気がつく…というわけである。
なお、本書は、大日本茶道学会の研究誌、月刊「茶道の研究」に6年間にわたって連載された「『茶の本』入門一歩前」を加筆・修正のうえ、1冊にまとめたものである。

新版 平家物語(二) 全訳注
講談社学術文庫
「おごれる人も久しからず」――権力を握った平清盛の専横は、平氏一門の運命を栄華の座から滅亡へと転回させる。東国の源氏が決起し、頼朝追討の平家の大軍は、富士川で敵前逃亡。ついで木曾義仲も挙兵し、平家に危機が迫る。そして清盛は、自らの体で湯が沸くほどの熱を発して、ついに――。かつて刊行された講談社学術文庫『平家物語』全12巻を4冊にまとめ、新版として刊行。第二巻は巻第四から第六までを収録。
12世紀末、日本が古代から中世へと大きく転換した時代に頭角を現した平家は、たちまちに権力の座に就くものの永く維持できず、東国の源氏勢によって急速に滅ぼされる。この平家一門の栄華と滅亡を軸に、歴史過程を物語ったのがこの『平家物語』である。
「おごれる人も久しからず」――権力を握った平清盛の専横は、平氏一門の運命を栄華の座から滅亡へと転回させる。東国の源氏がついに決起し、清盛は福原への遷都を断行。そして頼朝を追討せんと富士川に赴くも、あろうことか敵前逃亡。ついで木曾義仲も挙兵し、平家に危機が迫る。そして清盛は、自らの体で湯が沸くほどの熱を発して、ついに――。
疾風怒濤の歴史をたどる『平家物語』は、日本史上もっともあざやかな転換期の全容を語る叙事詩であり、民族的遺産といえるものである。
かつて刊行された講談社学術文庫『平家物語』全12巻を4冊にまとめ、新版として刊行。第二巻は巻第四から第六までを収録。

星界の報告
講談社学術文庫
ガリレオにしか作れなかった高倍率の望遠鏡に、宇宙はどんな姿を見せたのか?──1609年7月に初めて製作した望遠鏡の倍率は3倍。その4カ月後には、他の誰にも追随できない20倍の倍率を実現したガリレオは、翌年初頭から天体観測を開始した。人類が初めて目にしたレンズの先には、月の表面の起伏が、天の川をなす無数の星が、そして木星をめぐる四つの衛星が現れた。人類初の詳細な天体観測の貴重な記録、待望の新訳!
物体の落下法則を発見したことで有名なガリレオ・ガリレイ(1564-1642年)は、コペルニクス、ケプラー、ニュートンと並ぶ「近代科学革命」の中心人物として知られている。
そのガリレオが初めてみずからの手で望遠鏡を製作したのは1609年7月のことだった。最初に完成したものは倍率が3倍ほどしかなかったが、そこから改良を進めて8月中旬には9倍、そして11月末には20倍の倍率を実現する。これは当時の技術レベルでは驚異的な水準で、これほどの性能をもつ望遠鏡を製作できたのはガリレオただ一人だった。
この圧倒的な優位を得て、ガリレオは天体観測を開始する。まず月から始められた観測は、月表面に起伏があることを明らかにした。翌1610年1月には望遠鏡を恒星に向けたガリレオは、天の川が無数の星々から成ることを見出し、さらに木星の周囲をめぐる四つの衛星を発見するに至る。早くも同年3月に出版された本書は、望遠鏡の話から始まり、月、恒星、そして木星の衛星の詳細な観測記録を含む、生々しいドキュメントにほかならない。
本書が与えた衝撃は、やがて伝統的な宇宙観を打ち壊す動きをもたらすことになる。地上世界と天上世界は異なる世界ではなく、同じ法則に従っている、という前提の下で「近代科学革命」が人類を大きく変えていく。
このような計り知れない意義をもっている本書を、世界の第一線で活躍する研究者が新たに訳出し、詳細な解説を書き下ろす。人類が初めて宇宙の姿の詳細を目の前にした時の貴重な記録、決定版が登場。

ガリラヤからローマへ 地中海世界をかえたキリスト教徒
講談社学術文庫
イエスはローマ総督によって処刑された。しかし、まだそれは帝国にとっては辺境属州のささいなできごとでしかなかった。彼を神の子と信じる人びとの群れは大多数の帝国人からは無視されるか、まともに扱われることのない、いかがわしい、忌まわしいと見なされる状況にあったが、徐々に教徒の数と伝道の地域を拡大していった。それは結果的に地中海の心性を、そして社会のあり方そのものをも変化させるほどの影響を残したのである。
歴史のなかにあらわれたキリスト教徒を、現実の世界、あるいは社会とのかかわりのなかでとらえることを本書はめざす。ことばをかえれば、だいたい紀元前一世紀なかばから三世紀後半までの、地中海世界の人間、おおざっぱにそれはローマ帝国の住民ともいえるが、彼らの心性の一部をになうものとして、この世界にあらたに参入してきた初期キリスト教徒の周辺を、キリスト教の側からでなく、ローマ帝国史あるいは古代地中海世界のほうからながようとのもくろみである。ナザレのイエスは、ローマ帝国の属州の一辺境の田園地方から、人間の救いを告知する伝道をはじめた。彼は神と人との関係を、たとえば富んだ者より貧しい者が評価されると主張して、逆説的にとらえようとした。人目をひく奇跡や、魔術的な行為もなしたが、それらは社会的な弱者のためにほどこされることが主であった。彼の行為にはたしかに、独特の不思議なものがあったが、この時代のローマ帝国全域とまではいわずとも帝国東方、もっと狭くはユダヤだけでも、人びとに語り、不思議をおこない、しがらみのなかにある人間の解放を告げる予言者めいた人は少なからずいたのである。イエスを神の子と信じる人びとの群れが原始キリスト教徒集団を形づくった。教会という組織づくりと、外への宣教で天才的な力量を発揮したパウロの働きがあって、帝国の都市を拠点とする宗教集団がうまれた。ローマ帝国はその領域内に1000から2000の都市を有していた。帝国の行政の単位と、文化の舞台は都市であり、ローマ帝国の人間の本来的生活とは都市にしかない、と考えられていた。この都市で、最初のキリスト教徒はローマ帝国社会と直接ふれあうことになったのである。そのことはキリスト教徒がローマ帝国社会のなかで歓迎されていたことを意味しはしない。キリスト教徒はたしかに大多数の帝国人からは無視されるか、まともに扱われることのない、いかがわしい、ある人びとにとっては忌まわしいと見なされる状況にあった。それでも徐々に教徒の数と伝道の地域を拡大していったキリスト教は、この状況にたいして独特の対応をしめした。それは結果的に地中海の心性を、そして社会のあり方そのものをも変化させるほどの影響を残したのである。

哲学塾の風景 哲学書を読み解く
講談社学術文庫
カントにニーチェ、キルケゴール、そしてサルトル。哲学書は我流で読んでも、じつは何もわからない。必要なのは正確に読み解く技術。“闘う哲学者”が主宰する「哲学塾」では、読みながら考え、考えつつ読む、〈哲学の作法〉が伝授される。手加減なき師匠の厳しくも愛に満ちた授業風景を完全再現。万人に開かれた哲学への道がここにある!
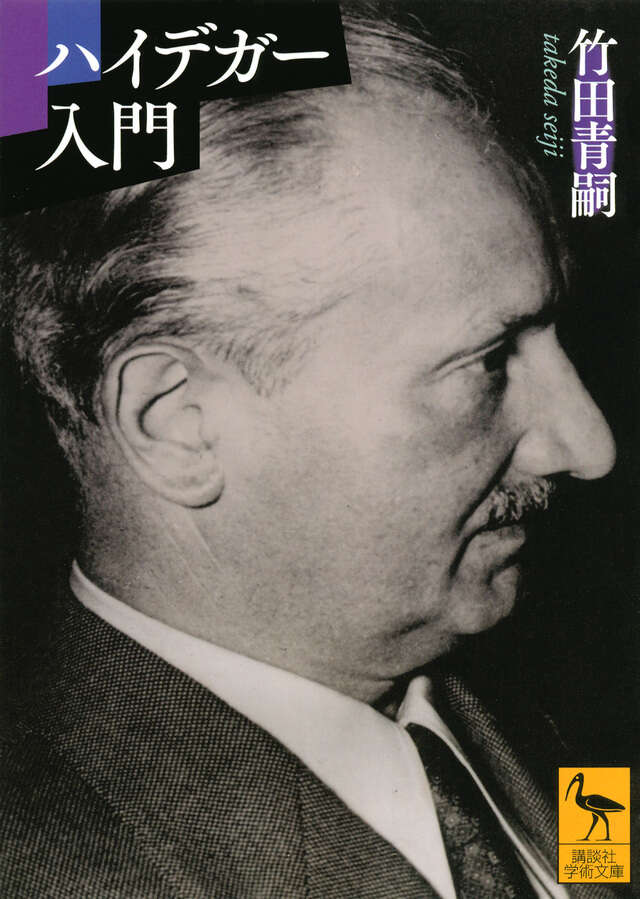
ハイデガー入門
講談社学術文庫
「20世紀最大の哲学者」として今なお読み継がれるマルティン・ハイデガー(1889-1976年)。その影響力は、現代思想、解釈学、精神病理学、文学研究に至るまで、あまりにも大きく決定的だった。本書は巨人ハイデガーの思想の全容を1冊で理解できる最良の入門書、待望の文庫化である。『存在と時間』の明快な読解から難解な後期思想の見取り図を掲げ、さらには今日再燃しつつあるナチズム加担問題に大胆に切り込む名著。
「20世紀最大の哲学者」として今なお読み継がれるマルティン・ハイデガー(1889-1976年)。その影響力は、サルトルからフーコー、デリダに至る現代思想、ガダマーに代表される解釈学、ビンスワンガーやミンコフスキーらの精神病理学、そしてバタイユ、ブランショといった文学研究まで、あまりにも大きく決定的だった。本書は、その巨人ハイデガーの思想の全容を1冊で理解できる、と長らく定評を得てきた名著、待望の文庫化である。
著者は、ハイデガーの生涯を概観した上で、「「ある」とは何か」という前代未聞の問いを掲げた『存在と時間』(1927年)を豊富な具体例をまじえながら分かりやすく読解していく。その理解を踏まえて難解で知られる後期思想の世界に分け入り、読者をたじろがせる膨大な著作群に明快な見通しが示される。その上で、20世紀末に突如として勃発した、ハイデガーのナチズムへの加担問題という微妙な話題にも躊躇することなく取り組み、この問題をどのように考えればよいのか、最良のヒントを与えてくれる一書ともなっている。ここにある「学問と政治」の関係という問題は、温暖化問題や原発問題など、今日世界中で次々にクローズアップされてきていることは誰の目にも明らかである。ハイデガーについては、「黒ノート」と呼ばれる草稿の公刊を機に、再び反ユダヤ主義と哲学の関係が取り沙汰されるようになってきている。
このように、今日ますます切迫した問題と深く関わるハイデガーの思想にアクセスするための最良の第一歩として、本書は他に類を見ない価値をもっている。学術文庫版のための書き下ろしをも加えた決定版、ついに登場。

新版 平家物語(一) 全訳注
講談社学術文庫
「おごれる人も久しからず」――権力を握った平清盛の専横は、平氏一門の運命を栄華の座から滅亡へと転回させる。院庁と山門の紛争、天台座主明雲の流罪、鹿ヶ谷の謀議。清盛激怒の末の鬼界が島への流罪と、俊寛の客死。さらに後白河法皇鳥羽離宮幽閉などなど、物語序盤にして時代は末期的様相を呈する。かつて刊行された講談社学術文庫『平家物語』全12巻を4冊にまとめ、新版として刊行。第一巻は巻第一から第三までを収録。
12世紀末、日本が古代から中世へと大きく転換した時代に頭角を現した平家は、たちまちに権力の座に就くものの永く維持できず、東国の源氏勢によって急速に滅ぼされる。この平家一門の栄華と滅亡を軸に、歴史過程を物語ったのがこの『平家物語』である。
「おごれる人も久しからず」――権力を握った平清盛の専横は、平氏一門の運命を栄華の座から滅亡へと転回させる。院庁と山門の紛争、天台座主明雲の流罪、鹿ヶ谷の謀議。清盛激怒の末の鬼界が島への流罪と、俊寛の客死。さらに後白河法皇鳥羽離宮幽閉などなど、物語序盤にして時代は末期的様相を呈する。
疾風怒濤の歴史をたどる『平家物語』は、日本史上もっともあざやかな転換期の全容を語る叙事詩であり、民族的遺産といえるものである。
かつて刊行された講談社学術文庫『平家物語』全12巻を4冊にまとめ、新版として刊行。第一巻は巻第一から第三までを収録。

死に至る病
講談社学術文庫
「死に至る病とは絶望のことである」。──この鮮烈な主張を打ち出した本書は、キェルケゴールの後期著作活動の集大成として燦然と輝いている。本書は、気鋭の研究者が最新の校訂版全集に基づいてデンマーク語原典から訳出するとともに、簡にして要を得た訳注を加えた、新時代の決定版と呼ぶにふさわしい新訳である。「死に至る病」としての「絶望」が「罪」に変質するさまを見据え、その治癒を目的にして書かれた教えと救いの書。
実存主義の祖セーレン・キェルケゴール(1813-55年)の主著、待望の新訳!
「死に至る病とは絶望のことである」。──この鮮烈な主張を打ち出した本書は、キェルケゴールの後期著作活動の集大成として燦然と輝いている。本書は、気鋭の研究者が最新の校訂版全集に基づいてデンマーク語原典から訳出するとともに、簡にして要を得た訳注を加えた、新時代の決定版と呼ぶにふさわしい新訳である。
キェルケゴールは、本書の第一編で、まず人間を普遍的かつ非キリスト教的な視座から描き、人間の特定のあり方が「死に至る病」としての「絶望」であることを明らかにした上で、絶望がさまざまな仕方で具現化されるさまを見ていく。そして続く第二篇では、キリスト教的な視座から人間を改めて捉え直し、その考察を通して、心理学的な概念である「絶望」がキリスト教的な概念である「罪」に変質していくことを指摘する。そうして、その罪がさまざまな仕方で具現化されるさまが描き出されて本書は閉じられる。
このようにして「絶望」と「罪」の精緻を極める診断が行われる目的は「死に至る病」を治療することにあった。キェルケゴールはこう言っている。「この書全体において、私は信頼できる航路標識にしたがって舵をとるように、信仰にしたがって舵をとっている」。そうして読者の一人一人をキリスト教の信仰に導き、「死に至る病」を治癒させること。キェルケゴールが生きたキリスト教世界からは遠く離れた現代日本であるが、人間が「絶望」から無縁ではいられない存在であるかぎり、本書は限りない教えと救いを与えてくれるに違いない。
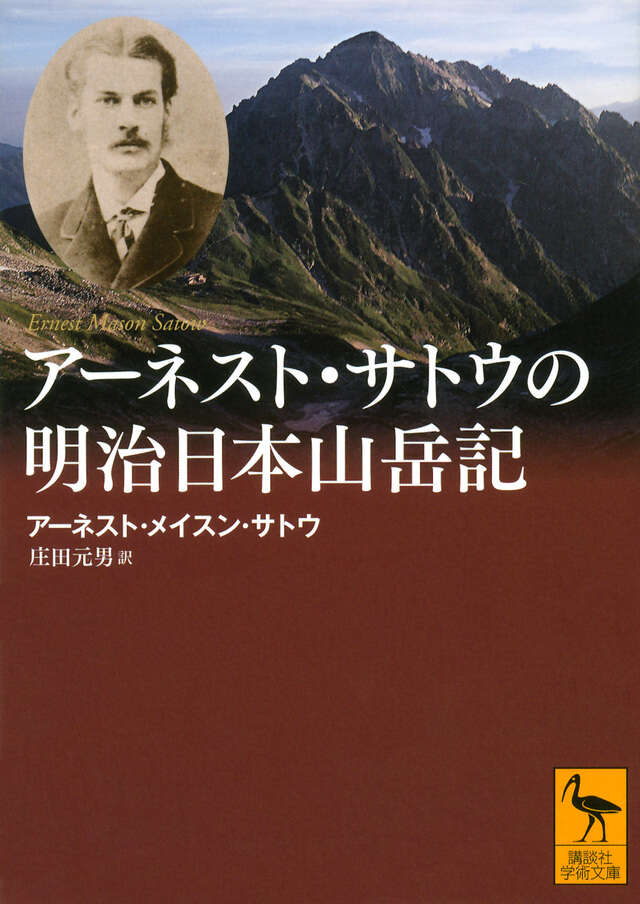
アーネスト・サトウの明治日本山岳記
講談社学術文庫
アーネスト・サトウの名は、幕末明治の日本に訪れたイギリスの外交官として知られている。しかしサトウが、日本の「近代登山の幕開け」に大きく寄与したことを知る人は案外少ない。本書は、サトウの登山家としての著作を抜粋・編集。富士山、日本アルプス、日光と尾瀬、吉野と熊野。描かれる明治の登山道は、現在はすでに廃れて使われなくなっていたり、逆に今もそのままの景色が読み取れるなど、興味をそそる。詳細な地図も掲載。
アーネスト・サトウの名は、幕末から明治の日本に赴任したイギリスの外交官としてよく知られているだろう。サトウは、幕末維新期には通訳官として活動し、いったん帰国した後、1895年(明治28年)には駐日公使として再来日を果たした親日家であった。サトウの自叙伝『一外交官の見た明治維新』は、いまも維新史研究の重要史料とされている。
しかし、サトウが、ウォルター・ウェストンやウィリアム・ガウランドと並んで、もしくは、むしろ彼ら以上に、日本の「近代登山の幕開け」に大きく寄与した人物であったことを知る人は案外少ないのではないだろうか。本書は、そうしたサトウの登山家としての仕事を、彼の残した著作から抜粋し、編集したものである。
抜粋・編集にあたっては、サトウが克明に記していた手書きの「旅日記」(邦題『日本旅行日記』平凡社東洋文庫)と、彼が欧米人向けに執筆したガイドブック『中央部・北部日本旅行案内』(邦題『明治日本旅行案内』平凡社)を底本とした。『日本旅行案内』は、東京近郊はもちろん、北は北海道・青森から、南は長崎・鹿児島までを網羅し、六十余の旅のルートを紹介した大部なものだが、それらのなかから本書では、富士山や日本アルプス、日光と尾瀬、吉野と熊野など、現代の日本人にも人気のある観光地、世界遺産の地を選んで掲載した。本書に描かれる明治期の登山道は、現在ではすでに廃れて使われなくなっていたり、また逆に今もほとんどそのままと思われる景色も読み取れるなど、おおいに興味をそそられるものである。詳細なルート案内と地図も掲載。
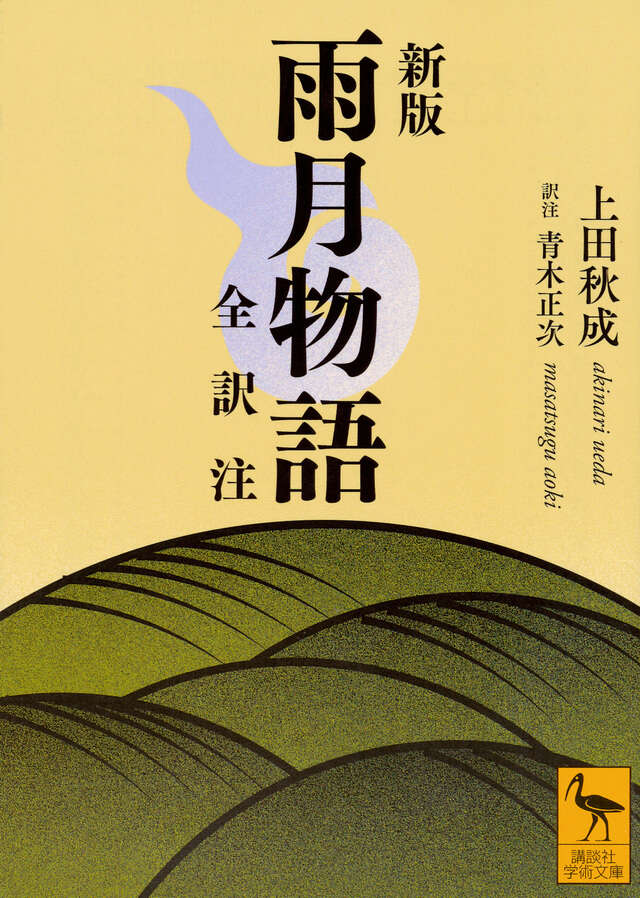
新版 雨月物語 全訳注
講談社学術文庫
上田秋成が遺した、江戸中期を代表する怪異小説集。安永5年(1776)刊、5巻9編。執念は彼岸と此岸を越え、死者との対話を繰り広げる。それは夢幻か、現実か――。現代語訳に語注、考釈も加えた決定版。
慕っていた崇徳上皇の御陵に参った西行が見たものとは? ――「白峯」
病に倒れた旅の武士。逗留先の学者と兄弟のちぎりを交わすが――「菊花の約」
怠け者勝四郎、都に上ると里は戦禍に塗れる。そして愛する妻は――「浅茅が宿」
絵が得意な三井寺の僧・興義。求める者には自作画を欲しがるまま与えながら、鯉の絵だけは頑として手放さなかった――「夢応の鯉魚」
高野山へ物見遊山の親子。「仏法」と鳴く鳥に応え歌など詠むも、そこに武士たちが現れ――「仏法僧」
吉兆なら湯が沸き上がるという釜。若い夫婦が祈願したが、釜は虫の声ほどの音も立てなかった――「吉備津の釜」
雨宿り先で邂逅した美しい女を追いかけ、幸せに暮らすはずが――「蛇性の婬」
遊行僧を泊めた老人は、紺染の頭巾をかぶり、「鬼」になった僧の話を始め、あることを懇願した――「青頭巾」
武士・岡左内は、度を越した倹約ぶりで奇人とまで言われた。ある日、黄金の精霊と名乗る老人が枕もとに現れる――「貧福論」

江戸の春画
講談社学術文庫
色事、濡れ事、笑ひ事――。「枕絵」であり「笑い絵」。公然の秘密であり縁起物。春画には、江戸のイマジネーションと絵師の技がなす、斬新、艶美、愉快な遊びが溢れている。何が描かれ、どう面白いのか。何が仕掛けられているのか。世界を虜にした浮世絵春画の軽さと深さを、豊富な図版とともに解き明かす。日本の春画への偏見を覆した名著にして、最良の入門書! (解説・辻惟雄)

『老子』 その思想を読み尽くす
講談社学術文庫
『老子』には、「無為自然」「道」「徳」の根本思想、「小国寡民」「無為の治」の政治哲学、「不争」の倫理思想、養生思想など、古代中国の思想の根幹がある。本書は、『老子』の諸思想を総合的・体系的に解明し、その諸思想の内容を分かりやすく解説。充実の【注】は、『老子』成立の諸事情と思想の内容にも深く立ち入る。原文全文と【読み下し】【現代語訳】も収録。『老子』の初学者から専門家までをカヴァーする決定版。
『老子』には、「無為自然」「道」「徳」の根本思想、「小国寡民」「無為の治」の政治哲学、「不争」の倫理思想、養生思想など、古代中国の思想の根幹があります。
後の世の『荘子』『呂氏春秋』『韓非子』『荀子』『淮南子』などに多大なる影響を与えました。
本書は、『老子』に含まれる諸思想を総合的・体系的に解明して、その諸思想のありのままの内容を分かりやすい形で提供します。その際、馬王堆帛書甲本を始めとする各種の出土資料本『老子』を重視して、古い『老子』の本来の姿を紹介することに努めています。
充実した【注】は、『老子』成立の諸事情を解明するとともに、思想の個々の内容にも深く立ち入るものとなっています。
巻末には、『老子』の原文全文と【読み下し】【現代語訳】を収録しています。
『老子』の初学者から専門家までをカヴァーする決定版です。