講談社学術文庫作品一覧

荻生徂徠「政談」
講談社学術文庫
悪魔の統治術か。近代的思惟の先駆けか。
江戸の<病理>に立ち向かった、日本近世思想史の巨人による政策提言集。
開闢以来第一の人物と同時代人にも称賛された日本近世思想史の巨人、徂徠。
将軍吉宗の下問に応えて彼が献上した極秘の政策提言書には悪魔的な統治術の数々がしたためられていた。
反自由・反平等・反啓蒙の立場の表れか。
近代的思惟の先駆けか。
それは江戸の現実と病理に立ち向かった実践的思索の集積であった。
いまも論争を呼ぶ経世の書を平明な現代語で読む。
<「政談」巻末より>
「機事、密ならざれば、則ち害生ず」(『易経』繋辞上伝)ということがあって、幕府の政治上の機密は明白に人に語るべきものではないから、この物語は弟子にも書かせず、私自身の老眼と悪筆で認(したた)めたことである。将軍様の上覧に入れたのちは、焼却していただきたい。
物部茂卿 敬 識(もののべのもけい つつしんで しるす)
※本書の原本は、1974年に『日本の名著 16 荻生徂徠』として中央公論社より刊行されました。
文庫化にあたっては、中公バックス版の同名書(1983年刊)を底本としました。

永楽帝――華夷秩序の完成
講談社学術文庫
簒奪、殺戮、歴史の捏造……。
その果てに築きあげた、中華の〈世界システム〉。
明朝第三代、永楽帝。甥である建文帝から皇位を簒奪し、執拗なまでに粛清と殺戮を繰り返し、歴史を書き換えて政敵が存在した事実まで消し去ろうとした破格の皇帝。
その執念と権勢はとどまるところを知らず、中華の威光のもと朝貢国六〇余をかぞえる「華夷秩序」を築き上げた。
それは前近代東アジアを律しつづけた中華の〈世界システム〉であった。
*
――彼の確立した体制は、中国国内ばかりか東アジア諸国でも、「近代」以前の社会を規定した。良きにつけ悪しきにつけ、中国の影響を受けつづけた周辺諸国は、彼の時に明朝を中心とした国際秩序に組み込まれ、その枠組みのなかでの行動を強いられた。(……)東アジアの国際関係を律するシステムの完成は、永楽時代にある。――<本書「あとがき」より>
※本書の原本は、1997年、小社より刊行されました。
【本書の内容】
はじめに
第一章 中華という名の世界
1 中華と夷狄
2 中華世界の変転
第二章 大明帝国の誕生
1 中華の回復
2 元から明へ
3 明初体制の意味するもの
第三章 皇統のゆくえ
1 燕王の事蹟
2 暗闘
第四章 奪権への階梯
1 南人朝廷
2 挙兵前夜
第五章 歴史の翻転
1 靖難の変
2 理念の末路
第六章 失われた時のなかで
1 建文出亡
2 滅びゆく者たち
第七章 天命の所在
1 聖王の御代
2 徳治の実態
第八章 クビライを越えて
1 四夷朝貢
2 拡大する中華
第九章 華夷秩序を統べる者
1 順逆の理
2 天子の都
第十章 永楽帝の遺産
1 盛世の翳り
2 中国史の転換点
参考文献
あとがき
文庫版あとがき

日本の産業革命――日清・日露戦争から考える
講談社学術文庫
製糸・紡績、鉄道、鉱山、金融。日本の近代化を支えたものは戦争と侵略だったのか? 本書は日清・日露両戦争と産業革命の関係を軸に、構造を変革する主体の姿を解明、新たな歴史像を描出する。明治の国家目標「殖産興業」が「強兵」へと転換する過程を追い、十九世紀末から二十世紀初頭にかけて世界経済の中で日本が選択した道を鮮やかに活写する。
日本の近代化を支えたものは戦争と侵略だったのか?
明治の国家目標「殖産興業」はいつ、なぜ、どのように「強兵」へと転換したか
製糸・紡績、鉄道、鉱山、金融。日本の近代化を支えたものは戦争と侵略だったのか? 本書は日清・日露両戦争と産業革命の関係を軸に、構造を変革する主体の姿を解明、新たな歴史像を描出する。明治の国家目標「殖産興業」が「強兵」へと転換する過程を追い、十九世紀末から二十世紀初頭にかけて世界経済の中で日本が選択した道を鮮やかに活写する。

大聖堂・製鉄・水車―中世ヨーロッパのテクノロジー
講談社学術文庫
「暗闇の中世」は、実は技術革新の時代だった!
建築・武器・農具・織機・印刷……直観を働かせ、失敗と挑戦を繰り返した職人や聖職者、芸術家たちが世界を変えた。
西洋中世の新たな実像を描いて定評ある著者による、テクノロジーの中世史。軍事、建築、交通から、織機や農具など、あらゆる具体的なモノの変遷と、社会や暮らしの変化をたどる。「停滞の元凶」とされる教会や修道院が時に技術革新の推進力となり、また、東方の文化を吸収しつつ千年にわたって緩やかに進行した技術革新が、近代の「革命」を用意していく。

儀礼としての消費 財と消費の経済人類学
講談社学術文庫
辻井喬氏による推薦のことば――
本書は消費を人間の活動のただ中に置くことで、消費についてばかりでなく、社会的活動に新しい光を当てた画期的論文である。世界で最も影響力のある人類学者のこの論文を読んで以来、私の中で消費は勿論のこと経済人類学そのものが新しい姿をもって現れるようになった。
人類学の巨匠メアリー・ダグラスが、「消費」と「財」という経済理論の難問に迫る。「財」の有用性を括弧に入れ、「財」を消費者の価値秩序を物理的に示す「標識(マーカー)」として、「消費」をコミュニケーションとして改めて定義する。ケインズ、ウェーバー、デューゼンベリー、フリードマン、エンゲル、レヴィ=ストロースなどの所説を検証し、消費社会を駆動する原理を解き明かす。
〔本書〕のねらいは、人類学もしくは記号論と経済学との間に一つの橋を架すること、すなわち、社会を律する象徴秩序を解明するという象徴人類学の手法を経済の領域に適用することにある。〔略〕本書は、記号論になじみの薄い経済学徒にとって、きわめてとっつきやすい経済人類学への入門書といえるのである。〔略〕本書で展開される消費の経済人類学は、今後の経済社会のありようを読み解く上で、きわめて適切にして新鮮な視点を一つ提供してくれたことになる。――<「訳者あとがき」より>
※本書の原本は、1984年、新曜社より刊行されました。

パラドックス―論理分析への招待―
講談社学術文庫
新たなパラドックスの発見と、それとの格闘が、人間の思索を深め、新しい論理学や意味論の形成をもたらした。「嘘つきのパラドックス」や「不意打ち試験のパラドックス」、さらに「自由と必然」「他人の心を知り得るか」など古来の哲学的難問を取り上げ、自然科学的世界像と日常的世界との亀裂に生じるパラドックスとして論理分析を武器に解明していく。(講談社学術文庫)
たとえば、この言明をどう理解するか?
この枠内に書いてあることは、ウソである。
パラドックスとの格闘が人間の思考を鍛えてきた
新たなパラドックスの発見と、それとの格闘が、人間の思索を深め、新しい論理学や意味論の形成をもたらした。「嘘つきのパラドックス」や「不意打ち試験のパラドックス」、さらに「自由と必然」「他人の心を知り得るか」など古来の哲学的難問を取り上げ、自然科学的世界像と日常的世界との亀裂に生じるパラドックスとして論理分析を武器に解明していく。
※本書の原本は、1972年、中央公論社より刊行されました。

地形からみた歴史 古代景観を復原する
講談社学術文庫
「地震」「水害」「火山」「雷」「大風」……。『記紀』に描かれた数多の自然現象とその災害の実態とは? 「浦」「江」「潟」「岸」「潮」「浜」……。『万葉集』に謳われた風光明媚な景を現在と比較すると? 「古墳」「池」「溝」「津」「水門」、人為は景観をどう変えたのか? 空中写真、地形図、遺構・遺跡、史料を突き合わせ、失われた古代日本を大胆に復原する。(講談社学術文庫)
自然と人間によって、大地は姿を変える
『記紀』『万葉集』に登場する「水門」「潟」「大溝」「津」とは?
古日本の姿を、地理学・考古学・歴史学を総動員して復原する
「地震」「水害」「火山」「雷」「大風」……。『記紀』に描かれた数多の自然現象とその災害の実態とは? 「浦」「江」「潟」「岸」「潮」「浜」……。『万葉集』に謳われた風光明媚な景を現在と比較すると? 「古墳」「池」「溝」「津」「水門」、人為は景観をどう変えたのか? 空中写真、地形図、遺構・遺跡、史料を突き合わせ、失われた古代日本を大胆に復原する。
……環濠とシュートバー(埋没礫堆)の調査では、あらかじめ用意した地形分類予察図、空中写真、検土杖(けんどじょう)などを持って現地に出かけ、発掘現場の露頭観察や検土杖による地質調査に汗を流し、(中略)広くて傾斜の緩やかな地域では地形図、空中写真、折れ尺などを手に、黙々とペダルを踏んだ。自転車は、平野の微起伏をとらえるのに、とても都合がよかった。(中略)私は地形環境と人間活動との関係を、かなりながい時間軸でとらえるという方法を、頑(かたくな)にとり続けてきた――<「学術文庫版まえがき」より>
※本書の原本『古代景観の復原』は、1991年に中央公論社より刊行されました。

江戸の食空間――屋台から日本料理へ
講談社学術文庫
盛り場に、辻々に、縁日に、百万都市江戸を埋め尽くしたファストフード屋台から、てんぷら、すし、そばは生まれた。庶民の愛した江戸前の味、意外に質素な将軍の食卓、調味料や嗜好品がもたらした食の発展、初鰹狂奏曲、料理茶屋の番付や料理書が出版されるグルメブーム、そして究極の料理茶屋「八百善」――。多彩で華麗な江戸の食空間を読み解く。
盛り場に、辻々に、縁日に、百万都市江戸を埋め尽くしたファストフード屋台から、てんぷら、すし、そばが生まれた。庶民の愛した江戸前の味、意外に質素な将軍の食卓、調味料や嗜好品がもたらした食の発展、初鰹狂奏曲、料理茶屋の番付や料理書が出版されるグルメブーム、そして究極の料理茶屋「八百善」――。多彩で華麗な江戸の食空間を読み解く。

無限 その哲学と数学
講談社学術文庫
有限な人間の抱える問題とは、それ自身、無限との格闘なのだ!!
アキレスと亀のパラドクスから、カント、ヘーゲル、ヴィトゲンシュタインへ。
カントール、レーヴェンハイム-スコーレムの定理、そしてゲーデルの定理……
古代ギリシアから現代まで、「無限の思想史」を通観する稀代の名編!
アリストテレスは、無限は可能的には存在するが、現実的には存在しないと述べた。数学的な無限は認めても形而上学的な無限は認めなかったのだ。カント、ヘーゲルらの哲学的思考、カントールの集合論の衝撃、ゲーデルの定理などを経てヴィトゲンシュタインへ。古代から現代までを通覧し、「無限」と「死」と格闘した人類の思索を跡づける魅惑の名作。
本書は、無限についての本である。しかしまた、有限についての、我々の有限性についての本でもある。無限についての我々の感覚の背後には、我々自身の有限性についての感覚が位置している。我々は、自分が有限であることを知っている。それは、我々の存在が矮小で短命であるといった問題ではない。それよりももっと根本的なことがらが、ここにはある。すなわち、我々が自分で作り出したのではない世界に投げ出されているという事実、我々が自分ではない他のものと向き合っていることに気づかされるという事実が横たわっているのである。――<本書「序文」より>
※本書の原本は、1996年、東京電機大学出版局より刊行されました。

新井白石「読史余論」 現代語訳
講談社学術文庫
「正徳の治」で名高い大儒学者による歴史研究の代表作。古代天皇制から、武家の発展を経て江戸幕府成立にいたる歴史を九変・五変に時代区分して論じ、徳川政権の正当性を主張する。天皇家や源頼朝、足利幕府への客観的で冷徹な評価、為政者の不徳と失政に対して天命が革まる「易姓革命」への警鐘など、実証的で先駆的な史論の現代語訳。(講談社学術文庫)
江戸期の大知識人による先駆的な歴史研究
天皇家の衰退から秀吉の天下統一への過程を実証的に描き、徳川政権の正当性を主張。
独自の歴史観を読みやすい訳文で。
「正徳の治」で名高い大儒学者による歴史研究の代表作。古代天皇制から、武家の発展を経て江戸幕府成立にいたる歴史を九変・五変に時代区分して論じ、徳川政権の正当性を主張する。天皇家や源頼朝、足利幕府への客観的で冷徹な評価、為政者の不徳と失政に対して天命が革まる「易姓革命」への警鐘など、実証的で先駆的な史論の現代語訳。(解説・藤田覚)
おおよそこれらの人びとのふるまいは、どう考えても大臣らしい行いとはいえない。思えば、よくよく恥を知らぬ人びとであった。(中略)世の中がすこしでも平穏になると尊位厚禄にあぐらをかき、武士をまるで奴婢や雑人のようにしか思わず、世間が乱れたときにはこそこそするばかりで、一人として身を投げだして忠功をはげむ者もいなかったのは、公家と僧徒だけ。まことに国家の害毒というのは、こういう連中のことをいうのであろう。だから、天道は、天に代わって功を立てる人に報いるのが道理ゆえ、その後に武家が世を治めたのも、理由のあることだと考える。――<本書第三巻より>
※本書の原本は、1969年、「日本の名著 15『新井白石』」として、中央公論社より刊行されました。本書は、中公バックス版「日本の名著 15」(1983年刊)を底本としました。

宗教と権力の政治―「哲学と政治」講義2
講談社学術文庫
それぞれに忠誠心を要求し、人間の行動を左右し、激しく衝突してきた「聖」と「俗」との長い抗争は、政治に何をもたらしたのか。「政治とは何か」を考えるシリーズ二冊目の本書は、教皇至上権とトマス・アクィナスの政治論、ルターの宗教改革、マキアヴェッリの権力論、さらに宗教戦争を経て、「政治の解体」が訪れ、中世が終幕をむかえるまでを論じる。(講談社学術文庫)
2003年、講談社刊の同名書籍の学術文庫化。
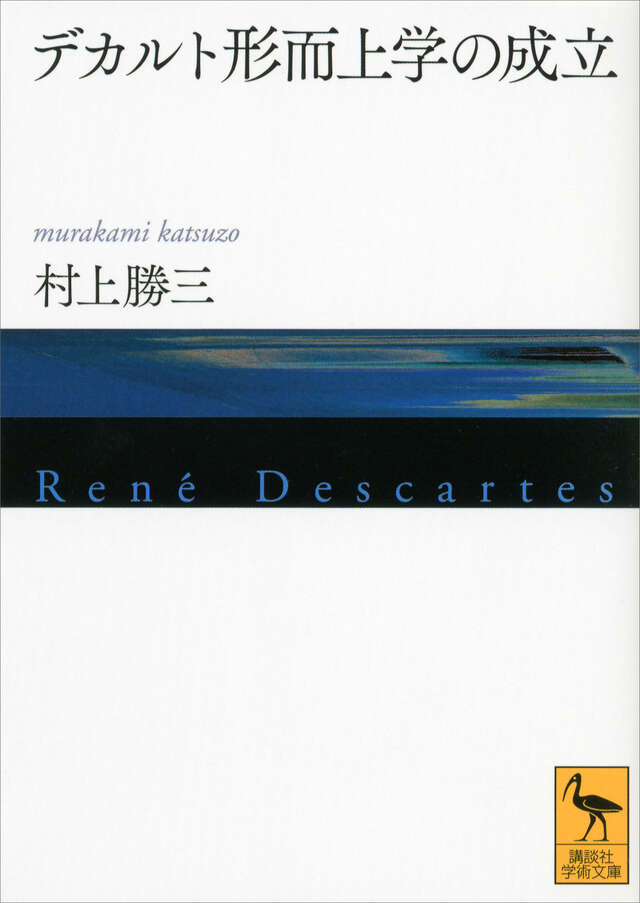
デカルト形而上学の成立
講談社学術文庫
「私はあり、私は実在する」という認識は、「すべての認識のうちで最も確実で最も明証的」である。――近代哲学の父ともいわれるデカルトのこの哲学とは、いったい何なのか。神の存在証明とは? 書簡・小篇から主著『省察』まで、細密に読み解き、デカルトの形而上学が成立した道筋を詳細に辿り、その本質を「観念(イデア)」論としてとらえた画期的力作! (講談社学術文庫)
「私は実在する」とはどういうことか。神が存在するとは?
四つの書簡から、「方法序説」『省察』まで、精緻に読み抜いた「これこそがデカルト」!
「私はあり、私は実在する」という認識は、「すべての認識のうちで最も確実で最も明証的」である。
――近代哲学の父ともいわれるデカルトのこの哲学とは、いったい何なのか。神の存在証明とは? 書簡・小篇から主著『省察』まで、細密に読み解き、デカルトの形而上学が成立した道筋を詳細に辿り、その本質を「観念(イデア)」論としてとらえた画期的力作!
「私」は間違えたことがある。疑いの道の始まりにはこのことがある。真であるか、偽であるかわからないから疑う。知らないから疑う。知らないと知っているわけではない。疑うことをとおして、疑うことの理由を見出すことをとおして、なぜ知らないのかわかる。「私はあり、私は実在する」。これはどのようにしても、どこからみても疑いえぬ立言である。疑うことは「思うこと」である。疑いつつ疑いえぬとわかる。「私は思うものである」。このことは揺るがない。確実である。しかし、知識として確実であるということとは異なる。――<本書より>
※本書の原本は、1990年、勁草書房より刊行されました。
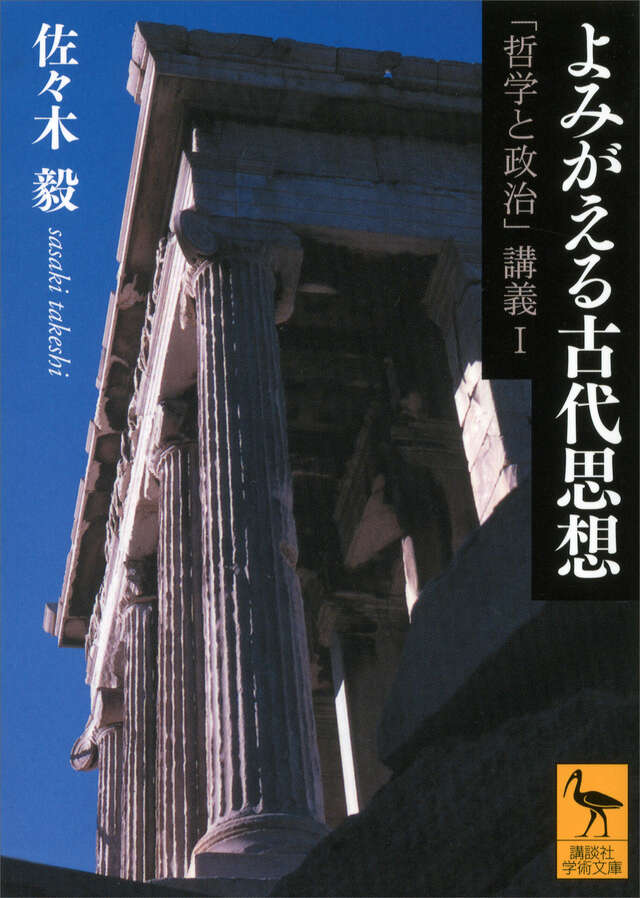
よみがえる古代思想―「哲学と政治」講義1
講談社学術文庫
政治について根源的に考えようとする時、人は古代ギリシア・ローマの哲学に立ち戻らざるを得ない。人間と政治の関わりについて、これほど深く、率直に議論された時代は他にないからである。ポリス最大の悪徳「ヒュブリス」とは。プラトンの唱えた「哲人王」とは。ローマの政治家はなぜ哲学を嫌ったのか。政治思想史の第一人者が「政治の本質」を語る。(講談社学術文庫)
2003年、講談社刊の同名書籍の学術文庫化。

東方的
講談社学術文庫
地球をおおいつくそうとするひとつの世界システムに「地域の論理」たちは繊細なたたかいを挑む。閉ざされつつある世界に、新しい超空間への通路を開く。
ボストーク――東の方。人間を乗せた最初の宇宙船の名前である。偉大なる叡智=ソフィアは、科学技術文明と近代資本主義が世界を覆い尽くす時こそが、真実の危機だと告げる。バルトーク、四次元、熊楠、マンダラ、シャーマニズム、製鉄技術、方言、映画とイヨマンテ……。多様なテーマで通底する「無意識」に、豊饒な叡智を探求する。(解説・沼野充義)
『東方的』は、……西欧的な知のあり方の行き詰まりを踏まえて、「東方的」な「ソフィア」(叡智)の方向に新たな可能性を見出そうとした、美しい希望の書物である。(略)その「明確なモチーフ」は……、「第四次元、あるいは日常的なリアリティを超えた高次元の霊的な世界が、われわれが普段住んでいる物質的な世界と接触した時、何が起こるか」ということに帰すのではないかと思う。――<沼野充義「解説」より抜粋>
※本書の原本『東方的』は、せりか書房より1991年に刊行されました。

茶経 全訳注
講談社学術文庫
中国唐代、「茶聖」陸羽によって著された世界最古の茶書『茶経』。茶の起源、製茶法から煮たて方や飲み方、さらに茶についての文献、産地による品質まで、茶に関する知識を実践的かつ科学的に網羅する「茶学の百科全書」を、豊富な図版とともに平易に読み解いてゆく。中国喫茶文化研究の泰斗による四十年余にわたる探究を経て完成した喫茶愛好家必携の一冊。(講談社学術文庫)
茶の起源、製茶法から飲茶まで、茶にまつわる諸学を網羅した「茶の百科全書」を完全読解!
“茶聖”、甦る
中国唐代、「茶聖」陸羽によって著された世界最古の茶書『茶経』。茶の起源、製茶法から煮たて方や飲み方、さらに茶についての文献、産地による品質まで、茶に関する知識を実践的かつ科学的に網羅する「茶学の百科全書」を、豊富な図版とともに平易に読み解いてゆく。中国喫茶文化研究の泰斗による四十年余にわたる探究を経て完成した喫茶愛好家必携の一冊。
※本書の原本は、2001年8月、淡交社より『茶経詳解』として刊行されました。

日本人の「戦争」――古典と死生の間で
講談社学術文庫
一人の戦中派が書きつづけた、死者と対話。古典と対話。
正成、信長、二・二六、そして「あの戦争」。
日本人にとって戦争とはなんだったのか。
なぜ「あの戦争」はあれほど悲愴な戦いになったのか。
なんのために死んだのか。なにより、なんのためなら死ねると言えたのか。
「戦中派」思想史家は、同年輩の死者たちの中断された問いかけに答えるため、死者と対話し、古典と対話する。痛恨の論考。鎮魂の賦。
【本書の内容】
まえがき
【1】日本人の「戦争」――古典と死生の間で
1 実感と「抽象」
2 「僕は妣の国に往かむと欲ひて……」
3 言霊の戦い――「海行かば」
4 修羅の戦い――「七生報国」
5 信長の戦い――「滅せぬ者のあるべきか」
6 「国民」の戦争
――「朝日に匂ふ日の本の 国は世界に只一つ」
7 歴史の中の「戦争」――「見るべき程の事は見つ」
【2】「開戦」と「敗戦」選択の社会構造
――“革命より戦争がまし”と“革命より敗戦がまし”
1 “戦争か平和か”の選択でなく
2 「国体」を支える社会構造
3 二・二六事件の後に
4 農地調整法と企画院事件
5 先制攻撃をうける懸念
6 内戦への懸念
7 革命か敗戦かの選択
【3】天皇・戦争指導層および民衆の戦争責任
1 半世紀後の戦争責任論
2 天皇の戦争責任
3 戦争指導層の戦争責任
4 民衆の戦争責任
【4】日本の「戦争」と帝国主義
――空腹の帝国主義と飽食の帝国主義
1 帝国主義の昔と今
2 金銭と暴力――シャイロックから帝国主義へ
3 日本の「戦争」――空腹の帝国主義
4 現代の帝国主義と超帝国主義
【終章】特攻・玉砕への鎮魂賦
1 「汝心あらば 伝へてよ玉のごと われ砕けにきと」
2 『戦友』と『同期の桜』
3 鎮魂の賦
初版あとがき
新版のためのあとがき
解説

世界人名物語――名前の中のヨーロッパ文化
講談社学術文庫
神々や英雄への憧憬、聖人や名君への賞賛から生まれた名前。歴史と文化に根ざす人々の思いと固有のイメージがこめられている名前の由来と変遷をさぐり、多様な文化の交流と積み重ねの上に成立しているヨーロッパの発想、価値観、社会観を明らかにする。ギリシャ・ローマ神話からハリウッドスターまで、人名で読み解くヨーロッパの文化、歴史、民俗。(講談社学術文庫)
神話、英雄伝説、聖人や名君への憧憬に根ざす系譜と豊かなイメージとは?
名前で読み解く西欧文明の成立と多様性
神々や英雄への憧憬、聖人や名君への賞賛から生まれた名前。歴史と文化に根ざす人々の思いと固有のイメージがこめられている名前の由来と変遷をさぐり、多様な文化の交流と積み重ねの上に成立しているヨーロッパの発想、価値観、社会観を明らかにする。ギリシャ・ローマ神話からハリウッドスターまで、人名で読み解くヨーロッパの文化、歴史、民俗。
※本書の原本は、1999年1月、小社より刊行されました。

幕末外交と開国
講談社学術文庫
無能無策な幕府が、黒船の「軍事的圧力」に屈し、不平等条約を強いられたという「日本史の常識」を検証。軍事衝突は起こり得るのか、交渉は何語で行うのか――。ペリー来航から和親条約締結までの一年間を日米の資料から追跡して見えてきたのは、幕府の高い外交能力と、平和的交渉の輝かしい成果だった。日本の近代外交と日米関係の原点を見直す。(講談社学術文庫)
黒船に揺れた1年間を検証 「無能な幕府」説は本当か?
日米双方の資料から、「開国」をめぐる常識を覆す。
日米和親条約は、戦争によらない平和的な交渉の
成果だった!
無能無策な幕府が、黒船の「軍事的圧力」に屈し、不平等条約を強いられたという「日本史の常識」を検証。軍事衝突は起こり得るのか、交渉は何語で行うのか――。ペリー来航から和親条約締結までの一年間を日米の資料から追跡して見えてきたのは、幕府の高い外交能力と、平和的交渉の輝かしい成果だった。日本の近代外交と日米関係の原点を見直す。
日米和親条約は一門の大砲も火を噴かず、平和的な交渉によって結ばれた。これが最重要の論点だと私は考える。(中略)アジア近代史から見れば、日米和親条約のような「交渉条約」は稀有の事例である。「交渉条約」を導いたのは偶然ではない。一定の政治的条件の下、日米双方の当事者による外交努力の成果にほかならない。日本外交史のなかでは、幕府の高い外交能力は特筆されるべきであろう。――<本書「あとがき」より>
※本書の原本は、2004年に筑摩書房より刊行されました。

ヒトはなぜ眠るのか
講談社学術文庫
進化の過程で睡眠は大きく変化した。肥大した脳は、ノンレム睡眠を要求する。睡眠はなぜ快いのか? 眠りの機能とは? 大脳と睡眠、身体と睡眠の関係、睡眠にまつわる病気、睡眠と冬眠の違い、睡眠を司るホルモン、体内時計の働き、短眠者と長眠者の謎、科学的な快眠の秘訣……。最先端の脳科学で迫る睡眠学入門の決定版。最新の知見と新規文献も充実! (講談社学術文庫)
子供は快眠、老人が不眠なのはなぜか?
病気のときに、よく眠れるのはなぜか?
睡眠学の第一人者による、眠りの不思議と快眠の秘訣!
進化の過程で睡眠は大きく変化した。肥大した脳は、ノンレム睡眠を要求する。睡眠はなぜ快いのか? 眠りの機能とは? 大脳と睡眠、身体と睡眠の関係、睡眠にまつわる病気、睡眠と冬眠の違い、睡眠を司るホルモン、体内時計の働き、短眠者と長眠者の謎、科学的な快眠の秘訣……。最先端の脳科学で迫る睡眠学入門の決定版。最新の知見と新規文献も充実!
いま、眠りの学問は急速に進歩し拡大し、「睡眠学」として世間に認知され、睡眠現象や睡眠障害を医学的に扱うだけでなく、睡眠をとおして社会の活動様式全般にも影響をおよぼすようになりました。睡眠に関連する保育・勤労・医療・生活習慣などの諸問題に的確に対処できなければ、国民的・国家的規模でいちじるしい損失をもたらすかもしれないからですね。――<「学術文庫版まえがき」より>
※本書の原本は、1994年に筑摩書房より刊行されました。
講談社学術文庫に収録するにあたり、適宜章末に補遺と文献案内を追加しました。

リチャード・ローティ=ポストモダンの魔術師
講談社学術文庫
分析哲学の学統から頭角を現しながら、ハイデガーを愛好し、「文化系左翼」批判とリベラリズムの擁護を謳う、「稀代のソフィスト」にしてアイロニスト。この知的巨人は、いかなる理路で「基礎」としての哲学の終焉を告げたのか。変幻自在で挑発的な言辞を丹念に腑分けし、その背後にある思考を体系的に読み解く。ローティの真価は、ここに明らかとなる! (講談社学術文庫)
真理は、正義は、存在は、リベラルは、いかに語りうるか――
ローティを体系的に読む本邦最良の一冊!
分析哲学の学統から頭角を現しながら、ハイデガーを愛好し、「文化系左翼」批判とリベラリズムの擁護を謳う、「稀代のソフィスト」にしてアイロニスト。この知的巨人は、いかなる理路で「基礎」としての哲学の終焉を告げたのか。変幻自在で挑発的な言辞を丹念に腑分けし、その背後にある思考を体系的に読み解く。ローティの真価は、ここに明らかとなる!
R・ローティという人物を一言で言い表すとすれば、それは現代の、そして稀代のソフィストということになろう。これは単なるメタファーではない。
これほどまでにレトリックの重要性を教えてくれた人物を私は知らない。もしもレトリックというものが、人々の心に訴えかける有効な力であるとすれば、もはや我々は、それを単なるソフィスト的軽薄さとして切り捨てることはできまい。ローティにおいて、それはまさしく、その内実を構成しているのである。――<本書より>
※本書の原本は、1999年に春秋社より刊行されました。