講談社学術文庫作品一覧

新装版 日本国憲法
講談社学術文庫
戦後日本を理念的に照らしつづけた〈憲法〉。
それは「人類普遍の原理」「崇高な理想と目的」を掲げながら、一貫して最大の争点でもありつづけた。
日本国憲法に、大日本帝国憲法、教育基本法、児童憲章、英訳日本国憲法、日米安全保障条約の全文を収録した新装版。
我々はどこへ向かおうとしているのか。
読んでから考えたい、語るために読みたい〈憲法〉。

〈玉砕〉の軍隊、〈生還〉の軍隊――日米兵士が見た太平洋戦争
講談社学術文庫
「降伏は名誉」とする米兵と、捕虜となることを恥、自決を名誉と考える日本兵。「バンザイ突撃」は、「9時から5時まで戦う」米兵の目には自殺行為にしか映らなかった。究極の文化衝突の場、戦場で両軍兵士は何を目にし、互いの認識をどう変えたのか――。日米元兵士への緻密なインタビュー調査を通して、「兵士」の誕生から戦地における彼らの思想と行動までを比較文化的観点から探究。「戦闘の社会学」が解明する、戦場の真実。
日米の元兵士へのインタビュー調査を通して比較文化的観点から考察する兵士の思想と行動
-究極の文化衝突-=戦場で日米の兵士は何を見たか
「降伏は名誉」の米兵。捕虜となることは不名誉、自決を名誉と考える日本兵。「バンザイ突撃」は「九時から五時まで戦う」米兵には自殺行為だった。そして、究極の文化衝突としての戦場で両者は互いの認識をどう変えたのか。両国の元兵士への緻密なインタビュー調査を通し、戦地の兵士の思想と行動を比較文化的観点から探究した戦闘の社会学、その成果。
たとえどのような文化的背景を持とうとも、兵士たちが戦闘を続けるかぎり、この差し迫った「死」の問題から逃れることはできない。両軍兵士は、戦場における「生と死の問題」をどのようにとらえ、この問題にいかに対処してきたのだろうか。そこには、なにか文化的な違いが見られるのだろうか。それとも、文化的な違いを超えた「人間としての兵士」の行動パターンにはなんらかの共通点がみいだされるのだろうか。これらの素朴な疑問が本書を貫く根源的な問題意識である。──本書「はしがき」より
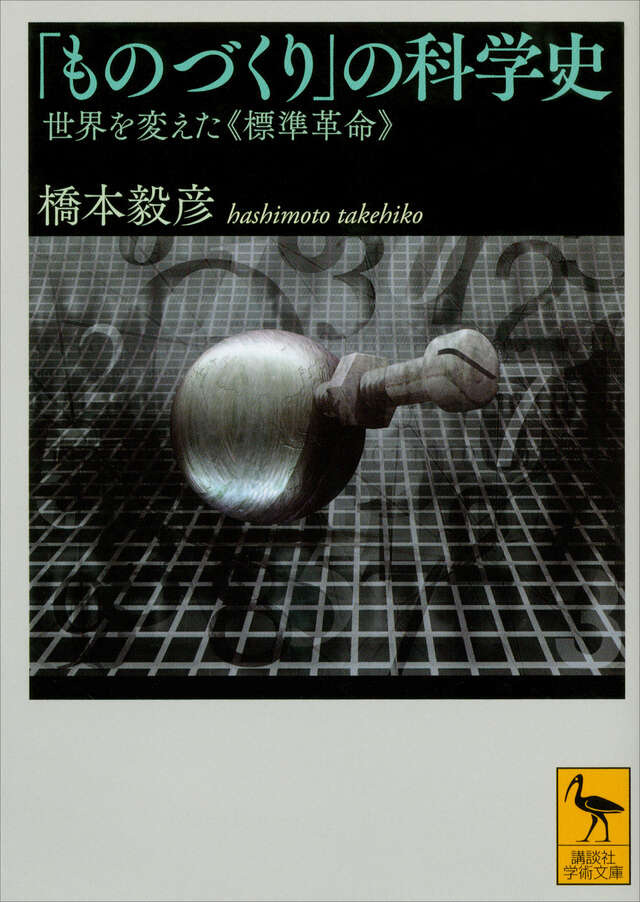
「ものづくり」の科学史 世界を変えた《標準革命》
講談社学術文庫
フランスのオノレ・ブランという技術者による「互換性部品」に始まる近代の標準革命。アメリカでその技術は、困難を乗り越え、「アメリカ式製造方式」として確立された。さらにテイラーによる作業の標準化は、アメリカを製造業大国にする。公的機関が標準を決めるデジューレから市場での占有によるデファクトの時代へ。「標準」をキーワードに、製造の現場のドラマと国家、企業、市場の関係、そして背後に潜む思想を探ります。
3世紀にわたる人類最大のプロジェクト=スタンダード・テクノロジーの物語
「標準」を制するものが、「世界」を制する!
「互換性」は技術者の壮絶な工夫と苦労の結晶であり、企業と権力の構想と交渉によって誕生した。標準技術の形成と受容過程の、驚くべきドラマの数々。標準化=製造の革命は、旧体制を破壊し、軋轢も生んだ。A4、飛行機の安全基準、コンテナ、キーボード……。今なお世界を覆い尽くさんと進む未完の巨大プロジェクトの意味と歴史と未来を探究する。
※本書の原本『-標準-の哲学 スタンダード・テクノロジーの三〇〇年』は、2002年に小社より刊行されました。文庫化にあたり、第六章・エピローグを大幅に改稿し、第七章を追加しました。

明治維新の遺産
講談社学術文庫
幕末、明治、昭和、そして……。近代以降の日本の歴史はひとつの対立軸を中心にかたちづくられてきた。本書は徳川官僚制とそのイデオロギー的基盤から説き起こし、明治維新、昭和維新、そして敗戦後まで「官僚的合理主義」と「維新主義」の相剋として描き出す。現れては消える〈維新〉はわれわれに何をもたらすのか? 歴史解釈は未来を見据える。(講談社学術文庫)
幕末、明治、昭和、そして……。
日本近代史を貫く、-維新-運動の原理。
幕末、明治、昭和、そして……。近代以降の日本の歴史はひとつの対立軸を中心にかたちづくられてきた。本書は徳川官僚制とそのイデオロギー的基盤から説き起こし、明治維新、昭和維新、そして敗戦後まで「官僚的合理主義」と「維新主義」の相剋として描き出す。現れては消える-維新-はわれわれに何をもたらすのか? 歴史解釈は未来を見据える。
近代日本の歴史は勝者─敗者の観点から見るよりも、大久保に典型的に見られる官僚合理主義的価値観と西郷に代表される理想主義的価値観の両極端の相互作用という観点から見た方が、よりよく理解しうるように思われる。この両極の原型の間に、日本人の理論的忠誠がつくられたりこわされたりする素材である文化的個性の力動的な現実が、度合いを異にし複雑に混じりあって存在しているのである。(本書より)
※本書の原本は、1979年9月に中央公論社より刊行されました。

ヨーガの哲学
講談社学術文庫
「俗なるもの」の否定に「聖なるもの」は顕現し、「聖なるもの」の力によって「俗なるもの」は「聖化」される──。世俗を捨て、「精神の至福」をもとめる宗教実践・ヨーガ。身体のエネルギーセンター・チャクラ、調気法、坐法、マンダラを前に瞑想する観想法など、仏教学の泰斗が自らの体験をとおして具体的にその哲学をときあかす、必読のヨーガ入門。
世俗を捨て「精神の至福」を求める宗教実践は「根源的統一への帰一」へと人々を導く
ヨーガはただ、道をしめして命ずるのみ──
「古き衣をぬぎすてて、眼下の海に身を投げよ」
「俗なるもの」の否定に「聖なるもの」は顕現し、「聖なるもの」の力によって「俗なるもの」は「聖化」される──。世俗を捨て、「精神の至福」をもとめる宗教実践・ヨーガ。身体のエネルギーセンター・チャクラ、調気法、坐法、マンダラを前に瞑想する観想法など、仏教学の泰斗が自らの体験をとおして具体的にその哲学をときあかす、必読のヨーガ入門。
カトマンドゥ盆地の周辺には、かつての大行者たちがヨーガをしたと伝えられる石窟が残っている。彼らはわずかな弟子などとの接触をのぞけば、ほとんどひとりで瞑想のなかに住んだといわれる。月の光のない夜などはまったくのくらやみであったろう。しかし、彼らは思考の混乱・退行などの兆しを見せなかった。これは、まさにヨーガのもつ力のゆえである。ヨーガ行者はこの生体そのもののなかから、外からの刺激によってではなく、統覚の自律性を完成させるのだ。──本書「第六章」より抜粋

川の文化
講談社学術文庫
日本中の子供たちが親から聞かされる叱責の言葉――お前は川の橋の下から拾われてきた――が、意味するところは何か? 民俗学者による「川と日本人」をめぐる調査と考察。島国日本は、「海の国」であると同時に、豊かな「川の国」でもある。大小の河川は、上流から河口まで、多彩な風景と、文化・風土をかたちづくってきた。舟運と川船、川の狩猟、渡しと橋、年中行事、信仰と伝承など、豊富な事例で語りつくす。
島国日本は豊かな「川の国」でもある。かつて柳田國男は、「川は、日本の天然のもっとも日本的なるものであった。」と述べている。
大小の河川は上流から河口まで、大地を刻んで多彩な風景と文化を育んできた。舟運の歴史と川船の種類、川での狩猟、渡しと橋、年中行事と信仰など、民俗学者が豊富な事例で語りつくす。日本中の子どもたちが親から聞かされてきた「お前は川から拾われてきたんだぞ」という言葉が意味するところとは?
1981年、日本書籍より刊行された同名書籍の文庫化。

タブーの漢字学
講談社学術文庫
はばかりながら読む漢字の文化史!
「且」は男性、「也」は女性の何を表す……?
性、死、名前、トイレなどのタブーをめぐる、ゆたかで隠微な漢字の世界。
中国科学院の院長までつとめた郭沫若の「士」=男根説。性器はやはり「陰」と「陽」で表される。「死」という漢字を避ける習慣。「トイレにいく」が「解手」となるわけ。皇帝やその祖先の実名を厳重に避ける「避諱」とは──。日常の話から歴史や逸話まで、幅広く、豊富な話題を紹介しながら、漢字とタブーの関係を鋭く、面白くつづった会心の名篇。
男女の性行為とか排泄、あるいは女性の生理などに関係することがらは、これまでは「隠しごと」とされ、それを表すことばや文字は社会の表層からはなかなか見えなかった。しかしそんな「隠しごと」も、人間の暮らしと社会の様相を示すものであることにはまったく変わりなく、実際に「隠しごと」に関してのソフトもハードも、時代とともに着実に進化を遂げてきた。そして文字も、その変化発展に完全に対応してきたのである。──本書「あとがき」より

日本の職人
講談社学術文庫
青銅鏡、墨、刺繍、タタラ製鉄、漆、べっ甲細工、扇、鯉のぼり、蒔絵(まきえ)、焼き物、竹細工……。二十世紀後半、科学技術史家である著者は、職人の仕事場を訪ね歩き、伝統の技とその現状を報告する。現代へとつながる、中世~近代の日本における職人の変遷を概観し、苦しくも誇り高き手仕事を再評価する。職人の盛衰から日本文化を読み解く試みでもある。
この風土の繊細で闊達な手仕事の魅力を探る!
現場ルポと歴史の両面から、伝統技術と日本文化を問い直す
青銅鏡、墨、刺繍、タタラ製鉄、漆、べっ甲細工、扇、鯉のぼり、蒔絵(まきえ)、焼き物、竹細工……。二十世紀後半、科学技術史家である著者は、職人の仕事場を訪ね歩き、伝統の技とその現状を報告する。現代へとつながる、中世~近代の日本における職人の変遷を概観し、苦しくも誇り高き手仕事を再評価する。職人の盛衰から日本文化を読み解く試みでもある。
とりちらされた竹屑の間には、とぎすまされてつめたく鋼鉄の肌を光らせる刃物が見える。……さまざまな形をした工具もある。そのどれもが長い間の手ずれで光っている。それらの形ひとつにも職人たちの独自の考案と工夫のあとがある。……それをまるで自分の手足のように自由自在に取り扱って、……物をつくり出す。そのひとつひとつに彼らの人間的なエネルギーがじっくりと注ぎこまれる。……すべてに充ちているのはほのかな温かさである。こうした生産活動をつづける人たち、それが職人である。日本の職人たちである。 (「プロローグ」より)
※本書の原本は、1976年に角川書店より刊行されました。

中世ヨーロッパの家族
講談社学術文庫
ヨーロッパ中世史の新たな実像を描いて定評のあるギース夫妻による「ある家族の歴史」。本作では、イングランド北部、ノーフォークの紳士階級・パストン家に残された千通を超す書簡から、15世紀の社会と一族の生活を復元していく。家族の健康や家政、商取引きと訴訟、子女の結婚問題などを虚飾のない文章で記した手紙は、英仏百年戦争の末期からバラ戦争にいたる乱世を懸命に生き抜いた人々の姿を今に伝え、圧倒的な生命力に満ちている。巻末解説に作家の佐藤賢一氏。
2001年に朝日新聞社より刊行された『中世の家族』を、文庫化にあたり改題。 原著は、 A Medieval Family by Frances & Joseph Gies(Harper Perennial, 1998)

関西弁講義
講談社学術文庫
関西人はなぜ声が大きいのか? 声が大きいのではなく声が高いのだ。二千万話者を擁する関西弁は発音の高低を駆使してこそ成り立つ言語なのだ――。強弱アクセントではなく高低のアクセントを導入することでその発音法則を見出し、文法構造によるイントネーションの変化など、標準語とは異なる関西弁独自の体系を解明する。読んで話せる関西弁教科書。めっちゃ科学的。(講談社学術文庫)
関西人はなぜ声が大きいのか? 声が大きいのではなく声が高いのだ。二千万話者を擁する関西弁は発音の高低を駆使してこそ成り立つ言語なのだ――。強弱アクセントではなく高低のアクセントを導入することでその発音法則を見出し、文法構造によるイントネーションの変化など、標準語とは異なる関西弁独自の体系を解明する。読んで話せる関西弁教科書。めっちゃ科学的。

東京裁判への道
講談社学術文庫
「A級戦犯」被告28人はいかにして選ばれたのか? 昭和天皇「不訴追」の背景は? 無視された証言と証拠、近衛の自殺、木戸の大弁明――アメリカに眠る膨大な尋問調書から明かされる真実。極東国際軍事裁判をめぐる歴史ドラマが、ここに開幕する!
第一人者による東京裁判研究の金字塔!
「A級戦犯」被告28人はいかにして選ばれたか
「天皇不訴追」決定の真実、無視された証言と証拠、近衛の自殺、木戸の大弁明──アメリカに眠る膨大な尋問調書から明かされる真実。極東国際軍事裁判をめぐる歴史ドラマが、ここに開幕する!
「A級戦犯」28人はいかにして選ばれたのか。天皇不訴追の決定プロセスの真実とは。釈放されていく「大物」たち、免責された毒ガス・細菌戦。冷戦が本格化してゆく中で、無視された証言・証拠……アメリカに残されていた膨大な尋問調書を丹念に読み解き、語られざる歴史の実相と当事者達の人間ドラマを描き出す。東京裁判はこうして始められた!

日本その日その日
講談社学術文庫
近代に染まる寸前の日本を科学者の目が見つめていた――
菓子屋の看板、人力車、屋敷の屋根瓦、和服の装い、そして、穏やかに暮らす人々。
大森貝塚の発見で知られるモース、その鋭敏な眼差し惹きつけられたのは、明治最初期日本の何気ない日常の営みだった。
東京大学教授として滞在する2年間にのこした、膨大なスケッチと日記には、卓越した科学者ならではの観察眼と、異文化を楽しむ喜びが満ちている。
彼が日本で出喰わした愉快な経験の数と新奇さは、ジャーナリストも汗をかくほどのものだ。
人通りの町を一列縦隊で勢よく人力車を走らせると、一秒ごとに新しい光景、新しい物音、新しい香り……
明治十年代のまだ近代に出会ったばかりの列島の生活を、モースは驚きと敬意をもって見つめていた。
当時の生活文化を記録した重要資料であり、なおかつ読んで見て楽しめる明治日本見聞記。(解説・牧野陽子)
※本書の原本は1939年に創元社より刊行された抄訳本です。

名将言行録 現代語訳
講談社学術文庫
幕末の館林藩士・岡谷繁実が、十六年もの歳月をかけて完成させた武将たちの逸話集『名将言行録』。千二百をこえる厖大(ぼうだい)な諸書を渉猟して編纂されたその内容は、戦国時代の武将から江戸時代中期の大名まで、数多の武士たちの言行を詳細に描き、彼らの人物像と叡知を活写する。本書は同書から戦国期の武将二十二人を選び、平易な文章で完全現代語訳する。
戦国武将たちの叡知と人物像を語る逸話集
「人は堀 人は石垣 人は城 情けは味方 怨は大敵」
これはまことのことだ──伊達政宗
幕末の館林藩士・岡谷繁実が、十六年もの歳月をかけて完成させた武将たちの逸話集『名将言行録』。千二百をこえる厖大(ぼうだい)な諸書を渉猟して編纂されたその内容は、戦国時代の武将から江戸時代中期の大名まで、数多の武士たちの言行を詳細に描き、彼らの人物像と叡知を活写する。本書は同書から戦国期の武将二十二人を選び、平易な文章で完全現代語訳する。
●本書でとりあげる戦国武将●
北条長氏(早雲)/太田資長(道灌)/山中幸盛(鹿之助)/毛利元就/武田晴信(信玄)/上杉輝虎(謙信)/直江兼続/織田信長/柴田勝家/池田輝政/蒲生氏郷/島津義久/伊達政宗/戸次鑑連/高橋鎮種/黒田孝高(如水)/立花宗茂/豊臣秀吉/福島正則/加藤清正/真田幸村/徳川家康

道徳感情論
講談社学術文庫
アダム・スミスの二大著作の一冊が『道徳感情論』(1759)です。本書こそが主著で、『国富論』はその副産物だったのです。個人とは「共感」能力を持ち、様々な「激情」を持っています。利己的であったり、社会的であったり、憤ったり、感謝したりします。スミスはこういった個人の心に「義務」「道徳」を確立して、新しい社会と人間のあり方を探りました。近代社会の原理を知るための必読書が読み易い新訳で登場!
『国富論』より重要なスミスの名著が、読みやすい訳文で登場!
調和ある社会の原動力とは何か?
鋭い観察眼・深い洞察力と圧倒的な例証により、個人の心理と社会の関係を解明した傑作!
調和ある社会構成の根幹に、個人の自己愛・自己利益の追求に加えて、「共感」を据えた。そして社会では、適合的な行為が是認され、非適合的な行為が否認されることにより、規則が誕生する。人間が社会的に是認された行為規範を遵守する努力によって、徳のある社会が実現するのだ。最高の啓蒙思想家が、生涯をかけて著した不朽の社会論は今なお光を放つ。
道徳の原動力について論じる場合、考察されるべき問題は二つある。第一に、徳はどこに存在するのか? すなわち、優れていて、賞賛に値する特徴となる、気分の調子や行為の傾向とは、いったいどのようなものか? そして第二に、それが何であろうと、このような特徴が我々に推奨されるのは、心のなかにあるどのような能力や機能によってであるか? 言い換えるなら、心が、ある傾向の行為を他のものよりも好み、一方を正しいと呼び、他方を間違いと呼ぶことになってしまうのはどうしてであり、またどのような手段によるのか?(本文[VII. i.2]より)

パラダイムと科学革命の歴史
講談社学術文庫
科学史の第一人者による「学問の歴史」。科学革命で生まれた新たなパラダイムが学問的伝統を形成していく過程を解明する。古代以来の東西学統の比較から、学会誌などのメディアの発明、職業的科学者の誕生、現代のデジタル化まで、社会的現象としての科学と科学者集団を分析。『歴史としての学問』(1974年、中央公論社刊)を学術文庫化にあたって改題し、新たに「学問のデジタル化・グローバル化」を論じた補章を加筆。
トマス・クーンの「パラダイム論」を日本に紹介した科学史の第一人者による「学問の歴史」。科学革命で生まれた新たなパラダイムが学問的伝統を形成していく過程を解明する。「記録的学問」と「論争的学問」という古代以来の東西学統の比較から、学会誌などのメディアの発明、職業的科学者の誕生、現代の巨大科学とデジタル化まで、社会的現象としての科学と科学者集団を分析。
『歴史としての学問』(1974年、中央公論社刊)を学術文庫化にあたって改題し、新たに「学問のデジタル化・グローバル化」を論じた補章を加筆。

欧化と国粋――明治新世代と日本のかたち
講談社学術文庫
西欧文明を前に、たじろぐ明治新世代。
初めて西洋型教育を受けた彼らは、この国のかたちがどうあるべきか論争した。
政府の欧化政策に反発しつつも下からの欧化主義を唱えた徳富蘇峰。
それに反発し国粋保存を訴える志賀重昂、文化的アイデンティティ確立を模索した陸羯南、三宅雪嶺ら。
日本人は何を誇ればいいのか?
若きナショナリズムは身悶えしていた。

鉄炮伝来――兵器が語る近世の誕生
講談社学術文庫
新たな兵器は、いかに伝わり、普及したのか。「種子島に漂着したポルトガル人が伝えた」という常識を覆し、武器から戦国史を見直す。

王陽明「伝習録」を読む
講談社学術文庫
中国・明代の儒学者、王陽明。その当時、新儒教として学術思想界の主座にあった朱子学の論理構造を批判的に継承した彼の実践的儒学は、陽明学として結実する。近世以降の中国のみならず、わが国でも大塩中斎や吉田松陰、西郷隆盛ら、変革者たちの理論的背景となった思想とは何か。陽明学の最重要書籍を原テキストにしたがって読み解き、その精髄に迫る。

世界の食べもの――食の文化地理
講談社学術文庫
美味いゾ!
日本、朝鮮、中国、東南アジア諸国、オセアニア、マグレブ……。
それぞれの風土や歴史と食生活の関連を探求し、日本の食事文化を位置づけたうえで、
米・酒・麺・茶・コーヒーなど食べものから見た世界地図を描き出す。
各地を探検し〈食文化〉研究を確立したパイオニアの手による入門書にして冒険の書。
舌は世界を駆けめぐる。美味いものに国境なし。
※本書の原本『食の文化地理』は、1995年に朝日新聞社より刊行されました。
【本書の内容】
序章 舌のフィールドワーク
【1】 諸民族の食事
第1章 朝鮮半島の食
第2章 世界における中国の食文化
第3章 東南アジアの食事文化
・フィリピンの食生活
・シンガポールのニョニャ料理
・マレーシアの食生活
・インドネシアの食生活
・モルッカ諸島の食事
第4章 オセアニア――太平洋にひろがる食文化
第5章 マグレブの料理
【2】 日本の食事
第6章 米――聖なる食べ物
第7章 日本の食事文化――その伝統と変容
第8章 現代の食生活
第9章 日本人とエスニック料理
【3】 食べ物からみた世界
第10章 世界の米料理
第11章 すしの履歴書
第12章 麺の歴史
第13章 料理における野菜の位置
第14章 世界の酒――伝統的な酒の類型
第15章 茶とコーヒーの文明
第16章 うま味の文化
あとがき
初出一覧
文庫版あとがき

中世のなかに生まれた近世
講談社学術文庫
後北条、武田、今川、上杉など東国の大名が発給した文書は、はんこを捺した「印判状型」。一方、毛利や大友、島津ら西国の大名は「非印判状型」。前者は官僚制的で強力な支配、後者は人格的でゆるやかな支配だった。戦国大名たちの膨大な文書をあざやかに分析し、そのうえで信長、秀吉、家康という天下人の支配の本質にせまる、刺激的な歴史学、登場!
判物(サイン)から印判状(はんこ)へ
人格的支配から官僚制的支配へ
諸大名が発給した膨大な文書の解析から、東国と西国
の支配の違いを明らかにし、天下一統の内実に迫った、スリリングな歴史学!
後北条、武田、今川、上杉など東国の大名が発給した文書は、はんこを捺した「印判状型」。一方、毛利や大友、島津ら西国の大名は「非印判状型」。前者は官僚制的で強力な支配、後者は人格的でゆるやかな支配だった。戦国大名たちの膨大な文書をあざやかに分析し、そのうえで信長、秀吉、家康という天下人の支配の本質にせまる、刺激的な歴史学、登場!
この本で私は、ひとつの旅をしてみようと思っています。中世の末、各地に割拠してとりどりの個性を競いあった魅力あふれる大名たち、そして彼らのなかから頭角をあらわして中原に覇を唱えた天下人たちを、かたはしから訪問してみようという、欲張りな旅です。(略)ここから、彼らが遺した文書をせっせせっせと蒐集し、それをもとに試行錯誤をくりかえしながら特徴を析出していくという、たいへんだけれど心楽しい作業の日々が始まりました。はたしてその成果やいかに。中世から近世へと時代が大きくうつり変っていく、その躍動の熱気を首尾よくつかまえることができるでしょうか。――<本書「序」より>
※本書の原本は、1991年、吉川弘文館より刊行されました。