新刊書籍
レーベルで絞り込む :
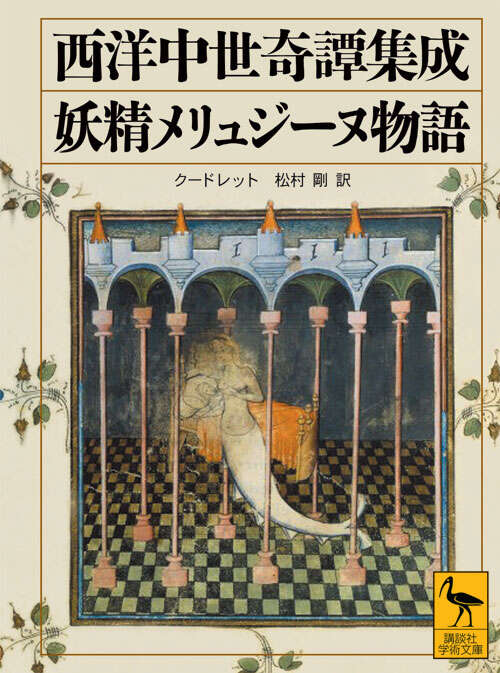
2014.11.28発売
西洋中世奇譚集成 妖精メリュジーヌ物語
講談社学術文庫
15世紀、フランスのポワトゥー地方。領主の命で、書籍商クードレットは家門の歴史を物語る。伯父を殺したレイモンダンは、森で出会った絶世の美女メリュジーヌと結婚。開墾、城塞、街、武勲溢れる子供たち……。しかし幸福な繁栄は、破棄された約束から暗転する。地方貴族の数奇な運命を描く一大叙事詩。(講談社学術文庫)
一地方の成立を語る。民話であり神話でもある半身蛇のメリュジーヌは、騎士に領地、城塞、子供、そして繁栄を与えた。物語の背景には、中世末の経済的発展と文化の浸透がある。ルゴフ、ラデュリ論文も併録。

2014.11.28発売
武士道
講談社学術文庫
“彼は「侍(さむらい)」である”という表現が今日でもしばしば使われる。では、侍とはいかなる精神構造・姿勢を指すのか――この問いから本書は書き起こされる。主従とは、死とは、名と恥とは……。『葉隠』『甲陽軍鑑』『武道初心集』『山鹿語類』など、武士道にかかわるテキストを広く渉猟し、読み解き、日本人の死生観を明らかにした、日本思想史研究の名作。(講談社学術文庫)
死を覚悟し、名を重んじ、我に勝つ
苛烈な武士の精神に日本人の思想のバックボーンを
見通した名著!
“彼は「侍(さむらい)」である”という表現が今日でもしばしば使われる。では、侍とはいかなる精神構造・姿勢を指すのか――この問いから本書は書き起こされる。主従とは、死とは、名と恥とは……。『葉隠』『甲陽軍鑑』『武道初心集』『山鹿語類』など、武士道にかかわるテキストを広く渉猟し、読み解き、日本人の死生観を明らかにした、日本思想史研究の名作。
「武士道といふは、死ぬ事と見付けたり」(『葉隠』)
人間というものは、何らかの絶対永遠なるものがなければ、生きて行けない。まして、死の覚悟などをきめることは出来ない。武士一般には来世が存在しなかったから、彼らが何を究極的なよりどころとしていたかが考えられなければなるまい。私はそれを、地上のものでありつつ地上をこえた人倫、名のはこばれる場としての武士社会の無窮性が、『葉隠』武士道を支える究極のものであったと思う。――<本書より>
※本書の原本は、1968年、塙書房より刊行されました。
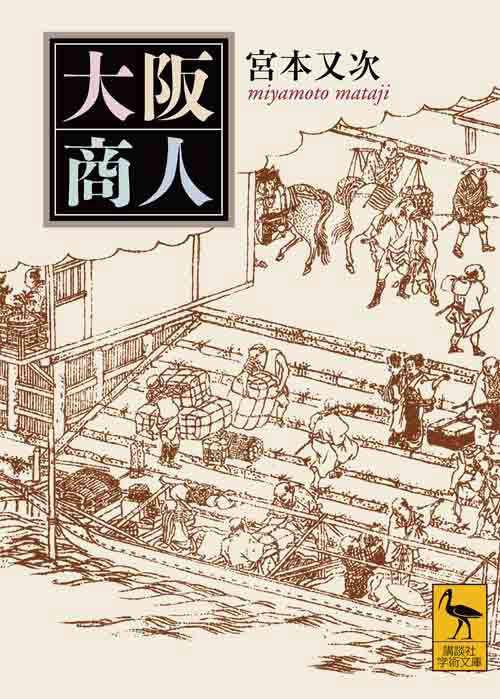
2014.11.28発売
大阪商人
講談社学術文庫
密貿易を組織した毛剃九右衛門〔けづり八右衛門〕、独占的地位で巨利をあげた糸割符商人。江戸城出入りの特権商人尼崎屋は新田開発をし、寒天輸出を一手に担う。廻船により各地物産は、荷受問屋を通して、流通する。秘伝南蛮吹の精銅技術をもとに鉱山開発までした住友家。「天下の町人」となった呉服商。江戸の経済を牛耳っていた商都大阪の活況を描く。(講談社学術文庫)
天下の台所を支えた商人の類型と実相を描く。貿易商人・天竺徳衛門、呉服商・下村彦右衛門から江戸の実業家・住友家まで。大阪を舞台に活躍した代表的商人とその同業者、社会・風俗・経済の実相を活写する。

2014.11.28発売
沈黙するソシュール
講談社学術文庫
ジュネーヴ大学就任講演、形態論、「書物」の草稿、ホイットニー追悼などソシュールの重要なテクストを訳出し、それに対する繊細かつ本質的なノートを付す。その往還自体がひとつのテクストとなって、本書でわれわれは、いつしかソシュールの思想の生の姿に立ち会うこととなる。あえて俗流解釈を排し、言語=ラングそのものを問い続けた記念碑的力作。(講談社学術文庫)
日本のソシュール研究に画期をなした快著。現代思想の扉を開いた言語学者として評価されるソシュールだが、その思想の本質とは何か。通念となった解釈をカッコに入れ、本来の魅力をあぶり出す野心作。

2014.11.28発売
酒場の文化史
講談社学術文庫
石器時代の洞窟にはじまる「ドリンカーの楽園」はどう変化してきたのか? 宿屋(タヴァン)、イン、パブ、キャバレー、カフェ、ギャンゲット、ジャズ・クラブ……。19世紀から20世紀にかけて起こった酒場の革命とは? ギリシア神話、チョーサー、シェイクスピア、ディケンズ、バルザック、シムノン……。同時代の小説をも資料として読み込み、人間臭い特殊空間の変遷を活写する。(講談社学術文庫)
ドリンカーの楽園はどう進化してきたのか? きわめて人間臭い特殊空間=酒場の起源を石器時代の洞窟に求め、その変遷を描く。チョーサーの酒場、バルザックの酒場……。時代精神の鏡としての酒場を読む。
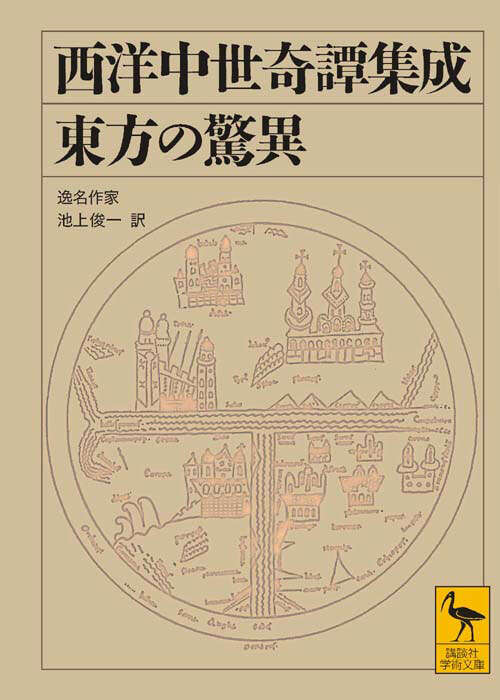
2014.11.28発売
西洋中世奇譚集成 東方の驚異
講談社学術文庫
謎のキリスト教王国を支配する「インド」の王中の王ヨハネ=プレスター・ジョンから西方の皇帝宛の書簡と、東方大遠征の途次にアレクサンドロス大王がアリストテレスに送った手紙。そこに描かれる乳と蜜の流れる東方の楽園には、黄金と象牙と宝石が溢れる壮麗な王宮が煌めく。一方で鰐皮の蟹、犬頭人など奇怪な動植物や人種が跋扈する。東方幻想に中世人の想像界の深奥を読み解く。(講談社学術文庫)
乳と蜜の流れる東方の楽園に表れた異国趣味。「インド」の王中の王ヨハネの手紙とは何か? 豊富な宝物、奇怪な動植物や人種たち。暗黒の時代=中世の人々の想像界と心性に分け入る。本邦初訳出。

2014.11.28発売
世界史再入門 歴史のながれと日本の位置を見直す
講談社学術文庫
西欧や中国など特定の地域に偏った歴史では、人類史の筋は見えてこない。日本の歴史も世界の動きに取り込み、普遍的な視点でとらえようと試みることで、教科書や全集ではつかむことのできなかった世界史の全体像が浮かび上がる。生産力発展の過程と生存・自由・平等を求める人々の努力で形作られた人類史を辿り、現代世界の課題を見つめ直す好著。(講談社学術文庫)
壮大な世界の歴史の流れを1冊でつかむ
西欧や中国など特定の地域に偏った歴史では、人類史の筋は見えてこない。日本の歴史も世界の動きに取り込み、普遍的な視点でとらえようと試みることで、教科書や全集ではつかむことのできなかった世界史の全体像が浮かび上がる。生産力発展の過程と生存・自由・平等を求める人々の努力で形作られた人類史を辿り、現代世界の課題を見つめ直す好著。
新しい世界史を構成するためには、西ヨーロッパとかアジアとか特定の地域を中心に世界史をみるのではなく、地域や時代をこえた普遍的な価値理念を視点とする必要がある。そういう視点がなければおよそ体系的な歴史把握は不可能なのであり、そして体系的な歴史把握なしには、いま私たちが世界史のどのような時点にたち、これからどのような方向へすすもうとしているのかを知ることもできないであろう。――<本書より>
※本書の原本は、1991年地歴社より刊行されました。なお、文庫化にあたり、第8章を加筆しました。

2014.11.28発売
カフェと日本人
講談社現代新書
大正・昭和の「カフェー」とAKB48の類似点って? なぜ名古屋人は喫茶好き? 210年前にコーヒーを飲んだ「人気文化人」といえば? 100年以上営業している国内最古の喫茶店はどこ? 「音楽系喫茶」と「特殊喫茶」がたどった経緯とは? あなたにとって「カフェの存在」とは? 日本初の喫茶店から、欲望に応えてきた特殊喫茶、スタバ、いま話題の「サードウェーブ」までの変遷をたどった、日本のカフェ文化論。
大正・昭和の「カフェー」とAKB48の類似点って?
なぜ名古屋人は喫茶好き?
210年前にコーヒーを飲んだ「人気文化人」といえば?
100年以上続く国内最古の喫茶店はどこ?
「音楽系喫茶」と「特殊喫茶」がたどった経緯とは?
「カフェラテ」と「カフェオレ」の違いは?
あなたにとって「カフェの存在」とは?
--------------------------------------------------
日本初の喫茶店から、欲望に応えてきた特殊喫茶、スタバ、
いま話題の「サードウェーブ」までの変遷をたどった、日本のカフェ文化論。
--------------------------------------------------
【おもな内容】
第1章 カフェの誕生
「日本初」の喫茶店はビリヤードつき/100年以上続く現存最古の喫茶店/戦後に庶民化した「ハイカラな味」/「昭和の喫茶店」と「平成のカフェ」 ほか
第2章 日本独自の進化を遂げたカフェ・喫茶店
文壇バーならぬ文壇カフェ/「談話室滝沢」があった時代/菊池寛も愛用した文化人のサロン/名曲喫茶・シャンソン喫茶・ジャズ喫茶・歌声喫茶・ゴーゴー喫茶/美人喫茶からメイドカフェへ/西からやってきた「ノーパン喫茶」 ほか
第3章 なぜ名古屋人は喫茶好きなのか
始まりは尾張徳川藩の振興策/昭和30~40年代から続く人気店/「一宮モーニング」と「豊橋モーニング」 ほか
第4章 カフェ好きが集まる聖地
シングルオリジンの味わい深さを追求する「バルミュゼット」(仙台)/コロンビアに直営農園を持つ個人店「サザコーヒー」(ひたちなか)/川端康成や池波正太郎に愛された「アンジェラス」(浅草)/ジョン・レノンや柴田錬三郎も利用した「ミカドコーヒー」(軽井沢)/「ご近所のコーヒー店」から進化した「カフェタナカ」(名古屋)/日本有数の温泉地にある「ティールーム・二コル」と飲食専門誌『カフェ&レストラン』編集長が絶賛した「茶房 天井棧敷」(由布院)
第5章 「うちカフェ」という見えざる市場
定着した「コンビニコーヒー」は多様化へ/「無糖」や「健康」を打ち出す缶コーヒー/「サードウェーブは「昭和の喫茶店」そのものだ ほか
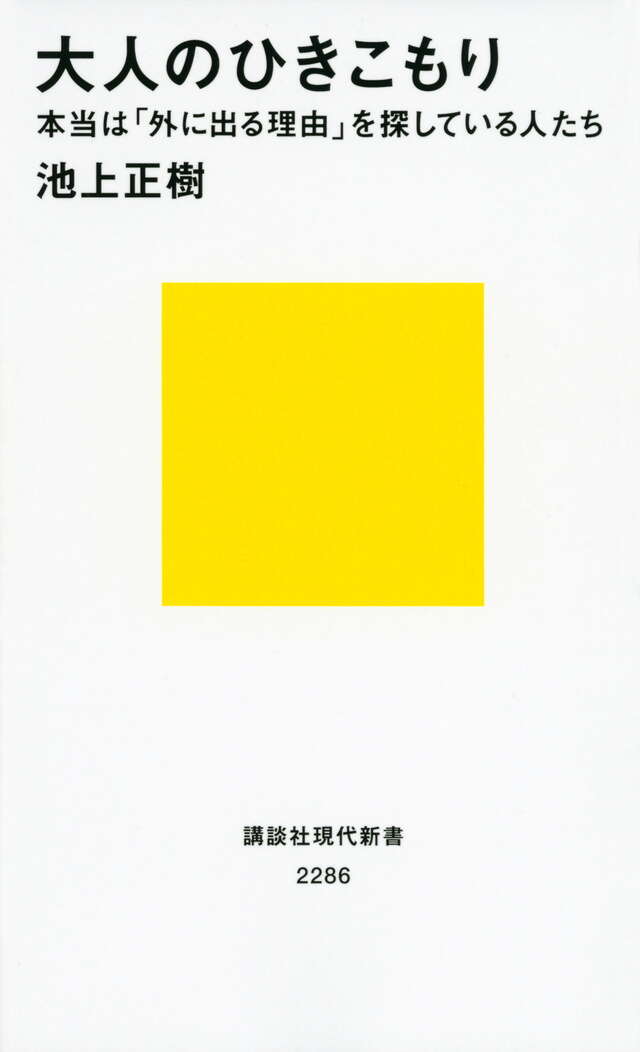
2014.11.28発売
大人のひきこもり 本当は「外に出る理由」を探している人たち
講談社現代新書
セーフティネットの狭間で置き去りにされた40歳以上は推定100万人! このままでは「老後破産」者が激増してしまう。ところが、どうすればいいのか、わからない。ハローワークを訪ねても同じ求人がグルグル回る「カラ求人」や、非現実的な「神様スペック」を求める企業が少なくない。いつの間にか時間が過ぎ去り、やがて家族ごと地域に埋没する―。ひきこもりが「長期化」「潜在化」する背景と、新たな取り組みを探った。
40歳以上のひきこもり+潜在群は推定100万人もいる。
このままでは、老後の蓄えがなく頼りの年金さえ受け取ることができず、
いずれ「老後破産」せざるをえない人が激増する可能性が高い。
どうすれば、日本に潜むこの大問題を解決できるのか。
答えのない問題が山積する時代。その答えをみんなが求めている。
しかし、専門家任せ、他人任せでは、なかなか解決できない。
支援の仕組みも、ミスマッチが起きている。
その答えを持っているのは、当事者たちである。
周囲の人たちは「上から目線」をやめて、
当事者たちの「声なき声」に、そっと耳を傾けるしかない。
-----------------------------------
親も子も、どうすればいいのか、誰に相談すればいいのかわからず、
気持ちばかりが焦ってしまう。
ハローワークを訪ねてみても、同じ求人がグルグル回る「カラ求人」や、
非現実的な「神様スペック」を求める企業が少なくない。
そうこうしているうちに、時間だけが過ぎていき、
やがて家族ごと地域の中に埋没してしまう――。
ひきこもりが「長期化」「潜在化」する背景と、
外に出るための新たな取り組みを探った。
-----------------------------------
【おもな内容】
第1章 ひきこもりにまつわる誤解と偏見を解く
1 データが物語る「高齢化」
2 ひきこもりの「潜在化」
3 ひきこもる女性たち「それぞれの理由」
第2章 ひきこもりの背景を探る
1 「立ち直り」を阻害するもの
2 「迷惑をかけたくない」という美徳
3 「家の恥」という意識
4 医学的見地からの原因分析
第3章 ひきこもる人々は「外に出る理由」を探している
1 訪問治療と「藤里方式」という新たな模索
2 親子の相互不信を解消させたフューチャーセッション
3 ひきこもり大学の開校
4 外に出るための第一歩――経済問題

2014.11.28発売
ヌードと愛国
講談社現代新書
一九〇〇年代から一九七〇年代に創られた、「日本」をまとった七体のヌードの謎を解く。推理のポイントは、時代と創り手の動機。時系列で並んだヌードから浮かび上がる歴史とは? 極上ミステリーのような謎解き方式で、ヌードから近現代史を読み解いていく。(講談社現代新書)
一九〇〇年代から一九七〇年代に創られた、「日本」をまとった七体のヌードの謎を解く。
推理のポイントは、時代と創り手の動機。
時系列で並んだヌードから浮かび上がる歴史とは?
極上ミステリーのような謎解き方式で、ヌードから近現代史を読み解いていく。
<本書の主な内容>
第一章 デッサン館の秘密
智恵子の「リアルすぎるヌード」伝説
第二章 Yの悲劇
「夢二式美人」はなぜ脱いだのか?
第三章 そして海女もいなくなった
日本宣伝映画に仕組まれたヌード
第四章 男には向かない?職業
満洲移民プロパガンダ映画と「乳房」
第五章 ミニスカどころじゃないポリス
占領と婦人警察官のヌード
第六章 智恵子少々
冷戦下の反米民族主義ヌード
第七章 資本の国のアリス
七〇年代パルコの「手ブラ」ポスター

2014.11.28発売
ふしぎな国道
講談社現代新書
空気のように、非常に身近でありながら、ほとんどその存在を意識されることのない「国道」。実は、この国道には不可思議なことが数多く存在する。・国道246号は存在するのに、国道60号や国道99号がない ・外環やアクアラインは高速道路なのに国道指定されている ・車が通れない商店街や階段が国道指定されている ・同じ国道なのに複数のルートがある 「国道マニア」として知られる著者が、こうした様々な謎を解き明かす
空気のように、非常に身近でありながら、ほとんどその存在を意識されることのない「国道」。その国道を真っ正面から扱った記念碑的作品。
実は、国道には不可思議なことが数多く存在する。
・国道246号は存在するのに、なぜ国道60号や国道99号はないのか?
・圏央道やアクアラインは高速道路なのになぜ国道指定されているのか?
・車が通れない商店街や階段がなぜ国道指定されるのか?
・道路すら走っていないフェリー航路が国道扱いされるのはなぜなのか?
など、いちいち挙げれば、数限りない。
国道をこよなく「国道マニア」として知られる佐藤健太郎氏が、こうした国道にまつわる、様々な謎を読み解くとともに、国道をこよなく愛する「国道マニア」たちのマニアックな生態を解説する。悪路を好んで走る「酷道マニア」。旧道を好んで走る「旧道マニア」。国道のありがたさを実感するために非国道のみを頑なに走行する「非国道走向マニア」、道路元標に異常な執着を示す「道路元標マニア」など、彼らのこだわりは相当なまでにマニアックである。抱腹絶倒の一冊

2014.11.28発売
教育の力
講談社現代新書
「ゆとり」か「詰め込み」か、「平等」か「競争」かなど、教育を巡る議論ほどに対立と齟齬が起こっている問題はないと言っても過言ではありません。しかしそれらは、論者の個人的な感想や思い込みによる独りよがりである場合がほとんどです。みんなが善意と熱意を持って教育を論じるのだけれど、ある種、独りよがりな「思い入れ」や「思い込み」が先走ってしまい、不毛な対立が至るところで引き起こされてしまっている……それが教育を巡る言説の現実ではないでしょうか。
しかし、この種の「対立」は冷静に考えてみれば錯覚であることが少なくありません。「ゆとり」か「詰め込み」かと二項対立で問われると、人はつい、どちらかの立場に与してしまいます。しかしそれは実は「問い方のマジック」に陥っているだけなのです。こういった偽の問題による不毛な対立を避けた、本当に意義のある教育を巡る議論が、いまこそ必要とされているのではないでしょうか。
こうした混乱に終止符を打つためには教育、とりわけ公教育はそもそも何のために必要なのかをまず定義しなければなりません。著者の考えによるなら、それは一人一人の子供が近代社会のルールを身につけその中でより自由に生きられるようになることということになります。個々の子供の自由の感度こそが社会に対する信頼の土台となり、みんなでよりよい社会を作るという真の意味での市民参加型の民主主義社会の礎となるのです。
では、どうすればそのような〈よい〉教育を作ることができるのでしょうか。著者の提案は様々ですが、その一つは、一方的に教師の授業を聞くという受け身の授業を改め、子供たちがある一つのテーマに関して自ら調べ、お互いに教え合う、授業の「プロジェクト化」です。日本ではあまりなじみのない方法ですが、すでにフィンランドやオランダなどでは成果を上げたメソッドです。競争よりも協力の方がそれぞれの子供の学力を上げることはすでに様々なデータで証明されています。
〈よい〉教育をつくるためには学校の物理的な「構造」はどうなっているのがいいのか? 〈よい〉教育を行うための教師の資質とは何か? そしてその実現のための〈よい〉社会とは?
本書は、義務教育を中心に、どのような教育が本当に〈よい〉と言えるのか、それはどのようにすれば実現できるのかを原理的に解明し、その上でその実現への筋道を具体的に示してゆくものです。

2014.11.28発売
弱者の居場所がない社会――貧困・格差と社会的包摂
講談社現代新書
貧困問題の新しい入門書。誰でも「居場所」「つながり」「役割」を持って生きていたいと願う。そのキーワードとなる「社会包摂」なしに、これからの社会保障政策は語れない。気鋭の研究者が、熱く熱く語る。(講談社現代新書)
貧困と格差社会についての新しい必読書。社会的排除とは「社会から追い出されること」。社会包摂は「社会に包み込むこと」。この新しい視点なしに今後の社会保障政策は語れない。気鋭の研究者が熱く語る。

2014.11.28発売
さようなら、私の本よ!
講談社文庫
国際的な作家である長江古義人と建築家の繁。この「おかしな二人組」は幼い頃から因縁があり、時を経て病院のベッドで再会を果たす。老人の愚行としてテロを画策する繁に巻き込まれていく古義人は、組織の青年達と精神の触れあいを深めながらも、「小さな老人(ゲロンチョン)」の家に軟禁されるのであった。二人の行き着く先には。
大江健三郎流テロリズムとは?
国際的な作家である古義人と建築家の繁。この「おかしな2人組」は幼い頃から因縁があり、時を経て病院のベッドで再会を果たす。老人の愚行としてテロを画策する繁に巻き込まれていく古義人は、組織の青年達と精神の触れあいを深めながらも、「小さな老人(ゲロンチョン)」の家に軟禁されるのであった。2人の行き着く先には。
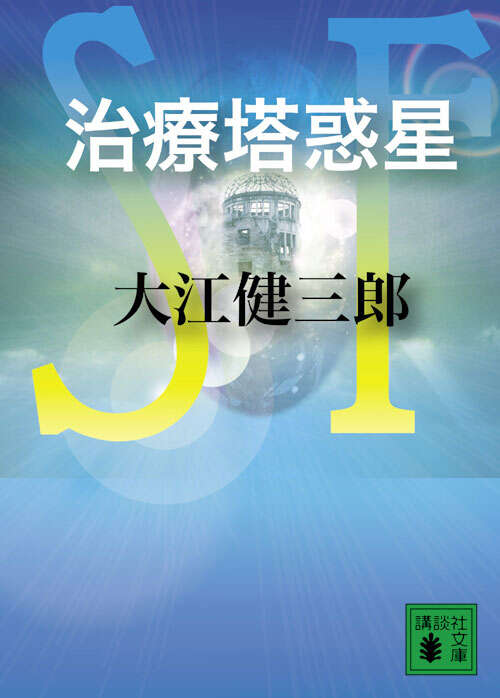
2014.11.28発売
治療塔惑星
講談社文庫
地球のさらなる荒廃『治療塔』に続くSF!地球に帰還した「選ばれた者」の朔ちゃんと、残留し「落ちこぼれ」となった私との間に子供・タイくんが生まれた。しかし、地球環境の悪化はさらに進む。世界宗教、宇宙ミドリ蟹、新しい地球、予戒、地球酸素1/4供給機構、向こう側の知性体――著者初のSFである前作『治療塔』をもしのぐ圧倒的スケールの作品。
地球のさらなる荒廃『治療塔』に続くSF!
地球に帰還した「選ばれた者」の朔ちゃんと、残留し「落ちこぼれ」となった私との間に子供・タイくんが生まれた。しかし、地球環境の悪化はさらに進む。世界宗教、宇宙ミドリ蟹、新しい地球、予戒、地球酸素1/4供給機構、向こう側の知性体――著者初のSFである前作『治療塔』をもしのぐ圧倒的スケールの作品。
※この作品は1991年11月、岩波書店より刊行されたものに、新たなあとがきを加えて文庫化したものです。
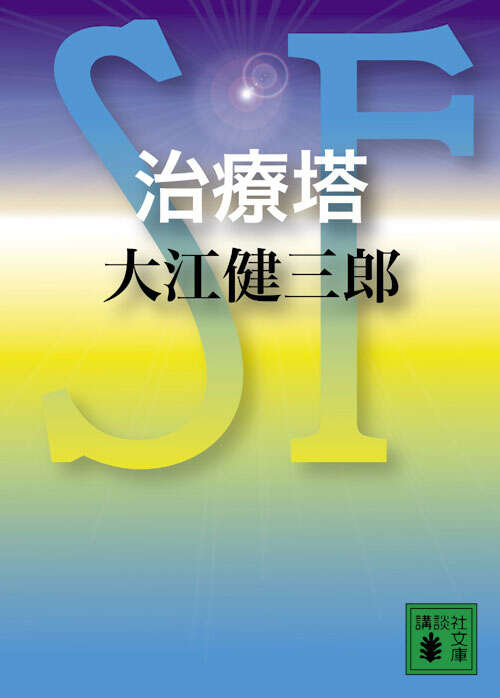
2014.11.28発売
治療塔
講談社文庫
「選ばれた者」たちが「新しい地球」に移住した。「残留者」たちは、資源が浪費され、汚染された地球で生き延びてゆく。出発から10年後、宇宙船団は帰還し、過酷な経験をしたはずの彼らは一様に若かった。その鍵を握る「治療塔」の存在と意味が、イェーツの詩を介して伝えられる。著者初の近未来SF小説を復刊。
「新しい地球」から移住者たちが帰還した
「選ばれた者」たちが「新しい地球」に移住した。「残留者」たちは、資源が浪費され、汚染された地球で生き延びてゆく。出発から10年後、宇宙船団は帰還し、過酷な経験をしたはずの彼らは一様に若かった。その鍵を握る「治療塔」の存在と意味が、イェーツの詩を介して伝えられる。著者初の近未来SF小説を復刊。
※この作品は、1995年5月岩波書店より刊行されたものに、新たなあとがきを加えて文庫化したものです。
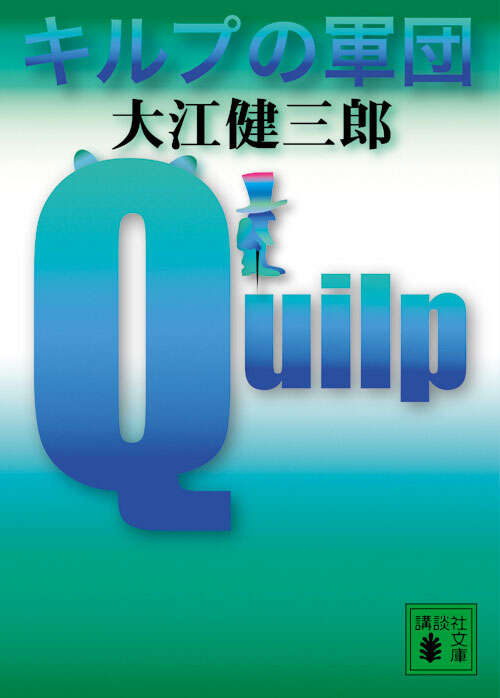
2014.11.28発売
キルプの軍団
講談社文庫
高校生の僕は、ディケンズの『骨董屋』を読み、作中のキルプにひかれる。そして、刑事の忠叔父さんと一緒に原文で読み進めるうちに、事件に巻き込まれてしまう。「罪のゆるし」「苦しい患いからの恢復(かいふく)」「癒し」を、書くことと読むことが結び合う新たな語り口で示した大江文学の結晶。
「罪のゆるし」「みずからの癒し」
若い人に語りかける小説
高校生の僕は、ディケンズの『骨董屋』を読み、作中のキルプにひかれる。そして、刑事の忠叔父さんと一緒に原文で読み進めるうちに、事件に巻き込まれてしまう。「罪のゆるし」「苦しい患いからの恢復(かいふく)」「癒し」を、書くことと読むことが結び合う新たな語り口で示した大江文学の結晶。若い読者に向けて、今復刊。
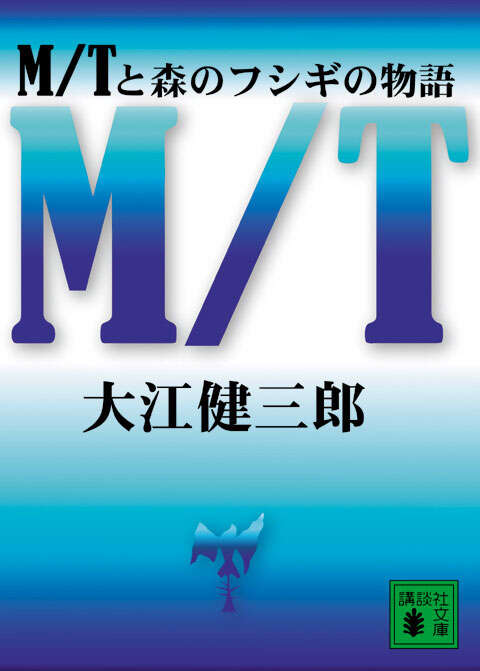
2014.11.28発売
M/Tと森のフシギの物語
講談社文庫
祖母から聞いた、四国の森の奥深くに伝わる「壊す人」と「オシコメ」の創造の物語を、MとTという記号を用いて書き記す。時の権力から独立した、1つのユートピアがつくり出される奇想天外の物語は、いつしか20世紀末の作家が生きる世界、われわれの時代に照応していく。海外で最も読まれている大江作品。
海外で最も読まれる作品を待望の文庫化
祖母から聞いた、四国の森の奥深くに伝わる「壊す人」と「オシコメ」の創造の物語を、MとTという記号を用いて書き記す。時の権力から独立した、1つのユートピアがつくり出される奇想天外の物語は、いつしか20世紀末の作家が生きる世界、われわれの時代に照応していく。海外で最も読まれている大江作品。
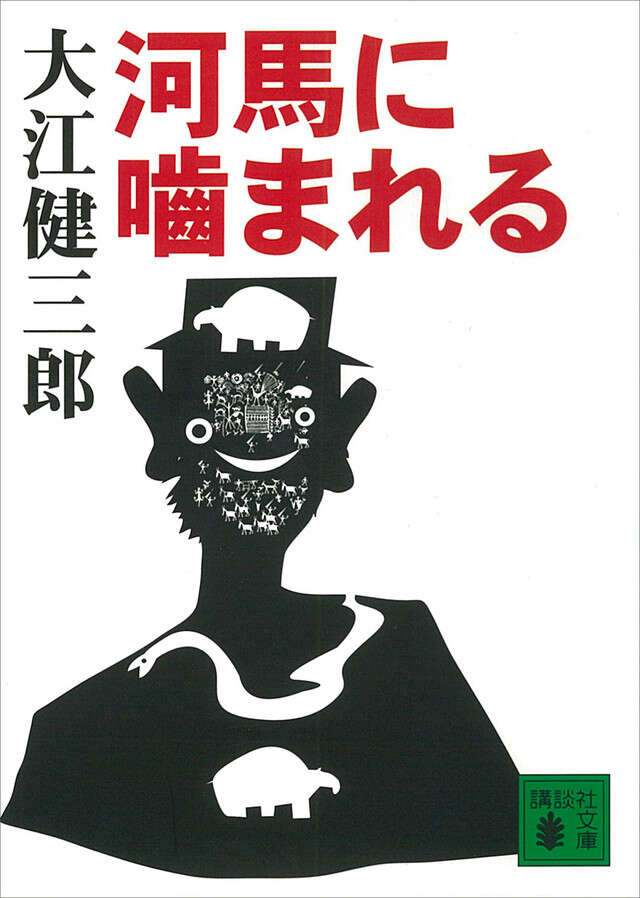
2014.11.28発売
河馬に噛まれる
講談社文庫
ウガンダで河馬に噛まれたことから、「河馬の勇士」と呼ばれる元革命党派の若者。彼と作家である「僕」との交流をたどることで、暴力にみちた時代を描く。若者に希望はあるのか。浅間山荘銃撃戦とリンチ殺人という、戦後日本の精神史に深い傷を残した悲痛で惨たらしい事件を、文学の仕事として受けとめた連作集。
暴力にみちた時代の若者に希望はあるのか
ウガンダで河馬に噛まれたことから、「河馬の勇士」と呼ばれる元革命党派の若者。彼と作家である「僕」との交流をたどることで、暴力にみちた時代を描く。若者に希望はあるのか。浅間山荘銃撃戦とリンチ殺人という、戦後日本の精神史に深い傷を残した悲痛で惨たらしい事件を、文学の仕事として受けとめた連作集。

2014.11.28発売
憂い顔の童子
講談社文庫
作家・長江古義人(ちょうこうこぎと)は、息子のアカリとともに四国の森に帰った。長江の文学を研究するアメリカ人女性ローズが同行する。老いた古義人の滑稽かつ悲惨な冒険は、ローズが愛読する『ドン・キホーテ』の物語に重なる。死んだ母親と去った友人の「真実」に辿りつくまで。『取り替え子(チェンジリング)』から続く、長編3部作の第2作。
小説家、「ドン・キホーテ」と森へ帰る。
作家・長江古義人(ちょうこうこぎと)は、息子のアカリとともに四国の森に帰った。長江の文学を研究するアメリカ人女性ローズが同行する。老いた古義人の滑稽かつ悲惨な冒険は、ローズが愛読する『ドン・キホーテ』の物語に重なる。死んだ母親と去った友人の「真実」に辿りつくまで。『取り替え子(チェンジリング)』から続く、長編3部作の第2作。