ブルーバックス作品一覧

地球進化 46億年の物語
ブルーバックス
海洋、岩石、生命、鉱物、大気──全てが複雑に絡み合いながら「共進化」する。誕生から46億年を貫く壮大なストーリー。
脳研究者・池谷裕二氏絶賛!
「とんでもなく壮大な物語に、「神秘的」という名の浮遊感が心を占有する」
小惑星衝突、超大陸の登場と分裂、生命の誕生、大酸化イベント、全球凍結と温暖化──。地球は誕生から現在に至るまで、絶えず変化しつづけてきた。その変化の歴史で重要な役割を果たしてきたのが、「生物と無生物の共進化」だ。それを示す一端が、他の惑星に比して圧倒的に多い鉱物種である。地球上には現在4500種もの鉱物が存在するが、そのうち3000種は生命がなければ生成されなかった。その一方で、鉱物や岩石が生命の発生を手助けしてきたことが最近の研究から明らかになろうとしている。
海洋や大気の組成が生命と密接に関係していることはすでによく知られているが、無機物として生命とはまったく関わりがないと思われてきた岩石(地球の地殻を形成し、大陸を形作っている)もまた、生物と無生物をつなぐ地球上の物質循環サイクルの主要な一端をなしている。
46億年に及ぶ壮大な「営み」を、生物と無生物の相互作用という新しい視点で描き出す、驚きに満ちた地球全史。
〈「はじめに」より〉 岩石に刻まれた記録を調べるほど、生物と無生物のどちらも含めた自然界が、何度も形を変えているのがわかる。これまで語られなかった壮大で複雑に絡み合った生命と非生命の領域には驚きがあふれている。私たちはそれらを分かち合わなくてはならない。それは私たちが地球だからだ。地球上の物質すべて、私たちの肉体をつくる原子と分子も、地球から生まれ、地球に戻る。私たちの故郷を知ることは、私たちの一部を知ることなのだ。

カラー図解 EURO版 バイオテクノロジーの教科書(下)
ブルーバックス
ユーロ圏を始めとしアメリカの大学でも採用される世界標準のバイオテクノロジーの教科書!
下巻では病気の原因となるウイルスの正体とウイルスから身を守るためのワクチンの開発、遺伝子操作による分子の働きからその応用まで。
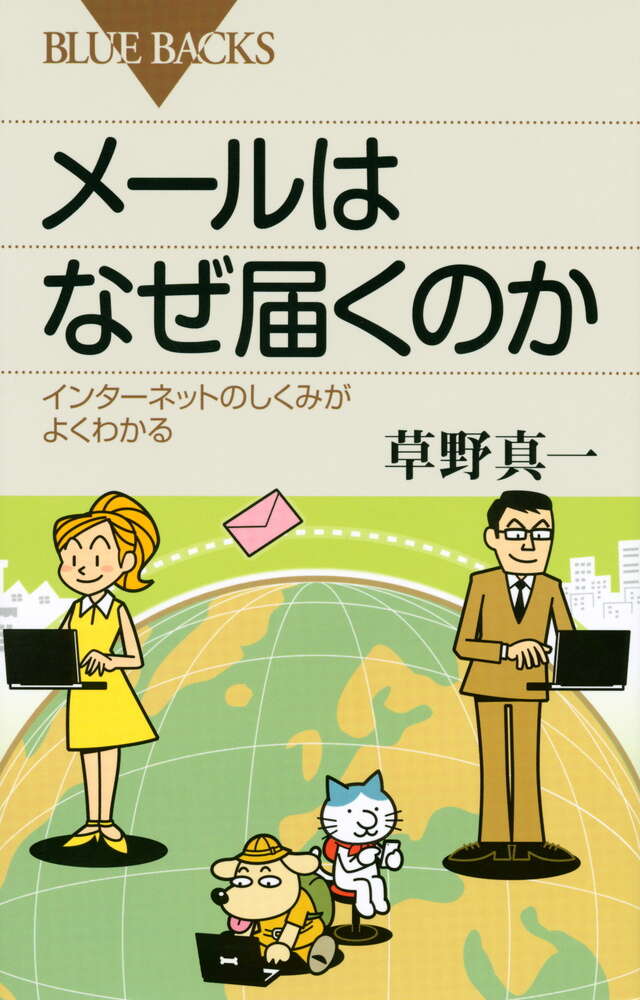
メールはなぜ届くのか
ブルーバックス
メールの送受信やウェブページの表示を可能にするインターネットの複雑な仕組みを、誰でも理解できるようにやさしく解説する入門書。(ブルーバックス・2014年5月刊)
メールの送受信やウェブページの表示を可能にするインターネットの複雑な仕組みを、誰でも理解できるようにやさしく解説する入門書

暗号が通貨になる「ビットコイン」のからくり
ブルーバックス
「通貨の未来」を徹底的に考える――。「国家の後ろ盾がある法定通貨」は、完全無欠ではない。暗号通貨は、「欠点だらけの現行通貨」を革新する可能性を秘めている。暗号がなぜ、おカネになるのか?電子マネーやクレジットカードとどうちがうのか?偽造される心配はないのか?ビットコインの背後に潜む数学や暗号技術と、経済へのインパクトをくわしく語る。
「通貨の未来」を徹底的に考える――。
「国家の後ろ盾がある法定通貨」は、じつは完全無欠ではない。
為替リスクを抑え、送金手数料も安い暗号通貨は、
「欠点だらけの現行通貨」を革新する可能性を秘めている。
シンプルな暗号が、なぜおカネになるのか?
電子マネーやクレジットカードとどうちがうのか?
偽造される心配はないのか?
私たちの生活に、どんな影響をおよぼすか?
投資家たちを震撼させても、なお進化を続けるビットコイン。
その背後に潜む数学や暗号技術と、経済へのインパクトをくわしく語る。

科学検定公式問題集 5・6級
ブルーバックス
アタマでっかちの知識から、使える・役に立つ知識へ
選りすぐりの例題と、こん切ていねいな解説、作問者の意図をくんだ予想問題を解くことで、応用力が身につき理解度も深まっていく。科学検定の問題を通して、教科書の枠にとらわれない科学の面白さと不思議さが実感できる一冊。
「科学検定の問題は、検定資格のための問題ではなく、あくまでも、科学の楽しさを再発見してもらうための問題。ですから、問題を解いて解説を読むことは、知的なエンターテインメントにほかなりません。
そして、過去問で充分な練習をつんだら、是非とも、次回の科学検定を受けてみてください。誰でも気軽にインターネットで受検することができます。その場で点数がわかります。そして、ここが大事なのですが、ちょっぴり緊張した雰囲気のもとで受検することで、知的エンターテインメントが、「あなた自身の挑戦」に変わります。」(「まえがき」 竹内薫 科学検定委員会委員長)

新幹線50年の技術史
ブルーバックス
1964年に世界初の高速鉄道として日本に誕生した新幹線は、2014年で50年を迎えた。日本初の高速鉄道技術はどう変化し、進歩し、停滞したのか。本書では、新幹線が歩んできた50年の歴史を技術の視点で振り返りながら、リニア中央新幹線の建設も見据えて将来像を考えていく。新幹線ともに鉄道技術人生を歩んできた筆者による渾身作。
1964年に世界初の高速鉄道として日本に誕生した新幹線は、2014年で50年を迎えた。新幹線の技術的ルーツが初めて世間に向けて発表されたのは「超特急列車 東京-大阪3時間への可能性」という1957年に開かれた講演会のことである。そこを起点とすれば57年になる。
当時、急速に劣化が進んでいた日本国有鉄道という組織の中で、新幹線は営業面でも技術面でも唯一の明るい部門であった。国鉄末期には停滞した時期もあったが、1987年に国鉄の分割・民営化が断行されて、新生JRによって再び活気を取り戻した。
極東の小国が自力で世界一の高速鉄道を造り、営業的にも大成功を収めたことに、鉄道先進国を自負していたヨーロッパ諸国は急追の動きを見せた。1981年にはフランスが新幹線を参考にして、また他山の石としてTGVというシステムを作り上げ,明確に世界一の座に就いた。
さらにその後、鉄道技術では後進国とのイメージが強かったスペインや中国によって、世界の高速鉄道の地図は大きく塗り替えられた。そのかげで、元祖新幹線には時代遅れや色あせたイメージさえつきまとうようになってきた。
一方で、災害大国でもある日本で、新幹線は奇跡ともいえるような安全実績を更新中であり、なお日本の新幹線には世界に貢献できる優れた技術も少なくない。日本の優れた技術と諸外国に見られる積極的な発想とを組み合わせれば、国の内外で鉄道の社会的役割が一層高められるであろう。
このように、新幹線が歩んできた50年の歴史を技術の視点で振り返りながら、リニア中央新幹線の建設も見据えて将来像を考えていく。新幹線ともに鉄道技術人生を歩んできた筆者による渾身作。
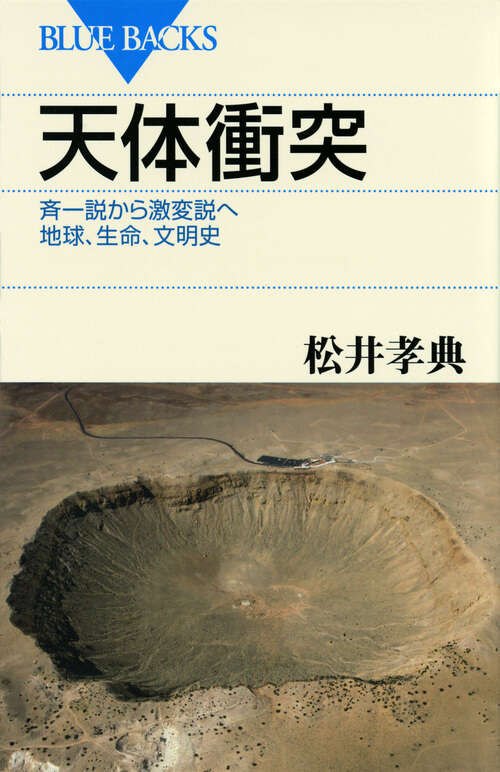
天体衝突
ブルーバックス
6550万年前、直径10~15kmの小惑星が、地表に対して約30度で、南南東の方向から地球に衝突した。衝突速度は秒速約20kmと推定されている。衝突地点周辺では時速1000kmを超える爆風が吹き、衝突の瞬間に発生する蒸気雲は1万度を超えた。この衝突によって引き起こされた地震はマグニチュード11以上と推定され、300mに達する津波が起こった。巻き上げられた塵が太陽光を遮り、「衝突の冬」が始まった。
1万度を超える蒸気雲、マグニチュード11以上の地震、300mの津波、酸性雨、そして「衝突の冬」が恐竜を滅ぼした。
6550万年前、直径10~15kmの小惑星が、地表に対して約30度で、南南東の方向から地球に衝突した。衝突速度は秒速約20kmと推定されている。衝突地点周辺では時速1000kmを超える暴風が吹き、衝突の瞬間に発生する蒸気雲は1万度を超えた。この衝撃によって引き起こされた地震はマグニチュード11以上と推定され、300mに達する津波が起こった。巻き上げられた塵が太陽光を遮り、「衝撃の冬」が始まった。
地球と生命。どちらも、日々起こる小さな変化の、長い間の積み重ねによって進化してきたと考えられてきた。これまでは、その方が「科学的」に思われたからだ。しかし、現実はまったく違っていた。
地球と生命は、「天体衝突」という突発的な大事件によって、劇的に変化してきたことが分かったのだ。 恐竜の絶滅も、地球が何度も経験してきた天体衝突による大絶滅の一つに過ぎない。
そして、今後も大きな天体衝突が、十分起こりうると考えられている。

発展コラム式 中学理科の教科書 改訂版 生物・地球・宇宙編
ブルーバックス
世界標準の理科の内容を押さえた一話読み切り型のコラム教科書。
大人の科学教養も身につくと大好評の既刊に最新情報をアップデート!

発展コラム式 中学理科の教科書 改訂版 物理・化学編
ブルーバックス
世界標準の理科の内容を押さえた一話読み切り型のコラム教科書。
大人の科学教養も身につくと大好評の既刊に最新情報をアップデート!
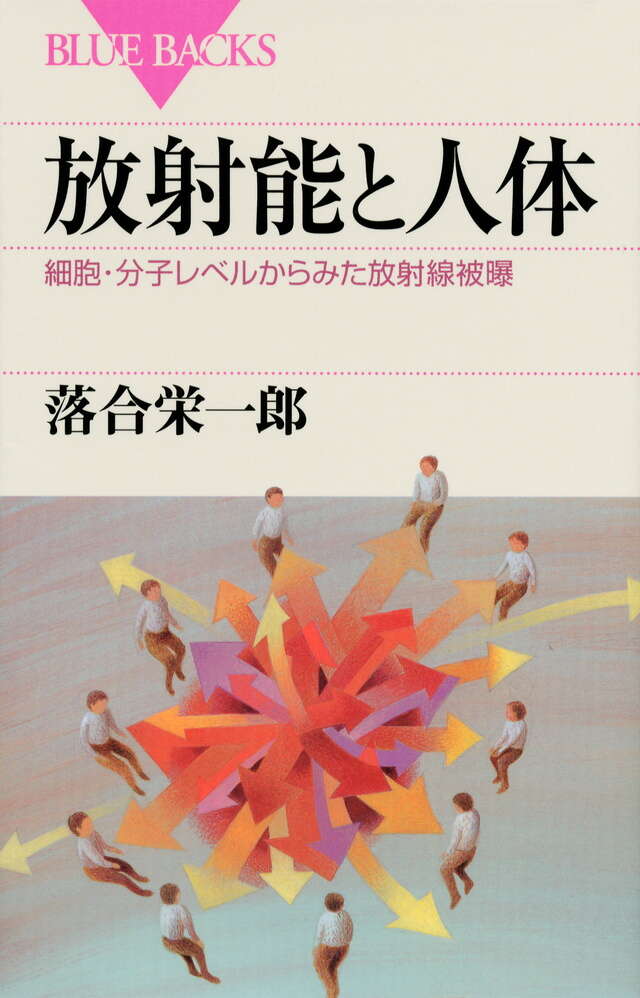
放射能と人体
ブルーバックス
「100ミリシーベルト以下の被曝は心配ない」は本当か?瞬時に高線量の放射線を浴びれば即死する。低線量の長期被曝では……?細菌やウイルス、化学物質に対して免疫システムや解毒作用を備える人体は、放射能にどれだけ耐えられるのか。原爆や原発事故、劣化ウラン弾による被曝の調査報告をもとに、放射線の生体への影響を科学的観点から詳細に検証する。
「100ミリシーベルト以下の被曝は心配ない」は本当なのか?
瞬時に高線量の放射線を浴びれば即死する。
では、低線量でも長期にわたって被曝したら……?
被爆から約70年を経た現在も、臓器内部から放射線が出続けているという。
細菌やウイルス、化学物質に対して免疫システムや解毒作用を備える人体だが、放射能にはどれだけ耐えられるのか。
原爆や原発事故、劣化ウラン弾による被曝の調査報告をもとに、放射線の生体への影響を科学的観点から詳細に検証する。

プロに学ぶデジタルカメラ「ネイチャー」写真術
ブルーバックス
何を撮りたかったかをどうダイレクトに伝えるか。自らの体験とワザを惜しげもなく披露!
画面になかに余分なものを入れないこと――。それがよい写真に仕上げる第一歩だ。主役を魅力的にする色彩と光、フォルムと動きが備われば、1枚の写真にストーリーが生まれてくる。第一線で活躍するネイチャー写真家の実践的な写真講座。
写真を魅力的にする条件
1.主役を目立たせる
2.目をひく色、形、光、動きをとらえる
3.ストーリーを感じさせる

宇宙最大の爆発天体ガンマ線バースト
ブルーバックス
宇宙で最大で最強の巨大な星の爆発、“宇宙のモンスター”ガンマ線バーストとはいったい何か? 数千億個の星からなる銀河よりも明るい大爆発は、どこで、どのように発生するのか? 長い論争の果てに下されたその結論に科学者たちが困惑した理由は一体? ブラックホールとの関係、宇宙の歴史、生命大絶滅との関係……。宇宙物理学で今もっとも注目される現象をひもといていく。(ブルーバックス・2014年3月刊)
ガンマ線バーストは、電磁波の一種であるガンマ線が大量に放出される「宇宙最大の爆発」のこと。数千億の星を集めた銀河よりもずっと明るく輝く想像を超えた大規模な爆発です。最近では恐竜の大絶滅の原因ではないかという説もあります。
ガンマ線バーストの発見は、米ソ冷戦下におけるアメリカの核爆発探知衛星による偶然の産物でした。どこかの国が核実験をしたために起きたものだと考えられ、秘密裏に研究が進められました。地球ではなく宇宙で起きたことが分かり、情報が公開されてからも、たった数十秒しか続かない短い現象を詳細に観測することは難しく、長らく謎の現象とされてきました。
研究が進展したのは、発見から30年たってからのこと。ガンマ線バーストが起きてから数日間、X線や光を出すことがわかったのです。その光を観測したところ、その起源は、数十億光年もの遠方だとわかりました。これほど遠くで起きるにも関わらず地球でも観測できるほどの大爆発だったのです。
また、はるか遠方で起きることから、ガンマ線バーストによって宇宙の起源が解明できるのではと言われています。数十億光年の距離を光が旅するには数十億光年の時間がかかります。つまり、遠くから来るガンマ線バーストをみることは、数十億年前の宇宙をみることでもあります。様々な場所から届くガンマ線バーストを観測すれば、宇宙はどのように始まったのか、最初の星はどのように生まれたのか、謎に包まれた暗黒の時代を照らし出すことができると考えられているのです。
では、この爆発を起こしたのは誰だろうと、犯人捜しが始まりました。観測の進歩によってブラックホールとの関連や、巨大な星が死ぬときに発生することも明らかになりました。しかし、犯人が見つかっても、ガンマ線バーストがどのように起こるのかは分からなかったのです。
たった1個の星の起こす爆発が、どうして数千億の星を集めた銀河よりも明るく輝くのか? そのエネルギーはどこから来るのか? 観測結果が集まっても研究者たちはそれをうまく理解できなかかったのです。その謎をとく鍵は相対性理論にありました。
巨大な爆発はどこでどのように起こるのか? ブラックホールや相対性理論はどのようにかかわってくるのか? 宇宙の起源や生物の大絶滅との関係は? 宇宙物理学で、今もっとも注目される現象を、第一人者が繙いていきます。

量子的世界像 101の新知識
ブルーバックス
素粒子からブラックホールまで、奇妙で驚きに満ちた量子世界をひもとく画期的入門書。この1冊で現代物理学の本質がわかる!
すべては確率に支配され、複数の状態が重ね合わさり、粒子は生成と消滅を繰り返す──古典物理学の世界観を覆す奇妙で驚きに満ちた量子世界。考え抜かれた101の項目でその全体像を見事に描き出し、量子物理学の最前線へと誘います。
”初めての人には「一冊読むならぜひこれを!」と、物理学者には「項目を見たら、きっと読みたくなりますよ」と申し上げたい”(監訳者・青木薫氏による巻末解説より)
著者・ケネス・フォード ジョン・ホイーラーの薫陶を受け、世界最大の物理学組織である全米物理学協会の会長も務めた斯界の重鎮。
監訳・青木薫 1956年生まれ。京都大学理学部卒業、同大学院博士課程修了。理学博士。サイモン・シン『フェルマーの最終定理』(新潮社)はじめポピュラーサイエンスの翻訳多数。著書に『宇宙はなぜこのような宇宙なのか』(講談社現代新書)。2007年度日本数学会出版賞受賞。
翻訳・塩原通緒 1966年生まれ。立教大学英米文学科卒業。主な訳書にリサ・ランドール『ワープする宇宙 5次元時空の謎を解く』(NHK出版)、フィリップ・ボール『流れ 自然が創り出す美しいパターン』(早川書房)など。

カラー図解 EURO版 バイオテクノロジーの教科書(上)
ブルーバックス
ユーロ圏を始めとし
アメリカの大学でも採用される
世界標準のバイオテクノロジーの教科書!

図解・内臓の進化
ブルーバックス
水中から陸上へ進出するとき呼吸器系に迫られた改革、肉食から草食へ移行するため講じられた「奇策」、体内の水を浪費しないための尿のつくり方の工夫、大敵「乾燥」を克服するため生殖器が採ったさまざまな戦略、ホヤに原型をもつ甲状腺ほか内分泌系の不思議な進化、そして昆虫と私たちの内臓の意外な類似性と決定的な違い――前作『図解 感覚器の進化』に続く「器官の進化シリーズ」第2弾、「内臓進化」の一大絵巻です。
「こういうものの見方こそ学校で教えてほしい」。書評ブロガー小飼弾氏絶賛の、かつてなかった内臓の進化史!
水中から陸上へ進出するとき呼吸器系に迫られた改革、 肉食から草食へ移行するため講じられた「奇策」、
体内の水を浪費しないための尿のつくり方の工夫、大敵「乾燥」を克服するため生殖器が採ったさまざまな戦略、
ホヤに原型をもつ甲状腺ほか内分泌系の不思議な進化、そして昆虫と私たちの内臓の意外な類似性と決定的な違い――
ものいわぬ「体の主役」内臓のデザインと機能には、動物たちがくぐり抜けてきた激動の歴史が刻まれています。
その戦略と設計思想を読み解くと、動物の進化の絶妙さに驚くほかはありません。
本書は、これまでに膨大な数の動物を実際に解剖し、観察してきた著者が前作『図解 感覚器の進化』に続いて贈る
「器官の進化シリーズ」第2弾、「内臓進化」の一大絵巻です。
渾身の図版の数々には、ページをめくるだけで圧倒されること間違いありません。

物理のアタマで考えよう!
ブルーバックス
ヨーロッパ各国の物理学会の連合体「ヨーロッパ物理学連合」の会誌に連載された珠玉のコラム集。「人間がエンジンなら何ワット?」という疑問から始まり、日常のさまざまな現象を物理のアタマで考えていきます。
たとえばクルマで前進するには抵抗に打ち勝たないといけませんが、その影響を計算してみると、時速100kmを越えたあたりから燃費が急激に悪くなることがわかります。あるいは、船旅は飛行機旅行よりエコな気がしますが、1席1kmあたりで計算するとクルーズ船の効率は飛行機より悪いこともわかります。高齢になると耳が遠くなりますが、その理由も物理で考えることができます。お風呂で歌を唄ったときに、カーテンを閉めていても声の音はほとんど減衰しません。その理由も説明できます。
そのほか、「サウナの石に水をかけるとなぜ熱くなるのか」「換気で部屋の温度はどれだけ変わるか」「日時計のずれはどれくらいか」「日没はなぜ美しいか」「雨粒は時速何kmで落ちていき、どのくらいの大きさになるのか」など、身の回りの現象を解き明かしていきます。あなたの「思い込み」や「直感」は、本当に正しいでしょうか?

チューリングの計算理論入門
ブルーバックス
本書は、コンピュータの原理としてのチューリング・マシンを解説するとともに、決定問題を解決した有名な「チューリング・マシンの停止問題」も分かりやすく説明します。さらに計算量と、7大難問の一つ「P=NP問題」についても、わかりやすく解説します。(ブルーバックス・2014年2月刊)
イギリスの数学者チューリングは、ヒルベルトの「決定問題」解決のために、万能計算機の数学的モデル「チューリング・マシン」のアイディアに至った。この「チューリング・マシン」こそが、コンピュータの万能性を保証する数学的基礎になった。
チューリングは、「チューリング・マシン」を使って、計算という行為を徹底的に検証した。そして、手順を示すことと、計算ができることが同じであることを示した。その手順はアルゴリズムと呼ばれ、いまではソフトウェアと言われている。
本書は、コンピュータの原理としてのチューリング・マシンを解説するとともに、決定問題を解決した有名な「チューリング・マシンの停止問題」も分かりやすく説明します。さらに計算量と、7大難問の一つ「P=NP問題」についても、わかりやすく解説します。
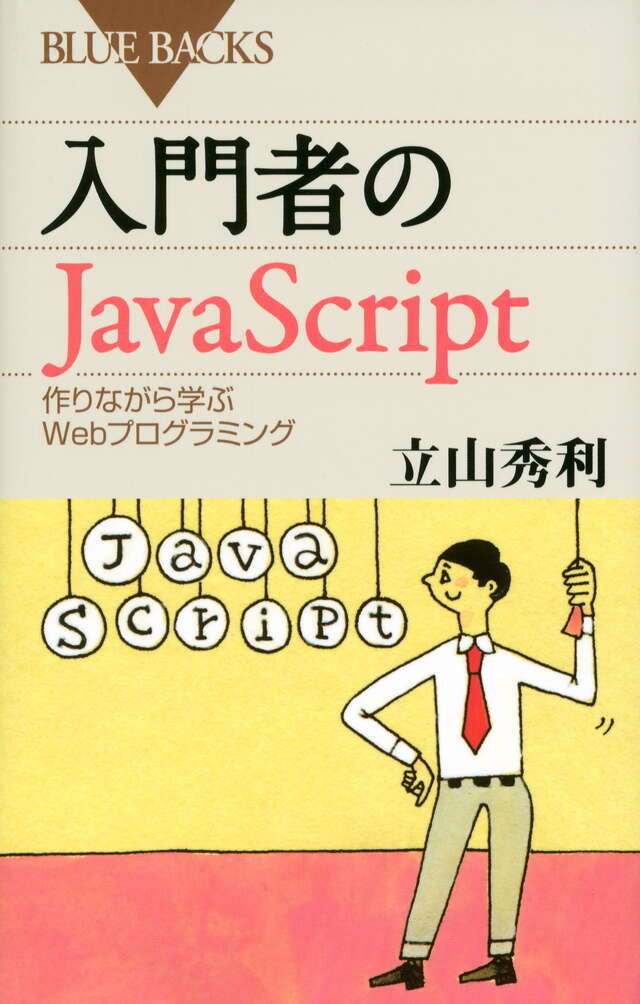
入門者のJavaScript
ブルーバックス
JavaScriptは、Webページに表示される画像や文字列などを、閲覧する人の操作に応じて自由自在に変えられるプログラミング言語です。本書では、1つ1つ作例を作り、動かしながらJavaScriptの基本を少しずつ学んでいきます。手順通りにやるだけで、HTMLやCSSの未経験者でもJavaScriptの使い方が必ずマスターできます。(ブルーバックス・2014年1月刊)
手順通りに書いて、動かすだけで
自然とJavaScriptが身につく!
JavaScriptは、Webページに表示される
画像や文字列などを、閲覧する人の操作に応じて
自由自在に変えられるプログラミング言語です。
本書では、1つ1つ作例を作り、動かしながら
JavaScriptの基本を少しずつ学んでいきます。
手順通りにやるだけで、HTMLやCSSの未経験者でも
JavaScriptの使い方が必ずマスターできます。

分子からみた生物進化 DNAが明かす生物の歴史
ブルーバックス
オスが進化の先導者だった!? ネアンデルタール人と現代人はいつ分かれたのか? 生物最古の枝分かれはどうおきたのか? いまだ多くの謎につつまれている生物の進化。化石には残らない進化の情報が、突然変異としてDNAには刻まれている。DNAに秘められた生物の歴史を丹念にたどり、進化のしくみを解き明かす分子進化学。その基礎から最先端の成果までをわかりやすく紹介する。DNAが語る生物35億年の歴史。
オスが進化の先導者だった!? ネアンデルタール人と現代人はいつ分かれたのか? 生物最古の枝分かれはどうおきたのか?
いまだ多くの謎につつまれている生物の進化。化石には残らない進化の情報が、突然変異としてDNAには刻まれている。DNAに秘められた生物の歴史を丹念にたどり、進化のしくみを解き明かす分子進化学。その基礎から最先端の成果までをわかりやすく紹介する。DNAが語る生物35億年の歴史。

今さら聞けない科学の常識3 聞くなら今でしょ!
ブルーバックス
知っているつもりだけれど、正確には説明できない。そんな科学の知識を集めたのが朝日新聞土曜版「be」の人気連載「今さら聞けない+」です。誰に聞いてよいのかわからない疑問を科学記者が懇切丁寧に解説したシリーズ第3弾。今さら聞けないけれど、聞くなら今でしょ!
主な項目 平均気温、温室効果ガス、酸性雨、活断層、コレステロール、ワイン、ブランド牛、DNA鑑定、出生前診断、熱中症、マイコプラズマ、認知症、宝くじの買い方、自動機械翻訳、バーコード、高速道路の渋滞、超伝導、不確定性、コンクリート、合板、レアアース、低燃費タイヤ、垂直離着陸機、蒸気機関車、絶滅危惧種、動物に見える色