講談社文芸文庫作品一覧

大東京繁昌記 下町篇
講談社文芸文庫
関東大震災から四年、復興へと邁進する帝都・東京の変貌する姿と、いまだいたる所に残された災害の傷痕を、当時を代表する文学者、画家たちが活写した名随筆。
昭和二年、「東京日日新聞」での好評連載を完全復刊。
※本書は、春秋社『大東京繁昌記 下町篇』(1928年9月刊)を底本としました。

虹と修羅
講談社文芸文庫
夫以外の男との関係を断ち切った後も新たな愛へと進んでいく主人公・滋子。
娘との隔絶に悩み、さらには自身の体が?
『朱を奪うもの』『傷ある翼』に続く三部作の最終章。谷崎賞受賞作。
※本書は、1997年9月新潮社刊『円地文子全集』第十二巻を底本としました。

犬をえらばば
講談社文芸文庫
石坂洋次郎、坂口安吾、吉行淳之介、遠藤周作、江藤淳、近藤啓太郎らとの交流を「愛犬」を通して綴る、ユーモアと知性溢れるエッセイ
※本書は、『犬をえらばば』(1974年4月、新潮文庫)を底本としました。
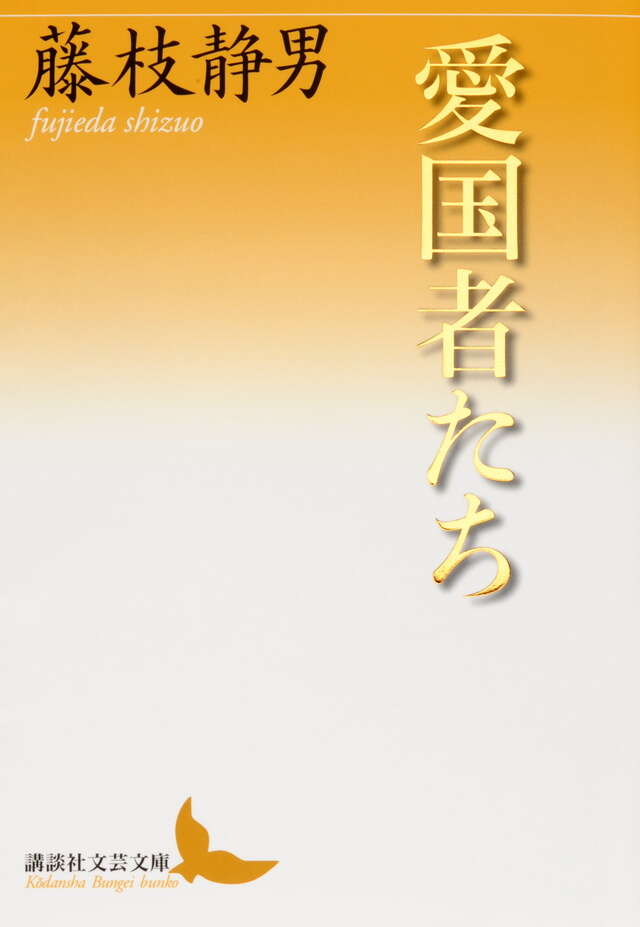
愛国者たち
講談社文芸文庫
異能の私小説家の知られざる名作ーー昭和24年、日本訪問中のロシア皇太子ニコラスへの暗殺未遂事件=大津事件に関わった愛国者たち……。津田三蔵、畠山勇子、明治天皇、児島惟謙らを軸に、歴史の変動の渦中にあつ人間を見つめた表題作、ほか7篇。戦後日本の転換点に直面した異能の私小説作家が、自己の文学的葛藤と追究の痕跡を刻印した、独自の私小説風世界の魅力が横溢する作品集。平林たい子文学賞受賞作品。
※本書は、『愛国者たち』(1973年11月、講談社刊)を底本としました。

恋と日本文学と本居宣長・女の救はれ
講談社文芸文庫
『忠臣藏とは何か』『日本文学史早わかり』と並ぶ、丸谷才一の古典評論三部作。中国文学から振り返って、『源氏物語』『新古今和歌集』という日本の文学作品を検証した孤立無援の本居宣長の思考を蘇らせ、さらにはその視点で近代日本文学をも明確に論じる。女系家族的な考えから日本文学を俯瞰した「女の救はれ」を併録した『恋と女の日本文学』を発表時の題に戻し刊行。
丸谷才一の古典評論
島国で育まれた特異な文学 その秘密を解く
有り余る才能を惜しまれつつ2012年10月に亡くなった丸谷才一。
古典にも造詣が深い著者の『忠臣藏とは何か』『日本文学史早わかり』に次ぐ作品。
※本書は、『恋と女の日本文学』(講談社文庫・2000年5月刊)を底本としたものを改題しました。

マス・イメージ論
講談社文芸文庫
カフカ、小島信夫、中島みゆき、山岸涼子ら、文学・漫画・CM・歌謡曲などを全体的な概念として捉え、「現在」を読み解く斬新な評論。新しい時代を予見した格闘の書! ーー文学、少女漫画、現代詩、歌謡曲、テレビCM……。マスメディアを通して現れた言葉やイメージを産み出している「現代」という名の作者をめぐって、果敢に挑んだ評論集。小島信夫、高橋源一郎、萩尾望都、糸井重里、中島みゆきらの諸制作品を、個別の批評方法から離れて解析・論述し、「戦後思想界の巨人」の新たな側面を示して反響を呼んだ。来るべき時代を予見し、今さらに輝きを増す画期的論考。

昭和戦前傑作落語選集
講談社文芸文庫
昭和戦前の名人たちがしたたかに仕掛けた笑いの爆弾
昭和4年から16年までの庶民落語を綴る。権力に迎合しながらも風刺を忘れなかった激動の時代の落語を口演速記から起こした名演集。
※本書は、『昭和戦前傑作落語全集』第一~六巻(講談社・1981年11月~1982年4月刊)を底本としました。

死の島 下
講談社文芸文庫
後世に残したいものがある 記憶や歴史とともに
著者を代表する長篇小説
日本文学大賞受賞
一年間の出来事と24時間の心模様、さらには小説内小説を複数取り込むという手法を用い人間の愛と死の極限まで迫った記念碑的作品。
※本作品の底本は、上巻を新潮社刊『福永武彦全集』第十巻(昭和63年4月)、下巻を新潮社刊『福永武彦全集』第十一巻(昭和63年5月)としました。

春夏秋冬
講談社文芸文庫
文学に捧げた人生――いぶし銀の随筆集
スタンダール『赤と黒』、フローベール『ボヴァリー夫人』の名訳者であり、第一級の仏文学者であった碩学の日常と思索を綴る名随筆。
※本書は、1979年5月冬樹社刊『春夏秋冬』を底本としました。

死の島 上
講談社文芸文庫
じっくりと長篇を読む楽しみ
日本文学の金字塔
広島で原爆に遭遇した女性画家、過去にいわくのある純真な女性、両者に愛を感じてしまった主人公。三人が生と死を突き進む24時間。

丸谷才一編・花柳小説傑作選
講談社文芸文庫
『花柳小説名作選』に続く小説集は、永井荷風から吉行淳之介、そして島村洋子まで、丸谷才一氏が長年あたためていた企画がここに実現。
最後の編纂本は「艶やか」
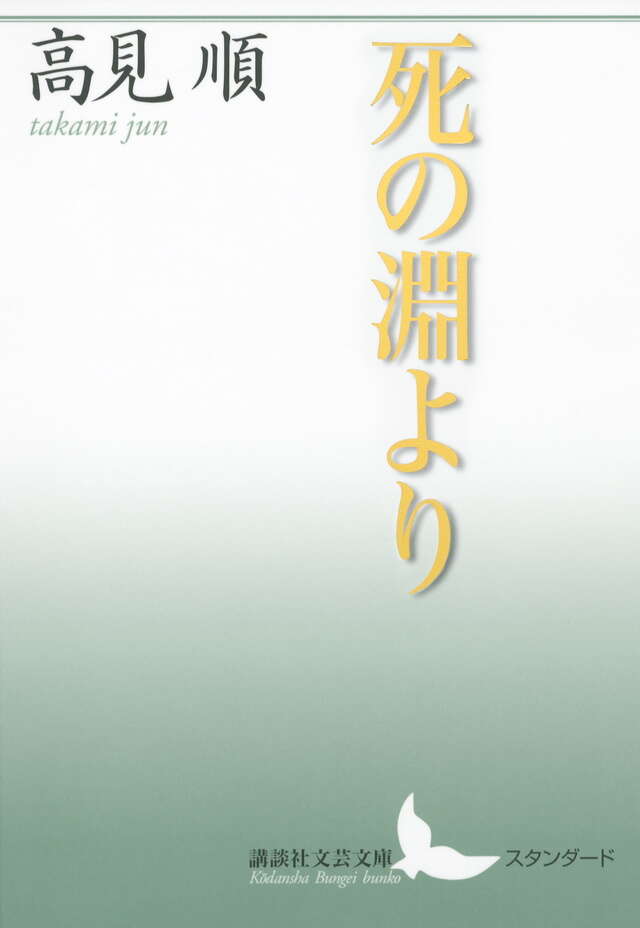
死の淵より
講談社文芸文庫
つめたい煉瓦の上に/蔦がのびる/夜の底に/時間が重くつもり/死者の爪がのびる(「死者の爪」)。死と対峙し、死を凝視し、怖れ、反撥し、闘い、絶望の只中で叫ぶ、不屈強靱な作家魂。醜く美しく混沌として、生を結晶させ一瞬に昇華させる。“最後の文士”と謳われた高見順が、食道癌の手術前後病床で記した絶唱63篇。野間文芸賞受賞作。
食道がんに冒され死に直面しながら、自らの生を透徹した眼差しで見つめ、文学的営為の限りを尽くし至高の韻文へと昇華させた、絶唱。
野間文芸賞受賞。
※本書は、1993年2月刊、講談社文芸文庫『死の淵より』を底本としました。
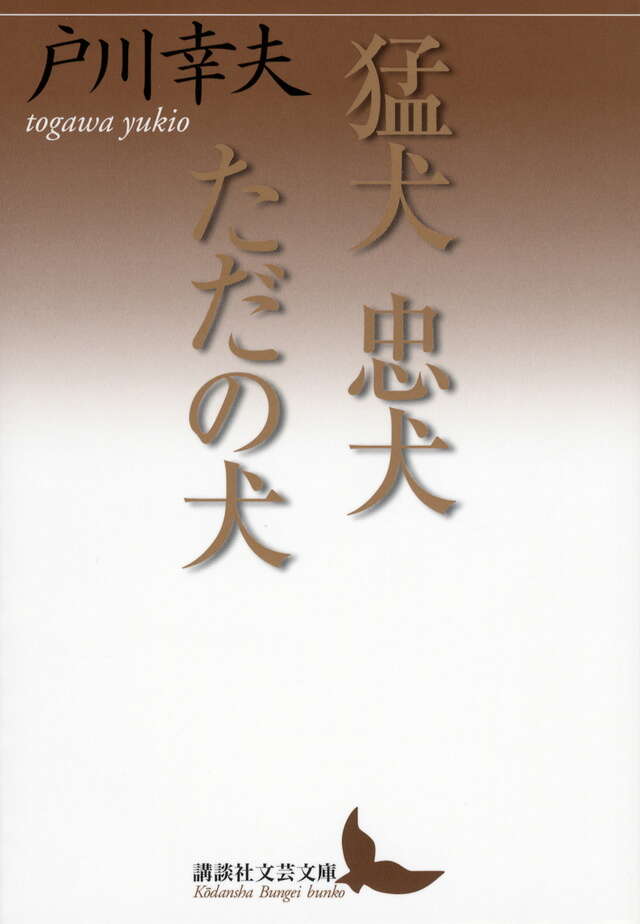
猛犬 忠犬 ただの犬
講談社文芸文庫
こよなく動物と自然を愛し続けた著者の自伝的小説。少年から青年へと成長していく過程でさまざまな犬との出会いと別れを綴った作品。……「動物文学」というカテゴリーを確立し、国民の支持を得た戸川幸夫の原点ともいうべき自伝的小説。もの心つく前から動物好きであったという著者が、さまざまな気質の犬と育った九州の幼い頃から、運命的な犬との出会いをする旧制高校時代までを、愛情を持った動物への的確な観察眼で描き切る。それは犬への鎮魂歌であるとともに、おのれの成長の証であった。動物文学の第一人者が犬と語り続けた自伝的小説。

続・酔っぱらい読本
講談社文芸文庫
酒にまつわる名作エッセイを吉行淳之介が選んだ『酔っぱらい読本』を再編集した第二弾。
さらなる酔っぱらいが大集合し織りなす喜怒哀楽。
永井龍男・北杜夫・星新一・小林秀雄・萩原朔太郎・梅崎春生・庄野潤三・獅子文六・中野重治・木山捷平・坂口謹一郎・井上光晴・田村隆一・伊藤整・加太こうじ・瀬戸内晴美・野坂昭如・長部日出雄・古今亭志ん生・開高健・小松左京のエッセイ・詩・落語に加え、佐々木侃司のイラストレポート「私の酒歴」も収録。
※本書は、講談社刊『酔っぱらい読本』(壱~陸、昭和53~54年)を底本としました。

落葉・回転窓 木山捷平純情小説選
講談社文芸文庫
男と女の出会いと恋愛の機微を永久の時間のなかで紡ぎ出す短篇小説の魔術師・木山捷平。その鮮麗なる筆致は読む者すべてを魅了する。「村の挿話」「猫柳」「空閨」「増富鉱泉」「男の約束」「落葉」「回転窓」「留守の間」「口婚」「好敵手」「七人の乙女」を収録。
男と女の出会いと恋愛の機微を永久の時間のなかで紡ぎ出す短篇小説の魔術師・木山捷平。
その鮮麗なる筆致は読む者すべてを魅了する。
※本書は『木山捷平全集』(講談社刊)を底本としました。

木山さん、捷平さん
講談社文芸文庫
飄逸な味わいで知られる私小説作家・木山捷平。
詩に惹かれ、文学・人物に魅了されて、いつしか人生を辿り、謳いあげた傑作長篇評伝。
※本書は、『木山さん、捷平さん』(1996年7月、新潮社刊)を底本としました。
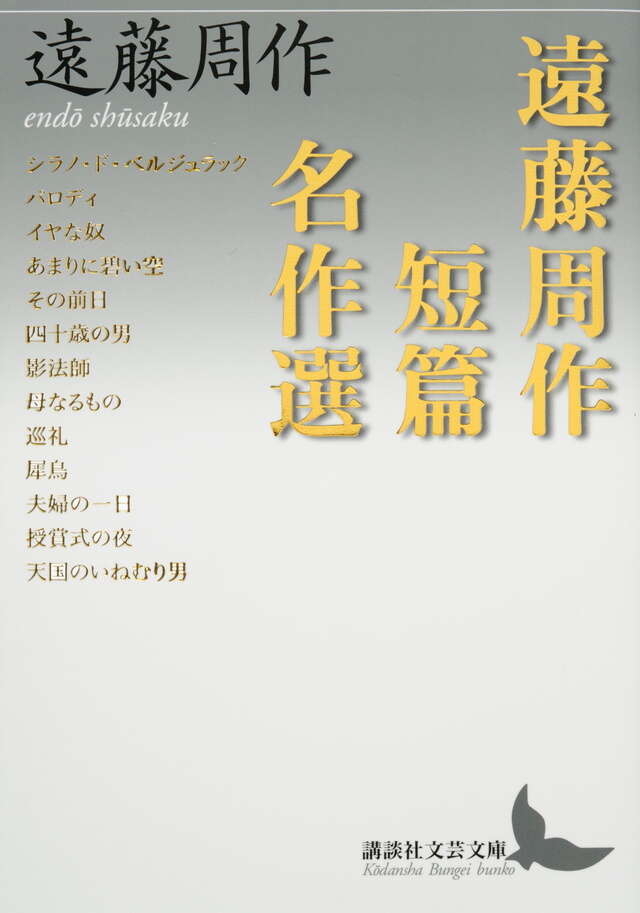
遠藤周作短篇名作選
講談社文芸文庫
『沈黙』から『深い河』にいたる代表的純文学長篇小説の源泉ともいえる短篇の数々ーー遠藤周作には、代表的長篇小説が多くあるが、それぞれの長篇には、源泉となる短篇作品がある。その遠藤文学の核となる13の名短篇を集めた。「シラノ・ド・ベルジュラック」「パロディ」「イヤな奴」「あまりに碧い空」「その前日」「四十歳の男」「影法師」「」「母なるもの」「巡礼」「犀鳥」……遠藤周作の文学・人生・宗教観がすべてわかる短篇集。
※本書は、『遠藤周作文学全集 第6~8巻』(1999年10~12月 新潮社刊)を底本としました。また『天国のいねむり男』は全集・文庫など未収録作品です。

鉄道大バザール 下
講談社文芸文庫
阿川弘之の流麗かつ芳醇な訳で贈る、ポール・セルーのユーラシア一周汽車の旅。
出会いと別れ。各国各様の人生を乗せて……。
※本書は、『鉄道大バザール』(講談社刊・1977年)を底本といたしました。

花月五百年 新古今天才論
講談社文芸文庫
最古の勅撰集・古今和歌集から新続古今和歌集まで、五百年にわたる二十一代集収録約三万五千首から、現代人の記憶に値する歌を勘案して選び抜き、書き上げた名著。
※本書は、『花月五百年 新古今天才論』(昭和58年11月 角川書店刊)を底本として使用しました。
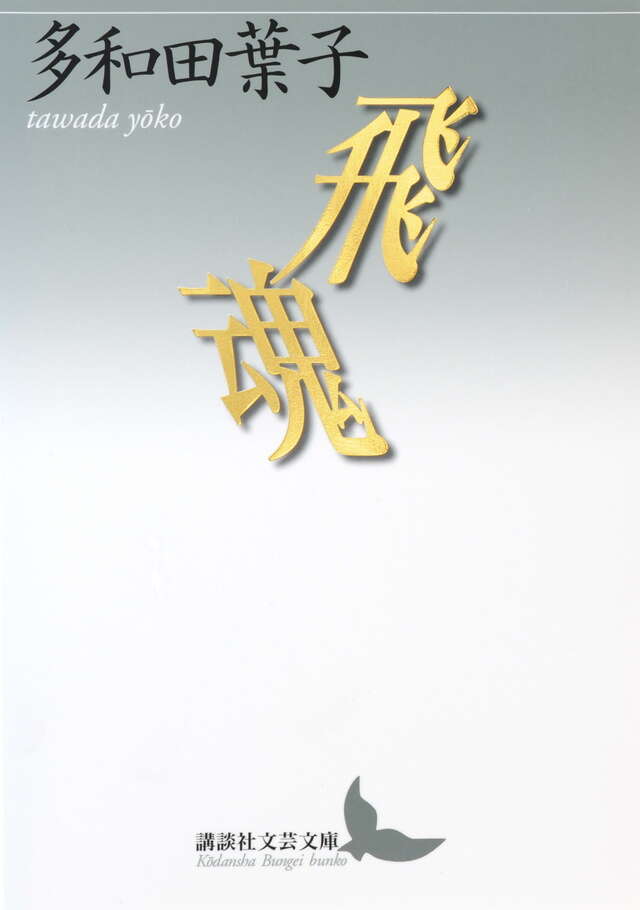
飛魂
講談社文芸文庫
虎使いとなるため、師とともに人里離れた森の中の寄宿舎で修行を続ける女性達の深遠なる精神の触れ合いを描いた作品。表題作ほか、「盗み読み」「胞子」「裸足の拝観者」「光とゼラチンのライプチッヒ」を収録。
虎使いとなるため、師とともに人里離れた森の中の寄宿舎で修行を続ける女性達の深遠なる精神の触れ合いを描いた作品。他短篇4作収録。
●飛魂
●盗み読み
●胞子
●裸足の拝観者
●光とゼラチンのライプチッヒ