講談社文芸文庫作品一覧

幽界森娘異聞
講談社文芸文庫
五感で選び取った世界を唯一無二の絢爛たる文章で描き、今も熱心に読み継がれ愛される作家、「森娘」。
春の日、雑司ヶ谷の路上で主人公は彼女の姿を?
「贅沢貧乏を読むまで人は死ねない」と断言する著者が無上の愛と敬意をもって織りなし、時空を振るわす、作家同士、魂と言葉の一大セッション。
泉鏡花文学賞受賞作。
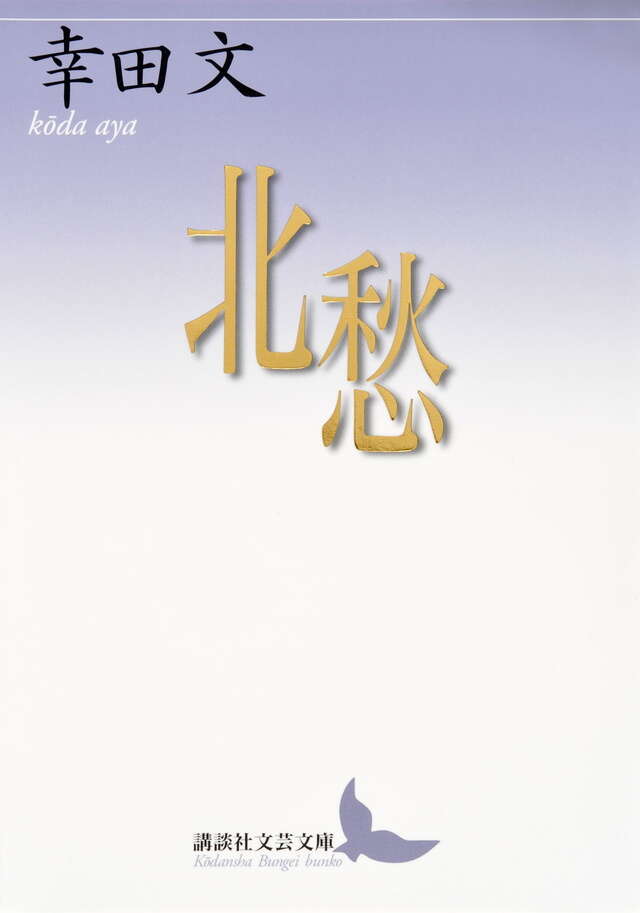
北愁
講談社文芸文庫
幼くして母を亡くし、継母と文筆家の父に育てられた才気煥発な娘あそぎ。そのまっすぐな気性は時に愛され、時に人を傷つける。婚家の没落、夫婦の不和、夫の病――著者・幸田文自身を彷彿とさせる女性の波乱の半生を、彼女を取り巻く人々とのつながりの中でこまやかに描きあげた長編小説。
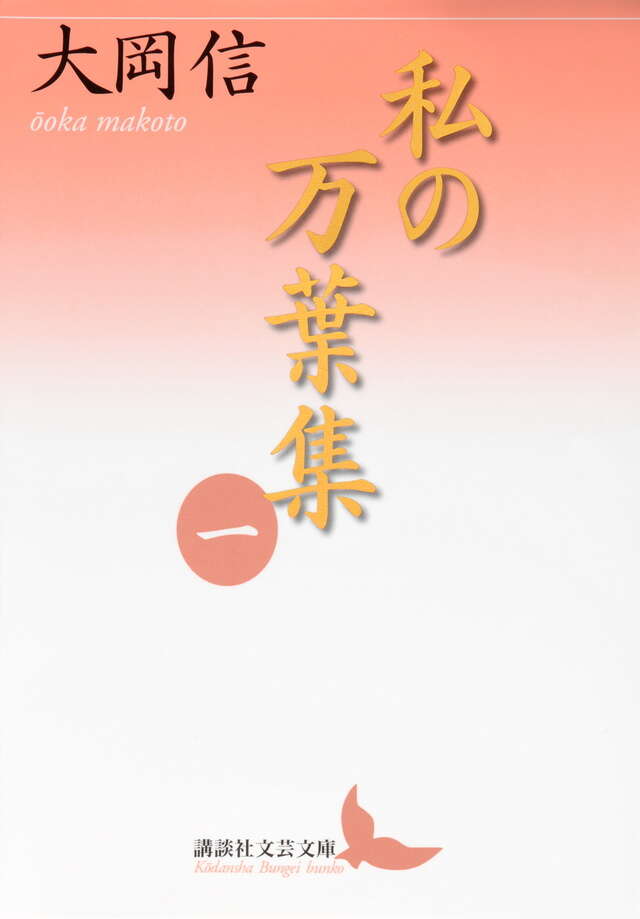
私の万葉集 一
講談社文芸文庫
新元号「令和」の出典、
『万葉集』の魅力を
現代詩の巨人が説きあかす!
現代詩人・大岡信の先見性に満ちた『万葉集』論、第一巻。
新元号の出典となった「梅花の宴」について、
日本文学史とこの宴との重要な関連を指摘。
『万葉集』を現代人が味わい楽しむ「生きた」歌集として読み解く。
詩歌の実作者が書いた『万葉集』の鑑賞。
八世紀前半に成立した『万葉集』はきわめて難解であり、しかしまた我々の心に残る多くの親しまれた歌がある。
その膨大な数の歌を、巻一から巻二十まで通読した大岡信の鑑賞には、日本の美学の起源をみる。
魅力ある読み方をするために現代詩人が挑んだ全5巻。

『少年倶楽部』短篇選
講談社文芸文庫
読書人を育てた伝説の雑誌。
古びないおもしろさと人間への信頼に満ちた22篇。
大正3年から昭和37年まで、青少年たちを夢中にさせ、後の知識人・読書家たちの礎を築いた雑誌『少年倶楽部』。数ある名作群から、いま大人が読んでも面白い短篇を厳選、小説の愉しみ、読書の醍醐味を心ゆくまで味わってほしい。
金子光晴、菊池寛、横光利一、池田宣政(南洋一郎)、川端康成、片岡鉄兵、山中峯太郎、サトウ・ハチロー、山本周五郎、椋鳩十、佐々木邦、山岡荘八、他全22人。
※本書は、月刊誌『少年倶楽部』(1946年4月号より『少年クラブ』と改名)及び単行本『少年倶楽部名作選3』(1966年12月刊、非売品)を底本といたしました。

狂い凧
講談社文芸文庫
虚無とアイロニーをまとい、人生の不条理を見つめ続けた異色の戦後派作家、梅崎春生。『桜島』『日の果て』で戦時の極限下における心象を、『蜆』『ボロ屋の春秋』で市井にひそむ人間の本質を描いた著者が、過去の戦争と現在の日常とを
緻密な構成でゆるぎなく繋ぎあげた、晩年の集大成。芸術選奨受賞作。
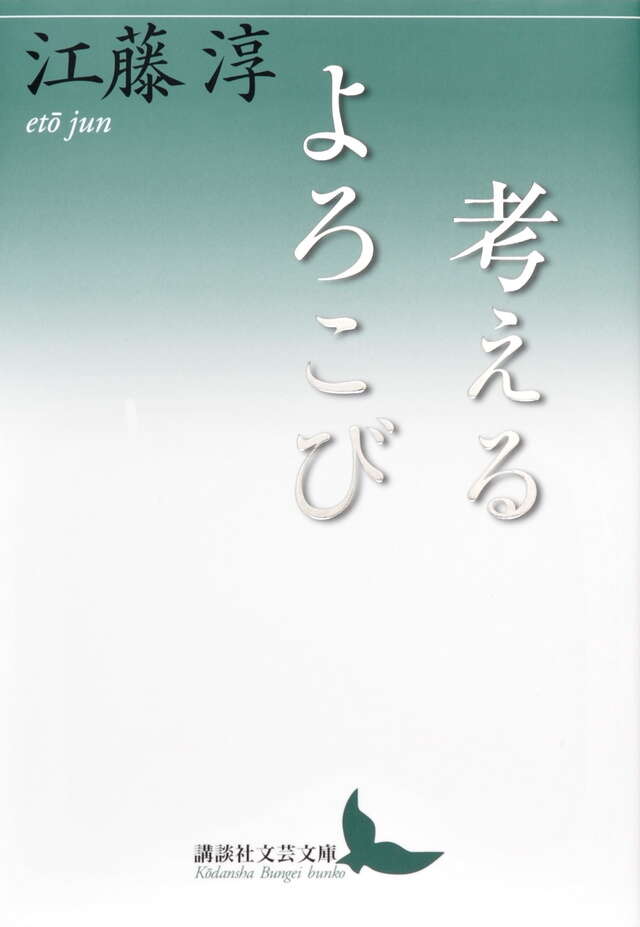
考えるよろこび
講談社文芸文庫
江藤文学への最高の入門書。『漱石とその時代』執筆当時に行った、若き著者の知性とユーモア溢れる講演録。表題作の他「転換期の指導者像」「英語と私」など、全6編ーーアメリカから帰国し、名作『漱石とその時代』を準備中の、1968年から69年にかけて行われた若き日の6つの講演。現代における真の「英知」とは何か……歴史を探り、人物を語り、表現の謎に迫り、大学や国際化の意味を問う。軽妙なユーモアと明快な論理、臨場感あふれる語り口で、読者を一気に江藤文学の核心へといざなう。多くの復刊待望の応え、甦った歴史的名講演集。
※本書は、講談社文庫『考えるよろこび』(1974年9月)を底本としました。

釣師・釣場
講談社文芸文庫
なつかしい、日本の原風景へ
三崎、九十九里、淡路島から木津川、吉野川、最上川に長良川。
その土地の名人に聞く釣談義と旅情あふれる釣行で綴った魅惑の名随筆。
※本書は、1997年12月新潮文庫版『釣師・釣場』を底本としました。
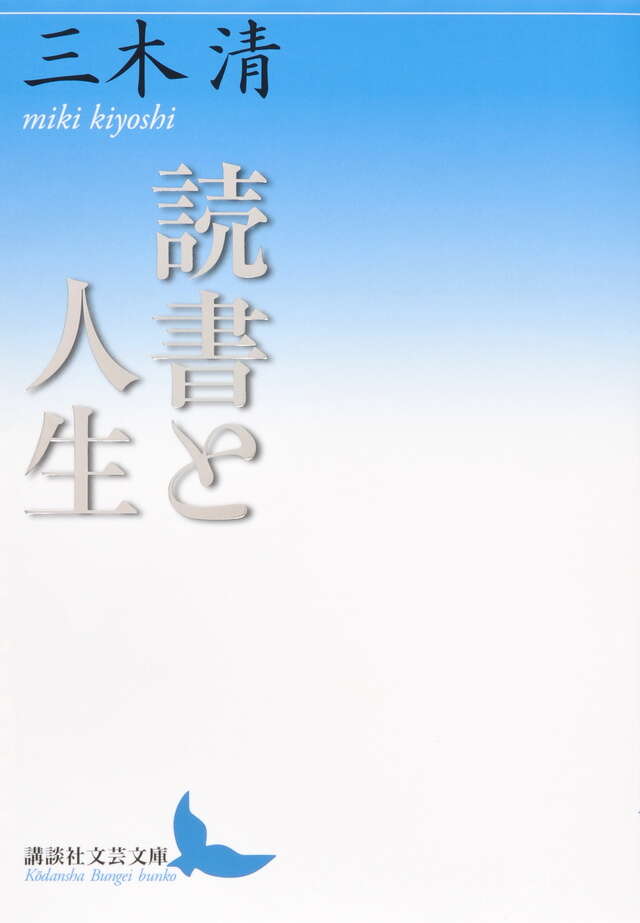
読書と人生
講談社文芸文庫
なにを、どう読み、いかに生きるか。真摯な問いかけが深い感動を呼ぶ、永遠の読書論。ファシズムに抗し獄死した近代日本を代表する哲学者による読書案内であり、秀逸な人生論でもある。混迷の時代を生きる現代人必読の書。
なにを、どう読み、いかに生きるか。
真摯な問いかけが深い感動を呼ぶ、永遠の読書論
ファシズムに抗し獄死した近代日本を代表する哲学者による読書案内であり、秀逸な人生論でもある。
混迷の時代を生きる現代人必読の書
※本書は、『読書と人生』(新潮文庫・1974年刊)を底本としました。

個人全集月報集 藤枝静男著作集 永井龍男全集
講談社文芸文庫
志賀直哉を師と仰ぎ、独自の文学世界を鋭く自在に創りあげた藤枝静夫。
短篇の名手であり、日本語を極限まで研ぎ澄ました永井龍男。
日本現代文学の本質的な香りを伝えた二人の小説家に寄せる、煌びやかな作家・評論家たち。すべての読者に贈る「個人全集月報集」第二弾。
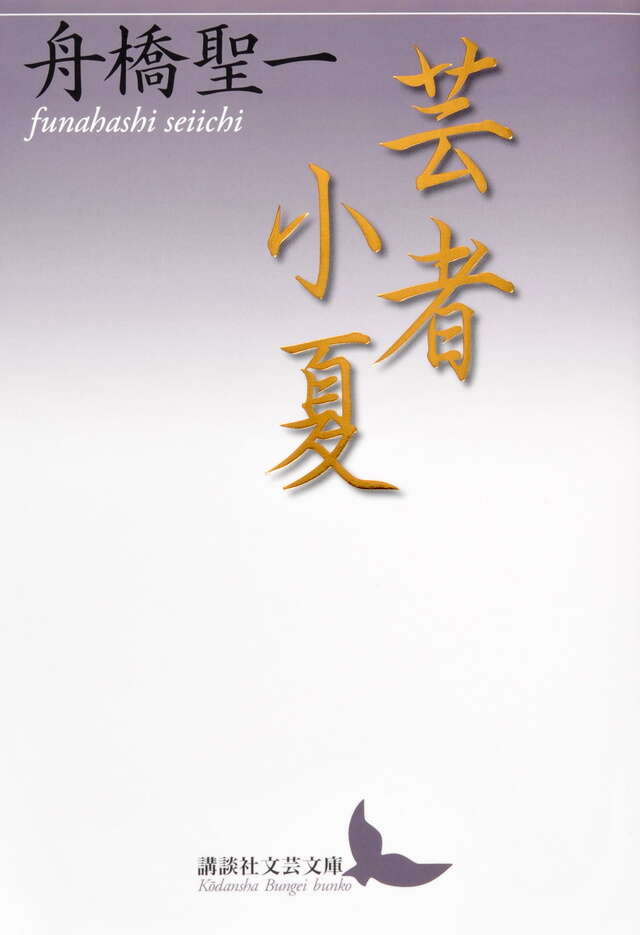
芸者小夏
講談社文芸文庫
故・丸谷才一氏が愛した、花柳小説の金字塔ーー温泉芸者の子に生まれ、水商売の中で育った夏子。この宿命の絆を断ち切りたいと希いながらも、外に道はなく、夏子は15で芸者小夏となった。純情を捧げた初恋の教師に裏切られ、夏子は日ましに「女」になっていく……。若き日に色町に親しみ男女の機微を知る著者が、戦後の脂の乗りきった時期に書き継ぎ、「夏子もの」として人気を博した連作小説の第1作。

戦後詩 ユリシーズの不在
講談社文芸文庫
谷川俊太郎から星野哲郎、塚本邦雄、西東三鬼、青島幸男にヒューズまで。
没後30年、今なお色褪せない独特の感性と言語観で綴る名篇。
※本書は、『戦後詩 ユリシーズの不在』(ちくま文庫・1993年刊)を底本とし、適宜、同書紀伊國屋書店版(1965年刊)を参照しました。

昭和戦前傑作落語選集 伝説の名人編
講談社文芸文庫
伝説の名人たちが時代という標的に笑いの銃撃!
昭和4年から16年までの、暗い時代に笑いの達人たちが咲かせた一輪の花。
落語を口演速記から起こし、話題となった名演集の第二集。
※本書は、『昭和戦前傑作落語全集』第一~六巻(講談社・1981年11月~1982年4月刊)を底本としました。

地下へ/サイゴンの老人 ベトナム全短篇集
講談社文芸文庫
ベトナム戦争時に特派員として滞在した著者が、小説で描いたベトナムの明と暗を網羅。
戦争に生きることを深く見つめる作品集。
※本書では、以下のものを底本としました。
「向う側」は『日野啓三短篇選集上巻』(1996年12月、読売新聞社)、「ヤモリの部屋」は『風の地平』(1976年4月、中央公論社)、「林でない林」は『どこでもないどこか』(1990年9月、福武書店)、「悪夢の彼方」は『日野啓三自選エッセイ集 魂の光景』(1998年12月、集英社)、「“向う側”ということ」は『都市という新しい自然』(1988年8月、読売新聞社)、それ以外の作品は、それぞれの末尾に示した初出誌に拠りました。
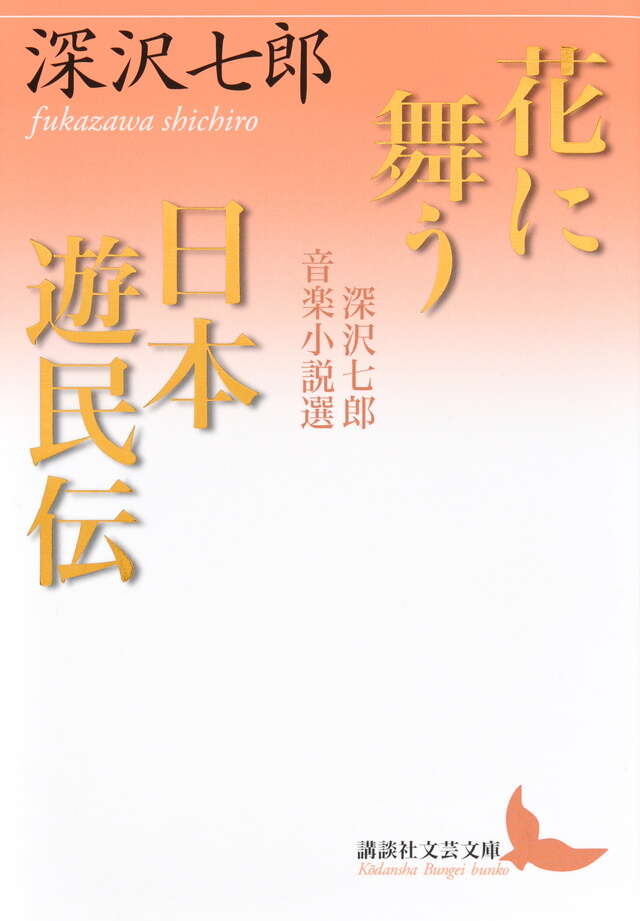
花に舞う・日本遊民伝 深沢七郎音楽小説選
講談社文芸文庫
時を越え人々の日常に寄りそうもの──。
「音」に着目し選びぬいた作品九篇。
演奏家でもあった著者の音楽を扱った小説集。「南京小僧」「浪曲風ポルカ」など気高い小品や「日本遊民伝」といった骨太作品も収録。
日劇ミュージックホールでの演奏など、ギタリストとしても活動した深沢七郎。エルビス・プレスリーを愛し、ジミ・ヘンドリクスを好んで聴いた彼の小説は音楽的と評されることも多い。その中から、俗謡、洋楽曲、楽団員といった、音楽を扱った作品を精選。著者の眼差しが見えてくる一冊。
※本書は、筑摩書房刊『深沢七郎集』(全十巻、1997年)を底本としました。

柄谷行人蓮實重彦全対話
講談社文芸文庫
予定調和なき言葉の世界へ
今なお世界へ向けて発信しつづける批評家・思想家が、1977年から約20年にわたって繰りひろげ、時に物議を醸したすべての対話を収録した、一時代の記録。文学、批評、映画、現代思想から言語、物語、歴史まで、ふたりの知性が縦横無尽に語り合う。
匿名性に守られたネット社会とは対極をなす、“諸刃の剣”の言論空間がここにある。
1977年から約20年にわたって行われた日本を代表する知性による全対話であり、今なお世界に発信し続ける二人の原点。完全保存版。
※本書は、『ダイアローグ』(1979年6月、冬樹社刊)、『ダイアローグ3』(1987年1月、第三文明社刊)、『闘争のエチカ』(1994年2月刊、河出文庫)、『群像』(1995年1月号)を底本といたしました。

ロッテルダムの灯
講談社文芸文庫
戦地における命あるものの美しさと儚さーー作家・庄野潤三の兄で、数多くの児童文学作品を世に残した著者が、従軍した中国や東南アジアで胸に刻まれた命あるものの美しさ、尊さ、儚さを、異国情緒をまじえて綴った初めての随筆集。戦中の思い出と戦後の日本、欧州とが絡まり、作者自らが「何よりも愛着深い作品」と述懐した、エッセイストクラブ賞受賞の名作。児童文学の大家である著者が、従軍した際の経験をまとめた名随筆集にして、弟の庄野潤三をして「英ちゃんのいちばんの名作」と言わしめた作品。
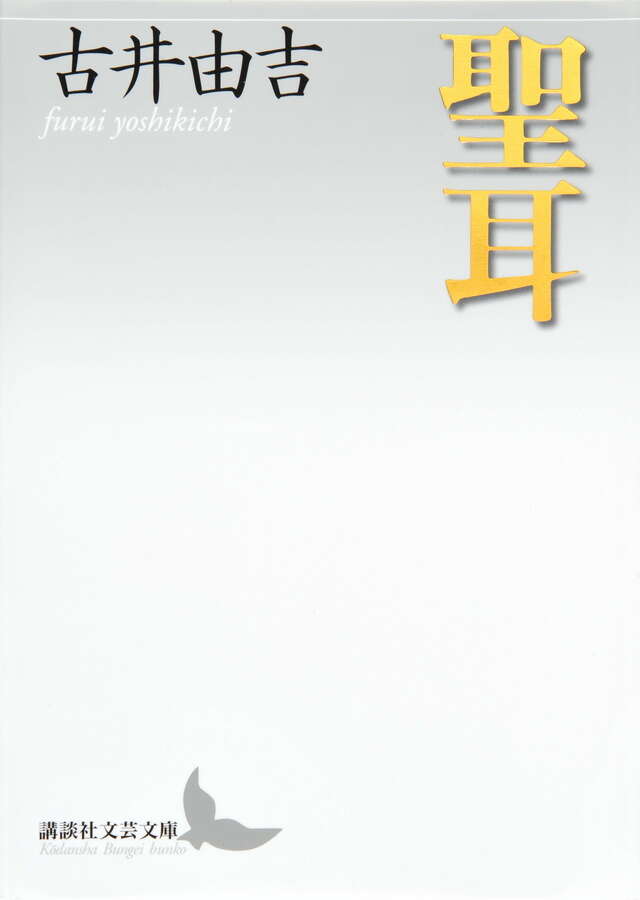
聖耳
講談社文芸文庫
眼の手術後、異様に研ぎ澄まされていく感覚の中で、世界が、時空が変貌を遂げていく。現代文学の極北を行く著者の真骨頂を示す連作集。「夜明けまで」「晴れた眼」「白い糸杉」「犬の道」「朝の客」「日や月や」「苺」「初時雨」「年末」「火の手」「知らぬ唄」「聖耳」
文学の可能性を拓く連作短篇集
骨の髄まで文学に浸る。
眼の手術後、異様に研ぎ澄まされていく感覚の中で、世界が、時空が変貌を遂げていく。現代文学の極北を行く著者の真骨頂を示す連作集。
※本書は、2000年9月刊『聖耳』(講談社刊)を底本としました。

折口信夫対話集 安藤礼二編
講談社文芸文庫
折口が語り合った日本の叡智たち。川端、犀星、小林秀雄、柳田国男、鈴木大拙……。
全集未収録も所載。
折口信夫の対話集。文学は北原白秋、川端康成、小林秀雄等と。民俗学は柳田国男等と。仏教・神道は鈴木大拙等との対談・鼎談を編纂。
※本書は中央公論新社『折口信夫全集』別巻3(1999年9月刊)、「鶴岡」第15号(1943年9月刊)、「悠久」第4号(1948年10月刊)を底本としました。

大東京繁昌記 山手篇
講談社文芸文庫
街歩きの歴史的名著
ひらけゆく街に秘かに残された、懐かしいたたずまい。
島崎藤村、高浜虚子、徳田秋声という大家が戦前の東京の町並みを舞台に競作。この巻は丸の内、小石川、早稲田など山手の作品を収録。
※本書は、春秋社『大東京繁昌記 山手篇』(1928年12月刊)を底本としました。

追悼の文学史
講談社文芸文庫
佐藤春夫、高見順、広津和郎、三島由紀夫、志賀直哉、川端康成――逝きし巨星への追悼文集。
<執筆者一覧>
阿川弘之、網野菊、石坂洋次郎、伊藤整、井上靖、上田三四二、江口渙、円地文子、大庭みな子、奥野信太郎、尾崎一雄、小田切進、上司海雲、亀井勝一郎、河野多惠子、佐多稲子、柴田錬三郎、瀬戸内晴美、高田博厚、瀧井孝作、武田泰淳、竹西寛子、田村泰次郎、檀一雄、丹阿弥谷津子、富沢有為男、中谷孝雄、中野重治、中村真一郎、新田潤、丹羽文雄、長谷川幸雄、平野謙、広津桃子、藤枝静男、舟橋聖一、本多秋五、松本清張、丸岡明、室生朝子、森茉莉、山本健吉、吉行淳之介(五十音順)
※本書は、『群像』(1964年7月号、1965年10月号、1968年12月号、1971年2月号、1972年1月号、同年6月号)を底本といたしました。