講談社文芸文庫作品一覧

遙かなノートル・ダム
講談社文芸文庫
「経験」することを哲学の領域に高めた思想家であり、深い思考を重ねたエッセイの名手でもあった著者のエッセンスが詰まった随筆集。
※本書は、角川文庫『遙かなノートル・ダム』(1983年11月)を底本としましたが、必要に応じて『森有正全集』第三巻(筑摩書房、1978年11月)を参照しました。

転々私小説論
講談社文芸文庫
仏文学が専門の学者・評論家であり、遊びや風俗から日本文化を独自に見つめていた多田道太郎は、私小説をこよなく愛していた。孤高の域にある、その語り口は軽妙かつ深遠で、「葛西善蔵の妄想」「諧謔の宇野浩二」「飄逸の井伏鱒二」「飄飄太宰治」と題された圧巻の文学評論4篇で、新たな視点から日本の私小説の真髄に迫る。

鉄道大バザール 上
講談社文芸文庫
アメリカの作家ポール・セルーが、贅沢にもローカル列車による世界の旅に、つまり、ドン行列車の旅に出た。世紀の大旅行を名訳で。
※本書は、『鉄道大バザール』(講談社刊・1977年)を底本といたしました。

夏目漱石論
講談社文芸文庫
「則天去私」「低回趣味」などの符牒から離れ、神話的肖像を脱し、「きわめて物質的な言葉の実践家」へと捉えなおしてまったく新しい漱石像を提示した、画期的文芸評論。
70年代後半、数多ある文芸評論とは一線を画し、読書界に衝撃を与えた斬新な漱石論。
三十数年を経た現在もなお挑発をやめない名著。
※本書は、1988年5月刊『夏目漱石論』(福武文庫)を底本とし、1978年10月刊『夏目漱石論』(青土社)を適宜参照しました。
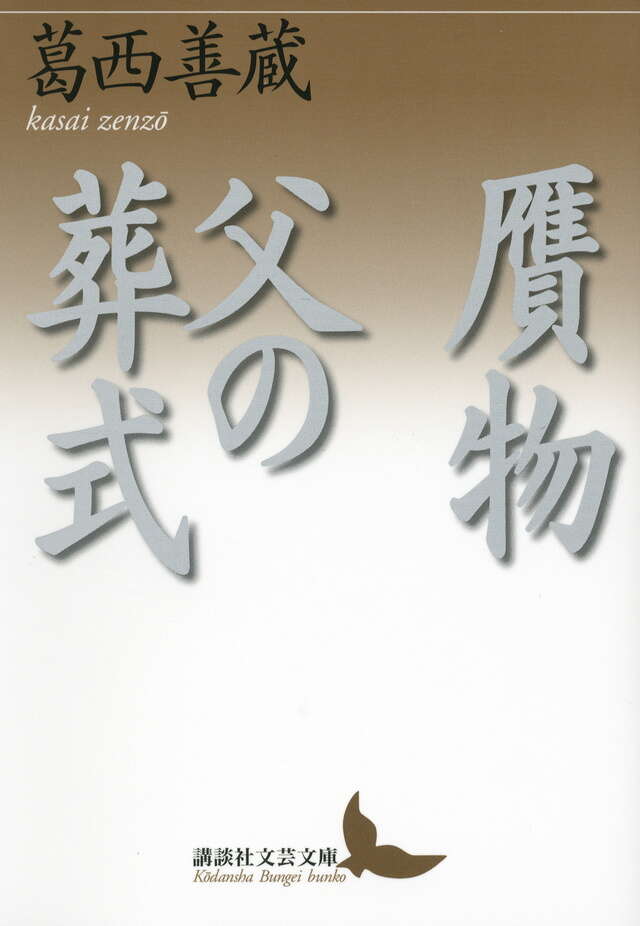
贋物・父の葬式
講談社文芸文庫
私小説作家にして破綻者の著者。彼の死とともに、純文学の終わりとまで言われた。その作品群は哀愁と飄逸が漂い、また、著者の苛烈な生き方が漂う。(講談社文芸文庫)
私小説作家にして破綻者の著者。彼の死とともに、純文学の終わりとまで言われた。
その作品群は哀愁と飄逸が漂い、また、著者の苛烈な生き方が漂う。
※本書は、文泉堂書店『葛西善蔵全集』第1~3巻(1974年10月刊)を底本としました。

個人全集月報集 安岡章太郎全集 吉行淳之介全集 庄野潤三全集
講談社文芸文庫
個人全集の中から、安岡章太郎全集・吉行淳之介全集・庄野潤三全集を選び、その月報に寄せられた名文を全網羅する。
珠玉の随筆集としても読める至福。
※本書に入っている作品は、講談社版『安岡章太郎全集』(1971.1~7)『吉行淳之介全集』(1971.7~1972.2)『庄野潤三全集』(1973.6~1974.4)の月報を底本といたしました。

地の果て 至上の時
講談社文芸文庫
紀州を舞台に圧倒的な物語を紡いだ現代文学の巨星が芥川賞受賞作『岬』、代表作『枯木灘』を凌駕すべく挑んだ最高傑作。
没後20年 <文学の力>が迸る
※本書は、1993年7月刊『地の果て 至上の時』(新潮文庫、初出は1983年新潮社刊)を底本としました。

プリューターク英雄伝
講談社文芸文庫
世界的名著であるプルタークの英雄伝を著者独自の視点で選び書き表した作品。
昭和5年という英雄願望が強い混沌とした時代が背景に。
※本書は、大日本雄弁会講談社『少年プリューターク英雄伝』(昭和5年3月刊)を底本とし、同『プルターク英雄伝』(昭和11年9月刊)を適宜参照にし、ふりがなを調整しました。
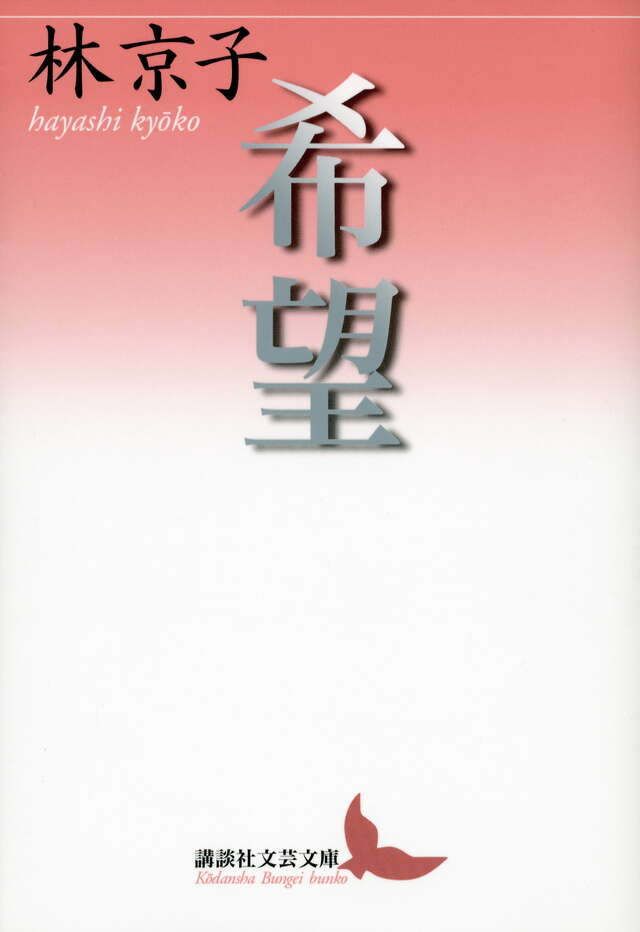
希望
講談社文芸文庫
1945年8月9日、長崎に投下された原爆によって、絶望が始まった。しかし、長い時間の末に、被爆者たちにも、一筋の光が見えた。もう悲劇を繰り返さないように。祈りの短篇集。
ーー8月9日、長崎で被爆した人たちの苦悩が始まった。生と死の狭間を体験し、未来への絶望との闘いの日々に、彼らは、時の流れで癒されていったのであろうか。自らの足跡を確かめ、振りかえり見つめ続けた著者が、いつかその運命を希望へと繋げていく……。3月11日を経験した、すべての日本の人々に捧げる、林京子の願いと祈りを込めた、短篇集。
※本書は、『谷間』(講談社刊 1988年1月)『希望』(講談社刊 2005年3月)を底本としました。
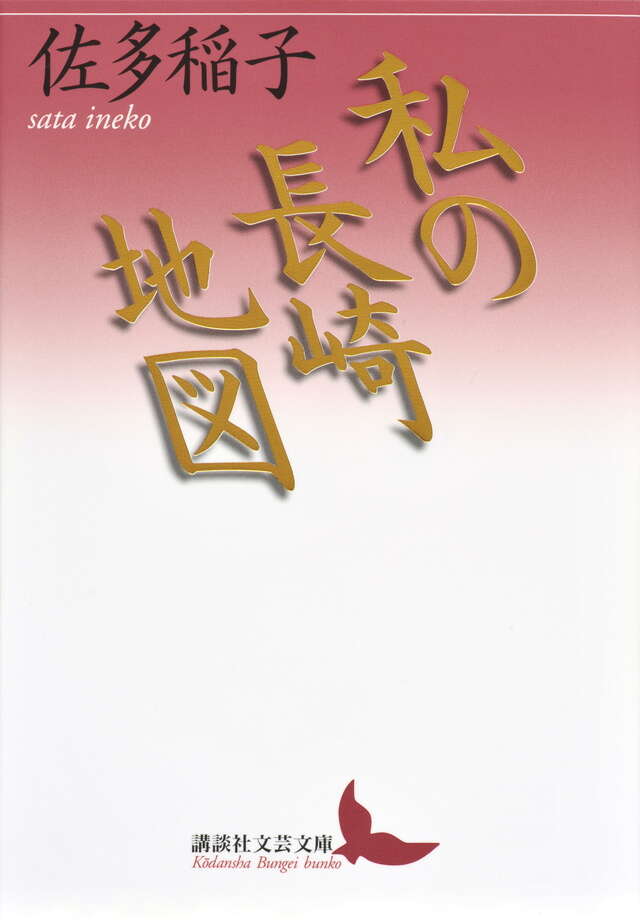
私の長崎地図
講談社文芸文庫
生まれ育った町を振り返りながら書き綴った「私の長崎地図」を中心に、筆者の長崎へ対する思いが溢れる小説、随筆を編纂した作品集。ーー生まれ故郷・長崎。しかし、そこは再訪するのに四半世紀の時を必要とした地でもあった。強い郷愁と訪れることへの不安が、町の色や海の香に彩られた過去から、現在に至る心の風景を紡ぎ出す。長崎を舞台にした「私の長崎地図」「歴訪」「色のない画」などの小説や随筆を精選したこの作品集は、『私の東京地図』と対をなす著者の魂の彷徨である。※本書は『佐多稲子全集』(講談社・昭和52年11月~昭和54年6月刊)、『小さい山と椿の花』(講談社・昭和62年10月刊)、『思うどち』(講談社・平成元年6月刊)を底本としました。

斎藤茂吉ノート
講談社文芸文庫
茂吉の短歌と人間と全力で格闘した不朽の名作。
太平洋戦争下に書きつがれた第一級の文学評論にして、感動的な「抵抗」の書でもある。
※本書は『斎藤茂吉ノオト』新版(筑摩書房、1943年刊。初版は1941年)に『中野重治選集7』(筑摩書房、1948年刊)の「はしがき」を加えたもので、『斎藤茂吉ノート』(ちくま学芸文庫、1995年刊)を底本といたしました。
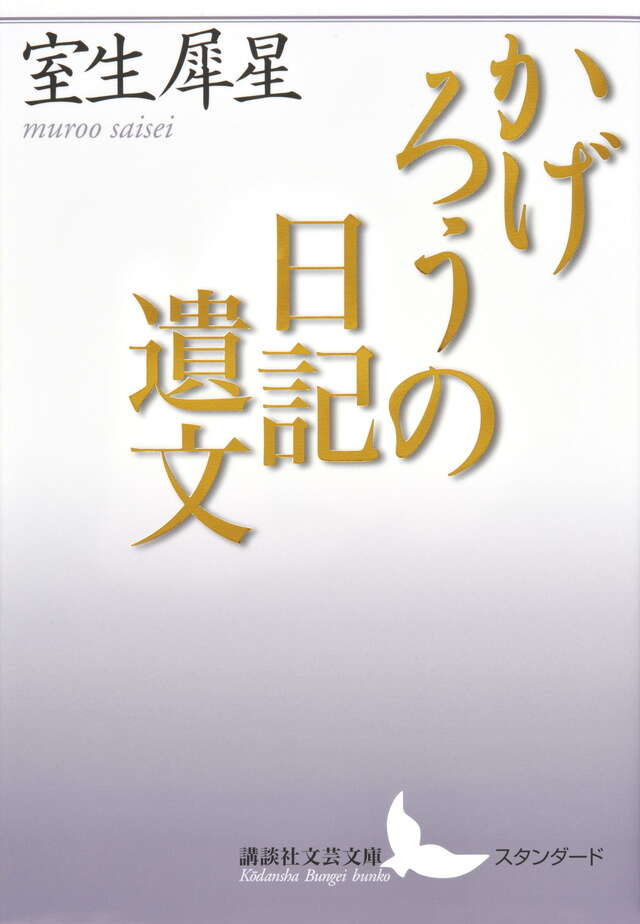
かげろうの日記遺文
講談社文芸文庫
生母への想いを『蜻蛉日記』の書き手・紫苑の上や下賤の女・冴野に投影。「言語表現の妖魔」といわれた犀星の女性への思慕を描いた名篇。
生母への想いを『蜻蛉日記』の書き手・紫苑の上や下賤の女・冴野に投影。
「言語表現の妖魔」といわれた犀星の女性への思慕を描いた名篇。
※本書は『日本現代文学全集61 室生犀星集』(増補改訂版 1980年5月 講談社刊)を底本としました。

早稲田作家処女作集
講談社文芸文庫
「作家の運命は、処女作によって決定される」(序文より)
青野季吉、谷崎精二監修による早大出身・中退作家アンソロジー。
正宗白鳥「寂寞」 中村星湖「町はずれ」 吉田絃二郎「蜥蜴」
加能作次郎「恭三の父」 牧野信一「爪」 中河与一「氷る舞踏場」
横光利一「御身」 井伏鱒二「山椒魚」 浅見淵「山」
逸見広「死児を焼く二人」 尾崎一雄「早春の蜜蜂」
丹羽文雄「鮎」 八木義徳「海豹」 宮内寒弥「蜃気楼」
井伏鱒二
私は早稲田に入学した翌年の夏休暇に、この山椒魚をモデルにして習作を書いた。しかし実体の山椒魚は餌にもらった蛙など見ると、がぶりと一とくちに食ってしまう。空腹になると自分の手をたべることがある。だから、この小説では山椒魚の生態を部分的に無視しているところがある。――<「『山椒魚』について」より>
※本書に入っている作品は、すべて『現代作家処女作集 早稲田作家篇 第一集』(潮書房・1953年刊)を底本といたしました。
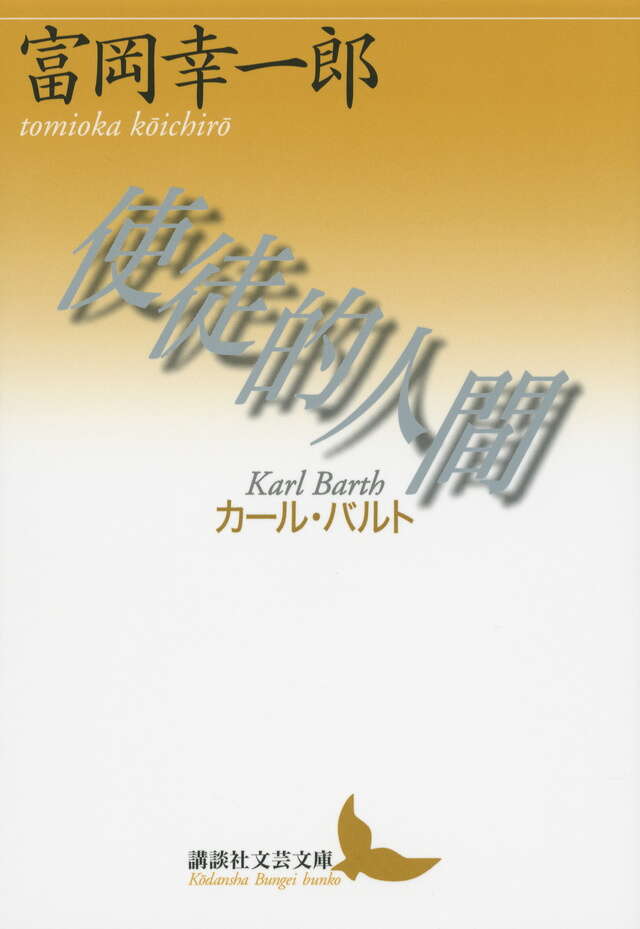
使徒的人間──カール・バルト
講談社文芸文庫
聖書のもつダイナミズムを解き放ち、人間の救済を志向する。
理性への信頼に基づく近代主義、あるいは人間中心主義を根底とした自由主義神学の内部から、それを打ち破るかのように登場したカール・バルト。神学を人間学へと解消する潮流に抗し、キリストと行動をともにした使徒によるドキュメントとして聖書をとらえ、神の言葉と啓示がもつ直接性の復活を果たす。使徒という存在に近代の超克を読みとり、来るべき人間として思想と文学の起点にすえる、画期的な長篇評論。
佐藤優
使徒は、人間を救済するという自覚を持つ人間だ。この救済は、個別具体的である。救済の一般理論は存在しない。(略)神の存在が生成において人間に理解されることに対応し、富岡氏の思想的営為も常に生成過程にある。イエス・キリストという名に徹底的に固執することによって、日本人の歴史物語、特に天皇と救済の関係について、いつか適切な言葉が見つかることを信じながら、富岡氏は評論活動を展開しているのだと私は見ている。――<「解説」より>
※本書は、講談社刊『使徒的人間――カール・バルト』(1999年5月)を底本として使用しました。

私小説名作選 下
講談社文芸文庫
破滅型から第三の新人へ、現代に繋いだ「私小説」を読み解く。
いわゆる「私小説」への批判に対して、多くの愛着をもった読者は、その世界の中に迷い込み、取り付かれ、魅せられていった。
藤枝静男・大岡昇平・島尾敏雄・水上勉・安岡章太郎・庄野潤三・遠藤周作・吉行淳之介・田中小実昌・三浦哲郎・高井有一の名短篇に加えて、中村光夫と水上勉による対談解説「私小説の系譜」収録。
<収録作品>
藤枝静男 「私々小説」
大岡昇平 「歩哨の眼について」
島尾敏雄 「家の中」
水上 勉 「寺泊」
安岡章太郎 「陰気な愉しみ」
庄野潤三「小えびの群れ」
遠藤周作 「男と九官鳥」
吉行淳之介 「食卓の光景」
田中小実昌 「魚撃ち」
三浦哲郎 「拳銃」
高井有一 「仙石原」
※本書に入っている作品は、すべて『私小説名作選』(集英社文庫・1980年刊)を底本といたしました。
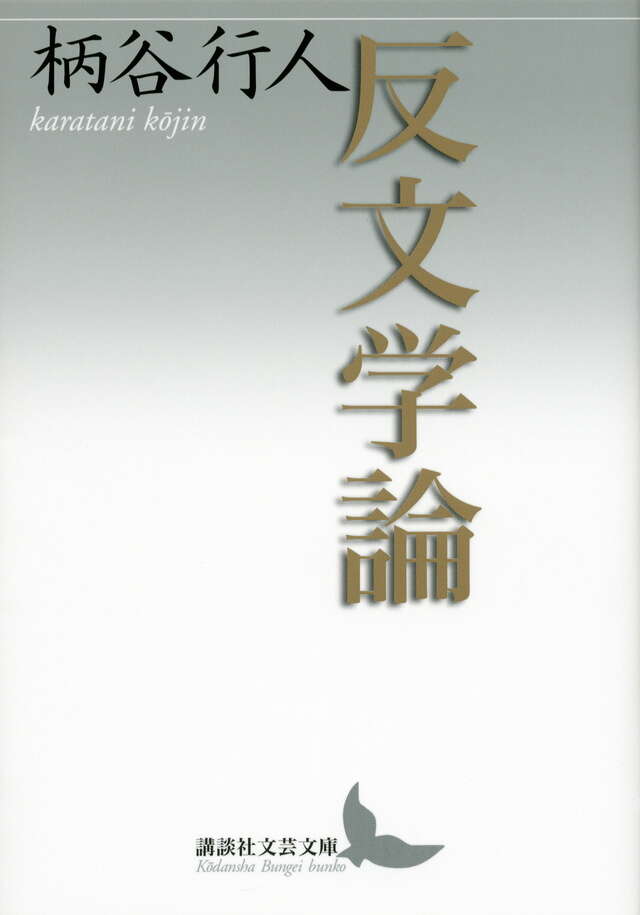
反文学論
講談社文芸文庫
抜群におもしろい文芸時評の白眉ーー1977年から78年にわたり、初期代表作となる『マルクスその可能性の中心』、『日本近代文学の起源』と並行して書かれた、著者唯一の文芸時評集。100人近い現役作家を俎上に載せた短い<時評>と<感想>に、この類稀な批評家のエッセンスが凝縮し、横溢する。転換期に立つ「近代文学」の終焉を明瞭化した記念碑にして、これから文学にかかわる者の、必読の書。
◎「……この『反文学論』は、著者の批評活動すべてが圧縮されたものだと言える。読者は、本書に対して、まるで「柄谷行人」という映画の予告編をみているような印象をもつであろう。そのことを可能としているのは、ひとえに本書が「文芸時評」という制約を受けていることによるのだ。」<池田雄一「解説」より>
※本書は、1991年11月『反文学論』(講談社学術文庫)を底本としました。

私小説名作選 上
講談社文芸文庫
近代日本文学の輝石
田山花袋から、といわれる「私小説」の軌跡をたどる。
近代日本文学において独特の位置を占める「私小説」は、現代に至るまで、脈々と息づいている。文芸評論家・中村光夫により精選された、田山花袋・徳田秋声・近松秋江・正宗白鳥・志賀直哉・嘉村礒多・梶井基次郎・太宰治・梅崎春生・井伏鱒二・尾崎一雄・上林暁・木山捷平・和田芳恵・井上靖
文学史を飾る作家十五人の珠玉の「私小説」の競演。
<収録作品>
●田山花袋「少女病」
●徳田秋声「風呂桶」
●近松秋江「黒髪」
●正宗白鳥「戦災者の悲しみ」
●志賀直哉「城の崎にて」
●嘉村礒多「崖の下」
●梶井基次郎「檸檬」
●太宰 治「富獄百景」
●梅崎春生「突堤にて」
●井伏鱒二「鯉」
●尾崎一雄「虫のいろいろ」
●上林 暁「ブロンズの首」
●木山捷平「耳学問」
●和田芳恵「接木の台」
●井上 靖「セキセイインコ」
※本書に入っている作品は、すべて『私小説名作選』(集英社文庫・1980年刊)を底本といたしました。

折口信夫芸能論集
講談社文芸文庫
祝祭の中で人は神となる
折口三部作堂々の完結
『文芸論集』『天皇論集』に続く編者安藤礼二によるオリジナル編集折口信夫第三弾は『芸能論集』。折口による民俗学は芸能を根幹としており、その起原は、沖縄をはじめとした南の島々にあり、さらに信州などの山深い地で洗練され、能や歌舞伎、詩歌へとつながっていく――。日本の英知・折口信夫の三部作、ここに堂々の完結。
安藤礼二
マレビトという、折口信夫が創り上げた概念もまた、一年に一度、祝祭をもたらすために共同体を訪れる、神であるとともに人でもあるような存在を指す。一年で最も厳しい季節を迎え、世界がやせ衰え「死」に直面したとき、神であり人であるマレビトが訪れ、時間も空間も生まれ変わり、世界は豊饒な「生」を取り戻す。世界が死に、世界が再生される瞬間、激烈な力が発生し、解放される。――<「解説」より>
※本書は中央公論社刊『折口信夫全集』17、18、21、22、28、別巻1(1996年8月、1997年11月、1996年11月、12月、1997年6月、1999年1月)を底本としました。

鷹
講談社文芸文庫
おひとよしらしい巡査ではあったが、巡査の復讐はおそろしい。今度見つかったらば百年目である。もうその靴音が背後に迫って来るようであった。いや、ばたばたという靴音を聞いた。「謀叛人。」その声が巷に木魂した。「おれは追跡されている。」足は夢中で駆け出していた。しかし、どこへ。不安は自分の顔にはっきり描いてあるだろう。
「万人の幸福のために」もっと上等のたばこを作りたいと考えたために、主人公はたばこの専売公社を追われ運河のほとりの妖しい秘密たばこ工場で働くことになる。さらには未来がわかってしまう明日語を学習させられ……。表題作「鷹」のほか「珊瑚」「鳴神」を収録。深遠なる幻想と独特のリズムの文体をもって痛烈に社会と世相を批判し、今日の抵抗を明日の夢へとつなぐ作品集。
鷗外・漱石・荷風の後、今日に到って、短い序・跋の文の朗々として誦ずべきものをつくることができるのは、おそらくただ一人の石川淳だけかもしれない。――<加藤周一「石川淳または言葉の力」より>
※本書は、「増補 石川淳全集」第4巻(昭和49年5月、筑摩書房刊)を底本としました。

さして重要でない一日
講談社文芸文庫
未知の空間、会社という迷路を彷徨う主人公。トラブル、時間、おしゃべり、女の子、コピー機。著者独特の上品なユーモアの漂う、なにか、もの哀しくも爽やかな空気の残像。会社員の日常を鮮やかに切り取った、野間文芸新人賞受賞作。サラリーマンの恋と噂と人間関係、奇妙で虚しくて、それでも魅力的な「星の見えない夜」も所収。
会社員の日常を鮮やかに描いた魅力的な小説二篇。
未知の空間、会社という迷路を彷徨う主人公。トラブル、時間、おしゃべり、女の子、コピー機。著者独特の上品なユーモアの漂う、なにか、もの哀しくも爽やかな空気の残像。会社員の日常を鮮やかに切り取った、野間文芸新人賞受賞作。サラリーマンの恋と噂と人間関係、奇妙で虚しくて、それでも魅力的な「星の見えない夜」も所収。
柴田元幸
だが伊井直行は、どこにでもある普遍的な会社像を描こうとしたのではない。伊井直行の小説を読んでいていつも感じることだが、彼の描くものは、社会であれ会社であれ、類型的なイメージを意識しつつも、類型から時として微妙に、時としてあからさまにずれるように描かれている(そこから独特の、味わい深いユーモアも生じている)。――<「解説」より>
※本書は、講談社刊『さして重要でない一日』(1989年9月)と講談社刊『星の見えない夜』(1991年8月)を底本としました。