健康ライブラリー作品一覧

漢方でアレルギー体質を改善する
健康ライブラリー
病院で改善しないアトピー、ぜんそく、花粉症に朗報!漢方の中医師が処方するアレルギー体質の改善と根治とは?
【主な内容】
●チェックリスト あなたはどの体質?
●アレルギーは、どの体質の人がなるのか
●アレルギー性疾患と漢方の関係
●アレルギー性鼻炎・花粉症について
●アトピー性皮膚炎について
●ぜんそくについて
●湿疹・じんましんについて
●漢方で改善した症例集
●日常生活でアレルギーを寄せ付けない法

アスペルガー症候群(高機能自閉症)の子どもを育てる本 学校編
健康ライブラリー
ひと目でわかるイラスト図解
《講談社 健康ライブラリーイラスト版》
【学校生活でのアドバイスと注意点が満載】
アスペルガー症候群の子の多くが学校生活に強いストレスを感じている。
本書では科目ごとの教え方のポイントから係や当番の対応、気になる進学のことまで、学校生活の様々なシーンでのアドバイスと注意点を紹介。
教育現場で役立つ必読書。
(まえがきより)
本当の意味で支援をするためには、子ども一人ひとりの特性と、彼らの気持ちを理解する必要があります。同じアスペルガー症候群の子でも、行動様式は一人ひとり違います。型通りの支援では、彼らの悩みに対応しきれないのです。
本書には、子どもたちが学校生活のなかでどのような点に困難を感じているのか、そして、どう対処していけばよいのかということを解説してあります。(中略)
だれにも相談できず、不安な人こそ、本書を読んでほしいと思います。相談する前に、いますぐできることがあるのです。子どもの行動をよくみて、その子の本当の気持ちによりそうように対応することです。子どもを理解すること、すべてはそこからはじまります。そのために本書が役立てば、大変うれしく思います。(佐々木正美)
【本書のおもなポイント】
●他人の気持ちが想像できないアスペルガーの子ども。ケンカを減らして、友達を増やすには
●発達障害のことをクラス全員に伝える方法
●TEACCHを教育現場にとり入れる――国語・社会・算数・英語など科目別アドバイス
●授業での対応の差が、劣等感につながらないように注意
●一人ひとりにあった一日のスケジュールの立て方と教え方
●給食・掃除の時間を守ってもらうには
●受験勉強や高校、大学への進学はできるのか
【本書の構成】
第1章 アスペルガー症候群の子の学校生活
第2章 ケンカを減らして、友達を増やすには
第3章 イラスト要素で授業の理解力アップ
第4章 係・当番・部活動のトラブル予防法
第5章 現実的に、進学はできるのか

自己愛性パーソナリティ障害のことがよくわかる本
健康ライブラリー
社会の変化に伴って、患者数は増加の一途!
他人に全く無関心。愛しているのは自分だけ。共感性のなさゆえに周囲の人を悩ませ続ける
【主なポイント】
●自己愛性パーソナリティ障害は健康な人間関係を築けないという障害
●根本にあるのは「愛しているのは自分だけ」という思い。タイプは2つで、両極端な現れ方をする
●〔周囲を気にかけないタイプ〕極端に自己中心的。他者からの賞賛を求めるが、他者への配慮はなく、傲慢・不遜な態度が目立つ
●〔周囲を過剰に気にするタイプ〕気にしているのは他者の目にうつった自分の姿。内気にみえるが、尊大な自己イメージをもっている
●価値観、家族関係など社会の変化に伴って、患者数は増加の一途
●多くの年代にみられるが、ほかのパーソナリティ障害に比べ中年層に多い
●批判や説教は禁物! 家族や周囲の人たちがとるべき好ましい対応法

PTSDとトラウマのすべてがわかる本
健康ライブラリー
フラッシュバックや感情のまひ……
症状の悪化をどう防ぎ、社会復帰するか。トラウマへの対処とPTSD治療の実際
【主なポイント】
●トラウマは心の傷。さまざまなトラウマ反応の一部がPTSDに
●きっかけは、予測できない災害や事故、暴力や性犯罪など
●いじめや虐待が子どものトラウマを引き起こす
●PTSDの中核症状は「再体験」「回避・まひ」「過覚醒」の3つ
●PTSD・トラウマは治療を受ければ治るのか?受診のめやすと診断基準
●治療方法は、認知行動療法・薬物療法・EMDRが中心
●認知行動療法は嫌な記憶と正面から向き合い、ゆがんだ考え方を治す
●家族や友人にできるサポートの基本と注意点

新版 痔と上手につきあう本
健康ライブラリー
痔イコール手術ではない! 切らずに治す方法がある!
痔の名医が日常生活での正しいケアから薬の使い方、最新療法までをやさしく解説。
【主な内容】
●痔はだれにでもある
●痛い! 出血した! 肛門からなにか出ている! ときの応急処置
●痔の診察はこわくない。医師選び・診察の前知識
●便秘・下痢を解消する
●お尻をいたわる暮らし方
●薬の上手な使い方
●痔核の新しい治療法、PPHとジオン注
●じつは大腸ガンでは?

「ふるえやけいれん」がよくわかる本
健康ライブラリー
手がカタカタふるえる
目のまわりがピクピクけいれんする
足が急につって痛くて歩けない
こんな症状が毎日続いて不自由さを感じるようになった人へ
【主な内容】
●「ふるえやけいれん」が気になりはじめたら
●顔に「ふるえやけいれん」があらわれたら
●くびや肩に「ふるえやけいれん」があらわれたら
●手や腕に「ふるえやけいれん」があらわれたら
●足や膝に「ふるえやけいれん」があらわれたら
●全身に「ふるえやけいれん」があらわれたら
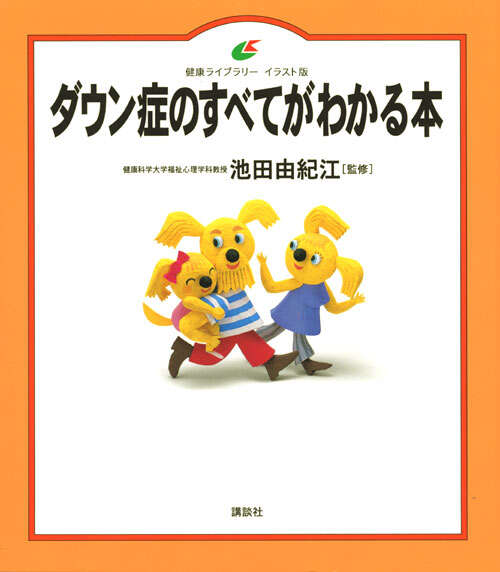
ダウン症のすべてがわかる本
健康ライブラリー
ダウン症の赤ちゃんはおとなしく、発達がゆっくりという特徴があります。そのため周囲とのかかわりが少なくなり、発達が促されないという二次的な問題が起こります。本書では、知っておきたい基礎知識から発達を促すための早期療育、日常生活の育ての工夫まで、イラスト入りでわかりやすく解説します。お子さんとご両親、そして養育にかかわるすべての人の助けになる、ダウン症の子どもを育てる上で欠かせない情報を網羅した一冊。
ひと目でわかるイラスト図解
《講談社 健康ライブラリーイラスト版》
【ダウン症の疑問に正しく答える!】
ダウン症の正しい知識から、発達をうながすために重要な早期療育までをイラストでやさしく解説。
また日常生活での育ての工夫や、合併症への対処の方法など、ダウン症の子どもを育てる上で欠かせない情報も網羅。
(まえがきより)
ダウン症の赤ちゃんはおとなしく、発達がゆっくりという特徴があります。こうした特徴によって周囲とのかかわりが少なくなるために、発達がうながされないという二次的な問題が起こることが少なくありません。この本では、ダウン症の子どもの特徴と、発達をうながすための早期療育について紹介しています。
また、日常生活でできる育ての工夫、合併症の基礎知識など、ダウン症の子どもを育てるうえで欠かせない情報を網羅しています。
この本が、ダウン症の子どもとご両親、そして養育にかかわるすべての人の助けになれば幸いです。
【主なポイント】
●ダウン症は「病気」とは異なる点が多い。発達はゆっくりで、個人差も大きい
●ダウン症に多く見られる合併症、かかりやすい感染症などトラブルの早期発見と対処法
●「早期療育」は病院や福祉センターなどで指導を受け、実践は家庭で
●おとなしく、なかなか反応しない赤ちゃんへの語りかけのポイント
●ダウン症の赤ちゃんに楽しく、正しく食べさせる食事のコツ
●離乳食やトイレのしつけなどの自立訓練を始める目安は?
●学童期の子どもへの、家族だから気をつけたい正しい見守り方
●社会生活を送るうえで利用できる支援制度とサービス
【本書のおもな構成】
《第1章 知っておきたい基礎知識》
ダウン症は病気?/発見と診断/進路 他
《第2章 育ちの手助け・早期療育》
どこでできる?/体を動かす/言葉の練習/文字の練習/数を覚える 他
《第3章 家庭でできること》
語りかけ/食事/進路選択 他
《第4章 健康管理のポイント》
定期検査/心臓の病気/消化器の病気/目の病気/適応障害 他
《第5章 ダウン症の疑問に答える》
原因は?/支援は?/相談先は? 他

森田療法のすべてがわかる本
健康ライブラリー
ひと目でわかるイラスト図解
《講談社 健康ライブライリーイラスト版》
【森田療法の理論と実践方法のすべて】
近年海外での評価も高く注目されている森田療法。
うつ病や神経症などの根底にある悩みの構造を紐解き、実際の治療の流れを詳しく解説します。
自身の生き方を探り、不安と悩みを解決。治療のゴールは「あるがまま」の自分です。
[まえがきより]
人生に悩みはつきものですが、共存することはできます。それができないのは、生き方、考え方に無理があり、悩みを拡大させてしまっているからです。森田療法は拡大した悩みの背景にある生き方、考え方に着目します。こうした森田療法の悩みのとらえ方が、不自然な生き方が増えているいまの時代に、改めて必要とされているのです。本書は、このような森田療法の理論をわかりやすくまとめたものです。
【本書のおもなポイント】
●森田療法は、日本で生まれた精神療法。原因探しに終始する西洋の精神療法とは異なる
●人はなぜ悩むのか――森田療法で考える悩みのメカニズム
●悩みを深める、感情の法則と陥りやすいワナ
●治療の原則は自分の陥っている悪循環を知ること
●薬に頼らず、考え方や行動を変える。治療のゴールは「あるがまま」の自分
●森田療法で慢性化した「うつ」から脱出し、再発を防ぐ
●不登校・ひきこもり、ターミナルケアにも有効。海外での評価も高い
●森田療法を受けられる専門クリニック、病院はここ
【本書のおもな内容】
《1.森田療法とはなにか》
【森田療法とは】【これからの展開】
《2.人はなぜ悩むのか》
【悩みのメカニズム】【悩む人の性格特徴】【感情をもてあます】
《3.治療の原則は事実を知ること》
【治療の原則】
《4.いろいろな治療方法がある》
【受診】【外来療法】【日記療法】【入院療法】【自助グループ】
《5.森田療法で「不安」と「うつ」を治す》
【生き方へのとらわれ】【うつとは】【うつの回復】
【体へのとらわれ】【不安へのとらわれ】【観念へのとらわれ】
【対人関係の恐怖】【対人関係への依存】
【不登校・ひきこもり】【ターミナルケア】

依存症のすべてがわかる本
健康ライブラリー
ひと目でわかるイラスト図解
《講談社 健康ライブラリーイラスト版》
【やめたくても、やめられない! 依存症とはなにか】
家族を犠牲にし、心身をむしばむ依存症。始まりは底知れないさびしさから。
本書では対人依存、プロセス依存、物質依存の心理を追究し、「生き方の病」から回復するルートを探る。
【本書の主なポイント】
●なにかに依存せずにいられないのは、底知れないさびしさを埋めるため
●家族や周囲に迷惑をかける依存症は、治療がかかせない生き方の病
●人とかかわるなかで安心したい「対人依存」
●「○○していれば幸せ」――仕事依存、買い物依存症などの「プロセス依存」
●深刻な結果につながりかねないアルコール依存症、むちゃ食い依存などの「物質依存症」
●「どん底」を見せる家族の覚悟が、本人を変える再生への第一歩
●ヨコのつながりが得られる自助グループへの参加は最も重要な治療法
【本書の構成】
第1章 「どうしてもやめられない」――依存症とはなにか
第2章 「人とかかわるなかで安心したい」――対人依存
第3章 「○○していれば幸せ」――プロセス依存
第4章 「食べたい、飲みたい」――物質依存症
第5章 結果は本人が引き受ける――回復へのルート

不登校・ひきこもりの心がわかる本
健康ライブラリー
ひと目でわかるイラスト図解
《講談社 健康ライブラリーイラスト版》
【現状から抜け出すヒントが満載】
100万人以上が悩んでいるといわれる不登校・ひきこもり。
どうして外に出られないのか? 本人は何を悩んでいるのか? 子どもの心理状態をイラスト図解。
八方塞がりの現状から抜け出すヒントが満載の一冊。
(まえがきより)
不登校・ひきこもりの問題で悩んでいる人にまず伝えたいのは「あせらないでください」という言葉です。
悩みを抱える本人はもちろん、周囲で見守っている家族や教師も、問題の解決を急がないことが大切です。学校や職場に行かなければならない、行かせなければならないと考えて、急ぐのはやめましょう。あせればあせるほど、精神的に追いつめられ、状況が悪化します。
学校や職場に通い続けることだけが人生ではありません。それだけに固執してあせるのはやめて、少し休みましょう。
不登校でも、ひきこもりでも、最終的に自分のやりたいことを、自分にあった方法でできるようになればいいのです。それをゆっくり探すことにしてください。
【本書の主なポイント】
●不登校とひきこもりは、同じことではない
●不登校のおよそ3割がひきこもりになる
●うつ病、強迫性障害にかかっている場合も
●登校したがらない子には、どう話しかける?
●強い励ましは、かえって萎縮させてしまう
●教師が家庭訪問をするとき、家族・本人に伝えるべきこと
●不登校の人の約8割が5年後に就学・就労している
●自助グループや親の会が大きな助けに
【本書の構成】
第1章 どうして外に出られないのか
第2章 本人はなにを考え、悩んでいるか
第3章 八方塞がりの家族へのアドバイス
第4章 人生を変える一歩のふみ出し方
第5章 医師・心理士に期待できること

抜かず、削らず歯を治す
健康ライブラリー
歯科治療に新しい時代が到来!
健康な歯を残す最新治療!
コンポジットレジン接着修復法なら歯周病でグラグラする歯も抜かずに治せる。歯を削らないでブリッジをつくることも可能に。
【主な内容】
●健康な歯を残す新しい治療法、コンポジットレジン接着修復
●接着修復は、なぜ削らずに治せるのか?
●10年以上たっても経過は良好! 写真と症例で見る接着修復
※まったく歯を削らずに、歯の形を整えたり、すき間をなくしたりできる
※隣の歯を削らずにブリッジをつくる
※歯周病でグラグラする歯も抜かずに治す
※ほとんど削らず虫歯をきれいに治す
●健康な歯を守るために知っておきたいこと

新版 外反母趾を防ぐ・治す
健康ライブラリー
足の親指が「く」の字になっていませんか?
外反母趾を予防するには、先の細いきゅうくつな靴やハイヒールをはかないこと。外反母趾かどうかは、足の親指の曲がった角度、すなわち外反母趾角で決まる。いったん足の親指が一定の角度以上に曲がると指の曲がりが指を曲げる悪循環に。外反母趾を悪化させないためには、「ホーマン体操」を1日10分、3回が効果的。慢性関節リュウマチや膠原病など他の病気で外反母趾になることがある。
<外反母趾のことがわかる! Q&A>
●外反母趾はどこに行ったら診てもらえますか?
●どこに行ったら自分に合った靴が買えますか?
●年をとると、外反母趾は進むのですか?
●外反母趾ですが、歩いた方がよいですか?
●外反母趾の治療に健康保険は使えますか?
●運動で予防できますか?
●手術をした方がよいか自己判断できますか?
●手術は何歳までできますか?

知的障害のことがよくわかる本
健康ライブラリー
生まれてきた子どもに知的障害があると診断されたら……。その子が社会にでるためには多くの困難があります。知的障害がある子どもは、日常生活のささいなことができなかったり、いろいろな病気にかかりやすかったりします。本書では、子どもとどのように接すればよいか、どのような支援があるか、正しい知識から社会支援まで具体的に解説しています。ひとりで悩まず、一歩を踏み出すために役立つ一冊です。
ひと目でわかるイラスト図解
《講談社 健康ライブラリ-イラスト版》
【ひとりで悩まず不安を解消】
できることは何か、どう育てればよいか。
ひとりで悩まず、一歩を踏み出すために役立つ一冊。
正しい知識から社会支援まで徹底解説。
[まえがきより]
生まれてきた子どもに知的障害があると診断された場合、その子をどのようにして社会の一員として送りだせるかということが問題になります。しかし、社会にでるためには多くの困難があります。知的障害がある子どもは、日常生活のささいなことができなかったり、いろいろな病気にかかりやすかったりするからです。そのため、お父さんやお母さんは深く悩んでしまうのです。本書では、このように悩んでいるお父さんやお母さんのために、子どもとどのように接すればよいか、どのような支援があるかについて具体的に解説しています。
【本書のおもなポイント】
●知的障害を判断する3つの基準
●知的障害の原因の約8割が出生前に発生している
●特徴はことばが覚えられない、物事を記憶できない、動きがぎこちなく、細かい作業が苦手など
●障害は幼いころほど気づきにくい。定期的な「健診」が早期発見に
●子どもの基礎能力を養うための療育法
●就学先を選ぶときの確認すべきポイント
●自立を助ける社会支援と地域サービスの利用のしかた
●差別やいじめ、将来について……不安を解消するQ&A
【本書のおもな内容】
理解度テスト
《1.知的障害への理解を深める》
知能の発達 知的障害とは 感覚 原因 合併症 特徴
《2.ひとりで悩まず、周囲の協力で不安を解消》
早期発見 検査 療法 相談機関
《3.子どもとむきあうために》
家族 環境 行動 ほめる しかる 工夫 生活習慣 問題行動
《4.子どもをささえる社会制度》
施設 統合保育 学校 連携 就労 地域生活 保護者 自立支援制度 家族のケア
《5.心配・不安を解消するQ&A》
人権 遊び場 遺伝相談 病院 将来 苦情解決 兄弟姉妹 性教育

ビジネスマンの心の病気がわかる本
健康ライブラリー
職場での不安と悩みをイラスト図解!
うつ、対人恐怖、パニック発作……。仕事にかかわる心の不調を徹底解説!
【主なポイント】
●出勤できない……。うつ病、社会不安障害、テクノストレス症候群など原因として考えられる11の主な病気
●新入社員がかかりやすい心の病気、管理職がかかりやすい心の病気
●心の病気による労災認定が増えている
●休職するタイミングと復職時の注意点
●いまある仕事をどうする? 休職中の給与、待遇はどうなる?
●どんなサインがSOS? 心の病気の克服にはまわりの協力は欠かせない
●上司、同僚、部下、それぞれが心がける言葉かけ
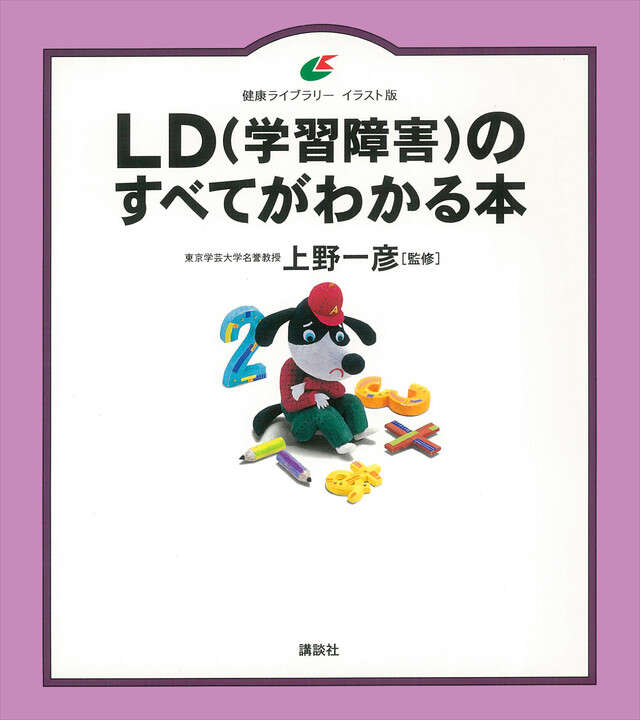
LD(学習障害)のすべてがわかる本
健康ライブラリー
LDは学習障害で発達障害の一つです。タイプはいろいろありますが、もっとも多いのは読み・書き・算数が苦手なタイプ。LDの子どもたちは「ほかの子と同じようにできない」だけであって、自分に合ったやり方であればできるようになります。本書では、子どもがLDかもしれない、あるいはLDだと言われたときに知っておきたい基礎知識をはじめ、家庭での接し方から特別支援教育と具体的な指導法までくわしく解説します。
どういうふうに教えればいいの?
家庭での接し方から特別支援教育まで、図解でわかる、はじめてのLD入門書。
【主なポイント】
●LDは学習障害で発達障害の1つ。しつけや遺伝が原因ではない
●小・中学生の4.5%にLDの傾向。就学してから初めて気づくことも
●タイプはいろいろ。もっとも多いのは読み・書き・算数が苦手な子ども
●言葉の使い方、聞きとり方にかたよりがある
●友達同士のルールがわからない・守れない
●運動が苦手で、不器用な子どももいる
●特別支援教育が始まって、LD教育はどう変わる?
●家庭に勉強を無理に持ち込まない、しつけのポイントと接し方

発達障害に気づいて・育てる完全ガイド
健康ライブラリー
《講談社 健康ライブラリースペシャル》
【小学生対象=先生・保護者がすぐに使える記入式シートつき】
発達障害はかならず改善できる!
2007年度からの特別支援教育に対応!
教育現場の「困った!」に応えて専門家がつくった、初めての記入式シートと実例集で、子どもの傾向と接し方がわかる
(まえがきより)
学校では、子どもたちの言動が、性格によるものなのか、障害によるものなのかの判断に迷うケースも多く、先生の判断しだいで、対応もかなり異なったものになる可能性があります。本書でも解説するように、障害のある子どもたちへの対応しだいでは、不登校や非行などの二次的な障害を引き起こし、問題をさらに深刻にすることもあるのです。診断も対応も手探りで、困惑する先生方も少なくありません。
そこで長年の研究をもとに、現場の先生方や保護者が子どもの傾向を確実に把握できる「行動と学習に関する基礎調査票」(以下、基礎調査票と表記)および、その結果をわかりやすく表示する「評価シート」を作成しました。
本書の目的は発達障害の有無をチェックすることではありません。子どもの特性を正確に把握することが、具体的な対応策につながります。子どもたちとご両親の悩みや苦しみに、周囲が早く気づいて、適切な支援が受けられるようにするのが目的です。(黒澤礼子)
発達障害の子どもが、全国に69万人!?
●席に座っていられない
●思い通りにならないとパニックに
●友達といっしょに遊べない
●ルールを守れない
●忘れものがひどく多い
●すぐにカッとなる
【本書の内容構成】
1.発達障害と特別支援教育の基礎知識
発達障害を正しく知ろう
2.基礎調査票・評価シートと実例集
基礎調査票と評価シートの使い方
10の実例にみる状況と経過
3.対応方法の具体例
学校と家庭が協力して成功体験で自信を育てる

アスペルガー症候群(高機能自閉症)のすべてがわかる本
健康ライブラリー
ひと目でわかるイラスト図解
《講談社 健康ライブラリーイラスト版》
【子どもの悩みと特性に気づき、正しい対応をするためのアスペルガー入門書】
自閉症の中でも言葉や知的発達の遅れがないため、
自分勝手、無神経と周囲の誤解を受けやすいアスペルガー症候群。
誤った対応が二次障害を引き起こします。
本書は、子どもの悩みと特性に気づき、正しい対応をするための入門書。
佐々木正美先生が薦める支援のヒントが満載です。
[まえがきより]
アスペルガーの子はだれもがすぐれた能力をもっています。
その力をみいだし、本来の才能を発揮できるよう、環境を整えましょう。
障害の弱点に目を向け、治療的修正をするのは、悲劇的なことです。
彼らの人生を支援する正しい知識をもってください。
【本書のおもなポイント】
●まわりから「わがままな子」といわれるアスペルガー症候群
●アスペルガーの子どもは、人の気持ちを読みとれず、いいたいことを一方的に話してしまう
●記憶することは得意だが、想像するのは苦手
●周囲の無理解は二次障害を引き起こす
●併存する障害には、AD/HD、LD、トゥレット障害がある
●療育の具体的な実践方法として大きな効果を発揮するTEACCHプログラム
●独り立ちはできるのか? 受験勉強、性の悩み、就労への準備
【本書のおもな内容】
アスペルガー症候群、高機能自閉症ってなに?
アスペルガー症候群は治せるの?
《1.子どもはこんなことに困っている》
【コミュニケーション】
【こだわり】
【学習】
《2.周囲の理解が、二次障害を防ぐ》
【周囲の理解】
【二次障害とは】
【家族の役割】
【友達の役割】
【教師の役割】
《3.アスペルガー症候群と自閉症の違い》
【アスペルガー症候群】
【診断基準】
【併存する障害】
《4.「視覚的な手がかり」が生活の助けに》
【対応の基本】
【対応】
《5.青年期に向けて、どんな基準が必要か》
【保育園・幼稚園】【小学校】【中学以降】【青年期】

新版 自然治癒力の驚異
健康ライブラリー
病に克つ自然治癒力を高める秘訣!
ガンの進行が止まった!
慢性肝炎が好転した!
アトピー性皮膚炎が改善した!……etc.
<主な内容>
●自然治癒力とはなにか
●「かならず治る」と信じる心がパワーになる
●西洋医学に中国医学を結合した治療の成果
●「場」が生命の根源、「場」のパワーこそが自然治癒力
●からだ、呼吸、心の3つを気功で整える
●自然治癒力を高める食養生・漢方薬・鍼灸・健康食品
●死を考えるのは生を考えること

新版 脳のリハビリQ&A
健康ライブラリー
脳の病気で失われたことば・運動・知能の回復のために
専門医がやさしく解説 介護に役立つ
脳が病気になったとき脳の働きはどのように破綻していくのだろうか。脳梗塞、脳出血、クモ膜下出血などの病気で脳に障害が起きると、ことばを失う(失語症)、動作の障害(失行症)、記憶障害、認知症などの「高次脳機能障害」をかかえてしまう。その障害は脳のどの部分が壊れたときに起きるのか、回復はできるのか、リハビリは有効なのか、さまざまな疑問にやさしく答える。
<主な内容>
●脳に障害を起こす病気
●失語症とリハビリ
●失行症とリハビリ
●半側空間無視とリハビリ
●失認とリハビリ
●記憶障害とリハビリ
●認知症とリハビリ
●情動の障害
<Q&A例>
●高齢者に多い脳に障害を起こす病気はなんですか
●脳のトレーニングによって失語症は回復するのですか
●失行症とよくまちがえられる運動無視とはなんですか
●半側空間無視とは、片側が見えないということですか
●失語症と視覚失認とはどうちがうのですか
●記憶障害は脳のどの部分の病気で起きるのですか
●治療可能な認知症というのはあるのですか
●情動(怒り、喜び、悲しみなどの感情の動き)の障害はどうして起きるのですか

ことばの遅れのすべてがわかる本
健康ライブラリー
ひと目でわかるイラスト図解
《講談社 健康ライブラリーイラスト版》
【遅れの原因と対応の仕方を徹底解説】
うちの子、ほかの子より、ことばが遅い……。
ことばの遅れは自閉症・AD/HDのサインとして現れることもある。
「他の子よりことばが遅い、病気なの?」と悩むママの不安に答える書。
遅れの原因と対処法をくわしく解説するとともに、ことばをはぐくむ育て方もあわせて紹介。
【本書のおもなポイント】
●「ことばの遅れ」って、どんなことをいうの?
●ことばが出るまで、何年待てばいい?
●ことばをはぐくむ10のポイント
●ことばを教える前に、心と体を育てよう
●家庭だけでは対応できない、専門的な治療や指導が必要な言語発達障害
●ことばの遅れは自閉症・AD/HDのサインとして現れることもある
●迷ったら利用する。医療機関以外の相談機関や親の会
●遅れの状況にあわせた子どもの就学先の選び方
【本書の構成】
第1章 ことばをはぐくむ10のポイント
第2章 うちの子は、ことばが遅い?
第3章 原因探しより、対応が大事
第4章 困ったときは、専門家に相談
第5章 対応のゴールは、楽しく暮らすこと