健康ライブラリー作品一覧

発達障害の子の「励まし方」がわかる本
健康ライブラリー
発達障害の子の感じ方や考え方は、親や先生とは違います。一般的な感覚で「大丈夫だよ」と声をかけても、「なにもわかってくれていない」と感じる場合もあり、励まし方の工夫が必要です。本書では4つのステップで励ましていく方法をイラスト図解。最初は「話を聞くこと」。その後、落ち着いてきたら「言葉かけ」。そして「できる」を増やして不安をやわらげ、最後に、自分を励ます「考え方」を教えていきます。
ひと目でわかるイラスト図解
《講談社 健康ライブラリースペシャル》
【本当の意味で励ます4つのステップ~最初は「話を聞くこと」から】
発達障害の子は傷つきやすく、落ち込みやすいものです。
でも親や先生が「大丈夫」「元気を出して」などと元気づけようとしても、
その言葉が通じないことがあります。
彼らにはさまざまな特性があり、ほかの多くの子や親、先生とは
違うことで悩んだり、失敗したりしているからです。
人の助言を聞いて努力してもうまくいかない場合が多く、
相手も自分も信じられなくなっています。
ただ「大丈夫だよ」と声をかけても、その子が
「この人はなにもわかっていない」と感じるのは当たり前。違う励まし方が必要です。
本書では、発達障害の子を4つのステップで励ましていく方法を紹介します。
この4ステップで発達障害の子を本当の意味で励ませるようになります。
【本書の内容構成】
プロローグ 傷つき落ちこみやすい子どもたち
ステップ1 最初は「話を聞くこと」が励ましに
ステップ2 落ち着いてきたら「言葉かけ」を
ステップ3 「できる」を増やして不安をやわらげる
ステップ4 自分を励ます「考え方」を教えていく

「腰ほぐし」で腰の痛みがとれる
健康ライブラリー
腰痛を治すには、ひんぱんに病院やリハビリに通ったり、薬を飲み続けたり、注射をしたりする必要はありません。必要なことは正しい腰痛の知識をもつこと、体を動かすこと、使うことに恐怖心をもたないことです。本書で紹介する「腰ほぐし」とは、痛みを根本からとる方法です。朝晩5分、1日10分の簡単な体操と気持ちを変える認知行動療法的な方法を合わせて、背骨、筋肉、そして心をほぐして、腰痛を治します。
ひと目でわかるイラスト図解
《講談社 健康ライブラリーイラスト版》
【朝晩たったの5分! 1日10分のらくらく腰痛対策】
腰痛を治すには、ひんぱんに病院やリハビリに通ったり、薬を飲みつづけたり、
注射をしたりする必要はありません。ご自分の治療法を見直してみませんか。
腰痛を治すために必要なことは正しい腰痛の知識をもつこと、
体を動かすこと、使うことに恐怖心をもたないことです。
また近年、慢性腰痛の8割以上は「異常がない」タイプで、
気持ちの問題が大きいということがわかってきました。
本書で紹介する「腰ほぐし」とは、痛みを根本からとる方法です。
朝晩5分、1日10分の簡単な「ゆっくり体操」と
気持ちを変える認知行動療法的な方法を合わせて、
背骨、筋肉、そして心をほぐして、腰痛を治します。
この体操に正しく取り組めば、一週間以内で効果が感じられはじめるでしょう。
そのほかに再発させない生活のポイントや注意点など役立つ情報が満載です。
【ゆっくり腰を曲げたり、反らすだけの「ゆっくり体操」
それだけで痛みがとれるのはなぜ?】
固くなっている背筋、臀筋、ハムストリングスを柔軟にする
固くなっている背骨を柔軟にする
背骨が自然なカーブを取り戻す
腰(背骨)を動かす(曲げる)ことへの不安感、こわさを取り除く
【本書の内容構成】
第1章 「ゆっくり体操」で「腰ほぐし」
《実例集》「ゆっくり体操」は、こんな人、こんな症状に効いた
第2章 認知行動療法的に心をほぐす
第3章 腰痛を正しく診断する
第4章 腰痛の治療法を総点検
第5章 再発させない生活を
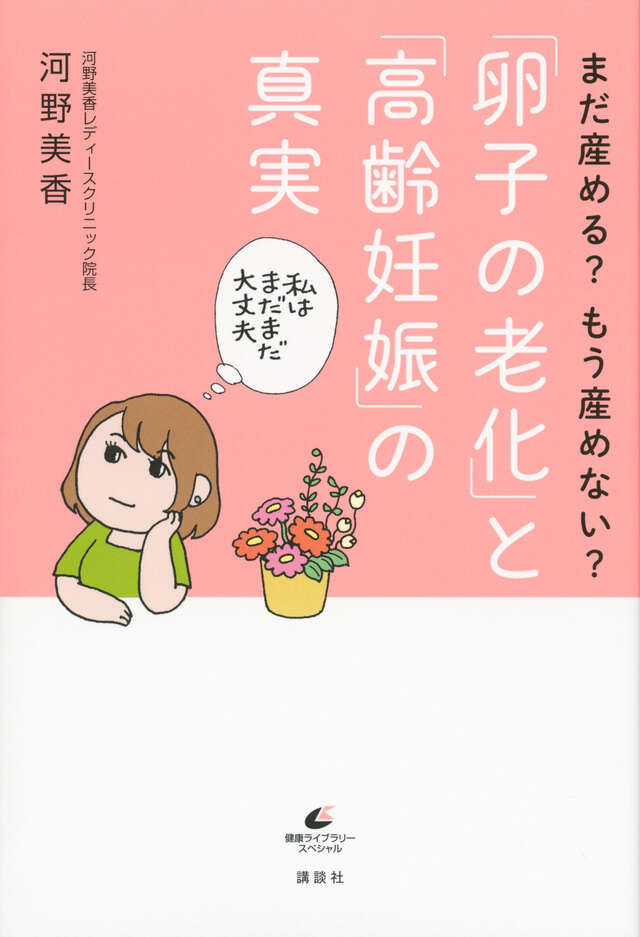
まだ産める? もう産めない? 「卵子の老化」と「高齢妊娠」の真実
健康ライブラリー
「子どもがほしい」「卵子が老化してしまったら、どうすればいい?」と思ったときに出てくる疑問や不安に、産婦人科医が答えます! 「卵子の老化」は止められませんが「老化=妊娠・出産ができなくなる」ということではありません。また、個人差も大きいので、「○歳以降は妊娠できない」とは言えません。ただ、タイムリミットは確実にやってくるもの。正しい知識を身につけ、自分にできることを知りましょう。
卵子が老化してしまったら、どうすればいい?
「子どもがほしい」と思ったときの疑問や不安に、産婦人科医が答えます。
日本では6組に1組のカップルが不妊治療をしています。
そして、不妊症の3割ほどは「卵子の老化」が原因ではないかといわれています。
仕事を持つ女性が増えたこともあり、結婚・出産は先送りになっていて、
出産年齢の高齢化が進んでいるのです。
不妊治療をするカップルが増えていることは、結婚・出産が先送りになっていることと
無関係ではないでしょう。
最近では、「卵子の老化」を知っている女性はかなり増えているようですが、
一方で、タレントさんの高齢出産が報道されたりすることの影響もあり、
「自分はまだ大丈夫」と思っている女性も多いのではないでしょうか。
しかし、日本産科婦人科学会の調査によれば、
体外受精などの生殖補助医療を受けた場合でも、出産率は30代半ばから2割を下回り、
40歳では9%、45歳では0.9%です。
このように、卵子の老化は止められませんが、
卵子が老化していると妊娠・出産ができないというわけではありません。
また、卵子の凍結という選択肢もとれるようになりつつあります。
卵子の老化について今わかっていることから、卵巣の働きや不妊治療、
そして高齢妊娠まで、
知っておくべき知識を豊富な図表とイラストでわかりやすく解説した、
「子どもがほしい」と考えている女性のための本!
産婦人科医としてたくさんの女性にかかわる中で、
「胎内に子どもを宿す」という特性を持った女性には、
「子どもがほしいと思ったときにはもう遅かった」ということがないように
「生殖可能な年齢に達したら読む本」が必要だと思って書きました。
―――― 「プロローグ」より
【本書の内容】
第1章 「卵子が老化する」ってどういうこと?
第2章 卵巣の働きと不妊
第3章 不妊治療でできること
第4章 高齢妊娠・出産で気をつけたいこと

発達障害の子の「会話力」を楽しく育てる本
健康ライブラリー
発達障害の子に必要な「会話力」は、一般的にイメージされる雑談や交渉をうまくおこなう力ではありません。子どもの個性的な話し方や聞き方をベースに、日常生活に必要な会話をおこなう力です。そのため、話し方のテクニック以上に、子どもが会話を楽しむ経験や「話したい」という気持ちが重要です。本書では、発達科学の知見に基づいた「会話を支える力」を解説、楽しみながら会話力を伸ばす支援法を紹介します。
ひと目でわかるイラスト図解
《講談社 健康ライブラリースペシャル》
話がかみ合わないのはなぜ?
「うまく話す」ことよりも「楽しく話す」ことを目標に
発達障害の子は、ほかの多くの子とは異なる
ユニークなコミュニケーション・スタイルをもっています。
それが会話のすれ違いにつながり、悩みのもとにもなっています。
一般的にイメージされる「会話力」は、雑談や交渉などをうまくおこなう総合的な力を指しますが
発達障害の子に必要な「会話力」は、子どもの個性的な話し方や聞き方をベースに、
日常生活に必要な会話をおこなう力です。
発達障害の子の個性的な「会話力」を育てるためには、
その子が会話に自信をもち、会話を楽しめるように、環境を整えることが有効です。
話しやすい相手や場面であれば、自信をもって話し、会話を楽しむことができます。
会話力の成長には、話し方のテクニック以上に
子どもがそうして会話を楽しむ経験や「話したい」という気持ちが重要です。
本書では、発達科学の知見に基づいた「会話を支える力」を解説、
楽しみながら会話力を伸ばしていくために役立つさまざまな支援法を紹介します。
発達障害の子は会話のどの部分が苦手なのか、ASD、ADHD、LDのそれぞれの特性とともに、
話がすれ違う背景をくわしく説明しているので子どもに合ったサポートのしかたがみえてきます。
さらに療育の現場で実践している支援法から、「会話力」の成長に役立つ内容を厳選して紹介、
ご家庭でも活用できる内容です。
【本書の内容構成】
1 会話がすれ違ってしまう子どもたち
2 話がかみ合わないわけを理解しよう
3 子どもに合った「会話力」の基本的な育て方
4 「療育」の活用で「会話力」をさらに伸ばす

発達が気になる赤ちゃんにやってあげたいこと 気づいて・育てる超早期療育プログラム
健康ライブラリー
発達障害の特性があるかもしれないと思われる子どもを、どう育てていったらよいのでしょうか。発達障害があると子どもが大きくなるほど事態は深刻化していきます。小さいうち、それもできるだけ小さいうちだからこそ、できることがあります。抱きづらい、反応が少ない、抱いても目を合わせない……赤ちゃんの違和感に気づいたらすぐに始めたい、親子で楽しみながらできる子育て法。遊びの中で人とかかわる力が育ちます。
ひと目でわかるイラスト図解
《講談社 健康ライブラリースペシャル》
【小さいうちだからこそ、できることがある!】
発達障害の特性があるかもしれないと思われる子どもを、どう育てていったらよいのでしょうか。発達障害があると、子どもが大きくなるほど事態は深刻化していきます。今、小学校や中学校でいちばん問題になっているのは、集団に参加できない子どもたちです。
その背景に発達障害の可能性が感じられる子どもたちがたくさんいます。大きくなればできるようになると言いたいところですが、大きくなるほど事態は深刻化していくのが現状です。
ですが小さいうち、それもできるだけ小さいうちだからこそ、できることがあります。赤ちゃんに抱きづらい、反応が少ない、抱いても目を合わせない、気持ちが通じないように感じる、なかなか寝ない、かんが強い、言葉が少ない……などの違和感がありませんか? 発達が気になる赤ちゃんは、愛情をもって見守ってさえいればいいとはいえません。早くから困難に「気づいて・育てる」ことで、環境に適応していく力を育てていくことが必要です。
本書の「気づいて・育てる超早期療育プログラム」は、家庭でできる、0歳から始められる発達を促すプログラムです。教え込むのではなく、赤ちゃんの興味や関心をもとにおこないます。できているところは伸ばし、できないことは、むりなく楽しく、刺激を与えて、成熟をめざします。
遊びの中で、人とかかわる力が育っていきます。 また、気持ちのコントロールができるようになります。発達障害があってもなくても、どんな子にもやってあげたい子育て法です。保護者だけでなく、保育士さん、保健師さんにもぜひ手にとっていただきたい一冊です。
【本書の内容構成】
1 赤ちゃんのうちから始めよう
2 人とかかわる力を育てる
3 気持ちのコントロールができる子に
4 考える力や想像する力を育てる
5 体の動きをスムーズに

支援・指導のむずかしい子を支える魔法の言葉
健康ライブラリー
いくら正しいことを伝えても、子どもの反抗的な態度や言葉、なげやりな様子、一方的な主張のくり返しに、支援・指導する側もイライラ。子どもとのやりとりが起きなければ、おそらくなにも変わりません。しかし、投げかける言葉しだいで、相手の反応は変わってきます。本書では状況を劇的に変える、子どもの心に響く対話術を紹介。いじめ、不登校などの困った場面を乗りきれる! 保護者との対話もうまくいく!
ひと目でわかるイラスト図解
《講談社 健康ライブラリーイラスト版》
【子どもの態度が変わる! 保護者との対話もうまくいく!】
すぐに暴力をふるう、規則違反をくり返す、学校に行かなくなってしまった、夜遊びがやまない……。「困ったふるまいが多い子も気長に寄り添えばきっと変わってくれるだろう」と思って接していても、子どもは言い訳や悪態、勝手な発言ばかり。子どもの反抗的な態度や言葉、なげやりな様子、一方的な主張のくり返しに、支援・指導する側もイライラ。
正しい意見を言い聞かせるだけではなかなか変わりません。子どもの訴えにじっくり耳を傾け、寄り添うだけでは、一向に望ましい方向へは進めません。子どもとのやりとりが起きなければ、おそらくなにも変わらないのです。
このような傾聴・受容などよくある働きかけの方法が通用しない、支援・指導がむずかしいと思われる子どもに対して、必要になるのが「対話」です。支援者の発する言葉しだいで、相手の反応は変わってきます。
本書では話がかみ合わない状況を変える、子どもの心に響く言い聞かせ方のエッセンスをちりばめた「魔法の言葉」を紹介していきます。
また、加害行為、パニック、いじめ、不登校などの困った場面をのりきる、保護者との対話もうまくいく「魔法の言葉」も紹介。学校でも、施設でも、医療機関でも、家庭でも、支援や指導に行き詰まったときの知恵としてぜひ、本書を活用してください。
【魔法がかかれば対話が進む】
*対話のきっかけをつくる“的外しの魔法” ⇒⇒⇒ 「困っていたんだね」
*暴言・暴力が多い子に“「気づき」を促す魔法” ⇒⇒⇒ 「がまんしていることが多いよね」
*他者批判をする子に“視点を変える魔法” ⇒⇒⇒ 「そこに気がつくきみはすごい!」
*虚言癖がある子に“ウソを終わらせる魔法” ⇒⇒⇒ 「あ、きみ○○に興味があるの?」
【本書の内容構成】
第1章 「話せばわかる」が通じない!
第2章 子どもに伝わる! 魔法の言葉
第3章 困った場面でこそ「言葉の力」が重要
第4章 「これから」につながる支援・指導のために
第5章 保護者との対話がうまくいく魔法の言葉
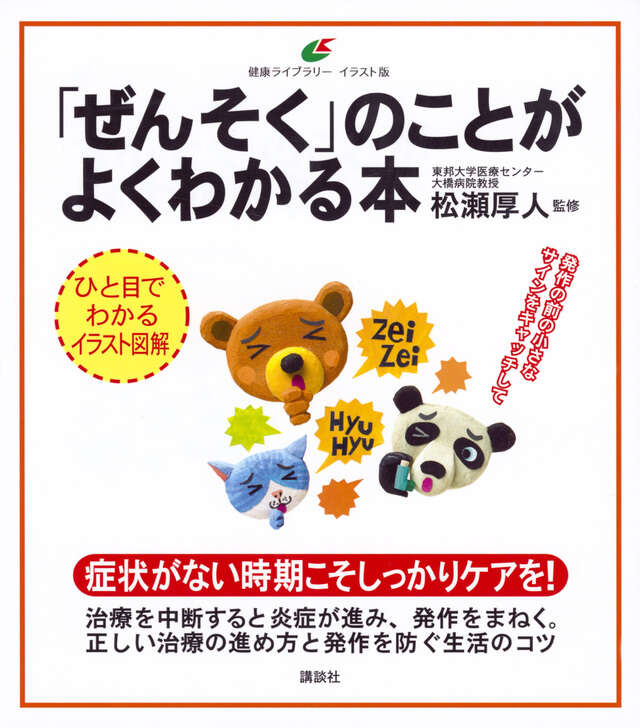
「ぜんそく」のことがよくわかる本
健康ライブラリー
ぜんそくはアレルギー体質によらず、一生付き合っていかなければならない病気ですが、薬を正しく使えば症状を軽くできます。問題は「正しく」使わない人が多いこと。症状がないときに薬を自己判断でやめてしまう人も少なくありません。本書では、ぜんそくの症状・診断方法をはじめ、治療方針の決め方や薬の使い方、発作を起こさない生活のコツなど、長く付き合っていくために必要な正しい知識をわかりやすく図解します。
ひと目でわかるイラスト図解
《講談社 健康ライブラリーイラスト版》
【症状がない時期こそしっかりケアを!】
子どものころからのぜんそくが治りきらない人や、中高年以降に新たにぜんそくを発症する人が増えています。以前はアレルギー体質が原因と思われていましたが、アレルギー体質でなくても発症することがわかってきました。大人になってからの発病は重症化しやすいので注意しなくてはなりません。せきが続き息苦しさがあると、ぜんそくだと判断しがちです。ぜんそくは診察を受けるときに症状が起こっているとは限らないため、診断が難しいといわれます。正しい診断には検査方法や診断に必要な情報を知っておくと安心です。
また、ぜんそくはアレルギー体質によらず、一生付き合っていかなければならない病気です。治療は薬物療法と生活改善の両方が大事ですが、発作のない状態が続くと、通院を中断する人がいます。治ったと思い込んで、薬も、日常生活の注意もやめてしまうのです。すると、気道の炎症が悪化するうえに、環境的にも発作の起こりやすい状況に陥りやすく、ほとんどの場合、再び悪化することになります。
薬にはどのような作用があるのか、生活上の注意がなぜ必要なのか……。ぜんそくは長く付き合う病気なので、薬についても知識をもっておくと納得して治療に取り組めるようになります。
本書では、ぜんそくの症状・診断方法をはじめ、治療方針の決め方や薬の使い方、さらには発作を起こさない生活のコツなど正しい知識をわかりやすく図解します。
【本書の主なポイント】
*ぜんそくで問題なのは、発作だけでなく、気道に炎症が「常にある」こと
*「ゼイゼイして息苦しく、せきが止まらない」が典型的な症状
*原因が特定できない非アレルギー性のタイプ(非アトピー型ぜんそく)もある
*かぜや疲れ、ストレスが発症の引き金になる
*「かぜ」と混同しやすい「せきぜんそく」とは
*重症度(大人)は4段階。重症度を知ることが治療のスタート
*吸入ステロイド薬は発作が起こっていない時期にも気道の炎症を抑える大切な予防薬
*気管支拡張薬は呼吸を楽にするが、使いすぎると悪化する
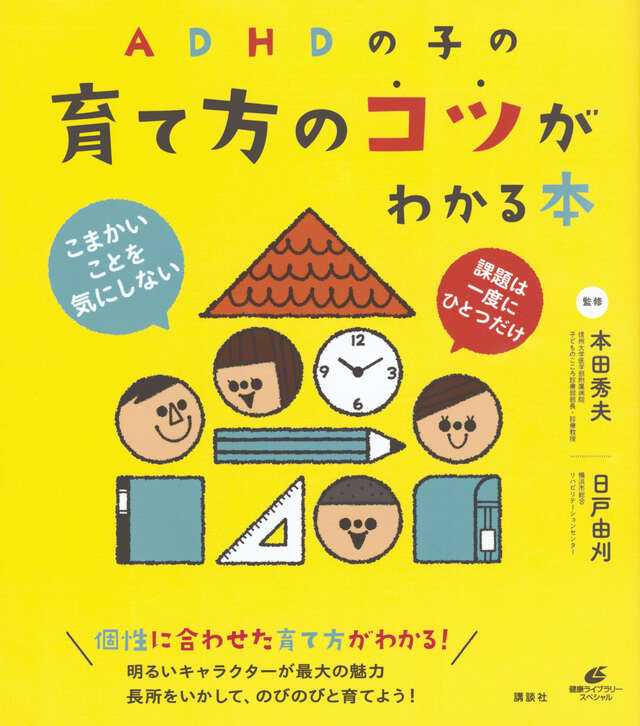
ADHDの子の育て方のコツがわかる本
健康ライブラリー
【NHK『プロフェッショナル 仕事の流儀』に本田秀夫先生出演で大反響!】
ひと目でわかるイラスト図解
《講談社 健康ライブラリースペシャル》
【個性に合わせた育て方がわかる!】
ADHDの子にはアイデアが豊富で、思い立ったらすぐに動き出せるという特徴があります。前向きに、建設的に枠からはみ出していくタイプです。性格的に明るい子が多く、「にくめないお調子者」といった魅力があります。
そのいっぽうで、勢いよく動き回る分、うっかりミスが多く、まわりから「落ち着きがない」と言われることもあります。そうしてネガティブに評価され、何度も叱られていると、子どもは本来もっていた積極性や明るさを失っていきます。そのうえ緊張感が強くなり、ミスはそれまで以上に増えます。
ADHDの子どもを健全に育てていくためには、まわりの人が「こまかいことを気にしない」ということが、きわめて重要です。こまかいことをいちいち叱るのは、やめましょう。ADHDの子が一つひとつのミスを反省して改善策にとりくんでいたら、人生が何回あってもたりません。それよりも、親が子どものミスを補い、成功体験を積み重ねていくほうが、よっぽど建設的です。
この本には、ADHDの子の特徴を理解し、生活を工夫するためのヒントをまとめました。片付けや勉強など場面別のサポートも解説しています。ぜひ参考にしてください。
(まえがきより)
【ADHDの子の育て方のコツ(一例)】
●打たれ強いようにみえるけど、傷つきやすい心に配慮して
●高いパフォーマンスを求めず、「OKレベル」を下げる
●まわりもおおらかになればうまくいく――課題は一度にひとつだけ
●言っても動かないときは、子どものハートをくすぐるかけひきを
●内申点や学歴よりも、本人の選択を重視して
●苦手なことを「致命的だ」と思わせてはいけない
【本書の内容構成】
巻頭 マンガでわかる! ADHDの子の将来
1 ADHDの子はどんなことで困るのか
2 ADHDは問題か、それとも個性か
3 「子育ての基本」を見直すためのコツ
4 子どもの「苦手な場面」をサポートするコツ
巻末付録 薬物療法をおこなうのはどんなとき?

狭心症・心筋梗塞 発作を防いで命を守る
健康ライブラリー
狭心症や心筋梗塞が怖いのは、ある日突然発作におそわれることです。狭心症の発作は冠動脈の血流が途絶えることによって起こります。完全に冠動脈が詰まると心筋梗塞になり、処置が遅れれば死に至ることも。本書は、狭心症とまぎらわしい病気の見分け方、症状の現れ方、心筋梗塞に移行しやすい危険度、発作を鎮める薬の使い方など、狭心症の人が身につけておきたい知識を図解でわかりやすく紹介する一冊です。
ひと目でわかるイラスト図解
《健康ライブラリーイラスト版》
【動脈硬化がなくても油断は禁物! もしもに備えて自分でできる対処法】
狭心症や心筋梗塞が怖いのは、ほとんどがある日突然発作におそわれることです。狭心症の発作は冠動脈の血流が途絶えることによって起こります。完全に冠動脈が詰まると心筋梗塞になり、処置が遅れればそのまま死に至ることもめずらしくありません。
これほど怖い病気にもかかわらず、正しい知識は十分に周知されていません。例えば、狭心症には発作止めのニトロさえあれば安心だと思っている人が多いというのもその一例です。
本書は、狭心症とまぎらわしい病気の見分け方、症状の現れ方、心筋梗塞に移行しやすい危険度、発作を鎮める薬の使い方、心筋梗塞になるしくみ、発作が起こったときの対処法など、狭心症の人が身につけておきたい基礎知識から最新療法、生活習慣の改善まで図解でわかる一冊です。
【本書の内容構成】
第1章 心臓発作を招く狭心症・心筋梗塞とはどんな病気?
第2章 狭心症・心筋梗塞が起こるしくみを理解する
第3章 薬物療法――発作を鎮め、予防するために
第4章 カテーテル治療、バイパス手術――血流を確保
第5章 これまでの生活を見直し、自己管理を

出生前診断、受けますか? 納得のいく「決断」のためにできること
健康ライブラリー
羊水検査、母体血清マーカー、NIPT(新型出生前検査)……出生前診断への関心は、妊婦さんの高齢化とともにますます高まり、検査技術の進歩によって、妊婦さんが知っておくべきことも増えています。本書では、出生前診断の現状、そして検査を受けた人たちの葛藤や決断をまとめ、検査を受けることを考えている人はもちろん、どの検査を受ければいいのか、そもそも受けるかどうか迷っている人にも役に立つ情報を網羅しました。
「出生前診断」といえば、よく知られているのは母体血清マーカーや羊水検査などですが、2013年には臨床研究という形で、妊婦さんの血液検査だけで染色体異常が99%以上の精度で
診断できるとされる「新型出生前検査(NIPT)」が始まりました。
出生前診断への関心は、妊婦さんの高齢化とともに、ますます高まっており、例えば羊水検査の実施件数は10年前の2倍になっています。
また、妊婦さんが必ず受ける超音波(エコー)検査についても、日本産科婦人科学会は出生前診断であるとしています。近年、機械の飛躍的な進歩により、「生まれるまで分からない」とされてきた病気や障害が、かなり詳細に分かるようになってきているからです。
今や、妊婦さんであれば誰もが否応なく出生前診断を受ける状況になっており、それに伴って妊婦さんが知っておくべきことも増えています。
本書では、出生前診断の現状から、検査を受けた人たちの葛藤や決断、そして出生前診断とどう向き合えばよいのかについて、緻密な取材に基づいてまとめました。
出生前診断を受けることを考えている人はもちろん、どの検査を受ければいいのか、そもそも受けるかどうか迷っている人にとっても指針となる情報が網羅されています。
【本書の内容】
プロローグ 出生前診断の今
第1章 出生前診断でわかること
超音波検査/羊水検査/絨毛検査/母体血清マーカー/NIPT(新型出生前検査)
第2章 出生前診断に向き合った人たち
出生前診断に「巻き込まれた」とき/障害を受け入れるということ/「あきらめる」という決断/
「心の準備」としての出生前診断/出生前診断を受けたからできたこと
第3章 出生前診断をめぐる不安とサポート
出生前診断で「知りたいこと」「知りたくないこと」/遺伝カウンセリングってどんなこと?/
納得できる結論を出すために/障害のある子どもと生きるということ/
産むことをあきらめた女性たちを待つもの
第4章 出生前診断で悩んだら
「決めなければ」から「決めてもいい」へ/「障害」の不安にとらわれたときに知っておきたいこと/
「自分が納得できる」ことを大切に
エピローグ

糖尿病は先読みで防ぐ・治す ドミノでわかる糖尿病の将来
健康ライブラリー
糖尿病は、それ自体の症状はほとんどない。ではなぜ治療しなければならないかというと、合併症が起こるから。放っておくと新たな合併症がドミノ倒しのように起こる。本書では2型糖尿病を2つのタイプに分け、糖尿病・合併症の原因や病気が現れてくる時期をドミノに例えて時系列で解説。タイプに合わせた治療で合併症を未然に防ぐことができる。“ドミノ”という新しい概念で解説した、糖尿病の先行きが読める画期的な一冊
ひと目でわかるイラスト図解
《講談社 健康ライブラリーイラスト版》
【危険度と防ぎ方が一目瞭然! タイプで違う合併症の現れ方】
糖尿病は、それ自体の症状はほとんどありません。ではなぜ治療しなければならないかというと、合併症が起こるからです。放っておくと新たな合併症がドミノ倒しのように起こってきます。本書では、2型糖尿病を2つのタイプに分け、糖尿病・合併症の原因や病気が現れてくる時期をドミノに例えて時系列で解説します。
合併症には現れる順番があり、タイプに合わせた治療で未然に防ぐことができます。本書は“ドミノ”という新しい概念で解説した、 糖尿病の先行きが読める本です。やみくもに糖尿病をおそれることなく、将来を先読みして適切な時期に適切な治療に取り組みやすくなります。すでに糖尿病になった人はもちろん、予備軍の人や糖尿病のリスクが高い人にも役立つ一冊です。
【タイプ別糖尿病の危険度と防ぎ方】
メタボタイプ――家族歴にかかわらず肥満・メタボの人 《ドミノが短く裾広がり》
*血糖値は食後だけ跳ね上がる「血糖スパイク」
*動脈硬化による大血管症が早く起こる。合併症の数が多く悪化のスピードも速い
*食事改善(エネルギー制限・糖質制限)だけで高血糖が治る人も
やせタイプ――家族歴があり、肥満・メタボでない人 《ドミノが細長い》
*血糖値はふだんから高めの「底上げ」
*動脈硬化の危険性は低く合併症の数は少ない。進み方はゆっくり
*食事や運動だけでは血糖値は下がりにくい。適した薬を早めに使って
【本書の内容構成】
第1章 糖尿病の将来はタイプで違う
第2章 合併症は現れる順番で気づく
第3章 今すぐできること
第4章 合併症が現れたら必要なこと
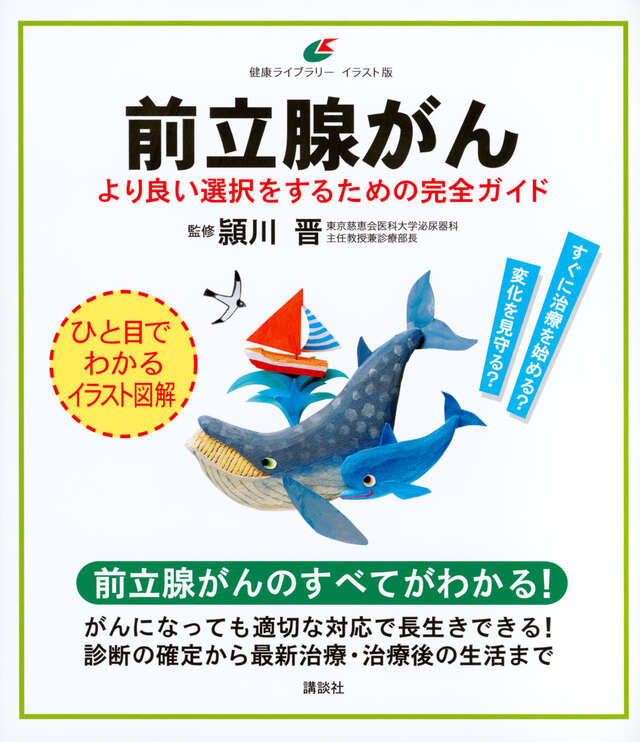
前立腺がん より良い選択をするための完全ガイド
健康ライブラリー
前立腺がんは治療の選択肢が非常に多い。「ゆっくり進行する」といわれるため「進行が遅いから治療は不要」という説も聞かれる一方、PSA 検査の普及により早い段階から異変をキャッチできるようになり、その後の対応に悩む人も増えている。本書では、がんの特徴や診断の確定から各治療法の特徴、治療による日常生活への影響などを図解でわかりやすく紹介する。正しい知識で自分に合った治療を選択できる一冊。
ひと目でわかるイラスト図解
《講談社 健康ライブラリーイラスト版》
【すぐに治療を始める? 変化を見守る?】
現在、日本人男性がいちばんかかりやすいがん――それが、ほかでもない前立腺がんです。
「ゆっくり進行する」といわれるため、「検診など受けないほうがいい」「見つかっても治療は不要」などという説も聞かれます。一方で、年間1万人を超える男性が前立腺がんで命を落としているという現実もあります。
PSA 検査の普及とともに、ごく早い段階から異変をキャッチできるようになり、その後の対応に悩む人も増えています。
前立腺がんは、治療の選択肢が非常に多いがんでもあります。迷いを解消するには、まず現状を知ること、さらにご自身が「大切にしたいことはなにか」をしっかり考えてみることが必要です。
「根治を目指す方法」も「上手につきあう方法」も、それぞれに進化を続けています。本書では、図解で前立腺がんの特徴や診断の確定から各治療法の特徴、治療による日常生活への影響などをわかりやすく紹介します。正しい知識で自分に合った治療を選択できる一冊です。
【本書の内容構成】
第1章 PSA検査を受けて前立腺がんを見つけよう
第2章 「前立腺がんの疑いあり」といわれたら
第3章 自分にとってベストな治療法を選ぼう
第4章 前立腺がん治療の実際
第5章 治療中・治療後もいきいき過ごすために

図解 プログラミング教育がよくわかる本
健康ライブラリー
小学校で2020年度から必修化、プログラミング教育が「読み書きそろばん」と同じくらい重要に。本書では、家庭で実践するときのコツや民間教室の活用法、学校現場への導入のポイントなどを、実例もまじえながら広く解説。「そもそもプログラミングとは」「プログラミング教育で子どもの将来はどう変わるのか」「親や先生が今すぐできること」など“はじめてプログラミング教育と向き合う”ときに役立つ一冊です。
【家庭で、学校で、子どもと一緒に体験しよう! はじめてのプログラミング教育】
子どものプログラミング教育に注目が集まっています。小学校で2020年度から必修化されることが発表され、都市部を中心に民間教室が急増しています。あらゆるものがインターネットにつながり、テクノロジーの重要度が増すなかで、子どもたちにとってプログラミングが、「読み書きそろばん」と同じくらい重要になってきています。
本書では、家庭で実践するときのコツや民間教室の活用法、学校現場への導入のポイントなどを、実例もまじえながら広く解説。「そもそもプログラミングとは」「プログラミング教育で子どもの将来はどう変わるのか」「親や先生が今すぐできることはなにか」など“はじめてプログラミング教育と向き合う”ときに役立つ一冊です。
子育て中の保護者の方から、これから導入を考えている小学校の先生方、プログラミング教育に関わっている教育関係者の方まで活用していただけます。
【本書の内容構成】
1 プログラミング教育とはなにか
2 家庭で遊びながら学べるもの
3 小学校での実践がはじまっている
4 なぜいま子どもたちに必要なのか
5 プログラミング教育の効果とは

パーソナリティ障害 正しい知識と治し方
健康ライブラリー
ひと目でわかるイラスト図解
《講談社 健康ライブラリーイラスト版》
【その生きづらさ、パーソナリティ障害では?】
パーソナリティとは、その人らしさのこと。それが障害されるとはどのような状態なのでしょうか。
パーソナリティ障害は、思春期から問題が表にでてきます。ものの考え方や行動のパターンが著しく偏ってしまい、対人関係がうまくいかずトラブルを起こすため、近年、発達障害との合併症や誤診といったことが問題視されています。
さらに本人に病識のないことから周囲が巻き込まれやすく、その対応に負担に感じている家族も少なくありません。摂食障害や人や物への依存などの問題行動、引きこもりなどの背景にパーソナリティ障害が隠れているケースもあると言われています。
本書ではとくに患者数が多い「境界性」と「自己愛性」の2つのタイプを中心に障害の特徴、背景から自分自身で治すためにできること、家族や周囲の正しい対応法まで解説します。本人だけでなく、家族や職場など周囲の人に役立つ一冊です。
*パーソナリティ障害とは
・パーソナリティに著しくかたよりがあり、対人関係がうまくいかず問題が起こる状態
・自閉スペクトラム症などの発達障害が隠れている場合もある
*境界性パーソナリティ障害の特徴
・根底に「自分は見捨てられた子」という強い思い込み(幻想)がある
・よい子と悪い子、両極端の自分がいる。周囲に対しても態度が激変する
・過食、親への暴力、人や物への依存などの問題行動で、周囲を巻き込む
*自己愛性パーソナリティ障害の特徴
・「理想化した万能の自分」しか愛せない。等身大の自分がない。
・健全な自己愛が育っていない。失敗や挫折に弱く、うつや引きこもりに
・目に見える結果がすべて。他人の評価を過度に気にして批判されるとキレる
【本書の内容構成】
第1章 パーソナリティ障害について知る
第2章 パーソナリティ障害の要因はなにか
第3章 境界性パーソナリティ障害――「私を見捨てないで」
第4章 自己愛性パーソナリティ障害――「私をもっと賞賛して」
第5章 治すために必要なことがある

発達障害の子の健康管理サポートブック
健康ライブラリー
体を清潔にすること、身だしなみを整えることや、食事の習慣を見直して肥満を防ぐこと、体調の変化を自覚すること、性の知識を得ること――このような日常の当たり前のように思えることが、発達障害の子どもたちはなかなかうまくできません。見過ごされがちな健康面のスキルを習慣として適切に学べるよう、ASD、ADHD、LDなど発達障害のタイプへの配慮もふまえて、厳選したサポート法を紹介します。
ひと目でわかるイラスト図解
《講談社 健康ライブラリースペシャル》
【ライフスキルの基盤ができる!すこやかに暮らしていける!】
体を清潔にすること、身だしなみを整えることや
食事の習慣を見直して肥満を防ぐこと、体調の変化を自覚すること、
性の知識を得ること――このような日常の当たり前のように思えることが、
発達障害の子どもたちはなかなかうまくできません。
見過ごされがちな健康面のスキルを習慣として適切に学ぶことで、
ライフスキルの基盤ができ、大きなトラブルもなく
すこやかに暮らしていけます。
本書ではASD、ADHD、LDなど
発達障害のタイプへの配慮もふまえて、
「体のケア」「食事の習慣」「病気・ケガ」「性の問題」という
4 つの分野の厳選したサポート法を紹介します。
【本書の内容構成】
1 どうして健康管理が苦手なのか
2 苦手なところはサポートできる
3 まずは体のケアと食事をサポート
4 体調不良や病気への対応を教える
5 性教育をほかの子よりも丁寧に
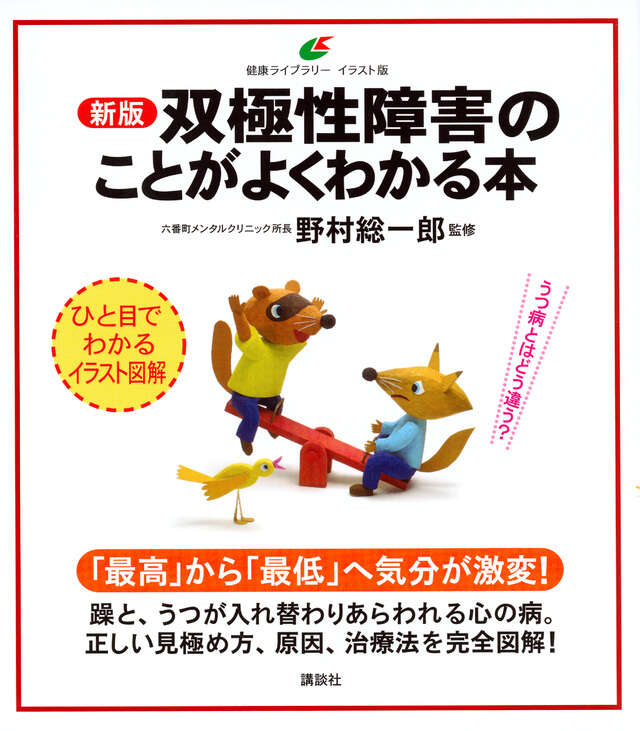
新版 双極性障害のことがよくわかる本
健康ライブラリー
双極性障害は、躁とうつが入れ替わり現れる心の病気。うつ症状の時に受診するとうつ病と診断され、正しい診断まで時間がかかる。なかなか改善しないうつ病はじつは、双極性障害だったということも。また、躁状態では本人に病識がなく、そのまま突っ走ると仕事、人間関係、財産など、多くの大切なものを失う。診断の難しさと正しい見極め方、新薬など最新の情報を盛り込み、正しい知識で双極性障害をイラスト図解した一冊。
ひと目でわかるイラスト図解
《講談社 健康ライブラリーイラスト版》
【「最高」から「最低」へ気分が激変! うつ病とはどう違う?】
双極性障害は、躁とうつが入れ替わり現れる心の病気です。
うつ症状の時に受診するとうつ病と診断されることが多く、正しい診断まで時間がかかります。うつ病と同じ種類の病気とされてきましたが、うつ病に効く薬は、双極性障害では症状を悪化させることもあります。そのため、なかなか改善しないうつ病はじつは、双極性障害だったということもあります。また、躁状態のときには、本人に病識がなく、そのまま突っ走ると仕事、人間関係、財産など、多くの大切なものを失ってしまいます。
発病は全年齢にわたりますが若い世代に多く、双極性障害の特徴の一つに衝動性があるため、ADHD(発達障害)と誤診も合併もしやすいという問題もあります。本書は双極性障害の原因、診断の難しさと正しい見極め方、新薬など最新の情報を盛り込み、わかりやすく解説した一冊です。
【本書のポイント】
*双極性障害はうつ病と似ているが別の病気
*初診時にうつ状態で受診した場合、うつ病と診断されることが多い
*治らないうつ病は、双極性障害の可能性も
*双極性障害のうつ状態は、うつ病とは薬が違う
*うつ病の薬の副作用で躁状態になることも(躁転)
*躁状態は絶好調、陽気な性格にもみえ、病気かもしれないと気づきにくい
*躁状態では、家族や周囲を巻き込んでトラブルを起こすことが多い
*発病は若い世代に多く、発達障害のADHDと合併も誤診もしやすい
*病的な躁か、うつか自己診断ができるチェックシート付き
【本書の構成】
第1章 躁とうつが入れ替わりあらわれる
第2章 大きくみると二つのタイプがある
第3章 発病の原因やきっかけは、単純ではない
第4章 薬物療法と認知療法を中心に
第5章 日常のなかで本人や周囲ができること

下肢静脈瘤 最新の日帰り治療できれいな足を取り戻す
健康ライブラリー
下肢静脈瘤は、足の静脈が浮き出てボコボコと小さなコブのようになったり、赤紫色の細い血管がクモの巣のように透けて見えたりする病気です。一度発生した下肢静脈瘤は自然には治りません。根本的に治すには血管内治療が必要です。本書では、保険適用になり気軽に治療を受けられるようなった最新のレーザー治療や高周波治療の実際を徹底解説。受診先の選び方から治療後の血行改善の生活術までを紹介します。
ひと目でわかるイラスト図解
《講談社 健康ライブラリーイラスト版》
【気になる足のボコボコがすっきり消える!】
下肢静脈瘤は、足の静脈が浮き出てボコボコと小さなコブのようになったり、赤紫色の細い血管がクモの巣のように透けて見えたりする病気です。見た目の変化だけでなく、足のむくみやだるさなど、不快症状が起きてくることもあります。
最新のレーザー治療などが保険適用になり、気軽に治療を受けられるようになりましたが、受診先によっては不安をあおるようなことをいわれたり、むやみに治療をすすめられたりするようなことも起きてきています。
下肢静脈瘤にはいろいろなタイプがあり、レーザー治療の対象とはならないものもあります。どんな状態なら治療を受けるべきか、治療を受けないとどうなるのか、受診先はどう選ぶか、治療費は……。
本書では受診先の選び方から治療後の血行改善の生活術までを徹底解説します。
【本書の主なポイント】
レーザー治療、高周波治療のすべてがわかる!
*一度発生した下肢静脈瘤(コブだらけになった血管)は自然には治らない
*保険適用のレーザー治療や高周波治療で根本的に治せる
*専門の医療機関を受診。超音波検査と問診で静脈瘤のタイプや程度を診断
*むくみやだるさ、痛み……。検査で静脈に異常がなければ原因は別にある
*治療は日帰り、最低3回の通院でOK
*治療するかどうかは本人しだい。「治療しない」という選択肢も
*高額な自費診療のほうが、よりよい治療を受けられる?
【本書の内容構成】
〈マンガで学ぼう〉受けてみました!下肢静脈瘤の最新日帰りレーザー治療
第1章 もっと知りたい! 下肢静脈瘤の最新日帰り治療
第2章 いつ受診する? どこを受診する?
第3章 知って安心、下肢静脈瘤の正体
第4章 症状を楽にする暮らし方のポイント

図解 マインドフルネス瞑想がよくわかる本
健康ライブラリー
そもそもマインドフルネスとはなにか。瞑想にどんな効果があるのか。本書ではイラストやチャートを使い、マインドフルネス瞑想の基本的な手法と理念をわかりやすく紹介します。もっとも基本的な呼吸の瞑想をはじめ、食べる瞑想、飲む瞑想、座る瞑想、立つ瞑想、歩く瞑想、慈悲の瞑想など様々な手法を紹介。チャートを見ながら実践ができ、うまくできないときはチェックリストで対処法を学べる“図解で理解が深まる決定版”です。
ひと目でわかるイラスト図解
《講談社健康ライブラリースペシャル》
【瞑想のしくみがわかる!今すぐ実践できる!】
マインドフルネス瞑想は、簡単に言ってしまえば悩みごとやストレスの解消につながる瞑想法です。しかし、いまはそのような概要だけが広く伝わっていて、本当の意味や正しいとりくみ方が、あまりよく理解されていません。
マインドフルネスとは本来、いまこの瞬間に起こっている感覚や感情、思考に気づき、ありのままに受け入れること。そのような状態になるための瞑想が、マインドフルネス瞑想です。
「感覚や感情、思考に気づく」と言われても理解できないかもしれませんが、その「わからない」という思いが、あなたの「思考」です。わからないと思ったときに、それは思考だと気づき、心のなかで「思考」と実況中継する。それがマインドフルネス瞑想の実践法のひとつです。
本書ではイラストやチャートを使い、マインドフルネス瞑想の基本的な手法と理念をわかりやすく紹介します。もっとも基本的な呼吸の瞑想から、食べる瞑想、飲む瞑想、座る瞑想、立つ瞑想、歩く瞑想、感じる瞑想、慈悲の瞑想、日常の瞑想まで様々な手法を紹介。チャートを見ながら実践ができ、うまくできないときはチェックリストで対処法を学べる“図解で理解が深まる決定版”です。
【本書の内容構成】
巻 頭 5 分でわかるマインドフルネス瞑想の基本
第1章 そもそもマインドフルネス瞑想とはなにか
第2章 瞑想をすると、悩みの正体がみえてくる
第3章 マインドフルネス瞑想をはじめてみよう
第4章 うまくできないときの対処法
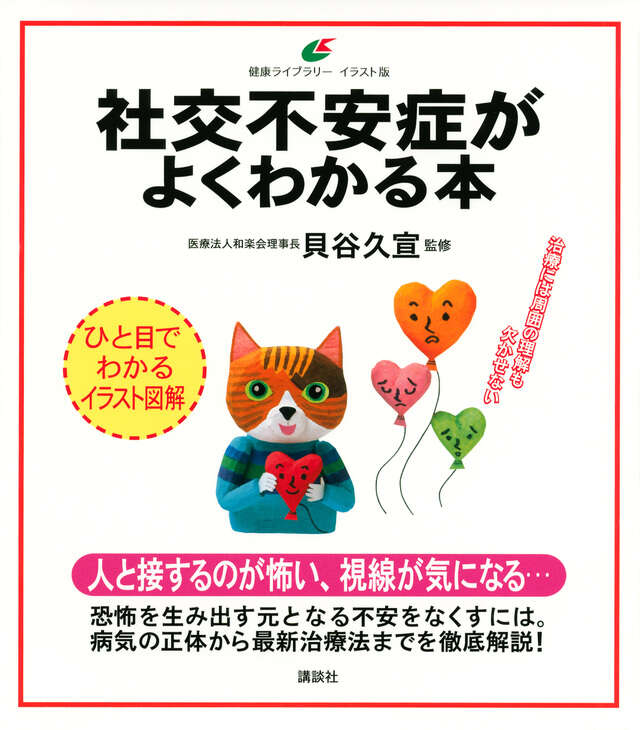
社交不安症がよくわかる本
健康ライブラリー
人と接するのが怖い(対人恐怖)、オフィスで電話に出られない(電話恐怖)、人と一緒に食べるのが苦痛(会食恐怖)、人が近くにいると排尿できない(排尿恐怖)……。他人がいる場にいるだけで苦痛に感じるほどになり、社会生活にも日常生活にも支障をきたす不安の病。恐怖が生まれる複雑な心の背景をわかりやすく図解し、医療機関での認知行動療法の進め方をはじめ、考え方や生活改善で自分を変えていく対処法を徹底解説
ひと目でわかるイラスト図解
《講談社 健康ライブラリーイラスト版》
【恐怖を生み出す元となる不安をなくすには】
社交不安症は従来「社会不安障害」「対人恐怖症」と呼ばれていた心の病です。人前に出るのが怖く、社交的な場で他人と交流するときにたいへん緊張します。他人がいる場にいるだけで苦痛に感じるほどになり、外に出ることができず、社会生活にも日常生活にも支障をきたしてきます。周囲からは「あがり症は性格の問題」などと、苦痛が理解されない傾向がありますが、治療をすれば治る病気なのです。
本書では、複雑な心の背景をわかりやすく図解。社交不安症を理解するための基礎知識をはじめ、改良され効果が高まった認知行動療法、さらに今話題になっているマインドフルネスについても紹介。不安に負けない心を育てるために役立つ一冊。
【強い不安から、心と体にさまざまな変化が起こる】
*人前で話すのが非常につらい(スピーチ恐怖)
*オフィスで電話に出られない(電話恐怖)
*人と一緒に食べるのが苦痛(会食恐怖)
*汗が気になってしかたがない(発汗恐怖)
*おなかの音が鳴るのが心配(腹鳴恐怖)
*人が近くにいると排尿できない(排尿恐怖)
*自分の臭いが気になって仕方がない(自己臭恐怖)
【本書の内容構成】
第1章 不安や恐怖がさまざまな症状として現れる
第2章 社交不安症を理解するための基礎知識
第3章 医療機関でおこなう治療法を知っておこう
第4章 考え方や生活のしかたを少しずつ変えていく
第5章 マインドフルネスで心を開放する
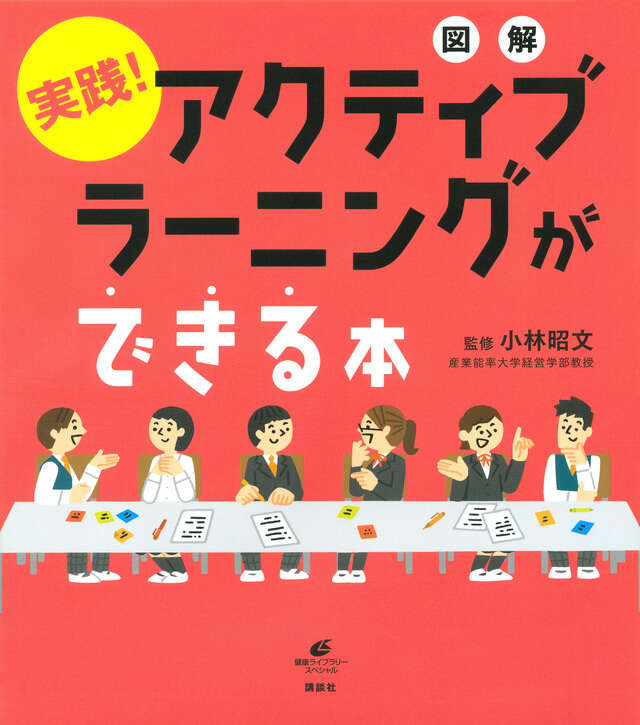
図解 実践! アクティブラーニングができる本
健康ライブラリー
授業で最初に見直すポイント、グループワークの基本的な設定、子どもたちの対話をうながすテクニック、新しい授業の評価基準、集団が苦手な子に対するフォロー、校内での先生同士のチームワークのつくり方……。先生たちが直面しやすい悩みと解決法をイラスト図解。管理職にも役立つように現場への指示の出し方やサポートの仕方も解説します。
【アクティブラーニング型授業の実践のコツを徹底図解】
先生が直面する悩みと解決法がひと目でわかる!
本書は、アクティブラーニングの基礎知識をまとめた
『図解アクティブラーニングがよくわかる本』(2016 年7 月発売)の第2弾。
アクティブラーニング型授業をはじめたときに
先生たちが直面しやすい悩みと解決法をイラスト図解。
授業で最初に見直すポイントから、グループワークの基本的な設定、
子どもたちの対話をうながすテクニック、新しい授業の評価基準、
集団が苦手な子に対するフォロー、校内でのチームワークのつくり方まで、
さまざまなテーマを取り上げました。
また、現場をバックアップする管理職にも必携の一冊です。
【本書の内容構成】
第1章 授業をどこまで変えればよいのか
第2章 どうすれば子どもたちがついてくるか
第3章 同僚にどう言えばわかってもらえるか
第4章 あらためてアクティブラーニングを考える