講談社選書メチエ作品一覧

実力発揮メソッド パフォーマンスの心理学
講談社選書メチエ
能力を直ちに向上させるのもいいが、その前に、自身の力を最大限に発揮するためにはどうすればよいか? 日々のあらゆる局面においての、効果的な目標の立て方、他人との比べ方、アドバイスの送り方・受け方、あがりの手なずけ方を、心理学の知見より裏付けし、パフォーマンス向上への道筋を示す。
あなたの力は、きっとそんなものじゃない――。自己啓発本と一線を画す、
教育心理学の最新の成果に裏付けられた「最強の自分をつくる」ための上質なヒント。

発達障害の内側から見た世界 名指すことと分かること
講談社選書メチエ
精神科医が自分を振り返り自らに「発達障害」という診断を下したとき、自分というもののあり方、他者との関係や理解はどのように見えてくるのか。
ASD(自閉症スペクトラム)、ADHD(注意欠陥多動障害)、DCD(発達性協調運動障害)などの診断名で呼ばれる「発達障害」は病気ではないし、必ずしも「障害」ではない。脳のスペックの傾向であり、そのスペックに適した環境に置かれていないがゆえの不適応と考えるほうがはるかに実態に近い。
私のスペックは、たとえば精神科医、牡羊座、A型、DCD、右利き、日本人、大学教授などさまざまに表される。しかし、その中の一つに焦点をあて人としての本質として前景化した形で周りから名指されてしまうと、その「分かられ方」は自分からは切り離され、独自の存在として扱われることになる。
物事を認識すること、人を理解することにおいて、人間の思考の営みは常になにかを捨て去り、排他的に対象を輪郭づけようとするのではないか。ゆで卵が生卵からゆで卵に変貌する臨界点はどこにあるのか。
人工的に作られた名前が必ずしも「定義」から出発しているとはかぎらず、定義もまた定義づけられた瞬間からその「過不足のなさ」は揺らぐことになる。
人を了解すること、人を説明すること、それらの間にはなにか質的な違いがあるのではないか。また自分が自分を分かるということはじつは大きな謎であり、他人のことが分かることの謎へと連続的に連なっている。
本書は、著者による発達障害の自分史を事例としてつつ、「私」あるいは「私」と他者との関係の「分かり方」を考察する。名指すことによって分かるのでなく、繰り返し語らい合い、ともに眼差すことによって「分かる」ことへと接近するだろう道筋を探って。

名前の哲学
講談社選書メチエ
「名前」ほど、日常にありふれたものでありながら不思議なものもない。自らをあらわす自分の名前さえ、ほとんどの場合、自分ではない他の誰かに付けられたものであり、死後まで自分の存在は、その誰かに付けられた名前によって語られることになる。なにより自分の名前は、自分で使うよりも他者から呼ばれることのほうが圧倒的に多い。最も身近で最も遠い、それが「名前」である。
「名前」をめぐる哲学は、西洋の形而上学では真理についての文脈で考えられてきた。初めて「名前」を哲学の対象にしたプラトン、アリストテレスにはじまり、その流れを受け継いだ二〇世紀のミルやフレーゲの名前論をひもとけば、伝統的な西洋哲学がいかに「名前」を厄介者としてきたのかが浮かび上がる。
ところが、ヴィトゲンシュタイン、ローゼンツヴァイク、ベンヤミンの三人の思想を解き明かしていくと、真理論の舞台から解き放たれて、名前の哲学はこれまでにない生き生きとした姿を見せはじめる。著名なジャック・デリダの三部作にかぎらず、先鋭的な名前論はなぜユダヤ系の思想家から生まれるのか――。その背景には、名前と同化をめぐるユダヤ系の人々の苦難の歴史があった。
外側から貼られた単なるレッテルではない、「呼びかける」ものとしての名前がひらく、新たな時代の共同体論。
[本書の内容]
まえがき 名前――もっともありふれた不思議なもの
第1章 名前の哲学史――古代ギリシアから二〇世紀まで
第2章 生活形式――ヴィトゲンシュタイン
第3章 対話――ローゼンツヴァイク
第4章 純粋言語――ベンヤミン
終章 名前の哲学が教えること
注
書 誌
あとがき

西田幾多郎の哲学=絶対無の場所とは何か
講談社選書メチエ
『善の研究』から「場所の哲学」へ――。西田の哲学遍歴は「場所の哲学」にいたって、ついに独創的な境地にいたったとされる。
『善の研究』の冒頭に出てくる「純粋経験」からはじまって、後期の「絶対無の場所」にいたる思考とは、どのようなものなのか。
近年とみに影響関係が指摘されるベルクソンとの関係、あるいは仏教の時間論と西田の時間論の共通点と相違。フッサールやレヴィナス、あるいは鈴木大拙、井筒俊彦にいたるまで、あるいは量子論との相関など、様々な角度から丁寧に参照しつつ、著者はするどい考察を繰り広げて、独自のスタイルで西田の本質に迫っていく。
それは西田自身の言葉をかりれば、さながら「悪戦苦闘のドッキュメント」の様相を呈しつつも、きわめて鮮明に、西田哲学の真のすがたが浮かび上がってくる。
「存在と無」(=あるとない)という、われわれがごく日常的に想定する対立の以前に、「場所」というものを考え、そこに人間の根本をみようとした近代日本哲学の巨峰を、これまでにない明解な叙述で味わい尽くす力作!

MMT 現代貨幣理論とは何か
講談社選書メチエ
いま世界の政治、ビジネス、経済論壇を席巻する現代貨幣理論(Modern Monetary Theory=MMT)について、
知るべきことがすべて、これ1冊で、明快にわかる!
日本が/世界が変わる “異端”の経済学、最良の入門書。
「財政破綻の危機」は幻想か?
政府はどこまで借金ができるのか?
経済のマクロな仕組みの初歩から貨幣というものの本質論まで、
標準的な経済学の理論もふまえてMMTを中立的に分析。
ベストセラー『人工知能と経済の未来 2030年雇用大崩壊』によって、
AIによる雇用危機の可能性を提起、社会現象を惹起した、
日本でいまもっとも注目される経済学者のひとりである著者が、
MMTが日本が長期低迷から脱するための理論となりうるか否かを明快に解説。
さらには、「すべての人々のための貨幣制度」を展望する意欲作!
【本書より】
MMTは、非主流派の経済理論、つまり一般的な経済学の教科書には載っていない理論です。主流派の経済学者からすれば、MMT派は「異端派」ということになります。
私は、大学の講義で「ミクロ経済学」とか「マクロ経済学」といった主流派の経済学を教え、学術的な論文も主流派のフレームワーク(枠組み)にしたがって書いています。しかしながら、主流派とか非主流派といった区分に本質的な意味があるとは思っていません。
私自身は、MMTに全面的に賛成でも、全面的に反対でもありません。明確に賛成できる部分と疑問や違和感を抱かされる部分とが混在しています。本書は、そうした立場の経済学者から著されたものです。
MMTは、拡張的財政政策を採用して借金を増やすのが正しいのか、逆に緊縮的財政政策を採用して借金を減らすのが正しいのか、という国の命運を左右するようなテーマに関わっています。この問題の重要性の前では、主流派経済学かどうかといったことは些末なことであり、最終的な賛否はさておくとしても、まずはMMTの主張に耳を傾けるべきでしょう。
私は、もとより拡張的財政政策を採用するのが正しいと思っており、その考えを補強したいがために、MMTの理解に努めました。その成果をまとめたのが、本書ということになります。
【本書の内容】
なぜいまMMTが注目されるのか?
貨幣の正体―お金はどのようにして作られるか?
政府の借金はなぜ問題にならないか?
中央銀行は景気をコントロールできるのか?
政府は雇用を保障すべきか?―雇用保障プログラム
MMTの余白に―永遠の借金は可能だろうか?
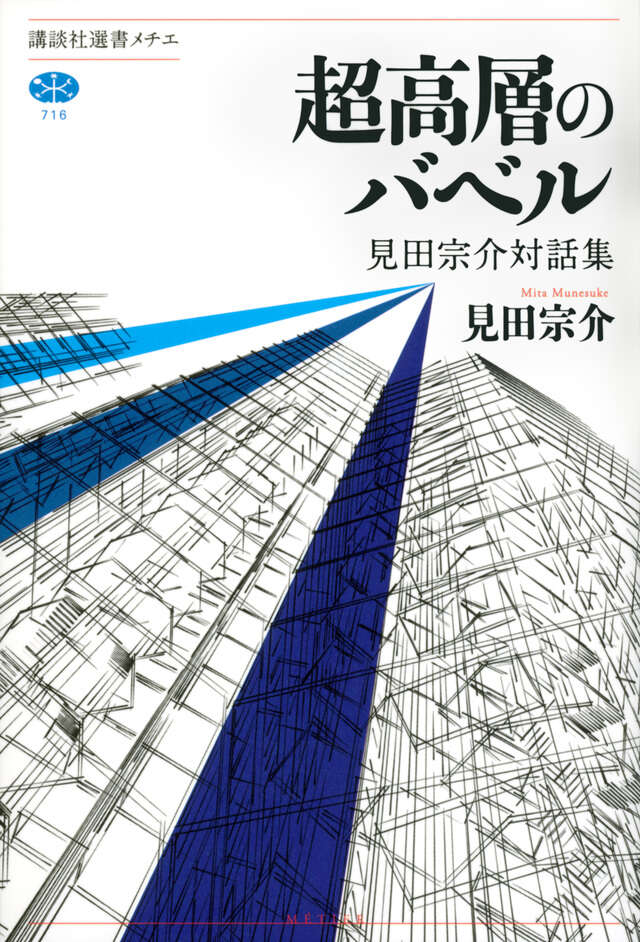
超高層のバベル 見田宗介対話集
講談社選書メチエ
『現代日本の精神構造』(1965年)や『近代日本の心情の歴史』(1967年)で日本と日本人がたどってきた道行きを具体的な事象を使って鮮やかに分析した社会学者は、人々を震撼させた連続射殺事件の犯人を扱う「まなざしの地獄」(1973年)でさらなる衝撃を与えた。その名を、見田宗介(1937年生)という。
続くメキシコ滞在を機に、さらなる飛躍を遂げた社会学者は、「真木悠介」の名を使ってエポックメイキングな著作『気流の鳴る音』(1977年)を完成させる。ここで形を得た人間観と、そこから導かれるコミューンへの憧憬は、独自の理論に結晶していき、数多くの信奉者と、数多くの優れた弟子を生み出した。その成果は、『時間の比較社会学』(1981年)や『自我の起原』(1993年)といった真木悠介名義による労作を経て、ついに『現代社会の理論』(1996年)に到達する。現代の世界に向けられた冷徹と愛情の共存するまなざしは、最新の社会現象についても常に鋭利な分析をもたらし、今なお他の追随を許すことがない。
その思想が、かけがえのない「他者」たちとの対話を源泉にして生まれてきたこともまた間違いのない事実である。対談や座談会は収録の対象としなかった『定本 見田宗介著作集』(全10巻、2011-12年)と『定本 真木悠介著作集』(全4巻、2012-13年)を補完するべく精選された、珠玉の11篇。現代日本社会学の頂点に君臨する著者が望んだ初の対話集がついに完成した。
[本書収録の対話]
河合隼雄 超高層のバベル
大岡昇平 戦後日本を振り返る
吉本隆明 根柢を問い続ける存在
石牟礼道子 前の世の眼。この生の海。
廣松 渉 現代社会の存立構造
黒井千次 日常の中の熱狂とニヒル
山田太一 母子関係と日本社会
三浦 展 若い世代の精神変容
藤原帰一 二一世紀世界の構図
津島佑子 人間はどこへゆくのか
加藤典洋 現代社会論/比較社会学を再照射する
交響空間――あとがきに(見田宗介)

ワイン法
講談社選書メチエ
500円のワインより1万円のワインは、ほんとうに20倍もおいしいのか?
ロマネコンティ グラン・クリュと格安ワインの差を生み出すのは、
品種か? 製法か? 醸造家か? 歴史か? あるいは国家か?
高級ワインを高級たらしめているのは、ただ「美味しさ」だけではない。
特定の産地、特定の生産者のワインだからこそ高く売れるのである。
産地名、生産者名、ヴィンテージ、ぶどうの品種名……これらの情報が、ブランドをブランドたらしめているとも言える。
とりわけワイン王国フランスにて繰り広げられた、ブランドを守るための数百年にわたる戦いと、
そこから生み出された法と制度すなわち「ワイン法」について、第一人者が語り尽くす!
1855年格付け、1889年グリフ法、そしてEU法。苛烈な競争、疫病と害虫、税と規制などをめぐる生産者たちの戦いは、AOC(原産地呼称制度)などのブランドを守る法と制度へと結実した。
そしてAOCは、GI(地理的表示)として世界に広がり、いまや日本でもヨーロッパのワイン法は大きな意味を持つ。
本書で語られることは、わたしたちの生活、ビジネスにも直結する大きな問題となっている。
ワインを愛する人のみならず、人々の生活が動かす歴史に興味のある人、
世界の食を動かす制度はいかなるものかを知りたい人、
いずれの読者にも、驚きと発見をもたらす、無二の解説書!
【本書の内容】
プロローグ―ワイン法はなぜ生まれ、何を守るのか
第1章 「本物」を守る戦い―原産地呼称制度の萌芽
1 フランス革命とワインの自由化
2 黄金時代の到来
3 「本物のワイン」を守る戦い
第2章 「産地」を守る戦い
1 不正ワインとの戦い
2 混迷する「産地」画定
3 原産地呼称制度の誕生
4 「コントロール」される原産地呼称へ
第3章 生き残りをかけた欧州の戦い
1 欧州統合下のワイン政策
2 ワイン共通市場制度の発足
3 本格化する生産管理
第4章 新たなプレーヤーとの戦い―畑=テロワールの思想と品種=セパージュの思想
1 新世界の「発見」
2 悩ましい新世界
第5章 「危機」から新時代へ―欧州産ワインの戦い
1 一九九九年のEUワイン改革
2 抜本的な改革をめざして―二〇〇八年の改革
コラム 補糖禁止のねらい
3 二〇〇八年の改革は成功したか?
コラム EUワイン法におけるラベル記載事項
コラム ボトルに関するEU法の規制
4 新時代のワイン法へ
5 ワイン法と日本

維摩経の世界 大乗なる仏教の根源へ
講談社選書メチエ
紀元1~2世紀頃、インドで興起した大乗仏教。それまでの教理を批判し、自利よりも利他行を強調する考え方は広く中国・日本にも及ぶ教えとなった。同時代にその教理は「法華経」「涅槃経」「華厳経」などの経典にまとめられたが、日本では「法華経」「勝鬘経」とともに「維摩経」の三経を仏教の根本として聖徳太子が注釈を加えている。
本書の主題「維摩経」はやはり紀元1~2世紀頃の成立とされ、支謙(3世紀)、羅什(4~5世紀)、玄奘(7世紀)らが漢訳するなど、大乗経典のなかでも特に重要な経典であったが、もともとサンスクリット語で記された原典はこれまで存在が知られていなかった。それが2001年、大正大学の研究チームによってチベット・ポタラ宮の書庫でサンスクリット語写本が発見され一大ニュースとなった。
その経典のなかで教えを説くのは、在家仏教者でありながら悟りを開いたとされるの「ヴィマラキールティ(維摩詰)」である。病を得た維摩のもとへ、世尊シャーキャムニの指示により訪ねてくる弟子・シャーリプトラ、マハーカーシュヤパや文殊菩薩たち。そこで繰り広げられる弟子や文殊たちと維摩との真理に関する問答。核心にあるのは「空」「煩悩即菩提」の思想であり、菩薩とはなにか、仏国土とはなにかという大問題が展開されるが、それぞれの場面は芝居仕立てによって読む者・聞く者を強く惹きつけていく。
本書は、サンスクリット語原典写本からの和訳を引用しつつ、人びとに強烈なインパクトをもたらす大乗仏教の利他行思想を紹介する。

哲学者マクルーハン 知の抗争史としてのメディア論
講談社選書メチエ
「メディアはメッセージ」「グローバル・ヴィレッジ」「空間と時間の消滅」などインパクトの強い言葉で1960年代を席巻したマクルーハン。
「文明批評家」「未来学者」「メディア社会学者」「ポップカルチャーの哲学者」「インターネット時代の預言者」「コミュニケーション理論家」など、さまざまな呼称で輪郭づけられたトロント大学英文学者マーシャル・マクルーハンの正体と思想の中身は、本当のところ何だったのか。
エリザベス朝文学を出発点とする個人研究史は、メタファーが持つ人間的思考の本質の探究へ、さらに狭いアカデミズム世界を超え出て技術・社会・文化の問題へと射程を広げてゆく。そこで焦点化されてくるのは人間の思考・行為を方向づけている「メディア」の偉力であった。
メディアとは単なる媒体ではない。印刷・電信・電話・テレビはもちろん、衣服も住宅も貨幣も、道具も兵器も、あらゆる人工物がメディアであってそれは人間の拡張をもたらすこと、また究極のメディアは言語であってそれは人間を整形し、知のかたちを変形しうることを見通すに到ったのである。
古今東西の事象に精通し博覧強記をもって知られたマクルーハン。また「論」を立てること、論理的文章を練り上げることを忌避したマクルーハン。アルファベットの発明がやがて文字・概念重視、視覚優位の西洋思想を築き上げていったことへの警鐘、そのアンチテーゼとしての聴触覚重視「口誦」文化復権への主張。難解と言われる著書と研究の射程を見抜き、計り知れない現代的意味の重さを読み解く。

新しい哲学の教科書 現代実在論入門
講談社選書メチエ
今、哲学は「人間」から離れて「実在」に向かっている。
21世紀を迎えてすでに20年、哲学の世界では大きな変動が起きています。そこで問われているのは、「人間以後」の世界をいかに考えるか、というものです。「ポスト・ヒューマニティーズ」とも呼ばれるこの動向は、思弁的実在論、オブジェクト指向存在論、多元的実在論、加速主義、アクターネットワーク理論、新しい実在論など、狭い意味での「哲学」をはるかに越えた多様な領域に広がりつつあります。本書は、こうした動向の明快な見取り図を与え、自分の問題として考える手がかりを示すために気鋭の著者が書き下ろした渾身の1冊です。
本書で取り上げられるのは、2016年に『有限性の後で──偶然性の必然性についての試論』の日本語訳が出版されて話題になったカンタン・メイヤスー(1967年生まれ)、2017年に『四方対象──オブジェクト指向存在論入門』の日本語訳が刊行されたグレアム・ハーマン(1968年生まれ)、そして2018年に日本語版『なぜ世界は存在しないのか』(講談社選書メチエ)がベストセラーとなって広く名前を知られるようになったマルクス・ガブリエル(1980年生まれ)ら、最先端の哲学者たちです。
「人間以後」の世界を考えることとは、「人間が消滅したあとの世界」という、ますますリアリティを帯びつつある世界を考えることだけではありません。それは同時に「人間の思考が届かない場所」を考えることでもある、と著者は言います。それはもちろん矛盾していますが、「実在論」への注目は、そこに現在の人間が希求するものがあることを示唆しているでしょう。
それは、別の言葉で言えば、「実在論(realism)」とは「実存論(existentialism)」でもある、ということです。1987年生まれの著者は、「今」に生きることのリアリティを手放すことなく、哲学の問題とは「生きること」の問題にほかならないことを分かりやすく示しています。
新しい哲学のムーブメントをただの流行で終わらせないために。
未来のスタンダードが、ここにあります。
[本書の内容]
プロローグ 「何をしたいわけでもないが、何もしたくないわけでもない」
第I章 偶然性に抵抗する──カンタン・メイヤスー
第II章 人間からオブジェクトへ──グレアム・ハーマン
第III章 普遍性を奪還する──チャールズ・テイラーとヒューバート・ドレイファス
第IV章 新しい実在論=現実主義──マルクス・ガブリエル
エピローグ メランコリストの冒険

AI時代の労働の哲学
講談社選書メチエ
2019年10月6日「読売新聞」書評/坂井豊貴さん「人工知能は恐ろしい?」
2019年11月9日「朝日新聞」書評/呉座勇一さん「〈人〉か〈物〉か、二分法がゆらぐ」
「東洋経済」2019年11月23日号 書評/河野龍太郎さん「AIで雇用喪失は杞憂だが、疎外、所得偏在は加速か」
*
この本は(…)人工知能技術の雇用・労働条件・生活に対するインパクトについて考察してみよう、というものではありません。むしろそこから一歩引いて、「我々は人工知能技術の発展が社会に、とりわけ労働に及ぼすインパクトについて考える際に、どのような知的道具立てを既に持っているのか?」を点検してみる、というところに、本書の眼目があります。――「はじめに」より
*
AI(人工知能)が人間の仕事を奪う――これは「古くて新しい問題」です。
馬車は自動車になり、工場はオートメーション化される。
技術(テクノロジー)は、いつの時代も仕事を変えるのです。
では、AIのインパクトは、これまでの機械化と同じなのか、決定的に違うものなのか。
「労働」概念自体から振り返り、資本主義そのものへの影響まで射程に入れて検討します。

叱られ、愛され、大相撲! 「国技」と「興行」の一〇〇年史
講談社選書メチエ
日本の伝統文化にして「国技」とされる大相撲は、一方で八百長疑惑や「横綱の品格」をめぐって、世間から叱られ続けている。この「叱られ体質」は、いつから、何に由来するのだろうか。大相撲100年の「叱られ、愛された歴史」を、「スー女」を自認する著者が丹念に掘り起こした意欲作。
明治42年(1909年)、落成したばかりの相撲常設館、その名も「国技館」の「玉座」で、8歳の少年が相撲を観戦した。この少年ーー明治天皇の皇孫、のちの昭和天皇に愛されたことが、大相撲の黄金時代と深い苦悩の始まりだった。
「国技」とは一体何か。「初っ切り」や「相撲甚句」「化粧まわし」は、「国技たる武道」の堕落ではないのか? 本書には、それぞれの「相撲道」を模索した人々が登場する。植民地台湾に力士100人を招いた任侠の親分。東京の相撲界に反旗を翻し、大阪で「角力」を興した異端児。「相撲体操」を考案し、台湾や満洲で相撲教育に邁進した熱血教師。勃興したスポーツジャーナリズムの中で、独自の相撲論を展開するインテリ力士。戦地慰問に疲労困憊しながら連勝記録を樹立した大横綱。そして1945年11月、焼け野原の東京、損壊甚だしい国技館に満場の観客を集めて、戦後初の本場所が開催される。
「国技」と「興行」のジレンマに悩みながら、いつも愛され、そこにあった大相撲の近代史。

「私」は脳ではない 21世紀のための精神の哲学
講談社選書メチエ
今、世界で最も注目を浴びる哲学者マルクス・ガブリエル。大ヒット作『なぜ世界は存在しないのか』の続編にして、一般向け哲学書「三部作」の第2巻をなす注目の書が日本語で登場です。
前作と同様に目を惹きつけられる書名が伝えているように、本書が取り上げるのは昨今ますます進歩を遂げる脳研究などの神経科学です。それは人間の思考や意識、そして精神は空間や時間の中に存在する物と同一視できると考え、その場所を特定しようと努めています。その結果は何かといえば、思考も意識も精神も、すべて脳という物に還元される、ということにほかなりません。でも、そんな考えは「イデオロギー」であり、「誤った空想の産物」にすぎない、というのがガブリエルの主張です。
「神経中心主義」と呼ばれるこのイデオロギーは、次のように主張します。「「私」、「意識」、「自己」、「意志」、「自由」、あるいは「精神」などの概念を理解したいのなら、哲学や宗教、あるいは良識などに尋ねても無駄だ、脳を神経科学の手法で―─進化生物学の手法と組み合わせれば最高だが―─調べなければならないのだ」と。本書の目的は、この考えを否定し、「「私」は脳ではない」と宣言することにあります。その拠り所となるのは、人間は思い違いをしたり非合理的なことをしたりするという事実であり、しかもそれがどんな事態なのかを探究する力をもっているという事実です。これこそが「精神の自由」という概念が指し示すことであり、「神経中心主義」から完全に抜け落ちているものだとガブリエルは言います。
したがって、人工知能が人間の脳を超える「シンギュラリティ」に到達すると説くAI研究も、科学技術を使って人間の能力を進化させることで人間がもつ限界を超えた知的生命を実現しようとする「トランスヒューマニズム」も、「神経中心主義」を奉じている点では変わりなく、どれだけ前進しても決して「精神の自由」には到達できない、と本書は力強く主張するのです。
矢継ぎ早に新しい技術が登場してはメディアを席捲し、全体像が見えないまま、人間だけがもつ能力など存在しないのではないか、人間は何ら特権的な存在ではないのではないか……といった疑念を突きつけられる機会が増している今、哲学にのみ可能な思考こそが「精神の自由」を擁護できるのかもしれません。前作と同様、日常的な場面や、テレビ番組、映画作品など、分かりやすい具体例を豊富に織り交ぜながら展開される本書は、哲学者が私たちに贈ってくれた「希望」にほかならないでしょう。
[本書の内容]
序 論
I 精神哲学では何をテーマにするのか?
II 意 識
III 自己意識
IV 実のところ「私」とは誰あるいは何なのか?
V 自 由

月下の犯罪 一九四五年三月、レヒニッツで起きたユダヤ人虐殺、そして或るハンガリー貴族の秘史
講談社選書メチエ
1945年3月24日の晩、ハンガリー国境沿いにあるオーストリアの村レヒニッツで、約180人のユダヤ人が虐殺された。彼らは穴を掘るように命じられ、その縁に服を脱いでひざまずかされた挙げ句、射殺される。死体は穴の中に崩れ落ち、折れ重なっていった。穴を埋めたのもユダヤ人たちだったが、彼らもまた作業を終えた翌朝には無残にも射殺された。
主犯とされているのは、当時レヒニッツにあった城でパーティーを行っていたナチスの将校や軍属たちである。ナチス・ドイツの劣勢が明白になり、ヒトラーが自殺するひと月前にあたる。戦後になって、彼らが埋められた場所が捜索されたが、今に至るまで死体はおろか、何の証拠も見つかっていない……。
本書は、この「レヒニッツの虐殺」と呼ばれる事件の真相を追っていくノンフィクションである。2016年に出版されると、たちまち話題を呼び、ベストセラーになった。英語をはじめ、各国語への翻訳も進められている。
この書物の最大の特徴は、1973年生まれの著者サーシャ・バッチャーニの出自にある。主犯格の将校たちが集っていた城はバッチャーニ家の持ちものであり、当主イヴァンの妻マルギットが問題のパーティーを主催したと言われている。イヴァンは著者サーシャの祖父の兄。つまり、マルギットは著者の大伯母にあたる。
一時は「ヨーロッパで最も裕福な女性」とまで言われ、派手好みで娯楽にふけり、狩猟を趣味にしていたマルギットこそ、この事件の首謀者だったのではないか、という噂は事件の直後からささやかれ続けてきた。近年でも、これを題材にして、劇作家エルフリーデ・イェリネク(1946年生まれ)が戯曲『レヒニッツ(皆殺しの天使)』(2008年)を書いている。
では、本当の真相はどうだったのか? 新聞記者を務める著者サーシャは、祖母マリタが残した日記、レヒニッツで食料品店を経営していたユダヤ系の娘アグネスの日記などを手がかりに、レヒニッツはもちろん、関係者に会うために各地を訪れながら、謎に迫っていく。実に7年間に及ぶ探求の旅は、著者自身が抱える父との関係に潜む闇とも交錯しながら、さらに深い次元に向かうことになる。
こうして、ドキュメンタリーふうに進行する調査を描写していくパートのあいだに、当事者たちが残した手記が挟み込まれ、時には当時展開されたはずの会話を再現するシーンも織り交ざって、独特の雰囲気をそなえたスリリングな読みものが完成した。
はたして著者は真実に到達できるのか? 探求の旅はどこにたどりつくことになるのか?──衝撃のラストまで読む者を飽きさせない話題の書、ついに選書メチエで登場!

昭和・平成精神史 「終わらない戦後」と「幸せな日本人」
講談社選書メチエ
敗戦から70年以上が過ぎ、元号も2度あらたまって、いよいよ昭和も遠くなりつつある。「もはや「戦後」ではない」という宣言から数えてもすでに60年以上が経った。しかし、私たちが生きているのは、今なお「戦後」なのではないだろうか。毎年、戦後何年になるかを数え、ことあらば「戦後初」をうたう。私たちが生きている時間は、つねに「戦後」を起点とし、「戦後」に規定されている。これはいったいなにを意味しているのだろうか。令和の時代を迎えても加速する一方の「息苦しさ」、「生きづらさ」は、実はこの「終わりなき戦後」の終わらなさにこそ原因があるのではないか――。
本書は、「戦後」という幸福な悪夢の外側に、どうにかして越え出るために、昭和・平成を貫く時代精神の真の姿を映し出す試みである。
太宰治の絶望、ゴジラに仮託された不安、力道山が体現した矛盾、さらにオウム真理教という破綻と癒えることのない東日本大震災の傷。戦後日本社会の精神史は、東京オリンピックや大阪万博、インターネットの普及など華やかな出来事や物質的豊かさの影で、それを支えるためにそこから排除されてきた人々の嘆きと悲しみの声に満ちている。その声に耳を傾け、「息苦しさ」と「生きづらさ」の根源から目を逸らさず、その姿を受けとめること。「戦後」を終わらせるため、声高になることなく、著者は静かに繰り返し私たちに語りかける。
うわべだけの「幸せな日本人」を脱ぎ捨て、敗戦から日本社会が抱えこんできた絶望を直視したときにはじめて、希望もまた輝きはじめる。「終わりなき戦後」から、かけがえのない一歩を踏み出すのための、時代に捧げる鎮魂歌。

ヒト、犬に会う 言葉と論理の始原へ
講談社選書メチエ
人間は自分たちだけで文明への階梯を上がって来たのではない。
一万五〇〇〇年前、東南アジアいずれかの川辺での犬との共生。
ニッチを見出す途上にあったお互いの視線の重なりが、
弱点を補完し合い、交流を促し、文明と心の誕生を準備した。
オオカミは人間を振り返らないが、犬は振り返る。
人間は幻想や感情で判断するが、犬は論理的に判断する。
犬は人の言葉を理解し、人の心を読み、人の窮地を救う――
人間と犬、運命共同体としての関係の特異性と起源を探る。

解読 ウェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』
講談社選書メチエ
これならわかる!
『プロ倫』はなにを解き明かしたのか? いま受け取るべきメッセージはなにか?
超難解書の全体像と核心が明快にわかる、驚異の解説書が登場。
これが、ウェーバーの言いたかったことだ!
《冒頭10頁強で、ウェーバーってどんな人&『プロ倫』のあらすじが、ざっくりわかる!》
《基礎知識から "ライバル" ゾンバルトやマルクス主義とのわかりやすい対比まで、たのしくわかるコラム満載!》
『プロ倫』は「プロテスタンティズムと資本主義の発展の関係」を論証したとされるが、本当にその試みは成功していたのだろうか? いまなお読み解くべき意義があるのだろうか? そんな素朴かつ核心的な問いをスタート地点にして、ウェーバーの論考のエッセンスを、クリアーで平明な文章で徹底解説。
宗教改革によって勃興したプロテスタンティズムは、「天職」という概念や、神が誰を救うか/救わないかをすでに決めているという「二重予定説」なる教説を生み出した。快楽を排しひたむきに貨幣獲得に生きがいを見いだすような精神が生まれ、資本主義社会が発展していくが、しかし資本主義が爛熟すると崇高な精神が失われてしまう――ここに、ウェーバーの問題意識の核心があった。そして、その問いと思考は、現代における新保守主義という思想と響き合うものだった。
市場経済の発達が加速度を増し、その行く末を誰も見通すことができなくなりつつあるいまこそ、近代とは、資本主義とはなにかを正面から考えた『プロ倫』のエッセンスを読もう!
【本書の内容】
序章 ウェーバーってどんな人?
第1章 「問題」はどこにあるのか?
第2章 資本主義の精神とはなにか?
第3章 「天職」の概念が生まれた
第4章 禁欲的プロテスタンティズムの倫理とはなにか? -1-
第5章 禁欲的プロテスタンティズムの倫理とはなにか? -2-
第6章 天職倫理と資本主義
第7章 現代社会で生きる術を考える
補論

日本語の焦点 日本語「標準形」の歴史 話し言葉・書き言葉・表記
講談社選書メチエ
「スタンダード」とは本来は標準語のことである。しかし、「標準語」というと、たいていは、明治以降の「標準語」を思い浮かべるだろう。現在、アナウンサーがしゃべっている言葉、東京山の手の言葉などと言われるあの言葉だ。
ところが、本書では、江戸期以来、一貫して「話し言葉の標準形態」つまり「標準語」があったと考えている。これを、一般にイメージされる「標準語」と区別して「標準形(ルビ:スタンダード)」と呼ぼう。
書き言葉にも、標準形があった。これも、歴史をたどれば、室町時代までさかのぼる。
書き言葉を書く際の表記にも、標準形はあった。
これも、明治維新と供に成立したものではない。いわゆる、仮名遣いの問題である。
時折言われるように、歴史的仮名遣いは正しいのだろうか。
いや、江戸期には、もっと多様で柔軟な表記を許すスタンダードがあった。
このようにして、「スタンダード」と言うことを軸として、本書は話し言葉、書き言葉、仮名遣いの歴史に分け入っていく。
豊饒な言葉の世界を堪能してください。

地中海の十字路=シチリアの歴史
講談社選書メチエ
長靴の形をしたイタリア半島に蹴り上げられるように、地中海に浮かぶ最大の島、シチリア島。マフィアの故郷として知られ、人気の観光地でもあるこの島は、現在はイタリア共和国の一部となっているが、しかし、古くからここは「イタリア」だったわけではない。文明の先進地域・地中海とヨーロッパの歴史を常に色濃く映し出し、多様な文化と宗教に彩られてきたシチリア島。その3000年に及ぶ歴史を描き出し、シチリア島から世界史を照射する。
シチリアの覇権をめぐって最初に争ったのは、古代ギリシア人とフェニキア人だった。その後、ローマの「最初の属州」となり、ローマ帝国の穀倉となった。中世にはイスラーム勢力が柑橘類の栽培や灌漑技術を導入し、当時の先端文明と通商ネットワークをもたらしたが、北フランス出身のノルマン人たちがこれを屈服させて「シチリア王国」を建て、栄光の時代が訪れる。さらにドイツのホーエンシュタウフェン家、フランスのアンジュー家の支配が続き、ヴェルディのオペラで知られる「シチリアの晩祷事件」を境に、アラゴン・スペインによる「長く、暗い時代」に入る。フランス革命期にはイギリスの保護下に置かれるが、19世紀にはイタリアの統一運動、すなわちリソルジメントに巻き込まれ、イタリアに併合されていく。
絶え間なく侵入した「よそ者」と、宗教・文化の交錯の過程で、シチリア人の誇り高いアイデンティティは形成された。そして今、北アフリカから小さなボートで「新たなよそ者」が押し寄せているシチリアは、まさにグローバル化した世界の台風の目となっている。
〈目次〉
序章 シチリア島から世界史をみる
第一章 地中海世界と神々の島
第二章 イスラームの支配と王国の栄光
第三章 長くて、深い眠り
第四章 独立国家の熱望と失望
第五章 ファシズムと独立運動
終章 「シチリア人」の自画像
あとがき
参考文献
関連年表
シチリア王の系譜

インフラグラム 映像文明の新世紀
講談社選書メチエ
2019年7月6日「日経新聞」書評/武田徹さん「写真・映像は情報文化の基盤」
2019年7月6日「北国新聞」他書評/鷲田めるろさん「像で論じる情報化社会」
2019年5月18日「毎日新聞」記事/「SNSによる激変 その先を問う」
2019年11月10日「読売新聞」編集手帳
『美術手帖』10月号 書評
*
映像は現代社会の生活基盤(インフラ)である。これを「インフラグラム」と呼ぼう。
通信は5G時代に突入し、軍事からコミュニケーションまで、インフラグラムはますます、情報社会の根幹をなしている。
すべてが可視化されているようなこの映像文明において、
わたしたちは何を見て、何に見つめられ、何を見ていないのか――?
5G時代の映像論を、眼差しの歴史として考える。
*
写真の誕生から180年。
「光による描画」の技術は、スマートフォンから人工衛星、
地図、医療、娯楽から政治、軍事、戦争まで、
情報社会を動かすインフラとなった。
視線は労働し、〈わたし〉はデータ上に増殖している。
こうして映像は、監視社会を強化するいっぽうで、
他者が生きた時間を再起させる記憶の装置でもある。
わたしたちの現在を、生と死を、そして自由とは何かを考える、
〈眼差しの歴史〉。
〈目次〉
01 神経エコノミーの誕生
02 インフラグラムの時代
03 軍事の映像人類学
04 空の眼
05 記憶の身体