新刊書籍
レーベルで絞り込む :
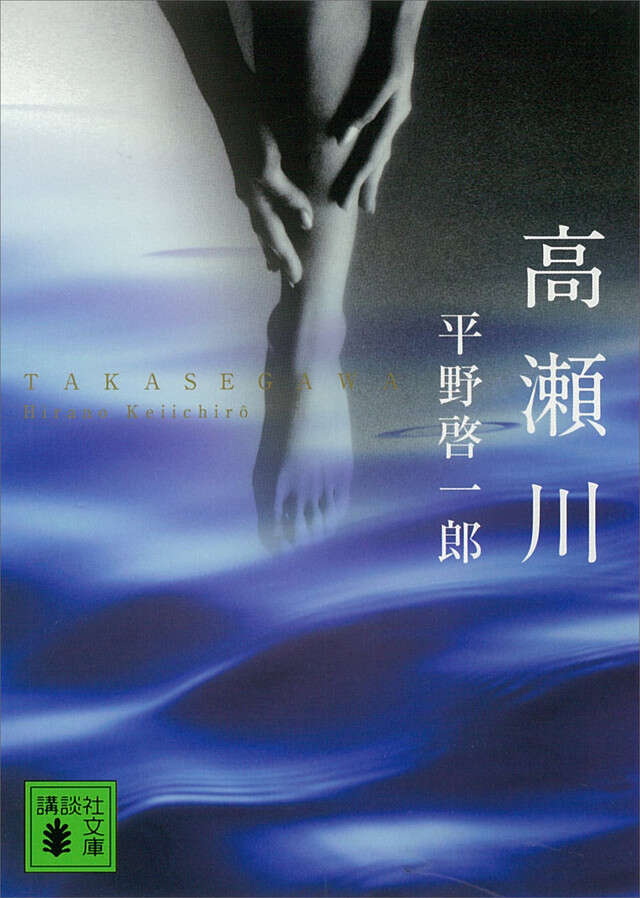
2014.10.24発売
高瀬川
講談社文庫
芥川賞作家が描き出す 一夜の「性」と「生」
清冽で美しい言葉の流れ――
小説家と女性誌編集者が過ごす、京都の一夜を繊細な心理主義的方法で描き、現代の「性」を見つめる「高瀬川」。亡くした実母の面影を慕う少年と不倫を続ける女性の人生が並列して進行し、やがて1つに交錯する「氷塊」。記憶と現実の世界の間(あわい)をたゆたう「清水」など、斬新で、美しい技法を駆使した短編4作。
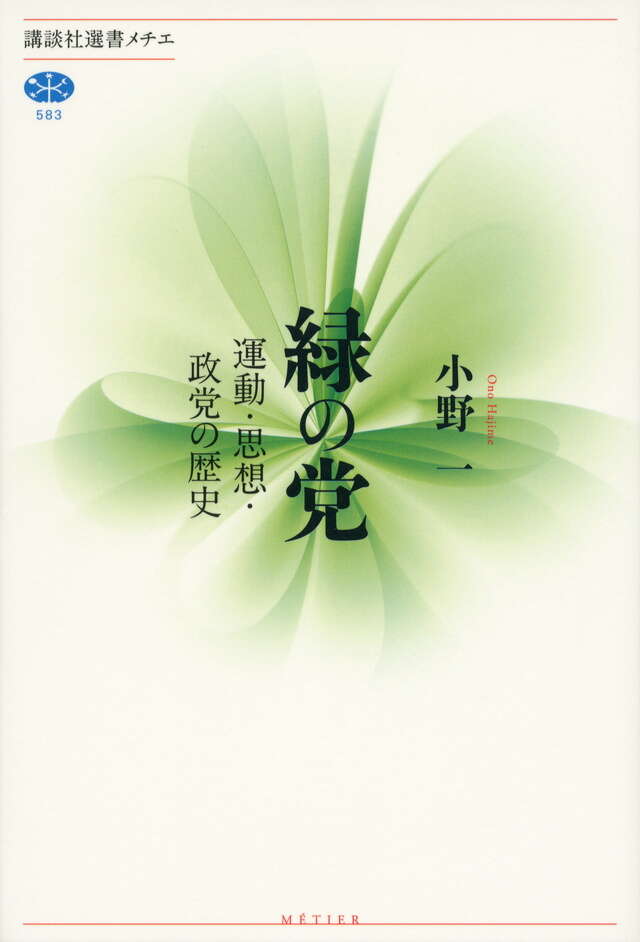
2014.10.24発売
緑の党 運動・思想・政党の歴史
講談社選書メチエ
一九六〇年代末~七〇年代初頭、先進国で高揚した「新しい社会運動」。そこから出発した緑の党は、役割を変化させながら現在に至っている。ドイツをはじめとした諸外国のケースを検討しながら、運動・思想・体制(政権党)の三つの側面を分析する。私たちはどのような社会を望むのか。緑の党はその選択肢になりうるのか。いま改めて考え直す。
【目次】
序章 なぜいま緑の党か
第1章 世界に広がる緑の党
1.欧州諸国
2.ドイツ
3.フランス
4.アングロサクソン諸国
5.グローバル・グリーンズ
第2章 運動としての緑の党
1.転換点としての一九六八年
2.多様なテーマ
3.社会運動から政権党へ
第3章 思想としての緑の党
1.エコロジー思想は左翼か
2.環境思想│源流からエコロジー的近代化まで
3.新しい生き方・働き方を求めて
第4章 体制(政権党)としての緑の党
1.シュレーダー政権の軌跡と緑の党
2.焦点としての脱原発問題
3.政権参加と緑の党のアイデンティティ
4.ポスト赤緑時代の政党連立問題
終章 緑の党と私たち
1.戦後日本政治と革新勢力の脆弱性
2.緑の党研究から私たちは何を学ぶか
3.私たちはどのような社会を望むのか
注釈
あとがき
索引

2014.10.24発売
「イタリア」誕生の物語
講談社選書メチエ
一八世紀末、イタリア半島は小国の集合体だった。サルデーニャ王国、ジェノヴァ共和国、ヴェネツィア共和国、モデナ公国、パルマ公国、トスカーナ大公国、教会国家、ナポリ王国、ハプスブルク帝国領のミラノ公国……。フランス革命の風を受け、統一国家「イタリア」の実現を目指す「再興(リソルジメント)運動」の激しいうねり。大国フランスとオーストリアの狭間で、いかにして「想像の政治的共同体」は成立したのか?
【目次】
はじめに
地理的名称・イタリアを国家に/明治のイタリア史ブーム/イタリアへの親近感/『伊太利建國三傑』/中国と朝鮮でも
第一章 「自由の木の酸っぱいけれども甘い果実を味わった最初の国」──一七九六~一七九九年
イタリアとヨーロッパ/フランス革命とイタリア/「革命の三年間」(一七九六~一七九九年)/「姉妹共和国」の誕生/他
第二章 皇帝ナポレオンのイタリア支配──一八〇〇~一八一四年
統領ナポレオンの領土再編成/皇帝ナポレオンの領土再編成/ナポレオン支配の光と影/反ナポレオンの運動/ナポレオンの失墜
第三章 不安定な王政復古体制
ウィーン体制下のヨーロッパ/ウィーン会議によるイタリアの編成/秘密結社運動の活発化/ナポリとトリノの革命/
第四章 秘密結社運動から政党の運動へ
リソルジメント運動と亡命者たち/マッツィーニと「青年イタリア」/「青年」が意味するもの/「イタリア」の地理的定義/他
第五章 革命ではなく改革を目指した穏和派
穏和派とは/ジョベルティの『イタリア人の道徳的・文明的優位』/バルボの『イタリアの希望』/他
第六章 イタリアの長い「一八四八年革命」
一八四八年のイタリアとヨーロッパ/ミラノの煙草ストライキ/南から北へ連鎖する憲法発布/「一八四八年革命」の国際化/他
第七章 リソルジメントの国際化
第二次王政復古時代の特徴/憲章を堅持したサルデーニャ王国の動向/サルデーニャ王国に流入した亡命者/他
第八章 職人的なイタリア統一
第二次独立戦争の開始/中部イタリアにおける反乱とヴィッラフランカ休戦協定/サルデーニャ王国に併合された中部イタリア/ガリバルディの「千人隊」/他
第九章 半島の名前から民族の名前となったイタリア
統一に「洗礼」を授けた住民投票/イタリア王国の誕生/カヴールの急逝に対する反応/「歴史的右派」政権が取り組んだ諸問題/他
第十章 「クオー・ヴァディス、イタリア」──「おわりに」にかえて
「イタリアよ、何処に行きたもう?」/論争の二つの契機/近現代イタリアにおける三つの異なる政治体制/一九一一年の統一・五〇周年/他
あとがき
文献案内
年表
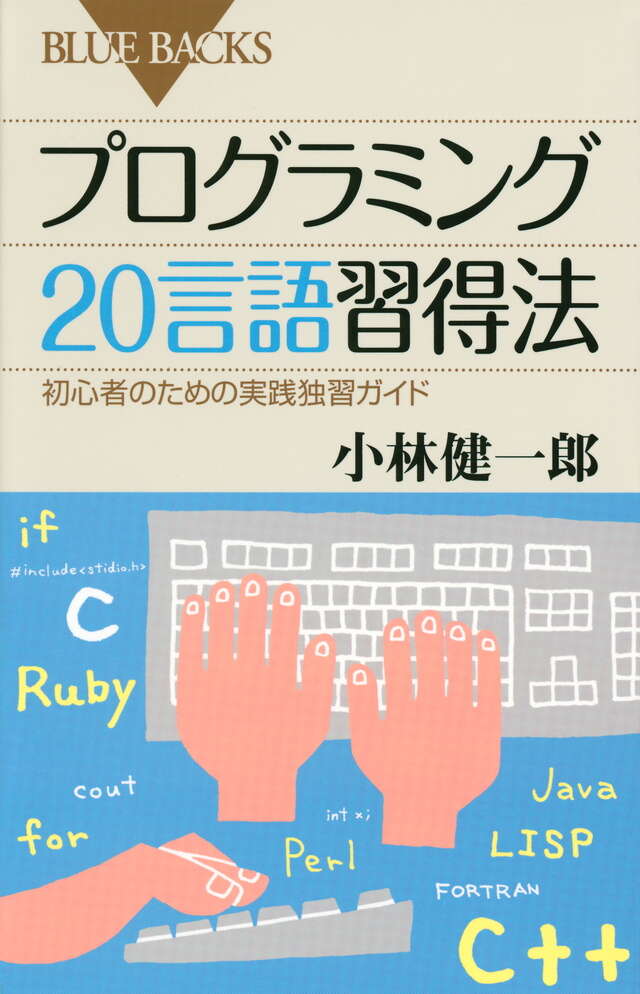
2014.10.24発売
プログラミング20言語習得法
ブルーバックス
「パソコンを自在に操ってみたい」──そんな夢をかなえるのがプログラミング言語。ではどの言語を学べばいい? どうやって学べばいい? 本書では、現在主流の言語を中心に、各言語の基本構造と特色を紹介。見比べながら、自分に合った言語と学習法を見つけることができます。さらにプログラミングに共通するしくみを知れば、複数の言語を身につけることも簡単に。楽しみながら効率よく独習するコツを伝授します。
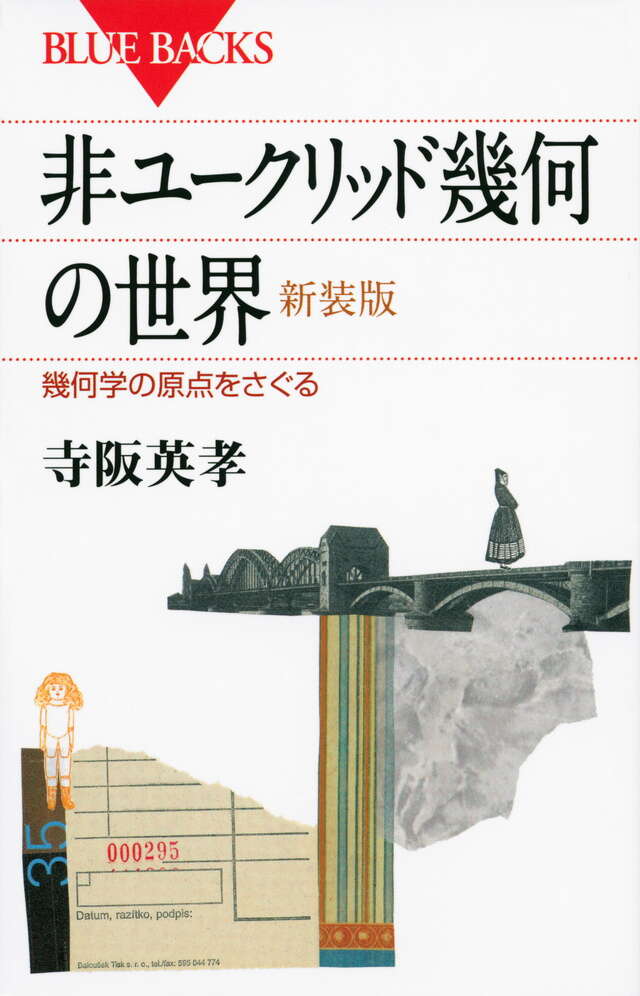
2014.10.24発売
非ユークリッド幾何の世界 新装版
ブルーバックス
名著復刊! 考える喜びをあなたに! 平行線とは同じ平面にあって互いに交わらない二直線のことである。では、この平行線はどう見えるだろう? 東西にまっすぐに延びた線路――この平行な二直線は地平線の一点に集まって見える。東を見ても西を見ても……。それでは平行線とは二つの無限遠点で交わっている直線なのだろうか? (ブルーバックス・2014年9月刊)
名著復刊
考える喜びをあなたに!!
平行線とは同じ平面にあって互いに交わらない二直線のことである。では、この平行線はどう見えるだろう? 東西にまっすぐに延びた線路――この平行な二直線は地平線の一点に集まって見える。東を見ても西を見ても……。それでは平行線とは二つの無限遠点で交わっている直線なのだろうか?
本書とともにこんな素朴な疑問を追っているうちに、いつの間にか、あなたは、幾何学とはどんな学問かを悟り、非ユークリッド幾何の世界に踏み込んでいる自分に気づくことだろう。

2014.10.24発売
山に登る前に読む本
ブルーバックス
たとえば、ある山に登ろう、と決心したとき、体力はどれくらい必要で、水と食料はどれくらい持って行けばいいのか。さらに、山の気温はどれくらいで、衣服はどれほど持って行けばいいのか。食料、水はどうか。これらを余分に持って行きたくなるが、荷物が重くなると登山どころではなくなってしまう。本書は、このような問いに答えるべく、登山というスポーツを環境・運動生理学の立場から科学的に解説したものである。
たとえば、ある山に登ろう、と決心したとき、体力はどれくらい必要で、水と食料はどれくらい持って行けばいいのか。体力とは自動車のエンジンのようなもので、自分のエンジンが大型なのか小型なのかを理解しておくことも大切だ。さらに、山の気温はどれくらいで、衣服はどれほど持って行けばいいのか。食料、水はどうか。これらを余分に持って行きたくなるが、荷物が重くなると登山どころではなくなってしまう。
本書は、このような問いに答えるべく、登山というスポーツを環境・運動生理学の立場から科学的に解説したものである。実験データに基づいた、無理のない登山術を紹介する。
いうまでもなく、登山でもっとも重要なことは安全である。最近は中高年者の登山事故が増えているが、その原因には「自分の体力を自覚していない」「登山というスポーツのキツさを知らない」「自分の体力にあった登山計画を立てられない」といったことがあげられる。これらの対策をすれば、事故はもっと減り、より安全で挑戦的な登山が可能になるだろう。
山に登る前に知っておきたい、身体と運動のメカニズムをわかりやすく解説する。

2014.10.24発売
誰が本当の発明者か
ブルーバックス
発明の歴史は「人と金と裁判の歴史」だった。技術開発史を彩る発明者たちの本家争い。●エジソンは白熱電球の25番目の発明者!? ●ワットは単なる改良家!? ●アークライトは発明の盗人!? ●2時間差でベルに敗れた男とは!? ●高峰譲吉はなぜ「発明者」になれなかったか!? 世界を変えた偉大な20の発明の謎に迫る!
エジソンは白熱電球25番目の発明者だった。ワットの蒸気機関は発明ではなく改良。高峰譲吉の抹殺された発見とは。アークライトの水力紡績機は盗んだ発明。世界を変えた偉大な20の発明の謎に迫る!
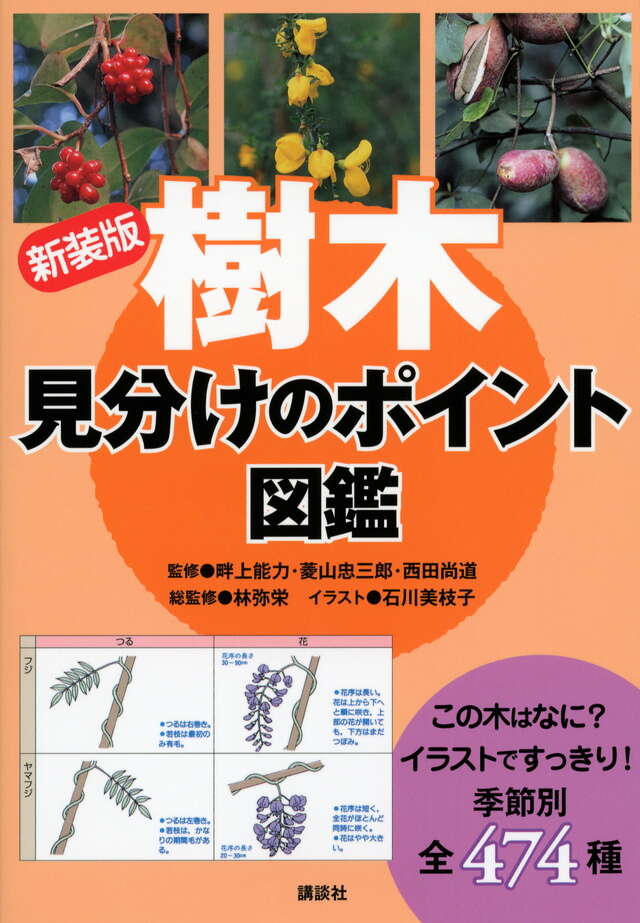
2014.10.24発売
新装版 樹木 見分けのポイント図鑑

2014.10.24発売
新装版 野草 見分けのポイント図鑑
日本の野草555種の見分け方を完全図解。アヤメとノハナショウブ、ホトケノザとカキドオシ・・・・・・。似通っていて区別がつきにくい野草の見分け方をイラストで完全図解。美しい花の写真も満載のカラー図鑑です。総索引から見つけることはもちろん、花の咲く季節ごとに章立てしてありますので、目にした植物をすぐに見つけ出すことができる構成になっています。

2014.10.24発売
松平家 心の作法
「本来なら、お姫様であった人の礼法の書は、現代の若い女性たちへの、最高の贈り物になるだろう」――櫻井よしこ(ジャーナリスト)推薦徳川270年、一流の気品から生まれたしあわせを呼ぶ、シンプルな教え。心の整え方、人づきあい、美しい所作、愛される秘訣など、人生に役立つヒント。世界一美しい、自分磨き。
「本来なら、お姫様であった人の礼法の書は、
現代の若い女性たちへの、
最高の贈り物になるだろう」
――櫻井よしこ(ジャーナリスト)推薦
徳川270年、一流の気品から生まれた
しあわせを呼ぶ、シンプルな教え。
心の整え方、人づきあい、美しい所作、
愛される秘訣など、人生に役立つヒント。
世界一美しい、自分磨き。
●心に自分だけの城を持つ
●誰かに優しくするだけで救われる
●嫌なことは「丹田」に納める
●人生とは上手に感情を自制する技
●質素倹約は本質を見極める
●おしゃれは自分の身を守るもの
●一汁一菜、腹八分目の精神で ほか
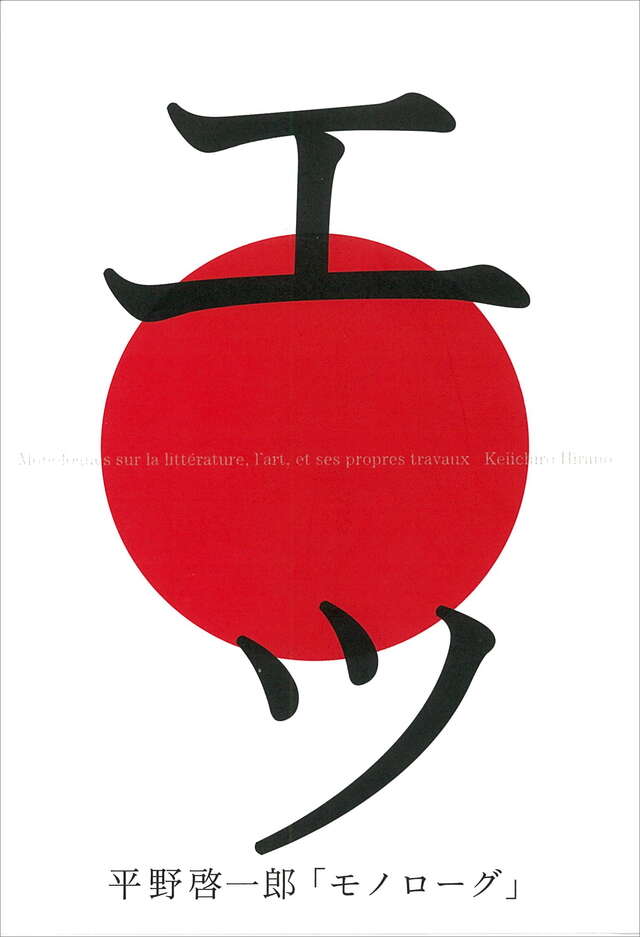
2014.10.24発売
モノローグ
文芸(単行本)
三島由紀夫/ミルチャ・エリアーデ/小林秀雄/紫式部/ランボー/トーマス・マン/ボルヘス/森鴎外/ピカソ/篠山紀信/フランク・ロイド・ライト/マイルス・デイヴィス――文学、音楽、美術、建築、そして、自らの作品について論じた ファーストエッセイ集。『日蝕』の衝撃的デビューから現在まで、常に時代の最前線に立ちつづけた著者の軌跡
三島由紀夫/ミルチャ・エリアーデ/小林秀雄/紫式部/ランボー/トーマス・マン/ボルヘス/森鴎外/ピカソ/篠山紀信/フランク・ロイド・ライト/マイルス・デイヴィス――文学、音楽、美術、建築、そして、自らの作品について論じた ファーストエッセイ集
『日蝕』の衝撃的デビューから現在まで、常に時代の最前線に立ちつづけた著者の軌跡
三島由紀夫の新たな読みを提示した「『金閣寺』論」、「『英霊の声』論」を中心に、あらゆるジャンルにわたって書かれたエッセイ集。現代における最重要人物・平野啓一郎がデビューから10年、主に20代に考えたこととは――
私が文学というものに目覚めたきっかけが、14歳の時の『金閣寺』体験だったことは既に方々で語ってきたが、ここで強調したかったのは、『金閣寺』及び『鏡子の家』の両作が、戦争体験と昭和40年代の政治活動とに挟まれた、三島の生涯に於ける決定的な分水嶺であったという点である。――<「あとがき」より>
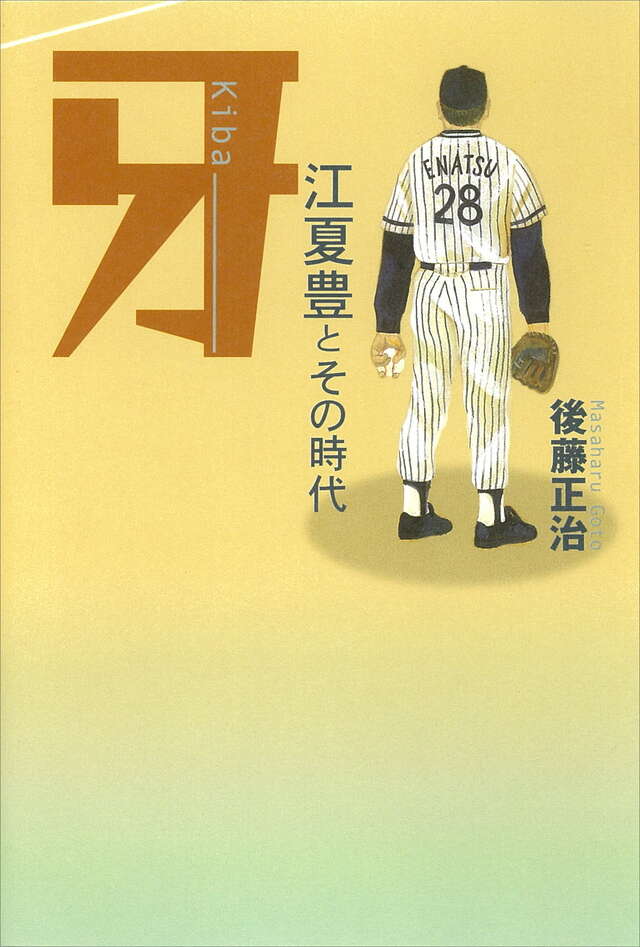
2014.10.24発売
牙―江夏豊とその時代
長嶋がいて王がいた。手に汗握るような王―江夏の一騎討ちがあった。どの時代にも人々を吸引するスターがいる。人は過ぎ去った日々に思いを込めるものであるが、それを差し引いてもなお、プロ野球を包む風景はいまよりずっと熱気に溢れてあったように思える。失われた〈黄金時代〉の一端を、長くプロ野球ファンであったものとして記してみたかった。――(「あとがき」より)
ONがいた。堀内がいた。村山がいた。
日本中が燃えていた。
そして江夏豊がいた!
人工芝も屋根付き球場もなかった。もっと速く、もっと遠くへ――。
グラウンドは「真剣勝負」に溢れていた。単純で、むき出して、けれども胸躍る、熱いもの。それがプロ野球だった。
長嶋がいて王がいた。手に汗握るような王―江夏の一騎討ちがあった。どの時代にも人々を吸引するスターがいる。人は過ぎ去った日々に思いを込めるものであるが、それを差し引いてもなお、プロ野球を包む風景はいまよりずっと熱気に溢れてあったように思える。失われた〈黄金時代〉の一端を、長くプロ野球ファンであったものとして記してみたかった。――(「あとがき」より)
現役生活18年の通算成績は、206勝158敗193セーブ。最優秀防御率1回、最多勝2回、最優秀救援投手5回、セ・パ両リーグにまたがってMVP(最優秀選手賞)……。
残した数字も傑出しているが、江夏は記録よりも記憶に残る投手だった。
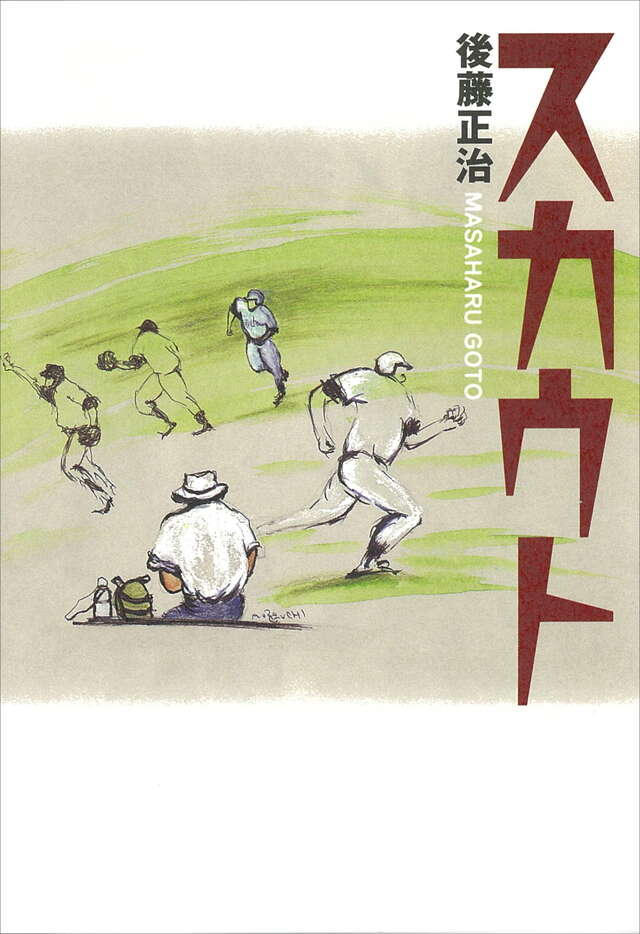
2014.10.24発売
スカウト
プロの夢と現実を肌で知る男の物語。衣笠祥雄、達川光男、大野豊、三村敏之、池谷公二郎、川口和久、高橋慶彦、長嶋清幸、正田耕三、金城基泰……無名の選手を発掘する目利きの男。広島カープの黄金時代に貢献し、のち大洋、オリックス、日本ハムで40年以上のキャリアを重ねるスカウト木庭教(きにわさとし)。プロ野球を陰で支える男の愛すべきドラマ。
プロの夢と現実を肌で知る男の物語
衣笠祥雄、達川光男、大野豊、三村敏之、池谷公二郎、川口和久、高橋慶彦、長嶋清幸、正田耕三、金城基泰……
無名の選手を発掘する目利きの男。
広島カープの黄金時代に貢献し、のち大洋、オリックス、日本ハムで40年以上のキャリアを重ねる現役スカウト木庭教(きにわさとし)。プロ野球を陰で支える男の愛すべきドラマ。
[本書には、プロ野球の“裏面史”、あるいはスカウト合戦における“内幕”という色彩が潜んでいるかもしれないが、私が主題としたのは、この職を生涯の仕事とした一老スカウトの物語である。1994年夏からほぼ3年、主人公のスカウトと折に触れて行動をともにし、またそれまでの歩みを辿ってきた。いま振り返ってよぎるのは、直射日光が照りつける地方球場の堅い椅子や、その足元を這う黒い蟻や、頬をなでる一陣の風である。スカウトとの日々は、そんな情景のなかで過ぎていった]――(「あとがき」より)
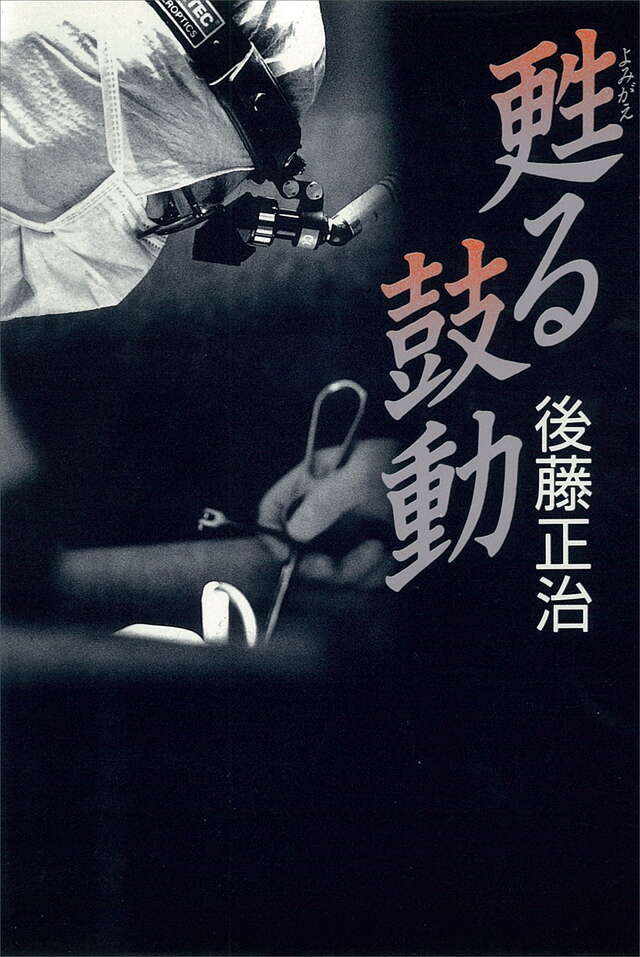
2014.10.24発売
甦る鼓動
臓器移植の新たな潮流と苦闘を描く意欲作! 大きく変貌し前進する移植外科――脳死移植の是非の嵐の中で、確かな橋頭堡を築くために、さまざまな領域で情熱の炎を燃やしつづける外科医たちの苦悩と成果。
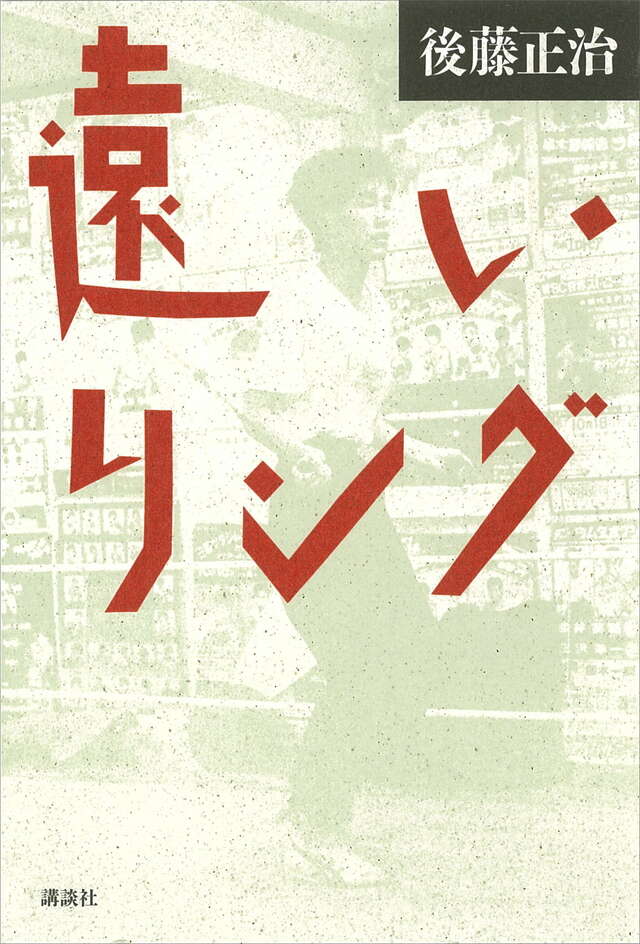
2014.10.24発売
遠いリング
【講談社ノンフィクション賞受賞作】 ボクシングに賭けた少年たちの「光と闇」! 夢を見ることだけが少年たちを支えた。たとえ敗者になろうと、燃焼しつくすまでリングに上がろうとする少年たちを見守り続けた、講談社ノンフィクション賞、大宅壮一ノンフィクション賞受賞作家・会心の書下ろしノンフィクション。
ボクシングに賭けた少年たちの「光と闇」! 夢を見ることだけが少年たちを支えた。たとえ敗者になろうと、燃焼しつくすまでリングに上がろうとする少年たちを見守り続けた、会心の書下ろしノンフィクション。
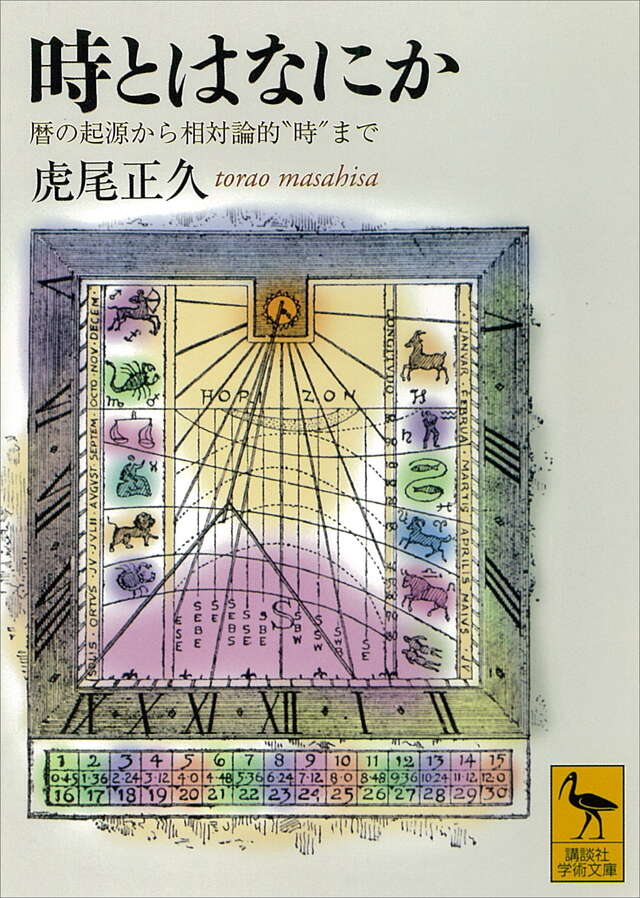
2014.10.24発売
時とはなにか 暦の起源から相対論的“時”まで
講談社学術文庫
人々の生活の基本にあり、日常を区切り律する「時」。その成り立ちや仕組みはあまり知られていない。幾多の不備があっても習慣として使い続けられる暦がある一方、高い精度が求められ原子単位となっていく「時」もある。一体「時」はどのように決められているのか。先人たちが苦労を重ね定めてきた歴史とともに、現代的な観点も含めて、「時」の専門家が壮大なテーマを易しく解説する。(講談社学術文庫)
時はどのように定められ、使われてきたか。人は時を測り、定め、保ち、利用してきた。日々の生活に密着した「時」は、どのような歴史を経て決められたのか。その道程や概念を時の専門家が易しく解説する。

2014.10.24発売
西洋中世奇譚集成 皇帝の閑暇
講談社学術文庫
西洋史の泰斗ジャック・ルゴフが「先駆的民俗学者」と呼んだティルベリのゲルウァシウスによる奇譚集。南フランス、イタリアを中心にイングランドやアラゴンなどの不思議話を129篇収録。幽霊、狼男、人魚、煉獄、妖精、魔術師……。奇蹟と魔術の間に立つ《驚異》は「人間と世界の在り方の反省へと、謙虚に誘う」神聖な現象だった。中世人の精神を知るために必読の第1級史料。(講談社学術文庫)
奇蹟と魔術の間に立つ《驚異》は教訓となる。幽霊、狼男、人魚、煉獄、妖精、魔術師……。ここに収録されたのは「科学的驚異」である。自然でありながら、理解を超えた真実が、中世人の精神を陶冶したのだ。

2014.10.24発売
近代文化史入門 超英文学講義
講談社学術文庫
今まで何の関係もないと思われていた2つのものが、1つであることを知ることこそ、魔術・マニエリスムの真諦である。そして、これこそが究極の「快」である。光学、辞典、哲学、テーブル、博物学、造園術、見世物、文字、貨幣、絵画、王立協会……。英国近代史を俯瞰し、歴史の裏に隠された知の水脈を、まるで名探偵ホームズのように解明する「脱領域の文化学」の試みである。(講談社学術文庫)
ニュートンと庭と絵と文学はつながっている。科学、美学、社会学、歴史学、哲学、辞典学、庭園術、観相学、博物学……。あらゆる知の領域を繋ぎ合わせて、紡ぎ出す、奇想天外にして、正統な近代視覚文化論。

2014.10.24発売
太平洋戦争と新聞
講談社学術文庫
満蒙の特殊権益をめぐる中国との対立から戦争の泥沼へとのめり込んでゆく日本。満州事変、日中戦争、太平洋戦争と続く動乱の時期、新聞は政府・軍部に対しどんな論陣を張り、いかに報道したのか。新聞紙法を始めとする法令、厳しい検閲に自由を奪われるとともに、戦争遂行へと自らの主張を転換する新聞。批判から迎合的煽動的論調への道筋を検証する。(講談社学術文庫)
新聞はなぜ戦争への道を阻止できなかったか。満州事変から日中戦争、太平洋戦争へと突き進む政府・軍部に対し、新聞はいかに報道し、どんな論陣を張ったのか。批判から迎合的煽動的論調への道筋を検証する。

2014.10.24発売
人類史のなかの定住革命
講談社学術文庫
霊長類が長い進化史を通じて採用してきた遊動生活。不快なものには近寄らない、危険であれば逃げてゆくという基本戦略を、人類は約1万年前に放棄する。ヨーロッパ・西アジアや日本列島で、定住化・社会化はなぜ起きたのか。栽培の結果として定住生活を捉える通説はむしろ逆ではないのか。生態人類学の立場から人類史の「革命」の動機とプロセスを緻密に分析する。(講談社学術文庫)
数百万年の遊動生活から定住への革命的転換。不快なものには近寄らない、危険であれば逃げてゆくと、いう基本戦略を棄て、定住化・社会化へと方向転換した人類。そのプロセスとは? 通説を覆す画期的論考。